2004年10月31日
東京国際映画祭リポート
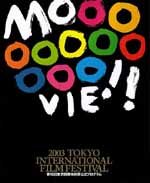 というわけで、雨の中初参加してきたわけですが、いろいろな意味で先日参加した東京ファンタスティック映画祭との差を実感した次第です。アジア最大の映画祭と言うだけあって様々な意味で“官僚的”な感じがしましたね。
というわけで、雨の中初参加してきたわけですが、いろいろな意味で先日参加した東京ファンタスティック映画祭との差を実感した次第です。アジア最大の映画祭と言うだけあって様々な意味で“官僚的”な感じがしましたね。
1本目はチャウ・シンチー監督『カンフーハッスル』。これを選んだのは、端的に言って、公開までとても待ちきれなかったからという理由によります。16:45開場ということでしたので、30分くらい前にbunkamuraに到着しました。オーチャードホールの前には、すでに数十人の列が出来ていたのですが、それよりもプレス関係者が正面入り口前に殺到していた様子。無論、チャウ・シンチーの到着を待っていたのです。予定より遅れて到着したチャウ・シンチー、多くのフラッシュと女性陣の歓声に、ゆっくりと数回肯いていました。私も背伸びしながら彼の姿を遠目に確認できたわけですが、ふと隣に目をやると、高校生くらいの派手なファッションの女性が、ピンク色の花を1本だけ持って、所在無げな目で遠くを見つめていました。恐らく彼女は、チャウ・シンチーが目の前を通った時のためにその花を買ってきたのでしょう。しかし、彼女の思いとは裏腹に現実は残酷なもの。写真撮影すら儘ならず(兎に角警備が厳重でした)、ほんの1~2分後には、チャウ・シンチーも舞台挨拶のため劇場内に入ってしまったのです。残された彼女の、あの悲しそうな目を見て、なんだか可愛そうになりました。チケットを再度確認する彼女の手には、同日夜の回(こちらはヒルズのほう)のチケットも。ヒルズで花を渡せたのかどうか、もはや知る由もありませんが。
いざ開場ということで場内に入ろうとすると、厳重な手荷物チェックが。香港は海賊版が横行しているようで、それを危惧した主催者側の配慮ということでしょう。映画を観るのに金属探知機を当てられたのは生まれて初めてでした。
さて、初めて入ったオーチャード・ホールは、とても映画を観る環境ではありませんでしたね。私は3Fの最前列でしたが、あそこまでスクリーンを見下ろしたのは初めてです。目の前にはスクリーンをさえぎる鉄製の柵があって邪魔なことこの上なし。まぁそもそも映画館ではないのですからしかたありません。
舞台挨拶に特筆すべきこともありませんでしたが、チャウ・シンチー自身が、厳重なセキュリティチェックをしなければならなかったことを何回か詫びていました。監視下での映画鑑賞、これも始めての経験だったかと。
『カンフーハッスル』上映後は一端帰宅して、深夜の上映に備えました。と言っても、ただ酒を飲んでいただけですが。次の『ターネーション』は会場がヒルズでしたが、あいにくの雨模様だったために自転車での移動は断念。地下鉄を乗りついで六本木へと向かいました。到着したのは23:20ごろでしょうか。TOHO CINEMA自体には結構な人だかりが出来ていました。私が観た5番スクリーン前にも、『ターネーション』を待っている人が数人ほど。階下では、どこぞの映画監督と思しき人間がサイン攻めにあっていたりも。誰だったかは、まったくわかりませんでした。
ジョナサン・カウエット監督のデビュー作『ターネーション』には、監督自身の舞台挨拶がありませんでした。なんでも家庭の事情だとか。こういう理由もあまり聞きなれないのですが、映画を観て納得。その代わりに、監督とメールでやり取りした映画ライターの方(名前は忘れました)のトークが数分間ありました。気付けば予想に反して開場は結構埋まっていて驚かされたりも。ちなみに、『ターネーション』を選んだのは、サンダンスで話題になっていたこともありますが、それがどうやらドキュメンタリーだったから。およそTIFFには似つかわしくないその孤独な存在感に惹かれたのです。
上映後は電車も無いので、タクシーにて帰宅。blogを更新しようかとも思いましたが、あまりに疲れ果てていたので即寝。朝から渋谷と自宅を3往復もしたことに加え、『ターネーション』の内容にもかなりヤラレたことが原因だったのだと思います。
各作品については、また後で。初のTIFFは、非常に疲れました…
その疲れは未だに尾を引いていまして、折角天気は回復したのにとても映画に行く気にはなれないので、『春夏秋冬そして春』は来週に持ち越し。2日連続でヒルズに行くのもいやなので、『SAW』も来週になりそうです。
2004年10月30日
rain,rain,rain...
雨が降っています。
今日は夕方に1本、深夜に1本と東京国際映画祭に参加する予定なのに。あまりにやるせないので、昼間からウォッカなど飲んでいます。
ちなみに明日は『春夏秋冬そして春』を観にいく予定です。せめて『魚と寝る女』を観てから、と思っていましたが、今、何故かヴィデオを観る気分ではないのです。
この雨では渋谷~六本木間を自転車で回るのは難しそうです。
そう思うと何だか怒りがこみ上げてきます。何だ、この理不尽な雨は!
私は、今この瞬間、東京で最も怒れる男かもしれません。いや、そんなことないですね…
『2046』、ウォン・カーウァイはやはりウォン・カーウァイであること
 初めて『2046』の話題に触れたのは、確か『花様年華』を観るよりもっと前だったような気がします。『花様年華』でトニー・レオンとマギー・チャンの逢瀬の場となったホテルが、2046号室であることが示されたあのシーンが、妙に忘れがたかったのを覚えています。様々なトラブルがあったにせよ、結局『2046』は出来上がり、こうして日本でも観る事が出来たわけですから、長らく待っていた私としてはそれを喜ばずにはいられません。それが近未来を描いたSFであろうが、『花様年華』のようなメロドラマであろうが、それは紛れも無いウォン・カーウァイの作品であって、それ以外の何物でもないのです。上映前、私は意識的にそう思うようにしました。
初めて『2046』の話題に触れたのは、確か『花様年華』を観るよりもっと前だったような気がします。『花様年華』でトニー・レオンとマギー・チャンの逢瀬の場となったホテルが、2046号室であることが示されたあのシーンが、妙に忘れがたかったのを覚えています。様々なトラブルがあったにせよ、結局『2046』は出来上がり、こうして日本でも観る事が出来たわけですから、長らく待っていた私としてはそれを喜ばずにはいられません。それが近未来を描いたSFであろうが、『花様年華』のようなメロドラマであろうが、それは紛れも無いウォン・カーウァイの作品であって、それ以外の何物でもないのです。上映前、私は意識的にそう思うようにしました。
すでに公開から数日が経っていますが、初日に鑑賞した私と同様、(その理由はともかくとして)『2046』を待ち焦がれたであろう人々がその感想をインターネットに寄せているのを見るにつけ、その賛否両論ぶり(というより、多くは否定的でしたが)にほっと胸を撫で下ろしたりも。このサイトでも幾度か繰り返していることですが、ただ人を呼ぶことに特化された宣伝文句(そもそも宣伝とはそういうものですが)は決して鵜呑みにすべきではないという事実をまたもや再確認した次第です。これは宣伝等を批判しているというよりもっぱら観客側の問題、やはり観る映画は自分の判断基準で決めるほか無いという、私なりの主張に過ぎないのですが。
これまでミニシアターでしか公開されてこなかったウォン・カーウァイの作品が、大きな小屋や多くのシネコンでもかかっている様子からもわかるように、今回は、今まで全くウォン・カーウァイに興味がなかった人々が劇場に押し寄せるに足る大きな要因がありますから、意見が割れるのもまぁ予めわかっていたことではあります。作品にはそれに相応しい劇場があり、また、興行形態があってしかるべきだと思うのですが、今回のような“珍事”、今後のウォン・カーウァイ作品の国内における興行に悪しき影響を与えなければいいのですが…
ところで、すでに様々な場所で言及されていることではありますが、『2046』は、やはり60年代の香港を描いた『欲望の翼』(1990)や『花様年華』(2000)“以降”を描いた映画であることは間違いないでしょう。登場人物の名前や個々の関係性、職業、舞台等々(タイトルロールや文字列の挿入を指摘することも出来ます)を見れば、それは明らかです。ウィリアム・チョンやクリストファー・ドイルというスタッフにもそれは表れているといえるかもしれません。まずはその意味で、『2046』は、上記2作品を観た人間と観ていない人間をあからさまに振るいにかける映画だと思います。明らかに『欲望の翼』と『花様年華』を踏まえた記号(目配せ)が横溢していること、過去(の作品)に執着しつつ現在を生きなければならない宿命、これらはそのまま『2046』を物語る重要なファクターではないでしょうか。
さて、それでは『2046』とはどのような作品と言えるのか。最も、ここで『2046』の物語について言及しようというのではありません。端的に言って、その行為は無意味だと思うからです。よって、ここでは本作と前2作とを隔てている部分に着目しつつ、そこから見えてくるものについてを何点か指摘するにとどめます。
最も注目すべき相違点、それは『2046』がシネマスコープで撮られているということです。『2046』はウォン・カーウァイ作品にあって初めてシネマスコープ(1:2.35)で撮られた作品なのですが、美学的な要請なのか、それとも物語的要請がシネマスコープへと向かわしめたのか、正直に言えばわかりません。しかし、スコープサイズとは、作品そのものを決定づけるという点で、やはり決して見逃してはならないのです。
例えば、『2046』の画面を思い起こせば、カメラと撮られるべき対象との間に、例えば壁、ガラス、ドア、ビロードのカーテン等の夾雑物があり、それらが画面の多くを占めていました。いきおい、人物は画面の右、もしくは左に追いやられてしまうのです。この事実は『花様年華』においても見受けられたと思いますが、ヨーピアンヴィスタで撮られた『花様年華』に比べ、やはりシネマスコープの『2046』にいたっては、ほとんど凶暴といっていい程であったと指摘しておきたいと思います。
また、主要な舞台となるホテルの屋上を捉えたショットが数回リフレインされるのですが、やはり画面の多くはホテルのネオン看板が占め、左の方に人物が配されています。この場面が感動的なのは、そこにある空の色が、時になんともいえないグレーだったり、美しいブルーだったりと微妙に変化していたことです。人物の動きと空の色が奇妙にシンクロしているかのような、しかしそれが作為的というよりは、限りなく透明な印象を齎す、そんな気がしました。
あるいは、女性の歩く姿。とにかく美しい女性が揃いも揃った『2046』においては、女性が歩くシーンがとりわけ記憶に残っています。時にスローモーションで撮られたこれらのシーン、しかも、それはちょうど腰を中心に据えられた構図が多く、チャン・ツイイーやコン・リーの腰の線がいまだ頭から離れないほど。シネマスコープであのような構図に出会うとは思っていなかったので、それにはただ感動しました。
ところで、『2046』は多くの楽曲が使用されていますが、個々の音楽がどうというより、その音楽と画面の関係性について考えてみたりもしました。つまり、これは『花様年華』の時も同様だったと思うのですが、音楽が画面を明らかに干渉しているシーンが何度か見受けられたのです。ここでいう干渉とは、決して邪魔しているという意味ではなく、画面を音楽が制御しているといいますか、例えばしかるべき音楽がなり始めた時、しかるべき画面が始まるという、こう書いてみるとなんとも間抜けで当たり前のような話ですが、音楽の優位みたいなものを感じたのです。その時音楽は、決してbackgroundにではなく、foregroundとしてそこにあったのだと。
それにしても、『2046』におけるキャストの途方も無い魅力にはため息が出ました。とりわけ、トニー・レオンの美しさは、どうもただごととは思えません。特に、机に向かって煙草の煙を燻らせながら文章を書く場面。あの表情、顔に落ちる影、指、そして煙までもが美しく、それは彼が演じる役柄の残酷さともあいまって、まさしく“残酷な美”と言うべき凄みをスクリーンに放射していました。女優陣もまた、総じて輝いていたと思います。チャン・ツイイーはもはや言うまでも無いと思いますが、私が印象的だったのはそれほど多く出演しなかったコン・リーです。彼女とトニー・レオンとの別れの場面、あの匂い立つようなキスシーンのエロティックさと激しさ。唇が離れた直後の表情。もう一度見たいシーンの一つです。
結局、『2046』は、これまでのウォン・カーウァイ作品といささかも変らなかったのかもしれません。断片と統合をひたすら繰り返す映画作家であるウォン・カーウァイは、全ての人間の思惑の遥か彼方で、やはりウォン・カーウァイでしかない。しかしながら一つだけ付け加えれば、『2046』には、ウォン・カーウァイの混乱と苦悩がそのまま全編に染み込んでいると言う意味で、永遠に未完成のような気がしてなりません。他でもないこの印象だけが、これまでの作品とは大きく異なっているのです。
2004年10月27日
『2046』の作品評、難航中
これではわざわざ初日に観た意味が無いのではないか、と自問してしまいますが、いち早くその作品評を書き上げようと思っていた『2046』、その難解さゆえか、なかなか筆が進みません。予習が足りなかったのか、復習が足りなかったのか、その両方かどうかはわかりませんが、やはりもう一度観る必要があるのかもしれません。とはいっても、今週末は東京国際映画祭に行かなければなりませんし、そうかと思えば、キム・グドクの新作も始まってしまうし、平日は映画以外の予定が。さて、どうしたものでしょう。
そもそもウォン・カーウァイの作品について何がしかの文章を綴ることに困難が伴うlことなど知れたことですし、その断片性や美学をとっても、一度観たくらいでは語り得ないことも承知していた気がするのですが…いや、参りました。
とりあえず、『2046』に関して何らかの結論を出すのは難しそうです。というより、無意味なので今回そのようなアプローチは止めようかと。とりあえず、今日の時点で『シークレット・ウィンドウ』に次いで興行成績は第2位のようですが、公開規模、宣伝と作品の激しすぎる乖離等を考慮すると、なかなかまずいことになりはしないかという心配ばかりがよぎります。
いずれにせよ、何とか日曜日までには書き上げなければと、自らにプレッシャーをかけつつ……
2004年10月25日
『コラテラル』、巻き込まれた果てに…
監督はマイケル・マン。彼を初めて知ったのは、高校生の時に観た『刑事グラハム 凍りついた欲望』だったと記憶しています。少なくとも『レッド・ドラゴン』より面白かったような気がするのですが、もう何年も観ていないので定かではありません。初期の作品は観ていませんし、あまり適当な事は言えないのですが、私の中の“マイケル・マン像”に直結するイメージ=言葉は“対決”というものになろうかと。刑事vs犯罪者、個人vs組織、部族vs部族、等々。ただし、広義の“対決”はアメリカ映画のあらゆるジャンルを包括してしまうかも知れず、そう考えると“対決”を全く描かない監督の方が少ないのかもしれません。と、いきなり自ら出鼻を挫いたわけですが、やはりここでは強引に、対決の映画(と言えなくも無い)『コラテラル』について、話を進めます。なお、いつものように結末に触れまくっています。といっても、この手の映画はネタバレとかそういう次元で面白かったりつまらなかったりするものではないかと思うのですが、一応、公開前ですので。
例によって原題である『COLLATERAL』の意味を調べてみると、公式サイトには、“間違った時に、間違った場所に偶然居合わせてしまうこと=巻きぞえ”とあります。まぁ全くもってそのまんまです、この映画は。極めて真っ当なタイトルではありますが、果たしてそれだけで終わってしまう映画かということです、問題は。仮にそうだとするなら、『コラテラル』は面白みに欠ける映画だと言わざるを得ないのですが、“巻きぞえ”という主題以外の部分で、少なからず興味深い部分を発見できたのは幸いでした。
今回、トム・クルーズは冷酷な殺し屋という触れ込みですが、このフレーズが、相も変らぬ捏造された宣伝文句であるという事実は、観た方であれば大いに納得できることだと思います。というのも、トム・クルーズ演じる殺し屋は、実はかなり人間味のある人物に見えてしまうからです。頭は切れるし、フィジカルも屈強なこの殺し屋は、しかし、最終的な対決には勝てないでしょう。では、何故ジェイミー・フォックス演じる凡庸なタクシー運転手に負けることになるのか。
いささか倒錯的ですが、トム・クルーズの敗北は、まさにトム・クルーズ自身がそのように仕向けたとすら思ってしまうほどだったのです。実際、ジェイミー・フォックスが、とりわけフィジカル面でトム・クルーズに到底太刀打ち出来ないという事実は、映画の中盤で簡単に証明されてしまいます。この時私は、ラストシーンは絶対に銃による対決になるだろうと確信しました。アメリカ映画における一つの“型”ともいえるラストの殴り合い、これはまずありえないだろうと。であれば、この1対1の対決は、銃に頼らざるを得ないと考えたわけです。もちろん、銃の腕前もトム・クルーズの方が圧倒的に上です。というよりも、ジェレミー・フォックスは、銃すら撃ったことがない人間として描かれています。だとすれば、最後に勝利するものが持つべき強さ、それは“運”に他ならない。強運の持ち主こそが勝つのだという、一見必然を欠いた、だからこそ現われてくるご都合主義が、しかし、かなり弱いながらも(実はこう書かざるを得ないところが、この映画の限界でもあると思いますが)、ラストへと収斂されていたこと。もし『コラテラル』に美点があるとすれば、その部分ではないでしょうか。
若いチンピラめいた2人組を、トム・クルーズが瞬間的に撃ち殺すシーンがありました。その時、彼は律儀に両手で銃を構えて銃を撃つのです。私が『ヒート』において印象的だったのは、まさしく、ロバート・デ・ニーロが“正確に”銃を構える姿勢だったのですが、それを今度はトム・クルーズが反復しているかのようです。相手も銃を持っているがゆえに、一瞬の動きで勝負が決まる、こんな切羽詰った状況であったにもかかわらず、彼はきちんと両手で銃を構える。私はここに、ある種の違和感を感じました。あの律儀さ、というか几帳面さが、しかし、自分自身を追いつめていくことになったのだと気づいたのは、映画が終わった後でしたが(そういえば、3人目のターゲットを殺す前にも、彼はかなり丁寧に話を聞いてやるのです)。
対するジェイミー・フォックスですが、彼は始めのうち、あたかも、目の前にある事物に即時に反応しつつ、行動を起こすことの出来ない人間であるかのように描かれていました。将来の夢に対してもしかり、女性に対してもしかり、そして殺し屋にたいしてもまた…そのようにして12年もタクシー運転手を続けざるを得なかった彼が、そんな自分の弱さを克服していくことで最後に勝者になるのですが、この手助けをしていたのが、図らずもトム・クルーズだったということは、もはや言うまでもないでしょう。それが最も端的に表れていた場面が、あの4人目のターゲットの資料を取りにジェイミー・フォックスが依頼人のもとを訪ねるシーンです。あの時点でジェイミー・フォックスは、生き残るために、という理由だけでは到底説明されないような、劇的な飛躍を見せていました。その後「もう何も失うものはない」とまで決意させ、捨て身のヒーローを演じることになるのですが、そうなったのも、トム・クルーズがそんな“飛躍”に至る“試練”をジェイミー・フォックスに与えたからに他なりません。あの凡庸なタクシー運転手の成長を誰よりも願っていたのは、他でもない、トム・クルーズなのではないか、と思わせるほどです。
ラスト、地下鉄車内における至近距離の銃撃戦は、ほとんど出鱈目に撃ちまくったジェイミー・フォックスの弾がトム・クルーズにたまたま当たった結果となりましたが、これも、前述した“運”が彼に備わっていたからに他なりません。やはりきちんと構えずにはいられないトム・クルーズより、出鱈目とはいえ先手を打ったジェイミー・フォックスのほうに“運”が向いていたからです。自らの暗い記憶(彼の苦悩とニヒリズム)をなぞるように車内で死んでいくトム・クルーズは、結局、冷酷な殺し屋というよりは、自分の死に様を他でもない、ジェイミー・フォックスに看取られたいがために、執拗に彼を追いかけていたのではないか、などと思ったりもしました。
しかしながらどうしても言わなければならないと思うのは、『コラテラル』にはやはり、たいして感動できなかったということです。少なくとも、人に薦める映画では無いような気がしました。これを薦めるのであれば、今、他に薦める映画が間違いなく5本はありますから。ただし、俳優陣の演出は決して悪くありません。
2004年10月24日
『ディボース・ショウ』、回らないスクリューボール
コーエン兄弟の新作は封切りで観るようにしていたのですが、ここ最近の2作品については何故か観ておりません。理由はもはや忘れましたが。だからと言って決して観たくないわけではないので、遅まきながらヴィデオにて『ディボース・ショウ』を。
コーエン兄弟をどのように評価していいものか、これはなかなか微妙な問題だと言わざるを得ません。端的に言って、あの過剰ともいえるユーモアを好きになれるかどうか、だと思うのですが、それぞれのギャグや身振りに笑うことがあっても、一つの作品としてそれが長く記憶に残るかと言うと、そこでふと考え込んでしまうのです。つまり、突出した“部分”だけが記憶に残る作家なのではないかと。例えば、キャスティング(特に脇役)の妙。俳優によって歌われるカントリーミュージック。あるいは、とぼけた“間”とそれに続く“大袈裟な”アクション。それらが全体として、“なんとなく”上手くまとまっている感じがしないでもない、と言う部分こそがコーエン兄弟の映画なのではないかと、今は考えています。
『ディボース・ショウ』も多分に漏れず、そのような映画として観ました。本作は、スクリューボール・コメディの変奏だといえるのかもしれません。そこには、ブルジョア的な男女の軽妙な会話が作品の多くを占めることになるでしょう。しかし、そこに繰り広げられるであろう“マシンガンのような会話”がこの映画にはほとんど見当たりません。
相変わらず、細部にはところどころで笑うことが出来ます。個人的にはコーエン兄弟の得意技だと思っているんですが、誰かが誰かを始めて紹介する場面(広く言えば、初めて対面する場面)に見られる作りきった笑顔とその直後の困惑した表情の温度差などはいつも可笑しいですし、やっと騙されていたことに気付いたジョージ・クルーニーといかにもコーエン的脇役ポール・アデルスタインが顔を見合わせて叫ぶ場面にいたっては、それがコメディ映画にあってお約束的だとわかっていながらも、その“過剰さ”に笑わざるを得ないとも言えるのです。にもかかわらず、スクリューボール・コメディの核心がそこには無い。
いや、もしかすると『ディボース・ショウ』はやはり、スクリューボール・コメディではなく、“コーエン流”のラブ・ロマンスなのかもしれず、そう思うとそれほど悪くはないのです。現代においてスクリューボール・コメディを題材にすることの難しさ(すでにハワード・ホークスという巨人がいるわけですから)を承知の上で、そうではないコメディを撮ろうとしたのかも。そうなってくると、この『ディボース・ショウ』は、やっぱりそれほど悪くはないという結論にならざるを得ません。まぁ、これはこれで…ですね。
2004年10月22日
東京国際映画祭2004
23日から開催される東京国際映画祭2004。渋谷に住む人間としては、メインの会場がほとんど六本木に移ってしまった事態になんとも複雑な心境ですが、それでも2本ほど鑑賞するつもりです。本当は3本観ようと思っていましたが、「アジアの風」部門の『狂放』(レスト・チェン監督)は、チケットが完売していまして、そのときばかりはただひたすら怒りが込み上げてきて、『狂放』が上映される日は、bunkamuraに隕石でも落ちてくることを願ったりもしました。ただし、実際にそんな事態がおこれば、30日の『カンフーハッスル』も観られなくなるので、そんな事件が起きないことを逆に願ってみたり。いつもどおりの通俗的な発想に立ち返るわけです。
さて、30日は『カンフーハッスル』を観た後、夜中の12時から『ターネーション』を鑑賞する予定です。最近は妙にドキュメンタリーづいている気がしてならないのですが、11歳のときから自らにカメラを向け続けたと聞いただけで、こちらの期待はただ膨らむばかりです。
ちなみに、Yahoo!オークションで『狂放』のチケットを探しましたが、全く興味の無い韓流映画はそれなりの値段で出品されているのに、やはりまだその名が知られてはいない台湾映画のチケットをすすんで買うような人は、オークションに出品するなどという愚行には走らないのでしょう。悔しいですが、納得せざるを得ません。
で、明日は『2046』と『コラテラル』を先行オールナイトで。どちらも眠気を誘うような映画ではなさそうなので、軽くワインでも引っ掛けてから観にいくとします。
2004年10月20日
TOP ILLUSTをさりげなく変更
今回も『軽蔑』の1シーンより。
いや、厳密に言うと前回のマラパルテ邸は『軽蔑』には登場しませんが。
フリッツ・ラング監督『オデュッセイア』が“本当に”実現していたら、それはすごい映画になっていたでしょう。
今日はものすごい雨ですが、22号の時みたいに、こんなときこそ劇場に足を運べば快適に映画を鑑賞出来るんだろうな、と思ったりも。しかし、今日は観たい映画がないのです。
2004年10月19日
建築と映画と超間接的な賛辞
映画において、建築の果たす役割は非常に大きいと思います。というのも、建築物が全く出てこない映画はほとんど無く、時に背景として、時に主要な舞台として、何らかの形として画面に登場するからです。人は無意識のうちに、衣・食・住という言葉を口にしますが、それはそのまま映画において重要な要素でもあるのです。テキサスのみすぼらしい小屋であれ、豪奢なアパルトマンであれ、住空間を抜きにした映画など、容易に思いつきません。
すでに当サイトでも何度か言及しているゴダールの『軽蔑』。もちろん、マラパルテ邸に触れずにこの映画を語り得ないように、バルドーとピッコリが住むアパルトマンのインテリア(インテリアも広義の建築として捉えることができます)やそのアパルトマン自体を仰角で捉えたショットを抜きに『軽蔑』は語りえません。
『サイコ』も『去年マリエンバードで』も『熊座の淡き星影』も『ソナチネ』も『ミスティック・リバー』も、建築に対する繊細な感性なくして撮られ得なかった作品だと思うのです。
唐突にこのような話を持ち出した理由、それは、映画を観るに当たって、建築(装置)と人物の関係はことのほか重要だと言う事実を言いたいがため、ではなく、ちょっと気になったトークイベントがあるからという、至極単純な理由に拠ります。建築家の話を聞くことは、そのまま、映画監督の話を聞くことに等しいのではないか。そう思ったまでです。
ということで、私には何の特にもならない告知を。
「青木淳 JUN AOKI COMPLETE WORKS |1| 1991-2004』刊行記念トーク〜「つくるときにおもいめぐらすこと」というトークイベントが催されるようです。今、青木淳という名前に反応しえない人間に建築はおろか、映画に言及するのもほとんど困難ではなかろうか、と言ってしまいたくなるほど、氏の建築には“物語(ロマン)”があり、“論理(ロジック)”があります。映画好きであれば、この2語に反応してもおかしくないのではないでしょうか?
2004年10月17日
『jackass the movie 日本特別版』、言葉を奪う挑発性
映画は面白ければいい、という意見もあるでしょう。もちろん、映画など面白くなくたっていいのだ、という意見があってもおかしくはありません。私自信、まだその問いに対する答えを見出せずにいますが、しかし、これだけは万人に共通して言えることではないでしょうか。つまり、人生は面白ろいうががいい、と。
『jackass the movie 日本特別版』は、そんな人生への問いを投げかけてくれた、示唆に富んだ作品でした。予め断っておけば、この映画の前にどんな言葉も無力なのです。その映像は言葉という言葉を完全に圧倒し、あらゆる賛辞も野次も、等しく敗北し続けるでしょう。映画を観てそのように感じたのは、間違いなく『ヴァンダの部屋』以来です。観客から言葉を奪う映画、それが『jackass the movie 日本特別版』なのです。
言葉を奪う代わりに『jackass the movie 日本特別版』が容赦なく強いるもの、それは、“笑い”に他なりません。ジョニー・ノックビル率いるjackassは、“笑う”という人間特有の行為を、極めて純粋に追求しているかのようです。ここで強引にジョルジュ・バタイユの言葉を借りれば、“笑い”の本質は“恐怖”の表れであり、これをまたもや強引に飛躍させれば、常に死と隣りあわせでなければ、真に“笑う”ことは出来ないということになるでしょう。その真理をjackassの連中は体一つで実践して見せます。ここに、途方も無い感動が生れ落ちることになるのです。
jackassは多くの人間によって、“バカ”だと断定されてきました。それが正しい指摘だとしても、単なる揶揄だとしても、やはり無力な言葉なのであり、つまりいかなる指摘も無意味だということになりますが、それでもそれらの言葉に納得することは容易い。例えば、下記の写真をご覧ください。

誰が何と言おうと、こいつは“バカ”だと断言したくなります。ワニに自分の乳首を噛ませる理由などあるはずがない。それがたとえ子ワニであったとしても、やはり同じことです。しかし、彼らはそんなことは百も承知しています。常に何らかの理由や必然を求めてしまう通俗的な人間をこそ、笑い飛ばしているのがjackassなのですから。そして、jackassを観て笑ってしまう人間もまた、あまりに通俗的なのです。自らの通俗性を隠蔽しようとすればするほど、観るものはただ、笑うしかないからです。
jackassには“笑い”という要素のほかに、もう一つ見落としてはならない側面があります。それは、誰もが持ってはいるものの、自分自身でそれを見ることの出来ない、極限状態に置かれた人間が見せる根源的な表情です。生理的嫌悪感を強いるようなその表情は、観るものの感情を揺さぶらずにはおきません。彼らは、常に本気です。本気で恐怖し、本気で痛がり、本気で嘔吐し、本気で笑う。これこそが感動的なのです。事実、バカをやる彼らの傍らには、それを観て本気で爆笑している仲間の存在があります。カメラは、バカをやらかす人間を映すのと同じくらい、それを観て爆笑する人間をも映し出していたことを見落としてはならないと思います。
いずれにせよ、『jackass the movie 日本特別版』は、あらゆる意味で観客を挑発する映画であるという事実は揺るぎないと言えるでしょう。
最後に付け加えると、映画において、リアルな嘔吐を目撃したのも『ヴァンダの部屋』以来でした。劇場では私の前に恋人同士と思しきカップルが座っていたのですが、嘔吐場面で目を背けていたのは決まって男性の方だったというのが印象的でした。
あ、それともう一つ。
今回の【映画秘宝スペシャル 秘宝ジャッカス祭り〜世界のバカ大集合〜】は2本立てで、もう1本『ヘブンズ7』といういかにも出鱈目なタイ映画も上映されましたが、冒頭から全くと言っていいほど乗れず、それでも我慢し続けて40分ほど観続けたのですが、その常軌を逸した弛緩ぶりにあまりに腹が立ったので、恐らく生まれて初めて、途中退出しました。秘宝編集長・田野辺氏の熱い推薦を聞いていただけに、あまりに残念な結果です。いくらバカ映画といっても、それだけで何でも許されるのかというとそれは大きな間違いです。そう思ってしまうほど、『ヘブンズ7』には“真面目さ”が感じられなかったのです。この“真面目さ”は、バカ映画にこそ必要とされる要素なのではないでしょうか。
よって、『ヘブンズ7』については、ノーコメントとさせていただきます。
2004年10月16日
東京ファンタスティック映画祭リポート
今年は映画祭初出陣の年ということもあるので、参加した映画祭については、簡単なリポートを綴ろうかと思います。現場の状況、客層、雰囲気など、それぞれ特徴もあるのでしょうし、来年行かれる方の参考にもなるかも知れないので。もちろん、作品については別途書きます。
今年で20周年といいますから一応歴史ある映画祭といっていい「東京ファンタスティック映画祭」3日目。目当ては『jackass the movie 日本特別版』。本当は今日の夜中に上映される『SAW』も観たかったのですが、どうしても予定がありまして、泣く泣く断念。『SAW』は結局、その残酷な描写ゆえに、アメリカでの公開が延期され、新たに編集された模様。今回上映されるのは、アメリカで公開禁止になった貴重なバージョンらしいのです。正式に公開されたら初日にでも観にいこうかと思います。
映画祭の舞台は新宿ミラノ座。四方を劇場に囲まれた、あの歌舞伎町の広場では、映画祭にちなんで特別に出展されたカフェなどがあり、何やらライブ演奏などもされていたようです。
開場予定時間の1時間ほど前に到着した時には、約20人ほどの人がすでに列をなして待機していました。全席指定のはずなのに、何故列が? と疑問に思っている私も、ちゃっかり1時間前に到着しているのですが、私の場合は、どんな映画もそれくらいの余裕をもって劇場に入る習慣がありますので、同じとはいえません。
開場30分ほど前になると、劇場前には多くの観客たちが溢れかえっていました。それらの人々に目を凝らしてみると、男性が圧倒的に多く、心なしか、坊主・ヒゲ・眼鏡率が高く、普段私が付き合うことのない人(これはあくまで便宜上こう書いたまでで、他意はありません)が多く目につきました。年齢層は20~30代が中心といった感じで、所謂“秘宝系”と言われている男性が圧倒的に多かったのだと思います。上映される作品が作品ですから、当たり前と言えば当たり前の結果です。何故か、これから公開される『約三十の嘘』のパンダ(詳しくは公式サイトをご覧ください)の気ぐるみを着た(恐らく)男性が突然劇場前に登場しまして、ほとんど場違いなダンスをしてみたり、並んでいる観客にちょっかいを出して苦笑を誘ってみたりしていました。幸い、しかめ面で本を読んでいた私には絡んできませんでしたが。
開場後、何故列が出来ていたのかを理解しました。限定のTシャツを購入するためだったんですね。“秘宝系”の人々と言うのは、そういうグッズを買い求める傾向にあるのでしょうか。
指定された席は結構いいポジションで、多分満席に近かったと思います。両サイドには立ち見と思しき観客もいましたから。
『jackass the movie 日本特別版』上映前には、あのIZOを演じた中山一也氏の舞台挨拶が。何でも、『IZO』に感銘を受けたタランティーノとの仕事が正式に決まりそうだとか。こういう勢いはやっぱり大事なんですね。どんな映画になるかは見当もつきませんが、まぁ初日に観にいくことになろうかと。
最後になりますが、あれですね、多分よほどのことが無い限り、この映画祭には二度と参加しないだろうと思います。端的に言って、私には合わない映画祭のような気がしました。早く外の空気を吸いたい…2本目を観ている最中そんなことばかり考えていて、結局40分ほどで出てしまったくらいで。もちろん、最大の理由は『ヘブンズ7』という作品が、度を越えてつまらなかったからなのですが。
『jackass the movie 日本特別版』については、後ほど。
2004年10月15日
ヴィスコンティ映画祭〜『異邦人』『疲れ切った魔女』
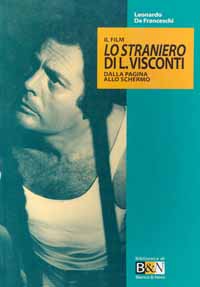 日本での上映は20年ぶりだと聞いて駆けつけた『異邦人』は、個人的な結論から言うと、途方も無い傑作というわけではありませんでした。しかし、それは果たして、監督であるルキノ・ヴィスコンティが原作に限りなく忠実たろうとした結果、私が“ヴィスコンティらしさ”を、あまり実感できなかったということが原因なのか。だとすれば、その“ヴィスコンティらしさ”とやらはいったい何なのでしょう? 世間で認識されている彼のイメージ、すなわち、“絢爛豪華にして、貴族的・退廃的な美を描いた巨匠”などは、彼の作風の一端を担ってはいたものの、それらとヴィスコンティが等号で結ばれてしまうことは、やはりあまりに短絡的だと(自戒を込めつつ)言わざるをえません。なぜ『熊座の淡き星影』や『異邦人』が、私たちの前から遠ざけられてきたのか。それには、これまで多くの日本人がが描いてきたであろう“凝り固まったイメージ”が、少なからず影響していたような気がするのです。その意味で、今回企画された全作品上映は、ヴィスコンティに纏わりつく“貧しいイメージ”から解放させるいい機会だったのではないでしょうか。今回の映画祭を観るにあたって、敢えてそのようなイメージから遠い作品ばかり選んだのも、その思いがあってこそです。ルキノ・ヴィスコンティは、決してある角度からだけ観られるべき監督ではないのです。ジャン・ルノワールの助監督から映画に関わり、ネオ・レアリスモへと発展させたという歴史的事実はそのまま、彼の豊かな感性や挑発性、何より繊細な人間性を表しているのだと、今改めて考えてみても無駄ではないと思うのです。
日本での上映は20年ぶりだと聞いて駆けつけた『異邦人』は、個人的な結論から言うと、途方も無い傑作というわけではありませんでした。しかし、それは果たして、監督であるルキノ・ヴィスコンティが原作に限りなく忠実たろうとした結果、私が“ヴィスコンティらしさ”を、あまり実感できなかったということが原因なのか。だとすれば、その“ヴィスコンティらしさ”とやらはいったい何なのでしょう? 世間で認識されている彼のイメージ、すなわち、“絢爛豪華にして、貴族的・退廃的な美を描いた巨匠”などは、彼の作風の一端を担ってはいたものの、それらとヴィスコンティが等号で結ばれてしまうことは、やはりあまりに短絡的だと(自戒を込めつつ)言わざるをえません。なぜ『熊座の淡き星影』や『異邦人』が、私たちの前から遠ざけられてきたのか。それには、これまで多くの日本人がが描いてきたであろう“凝り固まったイメージ”が、少なからず影響していたような気がするのです。その意味で、今回企画された全作品上映は、ヴィスコンティに纏わりつく“貧しいイメージ”から解放させるいい機会だったのではないでしょうか。今回の映画祭を観るにあたって、敢えてそのようなイメージから遠い作品ばかり選んだのも、その思いがあってこそです。ルキノ・ヴィスコンティは、決してある角度からだけ観られるべき監督ではないのです。ジャン・ルノワールの助監督から映画に関わり、ネオ・レアリスモへと発展させたという歴史的事実はそのまま、彼の豊かな感性や挑発性、何より繊細な人間性を表しているのだと、今改めて考えてみても無駄ではないと思うのです。
実際、『異邦人』は、傑作とまでは言いませんが、駄作ではないのです。いやむしろ、かなり楽しめる作品だったと言えるでしょう。アルベール・カミュの原作を読んだのは遠い昔で、詳細など完全に忘れていたのですが、“不条理”という若干手垢にまみれた言葉を深く理解している必要など決してなく、マルチェロ・マストロヤンニの器用な演技に改めて驚いてみたり、アンナ・カリーナが、ゴダール時代とは異なってまさしく“役を演じている”様に出会えたら、それだけで私は満足でした。さらにアンナ・カリーナについて言えば、彼女が公判で泣く場面など予想だにしていなかっただけに、何とも不思議な、それこそ“不条理”な感動にとらわれたほどです。もちろん、これまで一度も観たことのなかった裸体を目撃したときなどは、はっきり言ってかなり興奮状態にあったと、ここで告白します。
中盤、ちょうどマストロヤンニ演じる主人公とその仲間たちが、海を背景にアラブ人2人組と争う場面で、カメラが海側から浜辺にいる5人の男たちを映していたシーンがあったと思います(もしかすると、浜辺にはマストロヤンニしかいなかったかもしれませんが、詳しくは思い出せません)。その前に、普通に浜辺から海を映す場面があり、それはそれで後の『ベニスに死す』へと繋がるであろう美しいシーンではありましたが、海側から浜辺を映したのを観たのは、私の貧しい映画体験を思い起こせば、北野武『DOLLS』がすぐさま思い起こされ、その意外なシンクロニシティも少なからず感動的でした。
次にこの作品を観られるのはいつになるのでしょう。
もちろん東京で上映されるとなれば絶対に観にいきますが、それまでにヴィスコンティ好きと自称する人間に会う機会があれば、絶対に『異邦人』について語り合いたいという気がしました。私はとりわけヴィスコンティに強い執着を持っているわけではありませんが、やはり、この貴重な機会を逃した人間に、ヴィスコンティが好きだとは言ってほしくないからです。
同時上映された『疲れ切った魔女』については、そのタイトルバックが印象的でした。ちょうど、今月号の「pen」を読んだところでしたから。『疲れ切った魔女』は一応コメディということになっているようですが、何と言っても、シルヴァーナ・マンガーノの化けの皮をはがすシーンでしょう。美しいものがその虚飾をはがされていく様…これはやはりヴィスコンティ的なのでしょうか。
2004年10月14日
『アイ、ロボット』、逸脱の無い説話が示すこと
 映画を観る時、私はそのタイトル(多くの場合、原題)に注目するようにしていますが、それはやはり、作家がその作品に対し、何をも表さないタイトルをつけるはずがないという、言ってみればあまりに当たり前な事実に意識的でいようと思っているからです。
映画を観る時、私はそのタイトル(多くの場合、原題)に注目するようにしていますが、それはやはり、作家がその作品に対し、何をも表さないタイトルをつけるはずがないという、言ってみればあまりに当たり前な事実に意識的でいようと思っているからです。
さて、『アイ、ロボット』は原題を『I,ROBOT』を記します。“I am ROBOT”でも“I and ROBOT”でもありません。邦題では、そのまま直訳して『アイ、ロボット』となっていますが、さて、この“I”と“ROBOT”はどのような関係にあるのでしょうか。
『アイ、ロボット』は、一般的な視点に立てば、一先ずSFというジャンルに括る事が出来ます。現代において未来を描くということは、すなわち、CG(VFX)が画面の多くを占めるということになります(『CODE46』はその意味で、少なからず野心的だったと言えると思います)。そして、私たちが未だ見ぬ機械やアクションが、当たり前のように描かれていくのです。しかしだからといって、主題論的に『アイ、ロボット』が新たな何かを生み出していたかというと、それには首を傾げざるを得ません。ロボットが意思を持ち人間を支配しようとするだとか、意思を持ったロボットと人間との間に、“人間的な友情”が生まれるだとかは、すでに多くの映画が描いてきたことだからです(例えば、『ターミネーター2』)。たとえそのロボットのデザインが比較的斬新でも(見た目も動きの滑らかさも、人間のそれに近かったといえるでしょう)、ふと人間的な態度をみせたとしても(無表情だと思われていたロボットが、遂には目で表現するに到ったことは、新しかったと言えるかもしれません)、映像的にはあまりに“万能”な現代において、やはりそれだけで観客が感動するとは思えません。にもかかわらず、『アイ、ロボット』が多くの観客を集めているのです(国内観客動員数は、今この文章を書いている間もきっと1位でしょう)。
実のところ、『アイ、ロボット』を見終えた後、予測されたであろう“憤り”とともに劇場を出たわけではありません。意外にも(!)、それほど悪くないとさえ思いました。SFと呼ばれるものにはほとんど興味がなく、もちろんアイザック・アシモフの著作など一冊と読んだこともなく、思えば、大掛かりなアクションと常にその口から飛び出す過剰とも言えるブラックジョークとが、上手い具合に調和していることが評価されているのかもしれないウィル・スミスを積極的に好きなわけでもない私が、そう思うに到ったのは何故か。アレックス・プロヤスという監督に対する期待からでしょうか。それがゼロだとは言えませんが、『スピリッツ・オブ・ジ・エア』と『クロウ/飛翔伝説』を観ただけの私です、それすらかなり曖昧といわざるを得ません。それらは、私を途方に暮れさせるほどの作品ではなかったからです。では、何故か。
ここで結論を言ってしまえば、『アイ、ロボット』の説話的展開にこそ、その理由を求めることが出来るのだと思うのです。
これまでのSF的範疇を大幅に踏み出すことはありませんが、アメリカ映画的な御都合主義を支えに、結局は“ヒューマンドラマ”として(相手がロボットなのですから、これほどの皮肉もありませんが)物語を全うしたこと。主人公の抱えるトラウマを随所に示しながら、ラストに向けて、そのトラウマの克服こそが主題だと感じさせた映画、私が観た、『アイ、ロボット』はそのような映画だったのです。そんな視点に立つ私は、冒頭の問題に立ち返れば、『I,ROBOT』というタイトルにも肯いてしまうのです。つまりそれは、“I”(半分ロボットと言えなくも無いウィル・スミス)と(文字通りロボットではあるけれど人間に近い感情を持つに到った)“ROBOT”との、曖昧な境界線を“,”で結んでいるのではないか、という結論に到った、ということなのです。そして、これが『アイ、ロボット』の主題ではないかと。
その意味で、『アイ、ロボット』は決して駄目な映画ではなかったのだと思います。この映画に駆けつける多くの観客が私と同じ思いだったとまではもちろん言えません。いかにも“『マトリックス』以後”と言えそうなアクションやスローモーションに感動した人も居るでしょうし、あの虚構としてのシカゴに心から新しさを感じた人がいてもいいでしょう。しかし、『アイ、ロボット』が結果として多くの観客を集めているのは、純然たる事実です。そう断言するのにかなりの躊躇があるとは言え、『アイ、ロボット』のような映画の優位は、アメリカ映画の持つ“屈強さ”みたいなものを示しているのではないでしょうか。
2004年10月13日
『イズ・エー』、映画とモラル
 時計の針が時を刻むシーンがクローズアップで撮られる場合、それが“残された時間”を強調することになるのは映画史的に見てもほぼ明らかです。本作における文字盤のクローズアップも、“時限爆弾が爆発するまでの残り時間”をこそ強調するため、であればこそ、これも常套ですが、「カチッカチッ…」という音がそのシーンに律儀に被さることになるのです。あるいはその“残り時間”とは、犯人の少年に訪れるであろう“しかるべき”結末に至るまでのそれだったのかも知れません。
時計の針が時を刻むシーンがクローズアップで撮られる場合、それが“残された時間”を強調することになるのは映画史的に見てもほぼ明らかです。本作における文字盤のクローズアップも、“時限爆弾が爆発するまでの残り時間”をこそ強調するため、であればこそ、これも常套ですが、「カチッカチッ…」という音がそのシーンに律儀に被さることになるのです。あるいはその“残り時間”とは、犯人の少年に訪れるであろう“しかるべき”結末に至るまでのそれだったのかも知れません。
『イズ・エー』において、爆発する瞬間はその“音”だけで表現されていました。2回目の爆発ではビルの一部が吹っ飛ぶシーンも観られましたが、それは第二波としての爆発であって、最初の爆発はやはり、“音”によって示されているのです。
何を“省略”して、何を“見せる”のか。本作が長編第一作目となる藤原健一監督は、その問題に意識的だったのではないかと思います。何かを省略することも何かを見せることも、この劇映画においては等しく積極的な役割を果たしていたのではないでしょうか。
『イズ・エー』というタイトルにはどんな意味が込められているのでしょう。主語に相当する何かを欠いたこのタイトルに惹かれて映画を観た私にとって、この問題は非常に興味深い。作品のテーマから類推すれば、Aとは犯人の少年を指すことは間違いないでしょうが、匿名の少年犯罪者と解することも出来ます。だとするなら、“○○ is A”の○○に当たる部分に相当するのは、what、who、whyなど、A(少年犯罪者)に対する数々の疑問詞ということになるのではないか、これはあくまで私の考えです。一体どうしてそのような犯罪を犯すことになったのか、何故他の少年ではなくAなのか、そもそもAとは何なのか? 現在、少年犯罪が起こるたびに持ち上がるこれらの疑問。しかしながら、そんなことは問題ではないとでも言うように、このタイトルは曖昧なままです。恐らくこの映画における問題は、残された人物(被害者の父であり加害者の父でもある)に視線を向けることによって見えてくるものに存しているのです。
ラストシーンは様々な意味で、象徴的でした。
結局、Aである少年も、その父親も、どうしたらいいのかわからないのです(事実、2人にはそういった台詞がありました)。そんなどうしようもない状態を、津田寛治演じる被害者の父が、“怒り”(『seven』のブラッド・ピットが犯人を前に囚われていた感情と同じものです)によって裁いてしまう。明らかにモラルに反する行為だとわかってはいても、ここでの結論はそういうことです。モラルより感情を優先させたこのラストシーンは、内藤剛志による、まさしく迫真の演技とあいまって、ある程度の説得力を持ち得ていたと思います。さらに言えば、少年が仲間を拳銃で殺すシーンはやはり見せず、彼が撃たれるラストは正面から見据えていたという事実。見せるべきは、あのAの死だった、ということでしょうか。
この結論に異を唱える人間ももちろんいるでしょう。しかし、言うまでもなく『イズ・エー』は映画なのです。映画がモラルを遵守しなければいけない理由など、ありはしないのですから。唯一確かに言えるのは、時計の針はやはり正確に時を刻んでいた、と言うことだけなのかもしれません。
2004年10月12日
ヴィスコンティ映画祭〜『熊座の淡き星影』『ある三面記事についてのメモ』
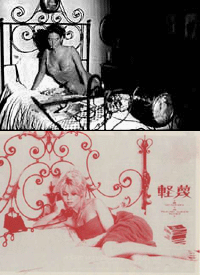 ヴィスコンティの死後になって初めて日本公開された本作は、周知の通り、ヴィスコンティ監督作品内唯一のミステリーだと言われています。ヴェネチア映画祭で金熊賞に輝いたにもかかわらず、モノクロの現代ミステリーという、当時日本人が抱いていた“絢爛豪華にして貴族的”ヴィスコンティのイメージとのズレが、日本公開をそれほどまでに遅らせたのでしょうか。何故だかはわかりませんが、私は長い間、どうしてもこの作品を観たいと思っていたのです。ギリシア悲劇「エレクトラ」を現代に移植した物語に反応したのか、モノクロのミステリーという部分に反応したのか、圧倒的な美を誇るクラウディア・カルディナーレそのものに拠るのか、今となっては忘れてしまいましたが、ともあれ、スクリーンで観ることが出来たという喜びは大きなものです。
ヴィスコンティの死後になって初めて日本公開された本作は、周知の通り、ヴィスコンティ監督作品内唯一のミステリーだと言われています。ヴェネチア映画祭で金熊賞に輝いたにもかかわらず、モノクロの現代ミステリーという、当時日本人が抱いていた“絢爛豪華にして貴族的”ヴィスコンティのイメージとのズレが、日本公開をそれほどまでに遅らせたのでしょうか。何故だかはわかりませんが、私は長い間、どうしてもこの作品を観たいと思っていたのです。ギリシア悲劇「エレクトラ」を現代に移植した物語に反応したのか、モノクロのミステリーという部分に反応したのか、圧倒的な美を誇るクラウディア・カルディナーレそのものに拠るのか、今となっては忘れてしまいましたが、ともあれ、スクリーンで観ることが出来たという喜びは大きなものです。
と、ここまで書いていて思い出したことが。右の写真をご覧下さい。上はリバイバル時の『熊座の淡き星影』チラシ、下はやはりリバイバル時の『軽蔑』のチラシになります。ベッドに横たわる美女と同じような構図。この類似性にこそ反応したのかもしれません。BBとCC。ああ、なんという近親性!
ヴィスコンティ作品のタイトルはどれも魅力的かつ印象的なものが多いと思います。中でも『熊座の淡き星影』というタイトルは、それ自体が詩のようで美しい。イタリアの大詩人、ジャコモ・レオパルディの詩の一節からとられているらしいこのタイトルは、その詩を読んだこともない私のような人間にとっても、この上なく印象的でした。
印象的といえば、本作においてはやはり“風”について触れなければならないでしょう。クラウディア・カルディナーレ演じるサンドラとジャン・ソレル演じるジャンニが数年ぶりに再会する場面の、あの強風。夜の庭園に吹きつける風が、容赦なく二人を襲う。“禁断の関係”にあるこの二人の関係性はラストまで明かされはしないものの、このシーンを観ただけでそう確信するにいたったのは、まさにあの風の存在に拠るのです。ラストシーンも、同じ場所を舞台としていますが、亡き父の銅像の除幕式に相応しく燦々と輝く太陽の下で、やはり不吉な風が吹いていました。新たな旅立ちを決意したサンドラと死を選んだジャンニの切り替えし…このシーンの忘れがたい美しさも、その風の存在を無くしてありえないものだったと思います。まさに“風の残酷さ”が見事に表現されていました。
ミステリーというよりも、サスペンスやホラーに近いカメラワーク(ズームの効果的な使用など)だったようにも思える本作ですが、それは、主題となるであろう姉弟の心理的葛藤のエロティシズムと、疎外感を募らせる夫との危うい関係性を捉えるカメラの視線が、なんだか第三者的人間性を獲得していたようにも思えたからです。水道塔で密会するサンドラとジャンニの、あからさまな近親相姦的描写に加え、サンドラが去った後、一人残されたジャンニが映る水面をあえてクローズアップで捉えるシーンの得も言われぬエロティックさ。冷徹な第三者が覗いているようなカメラの視線が、とりわけ印象的でした。
同時に公開された『ある三面記事についてのメモ』は、冒頭にヴィスコンティ自身によると思われる文面が提示されます。それは確か、「この作品は新たな映画の始まりとなるであろう」といった内容だったと思います。ある少女の殺人事件に関するたった5分のドキュメンタリーですが、ナレーションと画面の意図的なズレがあったように思いました。事件の残酷さを強調するようなシーンではなく、ベッドタウン特有の倦怠感が覆う日常だけをただ切り取っていたという点で。緩やかなパンとロングショット。ヴィスコンティのネオ・レアリズモ的方法論は、たった5分の中にも表れていたということなのでしょうか。この辺りは、もっと調べてみないとわかりませんが。
しかし、あのマルコ・フェレーリがこのニュースドキュメンタリーの制作に携わっていたとは…後に大傑作『最後の晩餐』を生み出すことになるこの監督の“育ちのよさ”ということになるのでしょう。
連休も休まずに映画
今回の連休中も結局映画三昧でした。イタリア・日本・アメリカと全くバラバラなセレクトではありますが、計5本の映画を観ました。一度にたくさんの映画を観てしまうと、このようなサイトを運営している人間としては、短期間に自分の首を絞めることになります。私の場合、気分が乗らないと文章がかけないという欠点がありますが、とりあえず少しずつ文章を練ってみたり。明日の午後も、会社を早退して再度ヴィスコンティ映画祭に行く予定ですが、残りの作品評は何とか週末までに書き上げたいな、と。
ヴィスコンティ映画祭は、かなり人が入っているようで何よりです。出来ればもう少し大きなスクリーンで観たいという願望がないこともありませんが、このような貴重な機会はそうはないですから、贅沢は言えません。
何とか舞台挨拶を避けて駆けつけた『イズ・エー』も、8割くらいの入りでした。監督はまだ新人ですから、やはり題材の現代性というやつが、これだけの人を集めたのでしょうか。
期待に反してなかなか愉しむことができた『アイ、ロボット』は、どうやら賛否両論のようで、私の周囲では好んで観にいっている人間のほうが少ないような気も。かくいう私も、全く期待などしていなかったのですから人のことは言えませんが。アレックス・プロヤスという名前に反応しつつも、VFXが主体となったこの映画について、半ば悪口を言うために観たようなところがあるのですが、そんな“嫌な観客”である私にしてはほとんど意外な感想を持ってしまったことについては、また後日書くとします。
明日は、仕事を放り出してまで観にいくべきだ、と個人的には強く思っている『異邦人』を。原作の内容はまるで忘れてしまっていますが、映画を前に、そんなことは関係ないでしょう。
明日は早朝からジムに行くので、今日はこの辺で。
2004年10月10日
『ツイステッド』、そこに“ねじれ”はあったのか
ほとんど映画のような暴風雨に挫けそうになりながらも、渋谷東急に映画を観にいくというのもそれほど悪くはなかったのですが、それというのも、初日にもかかわらず観客が6人しか居なかったという事実に拠るもので、比較的大きな映画館にポツリ、ポツリとしか観客が居ない中で観る映画は快適そのもの。まるで地方のシネコンの最終回を観ているときのような、そんな気分でした。
フィリップ・カウフマンと言えば、『存在の耐えられない軽さ』ということになるのでしょうが、実は『アウトロー』の脚本家だったと知ってちょっと驚いてみたり。前作『クイール』はマルキ・ド・サドが描かれていたにもかかわらずほとんど印象に残っていませんが、今作は何やら陰惨な猟奇殺人もので、サミュエル L.ジャクソンとアンディ・ガルシアが脇を固めているのですから、やはり観にいくほかないな、と思った次第です。
丁寧に撮られた映画だったとは思います。演出もそれなりに良く、俳優陣も大いにノッていたのではないでしょうか。がしかし、脚本が弱い。音楽は全く駄目、というより邪魔なだけ。驚くような画面もない。ということで、楽しめた部分があるとすれば、やはり俳優たちの“顔”だけだったのではないかと。
本作のように、ラストで観客を驚かせるような映画はよくありますが、その“驚き”が作品の“面白さ”とは実は何の関係もないという事実が、図らずも露呈していました。実際、観客を驚かせるだけであれば、実はそれほど難しくはなく、思わせぶりなシーンを合間に挟み込んで、俳優がそれなりの演技をしていれば、意外性はあっさりと生まれるものだと思いますが、そんな“ラストシーンのためだけの”映画などは面白かったためしがないし、肝心なのは、人間関係の微妙な揺らぎだとか、舞台となる場所の陰鬱さだとか、小道具に対するこだわりだとか、あくまで私見ですが、そんな部分なのではないかと思うわけです。『ツイステッド』は、それらがまるっきりないがしろにされていたような気がしてなりません。レイティングの対象となったであろう死体の残酷さも、物語的な要請という感じはなく、なんだか“浮いて”いて、残念至極です。
冒頭、アシュレイ・ジャッドのアップからカメラが引いていくのは悪くないのですが、そもそもどういう経緯であの場面に到ったのかがわからないのです。あの一連のシークエンスには、その凡庸さ故に結構引いてしまいました。ファーストシーンとして相応しくなかったと思います。まず彼女のトラウマの要因を強烈に示す必要があったのではないかと。両親が死ぬ場面が全く描かれていないので、トラウマ自体も弱いのです。
まるでジャン・コクトーのような表情を見せたデイヴィッド・ストラザーンはなかなかの存在感でしたし、ラッセル・ウォンも悪くはなかったです。魅力的な俳優陣を揃えていただけに、全く残念な出来だったと言うほかない映画でした。いったい何処に“ねじれ”があったのか、未だわからないままです。
:::訂正:::
カウフマンの前作は、『クイール』ではなく『クイルズ』でした。訂正します。
2004年10月09日
怒りが頂点に達しても変身出来ない日常
昨日は久方ぶりの友人と飲んだ後、何を思ったか一人で飲みに行ってしまい、深酒→牛丼→爆睡→寝坊 といういつもながらの体たらくぶり、今朝は見事なまでに気が滅入っていました。そんな状態にさらに追い討ちをかけるように、今朝10:00から販売開始となった東京国際映画祭 オープニング・イブ『2046』のチケットは一瞬で売り切れるわ、特別招待作品『カンフー・ハッスル』は何とかして獲ろうと必死にリロードを繰り返すも、あまりのアクセス数にまったくページが表示されないわ、ついでにこのサイトにも如何わしきコメントスパムが襲ってくるわ、全く踏んだり蹴ったりどつかれたりでアンダルシア…
ふざけるなよ、「チケットぴあ」…
このまず過ぎる状態を吹き飛ばすがごとく、ジムに行ってアルコールを抜き、今こうして文章を綴っています。
さて、来週から始まる“映画祭ラッシュ”、すでに開催している「ヴィスコンティ映画祭」も入れて、3つの映画祭に駆けつける予定です。あまりの作品数に頭を抱えながら、初めてYahoo!カレンダーなど使ってスケジューリングしたところ、一先ず来週から月末にかけての予定が決まりました。ヴィスコンティは4本、ファンタスティック映画祭は2本、東京国際映画祭は多分2本ほど鑑賞します。その都度作品評を書いていきたいと思いますので、ご期待ください。
で、本日は夕方から『ツイステッド』を鑑賞予定。また夜にでも続きを書くことになろうかと。
2004年10月07日
『誰も知らない』、フィクションとドキュメンタリーの狭間で
 公開から大分時間が経っていますが、2度観たこの映画について、やはり何らかの文章を残さねばという妙な義務感から、今更ながら。
公開から大分時間が経っていますが、2度観たこの映画について、やはり何らかの文章を残さねばという妙な義務感から、今更ながら。
まず問われるのは、現在の映画において、フィクションとドキュメンタリーという二元論は成り立つのか、ということです。 それに答えるのが難しいというより、その問い自体の無意味さに、人はだんだんと気付き始めているのではないでしょうか。そもそも“ドキュメンタリー映画”とは、いったいどんな映画を指すのか? 『誰も知らない』が多くの人に感動を与えるのだとすれば、それは『誰も知らない』について回る“ドキュメンタリーのような”という指摘に拠るものなのか? ここでただ一つ言えることは、『誰も知らない』は様々な意味で記憶に残る作品に違いないということです。その理由を探ることが、ここでの主たる目的となるでしょう。
フィクションとドキュメンタリー。言い換えれば、虚構と記録。
恐らく一般的には、対立する概念だと思われている節もあるこの二者ですが、映画とはもともと、これら両方を同時に孕み持つメディアであり、映画である以上、虚構(≒演出)は少なからず存在し、そしてそれを記録することで初めて成り立つメディアなのではないかと思います。であれば、ある映画がフィクションであってもドキュメンタリーであっても、それ自体は作品の価値を高めたり貶めたりするものではないということです。あらゆる映画には、絶対に人間の意思が介在しているのですから。言うまでもありませんが、ただ事物を撮るだけでは、映画は成立しません。監督の思想は、何らかの形で必ず画面に現れてくる。恐らくリアリズム(私たちが思い描く現実と映画との距離)が基準になっているであろう、フィクションとドキュメンタリーの境界線は、機械が主体となって映画を撮っているのでない以上、フィクションでありドキュメンタリーなのであり、カメラとは、人間の目であり、機械としての目でもあるのです。
例えば、昨今流行している“擬似ドキュメンタリー”に対する賛否は、“ドキュメンタリー的”(それは現実に似ているであろうと虚構として撮られています)であろうとする“戦略”(あるいはそれが齎す結果)についての賛否であって、議論となる次元が異なっています。フィクションとドキュメンタリーには決して優劣など存在せず、私たち観客側の幻想に過ぎないのではないか。私はそういう視点に立っています。
ところで映画史には、フィクションとドキュメンタリーという二元論にはとうてい収まりきらないであろう作品が存在しています。例えば、1959年に撮られた『アメリカの影』という映画。この映画は紛れも無くフィクションですが、“シナリオなしのアドリブ演出で、ある種セミドキュメンタリー的な色合いがあり、そのリアリティと臨場感は映画の新たな方向性を確かに見据えていた”(allcinema onlineから引用)と言われています。一つのフィクションであるにもかかわらず、監督であるジョン・カサヴェテスは“俳優によって演じられている”ということよりも、彼らがまさに画面の上で“生きている”瞬間があればそれでいい、と判断したのではないか、と思うのです。その一瞬一瞬に生まれていく仕草が、時に過剰なカメラの動きによってまさしく“アクション(それは画面に映る対象が、まさにそこに居る者として現前に迫ってくる印象に他なりません)”というほか無い何かに変貌していく、稀有な映画なのです。
あるいは、2000年に撮られた『ヴァンダの部屋』。もうここまでくると、先の二元論は全く通用しません。画面に映るのは、それが意図的に作られていようが、偶然による産物だろうが、紛れも無い“現実(画面が生きているという感覚)”だと断言せざるを得ないのです。現実故の強烈な痛み…『ヴァンダの部屋』には、それが横溢しています。監督のペドロ・コスタは、2年間にわたり、主人公であるヴァンダ・デュアルテと共に生活しました。フォンタイーニャスの荒んだ日常の中で、カメラが回る瞬間だけが“とりあえず”ヴァンダを映画として切り取りますが、彼女にとって、カメラが回っている以外の時空間との決定的な差などないかのようです。換言すれば、カメラが回っているかいないか、その差すら消滅している。所謂演出の有無などは問題ではく、対象を“生かす”のでなければ映画にする意味が無い、『ヴァンダの部屋』はそう告げているかのようです。
閑話休題。ここで改めて冒頭の話題に立ち返ります。
私は恐らく、『誰も知らない』に心を動かされました。果たして、それを感動と言い換えて良いものか、今は判断がつきません。ただし少なくとも、『誰も知らない』が“ドキュメンタリー風”だったこととは何の関係もないと断言できます。実際、『誰も知らない』はかなり“脚色”されています。それはあの事件の詳細を調べればすぐにわかることです。さらに言うなら、現実に起こった事件から、意図的に“陰惨さ”が取り除かれているような気もします。だからといって、それをオプティミスムだ、とまでは言いませんが、そこには『ヴァンダの部屋』に見られたような“痛み”を感じませんでした。だとするなら、その代わりに何があったのか。
それは、是枝監督の俳優に対する、風景に対する、そして、(事件性の向こう側にある)未来に対する真摯で温かい目線(それは是枝監督の人間性ではないでしょうか)だったのではないか、と思います。4人の兄弟が始めて“外”に繰り出し、排水溝から突き出した赤い花の種を持ち帰ろうとする場面。カップヌードルのカップに4人が自分の名前を書くとき、清水萌々子の手に柳楽優弥が自分の手を添える場面。そして、ラストシーンに相応しい(これは若干皮肉ですが)、4人が画面の“向こう側”へと去っていく場面などに表出していたと思われます。1年以上を費やして子供たちと接し、彼らの“生(演技には還元できない部分)”が画面に現われる瞬間を待つ。是枝監督のこういった映画へのアプローチがあったからこそ、あのようなシーン(それこそがドキュメンタリー風だったのかもしれません)が生まれたのではないでしょうか。決して“演技”をしているとは言えない子供たちは、にもかかわらず、是枝監督の思い=視線と共鳴しあい、輝いていました。それが多くの観客に感動を与えたのだと。むしろ、演技などしていなかったことこそが、肝要だったのです。もちろん、“演技などさせない”という“演出”の存在は、見落としてはならないと思いますが。
『誰も知らない』を、結果的に“擬似ドキュメンタリー”だと言う人もいるでしょう。しかしこの際、それはどうでもいい話です。その上で私が何らかの結論を出すとすれば、是枝監督は一瞬でも画面に“生”を刻み付けることが出来る監督だということだけです。その事実は、非常に貴重だと思います。結論ならざる結論ですが、そう言わざるを得ないというのが、『誰も知れない』を2度観た私の結論です。
【関連ページ】
『誰も知らない』を再度観直しました
『誰も知らない』とフォトジェニック
『誰も知らない』は誰もが知っているのか?
東京ファンタスティック映画祭2004
昨日、チケットを購入しました。
目当てのプログラムは「映画秘宝スペシャル 秘宝ジャッカスまつり〜世界のバカ大集合〜
」という、この映画祭に相応しい2本立て。まんまと集合してしまう私も、世界のバカの一人、ということになりましょうか。内訳は以下の通りです。
:::jackass:the movie 日本特別版:::
日本にもファンが多いであろうMTVの人気シリーズの映画化です。てっきりヴィデオかと思いこんでいたら、35mmで撮られているようで。“バカ”が“バカ”を超える瞬間があってもなくても、非常に楽しみです。
:::ヘブンズ7(仮題):::
“マカロニ魂が宿った7人のタイ人戦士”って…この一文に負けました。あまりにも出鱈目すぎる……が故に期待は限りなく膨らんでいきます。“『荒野の七人』『黄金の七人』に連なる集団型バトル・アクション、最進化系”なんてことも書いてありますよ。7人という数字しか共通点がないこれらの作品を同一線上に並べること。新たな映画史の始まりかもしれません。
その他にも、なかなか魅力的なプログラムが組まれているようで、中には先日観た『モンスター』のドキュメンタリー版『「シリアル・キラー アイリーン「モンスター」と呼ばれた女」』やサンダンスで話題を呼んだ『SAW』にも駆けつけたかったのですが、どうしてもスケジュールの都合がつかないので見送ることに。子供の頃テレヴィで夢中になった『スパイダーマン 東映版』は……まぁ観たい気もします…あの出鱈目極まるレオパルドンのだけを。
2004年10月05日
今週必ず観る映画
今現在、遅ればせながら『誰も知らない』に関する文章をまとめようとしています。おかげで、観るつもりだったキム・ギドク『魚と寝る女』を断念。そういえば先週改めて『変態家族 兄貴の嫁さん』を観直して、それと関連付けて「ピンク映画とAVの不幸な差異」という文章を構想していましたが、それも後回しになりそうです。
で、先週1本しか観られなかったので、今週末は3本程観ようと思っています。
まずは『イズ・エー』。これはチラシを観たときから決めていました。次に『アイ、ロボット』。こちらの確信が裏切られればいいのですが…そして『ツイステッド』。毎日通っている代々木駅の通路にポスターが貼ってありまして、そのデザインとキャストに惹かれて。もしかしたら、明日、ラス・メイヤー映画祭に行くかもしれませんが、予定は未定です。
ところで、14日から始まる東京ファンタスティック映画祭、何本か観たい作品があるのですが、行かれる方はいますか? 毎日数十分はそのことばかり考えています。大嫌いな新宿ですけど。これまで映画祭には全く関心が無かった私ですが(いずれ公開されることは知れていますから)、自分でサイトを始めてみて、急に関心を寄せるようになりました。これを“いやらしい”ととるか、“熱心だ”ととるか、もしくは“政治的”だととるか、それはご想像にお任せしつつ、でもやっぱり一本も足を運ばなかったりするかもしれない秋の夜です。
2004年10月04日
『靴に恋して』、日本の女性は何を思うのか
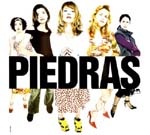 シアター・イメージフォーラムにて、本作が長編デビュー作となるラモン・サラサール監督の『靴に恋して』を鑑賞。2回目で客席は4割程の入りでしたが、上映後外に出てみると70人くらいは待っていたようです。そのほとんどが女性だったという事実は、“グッチやプラダなど最高級の靴が300足登場!”とか“今を生きるリアルな女性たちが真実の愛を求めて疾走する”という宣伝文句が、ある程度機能したということなのでしょう。
シアター・イメージフォーラムにて、本作が長編デビュー作となるラモン・サラサール監督の『靴に恋して』を鑑賞。2回目で客席は4割程の入りでしたが、上映後外に出てみると70人くらいは待っていたようです。そのほとんどが女性だったという事実は、“グッチやプラダなど最高級の靴が300足登場!”とか“今を生きるリアルな女性たちが真実の愛を求めて疾走する”という宣伝文句が、ある程度機能したということなのでしょう。
そもそもこの映画の原題は『PIEDRAS』というもので、邦題とは全く関係の無い“(複数の)石・岩”といった意味です。文字通り“堅い”タイトルのままではどうにもまずい、という配給側の配慮でしょうか、スペインのファッション性(思えば過去のアルモドバル作品では、登場人物たちが着ている衣装のブランドが強調されていました)や、作品内容に全く関係ないわけではない“靴”を全面に押し出すことで、“お洒落で自立した女性のための映画”という位置付けにせざるを得なかったようです。確かに主人公は5人の“女性”なのですから、それは嘘でも誇張でもありませんが。
さて、そのような映画として『靴に恋して』を観た私としては、女性の群像劇として観ればそれほど悪くはなかった、というのが正直なところ。とはいっても途中までは全く乗れず、それは私が男性だからなのか、それとも、そういった先入観を捨ててもやはり好みではないからなのかと、少なからず考え込んでいたのですが、何の関係も無い5人が少しずつつながり始めるあたりからだんだんと画面にひきつけられ、最終的にはまぁ良かったんじゃないか、と思った次第です。
この映画はシネマスコープで撮られていましたが、例えばラスト近く、リスボンのとある埠頭である人間(ここはあえて隠しておきます)の遺灰を撒くシーンは、その横長の画面を上手く利用していて、印象的でした。あるいは、ほとんど男性かと思われるようなアデラ役のアントニア・サン・フアンと彼女を慕う高級官僚・レオナルド役のルドルフォ・デ・ソーザの別れが決定的になる場面。丈の長い枯れた草原のような場所にやや距離を置いてたたずむ2人を、引き気味のカメラで捉えるショットは、デビュー作にしては堂に入った感じでこちらもいいシーンでした。ついでにもう一つ付け加えれば、本作では、所謂“つなぎ”にそれなりの工夫がされていて、あるシーンの終わりがそのまま次のシーンの始まりでもあるといった編集がなされていました。想像するに、この群像劇を最終的にある一点に収斂させるのはほとんど力技だったと思いますが、その割にはある種の余裕めいたものを感じました。その時想起したのは、北野武の『HANA-BI』にあった1シーンでしたが、それはここでは置いておきます。
邦題では“靴”に焦点を当てているこの映画、チラシによれば“王子様のいない5人のシンデレラたちが、古い靴を脱ぎ、新しい靴に履き替えるように人生を変えることができるのか”ということが主題に当たるそうです。では、原題の“(複数の)石・岩”とはいったい何のことでしょうか。
画面を見る限り、説話上、ある意味を持った石や岩が出てくることはなかったと思います。とすれば、“(複数の)石・岩”とは、人生における困難やアクシデントの暗喩ということになりましょうか。誰もが一度は躓き挫折する対象としての石。そう解せば、なるほど、それぞれに悩みを抱える主人公5人(ひょっろすると彼女たちが“石ころ”なのかもしれないという可能性もありますが、ここでは無視します)が如何にして困難に対峙していくのかを描いていたことが思い出されます。
私はスペイン映画をそれほど沢山観ているわけではありませんし、ブニュエル、アルモドバル、アメナーバルくらいしかまともに観ていないのですが、その上でスペイン映画に対する印象を言わせてもらえば、倒錯が日常と違和感無く調和しうる土壌といますか、そんなものを感じました。セクシャリティに対する寛容度から言っても、そこにポップとしての軽さみたいなものを感じてしまうのです。この感覚が間違っているであろうことは充分自覚していますが、少なからずそのようにおもっている人は多いのではないでしょうか。
実は監督も俳優として出演しています。なかなか熱いものを見せてくれましたが、それがどんなシーンだったかは観てのお楽しみということで。
2004年10月02日
1959年の豊饒さ〜『草の上の昼食』と『リオ・ブラボー』
 金曜日はヴィデオにて『草の上の昼食』と『リオ・ブラボー』を。共に大傑作なのは言うまでもありませんが、様々な場所で散々語りつくされている感もあるのでここでは詳述しません。その代わり少しだけ雑感をば。
金曜日はヴィデオにて『草の上の昼食』と『リオ・ブラボー』を。共に大傑作なのは言うまでもありませんが、様々な場所で散々語りつくされている感もあるのでここでは詳述しません。その代わり少しだけ雑感をば。
『草の上の昼食』は横笛によって吹き荒ぶ魔術的な風が、何かを奪うのではなく、ある“豊かさ”を生み出していくという物語です。フランスで公開されたのが59年。この年は、ジャン=リュック・ゴダールとフランソワ・トリュフォーがフランス映画界に津波を起こした記念すべき年です。あの突風が、ヌーヴェル・ヴァーグをも引き起こしたのかもしれない、などと空想に耽ってみるのも、それほど無意味なことではないと私は思っています。
『草の上の昼食』の美しさを前に、もはや形容すべき言葉も見つからないので安易に比較へと逃げますが、例えば『草の上の昼食』と同様に、草原と木々に降り注ぐ眩い太陽の光と、そこでの昼食とを画面に映したアニエス・ヴァルダの『幸福』(1965)の美しさは、それがタイトルとは間逆とも言える悲劇性を帯びていた分、紛れも無い“幸福な”喜劇である『草の上の昼食』の優位は揺るがないと確信しました。このテクニカラーは本当に美しかった。
これは全くの偶然ですが、『リオ・ブラボー』も1959年の作品です。「ヒッチコック=ホークス主義」を打ち出したのも批評家時代のゴダールやトリュフォーだったという事実が示すとおり、ハワード・ホークスは絶対的な映画作家であるという厳然たる事実を再確認。
その昔、私がレンタルヴィデオ屋でアルバイトしていた時、アメリカ映画狂いだった先輩に向かって、「ホークスの『ハタリ!』で最も感動的だったのは、ピアノを前に男たちが歌う、あの合唱シーンでした!」とやや興奮気味に言ってみた時、その先輩は一言「ああ、あれ全然普通のシーンだったじゃん…」とだけ言い放ってその場を離れたのですが、今ならこう断言できるでしょう。先輩、あなたの目は節穴ですか? と。それ位、『リオ・ブラボー』の合唱シーンも素晴らしいのです。
数年後に『ビッグ・バッド・ママ』において呆気なく死んでみせるアンジー・ディッキンソンの、控えめでありながらも図々しい愛の形がすこぶる感動的でした。
西部劇でワード・ボンドが出てくれば胸が躍るし、ウォルター・ブレナンの豪快でいて聡明な素振り、ライフルよりはやはりギターの似合うリッキー・ネルソンのややニヒリスティックな演技をギターによって武装解除させてしまうホークスの完璧な演出等々、映画好きなら“誰でも知っている”はずの『リオ・ブラボー』ではありますが、むしろ若い女性にこそその凄さに打ちひしがれていただきたいものです。
2004年10月01日
熱意と勇気〜近刊の書籍・雑誌と映画パンフについて
 本日は、映画から少しだけ離れて、最近購入した書籍・雑誌に関して。
本日は、映画から少しだけ離れて、最近購入した書籍・雑誌に関して。
書籍も雑誌も、日々読んでいない時が無いくらいで、サイトを始めた当初は、それらについても言及したかったのですが、映画ばかり観ていてなかなか触れることができなかったというのが実情。仕事柄、数年前は毎日様々な書店を訪れたものですが、最近は専ら阪急ブックファースト渋谷店にしか行かなくなってしまいました。よって、下記に挙げたものも全部そちらで購入しました。
書籍と言えば、最近の映画のパンフレットは、どれも公式WEBサイトの内容と変わりませんね。いくつかの批評がプラスされていればまだいいほうで、全く同じ内容のものも。只で見られるものに金を払うのが馬鹿馬鹿しくなってきた今日この頃です。一時、シネセゾン辺りでセルジュ・ゲンズブールのリバイバルが盛んだった頃、パンフレットにも相当金がかかっていたことを思うと、結局はその作品に“狂った”であろう人々の手によって作られたもので無い限り、もはや購入するには値しないと言うことなのでしょうか。一部の劇場を除けば、そもそもパンフレットにフォーマットなど無いのですから、それはつまり、デザインにも内容にも、“熱意”の程が端的かつ残酷に表れてしまうものなのだということです。
以下に挙げた書籍・雑誌には、作り手の“熱意”が込められていることが読者にもダイレクトに伝わると言う意味で、購入・保存するに値する商品であるのは言うまでもありません。
『映画への不実なる誘い−国籍・演出・歴史』(蓮實重彦 著 エヌティティ出版)
『映画狂人最後に笑う』(蓮實重彦 著 河出書房新社)
『中条省平は二度死ぬ!』(中条省平 著 清流出版)
『映画芸術 2004 SUMMER 408』
『STUDIO VOICE 2004 OCTOBER VOL.346』
一点だけ映画とは関係の無い雑誌が含まれていますが、ここではその『STUDIO VOICE』に関して一言二言。
嘗ては定期購読していた時期もあったこの“MULTI-MEDIA MIX MAGAGINE”ですが、購入したのは7ヶ月ぶりになります。所謂ワンテーママガジンには、どうしてもその都度読者を選ばざるを得ないという欠点(?)があり、興味の幅がどんどん縮小されている現在の私には、もはや毎月購入することなどとても出来ないのです。にもかかわらず今回購入したのは、“ケイト・モスとは誰か?”という人を食ったような特集タイトルに惹かれたからです。
かれこれ7〜8年ほど前でしょうか、私がケイト・モスに最大限の賛辞を送り続けていたのは。写真集を買い、広告を切り抜き、何枚も絵を描き、彼女がミューズだったブランドの香水をつけ……けれど彼女は、決して懐かしさの対象となったりはしていません。未だ現在形で活躍を続けているのです。時代が彼女を求めるのは何故か? 『STUDIO VOICE 2004 OCTOBER VOL.346』はそんなことを考えさせてくれました。
公式サイトが休止してからかなりの月日が流れているinfasですが、今あえてケイト・モスを特集として取り上げる“勇気”には、やはり頭が下がる思いです。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]



