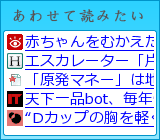2004年10月15日
ヴィスコンティ映画祭〜『異邦人』『疲れ切った魔女』
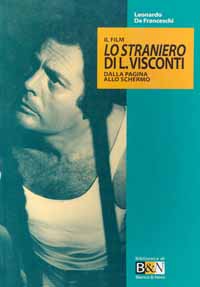 日本での上映は20年ぶりだと聞いて駆けつけた『異邦人』は、個人的な結論から言うと、途方も無い傑作というわけではありませんでした。しかし、それは果たして、監督であるルキノ・ヴィスコンティが原作に限りなく忠実たろうとした結果、私が“ヴィスコンティらしさ”を、あまり実感できなかったということが原因なのか。だとすれば、その“ヴィスコンティらしさ”とやらはいったい何なのでしょう? 世間で認識されている彼のイメージ、すなわち、“絢爛豪華にして、貴族的・退廃的な美を描いた巨匠”などは、彼の作風の一端を担ってはいたものの、それらとヴィスコンティが等号で結ばれてしまうことは、やはりあまりに短絡的だと(自戒を込めつつ)言わざるをえません。なぜ『熊座の淡き星影』や『異邦人』が、私たちの前から遠ざけられてきたのか。それには、これまで多くの日本人がが描いてきたであろう“凝り固まったイメージ”が、少なからず影響していたような気がするのです。その意味で、今回企画された全作品上映は、ヴィスコンティに纏わりつく“貧しいイメージ”から解放させるいい機会だったのではないでしょうか。今回の映画祭を観るにあたって、敢えてそのようなイメージから遠い作品ばかり選んだのも、その思いがあってこそです。ルキノ・ヴィスコンティは、決してある角度からだけ観られるべき監督ではないのです。ジャン・ルノワールの助監督から映画に関わり、ネオ・レアリスモへと発展させたという歴史的事実はそのまま、彼の豊かな感性や挑発性、何より繊細な人間性を表しているのだと、今改めて考えてみても無駄ではないと思うのです。
日本での上映は20年ぶりだと聞いて駆けつけた『異邦人』は、個人的な結論から言うと、途方も無い傑作というわけではありませんでした。しかし、それは果たして、監督であるルキノ・ヴィスコンティが原作に限りなく忠実たろうとした結果、私が“ヴィスコンティらしさ”を、あまり実感できなかったということが原因なのか。だとすれば、その“ヴィスコンティらしさ”とやらはいったい何なのでしょう? 世間で認識されている彼のイメージ、すなわち、“絢爛豪華にして、貴族的・退廃的な美を描いた巨匠”などは、彼の作風の一端を担ってはいたものの、それらとヴィスコンティが等号で結ばれてしまうことは、やはりあまりに短絡的だと(自戒を込めつつ)言わざるをえません。なぜ『熊座の淡き星影』や『異邦人』が、私たちの前から遠ざけられてきたのか。それには、これまで多くの日本人がが描いてきたであろう“凝り固まったイメージ”が、少なからず影響していたような気がするのです。その意味で、今回企画された全作品上映は、ヴィスコンティに纏わりつく“貧しいイメージ”から解放させるいい機会だったのではないでしょうか。今回の映画祭を観るにあたって、敢えてそのようなイメージから遠い作品ばかり選んだのも、その思いがあってこそです。ルキノ・ヴィスコンティは、決してある角度からだけ観られるべき監督ではないのです。ジャン・ルノワールの助監督から映画に関わり、ネオ・レアリスモへと発展させたという歴史的事実はそのまま、彼の豊かな感性や挑発性、何より繊細な人間性を表しているのだと、今改めて考えてみても無駄ではないと思うのです。
実際、『異邦人』は、傑作とまでは言いませんが、駄作ではないのです。いやむしろ、かなり楽しめる作品だったと言えるでしょう。アルベール・カミュの原作を読んだのは遠い昔で、詳細など完全に忘れていたのですが、“不条理”という若干手垢にまみれた言葉を深く理解している必要など決してなく、マルチェロ・マストロヤンニの器用な演技に改めて驚いてみたり、アンナ・カリーナが、ゴダール時代とは異なってまさしく“役を演じている”様に出会えたら、それだけで私は満足でした。さらにアンナ・カリーナについて言えば、彼女が公判で泣く場面など予想だにしていなかっただけに、何とも不思議な、それこそ“不条理”な感動にとらわれたほどです。もちろん、これまで一度も観たことのなかった裸体を目撃したときなどは、はっきり言ってかなり興奮状態にあったと、ここで告白します。
中盤、ちょうどマストロヤンニ演じる主人公とその仲間たちが、海を背景にアラブ人2人組と争う場面で、カメラが海側から浜辺にいる5人の男たちを映していたシーンがあったと思います(もしかすると、浜辺にはマストロヤンニしかいなかったかもしれませんが、詳しくは思い出せません)。その前に、普通に浜辺から海を映す場面があり、それはそれで後の『ベニスに死す』へと繋がるであろう美しいシーンではありましたが、海側から浜辺を映したのを観たのは、私の貧しい映画体験を思い起こせば、北野武『DOLLS』がすぐさま思い起こされ、その意外なシンクロニシティも少なからず感動的でした。
次にこの作品を観られるのはいつになるのでしょう。
もちろん東京で上映されるとなれば絶対に観にいきますが、それまでにヴィスコンティ好きと自称する人間に会う機会があれば、絶対に『異邦人』について語り合いたいという気がしました。私はとりわけヴィスコンティに強い執着を持っているわけではありませんが、やはり、この貴重な機会を逃した人間に、ヴィスコンティが好きだとは言ってほしくないからです。
同時上映された『疲れ切った魔女』については、そのタイトルバックが印象的でした。ちょうど、今月号の「pen」を読んだところでしたから。『疲れ切った魔女』は一応コメディということになっているようですが、何と言っても、シルヴァーナ・マンガーノの化けの皮をはがすシーンでしょう。美しいものがその虚飾をはがされていく様…これはやはりヴィスコンティ的なのでしょうか。
2004年10月15日 22:58 | 映画雑記, 邦題:あ行, 邦題:た行

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]