2004年08月31日
GAINSBOURG et cinemabourg*
 以前は60年代〜70年代のロックばかりを好んで聞いていたのですが、いや、ほとんど狂っていたと言えるのでしょうが、実はある一時期シャンソンに目覚め、連日連夜、あの難しい発音からなる、美しくも下品なシャンソンに傾倒していました。どのような経緯でそうなったのかは覚えていませんが、一つだけ記憶しているのは、当時の「タモリ倶楽部」でかかったセルジュ・ゲンズブールの「L'anamour」という曲、あの番組でかかったのですから、言うまでも無く「空耳アワー」で聞いたのですが、にもかかわらずこの曲に打ちのめされ、もう次の日には買いに行っていたような記憶が。ゲンズブールは映画も撮っていたので、東京で見られる限りの映画を観て、本を読んで、もちろんCDも聞いて、終いには彼の墓参りまでしてきたほどです。すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、当サイトの名前も、彼の名前から一部イタダいています。ですので、このサイトに正式な読み方があるとすれば、“シネマブール”ということになりますが、まぁそんなことはどうでもいい話で。
以前は60年代〜70年代のロックばかりを好んで聞いていたのですが、いや、ほとんど狂っていたと言えるのでしょうが、実はある一時期シャンソンに目覚め、連日連夜、あの難しい発音からなる、美しくも下品なシャンソンに傾倒していました。どのような経緯でそうなったのかは覚えていませんが、一つだけ記憶しているのは、当時の「タモリ倶楽部」でかかったセルジュ・ゲンズブールの「L'anamour」という曲、あの番組でかかったのですから、言うまでも無く「空耳アワー」で聞いたのですが、にもかかわらずこの曲に打ちのめされ、もう次の日には買いに行っていたような記憶が。ゲンズブールは映画も撮っていたので、東京で見られる限りの映画を観て、本を読んで、もちろんCDも聞いて、終いには彼の墓参りまでしてきたほどです。すでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、当サイトの名前も、彼の名前から一部イタダいています。ですので、このサイトに正式な読み方があるとすれば、“シネマブール”ということになりますが、まぁそんなことはどうでもいい話で。
ゲンズブールが監督した作品は、いずれも変な映画で、興行的な成功とは遠いものばかりだったと思います。それでも、渋谷でのリバイバルを連発していた90年代は、エディター・川勝氏やピチカート・小西氏の煽動もあって、かなりウケていた様子でしたが。何といいますか、独特というか“毒特”と言うか。ヘンテコな映画が多かったわけです。俳優としてのゲンズブール作品は、それなりに売れた映画もあります。『Slogan(スローガン)』などはバーキンとの関係上決して無視できない作品です。『Je vous aime (ジュヴゼーム)』に到っては、やはり当時大好きだったカトリーヌ・ドヌーヴとの競演でしたから、やはりはずせない一作でした。そして、『Je t'aime moi non plus(ジュテーム・モア・ノン・プリュ)』。この映画には個人的にかなりの思い入れがありまして、それは別に、ゴダールやトリュフォー以外の批評家から総スカンをくらったという事実にあるのではなく、スキャンダラスなテーマソングにあるのでもなく、もっぱら主演のジョー・ダレッサンドロの怪演にありました。私が観てきた俳優の中でも、群を抜いて怪しく、同時に、ほとんど神秘的ともいえる美しさを秘めた男でした。このようなアングラ俳優を主演にしながらも、傍らに男娼的美人・バーキンを据えるセンス。そして、あろうことか、白馬に乗ったジェラール・ドパルデューまで! ゲンズブールの類稀な才能に当時は嫉妬しつつ、心酔したのです。
全くの造語であるこんな名前をサイト名にすることで、例えば誰もこの名前では検索しないだとか、始めて説明するときに「意味は?」とか尋ねられて困ったりだとか、どちらかと言うとマイナス面ばかりが目立ちますが、それでも本人は意外と気に入っています。近々ロゴも作成予定ですので、出来次第、上にあるマラパルテ邸のイラストに重なることでしょう。
:::追記:::
写真を差し替えました。ゲンズブールの墓です。モンパルナス墓地にて[M]が撮影。
2004年08月29日
外出がつい億劫で『殺人の追憶』を観る
 まぁ完全にオヤジギャグですが、ご愛嬌ということで。
まぁ完全にオヤジギャグですが、ご愛嬌ということで。
今日は結局何もせず、何処にもいかず、よく食べて、それなりに…飲んで、ずうっとPCの前にいました。特に書くことも無い平穏無事な一日でした。
雨も降っていて何となく劇場に行くのも億劫でしたから、久々にヴィデオを借りました。『殺人の追憶』は封切りで見逃していて、ずっと観たかったのです。にもかかわらず、監督のポン・ジュノが『ほえる犬は噛まない』の監督だったと気付くのに結構時間がかかってしまったのですから、私の知識など知れたものです。
観ていて感心したのは、しかるべき部分で監督がカメラをグっと引いている部分です。このような陰惨な犯罪映画において私が最も注目する部分は、銃撃戦のアクション性でも、殺人手口の巧妙さでも、(この映画には最後まで訪れることがありませんが)犯人逮捕の瞬間でもなく、それは殺人の瞬間など何か途方も無いことが起こる瞬間や絶望感漂うシーンと言うことになるでしょうが、そういったシーンをロングショットで見せられてしまうと、もう大方満足してしまいます。『殺人の追憶』には、少なくとも4シーン程そういうロングショットがあって、そのどれもがかなりのロングだったような。これはある程度の勇気と、感性が無ければ出来ないと思うのです。
それと、このシーンはどう観ても黒沢清じゃないかと思って監督のインタビューを読んでみると、少なからぬ影響を受けた監督として彼の名前が挙がっていましたので、あれはやっぱりそうだったんだなぁ、と孤独に納得した次第です。どのシーンかは敢えて書かずにおきます。
最後に、韓国映画の食事のシーンは、どうしてかあまり美味しそうに感じないのですが、それは何故なのでしょう? 食事の好みの問題なのか、食べ方や慣習的なものが私と合わないのかわかりませんが。賛同される方、コメントいただければ幸いです。もちろん、反論も。
2004年08月28日
『誰も知らない』を再度観直しました
 同じ映画を封切り時に2回以上観るという行為は、私にとってはさして珍しいことでもありませんが、それが邦画であったことは非常に稀です。今思い出そうとしても、恐らく出てこないでしょう。今日、『誰も知らない』の2回目を観て来たのですが、1回目よりもむしろ味わい深かったと告白しておきます。最近は事あるごとにこの映画を薦めてきたのですが、それは私自身、久方ぶりに感情を乱された映画だったからです。悲しいとも違うし、もちろん可笑しくもない。カタルシスなどありませんが、人に薦めずにはいられない。何とも複雑な感情を呼び起こされた映画であることは間違いなかったと思います。
同じ映画を封切り時に2回以上観るという行為は、私にとってはさして珍しいことでもありませんが、それが邦画であったことは非常に稀です。今思い出そうとしても、恐らく出てこないでしょう。今日、『誰も知らない』の2回目を観て来たのですが、1回目よりもむしろ味わい深かったと告白しておきます。最近は事あるごとにこの映画を薦めてきたのですが、それは私自身、久方ぶりに感情を乱された映画だったからです。悲しいとも違うし、もちろん可笑しくもない。カタルシスなどありませんが、人に薦めずにはいられない。何とも複雑な感情を呼び起こされた映画であることは間違いなかったと思います。
公開からすでに数週間を迎えたシネ・アミューズは相も変らぬ混雑ぶりでした。15:35からの回を観ましたが、当たり前のように立ち見が。午前中にチケットを買っておいたにもかかわらず、43番目でした。ジムに行ってからの鑑賞を予定していたのですが、大分時間が余ってしまったので、例によって併設しているBis cafeにて美味しくないカレーを食べ、ビールを飲み、ワインを飲んでもまだ時間が足りず、今日のスケジューリングは完全に失敗だったと途方に暮れること30分、それでもまだ上映まで30分以上ありました。ただ視点を変えてみれば、そうまでして観る価値がある映画だと判断していたということなのでしょう。
この映画については纏まった文章を書くつもりでいます。明日何も予定がないようだったら、書き上げられるかもしれません。まだイメージが残っているうちに。それにしても、ゆき役の清水萌々子ちゃんの可愛さというか儚さというか、それはもうただごとではない感じがしました。同時に、是枝監督の戦略といっていいのかわかりませんが、少なくともその演出方法の確かさはこれで証明されたといえるのではないでしょうか。まぁ、後はちゃんと考えて書くこととします。
2004年08月27日
酒・映画・旅
昨日は日記を怠ってしまいました。といっても、それは私の意志によるものではなく、酒によってそうせざるを得なかったというのが正確なところ。別に今始まったわけではないので、今更深く考えてみてもしょうがないのかもしれませんが、それでも今朝、またもや遅刻しつつある総武線の車内で考えたのは、私が真に抗い難いもの、それは“酒”なのではないかということです。例えば女性。この存在は、時に途轍もない力で私に作用することがあるとはいえ、どうしても抗えない存在とはいえません。まだ“意志”が通用するからです。では仕事はどうか? それをあっさり放り出して『華氏911』を平日の午前中から観にいくくらいですから、言うまでもありません。でも、酒の圧倒的な力を前にした場合、私は完全に無力です。これでも人並みには生に対する執着がある私を、破滅へと追い込みかねない。こちらの強い意志など鼻先で笑いながら、私を着実に死の側へ導いていくのです。
そこまでわかっているのですから、では酒を止めればいい、人はこう言うでしょう。最もです。それが不可能であるにしても、やはり抵抗を見せなければなりません。この問題については、今後も意識的足らざるを得ないだろうと真剣に考えています。
さてさて、ここで唐突に話題を変えます。
昨日の日経産業新聞に興味深い記事がありました。それによれば、ネット利用者の過半数が旅行関連サイトを利用していると言う調査結果です。もはや旅の情報はネットから、というのが一般的のようで、前年比48%増の1739万人が利用しているのだそう。“旅⇒インターネット”という発想の方向性がより強固なものになっているということでしょう。
その記事を読んだ私も実は、(経験の少ない)旅好きです。しかも、私が経験した旅は、映画に関係しています(海だけを目的に訪れたGUAMは別です)。じゃぁ、このサイトにもそんなコーナーがあってもいいのではないかと思い至ったというわけです。まだデジカメなど無かった時代で、しかも一眼レフを持つほど写真を撮ることに興味など無かったので、もっぱら「写るんです」による写真ですが、かなりの枚数があるはず。当時の“旅行日記”も探せば出てくると思います。一人旅(二回目は二人旅)ですからエピソードにも事欠きません。何より“映画の旅”でしたから、このサイトの趣旨にも当てはまります。さらに言えば、このサイトにたどり着く人がどのような検索語で飛んでくるかを見てみると、「マラパルテ邸」という言葉で飛んでくる人が予想外に多かったのです。私自身、あの当時インターネットを日常的に利用していたら、もっと容易に「マラパルテ邸」について調べられていただろうと思い、それなら今後“映画の旅”を考えている人に多少なりとも貢献できるかもしれないと思いました。いや、本当はそこまでは考えていませんが。
ともあれ、今後はそんな旅話も織り交ぜていければと。そのうちカテゴリーにも“cinema-trip”が加わることになるでしょう。
2004年08月25日
突然炎のごとく…
 朝起きて、本当に背筋が凍りました。
朝起きて、本当に背筋が凍りました。
“酒は百薬の長”だなんて言いますが、今年はそのせいで肋骨にひびが入り、手を骨折したのですから、言うまでも無く古くからあるその格言は、私にとって何の意味もなしません。ここまで学習能力のない自分を呪う気持ちよりも、今朝は心から“生きていることに感謝”しております。
昨日は社内のとある飲み会に参加したのですが、諸々の理由から大いに飲んでしまい、そして、飲まれてしまいました。本来なら2メーターほどで帰宅できるはずのタクシーで熟睡し、最終的には数千円が水の泡に。運転手にしてみれば、どこに行ったら良いのかまるで検討がつかないわけですから多少は困惑したのでしょうが、間違いなく“おいしい客”である私を乗せたことに、少なからず得した気分だったのではないでしょうか。とまぁそんなことはどうでもいい話です。
とにかく何とか自宅近くまでたどり着いたのですが、ここで私の悪い癖が。私は飲んでいる最中はあまり食べず、いつも帰宅後にお腹が空いてくるという悪癖を持っているのです。何一ついいことなど無いこの悪癖が昨夜も顔を出し、気がけばコンビニで牛丼など買っている始末。本来ならここでカップラーメンもセットで買うところですが、朦朧とした意識の奥底で“それだけはやめておけ”という指令が下されたのでしょう、何とかそれは避けることができました。そして、帰宅。牛丼をがっついて、シャワーを浴びて、寝る。そのようにことが運べば、次の日に軽く後悔するくらいで済み、いつもの日常と変わりないはずだったのですが…
帰宅後の行動については、あまり覚えておりません。というか、思い出したくもないです。あろうことか、鍋にお湯を張り、強火でお湯を沸かすという奇行に出た私に、もはや健全な思考など無かったのです。ラーメンを買わなかったのに、何故お湯を沸かしたのか? その疑問も解消されることがないでしょう。折角暖めてもらった牛丼にも手をつけず、孤独に沸騰し続けるお湯を尻目に、私は深い眠りへと落ちていったのです。本来なら効き過ぎたクーラーの寒さによって目覚めるはずの朝が、なにやら禍々しい熱気に包み込まれた朝に変貌したことに気づいたのは今朝の9:30。ほとんど業火といってもいい炎に包まれた鍋が、私を責めているようでもありました。「次は無いぞ…」という鍋の声が、間違いなく私の脳裏に響き渡りました。よかった…本当に良かったと、信じていないはずの神に感謝したりするほど、今朝の私から流れる汗は、決して暑さからくるものではなく、冷たい汗だったのです。だからといって決して禁酒に至らないあたりに、私の愚かさが露呈しています。飲んだらお湯を沸かすな、とだけ言い聞かせておきます。自戒を込めて。
2004年08月24日
『ある日、突然』両足が…
 仕事を終え渋谷に着いたまでは良かったのですが、ああ、今日の晩飯もいつもと同じかな…とうんざりしながら109前のY字路に差し掛かったとき、こちらの意思に反して足がbunkamura方面に進みだして、稀にそちらから帰宅することが無いとはいいませんが、どうやら今日は無意識的に映画を欲していたようで、両足の赴くままにシネ・アミューズへ。整理券番号は7番、「今日の数字は悪くない」などと思いつつ、30分ほど時間をつぶして『ある日、突然』を鑑賞してきました。
仕事を終え渋谷に着いたまでは良かったのですが、ああ、今日の晩飯もいつもと同じかな…とうんざりしながら109前のY字路に差し掛かったとき、こちらの意思に反して足がbunkamura方面に進みだして、稀にそちらから帰宅することが無いとはいいませんが、どうやら今日は無意識的に映画を欲していたようで、両足の赴くままにシネ・アミューズへ。整理券番号は7番、「今日の数字は悪くない」などと思いつつ、30分ほど時間をつぶして『ある日、突然』を鑑賞してきました。
入りはざっと見積もって15人といったところでしょうか。隣で上映している『誰も知らない』は、月曜日のレイトにもかかわらず100人近くの入りだったようで。『ある日、突然』だって2年前のロカルノで銀豹賞(準グランプリ)と特別賞をダブル受賞しているにもかかわらず、この差。今日の光景を見るにつけ、先日『誰も知らない』の初日に感じた、あのマスコミによる過熱報道が結果的に齎した大入りの奇妙な“場違い感”を改めて確信するに到りました。あまりの客入りに、9月4日からシネ・アミューズは両方で『誰も知らない』を上映するらしいです。まぁ、この事実は祝福すべきことではありますが。
そんなことはともかくとして『ある日、突然』ですが、何より好感が持てたのはその上映時間で、93分という“やや短め感”がしっくりくる佳作でした。もう少し観ていたいと思わせる作品は、“絶対に”面白い作品だからです。言い換えれば、物語の終わりを示す記号は随所にちりばめられているにもかかわらず、その事実から目をそらしたい衝動に駆られる作品と言いますか。先日の『アデュー・フィリピーヌ』といい、本作といい、たまたま処女作を連続して観る事になりましたが、『ある日、突然』を撮ったまだ若いディエゴ・レルマン監督も処女作にモノクロを選んだあたり、少なからぬ“野心”を感じてしまいました。あえてリスクを負ってでも作品を輝かせることを望む姿勢。だからといって、よく言われているように、ヴェンダースやジャームッシュを引き合いに出すのもどうかと思います。まさかモノクロでロードムーヴィーという理由だけでそう判断されているわけでは無いですよね? 実際、『さすらい』と『ストレンジャー・ザン・パラダイス』は共に傑作だとは言え、それほど似ていないと思うのですが。そして、それら2作品と本作についてもまた然り。前者にあったいい意味での“弛緩”が、『ある日、突然』には感じられなかったのです。どちらかと言うと“鋭い”カット割りでしたし。まぁ、この比較にどれほどの意味があるとも思えないので、この辺でやめておきます。とか言っておきながら今思い出したのですが、これら3作品に共通する要素もあって、それは俳優陣の素晴らしさかと。本作でいえば、とりわけマルシアを演じるタチアナ・サフィルと、ブランカを演じるベアトリス・ティボーディンの演出には目を見張るものがありました。彼女たちの演技は、まさにその一瞬一瞬のアクションによって成り立っているという点で美しかったと思います。
はっきりと断言できるのは、この監督の次回作も必見だろうということですかね。
2004年08月22日
『アデュー・フィリピーヌ』に感動しつつ憤らなければならない不幸
 今でこそ滅多に行くこともなくなりましたが、嘗ては毎週のようにclubingしていた時期もあり、土曜の夜は浴びるほど酒を飲んで、表参道辺りを叫びながらダッシュしてみたりだとか、始発に乗った途端に深い眠りへと滑り落ちたかと思えば、何故か千葉にある実家とは間逆に位置する本厚木駅の駅長事務室で毛布をかけられ気を失っていたなんていう稀有な経験をしてみたりだとか、まぁ、言ってみればイカレポンティとしか言いようの無い若造だったのです。その時以来ですから、かれこれ7~8年の付き合いになる“わるい仲間”と3年ぶりに再会したのが昨日、すでにそれぞれが“いい大人”になり、環境が大きく変化した人もいれば、私のように相も変らぬ駄目人間もいて、だけれどもやっぱり飲んでしまえば、我々を隔てていた距離と時間がたちどころに消え去ってしまうのですから、共に馬鹿をした仲間と言う奴は貴重だなぁなどと再認識した次第です。とりあえず今この日記を読んでいる3名の方、約束どおり速やかに足跡を残してください。
今でこそ滅多に行くこともなくなりましたが、嘗ては毎週のようにclubingしていた時期もあり、土曜の夜は浴びるほど酒を飲んで、表参道辺りを叫びながらダッシュしてみたりだとか、始発に乗った途端に深い眠りへと滑り落ちたかと思えば、何故か千葉にある実家とは間逆に位置する本厚木駅の駅長事務室で毛布をかけられ気を失っていたなんていう稀有な経験をしてみたりだとか、まぁ、言ってみればイカレポンティとしか言いようの無い若造だったのです。その時以来ですから、かれこれ7~8年の付き合いになる“わるい仲間”と3年ぶりに再会したのが昨日、すでにそれぞれが“いい大人”になり、環境が大きく変化した人もいれば、私のように相も変らぬ駄目人間もいて、だけれどもやっぱり飲んでしまえば、我々を隔てていた距離と時間がたちどころに消え去ってしまうのですから、共に馬鹿をした仲間と言う奴は貴重だなぁなどと再認識した次第です。とりあえず今この日記を読んでいる3名の方、約束どおり速やかに足跡を残してください。
というわけで昨日は大いに飲んだくれてしまったので日記も書けず終いでしたが、彼らと会う前には、随分と前からチケットを買っておいた『アデュー・フィリピーヌ』を。上映に先立ち蓮實重彦氏による講演などもあったため、それほど広くない会場は言うまでも無く満員御礼でした。司会者の紹介によって壇上に現れた蓮實氏は、挨拶も無しにいきなり本題に入り始めこちらを若干驚かせもしたのですが、ニーチェ的アフォリズムに始まりヴェネチアでの裏話へと到る様々な話は相変わらず面白く、ところどころで蓮實節を炸裂させたりもしているうちに45分ほどの講演時間はあっという間に過ぎていきました。詳細についてはこのあたりを参考にしていただければ。
蓮實氏曰く、日本語字幕付での上映は、今後、何かの間違いでもなければまずありえないだろうという『アデュー・フィリピーヌ』は、噂どおりの作品で、一言で言ってしまえば傑作に違いありません。これは好みの問題ですが、私は映画における三角関係というやつが好きです。ジャンルで言えば恋愛映画に相当するのもしれませんが、この三角関係という極めて映画的な題材は、それ自体青春映画にもなり得るし、危うい均衡関係に注目すればサスペンスにもなり得る。また、三角関係が下敷きになった愛憎劇ならスリラーにもなり得るというわけで、題材としての表情の豊富さから言っても、三角関係には目が無いのです。
一人の男と2人の女と聞けば、これだけでそれなりの映画が出来上がるだろうと思いもしますが、にもかかわらず『アデュー・フィリピーヌ』は、こちらの予想が全く通用しない映画でもあります。故に、観終えた今も、どのように評していいのかわかりません。事実、息を飲むような独創的な構図があるわけでもないし、ほとんど素人同然の俳優たちの演技は、所謂“上手さ”ともかけ離れているでしょう。しかし映画とは、そういった次元でのみ評価し得るものではありません。実際、あの唐突なイタリア人の登場には、その辺のコメディ以上に笑わずにはいられないし、所謂ミュージカルとは程遠いダンスシーンにも、溢れるみずみずしさを感じてしまうのですから。同じベッドで寝ている女性同士が、早朝、いったいどちらが先に起き上がって「アデュー・フィリピーヌ!」と言うのかをはらはらした思いで見守っていると、あろうことか2人が同時に起き上がり「アデュー・フィリピーヌ!」と叫ぶ。観ていない人には何だかわからないと思いますが、それはつまり、『アデュー・フィリピーヌ』こそ、観ている人間と観ていない人間を厳しく分けてしまうような映画だということなのかもしれません。兎に角、このシーンには心底感動した、という以上の、興奮と喜びと愛らしさが渾然一体となったような複雑な印象を持ち、だからこそ忘れがたいシーンだったのです。これこそヌーヴェル・ヴァーグだと、さしたる理由も無いのに言い張りたくなりました。是非もう一度観たい。何としてでももう一度観たい映画なのです。
さて、そんな大傑作を観たにもかかわらず、私がここに記しておかなければならないことがあります。それは、『「アデュー・フィリピーヌ』の上映中、終始憤っていなければならなかったということです。その時感じた怒りは、それが極稀にしか観る事が出来ない作品であったことと無関係ではなく、つまりやや大仰に言えば、このような貴重な機会に伴う至福の喜びを根底から覆されたことに存しています。
映画などそれぞれが自由に愉しめば良いという意見は最もです。好きなときに泣けばいいし、笑ってもいい。しかるべき金銭と交換に観るのであれば、尚更のことです。がしかし、この“自由”にはまた、“慎み”というものが備わっていなければならず、それは、一つのスクリーンを集団で観るという、映画の本質的な条件を考えれば当然だと言えるでしょう。仮に観客が自分一人であれば話は別です。私も嘗て、出張の際に福島のシネコンにおいて、本当に一人だけで、『マトリックス』を観た経験があり、その時ばかりは前の座席に両足を乗せ、左右の座席に両手を乗せて、まるでどこかの中小企業の社長もかくや、とばかりに図々しく映画を愉しんだクチですから。しかしながら、200数十人が詰め掛け、明らかに満員の劇場で、しかも、かかっている作品が日本未公開にして稀有の傑作である場合であれば、やはりそれぞれの観客は、自由さの中に慎みを持たねばならないわけで、例えば作品中にどうしても笑いを堪えられないシーンがあるなら、声に出して笑うなとは言いませんが、少なくとも、“声高に笑う自分の虚栄心を他の観客に誇示する”などもってのほかだし、恐らくその笑う声には、“この場面で笑わなければ、蓮實先生の言っていたことを忠実に再現できまい”とか、“今この瞬間、このシーンに笑っている自らの感性はシネフィルの名に恥じないであろう”とかいう、こうして書くことすらはばかられる陰惨な自尊心と虚栄心が見え透いていて、隣に座っている私の神経をデッキブラシか何かでゴシゴシと逆撫でさせるに充分であり、もちろん正確には数えていないのですが、上映中少なく見積もっても7回ほどの殺意が私の心中に漲り、上映後にその顔を写真に収め、モザイクなしで公開してやろうかと本気で考えたくらいです。それほどの殺意を抱くのは非常に稀ですが、そういう輩は等しく地球上から消滅してほしいと心から願いましたし、今も願っています。なんとなく顔は覚えているので、次回どこかの劇場で見かけた暁には、こちらから隣に座らないのは当たり前だとしても、もし今回のように、予め確保した席の隣にあちらが座ろうとした際には、考えうる限りの嘘をでっち上げ、両隣を死守しなければならないと決意しているところです。
『アデュー・フィリピーヌ』を想起する際、あの馬鹿のこともセットで思い出さねばならないとは、なんという悲劇。本日は予定があっていかれませんでしたが、それがどんな条件での上映であっても、次回どこかでかかった折には、体と金銭が許す限り、何としても見直さなければならないでしょう。
2004年08月20日
夏休み第二弾と『アデュー・フィリッピーヌ』
 というわけで、本日も会社を休んだ私は、やはり夏休み中の先輩とともに江ノ島へ。日頃の行いとは全く関係ないと思いますが、いやむしろ日頃の行いに反して、本日も晴天なり、海はグレイでも空の青さと照りつける太陽には癒されました。“ホットワイン”と化した赤ワインに辟易しつつも、ビーチから眺める地平線は美しく、「ああ、これだよなぁ…」と思いながらふと遠くを見ると、憑かれたようにリフティングに興じる先輩が視界に入り、その“眩しい光景”に心を奪われた私は、恐らく高校以来となる“センタリング合戦”をしてしまったり。すでにピークを過ぎた晩夏の、人もまばらな江ノ島で、“サッカーらしきもの”にはしゃぐ30代の男約2名。これはやはり異様に映ったのかもしれませんね。本人たちは、遅れてきた青春を取り戻さんがごとく汗だくになっているというのに…こんなこと書いたら先輩に怒られてしまいます。まぁ、軽いフランスジョークです。
というわけで、本日も会社を休んだ私は、やはり夏休み中の先輩とともに江ノ島へ。日頃の行いとは全く関係ないと思いますが、いやむしろ日頃の行いに反して、本日も晴天なり、海はグレイでも空の青さと照りつける太陽には癒されました。“ホットワイン”と化した赤ワインに辟易しつつも、ビーチから眺める地平線は美しく、「ああ、これだよなぁ…」と思いながらふと遠くを見ると、憑かれたようにリフティングに興じる先輩が視界に入り、その“眩しい光景”に心を奪われた私は、恐らく高校以来となる“センタリング合戦”をしてしまったり。すでにピークを過ぎた晩夏の、人もまばらな江ノ島で、“サッカーらしきもの”にはしゃぐ30代の男約2名。これはやはり異様に映ったのかもしれませんね。本人たちは、遅れてきた青春を取り戻さんがごとく汗だくになっているというのに…こんなこと書いたら先輩に怒られてしまいます。まぁ、軽いフランスジョークです。
青春と言えば、明日はヌーベルヴァーグの青春映画、ジャック・ロジエ監督『アデュー・フィリッピーヌ』を鑑賞する予定です。かなり前からチケットを予約していたので、整理券番号は2番。それでも2番なのですから、世の中上には上…(以下略)。本来なら今週末は『ある日、突然』をと決めていたのですが、そういえばチケットを取ったんだった…と忘れていた自分に改めて呆れてみたり。フランソワ・トリュフォーは嘗て、『アデュー・フィリッピーヌ』をめぐった文章の中で、“ヌーベルヴァーグとは、まさに青春を捉えるために生まれてきたのだ”と言うようなことを言っていました。先日見た『子猫をお願い』を再考するいい機会になればいいのですが。ともあれ、明日を前に久々の映画的興奮状態にいます。
『軽蔑』好きの私としては、彼が撮った短編『Bardot et Godard』をどうしても観たいのですが、DVDとか出ていないものでしょうかね。多分無いですね…
因みに、上記特集上映について、初トラックバックを! と思ったのですが、なかなか上手く見つかりませんね… いい記事があってもblogじゃなきゃ駄目なんですから。
2004年08月19日
無知に鞭打つ映画〜『華氏911』を観て思うこと
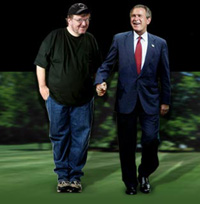 ある事実を知らないということ。それだけなら特に恐怖を感じることなど無い日常に我々は暮らしていますが、ある事実が隠蔽され、後からそれを知ったらどうなるか。恐らく、喜怒哀楽何らかの感情が表出するのではないでしょうか。
ある事実を知らないということ。それだけなら特に恐怖を感じることなど無い日常に我々は暮らしていますが、ある事実が隠蔽され、後からそれを知ったらどうなるか。恐らく、喜怒哀楽何らかの感情が表出するのではないでしょうか。
全ての映画監督に“観客に伝えたいこと”があるとは思いませんし、また、一観客として、常に映画に“監督のメッセージ”なるものを求めるという徒労を強いられたくもありません。しかし、『華氏911』を見終えた今思うのは、マイケル・ムーアが『華氏911』を作ったのは、それが隠蔽された結果であろうと無知であることに気づかないアメリカ人に対し、動かしがたい真実を伝えるという明確な目的に拠るものであったということです。そして、その目的を果たすためなら、誇張でもパロディでも泣かせる演出だってなんでもやってやるという強い意志があったのだと思います。
マヌケな日本人である私にもそれは理解できました。
『ボーリング・フォー・コロンバイン』比べ、マイケル・ムーアのストーリーテリングはかなり上手くなっていたように思われました。それはまず“娯楽映画”として観客を愉しませることを心がけたマイケル・ムーアの、映画に対する真摯な態度の表れでしょう。まず、そこを評価すべきかと。実際、エリック・クラプトンの「コカイン」が聞こえてくる部分や、西部劇の辛口なパロディ部分には笑いを禁じ得ませんでした。あるいは、オープニングからタイトルまでの展開の上手さ、9/11の映像を敢えて黒画面で隠し、次のシーンで上空を仰ぎ悲嘆にくれる人々を次々と映すことで、その“悲惨さ”を“効果的に”見せるあたりにも、マイケル・ムーアのテクニックを認めることが出来ると思います。
ブッシュについてはここで書くことなど何もありませんが、彼が“バカでマヌケ”だとしても、そのことに意識的でなければ(もしくはそれを上手く隠蔽されてしまえば)、アメリカ国民にとっても、我々日本人にとっても“バカでマヌケ”ではなくなってしまうということです。
結論として、無知はかくも恐ろしきものかな、と言ったところです。
2004年08月18日
『華氏911』は面白いのか考えてみる
折角の夏休みなのに早朝から映画に並び、その後の予定が何もないと言うのもあまりに悲しい感じがしたので、髪でも切りに行こうかと急に思い立ったまでは良かったのですが、いざ美容室に行ってみたらカーテンが下りていて、どうやらこちらも夏休み中だったようで。結局、映画+ジムという通常の週末と何らかわらない夏休み第一弾でした。
8:50分頃到着した恵比寿ガーデンシネマには、すでに20人弱の人だかりが。整理券番号をみると62番だったので、わざわざタクシーで来た甲斐もあったというものです。最終的にはほぼ満席だった『華氏911』ですが、思った以上に笑える部分が多く、同時に、真面目な部分も多い作品でした。その意味では予想以上の出来だったとは言えるものの、純粋に映画作品としての『華氏911』は、やはり非常にベタな作りではあって、例えば笑わせるための絵と音楽のタイミングは、今の“笑い”というよりは一昔前の手法なんじゃないかという気もしたくらいで。ただし、題材が題材ですし、マイケル・ムーアは、普段政治になど興味が無く、頭を使う必要もない映画を好んでみるような大方のアメリカ人のためにこの映画を作っていることを考えれば、それも戦略として受け入れることは充分できます。随所に過去の映画を引用している部分があるのですが、いずれも“政治的パロディ”としての引用で、間違っても『ドリーマーズ』におけるベルトルッチ的引用にはなっていません。
その他にも何点か思うところがありましたが、今ものすごく眠いので、続きは明日にでも。別にもったいぶっているわけではあり・・・・ま・せ・・ん・・・・・本当に眠い・・・ん・・・・・・・・・・です・・・zzz
孤独な夏休み第一弾=『華氏911』を観ること
登録してから2週間ほど経ちましたでしょうか、「blogランキング」はこのところ平行線を保っているようです。今現在19位ですが、30分ごとに更新されるランキングは以外と細かく変動しているようで、20位前後をフラフラしております。最近は、そのランキングを見てこちらに飛んできてくれる人が増えてきましたから、それなりの効果をもたらしてくれたと言って良いのではないでしょうか。私自身、他サイトのランキング上昇に貢献してみたりするのですが、いろいろ見ていますと、毎日ヴィデオを見て感想を述べていたり、毎週お薦めの映画を紹介したりと、皆さんそれぞれに精力的な感じです。ランキング上位だから面白いとかそういうことは決して無いとは思いますが、やはり頻繁に更新されているサイトというものは、それだけで一つの価値があるのでしょう。“いいとこ取り”で、見習って行きたいです。
もうすでに夏休みを消化された方も多いと思いますが、私も多分に漏れず明日あたりお休みをいただこうかと。ひとえに『華氏911』を観るためだけに。やや、というより、相当寂しい夏休みですが、それもこれも、恵比寿ガーデンシネマに行くには“それなりの覚悟”が必要だと思うからです。あそこの劇場は、以前苦い思いをさせられて以来久しく遠ざかっていたのですが、来週から拡大公開されるとはいえ、どうせ渋谷では上映しないのですし、だったら早く観てしまったほうがいいという判断で、会社を休むことにしました。まぁ、今週いっぱいはお盆休みの延長で休む同僚もちらほらいることですし、せめて映画鑑賞くらいさせておくれよ、と言った感じです。で、先日は『誰も知らない』でこちらの“甘さ”が露呈したので、今回は事前に混雑状況を聞いてみたり。しかし、何度かけても電話すら繋がらない状況。7回目くらいでやっと繋がったので、明日の初回の混雑具合を訪ねたところ、9:30の開場時間にも係わらず、8:30前からすでに列が出来ているだろう、とのこと。カンヌ効果ここに極まれり、といったところでしょうか。
というわけで、朝一で行く予定だったジムを午後一に延期し、明日は朝から並びます。ただし、観終えた後、したり顔でアメリカの政治を語ることだけは避けようと強く決意しています。すでにドキュメンタリーとフィクションの境界が曖昧になりつつある現代の映画的状況ですから、飽くまでその作品を愉しめればいいと。私は次期大統領選に意見するほど“政治的”な人間ではありませんから。
あ、それと本日よりトラックバックの受付が出来るようになりました。私も気になる記事があった時には活用していきたいと思います。
2004年08月17日
『誰も知らない』とフォトジェニック
 体の痛みも大分引いてきました。この時間になってようやく本調子になってきたのですが、こんな時間に元気なってみても仕方ないですね。
体の痛みも大分引いてきました。この時間になってようやく本調子になってきたのですが、こんな時間に元気なってみても仕方ないですね。
今日は懐かしい仲間に会いました。留学するとだけ言い残して日本を去った元同期なのですが、ひょっこりと戻ってきたと思えば、ほとんど何も変らない様子に調子が狂ってみたり。恐らく数日中にこの日記を読むことになるであろう同期に、一言だけ。
「ヴァン・ディーゼルは決してかわいくはない!!」
さて、いよいよ公開になった『華氏911』ですが、恵比寿では初日の初回が夜中だったにもかかわらず、予想通り超満員だったとか。東京でも多くの劇場で公開されますが、どうして渋谷で公開しないのでしょう? まぁ恵比寿も渋谷区だと言われてしまえばそれまでですが、『ボーリング・フォー〜』同様、これには首を傾げざるを得ません。私になど理解できないようなしかるべき理由があるのでしょう、今回は仕方なくヒルズにでも行こうかと思っています。加えて今週は、先週観られなかった『ある日、突然』を何とか観なければなりません。夏休みを未だ消化していないので、平日に会社を休んでマイケル・ムーアとはしごするのも悪くないですね。
昨日観た『誰も知らない』ですが、あれはもう一度観にいってもいいかな、と思っています。先ほど家に帰る途中、何故かあの映画のことばかり考えていたのですが、その時思ったのは、『誰も知らない』の中で最も素晴らしかった細部は、5人の子供たちに射す光ではなかったかと。彼らの髪が太陽の光を得て、“控えめに”輝くシーンがところどころとに出てくるのですが、どうもそのシーンだけが反芻されてしまうのです。どれほど照明を使ったのかは知りませんが、あの映画はかなりの部分を自然光で撮ったのではないかと思われ、ベランダのシーンが印象的なのも、そこに美しく輝く自然光があったからだと思わずにはいられません。別に、映画に常にフォトジェニックという概念を求めているわけではないつもりですが、是枝監督の“絵”は、それぞれが“絵”として成り立つ細部へのこだわりがあるのではないかと思うのです。『誰も知らない』は面白いだけでなく、美しい映画でもあったと。これは決して言葉では伝わらないでしょう。
2004年08月15日
『誰も知らない』は誰もが知っているのか?
 昨日は予定通り、“青”を求めて千葉の海まで行ってきました。快晴の青空に恵まれたものの、海の色は“青”とは言いがたく、それでも湘南などと比べると遥かに透明度の高い海だったような気がします。午前中より何をするでもなくただただ太陽の光を浴び、ビールをガブ飲みしつつ、うとうとしてみたり。気がつけばワインは2本ほど空いていて、体は真っ赤になっていました。実は今こうして日記を書いているこの瞬間にも、水着部分を除いた全身の“火傷”は甚だしく痛み、立つのも座るのも寝るのも儘ならない状態なのです。いい年して情けない限りですが、まぁ、たった一日でも“青”に同化出来たのですから、しょうがないですね。
昨日は予定通り、“青”を求めて千葉の海まで行ってきました。快晴の青空に恵まれたものの、海の色は“青”とは言いがたく、それでも湘南などと比べると遥かに透明度の高い海だったような気がします。午前中より何をするでもなくただただ太陽の光を浴び、ビールをガブ飲みしつつ、うとうとしてみたり。気がつけばワインは2本ほど空いていて、体は真っ赤になっていました。実は今こうして日記を書いているこの瞬間にも、水着部分を除いた全身の“火傷”は甚だしく痛み、立つのも座るのも寝るのも儘ならない状態なのです。いい年して情けない限りですが、まぁ、たった一日でも“青”に同化出来たのですから、しょうがないですね。
そんなこんなで昨日の夜は大して眠れなかったにもかかわらず、本日は『誰も知らない』の初回をシネ・アミューズにて。10:00からですし、雨も降っていたので流石にそれほど混雑していないだろうというこちらの“甘さ”をあざ笑うがごとく、9:30過ぎに劇場に到着したときにはすでに立ち見直前の大混雑状態。整理券番号120番なんて初めてです。受付の女性は次の回を盛んに薦めていましたが、また時間をつぶすのも面倒だったので予定通り初回を鑑賞してきました。夏休み中でしかも日曜日という悪条件もあるのでしょうが、ロビーを見渡すと、年配層と若年層が目立ち、それを見ただけで『誰も知らない』の興行的成功を確信したのですが、それは主演している彼がカンヌで主演男優賞を獲ったからというよりは、飽くまでマスコミ報道の加熱振りによるのだと思います。実際、いくら世界で一番有名な映画祭だからと言って、年に10本程度しか映画を観ない人たちが、そんな映画祭の動向に注目しているはずがないのだし、過去を振り返れば、『ユリイカ』だって2つも賞を獲得したにもかかわらず、とりわけテレヴィでの報道など皆無に等しかったがために、テアトル新宿での極短い上映期間しか与えられなかったのだし、確かに是枝監督のファンは確実に存在しているのでしょうが、少なくとも本日初回に駆けつけた人々の中には、彼の少ないフィルモグラフィーを全部観たと言える人は、恐らく2割もいないのではないかと。以上は故の無い私的恨み言だと捉えていただいて結構ですが。
そんな状況ではありましたが、映画のほうは大変面白く、満足しました。演技と言う意味でなら、YOUは映画初出演ながらなかなかいい演技を見せてくれましたし、ヤギラユウヤ君にいたっては、もはや演技とは言えないような感じも。だからと言って彼の仕草や表情には、超自然的な力が漲っていて結果的に見事としか言いようが無かったし、それは恐らく無=意識の演技に他ならず、それをさらに突き詰めれば、浅野忠信氏のようなレヴェルにまで達するのかも知れないとすら思いました。4人の子供たちは一年以上の撮影期間中、擬似的な兄弟として生活していたはずで、そのかりそめの自然さの中から演技を引き出していく是枝監督の即興的演出には前作同様舌を巻きました。それとあの一番下の女の子ですが、彼女は『KILLBILL Vol.2』に出てくる子役の女の子に匹敵するほどのかわいさと、あちらにはない悲しさが漂っていて、泣けましたね。
『誰も知らない』についても、いずれ文章にするつもりです。
本日は『ドリーマーズ』を書き上げようと思いましたが、途中まで出来上がっていた文章を会社のPCから転送し忘れていたことに気づき、また一から書くのもあまりに馬鹿馬鹿しかったので、またもや延期です。こうして書かねばならない文章がたまってくると、勢い、一つ一つが“やっつけ仕事”になりがちですが、それではこのサイトを始めた意味が全くなくなってしまうので、その辺には意識的でありたいと思う日曜日の夜です。
2004年08月13日
『13日の金曜日』に『軽蔑』を回想する意義
 昨日は結局仕事で疲れ果ててしまい、『ある日、突然』を観ることが出来ませんでした。新宿の雑踏だとか、味の薄い料理と同じくらい“夏”という季節が大嫌いな私ですが、その理由を改めて考えてみると、もちろんその暑さが一つ、汗の不快感が一つ、蝉の鳴き声が一つ、と挙げれば暇なく出てきます。すでに夏休みを満喫しているであろう学生たちや一部の社会人を横目に、若干混雑が緩和されたとはいえ、今こうして出勤しているという事実を鑑みれば、このような恨み言を連ねてしまいたくもなるというものです。
昨日は結局仕事で疲れ果ててしまい、『ある日、突然』を観ることが出来ませんでした。新宿の雑踏だとか、味の薄い料理と同じくらい“夏”という季節が大嫌いな私ですが、その理由を改めて考えてみると、もちろんその暑さが一つ、汗の不快感が一つ、蝉の鳴き声が一つ、と挙げれば暇なく出てきます。すでに夏休みを満喫しているであろう学生たちや一部の社会人を横目に、若干混雑が緩和されたとはいえ、今こうして出勤しているという事実を鑑みれば、このような恨み言を連ねてしまいたくもなるというものです。
ただし、そんな“夏嫌い”な私でも、夏の“青”に対する羨望は人一倍あると言えるかもしれません。“青”とはズバリ“海と空”に言い換えることも可能です。私などは、この“青”から最も遠い人物だと思われている節もありますし、多少は自覚もしていますが、だからこそ反動的に“青”を求めるのだということなのでしょう。常に“暑さ”とセットになった夏の“青”ですが、しかし、それが目の前に展開されてしまうと、“青”という色そのものに陶酔してしまう単純な私は、そのときばかりは“暑さ”をも忘れてしまうのです。
映画における“青”に対しても同様で、“夏”が舞台になった映画は決して嫌いではなく、むしろ好きだと言える位ですから、例えば明日から公開する『ステップ・イントゥ・リキッド』はサーフィンとは無縁の人生を送ってきた私も積極的に観に行きたいと思いますし、もちろん『ブルークラッシュ』のような映画にだって“青”という観点から見ればそれなりに美点もあることを知っています。恐らく、今に至る“青”に対する執着というか羨望は、『気狂いピエロ』と『軽蔑』に端を発していると思われ、あまりに月並みで凡庸ではありますが、実際に”あの青”を目撃してしまうと、どれほど月並みで凡庸と言われようがもうどうでもよくなってしまう、それほど衝撃的な“青”だったのです。上記2作をまだ未見の方は、是非ともこの時期に見られることをお薦めします。
さて、そんなことばかり考えているならいっそ行ってしまおう、というわけで、明日は2年ぶりに“青”を求めて千葉方面に。週末の習慣である映画とジムを追いやってまで行くのですから、一日中“青”に同化してきたいと思います。日に焼けて真っ黒になるか、酔っ払って真っ青になるかは当日次第ということで。いくら“青”が好きでも、後者は避けたいと思います。
2004年08月12日
Who is "CINEMA"
 ここ数日間、「ウイイレ8」にどっぷりはまってしまい、どうにも仕事後のヴィデオ鑑賞にまで手が回らない[M]です。
ここ数日間、「ウイイレ8」にどっぷりはまってしまい、どうにも仕事後のヴィデオ鑑賞にまで手が回らない[M]です。
あいかわらず、『ドリーマーズ』に対する言及も宙刷りのまま、今はイラストのほうを描いているのですが、今回は主要人物が3人とあって、イラストにも一苦労です。私はもともと女性を描くのが好きで、いやむしろ女性しか描かないといっても過言ではないくらいなのですが、その“完璧な”肢体に少なからず目眩を覚えたエヴァ・グリーンは、描いていても興奮してくるくらいです。ちょっと変態っぽい発言ですが、事実です。
ベルトルッチは、ヌーヴベルヴァーグへの、とりわけジャン=リュック・ゴダールに対する無防備ともいえる賛辞を連ねてきましたが、最近読み直している15年以上前の雑誌「GS」のゴダール特集には、『ドリーマーズ』でルイ・ガレルが引用して見せた有名な一節、“ニコラス・レイこそが映画だ”というゴダール流コピーの全文が掲載されていました。ゴダールはこういう言い回しが好きらしく、極端な単純化によって物事を鋭く切り取っていく彼の手さばきは、そのまま映画作品にも受け継がれている気がします。私が最近のベルトルッチに惹かれるのは、嘗てゴダールが熱烈に支持した“小さな映画”を意識的に撮ろうとしているからなのかもしれません。
さて、本日は上手く仕事が終わればシネ・アミューズにて『ある日、突然』を鑑賞する予定。ディエゴ・レルマンという新人監督が撮ったこのモノクロ・ヴィスタサイズの映画には、非常に期待しています。
ちなみに、写真はエヴァ・グリーンの母で女優のマルレーヌ・ジョベールです。ゴダールの『男性・女性』に出演した彼女の娘ですから、ベルトルッチが彼女を選んだのも頷けます。
2004年08月11日
“おすすめの映画は?”と聞かれて…
 昨日は友人らと大いに飲んでしまい、そのせいか帰宅後に律儀に蕎麦など茹でて食べたりしたくせに、いざ日記を書こうとPCに向かった途端に睡魔が襲ってきて、まさにキーボードを打ちながら睡眠に入るという離れ業をやってのけた私ですが、もちろん映画など観る余裕も無い上に、『ドリーマーズ』に関するテクストも途中のままです。
昨日は友人らと大いに飲んでしまい、そのせいか帰宅後に律儀に蕎麦など茹でて食べたりしたくせに、いざ日記を書こうとPCに向かった途端に睡魔が襲ってきて、まさにキーボードを打ちながら睡眠に入るという離れ業をやってのけた私ですが、もちろん映画など観る余裕も無い上に、『ドリーマーズ』に関するテクストも途中のままです。
飲んだ席である女性と映画の話をしたのですが、そんな時「おすすめの映画は?」などと聞かれてしまうと、自分はおすぎではないから「○○○を観て涙が止まりませんでした!」などとはとても言えないし、その女性の好みを聞くと、どうにも自分の観ている映画とはシンクロしないなと思ってしまったのですが、それでもかろうじて「『ミスティック・リバー』には感動しました」と言ってみたところ、「友達がつまらなかったって言ってた」とあっさり返されてしまう始末。その時思ったのは、例えば『シュレック2』や『トロイ』等のハリウッド大作(!?)を好んで観るさる女性に対して、『軽蔑』とか『アメリカの夜』とか『コック・ファイター』の話を熱く語っても始まらないばかりか、「ああ、映画オタクなのねこの人…」とあからさまな侮蔑の表情をされることもしばしばですが、だからと言ってその場で自分の好みを捏造してみせるほど器用ではないし、そうなるとやはり、予め2通りの答えを用意しておき、答えを上手く振り分けていくほかはないのかもしれません。映画の話はいつだって大歓迎だと思い込んでいたしていた私も、“暖簾に腕押し”では話す意味もありません。そんな反省を早朝からしているところです。
昨日観る予定だった『ある日、突然』は、木曜日に観るとします。
2004年08月09日
『ドリーマーズ』、悲痛さの彼方にある映画
 ベルトルッチは多分、ジャン=ピエール・レオーに対する羨望というか嫉妬を誰よりも抱いていた人物だったと思います。年齢は3歳しか違わない。でも、レオーはフランスに生まれ、ヌーベルヴァーグを文字通り“生きて”しまったのです。フランス人でない自分に激しく憤って見せた若きベルトルッチの思いが、30年という時間を経ていかに変化したのか、もしくは、しなかったのか。『ドリーマーズ』という私的な映画の内に、何らかの回答を読み取ろうとしたのも、まさにその一点においてです。
ベルトルッチは多分、ジャン=ピエール・レオーに対する羨望というか嫉妬を誰よりも抱いていた人物だったと思います。年齢は3歳しか違わない。でも、レオーはフランスに生まれ、ヌーベルヴァーグを文字通り“生きて”しまったのです。フランス人でない自分に激しく憤って見せた若きベルトルッチの思いが、30年という時間を経ていかに変化したのか、もしくは、しなかったのか。『ドリーマーズ』という私的な映画の内に、何らかの回答を読み取ろうとしたのも、まさにその一点においてです。
3人の主人公のうち、マイケル・ピットだけが“他者”なのは言うまでもありません。残る2人は決して分け入ることが出来ない双子で、しかもフランス人だからです。他者であるマイケル・ピットは、映画に夢を、未来を、政治を重ね、ヌーベルヴァーグへの憧れを抱える熱いシネフィルですが、ここにベルトルッチ自身の過去が少なからず反映しているのは間違いなかろうと思います。“巴里の伊太利亜人”であった10代のベルトルッチが、どれほどヌーベルヴァーグに傾倒し、正統な嫡子だと思い込んだところでどうにもならない国籍の問題が、ここには表れています。つまり、『ドリーマーズ』において、マイケル・ピットは“アメリカの友人”でしかないという真実を最後まで超えることは無いのです。
60年代のゴダールが臆面もなくやって見せた数々の引用が、『ドリーマーズ』にも多く見受けられます。あまりにストレート過ぎるヌーベルヴァーグへのオマージュについて考えてみた時、その対極にもう一人の監督が浮かびました。ヴィム・ヴェンダースです。
ヴェンダースは77年に『アメリカの友人』という作品を撮っています。やはり“ゴダール以降”の作家であるヴェンダースも、ある時空への郷愁を作品に刻んでしまった過去があります。ベルトルッチがヌーベルヴァーグへの想いを映画にしたように、ヴェンダースもアメリカ映画への想いを映画にしたというわけです。ただし、この2人の差は極めて大きい。とりわけ、ヴェンダースのそれははるかに屈折した形で映画になってしまったのです。『アメリカの友人』を観ても、『ドリーマーズ』を観たときに抱かせるようなノスタルジックな感慨は皆無でしょう。すでに老齢に差し掛かったサミュエル・フラー(『ドリーマーズ』にはフラーの『ショック集団』も引用されています)やニコラス・レイというアメリカ映画の巨匠たちを、あろうことか俳優にして引っ張り出したヴェンダースの歪んだ想いは、もはやノスタルジーですらありませんでした。しかし、そのほうが遥かに“ゴダール的”なのは言うまでもないでしょう。原典(歴史)を破壊しかねない強度、ほとんど破綻すれすれで模倣しようとする態度にそれが認められるからです。そしてその悲痛さが『アメリカの友人』を傑作たらしめているのだと思います。少なくとも人は、「ニコラス・レイこそ映画だ」というゴダールの言葉をそのまま引用することに、安易な印象しか抱かないでしょう。過去に対する倫理観の差が、この2人監督の間に厳しく横たわっているとのかもしれません。それにしても、ベルトルッチは本当に68年への青臭い郷愁だけで『ドリーマーズ』を作ったのでしょうか・・・…?
あるいは、ベルトルッチは自覚的だったのでは。あの当時の感情を今表現することの不可能性に。実際、3人がルーヴルを駆け抜けるシーンの直後に原典である『はなればなれに』を配置してみるベルトルッチにはある種の痛ましさすら覚えます。いくら『はなればなれに』の記録を更新したと言っても、それ自体がとてもパロディーにはなりがたく、律儀な反復への欲求を露呈するばかりです。その意味でこのシーンは、予め原典への負けを義務付けられていると言えます。現在のジャン=ピエール・レオーに過去(5月革命におけるアジテーション)を反復させることもまた、同様に悲痛な印象しか与えません。恐らく、ヌーベルヴァーグを模倣することの不可能性と無意味さの再認識、そして、もはや68年当時の、変革への期待や保護されたユートピア幻想などこの時代にはありえないという諦念が、『ドリーマーズ』の出発点に据えられたのではないでしょうか。つまり、ベルトルッチは60歳を過ぎた年齢にして改めて自己と向かい合い、当時の意識を対象化しようとしているのだと思います。自らのルーツを再び探りあてる試みには、あの時代を一端客観視し、時にはその対象に溺れる覚悟が必要だったのではないでしょうか。
『ドリーマーズ』において垣間見られぬでもない、近親相姦的官能だとか、年齢の割りに大人びた女の悪女的なまめかしさだとか、あるいは男色的退廃だとかは、ベルトルッチの諦念を隠すための、ほとんど無意味な隠れ蓑に過ぎません。にもかかわらず、迷路のようなアパルトマンと、深い諦念が全編を多い尽くしています。『ドリーマーズ』を駄作だと言うことが躊躇われるのは、決して破綻やしているわけではない物語や演出を許容できるからではなく、ひたすら悲痛さの印象しか与えないからです。
結局私が求めたベルトルッチの回答があったとすれば、そのように解釈したいと思います。
“話題作”『ドリーマーズ』
東京でもとりわけ苦手な場所である新宿、仕事関係ならともかく、プライヴェートだったらそれこそ映画を観るという目的でもなければまず足を運ぶことが無いのですが、日曜日は久々に新宿武蔵野館にて『ドリーマーズ』を。ここに来たのは確か『自殺サークル』以来だったような…。12:10の初回を観たのですが、84席ある客席は25人ほどしか埋まっていませんでした。武蔵野館にはスクリーンが3つあるのですが、11時台に初回を迎えていた『モナリザ・スマイル』とか『ぼくセザール 10歳半 1m39cm』などは早い時間にもかかわらず結構混雑していたことを考えると、“あのベルトルッチ”でも現実にはこの程度の客しか集められないということでしょうか。にもかかわらず、『ドリーマーズ』には68年という時代を知らない私にも感動的な細部に溢れていました。詳しくは、近々「reviews」のコーナーに。
今週は、シネ・アミューズでレイトショー公開している『ある日、突然』を観にいくつもりです。時間的に平日仕事の後というのがベストなので、明日にでも。アルゼンチン映画と聞いても、フェルナンド・E・ソラナスという名前がかろうじて浮かぶ程度、観ている映画もほとんど皆無に等しいような…そういえば、60年代〜70年代に流行した擬似ドキュメンタリー的ゲテモノ映画の代表的作品『スナッフ』もアルゼンチン映画でした。撮影中実際に殺人が行われたという噂が流れヒットしたらしい本作ですが、その後あっさりネタバレしていたみたいです。確か高校生のときくらいに雑誌で知って、地元のレンタルヴィデオ店を探しまくった記憶があります。まだまだ無垢だったあの頃…もうあんな時代は戻ってきません。
「blogランキング」は順調に推移しているようです。現在35位。知り合いからは「知らない作品ばかり出てきて、コメントの仕様が無い!」などと言われてしまった当サイトですが、「blogランキング」にあるサイトをいくつか見てみると、確かに所謂話題作の短評が大半。まぁ、あまり似たようなサイトばかりでも面白くないので、こちらはこちらのペースで続けていくしかないようです。この分だと誰もコメントしてくれないかもしれませんね。『ドリーマーズ』も充分話題作なんだけどナァ… 一部で誤解があるようなので書き添えておくと、基本的にあからさまな宣伝以外のコメントは削除したりはしませんyo。まぁ、あまりに私個人のネタ(笑えないようなヤツ)である場合は、やはりその限りではありませんが。ですから、別に『セカチュー』のことでも、『踊る〜』シリーズのことでも、現在公開していない作品についてでも、映画に関することであれば何でも結構ですので、お気軽・お気楽にお書き込みください。若干韻を踏んだところで、今回は終わります。
2004年08月07日
ウィークエンドですが、『WEEKEND』はまた今度
 週末のこの時間に家でインターネットです。本日鑑賞予定だった『ドリーマーズ』を訳あって明日に延期したのですが、これから我が家を訪ねて来るであろう友人を待っている手前、そうそう出かけるわけにもいかず、開き直ってウォッカなどを飲みながらblogっています。
週末のこの時間に家でインターネットです。本日鑑賞予定だった『ドリーマーズ』を訳あって明日に延期したのですが、これから我が家を訪ねて来るであろう友人を待っている手前、そうそう出かけるわけにもいかず、開き直ってウォッカなどを飲みながらblogっています。
さて、いつの間にやらゴダールの『WEEKEND』がDVD化されていました。今度は単品として。すでに鑑賞済みですが、これは買ってもいいかなと思っています。あの正気とは思えないトラヴェリングを観たいがために。とはいっても、私は基本的にdvdやヴォデオを購入することなどほとんどなくて、でもやっぱりいい作品は繰り返し観たいものですから、その都度レンタルするわけです。これを無駄遣いといわずして何と言いましょうか。『気狂いピエロ』など、もう何回借りたかわかりません。それこそ“気狂い”みたいに借りまくっていたくらいで。流石に今は入手しておりますが。
ある作品を“観たい”という欲求と“所有したい”という欲求は全く違う性質もので、私などはほとんど前者のみと言っていいくらいですが、つまりそれは“ケチ”だということなのでしょう。そうです、私はケチなんですね、多分…
大分気が滅入ってきたのでそろそろ終わります。
連日お伝え(むしろ宣伝?)している「blogランキング」ですが、現在59位です。基本的にランキングと名のつくものとは無縁の人生を送ってきましたが、400サイト程度しか登録されていない中で、どのくらいに位置すれば自分は満足なのか、まったく見当がつかないというのが本音です。まぁ、リンク一つ張っただけで見知らぬ人がこのサイトを訪ねてきてくれるなら、それだけで満足と言えるのでしょうね。
2004年08月06日
左側に気をつけろ
といっても、別にジャック・タチには関係ありません。このサイトの左側にある「reviews」部分に、『KILL BILL』を追加しました。
それと、昨日の日記に書きました、「blogランキング」へのリンクを、もう少し分かりやすい部分に移動させました。「about」の中です。ちなみに、今現在92位ですか。
意味あるのかな、これ…
2004年08月05日
遅ればせの『KILLBILL』評ですが…
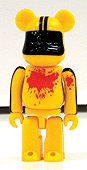 長らく放置されていた『KILLBILL』に関するテクストですが、これに決着をつけないと、この先、いかなる映画のテクストも書き上げられないと思い、昨日から再度書き始めました。で、どうやら完成しそうです。ページ作成の関係上、明日の昼には。これまで取り上げてきた3本はどちらかというと硬質の作品に属するものだったので、所謂娯楽作のように誰もが見るものではなかったと思いますが、『KILLBILL』は多くの人に観られている作品です。個人的な思い入れもありましたので、若干長めのテクストになってしまいました。まぁ、私の中では、これで一応の決着はついたと胸を撫で下ろしています。
長らく放置されていた『KILLBILL』に関するテクストですが、これに決着をつけないと、この先、いかなる映画のテクストも書き上げられないと思い、昨日から再度書き始めました。で、どうやら完成しそうです。ページ作成の関係上、明日の昼には。これまで取り上げてきた3本はどちらかというと硬質の作品に属するものだったので、所謂娯楽作のように誰もが見るものではなかったと思いますが、『KILLBILL』は多くの人に観られている作品です。個人的な思い入れもありましたので、若干長めのテクストになってしまいました。まぁ、私の中では、これで一応の決着はついたと胸を撫で下ろしています。
本当は『ドッグヴィル』や『エレファント』についても書きたいのですが、これまでのように過去を振り返って文章を書くということに、そろそろ限界を感じつつあります。よって今後は、毎週観る作品について、時評的に、それほど長くない文章を書いていこうかと思います。こういうサイトは、やはり、ある程度の作品数の多さが必要だと思うからです。自分の怠惰を棚に上げてよく言いますが、こんな姿勢も見る人が見れば精力的に見えてしまうこともありうるので、そちらのほうに期待したいと。
さて、これから最後の仕上げに入るとします。今日は映画が観られないでしょう……多分。
あ、それと、恥ずかしながら「blogランキング」というやつに登録してみました。ZEROに等しい赤子のようなサイトですから、未だ親を探している段階とでもいいましょうか…なんだかよくわからない言い訳ですが、まぁ、見られないよりは見られるほうがいいという単純な判断によるものです。このページをご覧になった方、私の親探しをどうか手伝ってやってください。左のメニューにある、しかるべきリンク(「LINKS」の最下部)をクリックしていただければ、幸いです。
2004年08月04日
『ジプシーは空にきえる』の簡潔なラストは悪くない
 “ジプシー”という言葉を聞いて、人は瞬間的に何を想起するでしょうか。一般的に、などと総括するほど、私は“ジプシー”について誰かと話をしたことが無いのですが、例えば“泥棒”とか、“ジプシー・キングス”だとか、“スペイン”だとか、“汚い服装”だとか、まぁいろいろな答えが出てくるのではないでしょうか。
“ジプシー”という言葉を聞いて、人は瞬間的に何を想起するでしょうか。一般的に、などと総括するほど、私は“ジプシー”について誰かと話をしたことが無いのですが、例えば“泥棒”とか、“ジプシー・キングス”だとか、“スペイン”だとか、“汚い服装”だとか、まぁいろいろな答えが出てくるのではないでしょうか。
それが映画好きともなると、トニー・ガトリフやエミール・クストリッツァの名前が挙がるのかもしれませんが、ここで鈴木清順を思い浮かべた人がいても、もちろん不思議ではありません。邦訳にして“ジプシーの歌”という映画を撮ったくらいですから。
さて、そんなことを言っておきながら、私自身は“ジプシー”に関する知識は皆無に等しいわけですが、昨日鑑賞した『ジプシーは空にきえる』は、彼らの歴史と生きる上での心構えみたいなものが“なんとなく”理解できたという意味で、なかなか興味深い作品でした。1976年のモスフィルム作品である本作は、同年のサンセバスチャン映画祭でグランプリに輝いた名作のようですが、恥ずかしながらその名前すら知りませんでした。例によって、無知な私にDVDをお貸しくださるFさんのおかげで知り得たのですが、当然、原作がゴーリキーの処女作だとか、その舞台がモルダヴィア共和国だということすら知らなかったのです。つまり、予備知識ゼロで作品に臨んだ、と。
若干身構えつつ、シネスコで撮られた画面を見ていると、ステップ気候による黄色い大地に数頭の馬が緩やかに歩いています。ジプシーたちの所有するその馬たちは、程なく、軍の将校らしき男たちに囲まれ、右往左往しながら何とか逃げようとする。ここで軍の将校とジプシーによる追跡シーンがあるのですが、注目すべきは、最終的に将校に撃たれるジプシーが馬から落ちる瞬間をスローモーションで捉えていたということです。全体を通せばやや異様にも映るスローモーションが、本作には数回出てくるのです(中盤、ジプシーの女性たちが踊るシーンでも、何故かスローが挟まれます)。撃たれるシーンを叙情的に引き伸ばしたのでしょうが、だとするなら、このソ連映画にもサム・ペキンパーの記憶を持つ監督がいたということでしょうか。
所謂“運命の女”と、彼女に翻弄される男という図式からはみ出ない本作ですが、ミュージカルというにはいささか粗野な、しかし悪くない歌とダンスのシーンが、さらに言えば、色彩溢れる衣装を加えても良いですが、“地味”なこの映画に“華”を添えていたのは間違いないと思います。
そして、ラストシーン。すでに中盤辺りで主人公の運命的な死を予感した私ですが、その死は、予想を超えた唐突さであっけなく画面から消えていきました。“運命の女”ラーダの心臓を、彼女を愛し、自由を愛するゾバールがナイフで突き刺すシーンは本当にあっけなくて、その直後にゾバールがラーダの父親からやはりナイフで報復されるシーンもまたあっけない。そして、それらの光景を下に見ながら、カメラはグっと引いていき映画は終わるのです。この潔いラストシーンは決して悪くなかったと言えます。前述のスローモーションや、やや凝ってはいますがちょっと不自然なカメラも、最終的にまぁいいんじゃないか、と思えたのもこの簡潔なラストシーン故だったのかもしれません。
2004年08月02日
庵野秀明『式日』とカタルシス
 週末からの寝不足を解消すべく、本日は早めに仕事を切り上げ自宅にてヴィデオを観ました。劇場公開を見逃し、それ以降も何故かレンタルしそびれていた『式日』を。作品の鑑賞において、そこに展開される世界への感情移入が行われることで、日常生活の中で抑圧されていた感情が解放され、快感がもたらされることを、一般には“カタルシス”というようですが、私が鑑賞後に味わった感情は、これに近いものだったのかもしれません。あるいは、全く関係ない感情かもしれませんが。まさか、と思われる方がいるのも先刻承知なのは、ほかならぬ私自身がそう思うからで、ではその原因とやらを考えてみると、藤谷文子が演じていた女性に対するある種のデジャヴュめいた感情によるものかと。ここでの詳述はしませんが、現実と虚構の境界線に意識的であっても、私のような通俗的人間にあっては、映画に現実世界の陰画を見てしまうことも大いにありえるのだというにとどめておきます。
週末からの寝不足を解消すべく、本日は早めに仕事を切り上げ自宅にてヴィデオを観ました。劇場公開を見逃し、それ以降も何故かレンタルしそびれていた『式日』を。作品の鑑賞において、そこに展開される世界への感情移入が行われることで、日常生活の中で抑圧されていた感情が解放され、快感がもたらされることを、一般には“カタルシス”というようですが、私が鑑賞後に味わった感情は、これに近いものだったのかもしれません。あるいは、全く関係ない感情かもしれませんが。まさか、と思われる方がいるのも先刻承知なのは、ほかならぬ私自身がそう思うからで、ではその原因とやらを考えてみると、藤谷文子が演じていた女性に対するある種のデジャヴュめいた感情によるものかと。ここでの詳述はしませんが、現実と虚構の境界線に意識的であっても、私のような通俗的人間にあっては、映画に現実世界の陰画を見てしまうことも大いにありえるのだというにとどめておきます。
庵野秀明監督の劇場長編作品は、『エヴァンゲリオン』2作品と『ラブ&ポップ』を観ていましたが、とりわけ“実写”である後者において印象的だった“ナレーション”と“線路”は、庵野氏の映画に対するアプローチとして重要なファクターになるのではないでしょうか。最も、『キューティーハニー』は未見ですし、そこにある重要な意味を持った“線路”が出てくるとは思えないので、単なる思い付きですが。
ラスト直前の、約8分間程続くシークエンスショットは、画面手前に岩井俊二を、左奥には母親役の大竹しのぶ、右奥には娘役の藤谷文子が、いうなれば三角形に配置された構図でした。その構図を変えずに、無論切り返しなど使わず緊張から弛緩、号泣から笑顔へと移行していく大変素晴らしいシーンで、それがラストシーンの“本当の笑顔”へと繋がる様は全く見事だと言うほかはありませんでした。
敢えてベタにCoccoの「レイン」エンディングとしてをもって来る辺りも、やはり『ラブ&ポップ』の感動的な「あの素晴らしい愛をもう一度」と同じくとても馬鹿には出来ませんよ。彼が観客に与えるであろう、技巧的で衒学的ないやらしさの印象が鼻につくという事実のすべてを否定はしませんが、私は決して嫌いではない監督です。
それにしても、あの留守電の声は大竹しのぶではなく、『エヴァ』の三石琴乃に聞こえて仕方ありませんでした…
2004年08月01日
フレームサイズと『地球で最後のふたり』
 土曜日は“フレームサイズを考える”と題した「boid.net」主催のオールナイトイベントに、本日はシネ・アミューズにて『地球で最後のふたり』を鑑賞し、帰宅後ヴィデオにて『コンクリート』を。先ほど観終えた『コンクリート』以外は、なかなか刺激的なフィルム体験をもたらしてくれました。
土曜日は“フレームサイズを考える”と題した「boid.net」主催のオールナイトイベントに、本日はシネ・アミューズにて『地球で最後のふたり』を鑑賞し、帰宅後ヴィデオにて『コンクリート』を。先ほど観終えた『コンクリート』以外は、なかなか刺激的なフィルム体験をもたらしてくれました。
よほどの映画好き以外、実はあまり意識して観る人がいないのではないか、とも思われる“フレームサイズ”。しかし、映画とはこの問題を無視して成立しえないメディアだ、なんて今更私が言うまでもありません。それを意識しないでいることは簡単でも、映画の制度上、もしくは成立条件から言っても、その抑圧から逃れることなど決して出来ないからです。今回のイベントでは、青山真治監督、キャメラマンのたむらまさき氏、批評家の安井豊氏によるトークショーが催されましたが、約1時間にわたる彼らの話を聞いてみて感じたのは、制作側と観客側の絶対的な温度差です。彼らはフレームサイズに対する大きなこだわりがあり、というよりも、フレームサイズが映画そのものを左右してしまいもするのですからそれは当然と言えば当然なのですが、それに対し観客はと言うと、ヴィスタサイズを観ても当たり前過ぎて特に何も感じず、たまにスタンダードサイズを観ればなんだか画面が小さいなぁ、くらいの感想しか抱かないのでしょうし、もちろんそのサイズがどんな比率から成り立っているのかを知っている必要もないわけです。しかし、何故『ユリイカ』はシネスコで撮られたのか、何故『エレファント』はスタンダードだったのか、そんなことを考えてみると、それはそれで新しい映画の愉しみ方を絶対に提供してくれるはずで、新たな発見もあったりするのではないかと。少なくとも昨日のイベントで上映された4作品に関しては、常に“フレームサイズ”を意識しながら鑑賞することを予め義務づけられてもいたので、朝方には欠伸を連発させもしましたが、悪くない疲労感とかなりの充実感を得られました。
『箪笥』のおかげでありえないほどの飽和状態だったシネ・アミューズで観た『地球で最後のふたり』は、クリストファー・ドイルにしては“落ち着いた”キャメラワークで、緩やかなトラヴェリングだとか、要所要所に見られる斜め上からの俯瞰だとか、対象をドア越しにやや引き気味で、突き放したような印象すら与える的確なロングショットだとかを見るにつけ、ことごとくこちらを上手く乗せてくれるので、比較的長めの上映時間を全く感じさせず、見終えた後は、外の蒸し暑い天気のわりには、妙に清清しい気分で家路に着くことが出来ました。浅野忠信氏の演技も、もはや“国際的俳優”に相応しく堂に入ったもので、特に驚いたときやちょっと笑う瞬間の、ほとんど“素”との境界線があるか無いかのラインでの演技は本当に素晴らしかったと思います。ヴェネチアでの賞も納得です。
最後に『コンクリート』に関してですが、敢えて意味が通らないのを承知して言えば、これはもう映画ですらない作品と言いましょうか、あそこまで安易な発想とテクニックの不在とに犯されてしまうと、それがたとえ映画作品であっても、容易くは認めたくないという反動的な姿勢にならざるを得ません。これは専らプロデューサーの責任ではないかと思うのですが、この作品の持つ“レア度”が、ありえない付加価値を与えてしまい兼ねないな、とも思ってみたり。諸々の背景を一端無視した上で、本年度、この作品を超えるワーストは存在しないと断言しておきます。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]



