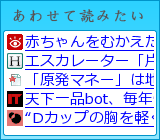2004年08月09日
『ドリーマーズ』、悲痛さの彼方にある映画
 ベルトルッチは多分、ジャン=ピエール・レオーに対する羨望というか嫉妬を誰よりも抱いていた人物だったと思います。年齢は3歳しか違わない。でも、レオーはフランスに生まれ、ヌーベルヴァーグを文字通り“生きて”しまったのです。フランス人でない自分に激しく憤って見せた若きベルトルッチの思いが、30年という時間を経ていかに変化したのか、もしくは、しなかったのか。『ドリーマーズ』という私的な映画の内に、何らかの回答を読み取ろうとしたのも、まさにその一点においてです。
ベルトルッチは多分、ジャン=ピエール・レオーに対する羨望というか嫉妬を誰よりも抱いていた人物だったと思います。年齢は3歳しか違わない。でも、レオーはフランスに生まれ、ヌーベルヴァーグを文字通り“生きて”しまったのです。フランス人でない自分に激しく憤って見せた若きベルトルッチの思いが、30年という時間を経ていかに変化したのか、もしくは、しなかったのか。『ドリーマーズ』という私的な映画の内に、何らかの回答を読み取ろうとしたのも、まさにその一点においてです。
3人の主人公のうち、マイケル・ピットだけが“他者”なのは言うまでもありません。残る2人は決して分け入ることが出来ない双子で、しかもフランス人だからです。他者であるマイケル・ピットは、映画に夢を、未来を、政治を重ね、ヌーベルヴァーグへの憧れを抱える熱いシネフィルですが、ここにベルトルッチ自身の過去が少なからず反映しているのは間違いなかろうと思います。“巴里の伊太利亜人”であった10代のベルトルッチが、どれほどヌーベルヴァーグに傾倒し、正統な嫡子だと思い込んだところでどうにもならない国籍の問題が、ここには表れています。つまり、『ドリーマーズ』において、マイケル・ピットは“アメリカの友人”でしかないという真実を最後まで超えることは無いのです。
60年代のゴダールが臆面もなくやって見せた数々の引用が、『ドリーマーズ』にも多く見受けられます。あまりにストレート過ぎるヌーベルヴァーグへのオマージュについて考えてみた時、その対極にもう一人の監督が浮かびました。ヴィム・ヴェンダースです。
ヴェンダースは77年に『アメリカの友人』という作品を撮っています。やはり“ゴダール以降”の作家であるヴェンダースも、ある時空への郷愁を作品に刻んでしまった過去があります。ベルトルッチがヌーベルヴァーグへの想いを映画にしたように、ヴェンダースもアメリカ映画への想いを映画にしたというわけです。ただし、この2人の差は極めて大きい。とりわけ、ヴェンダースのそれははるかに屈折した形で映画になってしまったのです。『アメリカの友人』を観ても、『ドリーマーズ』を観たときに抱かせるようなノスタルジックな感慨は皆無でしょう。すでに老齢に差し掛かったサミュエル・フラー(『ドリーマーズ』にはフラーの『ショック集団』も引用されています)やニコラス・レイというアメリカ映画の巨匠たちを、あろうことか俳優にして引っ張り出したヴェンダースの歪んだ想いは、もはやノスタルジーですらありませんでした。しかし、そのほうが遥かに“ゴダール的”なのは言うまでもないでしょう。原典(歴史)を破壊しかねない強度、ほとんど破綻すれすれで模倣しようとする態度にそれが認められるからです。そしてその悲痛さが『アメリカの友人』を傑作たらしめているのだと思います。少なくとも人は、「ニコラス・レイこそ映画だ」というゴダールの言葉をそのまま引用することに、安易な印象しか抱かないでしょう。過去に対する倫理観の差が、この2人監督の間に厳しく横たわっているとのかもしれません。それにしても、ベルトルッチは本当に68年への青臭い郷愁だけで『ドリーマーズ』を作ったのでしょうか・・・…?
あるいは、ベルトルッチは自覚的だったのでは。あの当時の感情を今表現することの不可能性に。実際、3人がルーヴルを駆け抜けるシーンの直後に原典である『はなればなれに』を配置してみるベルトルッチにはある種の痛ましさすら覚えます。いくら『はなればなれに』の記録を更新したと言っても、それ自体がとてもパロディーにはなりがたく、律儀な反復への欲求を露呈するばかりです。その意味でこのシーンは、予め原典への負けを義務付けられていると言えます。現在のジャン=ピエール・レオーに過去(5月革命におけるアジテーション)を反復させることもまた、同様に悲痛な印象しか与えません。恐らく、ヌーベルヴァーグを模倣することの不可能性と無意味さの再認識、そして、もはや68年当時の、変革への期待や保護されたユートピア幻想などこの時代にはありえないという諦念が、『ドリーマーズ』の出発点に据えられたのではないでしょうか。つまり、ベルトルッチは60歳を過ぎた年齢にして改めて自己と向かい合い、当時の意識を対象化しようとしているのだと思います。自らのルーツを再び探りあてる試みには、あの時代を一端客観視し、時にはその対象に溺れる覚悟が必要だったのではないでしょうか。
『ドリーマーズ』において垣間見られぬでもない、近親相姦的官能だとか、年齢の割りに大人びた女の悪女的なまめかしさだとか、あるいは男色的退廃だとかは、ベルトルッチの諦念を隠すための、ほとんど無意味な隠れ蓑に過ぎません。にもかかわらず、迷路のようなアパルトマンと、深い諦念が全編を多い尽くしています。『ドリーマーズ』を駄作だと言うことが躊躇われるのは、決して破綻やしているわけではない物語や演出を許容できるからではなく、ひたすら悲痛さの印象しか与えないからです。
結局私が求めたベルトルッチの回答があったとすれば、そのように解釈したいと思います。
2004年08月09日 10:38 | 邦題:た行

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]