2005年07月29日
現状=映画≦海
今月は映画サイト運営者としてあるまじき事態、とばかりに映画を観ておりません。先日書いた「必見備忘録7月編」を見直してみると、そこに掲げられた15本のうち2本しか観ておらず、体たらくというほかありません。
自分の意思によりそのような結果になったとは言え、じゃあ滞っているレビューのほうを書いても良さそうなものなのに、それもなかなか捗りません。かように怠惰がスパイラルを描いている日常ですが、今週末はまたぞろ海のほうに繰り出す予定。めっきり黒くなった自分を鏡で見るにつけ、一昔前のAV男優を見ているようで若干恥ずかしくもなりますが、期間限定ですし、いい気分転換にはなっております。
今日は上手く行けば日仏にてカール・テホ・ドライヤーの『ゲアトルーズ』に間に合うかもしれません。この1本が観られれば新作3本分くらいの満足感が得られそうな予感がするので、無理やりでも仕事を切り上げたいところです。
週末、出来れば『運命じゃない人』『アイランド』あたりも観られれば、と。
あ、『ミリオンダラー・ベイビー』のレビュー、少しずつ構想を開始しました。あくまで構想の段階です、はい。
2005年07月28日
『受取人不明』、その美しさは恐ろしくもある
原題:ADDRESS UNKNOWN
上映時間:119分
監督:キム・ギドク
前期キム・ギドク作品の、というより、私の中では今のところ一番評価しているかもしれない怪作。日本未公開の本作は、「韓流シネマフェスティヴァル」という、時流に乗っただけの軽い催しに組み込まれながらも、そんな軽さを強く拒絶するような狂暴な光を放っていました。
黒人との混血青年と受取人不明の手紙を出し続ける母、兄の玩具銃により片目を失った少女と彼女を救うどころかさらなる責め苦を与える薬中の米兵、混血青年をこき使う狂暴な犬の屠殺人、そして、少女に思いを寄せる内向的な少年……これらの人物は、言ってみれば韓国という国の底辺に蠢く獣です。彼らの、誠実で真摯な想いすら、不条理な不幸が容赦なくかき消していくでしょう。彼らがたとえ死から免れたところで、一体何が変わるのか。
『受取人不明』には、キム・ギドクの“怒り”が随所で炸裂しているかのようです。しかしだからといって、その“怒り”にはまるで温度を感じません。全てがただの出来事として、淡々と描かれていきます。そう、この“引いた目線”こそが最も恐ろしいのだということが、彼の作品から受ける印象です。そしてその事実が、これまで同様、絵画的なショットを生み出す理由でもあると思います。
この救いの無い残酷な映画においても、キム・ギドクの作品はやはり美しいのです。
2005年07月27日
『毛の生えた拳銃』と『世界』を経て、華麗に現実から逃避した数日間
 これまでは日常的に、目の前に横たわる現実を出来るだけ現実として見据え、それに対峙するようにしてきた私ですが、この季節、流石に現実から逃避したくもなり、それをストレスと言うなら、そのようなストレスがたまること事態、東京に住む現代人として出来る限り避けねばならないと思ってもいるので、ここは一つ「エスケイプ from 現実!」とばかりに、ちょっと現実逃避してきました。この場で詳述は避けますが、とりあえずの脱皮は完了し本日からまたもとの生活に戻れそうです。
これまでは日常的に、目の前に横たわる現実を出来るだけ現実として見据え、それに対峙するようにしてきた私ですが、この季節、流石に現実から逃避したくもなり、それをストレスと言うなら、そのようなストレスがたまること事態、東京に住む現代人として出来る限り避けねばならないと思ってもいるので、ここは一つ「エスケイプ from 現実!」とばかりに、ちょっと現実逃避してきました。この場で詳述は避けますが、とりあえずの脱皮は完了し本日からまたもとの生活に戻れそうです。
ちなみに、右上に掲げた1枚の写真にさしたる意味はありません。これを観た方は、なんだかホモセクシュアルな如何わしい写真のように思われるかもしれませんが、ストレスから開放されたある男のフィクションとして、軽く流し観していただければと。これもあくまで一つの象徴です。それが誰であるかはさして問題ではないのです。間違っても私ではありませんので、どうかお間違えなきよう。
というわけで、更新が滞っている間にも何件かコメント等いただきありがとうございます。先日観た『毛の生えた拳銃』や『世界』の内容については、別途短評あたりで触れることになるとは思いますが、ひとまず22日を振り返ってみたいと思います。実際、先週末も映画は1本も観ておらず、特に書くこともないのです。まぁ今月、来月はこんなペースになってしまうかもしれませんが、体よくまとめれば“充電期間”ということで、このスローペースをご了承いただければと。
さて、わざわざ会社を休んだ22日は先日も書いたとおり、まずはポレポレ東中野で開催中の「若松孝二レトロスペクティブ」から、あえて若松を避け、大和屋竺の『毛の生えた拳銃』に。平日の15:00過ぎの上映にもかかわらず、劇場は8割がた埋まっていました。同じ時間帯にユーロスペースで上映中の『運命じゃない人』に行ったとしても、恐らくここまでの観客は入らなかったのではないでしょうか。かつてはラピュタ阿佐ヶ谷で、つい最近もシネマアートン下北沢で特集上映されていた『荒野のダッチワイフ』をことごとく見逃し、だからといって何故か大和屋竺だけはdvd等で観る気にもならず、このような機会はもう逃せない、このセレクトはそんな理由に因るのでした。モノクロ・シネマスコープで撮られた本作は、68年の制作。保存状態はあまり良いとは言えず、タイトルバックなどはかなりのノイズと歪みが見られましたが、何とも説明しずらい程に不条理極まりない本編に入ってしまえば、“大和屋ワールド”とも言うべき言葉をはねつけるような画面の連鎖に終始目を奪われっぱなしで、80分はあっという間に終ってしまいました。若かりし麿赤兒と大久保鷹の挑発的な出鱈目さ。我々観客の目は、最後まで欺かれていたような気がします。時間軸はずらされ、交わされる会話も要領を得ず、消し去るべき存在を二人の殺し屋が消せないどころか、エロティックな夢想の対象となったりする。いや、こんな説明は観ていない人にとっては意味不明でしょう。しかし、もう一度観れば比較的長めの文章を書けそうなくらい、濃密な映画体験なのです。タイトルバックにおける写真の使用法に始まり、鏡を用いた象徴的ショットや妙に図式的なショットの数々。それらは一見馬鹿馬鹿しかったりするので笑いを誘いもするのですが、そんな笑いにごまかされてしまうと、最後まで大和屋の実像を掴みきれないでしょう。『処女ゲバゲバ』といい本作といい、日本映画はこの時点でかなりのレヴェルに達していたことがわかります。大和屋、ひいては若松は、今なお恐ろしき存在だと確信させます。
続いてSKIPシティで開催されていた「国際Dシネマ映画祭2005」に参加するため川口へ。17:40開場でしたので、東中野から急いで向かいました。初めて降り立った川口駅でしたのでバス停の場所もわからず、やっと見つけ出したバス停の時刻表を見るも、バスが1時間に2本しか走っておらず、半ば絶望しかけながら何とかタクシーを捕まえ、1600円jかけて会場入りしました(ちなみに、この日の鑑賞代は600円です)。300人強入る会場の7割は埋まっていたと思います。それは恐らく、上映後のジャ・ジャンクー監督によるティーチインがあったからなのかもしれません。
『世界』は、まずDVで撮られた後、35mmにブローアップされての上映でした。ジャ・ジャンクーらしからぬアニメーションの導入に驚いたり、相変わらず繊細な演出に納得したりするうちに、2時間強の上映時間はやはり瞬く間に過ぎ去っていきました。かなり長いシークエンスショットを特徴とするジャ・ジャンクーですが、今回は比較的ショットを割った印象が。それでも、1つのショットは平均して長かったと思います。生まれ故郷から大都会・北京へとその撮影対象を移したジャ・ジャンクーですが、ある大きな“流れ”に流されながらも生きて行こうとする人物を見つめる視線は変わらなかったと思います。本作において印象的だったのは、“世界”という概念の相対性と言うか、何が“世界”か、という問題の描き方だったのではないかと。「世界公園」という実在する公園には、それこそ世界各地の象徴を目にすることが出来ますが、そこにあるエッフェル塔やピラミッド、ロンドンブリッジなどは飽くまで10分の1の大きさのフェイクでしかありません。それら“世界”と、登場人物が生きる“世界”の残酷なまでの差異。そこには曖昧な男女関係はおろか、職業的な問題から死ぬということまで、我々現代人が生きる上で避けては通れない問題が重ねられていくでしょう。
まぁここであまり書いてしまうと、映画短評のほうで書くことがなくなってしまうので、この辺でやめておきますが、今、ジャ・ジャンクーの新作という名目で『世界』を心待ちにしている人々の期待を、決して裏切ることの無い映画だということは確かかと思います。
というわけで、“充電期間中”のこの時期は、普段よりも映画を観る本数が減るとは思いますが、その分、一本一本のセレクトには力が入ります。すでに日仏での特集上映も、若松特集も見逃している現状で、今は週末に何を観るか、そんなことばかり考えています。こんな状況でも、やっぱり私の中では、映画がかなりの位置を占めているということです。
『エレニの旅』、アンゲロプロスに打ちのめされる快楽
原題:TRILOGIA I: TO LIVADI POU DAKRYZEI
上映時間:170分
監督:テオ・アンゲロプロス
一映画好きとして大変恥ずかしながら、本作がアンゲロプロスの実質上初体験でした。“実質上”としたのは、嘗てヴィデオで『シテール島への船出』を観た際、序盤で挫折した記憶があるからです。
本作はとにかく事前にその完成度の高さを聞かされていたのですが、あの当時よりはかなりの数の映画をこなしてきた私の中で機は熟したなと判断し、再チャレンジと相成りました。
冒頭近く、最初にエレニが住む村を映すカメラの流麗な動き、その村へと続く川を小船が滑走してくるまでのショット。息を飲むショットとはこのようなものだと思いました。今、アンゲロプロス程に大胆不敵なショットを撮る人間がどれほどいるでしょうか。
中盤から物語などどうでもよくなり(これはかなりポジティブに解釈していただきたいのですが)、“境界線”(川であったり線路であったり土手であったり)が頭の中で抽象的な意味を拡散させていく。しかしそれも、あの大木にぶら下がる何頭もの羊の死体とそこから流れ出る血が川を形作る様を観て、吹っ飛んでしましました。
これがアンゲロプロスか……今はそのようにしか言えませんが、今後新作を追い続けていく強い意志が生まれたことだけは確かです。
2005年07月25日
『溶岩の家』、驚きが感動に直結する映画
原題:CASA DE LAVA
上映時間:110分
監督:ペドロ・コスタ
ペドロ・コスタの映画を観て毎度思うのは、彼が創る映画には何故か既視感がないということです。過去の映画を参照させないように意識しているためか、あるいは結果的に何にも似ていないのか、それは定かではないのですが。
『溶岩の家』は、あえて言うなら『骨』に似ていないこともありません。が、やはり、これはこれでどこか違う次元に存在する映画のような気がしてならない。“違う次元”という言葉は、しかし、理解不能であることを意味しません。
では、『溶岩の家』は面白いのか、というすこぶる曖昧にして、ある種根源的とも言える問いを自らに向けてみます。その時、私は映画に対し、これまで常に“面白さ”を求めてきただろうか、いや、今現在も果たしてそうだろうかと自問せずにはいられないのです。ここで確実なのは、少なくとも私は“驚き”を求めて映画を観てきた、あるいは、観ているのだろうということでしょうか。
そして、ペドロ・コスタは、確かに私を驚かせてくれる映画作家です。
『溶岩の家』には、長い長い横移動のシークエンスショットがあります。そこに、何らかの“意味”や“思想”、あるいは“無意識”が込められているかどうかはわかりません。しかし私は、間違いなくそのシーンに“驚いた”のです。
驚きがそのまま感動に直結する映画。それが私にとっての『溶岩の家』です。
2005年07月23日
大和屋竺とジャ・ジャンクー
昨日22日、私は会社を休んでしまいました。ある、重要な映画を観るため、というのが欠勤理由なのですが、世の中には、たかが映画で会社を休むなんて! と息巻く方もいらっしゃるのではないかと思います。恐らく、私の同僚もそのように思っているのではないでしょうか。いや、彼らには映画を観るために休む、とは言っていないので、この文章を読んで初めて知るのかも知れないのですが。
そんな“まともな”社会人らしからぬ私ですが、会社を休んで観るからには、それなりの映画を観なければ割に合いません。ただ“観たいなぁ”と思うような映画では駄目なのです。“観ねばならない”この義務的な心の声が全身を駆け抜けるような映画でなければ、わざわざ会社など休みはしないのです。
会社を休むに足る映画。例えば、『運命じゃない人』を私は今非常に観たいと思っていますが、そのレヴェルではまだまだです。いわんや、『逆境ナイン』程度では、私が仕事をサボタージュする理由にはなりません。『ヴェラ・ドレイク』あたりだとかなり心も動かされますが、それとて予告編の印象に過ぎません。銀座に出向かねばならない本作は、この後も見る機会を逸する可能性も高いのですが。
つまり、生半可な映画では駄目だ、ということです。
さて、そんなとき私がセレクトした映画は2本。
1本は『毛の生えた拳銃』、もう一本は『世界』です。この2本であれば、仕事をぶっちぎれる。そのように判断しました。大和屋竺とジャ・ジャンクー。既にこの世にない伝説的日本人監督と、若くしてその才能を爆発させた中国人監督であるこの二人のためなら、私の一日を費やすに値する、そう思いました。
と、ここまで書きましたが、実は明日朝早くに出かけなければならず、非常に中途半端ではありますが、この続きはまた後日。最後に付け加えると、二本とも素晴らしい映画でした。
『おわらない物語 アビバの場合』、トッド・ソロンズは極めて真摯な作家である
原題:PALINDROMES
上映時間:100分
監督:トッド・ソロンズ
わが国において、トッド・ソロンズはこの先も一部の観客に向けた映画作家なのでしょうか。
この作品を観て、いや、過去の作品を観た上でも、トッド・ソロンズは決して異端的な作家ではなく、ただ、“普通の人間”が見過ごしている、いや、見ようともしていない世界のある局面を、真摯に描こうとしているだけなのではないかと、私はそう信じるに至りました。
作術こそ違えど、『おわらない物語 アビバの場合』は(「回文」
8人のアビバの中で特に良かったのが、40歳を超えているジェニファー・ジェイソン・リーでした。この大胆極まりないキャスティングを含め、本作の出演者は誰もが素晴らしい。
2005年07月22日
『肌の隙間』、ここでは“セックス=死”という公式が成り立つ
原題:肌の隙間
上映時間:77分
監督:瀬々敬久
本作がデビュー作となる新人・小谷健仁扮する秀則が、田んぼで捕まえた魚の頭めがけて石を振り下ろすシーンがあります。4発も5発も殴られていくうち、魚の頭は変形し、血と肉のミンチと化していく。このシーンは、その一連の動作がワンショットで撮られていることと、何ら“劇的”な意味を与えられていないかのごとく、“ただそこにある”動作として放り投げられている気がして、戦慄しました。
魚の使い方はキム・ギドクの『コースト・ガード』に似ているな、とも。弱者としての魚……。
それほど多くのピンク映画を観ているわけでもないので、何の信憑性も無い全く個人的な印象に過ぎないのですが、ピンク映画におけるセックスシーンは、総じて悲しい。間違っても、昂奮とは結びつきません。“性”というよりむしろ“生”を感じるし、だからこそ、そこには“死”の匂いがこびりついているのです。
興味深かったのは、セックスシーンにおける、画面手前の草や木々の存在です。嘗て観たロマンポルノ的な、行為を隠す存在としてのオブジェとは何かが違った印象を持ちましたが、それについては、再見することでもう一度考えてみたいと思います。
2005年07月21日
『リチャード・ニクソン暗殺を企てた男』、ニルス・ミュラーの才能に賭けてみたい
原題:THE ASSASSINATION OF RICHARD NIXON
上映時間:107分
監督:ニルス・ミュラー
もちろん、本作の主演がショーン・ペンであるという事実は、予めある種の先入観を植え付けずには置きません。さらに、悪くなかった『21グラム』でも組んだ、いまや引っ張りだこのナオミ・ワッツが共演とくれば、一定の水準以上の出来だろうと予想するのも当然なのかもしれません。
しかし裏を返せば、この曖昧に設定した水準こそが、“期待”を阻むこともあります。だからこそ、予告編の段階で製作総指揮に名を連ねるアレクサンダー・ペインという名前に反応してしまったのです。
予告編で印象的だった、ショーン・ペンのストップモーション。それは、今まさに飛行機に乗り込もうとしている重要なシーンで、これが本編でも全くそのまま使われていました。しかし、もう見飽きたといったもいいくらい予告編で観ていたシーンにもかかわらず、衝動的に銃を撃っていくショーン・ペンはやはり何かが憑いているかのような迫力がありました。そして、そこからラストまで一気に駆け抜けていく堂々たる演出。
その無駄の無さに、監督の力量を確信した次第です。
今はニルス・ミュラーという名前を確実に記憶し、次の公開作を待つとしましょう。
2005年07月20日
『ダニー・ザ・ドッグ』、このキャストだから成り立つ映画
原題:UNLEASHED/DUNNY THE DOG
上映時間:103分
監督:ルイ・レテリエ
またぞろリュック・ベッソンが若手に作らせたと聞いても、もはや興奮とは程遠いニュースではありますが、ジェット・リーのアクションが観られるのであれば、多少の期待をせざるを得ません。
モーガン・フリーマンはもはや、そこにいるだけである種の避けがたい存在感を画面に定着させてしまうので、その演出については特に言うところもありません。当たり障りのない、と言うことも出来ますが、彼は彼でしかなかったという点は確認出来たので。
ユエン・ウーピンが振付けたアクションは今回、“暴力”という面をことさら際だ立たせていたように思います。ジェット・リーの身振りは、“効率=理性”から遠く離れ、瞬発的な凶暴性を主張していました。それは良いと思うのです。だけれども言うまでも無く、重力を感じさせないワイヤーアクションに“痛み”はなく、そればかりか、ワイヤーとは無関係の、決闘場で最初に戦うシーンですら、『マッハ!!!!!!!!』のほうが数倍上手かったと断言できます。
どうしようもなく図式的なラストの敵に関しては、もう何も言うことはありません。鑑賞後、キャストに救われる映画は、最終的には不幸なのではないか、そんな思いが頭をもたげたのでした。
サヴァリン・ワンダーマン・コレクション ジャン・コクトー展
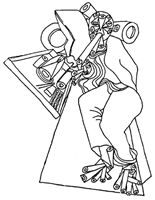 全くノーチェックで、つい先ほど知りましたが、本日より開催される模様です。すでに兵庫や北海道で開催された「サヴァリン・ワンダーマン・コレクション」、東京ではたった12日間だけのようです。
全くノーチェックで、つい先ほど知りましたが、本日より開催される模様です。すでに兵庫や北海道で開催された「サヴァリン・ワンダーマン・コレクション」、東京ではたった12日間だけのようです。
ジャンコクトー展といえば、2001年にbunkamuraで開催された「ジャン・コクトー展 【美しい男たち】」以来でしょうか。いや、もしかすると私が見逃していただけなのかもしれませんが、bunkamuraのそれには駆けつけた記憶があります。確かポストカードを5枚ほど購入しました。
私にとって最初のコクトー体験は、18歳だったような。もちろんそれ以前に多少の知識はありましたが、大学の生協で購入した『阿片 或る解毒治療の日記』(堀口 大学 訳)が最初でした。いや、もしかすると映画『オルフェ』のほうが先だったかもしれません。何しろ10数年前の記憶などかなり曖昧になっておりますので…
『阿片 或る解毒治療の日記』において最も衝撃的だったのは、その内容よりも挿絵として描かれた数十点のデッサンです。ほとんど分裂症的ともいえるそのデッサンの異様な力にノックアウトされ、以来、私にとってのコクトーは何より“デッサンの人”として記憶されました。
もちろん、映画における彼の想像力も見落としてはならないでしょう。トリュフォーやゴダールとのかかわりから生まれおちた画面を思い出すこともまた有意義な行為だと思います。
今回の展覧会は、どうやら私が嘗て観たことの作品も含まれているようです。時間の都合がつけば何とか足を運びたいと思います。まだ未見のかたは、是非とも。
サヴァリン・ワンダーマン・コレクション ジャン・コクトー展
7月20日(水)〜31日(日)
日本橋三越本店新館7階ギャラリー
AM10:00〜PM7:30※開催期間中無休
(最終日はPM6:00閉場、入場は閉場30分前まで)
(出品作品リストは北海道立近代美術館のHPにて確認できます)
2005年07月19日
『ジェリー』を爆音で観るという体験は感動的である
原題:GERRY
上映時間:103分
監督:ガス・ヴァン・サント
まず「爆音」について。
「爆音」とは、爆発する大音量であるが、音と言えど、「爆音」は“耳で聞く”というレベルをはるかに超えています。認識を超え、感覚的に“体験する”ものなのです。文字通り、全身で感じるという体験、それが「爆音」です。
このような実も蓋もないことは書きたくないのですが、今回はあえて断言したいと思います。
『ジェリー』を「爆音」で、しかもフィルムで観られるという体験がどれ程貴重かは、観た者でないと絶対に分からないでしょう。よってここでは「爆音」体験自体に対する言及はせず、映画作品としての『ジェリー』にのみ、先に書いたレビューの追記という形で触れたいと思います。
『ジェリー』は、その表現の純粋形態に秘められた途方も無い可能性を感じさせます。いや、“表現”は極限までそぎ落とされ、“表面”しかないのですが、だからこそ“見えてしまう”ことがあるのだと思いました。
重力、速度、風、音、無気力、そして絶望……それら見えるはずの無いものたちが、一斉に表面に立ち上がってくる。つまり、見える。それは例えば、タル・ベーラの『ヴェルクマイスター・ハーモニー』やモンテ・ヘルマンの『断絶』とどこかで通じ合っている気がしないでもない感覚です。
今画面上にある以外のことについて、観客は一切を知らされません。目にしている事物に纏わりつく“理由”や“経緯”なども、我々にはわからないのです。そしてそれは多分、そのような奥行き(外部)など予め無いのだ、と宣言する『ジェリー』においては、極当たり前の感想だと思います。それを退屈だと感じ、つまらないと断じる自由もあるでしょう。そして、この超禁欲的な作品において私が最も反応したのは、他ならぬ二人の俳優の、カメラの、自然の、“自由な動きと音”だということも書いておきたいと思います。
今はその体験を、一先ず“感動”という言葉に置き換えることで、何とかこの思いが伝わればと思います。
“青”により精神と肉体を弛緩させた週末
 気が付けは約一週間ぶりの更新になってしまいました。関東でも梅雨が明けましたが、皆様、サマーライフを満喫していますでしょうか。
気が付けは約一週間ぶりの更新になってしまいました。関東でも梅雨が明けましたが、皆様、サマーライフを満喫していますでしょうか。
映画に関してはこの連休中、珍しく新作の鑑賞を見合わせ、旧作を3本ほどdvdで鑑賞するに留まりました。本来なら昨日は、ジャ・ジャンクーの新作『世界』を鑑賞する予定でしたが、自らの怠惰により断念。それでもやはり何とか観たい気持ちはあるので、今週金曜日に仕事を休んで観にいこうかと画策しています。
このように連休中の予定が狂いに狂ってしまったのも、ひとえに、16日の土曜日にいち早く夏の“青さ”を体験してしまったからで、以降、心地よい(?)肌の痛みと熱さが、映画のように“文化的行動”へと傾く私の精神を、ひたすら太陽の下での“野生的行動”へと駆り立てずには置かなかったと、抽象的に言えばまぁそういうことです。
土曜日の早朝、未だ正式に梅雨明けもしておらず、東京はまだ曇り空でしたが、一か八かという賭けに出て江ノ島へと飛び出した結果、到着した頃には快晴。ビーチはもう結構な人で賑わっていてこちらのテンションも急上昇し、それと同時に私の体も徐々にその色を変化させ、午後4時を回るころにはほとんど痛々しいくらい赤黒く染まっていました。海に行った時の楽しみとして、もちろん、太陽の下で飲むビールやらワインやらもあるのですが、程よく火照った体を冷たいシャワーでクールダウンした後、クーラーの効いた部屋(店)で飲む酒が一際“癒し”の効力を発揮するもので、海を後にした私以下友人2名は、地元で獲れた上手い魚を食わせそうな居酒屋を見つけ、駄目押しのようにビールを流し込むことに。結局朝10時過ぎから夕方の6時ごろまで飲みっぱなし、解散後も私は別の約束があったので、夜11時まで三宿のビストロでワイン三昧という、これぞ“夏!”かどうかわかりませんが、個人的にこれ以上の満足もそうはあるまいと思われた、そんな一日でした。
明けた日曜日も観るべき映画があるにはあったのですが、どうにも体が映画モードになりきれず、個人的にはこの夏どうしても手に入れておきたいネックレスを探しに代官山〜恵比寿を徘徊。しかしあまりの暑さに一歩歩くごとに体力を消耗し、結局目当てのものも見つからなかったので途中で断念。こんな時こそ自宅でdvd三昧だ!とばかりにTSUTAYAでdvdを借り、久々に料理にもちょっと力を入れて、誕生日プレゼントとしていただいたトスカーナワインとともに堪能。そんな日に観るべきdvdは前から決めていて、それは今年観た中でも出色の傑作だった『サイドウェイ』に他ならず、もうかれこれ3度目になりますが、もう素晴らしいの一言。現在書いている『アバウト・シュミット』評の参考になればという気持ちが無かったわけでもないのですが、結局そんなことは微塵も考えず、ただただ画面にクギ付けになってしまいました。
昨日は昨日で、朝からジム、そして、再度ネックレスを求めて渋谷のめぼしい店を回るも、店が無くなっていたりいい商品に出会わなかったりで、15時過ぎには逃げるように自宅に戻り、モンテ・ヘルマンの、ある意味不条理極まりない60年代西部劇『旋風の中に馬を進めろ』と『銃撃』を2本続けて鑑賞、そのあまりの弛緩した凄みにほとんど呆気にとられてしまい、その双方に出演し共同プロデュースもしたジャック・ニコルソンの嗅覚に、ひいては、ヘルマンとニコルソンの師であり、この2本の製作総指揮であるロジャー・コーマンの“力技”に感動。新作を観られなかった週末ではありますが、この2本を観られたのなら、もう何も言うことはありません。西部劇に多少なりとも興味があり、かつまだ未見の方は是非。余談ですが、私はこの2本を通して、ヴィム・ヴェンダース『さすらい』をゆくりなく思い出したと最後に付け加えておきます。
さて、今週も週末は海三昧になろうかと。
金曜日は何とか休みをとって川口まで行ってくるつもりです。あ、あと下北で開催中の大和屋竺特集上映も1本くらいは観ておきたいです。
2005年07月15日
『オープン・ウォーター』、サメ映画更新さる
原題:OPEN WATER
上映時間:79分
監督:クリス・ケンティス
本作は、簡潔極まりない。そして、作品の出来は別にしても、それは一つの美点足りえると思います。
映画制作において、低予算は時に新たな表現を生み出してきました。
本作における新しさは、この手のパニック映画において、敵(=鮫)が主人公を襲うシーンを一切見せなかったことです。『ジョーズ』にも『ディープブルー』にも描かれていた、鮫が人間を食らうシーン。それを本作では、“直接的には”見せません。
スリルを誘うBGMは存在しています。いっそそれすら無かったらとも思わないでもありませんが、それでもかなり控え目ではありました。
つまり、“サメ映画”というジャンルを“地味に”更新したということです。それが怖かったかどうかは別として、これは評価出来るのではないでしょうか。
ただし、スタッフロールにおけるドキュメンタリー然とした場面は、端的に言って蛇足だったと思います。
2005年07月13日
出会いはスローモーション
先週は足の怪我もあり、あまり歩き回るのもいやだったのですが、『ライフ・アクアティック』が15日で終了してしまうと知り、痛みを押して自転車で恵比寿まで行ってきました。随分早く着いてしまい、ビアホールでビールをガブガブ、ソーセージやらザワークラウトやらフィッシュ&チップスやらをバクバク、あー眠くなってきたな、と思い、ガーデンプレイスのベンチで残りの時間を睡眠に当てようとしましたが、あの炎天下の中、それはあまりに馬鹿げていると思い直し、今度はカフェで甘いパンをバクバク…
何という自堕落さ! とほとほと呆れ帰り、運動できないストレスを食事で解消しようとしていた自分に嫌気がさし、映画が始まる前にテンションがローダウンしましたが、何とか時間を潰して観た『ライフ・アクアティック』は二回目とはいえ冒頭から乗せてくれるので嬉しくなり、最終的にはあっという間の118分、自己嫌悪もすっかり忘れてしまいました。やっぱり最高でした、この映画は。
そんなこんなで怪我から丸一週間たった今、痛み止めのクスリも飲み干してしまい、後は自然治癒に期待したいところですが、現在はまだ若干足を引きずっています。にもかかわらず、回復を待ちきれずに月曜からジムに行き、先週分を取り戻そうと躍起になっているのですが。それもひとえに、もうすぐそこまで迫ってきている夏のせいです。
ところで、本日7/13は特に記念することもない私の誕生日に当たり、自分へのプレゼントという都合のいい口実に従って何を買おうかとしばし考えたものの、実は誕生日を待つまでも無く、ここ2週間くらい洋服やバッグを買いまくっていて、いったい何がプレゼントに当たるのかもわからなくなるほど。そろそろ欲しいものも無くなってきたかなと思っていた矢先の誕生日です。よって本日は、モンテ・ヘルマンかアレクサンダー・ペインあたりのdvdを購入しようか、などと考えたり。無理に買うことも無いのですが。
そんな買い物週間で入手した夏用のスリッポンがあるのですが、オークションで購入したそれは思っていた色味とは若干異なり、まぁそんなことはよくあることなので、ここは一つカスタマイズだ! とばかりに昨日は東急ハンズに行き、革用の染料を購入。約2時間かけて真っ赤に染め直しました。今朝起きて出来上がりを確認すると、ほとんどパーフェクトな仕上がりで大満足。この夏はヘビーローテーションすることでしょう。
さて、別に誕生日だからということもないわけですが、今朝はちょっと感動的な出来事に遭遇いたしましたので、後になって忘れないよう最後に記しておきます。
いつものようにジムを終えて会社の最寄り駅に到着したのですが、地下鉄から地上に出る階段に挿しかかろうとした瞬間、その階段の中間地点から、20代後半と思しき女性が回転しながら私の足元目掛けて落ちて来たのです。あまりに突然の出来事な上に、その女性の回転ぶりがこれまでに遭遇したことの無いほど激しく、私にはその特異な光景がほとんどスローモーションのように感じられ、女性が足を踏み外した瞬間の表情、回転するごとにバッグから書類やらパソコンやらが飛び出していく様、強いて言えば“階段を転げ落ちる音”としか形容しようのない痛々しい音などがほんの1秒半くらいの瞬間にもかかわらず一気に目と耳に飛び込んできて、あまりに不謹慎な言い方かも知れないのですが、それは全くもって感動的と言うほか無く、誤解を恐れずに言えば、それは紛れも無くサム・ペキンパー的スローモーションであり、私としては、一生のうち後何度観られるかわからないような感動的なアクションを目の前で身をもって演じてくれたその女性に対する感謝が瞬時に行動として表れ、間違っても“大丈夫”とは思えない、恐らくショックと痛みで茫然自失となったその女性に対し、「大丈夫ですか!?」と場違いな声を掛けながら散らばった荷物を拾っていると、ただ単に親切心からか、あるいは私と同じ様にその光景に心を奪われた“サム・ペキンパー党”なのかは知りませんが、見知らぬ男性が一人、また一人と近寄ってきて、「立てますか?」などと言いながらやはり同じように荷物を拾ってあげていました。彼女は、膝からぺたっと地面に座りこんでしまっていましたが、恐る恐る立ち上がり体の状態を確認すると「大丈夫みたいです!」と満面の照れ笑いを浮かべ、足早にその場を去って行ってしまいました。これが通俗的なテレヴィドラマであれば、そのシーンは“出会い”のシーンとして、バックに意味ありげなBGMなどが流れるんだろうなぁなどとも思いましたが、やはり、そんな通俗的なドラマよりもさらにドラマティックなのが現実というものなのでしょう。あの女性の軽やかな足取りがたとえやせ我慢であったとしても、始まりから終わりまで1分あるか無いかの中で、ある一人の、加えて今日が誕生日の男を確かに感動させたという事実は記憶しておくべきだと、そんなことを思ったのでした。
私もつい一週間前に、同じように豪快極まりない転び方をして怪我をしたクチですから、彼女の気持ちが痛いほどよくわかります。彼女に怪我などが無いことを祈ります…(-人-)
2005年07月12日
『おちょんちゃんの愛と冒険と革命』に“反応”出来る貴重な体験
原題:OCHON-CHAN:PUSSY'S ADVENTURES IN LOVE AND REVOLUTION
上映時間:68分
監督:西尾孔志
西尾監督の“世界”は、いったいどこまで拡がっていくのだろうか、と思わずにはいられないような映画。
確かにその片鱗はすでに『ナショナルアンセム』にも見られました。
まず、ある“出来事”があり、どこかでまた別の“出来事”がある。その一つ一つの過去や存在理由は、問題ではありません。そして私は、ただ翻弄されるばかりなのです。
映画における種々の“コード”の隙間を縫うような、別次元の“コード”がそこにはあります。そのテクストを読み解くことは並大抵ではありませんが、その挑戦に受けて立つ覚悟がある人間にとって、それは幸福な体験です。
例えば、これは恋愛映画でしょうか? SFでしょうか? スリラーでしょうか?
「わからない」と、私なら答えます。いや、「知るか!」と暴力的に言い放つかもしれません。それもまた、問題ではないのです。こんな部分もきっと『ナショナルアンセム』から変わっていません。
もはや、映画にジャンルなど必要とされていないのだろうか、本作はそんな不安をも強いるかもしれない。それよりも根源的な“女と男と暴力”さえあれば映画は成り立つのか?とも。
「うるさい!」と彼は言うでしょう。そう、映画は最終的には、観客の反応に委ねられています。何かが反応する、それが全てです。
一先ず結論します。
『おちょんちゃんの愛と冒険と革命』は、“面白い”と“面白くない”の垣根を根絶やしにしようとする凄い映画である、と。そして私は、ベッドに女性二人が横たわる俯瞰の視線、ベランダから階下にある川沿いの道路へと移動する視線、画面奥にある玄関の薄明かりを背景に着替える女性のシルエットとその部屋の闇、この世ならざる世界へと続いて行きそうな歩道橋、間を心得たアラームの音、飛行機の轟音と爆破、そして、太ももから流れ落ちる鮮血に、確かに“反応”しました。
やはり、それが全てなのです。
2005年07月08日
必見備忘録 7月編
今月でまた一つ年を重ねてしまいます。
よって下記は、来るべき未来を見据えたセレクトになるでしょう。
まぁ冗談はさておき、今月は我が誕生月にふさわしく、大変なことになっています。必見に次ぐ必見で、時間がいくらあっても足りません。この中で何を観、何を落とすか。これには熟考せねばなりません。
■『ライフ・アクアティック』[上映中]
(恵比寿ガーデンシネマ 11:15/13:50/16:25/19:00〜21:15)
■『埋もれ木』[上映中]
(シネマライズ 10:45/12:50/14:55/17:00/19:05〜20:55)
■『樹の海』[上映中]
(シネ・アミューズ イースト/ウエスト 10:40/13:20/16:00/19:00〜21:00)
■『逆境ナイン』[上映中]
(アミューズCQN 11:00/13:35/16:10/18:45/21:15〜23:20)
■『運命じゃない人』[7/16〜]
(ユーロスペース 12:15/14:25/16:35/18:45〜20:40)
【若松孝二 レトロスペクティブ 2005】
■『赤い犯行』[7/19]
(ポレポレ東中野 20:10)
■『血は太陽よりも赤い』[7/20]
(ポレポレ東中野 20:10)
【国際Dシネマ映画祭2005】
■『世界』[7/22]
(SKIPシティ 18:00)
【映画におけるカップルたち〜『描くべきか愛を交わすべき』をめぐって〜】
■『アタランタ号』[7/10]
(東京日仏学院 14:30)
■『サンライズ』[7/10]
(東京日仏学院 15:30)
■『ピクニック』[7/16・17]
(東京日仏学院 14:30)
■『ママと娼婦』[7/17・23]
(東京日仏学院 17:30)
■『テオレマ』[7/23]
(東京日仏学院 14:30)
■『ゲアトルーズ』[7/29]
(東京日仏学院 19:00)
■『カップルの解剖学』[7/30]
(東京日仏学院 14:30)
まずもって早急に再見しなければならないのが『ライフ・アクアティック』になります。簡単に言えば、細部を大分忘れてしまったので文章を書けないということ。もちろん、もう一度観たいと言う気持ちもあるので。
『埋もれ木』は予告編を観て、ただ何となく。本当に何となく、です。
『樹の海』は予告編すら見ておりませんが、同様に何となく、です。
『逆境ナイン』もまた何となく、ですが、ギャグにどれほど笑えるのかと確かめてみたい気も。
『運命じゃない人』は、積極的に観たい作品。キャストとノリに惹かれました。
今月は特集上映や特別上映が多く、よって、渋谷以外での鑑賞が多くなりそうです。
「若松孝二 レトロスペクティブ 2005」は、観たい作品のほとんどが平日昼間の上映に当たってしまい、残念至極。dvd等で観られない上記2作品は、平日でも最終回なので、何とかして観なければと思っています。『女学生ゲリラ 』も『毛の生えた拳銃』も観られないなんて……
「国際Dシネマ映画祭2005」は、デジタルシネマをテーマとしたコンペティションです。目的は唯一つ、ジャ・ジャンクーの『世界』です。今後、いつ上映されるかもわからないため。
東京日仏学院では「映画におけるカップルたち〜『描くべきか愛を交わすべき』をめぐって〜」という特集上映が開催されています。全て旧作になりますが、新作を差し置いても「観たい!」と思う作品のみ。場所が場所ですので、どれだけ観られるのかは、全く持って不明です。
2005年07月06日
ヘア解禁無修正版な朝
 出来れば昨日のうちに「映画短評<2005.6>」を書き上げてしまいたかったのですが、何とも情けない事情により、それが果たせませんでした。これから書く文章は、久々に映画とは全く関係の無いものです。しかし、それでも無理やり映画を引き合いに出してみるなら、今現在、私は『ジェリー』終盤におけるケイシー・アフレックのような速度でしか、歩くことが出来ません。肩を落として一歩一歩、生命を振り絞るように歩くケイシー・アフレックの後姿と、一体どれくらい歩いたのか、いや、ほとんど進んでいないのではなかろうかと思わせる程のろい速度は、ほとんど感動的というべきものでした。そして、それと全く同じような状態になってしまった私。以下に、昨晩から今朝にかけて起きた悲喜劇を書き記します。
出来れば昨日のうちに「映画短評<2005.6>」を書き上げてしまいたかったのですが、何とも情けない事情により、それが果たせませんでした。これから書く文章は、久々に映画とは全く関係の無いものです。しかし、それでも無理やり映画を引き合いに出してみるなら、今現在、私は『ジェリー』終盤におけるケイシー・アフレックのような速度でしか、歩くことが出来ません。肩を落として一歩一歩、生命を振り絞るように歩くケイシー・アフレックの後姿と、一体どれくらい歩いたのか、いや、ほとんど進んでいないのではなかろうかと思わせる程のろい速度は、ほとんど感動的というべきものでした。そして、それと全く同じような状態になってしまった私。以下に、昨晩から今朝にかけて起きた悲喜劇を書き記します。
2005年7月5日深夜。
目黒区内の歩道で自転車に乗っていた私の目の前に、突如地面が迫ってきました。次の瞬間、激しい衝撃が全身を襲い、数秒間、雨に撃たれたまま地面にベッタリと顔をつけていました。無意識に顔をかばったからか、右腕全体を満遍なくすりむき、そして何故か、右足が痛くて動きません。とりあえず人に見られなかったことに安堵し自転車を起こすも、ブレーキが車輪に食い込み前に押すこともままなりません。腕からは血が流れ、右足に激痛が走り、自転車は動かない……何故このような酷い仕打ちを受けねばならないのか。その時の私は、沸々とわいてくる怒りというよりも、もはや年に一度は確実にわが身を襲う“不幸”に対する恐怖を感じていました。
確かに、アルコールが全く入っていなかったわけではありません。しかしそれは、“飲んではいたが酔ってはいなかった”という程度のもの。飲んでいなかったとしても、まだ購入したばかりの自転車は、雨に濡れた黄色い点字ブロックにその前輪を取られていたでしょう。
さて、それでもどうにかして自宅にたどり着いた私、大体こういうときにまずチェックするのは、怪我の具合よりも、指輪とブレスレッドをちゃんと身に着けているか、ということです。まったく、現金な男ですが、長年愛用しているもので、しかも、指輪にいたっては、嘗て一度(酔って)紛失し同様のものを再度購入したと言う前歴があるので、なおさらなのです。
果たして、指輪はありました。ここで一息。しかし、ブレスレッドがありません。ここで軽い絶望。いてもたってもいられず、“現場”に戻ってみました。犯人が必ず戻ってくるという“現場”に。すると、ブレスレッドは朽ち果てたような状態で、確かに“そこ”に存在していました。が、留め具が見事に粉砕され、およそブレスレッドとは言いがたい、ただの鎖としてですが。
普通ならこの時点で叫びだすところです。嘗ての吉田栄作氏よろしく、「ウォーーーー」と。でも私にはもう、そんな気力すら残っておらず、とぼとぼと家路につくほかありませんでした。
明けて今朝、起きてみるとシーツには血痕が。加えて、足の激痛は増しています。ほとんど歩くのもまま成らない状態です。先述したように、全く『ジェリー』そのままなのです。いくら「日本ジェリー党」に属しているとはいえ、ちょっとやりすぎ感が強いなと反省。
そこで、出社前に行きつけの整形外科に行くことにしました。
その整形外科は、オリンピック選手やらプロスポーツ選手やら、体育会系の学生などが掛かるような、なかなか有名な整形外科なのです。確かに、私もこれまで何度と無く治療してもらってきましたし、そこのセンセイは非常に信頼に足る名医だと言えるでしょう。しかしながら、すでに高齢のそのセンセイは、診察時、とにかく容赦なく患部を弄り回すという特殊な手法をとられているのです。よって、初診時の待合室で私は、いつも不安と恐怖に駆られることになります。そして今朝もまったく多分に漏れず、いや、これまでの中で最高の痛みを与えてくれました。思わず、「ウgyィェーーーー」とか「イyーーーーッツッツッツ」などという声にならないうめき声を上げ、いい年してかなりの羞恥を感じざるをえませんでした。しかも、羞恥プレイはそれだけじゃなかったのです。
私の患部は右足の股関節近くだったのですが、25〜27歳と思しきナースが注目する目の前で、センセイはあろうことか、私のアンダーウェアを予告無しに(!)むんずと引き下げ、患者である以上それを阻止することも出来なかった私は、ナースにアンダーヘアを晒すほかなく、[M]と名乗ってはいますがどちらかというと“S”であるところの私にとって、それ以上の屈辱もまたなく、朝から、痛いわ恥ずかしいわ凹むわで、もうこんな文章を書いている場合じゃないのですが、まぁ、センセイは「骨は大丈夫みたいね」などと涼しい顔で言ってくれたし、痛み止めもくれたので、後2〜3日は“ジェリー歩き”から逃れられないでしょうが、この夏の空や海の青さをまるまる棒に振るような事態はなんとか避けられそうですので、全て水に流して忘れてしまうことにしようと思います。
皆様、雨に濡れた点字ブロックにはくれぐれもご注意を。
2005年07月04日
『宇宙戦争』、『おちょんちゃん〜』、林由美香、『バス174』
先週は珍しく、平日にもかかわらず無理やり2本の映画を観ました。無理やりというからにはしかるべき理由がありまして、一つは『宇宙戦争』の初日だったから、もう一つは、友人の映画監督が撮った作品が限定で公開されたから、というものです。いずれも私のような人間にしてみれば、仕事を放り出してでも駆けつけるに十分な理由なのです。
すでに読んだかたもいるかもしれませんが、溜まっているレビューが10数本あるにもかかわらず、それらを置いて先に『宇宙戦争』に関する文章を書き上げたのは、ひとえに、鑑賞後に酒を飲みながら相棒・ng氏と交わした会話に強く思うところがあったからであり、トム・クルーズという人間に関する考察を中心に据えた議論、というか“熱い”雑談がことのほか興味深く、こういう生産的な雑談が出来るのであれば、普段は一人きりで観るようにしている私でも、誰かと映画を観る楽しみを実感できるという、まぁそんな感じです。よって、今回の文章は、いつもの捏造会話に比べるとより事実に基づいています。もちろん、基本的にはフィクションですけど。
一先ずng氏に感謝。
で木曜日はというと、有楽町にあるニッポン放送内にあるファンタスティックシアターという場所で開催された「大阪インディーズムービー☆最前線!」という特集上映に。そのイベントは昨日が最終日で、その時上映されたのが先に記した通り、友人の西尾孔志監督の最新作『おちょんちゃんの愛と冒険と革命』だったというわけです。
ネット上では何度もやりとりしている西尾監督ですが、実際に対面するのは今回が始めて。上映開始の30分くらい前に会場に滑り込み、タバコを吸いながら時間を潰していたら、監督と思しき男性が会場に姿を現したのですが、彼は私の顔も本名も知らないのです。すぐそばにいるのに、彼は私を認識できない。ネットを介して知り合うということの、なんとも不思議な感覚を改めて実感しました。まぁ私が立ち上がって「どうも、[M]です」などと挨拶すれば、そのような状態も解消できたのでしょうが、恐らく古くからの友人であろう人たちとの話に割ってはいく程無粋なことをしたくは無かったので、結局、上映後の中原昌也氏とのトークショーも含め、私と監督の間には一方通行の視線、すなわち、私から監督への視線のみが存在し、その逆は無かったということです。まぁ、このような出来事は、『おちょんちゃんの愛と冒険と革命』の驚くべき出来に比べれば何とも取るに足らない事だと言えます。私には、『ナショナルアンセム』とは明らかに違う点が“わかりやすさ”であるとは間違っても言えず、だけれどもそこに存在するある決定的な“何か”を感じることは出来たわけで、それだけであの日の収穫はあったと言えるのだと思います。それについては、中原氏とのトークを再度思い出してみなければなりませんが、やはり実際に聞いてみたい気がするので、仮に次の機会が存在するなら、恥も外聞も捨てて、監督にアタックしてみようか、などと考えております。
さて、いきなり話は変わりますが、奥崎謙三の不幸に続き、林由美香さんが急死しました。まだ35歳だったんですね。ピンク映画女優として現役で活躍されていた彼女ですが、私にとっての林由美香とは、AV女優としての印象がことのほか強く、それは、高校時代に彼女の作品にかなりの衝撃を受けたからです。それは言い換えれば、V&R PLANNINGの衝撃に他なりませんが、とりわけ、安達かおる監督による『ジーザス栗と栗鼠』シリーズの残酷さは、それまで観ていたAVとは全く異なる次元へと私を導き、林由美香は、そのシリーズにおける私が観た最初の女優として強烈なインパクトを残したのです。彼女は、私の中の“サド性”を初めて意識させたという意味で、特権的なAV女優だったと言っても決して大袈裟ではありません。
『由美香』や『たまもの』では、一般映画ファンにも広くその名を知らしめた彼女ですが、彼女の死をきっかけとして、今後もより多くの人がスクリーンやテレヴィの中の林由美香を発見していくことでしょう。私は一先ず『たまもの』をいち早く鑑賞しなければならないと決意しました。
最後に昨日観た『バス174』に関して。一言で言えば、雑誌「PEN」のブラジル特集の対極にある映画だ、と。サッカーやらデザインやらカーニバルやら、我々が普通に認識しているブラジルという国ですが、ある意味フィクションである『シティ・オブ・ゴット』とは別種の“救いがたさ”を痛感し、重い気分のまま家路につきました。
最後に、少なくとも「PEN」を読んだ方は必見だと付け加えておきます。
2005年07月01日
ある日の会話〜『宇宙戦争』を観て
:::caution:::結末に触れていますので、未見の方は読まないで下さい:::caution:::
 スピルバーグ監督でトム・クルーズが主演と聞けば、どうしても初日に駆けつけるという選択肢以外思い浮かばないね。今回は世界同時公開だけど、日本ではレディース・デイでもあるから、劇場には女性客が溢れていたなぁ・・・なんだか普通の映画よりも、途中で席を立つ人数が多かったように思うんだけど、率直にいうとお前はどうだった?
スピルバーグ監督でトム・クルーズが主演と聞けば、どうしても初日に駆けつけるという選択肢以外思い浮かばないね。今回は世界同時公開だけど、日本ではレディース・デイでもあるから、劇場には女性客が溢れていたなぁ・・・なんだか普通の映画よりも、途中で席を立つ人数が多かったように思うんだけど、率直にいうとお前はどうだった?
---まぁ俺は結構楽しめたけどね。良くも悪くもやっぱりトム・クルーズだよ、うん。それに尽きるって言うと実も蓋もないけど。少なくとも3箇所で大爆笑しそうになったなぁ。あのダコタ・ファニングに歌を唄ってやるシーン見たでしょ?
ああ、あれは凄かった。高音過ぎて全然歌えてないだけじゃなく、その歌のセレクトに意表を衝かれたのは確かだけどさ。この映画はさ、仮にトム・クルーズじゃなかったとしたら、相当悲惨なことになっていたようにも思うんだけど、どうかね?
---それは間違いないね。だってこれはトム・クルーズのために作った映画でしょう。最近はあまり聞かないけど、この映画のタイトルは『トムクルーズの宇宙戦争』にすべきだったね。俺はとにかく彼が出ていたから楽しめたって言ってもいいんだから。だけどさ、どうみてもこれは「宇宙戦争」じゃないよね。
うん、宇宙なんて一つも出てこないし、今回の敵というかエイリアンは確かに空から降ってくるんだけど、何百年も前から地中に潜んでいたっていう設定でしょ? 原題は「WAR OF THE WORLDS」で“WORLD”が複数系だから“宇宙”っていう意味にもなるけど、この映画がどこに視点を定めていたかっていうと、それは人間なんだよね。あくまで地球上に住む人間たちの目線で描かれていたし。
---例えばこれまでの侵略モノで言えばさ、何となく鳥瞰的視線を意識させることが多かったような気がするんだけど、『宇宙戦争』は全編が仰角の視線を中心に構成されていると思う。空を見上げるシーンがとにかく多かったし、カメラの動きも人間の目線を意識していたんじゃないかな。ついでに言えば、屋内から窓を通じて屋外を見るという行動も多かったね。内と外の世界が窓(壁・ドア)一枚隔てて全く異なっている感覚。
そうだね。『宇宙戦争』でスピルバーグは、戦争そのものというより、やっぱり家族(人間)を描きたかったと思うんだよ。でも、あのラストシーンは予定調和とかハリウッド的ご都合主義というのとは違う、ただただ欠乏感だけが残ったなぁ。息子とのキャッチボールとか、娘に歌を歌ってやるだとか、とにかく駄目な父親が何とかして失われた家族をとりもどそうとしているのはわかるんだけど、その帰結がただ抱き合って終わりっていうのがどうにも残念でならない。せめて最後に息子を一発殴って欲しかったよ。それくらいの“熱さ”が欲しかったように思う。
---う〜ん、重要な意味を持つと思われる描写がほとんど生かされていなかった感じはするね。どのシーンも唐突な印象を拭えない。あの息子と離れ離れになるシーンの、唐突な戦闘の展開っていったら…それぞれの演出は決して悪くないのに、シーンの有機的なつながりを感じられなかった。
冒頭、トム・クルーズはコンテナを積み上げるクレーンを巧みに操るような、特殊な技術を持った労働者として描かれる。普通、その技術は後にどこかで活かされるって思うけど、そんなシーンは一つも無い。じゃぁあのシーンは一体なんだったんだと。あるいは、怖がるダコタ・ファニングを兄がなだめるシーンで、両手を組ませて自分の領域を確保させることで安心させるっていう印象的なシーンがあったよね。トム・クルーズが兄に習って再度同じことをダコタ・ファニングにやってみせた時、その“間違い”を指摘させてまでいる。つまり、その身振りは親子のコミュニケーションにおいて重要な意味を持つんだと思うのが普通なのに、そんなシーンは後半には一切でてこない。じゃあ何故あんな意味深な撮り方をしたんだって思うでしょ。じゃあそれらは“マクガフィン”なのかっていうと、多分違うよね。やっぱりどこか意味を持たせたかったはずなのに、結果的に描ききれなかっただけなんじゃないかと。つまり、失敗しているんだと思う。
ところで失敗と言えば、今回のキャスティングはどうよ? ダコタ・ファニングもティム・ロビンスも、彼らである必然性が無かったと思わない?
今回、とりわけダコタ・ファニングには観るべき部分が無かったと思う。ただ、これまでとは違う“普通の子供”を演じたと言うのであれば、それは概ね成功してるとは思うけど。怖いから叫んだり泣いたりっていうのは極当たり前の演出で、面白みには欠けたな。ティム・ロビンスについては、確かに「?」なキャスティングだよね。途中から段々と偏執狂的になっていくけど、意外にあっさりと姿を消すし。
---たださ、ティム・ロビンスが絡むシークエンスは、全体からみると妙に異質じゃなかった? 彼は一体何の象徴だったんだろう……でも、ティム・ロビンスがトム・クルーズとダコタ・ファニングをかくまう家にエイリアンが忍び込んでくるシーン、あそこは流石スピルバーグっていう感じがした。『ジュラシック・パーク』で、二人の子どもがヴェロキラプトルから逃げ回るシーンをそっくり再現したかのようでさ。緊張と弛緩、そしてまた緊張。ああいうシーンはきっちりと楽しませるよね。
思うんだけど、『宇宙戦争』ではほとんど血が流れないよね。バイオレンスを意図的に回避しているんじゃないかって。いや、確かに間接的なバイオレンスは描かれるんだけど、生々しい鮮血は無かった。銃で人間を撃つシーンも、エイリアンが人間の生血を吸うシーンも、直接は見せない。トム・クルーズがティム・ロビンスを殺すシーンに至っては、音だけなんだよ。エイリアンが人間をレーザーめいたものでどんどん殺していくけど、人間は一瞬の内に灰になってしまうから、“死”というよりも“消滅”という言葉のほうがしっくりくる。これは何故なのかって考えると、やっぱりこの映画は“家族”に向けられているんだと思ったんだよね。だから残酷な描写を避けたんじゃないかって。家族にむけた家族の映画、それは結果的にあまり描ききれていないようにおもうんだけど、『宇宙戦争』はそういう映画なんだと思う。スピルバーグはSFという衣を纏った、家族のドラマを作りたかったというのが俺の結論で、それはこれまで幾度か見られた通り、この映画でも母より父の存在が重視されていることが証明しているんじゃないかと思う。だからあのラストシーンが物足りなかったんだけど。
---でも最終的にやっぱり楽しんだっていうのは変わらないんだよね。だって、この映画はどう考えても全部“現実の”トム・クルーズのための映画なんだもん。トム・クルーズはいつだって真剣で熱い男だったけど、今回も全くそのままだったでしょ。俺は、これほど大きなテーマを描いた映画においても、トム・クルーズが主演すれば、やっぱり俺たちが知っている、現実のトム・クルーズが主演している映画にしかならないっていうことに単純に驚くね。いくつかの欠点も、最後には許せちゃうっていうかさ。あんなに強烈なキャラクター、っていうか、もはやキャラクターですらなく、ほとんど生き様と言ってもいいけど、そんな俳優っていないんじゃない? ダコタ・ファニングに2回も「子守唄知ってる?」て聞かれながら、情けない表情で「知らない」「ごめん、知らないんだ」なんて言うことが出来る俳優は思いつかないよ。あれこそがトム・クルーズでしょう。もうそれで満足だよ、俺は。
なんか『宇宙戦争』の本筋とは随分離れた結論だなぁ。ただ、それには同意かな。何だかんだいっても、2時間以上を普通にもたせてしまったんだからね。
しかし、もっと別のトム・クルーズを観てみたい気がするなぁ。アメリカの監督じゃ難しいだろうけど。その意味で、いち早くトム・クルーズの新たな側面を引き出したキューブリックは偉大だったね。ありえないとは思うけど、次はギャスパー・ノエにトム・クルーズ主演の映画を撮ってほしいよ。『コラテラル』でさえ、残酷な人間にはなりきれなかった彼に、新たな表情を与えてくれるようなきがするからさ。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]



