2004年11月30日
今、ロバート・アルドリッチに思いを馳せてみる
 週末の劇場通いが完全に(!)定着してから、ということは当サイトがオープンしてからというもの、以前に比べ、毎週数本のヴィデオをセレクトし、私より上の世代、または、決してそうとは限りませんが所謂シネフィルと言われる人たちよりはるかに遅れながらも、旧作を発見していく喜びと感動の絶対数が、目に見えて減ってきているのは否めません。
週末の劇場通いが完全に(!)定着してから、ということは当サイトがオープンしてからというもの、以前に比べ、毎週数本のヴィデオをセレクトし、私より上の世代、または、決してそうとは限りませんが所謂シネフィルと言われる人たちよりはるかに遅れながらも、旧作を発見していく喜びと感動の絶対数が、目に見えて減ってきているのは否めません。
もちろん、劇場で観た作品評を核に据えるというこのblogのテーマからすれば、それもまた当然の成り行きといいましょうか、毎週のように新作は公開されていきますし、それを観た上でさらにある程度の分量を持った文章を綴るとなると、私のような遅筆にとってはそれなりの時間を要してしまう、よってなかなか旧作にまで手が回らない、と。
ただし、劇場で観た映画全てに対し文章を綴るつもりはありませんし、それはヴィデオやdvdにしてもしかりです。これは駄目だ、と思った映画について積極的に悪口のみを書く趣味は持ち合わせていないので、例えば先日観た庵野秀明監督の『キューティーハニー』にはこちらの淡い期待に反してあまりに途方に暮れてしまい、仮に文章を捏造しても欠点の指摘ばかりになってしまいそうだったので止めておいたし、逆に言えば、新作だろうと旧作だろうと、何らかの感動を齎してくれた作品については、積極的に評を書きたいということです。
しかしながらここで冒頭の話に立ち返れば、やはり旧作を観る頻度がどんどん落ちてきているので、どちらかというと、ヴィデオやdvdで自身の映画史的パースペクティヴを構築してきた身として、この事態は非常にまずい、と言わねばならないでしょう。これは何とかしなければいけない、ドラクエ8などに現を抜かしている場合ではないな、と思っていた折も折、ハリウッドで我が敬愛する映画監督ロバート・アルドリッチの『ロンゲスト・ヤード』がリメイクされるという事件を目にして吃驚。つい先日も、やはりアルドリッチが監督した『飛べ!フェニックス』のリメイクが進行中というニュースに驚きと不安感じたばかりでしたので。ハリウッドも本当にネタが尽きつつあるんですね。
さて、こうなってくると、ではリメイクという問題について考えてみたい気がするのですが、そうはいっても私自身、まだ確固とした考えを持つにいたっていないというのが正直なところ、セルフリメイクとなれば話は別かもしれませんが、一つだけ確かなことは、監督が変われば映画は別物だということです。だからといって、全てのリメイク作品を、それこそ“墓を荒らすな!”的に断罪するつもりなどさらさら無く、出来ればアルドリッチの10分の1でも面白ければいいと控えめに期待するくらいの寛容さは持っているつもりです。
私の中でロバート・アルドリッチという映画作家の存在はことのほか大きく、ほとんど“巨人”と形容できるほどの圧倒的な存在感を放ち続けているのですが、それは、もうかなり昔になりますが、『ロンゲスト・ヤード』を観た時の衝撃が未だ生々しく甦ってくるからであり、50年代という不遇の時代から映画を撮り始めたアルドリッチの強さは、それが西部劇であろうと、オカルト的ミステリーであろうと、警察モノだろうと、スポーツモノだろうと一向に揺るぎなく、もちろん時代と共に古びていく宿命などとは無縁の、常に“やたら面白い”作品群として、永遠に記憶されるべき存在なのです。
このところ見直すことが無かったアルドリッチですが、アメリカでこのようなリメイクが相次いでいる今こそ、改めて見直さねばと思っているところです。
どこか気の利いた小屋で、レトロスペクティヴでもやらないでしょうか…
2004年11月28日
『三人三色』と『ニワトリはハダシだ』
というわけで、結局bunkamuraを鼻先でスルーしつつ、イメージフォーラムに行き『ニワトリはハダシだ』2回目を鑑賞。7割くらいは埋まっていましたが、大半は40代以上の年配層でした。私自身、この映画を予想以上に楽しむことが出来たのは、思うに、この作品が持つ“明るさ”に拠るのだと思います。「ニワトリはハダシだー!」と主人公である知的障害者の少年が叫ぶまでの冒頭のシークエンスを観て、何故だか頬が緩んだのは、今思えば、この当たり前の事実に改めて目を向けざるを得ない自分自身に対する笑いだったのかもしれません。
それにしても養護学校の教師を体当たりで演じた肘井美佳の演技の、何ともいえない瑞々しさは、私の中で新たなる発見として記憶されるでしょう。彼女が放つ、唐突なとび蹴り! 笑い顔も泣き顔も怒り顔も、ここまで全てが魅力的な女優は久々です。原田芳雄は相変わらず泣かせますが、今回ばかりは肘井美佳に拍手を贈りたいと思います。
『生きてるうちが花なのよ 死んだらそれまでよ党宣言』から20年近く経っても、森崎東の衰えを知らぬパワーは顕在でした。
さて、昨日観た『三人三色』についてもやはり触れておきます。
土曜日の初回に鑑賞しましたが、UPLINK Xにいた観客はざっと5人ほど。もったいない、あまりにもったいないというのが今の本音です。
オムニバス一作目は韓国映画『インフルエンザ』。監督のポン・ジュノは個人的に韓国で最も注目している監督の一人です。28分という短い時間ながら、徐々に張り詰めていくテンションは相当なもの。“暴力の蔓延”と一先ず言える本作のテーマですが、特筆すべきはやはり、そのカメラにあると言えるでしょう。監視カメラ(的)映像のみで成り立っている、ということは、あまりに機械的なワンシーン・ワンショットで構成されている『インフルエンザ』ですが、暴力の圧倒的な勝利(鉄の棒と金槌で何発も殴った後、最後に車でその頭を踏み潰すシーンの衝撃!)のみが、画面に焼きついているかのようです。たった28分間で、よくぞここまで…と、改めてポン・ジュノの才能に気付かされました。
二作目の『夜迷宮』は、ジャ・ジャンクーの撮影監督として知られるユー・リクウァイ監督作品。所謂“無声映画”では無いのですが、台詞が全く無いという意味で、やはりサイレント映画だといえるのかもしれません。SF的なシチュエーションでありながら、そのような設定自体が画面そのものの力でその都度凌駕され、最終的に脳裏に残るのは、半ば歪んだ、ピントがずらされた人物だけなのです。現実と虚構の差など無く、無理やり表現すれば、現実には存在し得ない詩のような映画だったのではないでしょうか。
三作目『鏡心』は日本でもファンの多い石井聡互監督作品。この映画には全ての登場人物に名前がありません。“女優”とか“監督”とか“少女”とか、つまり匿名的でそれゆえ幻想のような映画です。ただし、その割りには主演の市川実和子がカメラの前で延々泣きながら独白するシーンの、抽象的でありながらも妙に生々しいシーンは素晴らしかった。そして、上記2作品にはない、極めて重々しい風景の美しさが印象的でした。あのような暗い空と海は、実は私の個人的な好みなのです。
どれもが短編ではありますが、満足できる映画体験だったと断言できます。騙されたと思って足を運んでみてください。
待つことが齎す喜び
金曜日から昨日にかけて、全く予定通りというほか無いほど忙しく、blogも更新できない始末。だからこうして、日曜日の朝っぱらから書いています。
さて、この週末は数年来待ち望んでいたものを2つ手に入れました。
一つは携帯電話。昨年5月に開催された「ビジネスショウ 2003 TOKYO」で最初に見かけたときから、発売した暁には絶対発売日に入手するぞ、と決めていたのです。金曜日朝10:00、今まさに開店しようとしているビックカメラ渋谷ハチ公口店前に、私はいました。「talby」と名付けられたその携帯電話をいち早く購入するために。まぁ、いい年してたかが携帯ごときで…と思われる方もいるでしょう。しかし私の場合、本当に欲しいモノに出会ってしまった場合、若干冷静さを欠くくらい購入への強固な決意をしなければ気がすまないし、これまでの人生において、そのような局面は少なく見積もっても十数回はあったのです。よって自分では自然極まりない態度だったということです。
もう一つの手に入れたかったものは、しかし、前述した携帯電話ほどには…と自分では思っていたのです。そしてまた、それを購入してしまうと現在の私の休日パターン、すなわち、映画中心の生活に支障をきたす恐れがある…だから正直迷っていました。
土曜日午前11:30。その日は予定が詰まっていたので、ジムを終えてすぐに帰宅、着替えてUPLINK Xに急がねばなりませんでした。が、約4年間にわたってそれを心のどこかで“待っていた”私の本能が、やはりと言うべきか反応してしまい、意思とは無関係に私の足は再度ビックカメラ渋谷ハチ公口店へと。気付いたら、「ポイントは全部使ってください」などと言っている自分がいました。ああ、これで向こう数ヶ月間の映画生活に翳りがでてしまうのか…まずい、これはまずいことになったなぁ……と思いながらも、いや、かつてハドソンの高橋名人が声高に訴えていた言葉、「ゲームは一日一時間まで!」というノスタルジックな決まり文句を実践すればいいんだ、うん、そうすればいい!! と思い、今朝に到ります。
私が欲しかったものの2つ目、それは言うまでも無く、「ドラゴンクエスト8」なのです。
というわけで、昨日は早速高橋名人の言いつけを破り、5時間ほどのめりこんでしまった、超駄目人間[M]ですが、本日は映画に行こうかどうか迷っております。初回以外では絶対に行きたくない『モーターサイクル・ダイアリーズ』の初回は、今こうして日記を書いているのですでに逃しつつあるし、それ以外に今週観たい映画も無いような気も。いや、決してDQ8のせいではないのですが。bunkamuraで開催中の「流行するポップアート」にも行きたかったので、今日はその辺りでお茶を濁すかもしれません。昨日観た作品『三人三色』や、オペラシティに自転車を飛ばして駆けつけた「ウォルフガング・ティルマンス展」のことも書きたいので、残りの時間はblog作業に費やそうかと。もちろん、DQ8は一時間だけ、です。。。。。。
2004年11月25日
充実の予感、あるいは『オールド・ボーイ』のすすめ
昨日は『たまもの』を観るべく、8時前に会社を出る決意をしておりました。例によって直前にユーロスペースのHPを覗いて時間を確認してみると・・・“「おすぎのシネマトーク」 ゲスト:佐藤友紀さん”という文字が。これは『たまもの』とは何の関係もないトークショーなのですが、あの狭いユーロスペースが混雑する様が頭をよぎり、またもや断念しました。いずれにせよ、近く仕切りなおします。
さて、今週は土曜日にアップリンクXにて『三人三色』、その後、オペラシティにて「ヴォルフガング・ティルマンス展」を。日曜日はまだ未定ですが、『モーターサイクル・ダイアリーズ』に行くかもしれません。
『三人三色』は、韓国はチョンジュ映画祭で2000年より始まったプロジェクト。アジアの映画作家三名によるデジタルフォーマットのオムニバス映画です。選ばれた監督はそれぞれ、ポン・ジュノ・ユー・リクウァイ・石井聡互です。全部併せても98分の短編作品、非常に楽しみであると同時に、これまで全くノーチェックだったことを後悔……観にいかれる方、是非コメントください。
それはそうと『オールド・ボーイ』はもう頭打ちでしょうか。昨日、mixiで知り合った京都の映画館に勤務している方からメールをいただき、それによると、京都ではすでにガラガラだとか。先日2回目の渋谷アミューズCQNでは6割くらいは入っていたと思うのですが、すでに興収ベスト10からは外れています。やはり、上映館が多すぎたのでしょう。そう思うと、『2046』は意外と健闘しているような気も。今、このサイトをご覧になっている方には『オールド・ボーイ』をまだ観ていない方も多いでしょうし、あのような映画を観るつもりなど端から無いと決めている方もいるでしょう。もちろん、それぞれの好みがありますから大きなことは言えませんが、少なくとも私は、会う人会う人に「絶対に観たほうがいい」と激しい口調で推薦し続けています。もし迷っている方には是非観ていただきたい作品です。これから作品評を書きますが、そこにも自由にコメントしていただければ幸いです。
2004年11月24日
『変身』は“変”であることを最後まで止めない
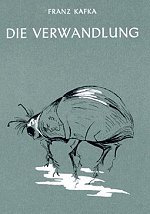 恐らく誰もが一度は目にしたことがあると思われる、フランツ・カフカによるあの有名な一節で始まる「変身」。何故という言葉が通用しないのが不条理の世界であるなら、全く不条理と言うほか無い物語だと一先ずは言えるでしょう。理由もなく巨大な虫に変身してしまうグレーゴル・ザムザは、しかし、人間性を失っているわけではないので、その点がより一層、この物語を荒唐無稽にしているのです。いや、荒唐無稽というよりはもっとシンプルに“変”な映画、ワレーリイ・フォーキン監督の長編処女作である『変身』を観た後、この“変”という言葉が真っ先に浮かびました。こんな経験は、これまで何回あったのか自分でも思い出せません。
恐らく誰もが一度は目にしたことがあると思われる、フランツ・カフカによるあの有名な一節で始まる「変身」。何故という言葉が通用しないのが不条理の世界であるなら、全く不条理と言うほか無い物語だと一先ずは言えるでしょう。理由もなく巨大な虫に変身してしまうグレーゴル・ザムザは、しかし、人間性を失っているわけではないので、その点がより一層、この物語を荒唐無稽にしているのです。いや、荒唐無稽というよりはもっとシンプルに“変”な映画、ワレーリイ・フォーキン監督の長編処女作である『変身』を観た後、この“変”という言葉が真っ先に浮かびました。こんな経験は、これまで何回あったのか自分でも思い出せません。
この印象はもちろん、映像のみに終始しません。その音もまた“変”です。いささか気味が悪い効果音と弦楽器による神経に障るBGM。わかりにくい描写はそれほど無いし、どちらかというと大げさな演技をする舞台俳優のリアクションも極めてわかりやすいと言えるのですが、それでもやっぱり最後には“変”だという思いからは逃れられないのです。
『変身』という映画は、全体を2つに分けて考えることが出来ると思います。一つは、グレーゴル・ザムザのいる現実世界、そしてもう一つは、彼が見る夢(幻)的世界です。それら2つの世界はそれぞれ、“雨(水)”と“陽光”のイメージを結んでいたような気が。実際、『変身』には雨が降るシーンが多いのです。
どしゃ降りのプラハ駅に、黒く巨大な機関車が画面手前に向かってゆっくりと到着するというファーストシーンは、左から右に、やはりゆっくりとパンするカメラがその列車の到着と同時にその動きを止めます。列車から降りてくる何人かの男たちは、ルネ・マグリット的な山高帽をかぶっていて、その中の一人であるグレーゴル・ザムザもまた時代がかった衣装を身に纏い登場します。唐突にカメラ(観客側)を真正面から見つめるグレーゴルのアップに画面が切り替わったかと思うと、またもや時間をかけて、今度はズームダウンしていく。そしてグレーゴルの全体像を捉えきったあたりで、彼は思い出したように(!)大げさな演技を開始するのです。
冒頭の数シーンをこのように記してみて思うのは、頭の中にあるこれらのイメージの“奇怪さ”など、私自身の貧しいボキャブラリーではとても表現しきれないという確信のみです。“変”です。何かがおかしい。
『変身』において、観客は決して“変身”する場面を目にすることがありません。ということはつまり、我々が勝手に思い描く巨大な虫なるもののイメージとそれに伴う“変身”シーンは、予め排除されているのです。観客が事前に描いてしまうであろう恐ろくグロテスクな虫などそこにはなく、グレーゴルは最後まで所謂“人間”としての姿を保ち続けます。よって、原作に存在した途方も無い虫に関する具体的な特徴、すなわち、“甲羅のように堅い背中・こげ茶色をした丸い腹・かぼそい無数の脚”等の説明(モノローグ)はなされることがありません。見た目は全くもって人間でしかないのですから、それも当然でしょう。エヴゲーニイ・ミローノフの驚くべきパントマイムは、手足の指の動きだけでその“虫”ぶりを表現していて、観客に彼を“虫”だと信じ込ませることに成功していると思うのですが、それでもやはり、彼は最後まで人間としての姿を裏切ることはないのです。
この予想外のアイデアを、私は優れて批評的だと思います。観客の意識に潜む“他者を見る目”を予め暴き立てているという意味で。グレーゴルが“変身”したという“事実”は実際には彼自身にしかわかっていないことで、人間の姿をしながら虫のような動きをしているだけのグレーゴルを、しかし、虫だと断言しようとしてしまう彼の周囲と我々観客は、言ってみれば共犯関係にあるような気がするのです。あの哀れな人間を見て観客がどう感じるのか。監督は、その辺りに鋭い視線を投げかけているように感じました。
にもかかわらず、まるでコントとも言える程に大仰な周囲の人間の反応の滑稽さときたら! グレーゴルを発見した瞬間に彼らは、飛び上がらんばかりに恐れおののくのですが、あの人を食ったような超スローモーションにより、グレーゴル以外の人間はあまりに滑稽に描かれているのです。ほとんど冗談かと思われるようなあの動きもまた、グレーゴルに劣らず非常にグロテスクだったといえるでしょう。
『変身』のラストシークエンスは私にとって非常に難解でした。
唯一グレーゴルのことを虫呼ばわり(ゴキブリなどの固有名詞は彼女以外の人間からは発されることがないのです)した女中が彼の死を発見するのですが、その後に続くラストシーンで、彼はまさに2本足で直立した人間(虫となった彼は常に4足歩行でした)として登場するのです。彼が死んで幸せそうな家族を見守りながら…あのシーンは、先に述べた分類で言えば、夢(幻)的世界だったのでしょうか。そうに違いないと思いたいのですが、この“変”な映画は、そういった指摘をいちいち曖昧にしつつ、私の結論をその都度先送りにし続けるのです。
2004年11月23日
紀伊国屋ホールにて
『変身』に関する文章が滞っております。いつでも評しがたい映画があるものですが、『変身』に関してはむしろその逆、かなり“掴みやすい”映画だとも思います。しかしながら、この舞台劇のような映画は、その細部の描写をこそ語りたいにもかかわらず、今思い出そうとしても、その細部が容易には思い出されないため、なかなか難しいな、と。ともあれ、明日の昼までには必ず。
で、映画を観なかった本日、実は久方ぶりの演劇を鑑賞。数年前、ナイロン100℃の作品(題名は忘れました)を観て以来の紀伊国屋ホールにて。ハラホロシャングリラによる「ワンダーランド」(作・演出 中野俊成)という作品です。松涛にあるBARのマスターが実はここの劇団に属していて、そのBARの半常連(?)である友人にチケットを譲っていただいたので。普段は映画ばかりで自分で演劇のチケットを取ったことなど一度も無い私ですが、この作品は予想以上に楽しめました。
漫画喫茶というファンタジーな空間を舞台に、うだつの上がらない印刷会社勤務のサラリーマンが、自らの幼年時代のトラウマを克服していくという話ですが、そこから想像される教訓劇のような物語性をはるかに超えて、この作品は紛れも無くコメディだったのです。実は冒頭15分くらいはなかなか乗れず、こんなところにまできて、映画と演劇のコメディについてその違いとやらを考えてしまいそうになりもしましたが、そんな夢想に耽る直前に再び現実に連れ戻されたのは、チャウ・シンチー的とあえて言いましょう“ギャグの反復”が、中盤から後半にかけて随所で炸裂していたからです。実際、終幕後には、もっと演劇を観にいくようにしようかなどと、本気で思った程。いくら目の前で演じられていても、見慣れてない演劇に関してはやはり詳述することが出来ませんが、このハラホロシャングリラというふざけた名前の劇団が演じる舞台にはどうやら、また足を運ぶことになるでしょう。
明日は時間があれば、ユーロスペースにて『たまもの』を鑑賞予定です。
2004年11月21日
コスチュームマリオキリストンユーロアミューズパーティ
 と盛りだくさんの金曜〜土曜でした。
と盛りだくさんの金曜〜土曜でした。
金曜日は早めに仕事を切り上げて恵比寿ガーデンルームで開催されたCostume Nationalのファミリーセールへ。以前はここの服ばかり着ていたので、毎回必ず大量購入していたんですが、このところてんでご無沙汰で、2年ぶりくらいに行ったような気がします。ただし、行った時間が時間だったので、すでにいいものはなくなっていまして、でも何も買わないで帰るのも悔しいので、結局パンツ一本だけ購入。
その後、本日で終了してしまう「マリオ・テスティーノ写真展 ポートレート」へ。すぐ隣の東京都写真美術館です。素晴らしいポートレートばかりで、感動することしきり。私も今はポートレートばかり描いているのですが、やはり、人間の表情というものは無限大だなと今更ながら関心。中でも、淡い陽光が全体を優しく包みこんだ、映画的な、あまりに映画的なケイト・モスの、全体としてみればそれほど大きくは無いポートレートには圧倒的な美が漲っていて、それはまさしく映画の一シーンのような、というより、映画そのものだと根拠も無く断言したくなり、ほとんど無理やり引っ張ってきてしまった同僚の女の子に「これは映画だ!」と興奮気味で同意を求めたりする始末。閉館時間が迫っていたせいでゆっくり観られなかったのですが、後一時間は観て居たかったというのが正直な気持ちです。
恵比寿から新宿に移動後、悪い仲間たちで悪い飲み会を開催。舞台となった「キリストン・カフェ」は渋谷店のほうがよりゴシック趣味が漂っているなぁなどと思っているうちに、記憶が曖昧になってきたので、そのまま笹塚の友人宅へ場を移し、気がついたら翌朝だったという、まぁいつもながらの体たらく。
土曜日は、昼過ぎからユーロスペースでロシア映画『変身』を。半分くらいの入りでした。上映後、渋谷に新しく建てられたpicasso347というビルにある「347CAFE」のプールサイド(!)テラスで、寒風に震えつつもビール・赤ワイン・白ワインを飲みながら、先に観た『変身』評の下書きをつらつらと書いて時間をつぶし、夕方からアミューズCQNにて2回目の『オールド・ボーイ』を鑑賞。前回観た時にはやや曖昧だった、“生涯の10本には入るかもしれない”という思いがほとんど確信へと変り、改めて感動に打ちひしがれ劇場を後にしました。
渋谷から今度は牛込柳町に場所を移し、高校時代の友人宅で催された“ボジョレーパーティ”へ。ほとんど空腹のまま恐らく2Lくらいのボジョレーを胃に流し込むと、文字通り“ジ・エンド”となった私は、今日という休日を見事に無駄にしつつ家でだらだらしています。
さて、『変身』評がどうにもはかどらないのですが、何とか本日中には仕上げたいなと。『オールド・ボーイ』評については、超絶賛の方向で思案中です。
2004年11月19日
インファンティリズムへと・・・
 私にはアメリカに住んでいる友人などいないつもりでしたが、昨晩、拙サイトの熱心なファンかもしれない“penis enlargement”という白人(?)男性から大量のコメントを頂きました。ざっと60くらいですね。まぁ映画と全く関係が無いとは言えないかもしれないこのコメントですが、今の私にはあまり必要の無いお誘いだったので、一つ一つ丁寧に(手動で!)削除させていただいた次第。スパムコメント対策、そろそろ真剣に考えなければならないようです。
私にはアメリカに住んでいる友人などいないつもりでしたが、昨晩、拙サイトの熱心なファンかもしれない“penis enlargement”という白人(?)男性から大量のコメントを頂きました。ざっと60くらいですね。まぁ映画と全く関係が無いとは言えないかもしれないこのコメントですが、今の私にはあまり必要の無いお誘いだったので、一つ一つ丁寧に(手動で!)削除させていただいた次第。スパムコメント対策、そろそろ真剣に考えなければならないようです。
さて、昨日はボジョレー2日目。営業時代お世話になった方々との定例会でした。
御徒町にある小さな中華料理店で飲んだのですが、興味深かったのは、まさかこの店にボジョレーなどおいてあるはずは無いじゃないか! と叫びたくなるような店にもかかわらず、出てきたのはアルベール・ビショーのボジョレー・ヴィラージュ・ヌーヴォー。それを数本空けた後、白ボジョレー、そして最後には瓶出しの紹興酒が。この3者を順番に口に運んでいくと、もう何が何だかわからなくなってきます。赤と白と茶のアマルガム・・・至福から泥酔へのカウントダウン・・・・・・まぁ結果的にはそれほど酔わずに帰ることができたんですけど。
先日の日記にも書いたとおり、今、私自身の最大の関心事は、いかにして現金を作り出すかということ。いい年してどうしてこんなことに腐心しなければならないのか、自分でもわからないというのが正直なところ。しかし、迫り来る現実を前にすべきことは明白です。錬金術、とワタクシが呼ぶところの方法についてはあえて詳述しませんが、飲みの予定を逆手に取ったこの手段を駆使すれば、とりあえず給料日までは食いつなぐことができるでしょう。
最近、映画サイト仲間との会話(メール)のなかで、“ボンクラ系”という言葉が幾度か出てきたのですが、例えば「ケヴィン・スミスはボンクラ系ですよね」などと発言する前に、ほかでもない私自身が最もボンクラなんじゃないかということに、つい先ほど気が付いてしまいました。ボンクラが自分のことを棚にあげているだけだったんですyo・・・・・・この事実には、ひたすら深く沈黙せざるを得ません。一応、社会的には“いい大人”と呼ばれる程に年を重ねている私ではありますが、現在の“錬金術師としての私”など間違っても“いい大人”ではないし、半ば諦念を感じつつあるくらいなので、いっそのこと、「血と薔薇宣言」にのっとり、インファンティリズム(!)へと突っ走るほかはないのだと決意を新たにしたところです。ボンクラ系でもロクデナシ系でも何にでもなってやる! ああ、狂気の女神よ!!!!!
・・・本日夜はボジョレー3日目です。
「どうなることやら・・・」(マリアンヌ・ルノワール)
2004年11月17日
マンマ!
先日鑑賞した『オールド・ボーイ』、未だ余韻の只中にいると言えますが、原作を読もうかどうしようかと迷っています。読んだら読んだで、その印象は少なからず映画の評価に揺さぶりをかけるだろうことは目に見えているので。とりあえず、最終的な評価は今週末に再度鑑賞した後に定まるかと。
気が付いたらもう今週いっぱいで終了してしまう「マリオ・テスティーノ展」にも行かなければと思っているので、ついでに『モーターサイクル・ダイアリーズ』も観て来ようと思っています。
さて、本日は最近読んだ&これから読む本について。
まずは「フィルムメーカーズ11/ヴィム・ヴェンダース」(キネマ旬報社/定価1,680円)。青山真治氏が責任編集をしていたので。黒澤・塩田・青山、そして樋口氏によるヴェンダースを巡る対談はなかなか興味深く、とりわけ“アメリカ映画=西部劇における床屋”とする言説には少なからず感心した次第。ほとんど読んでいないヴェンダースによる映画批評も、やはり必読だなと思います。初期アヴァンギャルド作品も観たいですが、こればかりは特殊な機会じゃなければ無理そうですね。
次は一応ベストセラーということで「アフターダーク」など読んでみたり。村上ファンではないので、彼の著作を全て読んだわけではありませんが、思い返すとそれなりに読んでいたような気も。本作については、一度読み終えた時に持った印象が余りに浅はかで途方に暮れてしまい、自分の印象を再度疑ってかかったわけですが、それでももう一度読むかと言われると言葉に詰まりそうです。
加えて、お金が無い私を哀れんで、読書家の友人が貸してくれた本が数冊。「亡国のイージス」やら「トリュフォー,ある映画的人生」やら「文藝春秋(以前話題になった若手女流作家の2作品が収録されている号。)」やらです。これで当分ジムで読む本には困りません。情けなくも友人に感謝。
雑誌では、「STUDIO VOICE〜ラディカル・コメディ190」「映画芸術〜2004年秋の映画を襲撃する!」「TITLE〜映画で世界は回ってる。」と、映画関連をまとめて購入。「映画の魔」(高橋 洋)は高かったので給料日後に持ち越しました。
さて、そんな貧乏状態にもかかわらず、今週は本日より3連投で飲み続けます。ボジョレーの解禁日もあるので。こんな生活してたら、そりゃ、母親も不安がりますね・・・・・・いわゆる郵便的不安っていうやつでしょうか。
最後にそんな母へ一言。
ジャンフランコ・フェレというファッションブランドがあるのですが、それを勘違いして「フェラよ、フェラ!」と大声で訴えるのだけは、金輪際止めてください。困るんです、本当に。
2004年11月16日
『SAW』、あのテンションをもう一度
:::caution:::結末に触れていますので、未見の方は読まないで下さい:::caution:::
 『SAW』を観終えた後、すぐさま想起された映画があります。それは『ナイトウォッチ』というアメリカ映画で、デンマーク映画『モルグ/屍体消失』のセルフリメイクです。観たのはもう大分昔の話ですから細部は思い出せませんが、簡単に説明すると、主人公を演じるユアン・マクレガーが手錠をかけられ身動きがとれない状態にあり、しかし、すぐにでも逃げなければ犯人に追いつかれ殺されてしまうという場面がありました。そこで主人公がとった行動は、ナイフ(だったと記憶しています)で自ら親指を切断し、手錠から抜け出るというものでした。実は『ナイトウォッチ』はたいした作品ではなく、このシーン以外ほとんど思い出せないくらいですが、逆に言えば、この指を切断するという方法論だけは悪くないなと思いました。
『SAW』を観終えた後、すぐさま想起された映画があります。それは『ナイトウォッチ』というアメリカ映画で、デンマーク映画『モルグ/屍体消失』のセルフリメイクです。観たのはもう大分昔の話ですから細部は思い出せませんが、簡単に説明すると、主人公を演じるユアン・マクレガーが手錠をかけられ身動きがとれない状態にあり、しかし、すぐにでも逃げなければ犯人に追いつかれ殺されてしまうという場面がありました。そこで主人公がとった行動は、ナイフ(だったと記憶しています)で自ら親指を切断し、手錠から抜け出るというものでした。実は『ナイトウォッチ』はたいした作品ではなく、このシーン以外ほとんど思い出せないくらいですが、逆に言えば、この指を切断するという方法論だけは悪くないなと思いました。
さて『SAW』ですが、このタイトルである“saw”とはノコギリのことです。それは序盤に存在が明らかになり、最後まで一応小道具としての機能を保ち続けます。がしかし、タイトルとして相応しかったのかどうか、多少の疑問が残ります。実際、それがノコギリ本来の効力を発揮するのは、ケアリー・エルウェズが足を切断するシーンだけなのです。時にはそれを放り投げることで監視者の存在が明らかになり、時には柄の部分で壁を粉砕することで隠された箱を手にしもするのですが、これらはノコギリでなくてはいけないという説話的必然性などなく、別のアイテムでも良かったはずです。そして結局、ノコギリが持つ“物を切断する”という(本来の)機能は一度しか発揮されません。その上、問題の切断シーンも多くは描かれず、切り始める瞬間と切り終えた後放り出されるノコギリというショットによって示されているに過ぎないのです(途中、自らの返り血を浴びるケアリー・エルウェズの短いショットがはさまれますが)。切断面も切り落とされた足も、全く見せることが無い。ケアリー・エルウェズが足を切断するにいたるまで高められた激情(その直前の彼はほとんど発狂寸前で我を失っていました)を生かすには、やはり、切断シーンをワンショットで見せて欲しかったという気がしてしまうのです。ノコギリは、そうなって初めて小道具としての強度を持ちえたのだ、と。
ただし、“saw”という言葉が、第一義としてノコギリではなく、seeの過去形、すなわち“(一部始終を)見た”という意味が付されていたらどうでしょうか。この場合、真犯人である“偽死体”が、全ての事件を、とりわけ、あのバスルームで起こった惨劇の一部始終を“(最前列で)見ていた”と解すことが出来、ちりばめられた様々な伏線も効いてくるというものです。だとすれば、なかなか機知に富んだタイトルだと思います。まぁ、こればかりは、我々観客の想像に委ねられているのでしょう。
さて、『SAW』は決してホラー映画ではありません。恐怖そのもので観るものを戦慄させるというより、身震いするほどの緊張感や、先の読めない不安感を観客に強いることで、エンターテインメントの域に達する、そんな映画だといえるでしょう。所謂サイコスリラーというジャンルにまずは収まるであろう『SAW』は、よって、これまで多く生み出されてきた諸作品と、それほど大きな違いはありません。サイコスリラーで注目すべき重要な部分は何点かあり、例えば、殺人の方法だったり、犯人が残すヒントだったり、使用される小道具だったり、高まった緊張がどのように解けるのか(あるいは、解けないのか)等が挙げられると思います。これらが観客の不安を煽り、その着地点が引き伸ばされるほど、結末が生きてくるのです。さらにいえば、謎(観客が持つ疑問点)は完全に解明されず、それぞれの部分で少しずつ余白(想像の余地)があるほうが良いと個人的には思っています。結局、全てのパズルが寸分の狂い無く解き明かされてしまうと、つまり残された謎の部分がないと、いわゆるライブ感といいますかドライブ感といいますか、そういった(一見、現実に似ている)臨場感のようなものが削がれてしまうような気がするのです。そもそも恐怖とは、人間の想像の中においてこそ生まれるものなのですから、このようなサイコスリラーは、謎が解き明かされることより、どれだけ緊張感が持続されるかが肝要なのです。
ところで、『SAW』における殺人の方法を見てみると、犯人は直接的に手を下しません。言い方を変えれば、犯人は殺人を犯しているというより、被害者に生き残るためのテストを課しているだけなのです。そのテストに合格できない場合にのみ、被害者は本当の意味で被害者になりえる。これは特筆すべき部分だと思います。危害を与えるというより、むしろ(これまで犯してきた罪に対する)“赦し”を与えているかのような、そんな印象すら受けます。“赦し”とは貴重な生に感謝するチャンスという程度の意味ですが。実際、テストに合格した唯一の女性は、犯人に感謝せざるを得ないのですから。自らの生の尊さを思い知ること、これが犯人の望みなのです。
興味深いのは、用意周到とも言える犯人の装置(それは殺人現場そのものと言い換えても良いかもしれません)に対するフェティシズムです。いずれの場合も、“時間の経過=死”というオートマティズムに基づいた装置が作成され使用されているのです。あの装置へのフェティシズムこそが、犯人のサイコパス性を端的に表していたと解するべきではないでしょうか。そしてさらには、この映画に課せられた低予算という制約を凌駕する程、この陰惨な物語の雰囲気作りに大きな役割を果たしていたと思います。
18日間という短い撮影期間は、それを逆手に取ったドライブ感溢れる演出へと繋がっていたと言えなくもありませんが、随所に挟み込まれるフラッシュバックに実は結構な時間を割いてしまったせいで、ところどころで張り詰めたテンションが弛緩せざるを得なかったという部分も指摘したいと思います。ケアリー・エルウェズが語りべとなったその長い回想シーンがこの事件を解き明かす鍵になるのは言うまでもありません。そもそもこのバスルームにおけるゲームは、ケアリー・エルウェズだけに課せられたゲームなのですから、ゲームの主導権は、彼が握らなければならないのです。それ自体には問題ないのですが、回想シーンの中の人物がさらに回想する等のメタ構造の複雑さからか、観客としては、張り詰めたテンションを一端解除して再度頭を切り替えねばならず、その結果若干の冗長さを拭いきれなかったのです。
とはいうものの、ラスト20分の展開はこちらの意図を超えて感覚的と言うほか無い速度を保っていたし、足を切断してからのラスト10分間で、突き放したような結末を文字通り観客に突きつける暴力性には、やはり舌を巻いたと言わなければならないでしょう。序盤では、どちらかというと単なる“被害者”であるリー・ワネルの取り乱しぶりを印象付けておいて、ラスト20分間で、今度はケアリー・エルウェズの混乱から狂気にいたる過程を見せる。そしてこんな対照的な2人の間に、奇妙な共犯者的感情(パートナーシップ)が生まれるあたりで、しかし、物語はあっけなく結末を迎える。『SAW』は103分の映画ですが、後10分短かったらと思わずにはいられません。
最後に、この映画にまんまと騙されることが出来たことは、やはり幸福だったと付け加えておきます。次回作が楽しみな監督がまた一人増えました。
それにしても…
人は映画に何を求めているのでしょう。いやもっと言えば、人は何を求めて『SAW』なる映画を観にいくのでしょう。映画において最もくだらないことだと私が確信していること、それは、無理やり欠点を探してみたり、元ネタ探しに躍起になってみたり、あるいはありえない可能性について想像して悦に浸ったりすることです。そうすることで、自分を映画よりも上位に位置づけようとするさもしい精神、ほとんどコンプレックスと言ってしまいたくもなるこれらの心理を、私は理解できません。
現在、『SAW』に関する文章を書いておりますが、いくつか他の人が書いた文章を読んで、上記のような思いにとらわれました。金を払っている以上、どのように映画を楽しもうがそんなことは本人の自由と言うしかありませんが、なんといいますか、私にしてみれば、そのようにしか映画を観られないのだとしたら、あまりに不幸と言うほかありません。完全に騙され敗北することにもまた甘美な快楽はあるのです。『SAW』のような映画は、結末が途中でわかったからといって何になるでしょう。現実との違いや、矛盾点を求めたところで、何かが生まれるでしょうか。聞くところによると、東京ファンタスティック映画祭でどこぞのバカが、ティーチインであまりに見当違いな指摘をして監督の失笑を買ったそうですが、映画を映画として観られない人間ほど、不幸な人間もまたといまい、私はそんな風に思ってしまいます。
作品評は、明日中に完成させます。
2004年11月12日
『血と骨』に関して追記
【関連ページ】
ある日の会話〜『血と骨』を巡って
昨日の文章を読み返してみると、どうにも悲観的側面ばかりが目立ち過ぎた感が。
いや、私が結果的にそれほど乗れなかったというのは否定しませんが、もう一点、重要なことを書き忘れておりました。あのような会話を捏造までしたにもかかわらずどうしても付け加えたかったこと、それは、全編に漂う“生々しさ”に他なりません。これを言葉で表現することの難しさは承知しているつもりですが、ここではあえて、それを強調しておきたいと思います。
“血は母より、骨は父より受け継ぐ”というキャッチコピーにもあるように、『血と骨』というタイトルに“家族”という概念が込められていることは周知の通りです。そして私は、この“血”と“骨”に深く関係するもう一つのファクター、すなわち、“肉”の存在をどうしても指摘したいのです。『血と骨』に溢れる“生々しさ”は、“肉”という概念を抜きには考えられないと思います。
例えば、北野武演じる金俊平が、豚を屠殺する場面があります。丸々と太った豚を逆さにつるし、よく砥がれた包丁で胸を一突きすると、あふれ出る鮮血を顔や服に浴びながら、たらいで受け止める息子がいるという場面。あるいはこのシーンの変奏が、借金をなかなか返済できない國村隼に対し、自らの腕を切り裂いて溢れ出る血を飲ませようとする場面だと言えるのかもしれませんが、これらの場面は、肉が切り裂かれ、その傷口から血が流れる、そしてその血が別の誰かに与えられるという、極めて直接的な表現がとられています。ここに、血を介した主従関係を読み取ることが出来ると思いますが、そもそも、肉の存在無くして血が流れることは無いのです。
半ば腐りかけ蛆が沸くような肉、蒲鉾工場の作業台にどっさり乗せられたグロテスクな魚の山など瞬時に認識される生臭さに加え、肉と肉がぶつかり合うようなセックスシーンを挙げても良いし、北野武の腹までもが生々しい迫力を放っていたと断言しても良いかと思います。『血と骨』は、かような生々しさを漂わせることで、原作に拮抗しようとしていたのかもしれません。原作を読んだ私が抱いた諸々のイメージのいくつかは、この生々しさにより、辛うじて実を結ぶことができたのだと思います。それはやはり、正当に評価しなければならないでしょう。
2004年11月11日
ある日の会話〜『血と骨』を巡って
先週『血と骨』を観たよ。日曜日だけどそれほど混んではいなかったなぁ。
----あ、ホント? で、面白かったの?
う〜ん、原作と映画を比べることは無意味だと思ってはいるんだけどさ。あれを読んだのは6年くらい前かな。後輩に薦められて一気に読んじゃったんだよ。
----つまり映画はいまいちだったっつうことか。 原作はそんなに凄いの? 映画のほうも武主演でかなり凄いらしいじゃん。
いや、俳優陣はなかなかのもんだったよ。これは誰もが思うことだろうけど、濱田マリには驚いたね。彼女の裸体を見るとは思ってもいなかったから。それは満足。オダギリ・ジョーも悪くない。柏原弟は、最近大分ノッてきてるしさ。鈴木京香の評価は分かれるところだと思うけど、彼女は流石に脱がなかったからなぁ…
----脱げばいいのかよ(笑)
いやそうじゃなくてさ。この映画は“濡れ場”というか、まぁほとんどはレイプに近いんだけど、そういうシーンが結構重要だと思うんだよ。絶対に綺麗なセックスじゃなくて、もう暴力の変奏としてのセックスみたいなね。武はまぁその辺の勘所は心得てたと思うんだけど、鈴木京香の服が脱がされないっていうのはどうなんだろう。とはいっても、実際には無理やり胸を揉まれたり、結構足を広げたりしてるんだけどね。なんていうか、比べるのもおかしいけど、せめて『モンスター』のシャリーズ・セロンくらい体張って欲しかったというのが正直なところだな。彼女だって全部見せてたわけじゃないんだからさ。何年も英姫役が演じられるのを待ち望んでたっていうなら、せめてね。『告発の行方』だって、やっぱりあのシーンでしょ?
----まぁ言わんとしてることはわかるけど。長いの?
2時間24分だったかな。決して退屈するほどだれることは無いけど、ちょっと長かったかな……あの壮大な物語を通常の上映時間に収めること自体無理な話だし、特に破綻している部分もなくあそこまで纏めたのは崔監督の力量だとは思うけど。単にこちらが観たかった描写が少なかっただけなのかも。
----崔監督の他の作品と比べるとどうなのかね。何か観た事ある?
実は無いんだよ。彼にはテアトル新宿で会ったことがあるんだけど。お前一緒じゃなかったっけ?
----いや、俺じゃないな、それは。何してたの?
何を観たときだったっけなぁ…ちょっと思い出せないけど、その時崔監督は、多分後に公開される次回作の前売りを自ら販売してたような…観客と気さくに話してたよ。後は、毎朝観てる「やじうま」のゲストコメンテーターとして毎週観てたくらい。映画のほうは、俳優として『御法度』を観たくらいで、監督作は一本も。だから比べられないし、作風もわからないなぁ。まぁそれもあまり関係ないっちゃ無いと思うけど。
----ふ〜ん。どこか観るべきシーンはなかったの、『血と骨』に。
主人公の金俊平って男は、とにかく凄い狂暴な絶対君主なんだけどさ、その多くは理不尽な暴力とセックスとして描かれるんだよね。彼自身にしか通用しない道理に従って行動するから、周りの人間をどんどん傷つける。もちろん死人も出るわけだけど、なんだろう、もっと執拗に彼の理不尽さを観たかったなぁ。美術セットとか陰惨さ漂う音楽は良かったんだけど、もう一つ物足りなかった感があるね。オダギリジョーとの喧嘩するシーンには、もっと途轍もない暴力が炸裂すると思ってたし、新井浩文との喧嘩もまたしかり。ただ、武の肉体には観るべきものがあったよ。醜悪な肉体美とでもいうかね。それと凄く良かったシーンがあって、ラスト近く、もう死ぬ間際の武が、質素な掘っ立て小屋のベッドで寝ててね、外は雪が降ってて、それがだんだんと吹雪になっていくんだけど、その吹雪のゴォー…という音が、そのまま次の回想シーンに重なる部分は素晴らしかった。上手い! と思ったなぁ。北朝鮮の吹雪と幼年時代に初めて大阪に到着しようとする船のイメージが上手く重なってね。
----なるほどね。武は好きだから、観てみよっかなぁ…まだ始まったばかりだし。
しかし、この映画の作品評は難しいなぁ…どうしよう……観なかったことにするのもあれだし…ものすごく駄目な映画っていうわけじゃないし、手放しで賞賛できるわけじゃないから。とりあえず、今お前と話してることをそのまま載せよっ。
【関連ページ】
『血と骨』に関して追記
2004年11月10日
『春夏秋冬そして春』、そして人生は続いていく
 『春夏秋冬そして春』は、これまでのキム・ギドク作品(ここでは正式に日本公開された前2作品を指します)を観てきた人間にしてみれば、やや趣が違うかもしれません。それは、心無い現実への攻撃性や挑発性の不在に拠るのではないでしょうか。ともすると、“静謐さ”もしくは“優しいまなざし”が見られぬでもない本作ですが、しかし、それはキム・ギドク監督の本質的な変化と言えるのでしょうか。
『春夏秋冬そして春』は、これまでのキム・ギドク作品(ここでは正式に日本公開された前2作品を指します)を観てきた人間にしてみれば、やや趣が違うかもしれません。それは、心無い現実への攻撃性や挑発性の不在に拠るのではないでしょうか。ともすると、“静謐さ”もしくは“優しいまなざし”が見られぬでもない本作ですが、しかし、それはキム・ギドク監督の本質的な変化と言えるのでしょうか。
まず指摘したいのは、『春夏秋冬そして春』は全編水に満ちているということ。『魚と寝る女』同様、水に浮かぶ建物という決定的なイメージなくして、本作には言及できません。また、周王山国立公園という“特殊な”自然を舞台に選んだことと、本作が多くのロングショットから成り立っていることのは、無関係ではないと思います。ここでは、激しく揺れ動く感情を持つ人間というよりもむしろ、自然(風景)の一部としての人間をこそ描いているのです。池を取り囲んでいる山の高みから寺を映した超ロングショットが幾度か見られますが、一見似たロケーションの『魚と寝る女』にはほとんど見られなかったショットではないでしょうか。
興味深かったのは、あの寺の動きです。それをはっきりと意識させるショットの挿入が、とりわけ秋の章において顕著だったと思います。何故、人物よりも背景の山に観客を注目させることになるあのようなショットが必要だったのか。人間も自然の一部だというキム・ギドクの意志がそうさせたのかどうかはわかりませんが、少なくとも、常に変化し続ける景色、止まることの無い寺というイメージは、強く観客に訴えるものだと思います。円を描くように、始点も終点もなく移動し続けるということが、この映画の構造そのものである季節の移り変わりのメタファーなのかもしれません。
さて、前2作品同様、『春夏秋冬そして春』においても台詞は極限まで削られています。つまり、画面そのものの力で観客に訴え、言葉による説明を極力排した上で、後は観客の想像に委ねるといった手法はこれまでとそう変らないのではないかと。観客の持つ“何故?”という疑問をそのまま宙刷りにすること。わかりやすい例で言えば、本作における紫のスカーフを巻いた女性ということになるのでしょうが、彼女の素性や行動の動機を明らかにしないのは、登場人物のバックグラウンドに関心を向けさせず、その瞬間起こりつつあるアクションにこそ、観客の意識を向けさせたいという事なのかもしれません。恰も、今画面に映っていることだけが重要だと言っているかのようです。
ところで、『春夏秋冬そして春』は、一人の人間の人生を、季節の移り変わりに重ね合わせて描かれていますが、その主人公は4人の俳優によって演じられています。一般的に考えれば、限られた撮影期間に幼い子供が壮年へと成長することなどありえませんから、例えばフランソワ・トリュフォーにおけるアントワーヌ・ドワネルという人物のようにその成長を数十年かけて追い続けるのでなければ、幼年期・思春期・青年期・壮年期を一人が演じることなど不可能です。にもかかわらずこの点に注目してみた場合、四季それぞれが別々の表情を持ち、春→夏→秋→冬→春と永遠に繰り返していくという自然の摂理と、その春夏秋冬に別々の俳優を使うこと、もしくは次の(本作においては最後の)春を冒頭と同じ子供が繰り返し演じているということが一致しているという事実は、やはり見逃すべきではないでしょう。だから、私にとっては、一人の人物を4人で演じていることに違和感はなかったということを、付け加えておきたいと思います。
始まりも終わりも無く繰り返していく円運動的イメージ……仏教における輪廻や、永劫回帰というニーチェ的思想をここで想起することは、さして難しくないしむしろ自然なことかもしれません。しかし私はここに、キム・ギドク自身を含むあらゆる(現実の)人生の反映を読み取りたいと思います。というのも、私がキム・ギドクに抱いてきたイメージは、消して宗教的・思想的なそれではなく、いつも現実的痛みだったからです。
意識的にせよ無意識的にせよ、誰もが罪を犯す。ある年齢で罪の意識に気付いたとしても、一時の気の緩みや狂おしい程の激情から、罪を重ねてしまうこともある。その時人は何らかの罰を受けるでしょう。そして反省し心を改める。人生とは死ぬまでその繰り替えしではないでしょうか。罪の大小や贖罪意識の大小は問題ではありません。結局人間の生は、そのようにしか成り立たないという考えと、そんな中で何を選択し何と闘い、そして何を得ていくのかということに対するキム・ギドクの優しい視線が、『春夏秋冬そして春』を創りあげているのです。
そう考えると、本作と前2作は、やはり本質的には変らないことに気付きます。3作観た上で、彼の作家としての揺るぎなさを実感しました。最後に付け加えれば、『春夏秋冬そして春』では、キム・ギドクの驚くべき想像力が随所で炸裂していますので、それらを是非観落とさないようにしていただきたいと思います。
2004年11月09日
cinamabourg* Ver.4
というわけで、またまたマイナーチェンジしました。今回はメニュー部分に少々手を加えつつ、“category”を細分化して、ついでにdvdやvideoで鑑賞した作品にも直接飛べるようにしました。TOPページには今後、比較的新しい作品(現在公開中の作品や直近に観たdvdなど)へのリンクに絞り、過去の作品評については“〜and more〜”というリンクをクリックしていただければ、一覧をご覧いただけます。
私も日頃から他のblogを見たりするのですが、アーカイヴとかblog内検索とかを利用することがほとんどないんです。で、それはこのサイトに訪れる人も同じようです。私のサイトは、映画評がメインですから、各作品評へなるべく少ないアクションで飛べるほうがいいのだろうと思った次第。ユーザーにしてみれば、劇場鑑賞作品とdvd等で観た作品が区別されていようといまいと関係ないのかもしれません。タイトルを見れば、現在公開中か過去の作品かはすぐに判断できるわけですし。その辺ももう少し考えてみます。
ただし、映画評メインのblogと言っても、“悲喜劇的”な日常を綴ることもありますし、映画以外の興味について書く事もあるでしょうから、その辺を以前より細かく分類したcategoryでカバーできればと。
さて、未だ書き上げていないテクストが2つほどありますから週末までに何とか書き上げ、土日は『オールド・ボーイ』『変身』『SAW』あたりを観にいければいいなぁと思っています。観ることと書く事が同ペースで進行していくのが理想ですから。
2004年11月08日
人は瞬間的に多くの物事を考えられるということ
 月曜日に先週の出来事をつらつらと書くというのも、何だかナァと我ながら思うのですが、今日は映画以外の話を。
月曜日に先週の出来事をつらつらと書くというのも、何だかナァと我ながら思うのですが、今日は映画以外の話を。
実は、というほどのものでもありませんが、先週木曜日から昨日まで、私はことごとく酒びたりでした。おかげでTSUTAYAが半額だというのにヴィデオも借りず、手持ちの金の大半は酒に消えていったのです。そんな中、土曜日は大学時代の悪友の結婚式の2次会がありまして、本来であればまぁパァーと酒を飲んで大いに騒ぐところなのですが、何とも途方に暮れてしまったという話。
2次会会場は白金のブルーポイント。自転車ならそれほど遠くないだろうという自信が不幸にも打ち砕かれ、地図も見ずに家を飛び出したのですからそれも当然と言えましょうが、気づいたら学芸大前辺りをふらふらと蛇行している始末。もうとっくに会は始まっているし、乗っている自転車はもらい物のママチャリなのでギアなどは無いし、何でこう坂道が多いんだろうという理不尽な憤りは沸いてくるし、その上2次会とはいえ一応ベルベッドスーツなど着ていたので暑いこと極まりないしで、ジャケットを脱いで黒いシャツのボタンを3つほど空け、ベルベッドのパンツを履いて目黒通りをママチャリで疾走する姿はかなり滑稽だな、などと思っている内に何とか会場までたどり着いたのですが、本当に困ってしまったのはここから。汗だくで会場に入るや否や、そうだった、ここには新郎以外誰一人知っている人間が居なかったのだと思い当たり、恐らく新郎新婦の仕事関係の友人やら学生時代の友人やらでごった返す会場の席という席はすでに埋まり、誰も知り合いの居ない汗だくの私は入り口付近でいかにも居心地悪く立ち尽くすほかなかったのです。程なく新郎が現われ、何とか一言声をかけたのですが、あまり酒の強くない新郎は完全に泥酔状態、本当に私のことを認識しているのかどうかも疑わしく、もうこれで頼みの綱が無いに等しい私は、とりあえず飲めという心の声に従ってワインをがぶ飲みするも、自身のあまりの孤独さと、それに反した周りの楽しげな雰囲気に完全に敗北し、結局わずが40分程で会場を後にしました。その間完全に無言だったので酔うことすら儘ならず、これからまた自転車で帰らなければならないことを思うと、なんで電車にしなかったんだ!と激しく自分を呪い、大きなため息と共に諦めの境地に辿りついて自転車をこぎ始めて数分後、何故か大崎駅前を何も考えずに颯爽と通り過ぎている自分に気づいたのが23:00頃でしょうか。何で今大崎にいるのだろう、もはや目黒区ですらないじゃないか…そう思って来た道をまたもや汗だくで戻っていると、そんな時に限って前方から警察官と思しき男性が私に近づいて来たので、
“いかん、このままでは「ちょっと自転車見せてもらえる?」などと声を掛けられてしまう、この自転車は紛れもなく自分の物ではあるが、厳密に言えばもらい物で、盗難シールを調べられたところでまず心配はないだろうが、名義が違っているからそれをいちいち説明するのも面倒だし、加えて、ネオレアリズモ映画『自転車泥棒』に触発されて自転車泥棒になったことがある恥ずべき過去の記憶が瞬時に甦ってきて、泥棒したわけでもないのに自分の立場の危うさだけが妙な現実感を持って迫ってきたので、よし、ここは先手必勝だ”
と瞬間的に判断し、「すいませ〜ん」と自ら警察官に近づき、「目黒区大橋にはどうやって行けばいいんすかね?」などととぼけた振りしてババンバンいう感じで善良な市民を装いつつ道を尋ねたわけです。その警察官は職業的義務感をその表情に漂わせつつおもむろに帽子を脱ぐと、その中に隠されている周辺地図を取り出し、警察官らしからぬたどたどしさで私に道を教えてくれようとしていましたが、私はというと、すでに結構冷静になっていたので帰り道の見当はついていたし、何より、帽子に隠されていた地図を出すしぐさが何故か“映画的”だったためそのしぐさだけが何度もリフレインされ、警察官の説明などほとんど耳に入らなかったのですが。まぁ結果的に泥棒とはみなされずに済みましたし、実際のところ私は泥棒ではないのですからそんなことは当たり前ですが、そこから約20分程で自宅までたどり着くことが出来たわけですから、めでたしめでたしでした。
帰宅後、多分今頃はトイレで胃の内容物を全て戻しているであろう新郎に、ほとんど恨み言めいたメールを送信したのは、言うまでもありません。
2004年11月07日
『カンフーハッスル』、アナログなギャグとデジタルなアクション
今現在、観客を爆笑させることが出来る監督というと、真っ先にチャウ・シンチーという名前が思い出されます。とはいっても、実はチャウ・シンチーについて、私はほとんど知りません。しかし、前作『少林サッカー』には、彼を良く知らない私にそう思わせる程に荒唐無稽で出鱈目で、愚直ともいえる“笑い”が渦巻いていたのです。
『少林サッカー』と『カンフーハッスル』を観て思うのは、そのキャラクター造形の上手さです。絵画における“デペイズマン”的手法といいますか、そこに相応しからぬ事物をあえて配置することで齎される効果が、チャウシンチーの特異なキャラクター性を生み出しているような気がするのです。アクション(カンフー)映画のヒーローとは無縁の禿げかかった中年や、ただ重いだけの肥満体が、画面を縦横無尽に飛び回り、常識はずれのアクションをしてみせる。まずはキャラクターで笑わせるという、いわば漫画的な手法です。そして恐らく、その漫画的な部分を徹底的に押し進めた結果、紛れも無い香港映画の輝きを見せるに至ったのではないかと。
『カンフーハッスル』(原題は『功夫』)というタイトルですが、本作は所謂往年のカンフー映画からは相当逸脱しています。生身の肉体がぶつかり合うシーンよりも、VFXやワイヤーによるアクションシーンのほうが圧倒的に多いからです。もちろん、昨今のアクション映画がそういったテクノロジーの呪縛から逃れることが困難なことも承知していますが、それは同時に、チャウ・シンチーが作り上げるキャラクター性とも切り離せない問題でもあるのです。“いかにも強そう”な人間など、彼の映画には必要とされていません。恐らく現実的にもカンフーアクションとは無縁であるような人物を主要なキャラクターにするわけですから、彼らにはブルース・リーやジャッキー・チェン、ジェット・リーのような芸当は端から求めるべくもありません。よって、VFXによってその“強さ”を生み出すほかないわけです。それはつまり、カットを細かく割ることであり、クローズアップやスローモーションを多用せざるを得ないという、技術的側面にまで影響してくるでしょう。『少林サッカー』において、普通にサッカーしているシーンなどほとんどなかったという事実も、そのように説明できるのではないでしょうか。
ただし、私はそれを非難するつもりなど毛頭ありません。前述したことが事実だとしても、チャウ・シンチー作品の面白さはいささかも減退しないのですから。
ただし、だからといって『カンフーハッスル』を手放しで絶賛できるかというと、そうとも言えません。今更カンフー映画における図々しい御都合主義や脚本の甘さなどを指摘しても始まりませんからそれには目を瞑るとして、私が指摘したいのは、『カンフーハッスル』における一部の映像のうんざりするほどの既視感です。『少林サッカー』に比べると、より多くのVFXを使用している本作おける、クライマックスのアクションシーンの常軌を逸した退屈さが非常に残念でいた。この映画の宣伝からして「ありえねー」などと謳っているわけですが、すでに『マトリックス・リローデット』という駄作を観ている私としては、今更VFXによる「ありえねー」アクションに驚きもしないし、武術指導にユエン・ウーピンを起用しているのでしょうがないかもしれませんが、やはり、何十人もの黒服たちがいっせいに中に舞うシーンだとか、人間の重量(つまりそれは“痛み”にも繋がるのですが)を感じさせないアクションには、もういい加減辟易しています。『マッハ!!!!!!!!』の素晴らしさが、その痛みを感じさせるアクションにあったことを思い出すと、このクライマックスにはどうしても乗り切れなかったのです。
ブルース・リーへのあからさまな目配せが、『KILLBILL』とは違った形で表されている部分などは悪くないし、普段は温厚なクリーニング屋だったり、全権力を握る恐妻にまったく逆らうことが出来ない弱弱しい夫だったりが、カンフーの達人としてその能力を発揮する場面の落差などには大いに笑いもしましたが、チャウ・シンチーが出てくる場面シーンが少なすぎたということに加え、本来最も見せるべきであった、彼の隠れた才能が炸裂するシーンへの伏線があまりに稚拙だったことなど、不満な点も指摘しておかなければならないでしょう。何だか言及するつもりがなかった脚本のまずさを小出しにしてきているので、このあたりで悪口はやめて起きますが。
『カンフーハッスル』は、いくつかの点を除けば、やはり面白い作品であることは間違いないと思います。純粋な意味での“ギャグ”にひたすら笑い転げることも出来るでしょう。あくまで伝統的なギャグとVFXを駆使したアクション。今、世界でもこんな映画を作れる作家は、香港にしかいないのかもしれませんから。
2004年11月04日
『悪い男』、キム・ギドクこそ文化の日に相応しかったと孤独に肯く
というわけで、文化の日は朝一で『春夏秋冬そして春』をル・シネマにて。その後、東京都写真美術館で開催中のマリオ・テスティーノ展を個人的事情で断念し、封切りで見逃した『悪い男』を鑑賞しました。祝日のbunkamuraは、朝から結構な人だかりで、1時間前に整理券をもらった私で28番。客層はバラバラでしたが、比較的年配層が多かった気がします。ほぼ満席。『春夏秋冬そして春』については別途作品評を書きますので、ここでは『悪い男』に関してニ言三言。
本作の主人公もまた、ほとんど言葉を発することがありません。しかしそんな男でも社会に暮らす人間であれば、どのような形であれコミュニケーションというものが不可欠です。さて、ヤクザな主人公を演じるチョ・ジェヒョンは、ではいかなる手段で意志を疎通させるのか。それは睨みつけること、暴力を振るうこと、そして煙草をさしだすことによってです。そして、それらの行為一つ一つが、物語のバネをギリギリと巻いていくことになります。
冒頭、人ごみにその黒い姿を現したチョ・ジェヒョンは、偶然見かけた女子大生ソ・ウォンの唇を暴力的に奪い、駆けつけた軍人らによって、暴力的に動きを奪われます。暴力を暴力で返され、なんとなく安心しているかのようなチョ・ジェヒョンが睨みつけるソ・ウォンには、それがまさか、愛を物語っているなどとは到底思えない。よって男は屈辱的に唾を吐きかけられる。
さて、この一連のシークエンスだけを観ると、その理不尽さのみが観客に植え付けられることになります。いや、チョ・ジェヒョン演じるヤクザは、常識的見地から見れば、最後まで理不尽極まりないのです。
ところで、『悪い男』に描かれた愛は、俗っぽい言葉で言えば“歪んだ愛”ということになるでしょうか。しかし、ここで勘違いしてならないこと、それは、歪んでいるように見えるのはヤクザであるチョ・ジェヒョンの行為(つまりコミュニケーションの方法)そのものであって、決して愛そのものではないということです。あまりに直線的なその想い故に暴力が先んじてしまうというのは、悲劇とも言い得る。悲しい男、チョ・ジェヒョンは、その悲しさを観念でなく、暴力(直接的な痛み)によって表現しているのです。前作『魚と寝る女』同様な印象を持ったのも、そういった共通点に拠ります。
“痛み”のない“理解”などありえない、キム・ギドクはそう確信しているのです。
興味深かったのは、刑務所に入れられたチョ・ジェヒョンを、彼の子分が尋ねていく場面。彼はチョ・ジェヒョンに対し、これまで様々な映画で描かれてきたように煙草を差し出すのですが、彼らの間にあるプラスティックの壁に空いた小さな穴から煙草を渡すというより、その穴の途中で火をつけ、チョ・ジェヒョンに吸わせてやるのです。火のついた煙草を渡して初めて煙草がコミュニケーションの手段となる。それは、やはりその子分の盗撮行為が発覚した際、実は病身の親のために金が必要だったと理解したチョ・ジェヒョンが、出て行った彼を追いかけ、そっと火のついた煙草を差し出す場面にも現われているのです。
『悪い男』を観た人間に求められる態度は、“女をバカにしてる!”とか“女性蔑視で不快だわ!”などでないことは、もはや明確でしょう。未だ自らの固定観念に囚われつつ、自身の持つ恥ずべき官僚性に気づくことの無い人間には間違ってもわからないであろう、この映画の持つ狂暴な優しさ。
ソ・ウォンによって切り取られたエゴン・シーレの絵が「抱擁」というタイトルだったことにを知り、私の思いは確信へと変わりました。
2004年11月02日
『魚と寝る女』、心無い現実
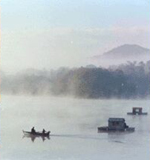 最新作『春夏秋冬そして春』が公開中のキム・ギドク監督の第4作目。今年のヴェネチアでも銀熊賞を獲得し、今、最も注目すべき映画作家であることは間違いなかろうと思います。「韓流」も結構ですが、韓国はそれほど底が浅い国ではないという事実を、キム・ギドクは“暴力的に”思い知らせてくれます。
最新作『春夏秋冬そして春』が公開中のキム・ギドク監督の第4作目。今年のヴェネチアでも銀熊賞を獲得し、今、最も注目すべき映画作家であることは間違いなかろうと思います。「韓流」も結構ですが、韓国はそれほど底が浅い国ではないという事実を、キム・ギドクは“暴力的に”思い知らせてくれます。
原題は『The Isle』。“(ある特定の)小島”ということでしょうか。この原題が何故『魚と寝る女』と改題されたのかは、ここでは問わずにおきます。その小島がいったい何を指すのか、それさえ示せば充分だろうと。タイトルが示す“ある小島”とは、恐らく、黄色い釣り小屋のことだと考えて間違いないでしょう。
冒頭から幾度となく繰り返される、ほとんど水墨画のように暗く美しい景色。湖上に点在する、一見島のように見える釣り小屋。しかしこの釣り小屋といわゆる島の決定的な違いは、それが移動するということです。水底に沈んでいる錨さえ引き上げてしまえば。移動する島。果たしてその島はどこへと向かうのか。そんな疑問を宙刷りにしたまま、この映画は終わるのです。
謎めいた湖に何かを沈めること。その逆に何かを引き上げること。あるいは、自らその湖へと沈んでいくこと。『魚と寝る女』には、これら垂直の運動に加え、湖面を緩やかに滑っていくひなびたボートの水平移動が度々挿入されます。そして、この二つの運動の、その緩やかさに反した途轍もない凶暴性が男女の(文字通り)悲痛な関係性を際立たせつつ、そのまま『魚と寝る女』を言い表しているではないかと思いました。
多くを語らない男と全く話すことのない女。言葉を必要としないという意味で、非人間的とも言える彼らは、“痛み”を通してしか、他者とのつながりを確認し得ない。“痛み”こそ生の条件だと宣言するかのような彼らに、もはや一般的な常識は通用しません。二度にわたって繰りかえされるあの釣り針での自傷シーンに観るものが耐えられないのは、その“痛み”が伝わるからではなく、その行為が自分の常識から完全に逸脱していることに対する恐怖からではないでしょうか。その恐ろしさを言葉で表現することの不可能性を知っているキム・ギドクは、あのようなショッキングなイメージによりそれを脳裏に焼き付けることを選んだのだと思います。
黄色い釣り小屋を遠景で捉え、そこで起こりつつある強姦場面にあくまで冷たい視線を向けるカメラは、時に水中にもぐり、そうかと思えば唐突に宙に浮いて、人間の行為を見下ろしたりします。極めて冷静な空間設計とそれがもたらす心無さ。静寂さと激しさが、その心無さを媒介に等号で結ばれてしまうような演出。それはもちろんキム・ギドク自身の心無さではなく、現実世界の心無さなのです。それが見事に表されているラストシーンを観て、これまでキム・ギドクの作品を観ていなかった自分を深く恥じ、同時にその恐るべき才能に背筋が凍る思いだったと告白します。
2004年11月01日
『ターネーション』、または東京国際映画祭を終えて
 31日をもって閉幕した東京国際映画祭2004。私はコンペティション部門を一作も観ていないのですが、ウルグアイを舞台にした『ウイスキー』という作品が東京グランプリとだった模様。主演女優賞も、この作品から選ばれたようです。で、黒澤明賞が、スピルバーグと山田洋次ですか……そもそも黒澤明賞っていうのはどうなんでしょうね…まぁどうでもいいです。
31日をもって閉幕した東京国際映画祭2004。私はコンペティション部門を一作も観ていないのですが、ウルグアイを舞台にした『ウイスキー』という作品が東京グランプリとだった模様。主演女優賞も、この作品から選ばれたようです。で、黒澤明賞が、スピルバーグと山田洋次ですか……そもそも黒澤明賞っていうのはどうなんでしょうね…まぁどうでもいいです。
2chなどを観てみると、チケットが取れないにもかかわらず空席が目立ったとか、何であいつがあの賞なんだとか、そんな否定的意見が多いような気もします。まぁ少なくとも私が観た作品は両方とも特別招待作品ですし、爆発するほどのストレスは感じませんでしたが。一つだけ気になるのは、今回コンペティションやアジアの風に出品された作品のうち、正式に日本で公開されるものがどのくらいあるのかということでしょうか。
さて、私が観た『ターネーション』とう怪作について。実は、別途作品評を書こうか迷いましたが、あの映画は一度観ただけでは容易に語れない気がしたのです。
最も特筆すべきは、この映画が218ドル32セントで撮られたということ。しかし、完成には20年近くを要しているのです。私はimacとimovieだけで編集された映画など恐らく初めてみました。確かに現在は、こうした機材さえあれば誰でも映画が撮れます。しかし、『ターネーション』が、安易な発想から生まれた映画でないことは明らかです。監督であるジョナサン・カウエットは、映画によって死を退けてきた人間だからです。映画を撮ることだけが、死以外の唯一の選択肢だったと言うべきかもしれません。そんな作品ですから、この映画を観るには、それなりの覚悟が必要だと思います。“監督の痛み=画面が発する痛み”を体全体で受け止めることが出来るかどうか…そんな覚悟が。
監督自身は、ハーモニー・コリンの映画を観て自らの可能性に気づいたようです。しかし、単なるオルタナティヴとして『ターネーション』を捉えてしまうことだけは避けねばならないと思います。そこには何か、もっと途方も無い可能性が秘められているようでなりません。次はどんな作品を生み出すのか、ひとまずそれが日本でも公開されることを願いつつ、ジョナサン・カウエットという名前は絶対に記憶しておかなければと、深く決意した次第です。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]



