2005年05月29日
cinemabourg*1周年
今日で当サイトも一周年を迎えました。書いたエントリーはこれで204本。これが多いのか少ないのかは分かりませんが、ブログの運営は、確実に私の生活を変えたということだけは言えるでしょう。そして月並みですが、1年などあっという間でした。
開設してから最初の2ヶ月くらいは普通のhtmlで作成していたのですが、ブログというツールとの出会いはことのほか大きく、ここまで続けられたのもまさに、ブログに移行したからです。映画とこのブログを通じて何人かの友人たちと知り合えたことも、望外の喜び記憶として今後もされるでしょう。改めて、日ごろcinemabourg*をご覧いただいているかたに、感謝いたします。
さて、現在水面下でリニューアル作業を薦めていますが、昨日、ちょっとしたトラブルがありました。すでにお気づきのかたもいらっしゃるかと思いますが、昨日の0:00から数時間、当ブログの閲覧が出来ませんでした。これは所謂「レジストリ・ロック」というやつでしょうか。簡単に言えば、「cinemabourg.com」というドメインの有効期限が27日いっぱいで切れ、本来であれば26日までに向こう一年分の更新料を支払っていなければならなかったのを、そのまま放っておいた結果、強制的にドメインが凍結されたというわけです。なにやら英語だけの、見た瞬間「ああ……」と溜息が漏れるようなナンセンスな画面がそこにはあり、見た瞬間はウィルスの可能性を疑ったりもしたのですが、よくよく考えたら、何のことは無い、ただの支払い忘れだったというオチです。
発見後すぐに支払いましたが復旧までに48時間程度必要とのことで、やや途方に暮れた私は、そのままmixiへと。初のmixi日記などしたためてみました。たまにはこれも新鮮だなぁと、そちらでの友人たちとのやり取りを半ば楽しみにしていたのですが、結局はものの30分で凍結が解除される始末。何が48時間だ! と朝から声を荒げました。まさに誰も見ていない一人芝居、久々に恥ずかしさの局地でした。
そんなこんなで迎えた1周年に観るべき映画として、ほとんど申し合わせたかのように昨日は『ミリオンダラー・ベイビー』の公開初日。これを観なければ何が1周年か、という強い意思のもと渋谷ピカデリーにて鑑賞。予想をはるかに超えるショックを受け、茫然自失のままフラフラと帰宅。詳述は後日に譲るとして、一言だけ感想を述べれば15ラウンドKO負けといった感じ。これほどの疲労感と絶望と感動を同時に味わったのはいつのことだったか容易に思い出せず、確かなことは『ミリオンダラー・ベイビー』には容赦ない凄みがあったということです。本作については、後2〜3回観た上で、改めて考えてみたいと思います。
今日から始まる2年目は、より多くの更新をしていければと思っています。このブログがいくらかでも生産的な場にならんことを切に願いつつ…
2005.5.29
[M]
2005年05月25日
『インファナル・アフェア』三部作(前編)〜香港映画を振り返ってみる
 先ず最初に断っておかなければならないのは、今の私に『インファナル・アフェア』三部作に関する文章を書くことが出来ないということです。
先ず最初に断っておかなければならないのは、今の私に『インファナル・アフェア』三部作に関する文章を書くことが出来ないということです。
1作目を劇場で観たのが2003年だったでしょうか。その時点で、確かに手ごたえはありました。言葉での説明より、とにかく早い展開で人物の関係性を強引に理解させる示す技法は、端的に“巧い”と思いました。しかし、若干の違和感を感じたのです。何かが違う、と…語りの経済性とでも言いましょうか、私はそこにアメリカ映画的な何かを感じました。いや、そういって悪ければ、少なくとも、私がそれまで感じていたような“香港映画的なもの”をあまり感じなかったということです。まぁとりあえず話を進めます。
『インファナル・アフェア』の冒頭、2人のスパイがそれぞれの身分を固めていく過程は的確で、エリック・ツァンがボスを演じるのマフィア側とタイ人との取引現場を押さえようとするアンソニー・ウォン率いる警察側との心理戦を、それに2人のスパイを加えた計4人のクローズアップを要所要所に配置しながら、それが双方にとって痛みわけで終わるまで一瞬の弛緩もなく緊張感を持続させる演出にも関心しました。さらに、本作は一応犯罪映画という体裁をとっているものの、最終的には2人の主役それぞれの自己同一性を巡る人間ドラマとして充分“魅せる”つくりであったようにも思え、例えば同じスパイもの繋がりで言えば、その前年あたりに観た『SPY_N』という、ほとんどこちらを塞ぎこませるような作品とは比べものにならないほど面白かったと言えます。要するに、私は『インファナル・アフェア』をかなり評価していたのです。
がしかし、もともと私には、一部の例外を除けば(そこにどのような基準があるのかは自分でもわかりません)香港映画の続編を観るという習慣がなく、何故だか2作目を鑑賞することはありませんでした。しかし2作目の評判も上々らしく、今年ついに完結するという情報を得ていくうちに、観なければ後悔するだろうという危機感が沸いてきて、あわててdvdにて2作目を鑑賞、そして、つい先日完結編を観るに至ったというわけです。
それでは何故書けないのかというと、これは単純にそれぞれ1回しか観ていない上に、1作目を観てから随分と時間が経ってしまったからです。すでに、雑誌やインターネットで多くの批評や感想等を読みましたが、概ね好意的な印象はそれらと大差ないものの、では、この三部作の何が決定的でそのような評価に至ったのか、実は未だにわからずにいます。もちろん、三部作を連続してもう一度観られればそれは自ずとわかるのかもしれませんが、残念ながら今はその機会がありません。
ただし、嘗て熱狂した香港映画から遠ざかっていた私が、もう一度香港映画を再評価するきっかけとなった『少林サッカー』と同じく、この三部作も、“香港ノワール”とここでは一応読んでおきますが、そのジャンルにおけるエポックであったことはどうやら間違い無いのではないかと思ってはいます。
とは言ってみたものの非常に致命的なのは、私が“香港ノワール”を実はそれほど観ていないということです。いきなり袋小路に迷い込みましたが、とりあえず、ここで私の香港映画史をざっと書きなぐりつつ、そこから何かが見えて気はしまいかと微かに期待してみましょう。
小学生時代、ブルース・リーからジャッキーチェン(及びその周辺)へと受け継がれる、エンターテインメントとしてのクンフーアクションで映画に目覚めた私は、ジャッキー・チェンが幾度かの失敗を経て、本格的にアメリカに進出し始めた時期を境に、90年代に到るまで香港映画から遠く離れていました。その後ヨーロッパ映画やアメリカ映画をはじめ、より広大な“世界”を発見していく過程において、それらがあまりに稚拙な印象を齎し始めたという相対的な要因に拠るのですが、やはり当時、70年代後半〜80年代にかけてのいくつかの作品に私が感じ取ってきた、香港映画の絶対的な魅力が明らかに減退したように感じられてしまったということもあるのでしょう。ただしここで言う“香港映画の絶対的な魅力”とやらは多分に曖昧かつ偏向的なものに過ぎず、その意味で当時の私は、香港映画のある一形態しか見ていなかったことも指摘できるでしょう。
ちょうど90年代前半に、ジョン・ウーに出会います。『男たちの挽歌』は1986年の作品ですが、実際に彼を発見したのはもう少し後になってからです。恐らくこの辺りから“香港ノワール”という言葉が使われ始めたのではないかと思うのですが、『男たちの挽歌』はそれほどまでの衝撃度を持ちえていたということでしょうか。アメリカ進出後のジョン・ウーを、私は特に評価していませんが、『男たちの挽歌』に関してはそれなりに感動したことを覚えています。二丁拳銃と踊るように死んでいく男たちとスローモーション。これらを“スタイリッシュ”だと、今は思いません。その代わり私は、これらを“出鱈目さの美学”と位置づけることで評価しています。
90年代に入り、ウォン・カーウァイの登場に直面した辺りから、次第に香港映画に対する考え方が変化してくるのですが、それまでの香港映画とはあまりにかけ離れたウォン・カーウァイの作品は、その洗練されたスタイル故か、その作品を香港映画として認識することにいささか抵抗があったのもまた事実です。よって私の中でのウォン・カーウァイ作品はむしろ、国籍を超えたところで評価したのであって、やはり“香港映画が復活した”とは到底思えませんでした。
しかしそんな中、90年代から徐々に頭角を現して来たチャウ・シンチーがあの『少林サッカー』を完成させた意味は大きかったといえるでしょう。香港映画史上最高の興行収入を記録した本作は、私の幼少時代の記憶を呼び覚ます程の傑作でした。何よりあまりに出鱈目な御都合主義的展開は私を大いに感動させ、やっと香港映画復活の兆しを見ることが出来たのです。
さて、駆け足で私の中の香港映画史を振り返ってみましたが、そこからわかったことがあるとすれば、香港映画は出鱈目だったということででしょうか。もちろんここで言う“出鱈目”とは、最大の褒め言葉として使っています。つまり、脚本の精巧さ、編集がもたらすリズム、ショットの強度などがそこに無くても、出鱈目さゆえに輝いていたと、かなり強引ながらそう言いたいのです。いきおい、『インファナル・アフェア』の上映に立ち会った時も、そのような思考で臨んだと言えるでしょう。だとすれば、もし『インファナル・アフェア』が出鱈目さの魅力に溢れていた場合の結論は容易に出せたと思います。しかし、恐らくそうではなかったのでしょう。故に、私の思考は混沌の只中へと陥るほかなかったのです。
(後編に続く)
2005年05月23日
週末は閉塞。カンヌは閉幕。
 自転車を盗まれて以来、出かけることが億劫になりつつある[M]です。そんなわけで、先週末は観た映画は『デカローグ 3話・4話』の2本のみです。昨日などは、あまりにダラダラ過ごしてしまいまして、一日無駄にしたナァと反省。今週末にでも自転車を購入し、週末こそ精力的に出かけるべきだと決意を新たにしました。
自転車を盗まれて以来、出かけることが億劫になりつつある[M]です。そんなわけで、先週末は観た映画は『デカローグ 3話・4話』の2本のみです。昨日などは、あまりにダラダラ過ごしてしまいまして、一日無駄にしたナァと反省。今週末にでも自転車を購入し、週末こそ精力的に出かけるべきだと決意を新たにしました。
さてその『デカローグ』ですが、新マスター・改訳字幕のデジタル修正版での上映でした。確かに画面上にノイズは見られなかったと思います。久々に観たキェシロフスキはやはり面白い。60分に満たない中篇にもかかわらず、なんとも味わい深いドラマです。これは自宅で酒でも飲みながらぶっ通しで観続けるのもいいなと思い、TSUTAYAに行ってみると、案の定全てレンタル中でした。同じように考えている人間はいるものです。しかたがないので、未見だった『アマチュア』『偶然』を借りました。これは今週中に観たいと思います。
ところでカンヌが幕を閉じました。パルムドールはダルデンヌ兄弟の『L'ENFANT』です。まぁ順当と言えば順当な、面白みに欠ける結果ではありますが、作品には非常に興味があります。審査委員長のクストリッツァは、何としてもヨーロッパ作品をパルムドールにしたかったのではないでしょうか。グランプリはジャームッシュの『BROKEN FLOWERS』。ジャームッシュは『COFFEE AND CIGARETTES』が短編部門でパルムドールを獲って以来12年ぶりのグランプリ獲得になります。主演男優賞はトミー・リー・ジョーンズです。今回は監督も兼ねた『THE THREE BURIALS OF MELQUIADES ESTRADA』というでの受賞です。ちなみに本作は脚本賞も獲得しています。彼は日本でも人気があるのでしょうから、その公開を楽しみにしたいと思います。
受賞結果の詳細についてはこちら
今週はいよいよ『ミリオンダラー・ベイビー』の公開です。その前に溜め込んだレビューを何とかしたいのですが……がんばっていきまっしょい。
2005年05月20日
都心ノ部屋ニテ泥酔シタルコト
昨日は新しく加わったアルバイトの歓迎会があり、飯田橋の中華料理店に行ったまではよかったのですが、その後、同僚を引き連れて飲みなおした挙げ句、最後には自宅で泥酔するという体たらく。朝目覚めてみると同僚の姿は無く、ついでに私の記憶も無く、さらに言えば何故か自転車も無いというNAINAI尽くし。毎度のことでもう慣れてしまったとはいえ、やはり少しは凹んだりするのです。
それにしてもそんなボロボロの状態でも思わず笑ってしまったのは、部屋のカフェテーブルの上に、飲みかけの白ワインの隣で鳥の唐揚げがものすごい存在感を放っているのを発見したからで、「何故こんなに唐揚げがあるんだ?」と記憶を辿ってみても一向に思い出せず、ただただほとんど山積みにされた唐揚げを前に呆気に取られて笑うしかなかったのです。パックに入った唐揚げでは足りなかったのか、コンビニで売っている“唐揚げ棒”も2本購入していて、そうまでして食べたかったはずの唐揚げなのに結局は2つしか食べておらず、朝から冷え切った唐揚げのたちの冷ややかな目線を感じざるを得ませんでした。
ところで無くなった自転車についてですが、これについては流石に少しだけ記憶が残っています。いつもどおり渋谷駅前に停めていたわけですが、昨日の夜同僚を引き連れてその場所に向かうと、あるはずの場所にないのです。つまり盗まれたということで、仕方ないからとぼとぼと歩いて自宅に向かったのでした。まぁそれについてはもうどうしようもないと思い諦めもつきますが、問題は、今朝になってマンションの駐輪場を通りかかるまでその事実を完全に忘れていたことにあり、「あれ? 自転車が無いぞ…」と一瞬真剣に考え込んでしまったことにあるのです。ここまでアルツな脳で、私は大丈夫なのでしょうか。
遅刻して会社に来てみると、同僚がやけにニヤニヤしていたのですが、私の泥酔っぷりはそれほど可笑しいようです。一度客観的に見てみたい気もしますが、見たら見たで死にたくなるやも……
『バッド・エデュケーション』、アルモドバルとアブノーマル
原題:LA MALA EDUCACION
上映時間:105分
監督:ペドロ・アルモドバル
デビュー当時、ペドロ・アルモドバルに“アブノーマルな作家性”を感じ取った人々が、ここ何作でそれが微妙に薄められてしまったという見解を目にしますが、それは本当でしょうか。いや、私自身、それを否定することは出来ないのですが、彼はそもそも、本当に“アブノーマル”だったのか。
かつて、澁澤龍彦が「スクリーンの夢魔」という著作の中でルイス・ブニュエルの『昼顔』に対し「やんぬるかな、ブニュエル神話くずれたり」というような感想を記していました。澁澤は『昼顔』を観て、彼の“永遠のスキャンダリスト、暴力と反抗の不屈のシネアスト”という作家性が年齢と共に衰えてしまったのではないかと言います。実はこれに対する結論も未だに出せずにいる私ですが、特にアブノーマルではない『バッド・エデュケーション』を観て思うのは、澁澤がブニュエルに対して抱いた思いの正当性を、今こそ検証してみなければならないということです。
アルモドバルは、本作で自分の歴史を描いたと言われています。そこには重要なヒントが隠されていると思うのですが、やはり、彼の初期作品を観直した上で、再度考えてみなければならないと思います。それでも今、本作に関して一つだけ言うとすれば、アルモドバルの美的センスは好みであるということだけです。
アルモドバルは本当にアブノーマルだったのでしょうか?
2005年05月17日
『コースト・ガード』、あるいは不定形の世界
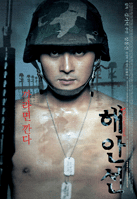 本作を観終えた後、昨年書いた『春夏秋冬そして春』の文章を読み返してみたのですが、今、当時の思いを若干修正しなければならないと思っています。その文章で私は、『春夏秋冬そして春』はそれまでのキム・ギドク作品といくつかの違い(最も顕著なのは超ロングショットの存在)はあるにせよ、やはり本質的には変わっていないと結論しました。ところで、基本的には自らの意思でコントロール不可能な何かを“本質”(キム・ギドクの場合は、現実的な“痛み”による意思疎通)と呼ぶのではないか、そう考えると、そもそも人間の本質など余程のことが無い限り変わるものではなく、この結論は少しも結論足りえていなかったことに気づくのです。だとすればやはり、『春夏秋冬そして春』はキム・ギドク前期作品とは異質な、転換的作品だったのかもしれません。少なくとも、世界に対する彼の視線の変化が、あのようなロングショットを生み出したのだと。ちなみにこの思いは、すでに『サマリア』を観てしまったことにも深く関係しているとのです。
本作を観終えた後、昨年書いた『春夏秋冬そして春』の文章を読み返してみたのですが、今、当時の思いを若干修正しなければならないと思っています。その文章で私は、『春夏秋冬そして春』はそれまでのキム・ギドク作品といくつかの違い(最も顕著なのは超ロングショットの存在)はあるにせよ、やはり本質的には変わっていないと結論しました。ところで、基本的には自らの意思でコントロール不可能な何かを“本質”(キム・ギドクの場合は、現実的な“痛み”による意思疎通)と呼ぶのではないか、そう考えると、そもそも人間の本質など余程のことが無い限り変わるものではなく、この結論は少しも結論足りえていなかったことに気づくのです。だとすればやはり、『春夏秋冬そして春』はキム・ギドク前期作品とは異質な、転換的作品だったのかもしれません。少なくとも、世界に対する彼の視線の変化が、あのようなロングショットを生み出したのだと。ちなみにこの思いは、すでに『サマリア』を観てしまったことにも深く関係しているとのです。
『コースト・ガード』は、『春夏秋冬そして春』の春の章を撮り終えた直後の2002年の初夏におよそ1ヶ月程で撮られました。前述を受けて考えてみれば、それまでに正式公開されていた2作品(『魚と寝る女』と『悪い男』)と『春夏秋冬そして春』にはある種の断層があり、『コースト・ガード』は間違いなく前者に属すべき作品です。ただし繰り返せば、やはり“本質”は変わっておらず、ある限定された場(そこは概ね、一般的な社会からはみ出した“現実ならざる世界”です)に蠢く権力者と弱者の淀んだ関係性や男と女の愛が、逆説的に現実世界を照射しているのです。自らの軍隊経験が少なからず反映されたと思しきこの『コースト・ガード』ですが、やはりというべきか、本作にもキム・ギドク的イメージの数々を容易に発見することが出来ます。それは水であり、ガラス(鏡)であり、あるいはそこにコミュニケーションとしての暴力やセックスです。
『コースト・ガード』には様々な対立的要素が溢れています。それらは恐らく、簡単に指摘できる程に分かり易い形で提示されていると言えるでしょう。AとBが対置する。そんなことが、この世界には当たり前のように存在しています。そして映画におけるドラマは時に、そのような対立的関係性の中から生れ落ちるのです。
例えば北と南。ここでいう北とはもちろん北朝鮮、南とは韓国を指しています。本作の主たる舞台は軍事境界線に近い、南側の海岸です。北からのスパイが一歩でも足を踏み入れた場合、それはスパイの死を意味します。そして本作の悲劇は、まさにこの場所で起こるのです。
主人公カン上等兵(チャン・ドンゴン)は、もともと一般的な社会生活を送っていた大学生です。徴兵制はある年齢から2年2ヶ月の間、彼を社会から引き離します。つまりその間は、一時的にでも社会通念を剥がされてしまうのです。軍隊という“社会ならざる場所”においては、殺人という行為の意味すら異なり、それが正常な人間を狂気へと駆り立てます。より残酷なのは、誰もが兵役を終えて社会へと戻ることが出来るわけではないということです。ここにも社会と軍隊という対立項を指摘することが出来るでしょう。
ところで、海兵隊は合法的に人を撃ち殺すことが出来るという意味において、民間人よりも強者だと言えます。だとすれば、弱者である民間人がとるべき行動はどのようなものか。本作でそれは、さらに弱い何か(水槽の中の魚)に対して束の間の強者となるか、あるいは強者である海兵隊を内側から骨抜きにするという形で描かれています。いずれにせよ本作において強者と弱者の間にあるのは、残酷な法則のみです。
さて、本作における登場人物に限らず、人間は2つの危うい均衡を保ちながら生きていると言えるのではないでしょうか。それらはすなわち、正気と狂気にほかなりません。しかし、自身の現実認識が正しいかどうかなど、実は誰にもわかりはしないという事実。例えば海兵隊員は銃を前に無力です。銃は、暴力的に撃つか撃たないかを迫ってくるからです。銃を手にした人間にとって、正気と狂気のバランスなど瞬時に崩壊するでしょう。もちろん、目の前で恋人を無残に殺された女性に精神の均衡など保てるべくもないのです。あるいはその事実を、現実と非=現実と置き換えることが出来るかもしれません。狂人にしか見えない事物があるとすれば、それを“非=現実”と呼ぶことが出来るかもしれませんが、狂人にとってそれは紛れも無い“現実”なのかもしれない。嘗て海兵隊の仲間だった人間が、今や敵となって軍隊に銃を向けている。しかし、誰もそれを現実だと確信できないのは、鬼と化したチャン・ドンゴンが銃を構える姿に“非=現実なフィルター”がかかり、現実に生きる人間(=観客)の眼を欺くからです。
さて、以上は本作を観た人であれば、いや、仮に本作を観ていなくても、一般認識として容易に指摘し得る対立的要素です。問題はしかし、『コースト・ガード』においてキム・ギドクが、そんな対立的要素など本当に存在するのかを疑っているということにあると思います。さらに言えば、本作でキム・ギドクが描いたのは、対立的要素の解消、というよりもその廃棄だったのではないか、と。我々人間は、いや、世界は、そのような分かり易い二極的対立項に回収されるべきものではないはずだ、と。実際、初期のキム・ギドク作品(『悪い男』や『魚と寝る女』)を観れば、何が“善”で何が“悪”かなど問題ではなかったことがわかります。そのような常識的見地を疑うことが、何よりもキム・ギドク的だったと思うのです。実際、本作で見出すことが出来たいくつかの対立的要素も、最終的にはその境界線が廃棄され、決して分かり易い図式には収まってくれないことが分かるでしょう。
海兵隊員たちが休憩時間にサッカーをするシーンが2シーンほど出てきます。サッカーと言ってもそれは一般に認識されているそれではなく、地面に描いた朝鮮半島をピッチに見立て、その半島に沿って配置された海兵隊員たちが、明確な敵・見方の区別などないままボールを蹴りあうというものです。その描かれた朝鮮半島に、南北境界線はありません。北だろうが南だろうが関係なく、ということはつまり、自分以外の全てが敵であり見方であるような空間において、その遊戯は行われるのです。
軍隊での任務を終え、社会へと帰還すべき人間であるチャン・ドンゴンがなぜまた軍隊へと戻って来ざるを得なかったのか。見えない足かせが彼を再び軍隊へと引き戻してしまうこと。明確だった社会と軍隊の境界線をも、彼は消してしまうでしょう。
恋人を射殺され、正気を失った紛れも無い弱者であった女性が、現実と非=現実を区別出来ぬまま海兵隊員に次々と体を許し、挙句営倉行きを恐れる彼らを無邪気に断罪していくシーンでは、スパイを追うものとしてその権力を盾に銃を手にする海兵隊員の人間的な弱さが暴かれ、強者と弱者は逆転します。そしてその女性同様、狂人と化した(であろう)チャン・ドンゴンもまた、いつの間に追われる者から追う者へと変遷していく……
以上のことからもわかるように、指摘しうる対立項を仕切る境界線は物語の進行と共に溶解し、それぞれの立場はその足元をぐらつかせつつ、何が善で何が悪かという根源的な問題を曖昧にしながら、極めて流動的な世界そのものの姿を炙り出していくのです。
『コースト・ガード』が描く世界は、ドロドロとした不定形の世界にほかなりません。あらゆる境界線を焼き尽くそうとするキム・ギドクの、価値観の凝り固まった世界に対する“怒り”が表明されているのです。ラストシーンで、社会へと帰還したかに見えたチャン・ドンゴンが民衆に向けて銃剣を突き刺す姿は、ほとんどテロリストのようであり、一人の被害者にも見えてしまうという矛盾。現代において、正しいことも間違ったこともあるのか。人は常にそのどちらに属してもおかしくないような、曖昧な世界に存在しているのかもしれません。
やはり『春夏秋冬そして春』とは一線を画する映画です。無論、『サマリア』を観た印象とも異なります。ともあれ、今私が注目せずにはいられない監督であることだけは間違いないと断言できるでしょう。
『海を飛ぶ夢』、もっと残酷であったなら…
原題:MAR ADENTRO
上映時間:125分
監督:アレハンドロ・アメナーバル
ハビエル・バルデムは、ほとんど“変身”とも言うべき凄まじい変貌ぶりを見せてくれました。その主題ゆえか、いくつかのシーンで余計な叙情性を感じざるを得なかったのですが、それに勝るとも劣らないほどのテクニック(何を見せないかという問題に対する対処)には感動しました。
ところで、ハビエル・バルデムが抱えていた“闇”とはいったい何だったのでしょうか。
彼は何故、嘗て海に飛び込んだのか。それは物語後半に発覚する、彼の詩作の才能にも繋がる重要なファクターだったと思うのですが。
またはあの服毒シーンを、何故ワンショットで見せなかったのでしょう。あのクローズアップの強度から言って、ハビエル・バルデムはそれに耐え得ることが出来たはずだと思うのです。
このような疑問が浮かぶにあたり、この適度に残酷な物語が、より徹底して残酷であったならと、思わずにはいられません。しかしながらそれでも、本作は今後もアレハンドロ・アメナーバルを見続けねばならないという、一つの方向性を与えてくれました。
2005年05月16日
様々なレヴェルで過激だった週末
先週の土曜日は14:00からUPLINK Xにて『ピンクリボン』初日に。ドキュメンタリー作家・藤井謙二郎氏4本目となる本作は、ピンク映画という特異なジャンルに憑かれた監督やプロデューサー、配給・興行関係者へのインタビューを記録したものです。私はそれほど多くのピンク映画を観ているわけではありませんし、書籍を通じて得た知識くらいしか持ち合わせていませんでした。1962年以降、幾度も他メディアの脅威にさらされながら43年経った今もなお生き続けているピンク映画は、端的に言って“強靭”というほかありません。数々の制約を逆手に取った“自由”が、それを裏付けていたのです。私にとって“目から鱗”的な発見や驚きはそれほどありませんでしたが、それでも本作を大いに楽しむ事ができたのは、恐らく、登場する彼らのキャラが相当立っていたということなのでしょう。1時間58分という時間を有無を言わせず見せてしまう力が、彼らにはあるのです。
続いて19:00よりシネマスクエアとうきゅうにて「韓流シネマフェスティヴァル」二回目へ。キム・ギドク『受取人不明』が目当てです。前回『コースト・ガード』を鑑賞した時の“驚き”は過去の日記に書きましたが、今回は所謂“四天王”が出演している作品ではないし、あのような状態にはならないだろうなと高を括っていました。ところが30分ほど前に会場についてみれば、「そんなわけないでしょ…」とあざ笑う声が聞こえてきそうなほどに多くのマダム達が狭い待合室を埋め尽くし、それを見るにつけ「今回の映画は描写的にも結構きわどく、いわゆる“韓流”の類とはワケが違うぞと思うのだが…」と思い、後は彼女達が途中退出しないことを祈るばかりでした。私は常に一番後ろで映画を観ることを好みますが、その日は前から三列目の一番端という悲惨な席で暗鬱たる思いに囚われ、こうなったら上映前に入場者特典として劇場側に配られた、ほとんどキャバクラでしか口にすることのない韓国焼酎「鏡月」のミニボトルを、その場で飲み干してしまおうかとやけっぱちにもなりましたが、結局それは映画に影響するのでやめておきました。
上映後、劇場を出て行くマダム達の言葉に耳を傾けてみると、「もう途中で何度も出ようかとおもったわ」とか「あんなにグロいなんて…」とかいう言葉が聞こえてきて、なんとなく安心したりも。それはそうだよなぁ…上映前に動物虐待に関するエクスキューズが出るような映画なんですから。しかしながら私の率直な感想としては、キム・ギドク的“怒り”がこれほどまでダイレクトに表出した作品はあったろうかと途方に暮れる程に、素晴らしかったと言えます。
日付が変わって昨日の日曜日はヒルズにて『美しい夜、残酷な朝』を鑑賞。昨年の東京国際映画祭で見逃して以来、長らく待っていた作品です。香港・日本・韓国から3人の監督が選ばれ、それぞれの世界観で“現代の会談”を撮ったこのオムニバス、上映前にはわざわざ係員らしき男性がスクリーンの前に立ち、観客に向かって「これからご覧頂く映画は、一作目からかなり過激な描写がありますので、ご了承ください」などと警告していましたが、まぁ言うほどのことはありませんでした。
三者三様のホラーを大いに楽しめた本作ですが、個人的にはパク・チャヌク監督『cut』が頭一つ抜きん出ていたかな、と。パンフレットを買い忘れたのですが、時間が許せば作品評を書きたいと思います。
さて、レビューが滞って久しいですが、そろそろ『コースト・ガード』の文章が書きあがりそうです。観たのはもう大分前になりますので、細かい描写を思い出すのが困難でしたが、キム・ギドクという作家についていろいろと考える良いきっかけにはなりました。今日、明日中には何とか更新したいと思います。
ところで、今週で終わってしまうキェシロフスキ・コレクションのほうは、どうやら一本も観られそうにありません。後は会社を休む以外には……残念無念。『デカローグ』は何としても見なければと思います。
『アビエイター』を前に複雑な心境になる
原題:THE AVIATOR
上映時間:169分
監督:マーティン・スコセッシ
『アビエイター』にいくつかの美点が存在するのは確かです。
それはまず、レオナルド・ディカプリオの“演出”やケイト・ブランシェットの“形態模写”など、俳優陣の輝きに見出せるでしょう。あるいはかなり苦労したであろう飛行機事故のシーンは、実に映画的な魅力に溢れていたとも言えると思います。
飛行機のボディをエロティックな対象として撫でたり、牛乳ビンを介した間接的な接吻にハワード・ヒューズの“接触の魅惑と偏執”を重ね合わせたりする描写も個人的に嫌いではありません。
しかし、この決して悪くは無い映画を、傑作と断言できないのは何故か。その原因を、スコセッシ自身に求めるべき時が来ているのかもしれません。彼はもう、いかなる我が侭をも通すことの出来る存在なのでしょうか。どうやっても正当な理由付けなど不可能だと知りながら、それでもあえて、端的に“長すぎる”と言ってしまいたい169分という上映時間には納得しかねるとここでは書いておきます。
いったい何が何だかと理解に苦しんだ、あの『ギャング・オブ・ニューヨーク』に比べてかなり良い出来であるという理由で、この作品を賞賛することは容易ですが、この大のつく程の力作を前に私が感じたのは、しかし、軽いショックだったと言わねばなりません。決して嫌いではない監督であっただけに、近年彼の作品との“行き違い”が残念です。
『アビエイター』は私にとって、傑作ではありません。そんな映画は世界に山ほどありますが、それが他でもない、スコセッシの作品であるが故に、あるいは今抱いているような複雑な心境になってしまうのでしょうか。
2005年05月15日
『愛の神、エロス』、エロスとは触覚可能でなければならないこと
原題:EROS
上映時間:109分
監督:ウォン・カーウァイ/スティーヴン・ソダーバーグ/ミケランジェロ・アントニオーニ
ウォン・カーウァイの「若き仕立て屋の恋」は、60年代の香港を舞台としています。
『花様年華』以降に漂う“エロティックなムード”は、愛=エロスを主題とした本作にも健在です。本作は鏡を、別の世界への入り口として効果的に機能させていますが、そこに映る世界はあくまで“触覚不可能”であるという事実を通じて、逆説的に触覚によるエロスを浮き上がらせています。コン・リーによる愛撫は言うまでもありませんが、肉体を持たない衣服をまさぐり恍惚とするチャン・チェンの表情に、それが端的にあらわれていました。エロスとは観念でなく、常に触覚可能な何物かでなければならないのです。
ミケランジェロ・アントニオーニの「危険な道筋」においても、それは変わりません。あの2人の肉感的な裸体が何よりの証左です。とりわけルイザ・ラニエリの、文字通り息を飲むような美しさは、エロスそのものだったと思います。
尚、スティーブン・ソダーバーグの「ペンローズの悩み」をここで取り上げたくない理由は、もちろんまともに観る事が出来なかったからなのですが、裏を返せば、エロスを前に、限りない抽象性の彼方へと逃げざるを得なかったソダーバーグと私との、決定的な断絶にこそ認められるでしょう。久々に腹が立った作品でした。
2005年05月10日
必見備忘録 5月編
今月も目が回りそうです。
■『エレニの旅』[上映中]
(シャンテ・シネ 11:30/14:55/18:20〜21:25)
■『ライフ・アクアティック』[上映中]
(恵比寿ガーデンシネマ 11:15/13:50/16:25/19:00〜21:15)
■『受取人不明』[5/14]
(シネマスクエアとうきゅう 19:00〜)
■『美しい夜、残酷な朝』[5/14〜]
(VIRGIN TOHO CINEMAS 10:00/13:00/16:00/19:00/22:00〜0:20)
■『ピンクリボン』[5/14〜]
(UPLINK X 11:40/14:00/16:20/18:40)
■『キェシロフスキ・コレクション』[5/14〜20]
(ユーロスペース 詳細は公式サイトを)
■『「DRAMADAS」シリーズ傑作選 其の壱』[5/21]
(アテネフランセ 15:30〜)
■『リトアニアへの旅の追憶』[5/24]
(アテネフランセ 19:00〜)
■『デカローグ』[5/21〜]
(ユーロスペース 詳細は公式サイトを)
先ず以って残念なのは、東京日仏学院で開催されている「記憶、引用、回想の中の映画」のほとんどを観られないことです。すでにゴダールやらユスターシュやらを見逃していることに加え、ブレッソンやタチも無理でしょう。しかしその代わり、なんと言ってもこの機会を逃したくないのが一連のキェシロフスキ特集上映です。「キェシロフスキ・コレクション」のほうでは、未見である『アマチュア』『傷跡』『終わりなし』『偶然』を、「デカローグ」は全て観なければならないと思っていますが、果たして時間的にどの程度可能か、悩むところです。
昨年の5月29日にこのサイトを開設したので、まもなく1周年ということになりますが、一応リニューアルなどしてみようなどと考えてもいるのですが、このスケジュールで本当にそんなことが可能なのか、まぁあくまで映画優先でぼちぼちやっていければと思います。
『コンスタンティン』がつまらない映画でも驚きはしないということ
原題:CONSTANTINE
上映時間:121分
監督:フランシス・ローレンス
まず、『コンスタンティン』には何があるのか、という問いを自らに向けてみます。
そこにあるのは、まず“無邪気さ”です。そしてそれは、あらゆる新人監督が持っているであろう“野心”とは別種の、“臆面の無さ”と言い換えることが可能かと思います。
時にそれは奇跡的にプラスに作用しもするでしょう。ゴダールやベルトルッチなどをここで例に出すまでもありませんが、最近で言えばヴィンセント・ギャロの『BUFFALO'66』など、彼の不遜ぶりが妙に小気味良く感動的だったことが思い出されます。
さて、翻って『コンスタンティン』はどうなのか。
結論から言うと、『コンスタンティン』は全体を通してみれば、かなり壊滅的な出来だと思います。もちろん、そんなことはいささかも珍しいことではないし、驚くには値しません。ましてや、憤ることも。むしろ、安心してしまいそうになる自分がいたりするほどです。そう簡単に奇跡が起こるはずもないのですから。
ただし一点だけ、レイチェル・ワイズの体を張った演出は大いに評価したいと思います。彼女は本作で、美貌に加わる“何か”を獲得したように思えるのです。当然、『ハムナプトラ』シリーズの彼女にはなかった“何か”です。それを確認したいがために本作を再見することは、しかし、かなりの苦痛を伴うと思われます。
2005年05月09日
GW通信 vol.2
 とうとうGWも終わってしまいました。これほど何もしなかったGWというのも過去にあったろうかと考えてしまうような連休でしたが、実際にはGWにしっかりと出かけた記憶などほとんどなく、むしろ連日映画館に通っていた今回のGWの方がよほど充実していたような気さえしてきているくらいです。
とうとうGWも終わってしまいました。これほど何もしなかったGWというのも過去にあったろうかと考えてしまうような連休でしたが、実際にはGWにしっかりと出かけた記憶などほとんどなく、むしろ連日映画館に通っていた今回のGWの方がよほど充実していたような気さえしてきているくらいです。
前回の日記では2日までの行動を記しましたので、今回は3日〜8日までを。
3日は多摩川の土手でバーベキューという、大学生みたいなことをしてきました。事実、私も18歳くらいの時に一度だけバーベキューというものを経験したことがあって、そのロケーションも多摩川の土手でしたから。天候にも恵まれ、心地良い風が吹き抜け、若干背の高い雑草が美味しげる土手の一角を占拠した我々は、11:00くらいからセッティングを始め、どんどん肉を焼いていきましたが、休日の午前中でしかも戸外という、酒飲みには堪えられないシチュエーションに早くも“やられた”私は、早々にビールやらワインやらをガブガブと飲み始め、気づいた時には、大してバーベキューを楽しむこともなく、眠り呆けている始末。あまりの日差しの強さに、サングラスをしたまま寝てしまったことを後に後悔することになります。流石に現在は治まってきましたが、指をさされて笑われてもおかしくない程の見事なサングラス焼けが、久方ぶりのバーベキューの代償だった、と。
4日以降は渋谷にて、ジムとカフェと劇場を行ったり来たりする日々。家でもdvd鑑賞と料理と睡眠を繰り返すという、まぁ言ってみれば“満たされた”日常でした。映画のほうは何本か観ましたが、それがなかなか作品評へと繋がらなかったのは、先日書いた通りです。毎日毎日渋谷を徘徊するという経験もそうなかったのですが、だからといって得るものなど皆無に等しかったですね。人が多くてうんざりすることはあっても。
それとこれは我ながらちょっと驚くべき事態でしたが、3日以降、毎日ワインを2本以上空けている自分に気づいたりもしました。その原因は、恐らく“書けなかったこと”に求められそうですが、あまりに情けないこの事態を本日より改善していかねばと決意。
とまぁ書いてみると本当につまらない連休みたいですが、本人的にはそれなりに満足行くGWではありました。先月は短評の割合が高くなってしまったので、一周年の今月は個別の作品評に時間を費やしたいと思います。まずは『コースト・ガード』と『インファナル・アフェア 三部作』あたりから。
『フライト・オブ・フェニックス』、アルドリッチは偉大だと再確認する
原題:FLIGHT OF THE PHOENIX
上映時間:115分
監督:ジョン・ムーア
リメイクである『フライト・オブ・フェニックス』とオリジナルの『飛べ! フェニックス』の間には、いくつかの変更点があります。いや、物語の骨子以外はほとんど別物のような気さえします。
そこには現代のハリウッドが要請せざるを得ない、いくつかの力学が働いているのでしょうし、だからこそリメイクはやはり難しいと改めて考えざるを得ないのですが、それでもこのほとんど話題にもならないハリウッド映画を積極的に貶める気にはなれなません。
残念なのはキャストの人選で、アーネスト・ボーグナイン的な人物を登場させず無意味に女性を配置してみたり、ジョヴァンニ・リビシは検討していたと思いますが、全体的に年齢を若返えらせたのは失敗だったのではないでしょうか。何故なら、アルドリッチ的な遊戯性は、中年の幼児退行的行動の内にこそ発揮されるような気がするからです。
上映時間が短縮されたのが唯一の救いだったというのが何とも寂しい限りですが、新ためてアルドリッチの偉大さを確認できたという意味でも、やはり観る価値はあると思います。
2005年05月08日
『香港国際警察/NEW POLICE STORY』を強く支持したい
原題:新警察故事
上映時間:124分
監督:ベニー・チャン
ジャッキー・チェン作品を自らの映画的ルーツに持つ私にしたところで、もはや50歳を超えた彼に『ポリスストーリー』を超えるアクションを求めてしまうことは自粛すべきなのかもしれません。人間は衰える、この当たり前の事実は、世界のアクションスターに対しても容赦なく襲い掛かるのです。
思えば『レッド・ブロンクス』あたりから、それは顕在化しつつあったと見るべきでしょう。しかし、だからと言ってジャッキー・チェンを決して見放そうとはしなかったのは、何故一体どうしてなのか。かつて映画に目覚めさせてくれたことに対する、一種の情のようなものでしょうか。
いや、そうではないと、ここでは断言します。
この問題は、私の人生にも直結した、極めて重要な問いかけでもあるのです。自分は映画に対し、いったいどの程度の寛容さを持ちえているだろうか、と……。
本作でジェッキー・チェンは、アクションよりもドラマに重点を置いています。あれほど悲壮感漂う彼を、私は『ファースト・ミッション』以来観ていません。しかし涙なしには観られなかったあの『ファースト・ミッション』と決定的に異なるのは、もはや体があそこまで動かないという、ジャッキー・チェンの深い諦念ではないか。事実、『香港国際警察』には、ジャッキー・チェンのある決意が感じられました。そしてその決意こそが、彼の深い映画への愛に等しいのです。
『インファナル・アフェア』をイタダいたかのようなクライマックスシーンを観て軽いショックを隠せなかったとはいえ、本作を支持したい気持ちに駆られるのは、映画人としてのジャッキーチェンの決意を感じ取ったものの義務だと思います。そして今後も私は、ジャッキー・チェン主演の“香港映画”(ここが大事です)に対し、ある種の寛容さを抱き続けるつもりです。
2005年05月07日
嗚呼……
気がつけば、というのもあまりに白々しいのですが、最近レビューの更新が著しく滞っていました。恐らく、映画レビューサイトの運営者として、必要最低限の本数を観ているとは思うのです。今はまだ連休中ですし、だからといってどこにも出かける予定もない私は、映画だけは観ているのですから。しかし、いざパソコンに向かうと、どうにも“筆が進み”ません。全く参りました。
これはどうしてでしょう? まぁ考えるまでも無く、それは私の怠惰のせいだとあっさり告白するのですが、若干の言い訳をすれば、もう一年近くサイトを運営しておきながら、未だに文章を書く“正しい”ペースがつかめていないということだと思います。最近はかなりいいペースで映画を観ているのですが、ある嗜好に沿って作品をセレクトしているのは否定できないとはいえ、かなり雑多なセレクトであることもまた事実で、一つの作品を観終えた後、次の作品を観るまでに思考を上手く切り替えることがなかなか出来ないでいるのです。
こんな言い訳をしても何の解決にもならないのは書いている本人が一番承知していて、ここ数日にいたっては、折角の休日にもかかわらず、このサイトを更新せねばならないオブセッションに襲われ、一日の行動が制限されるまでに。本末転倒としか言いようの無いこの事態ですが、サイトを運営している以上、遅かれ早かれこのような事態が生じることは予測できたことでもあります。ではどうすればいいのか?
ところで今、『交渉人』という映画がテレヴィで放映しています。この映画はもう、3回は観ている映画ですが、改めて観直してみると、ああ、あの傑作『サイドウェイ』のポール・ジアマッティが出ていただんだなぁ、とまた新たな視点が生まれてしまったりも。まず間違いなくこの映画を最後まで観てしまうのが自明なので、こうしてテレヴィを観ながら強引に文章を書いている始末です。
閑話休題。今私が取るべき行動についてでした。
正直言って、この“書けない”状態を容易に脱する術などないと思っています。あるとすれば、それはやはり何かを“書くこと”でしかないと。だからこうして具にもつかない文章を書いているのです。
連休中にもかかわらずこのサイトを見ていてくれている皆様、勝手にリハビリに入っている私ですが、いずれ、というよりも近く、これまで通りにレビューを更新できると楽観している私を、さりげなく記憶しておいていただければ幸いです。
今放映中の『交渉人』が終わった後、何とか「映画短評」だけは更新したいと思います。
それにしてもこの『交渉人』ですが、『シェーン』と『赤い河』や『リオ・ブラボー』を比べるのはどうかと……いや、つまらないことですね。
2005年05月02日
GW通信 vol.1
当ブログは、週末になるとウィークデーに比べPVが落ちるのですが、このGWにいたっては、皆さんあまり出かけていないのか、あるいは出かけた先でもインターネットに繋がる環境にいるのか、当ブログのPVも極端に減ることなく、いつもどおりに推移しています。この事実は、「GWだし更新は少しお休みしようか」と一瞬でも思った私を撃ち、今日も出社して昼休みにこんな記事を書いている次第。ブログは内容よりもむしろ、更新が肝、なんて思ったりもしている[M]です。
まずは映画のお話を。
先週は土曜日朝一で『インファナル・アフェアIII』を鑑賞。渋谷東急は50~60人程の客入りで、予想以上でした。前日に『インファナル・アフェア』を観直しておいたのですが、これが結構正解で、すんなり完結編へと思考を切り替えることが出来ました。“謎”の部分もきっちりと解明されましたし。結論から言うと、このトリロジーはなかなかの出来で、今後、少なくとも『ゴッド・ファーザー』三部作を観た回数以上は再見することになりそうです。
その後シネ・アミューズに行き、『ウイスキー』の整理券を買い求め、しかし次の上映まで2時間程ありましたので、お隣の「Bis cafe」で時間を潰すことに。このカフェ、以前来たときには、食事と言えばあまり美味しいとはいえないカレーしかおいていなかったのですが、メニューをリニューアルしたらしく、ハンバーガー等ジャンクな私好みのメニューが充実していて、チーズバーガーやらナチョスやらビールやらワインやらを胃に流し込みながら、『インファナル・アフェア』三部作に関する文章などを書くことでなかなかいい時間潰しが出来ました。
で、『ウイスキー』ですが、これは良作ですね。監督2人が公言している通り、本作はジャームッシュ、カウリスマキという作家2人を折衷したような感覚をもたらしますが、確実に5箇所で笑いを禁じえず、声を出して笑ってしまったほど。向こう一ヶ月間は、周りの友人たちに本作を熱くリコメンドすることにしようと決めました。
さて、映画以外に特に予定などない割りに、結構充実した日々を送っている私ですが、昨日は久々に大きな買い物を2つばかり。“大きな”というのは金額的な面と、文字通り一人では運べないデカイという意味ですが、それらは連休中に我が家のインテリアに加わる予定です。久方ぶりに歩いた目黒通りはちょうど「MIST」というイベントを開催中で、予想以上の人通りが。私が一人暮らしを始めた頃はすでに“インテリアといえば目黒通り”という認識がありましたが、最近はこのようなイベントにより、その認識はさらに広く共有されているようです。
3時間近く歩き続けて15くらいの店を冷かし、最終的にcafeテーブルとチェアを購入。cafeテーブルのほうは現品限りということで、定価の半額だったので即買い。チェアのほうは80年代knoll社製のもので、私の狭い了見ではknoll社といえばあの美しさと快適さを同時に兼ねそろえた傑作バルセロナ・チェアを直ちに思い出すのですが、私が購入した“重役椅子”も、なんとなくその延長上にあるようなデザインです。といっても、誰がデザインしたのかは聞きませんでしたが。というわけで、昨日購入したチェアは、死ぬまでに絶対購入するつもりであるバルセロナ・チェアの、言ってみれば予行演習的な買い物ということになろうかと。
さてさて、書きかけのレビューは連休中に一気に書き上げますので、期待せずお待ちいただければ幸いです。新しい椅子は、必ずや作業効率をUPさせてくれるでしょうから。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]



