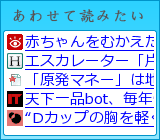2005年05月25日
『インファナル・アフェア』三部作(前編)〜香港映画を振り返ってみる
 先ず最初に断っておかなければならないのは、今の私に『インファナル・アフェア』三部作に関する文章を書くことが出来ないということです。
先ず最初に断っておかなければならないのは、今の私に『インファナル・アフェア』三部作に関する文章を書くことが出来ないということです。
1作目を劇場で観たのが2003年だったでしょうか。その時点で、確かに手ごたえはありました。言葉での説明より、とにかく早い展開で人物の関係性を強引に理解させる示す技法は、端的に“巧い”と思いました。しかし、若干の違和感を感じたのです。何かが違う、と…語りの経済性とでも言いましょうか、私はそこにアメリカ映画的な何かを感じました。いや、そういって悪ければ、少なくとも、私がそれまで感じていたような“香港映画的なもの”をあまり感じなかったということです。まぁとりあえず話を進めます。
『インファナル・アフェア』の冒頭、2人のスパイがそれぞれの身分を固めていく過程は的確で、エリック・ツァンがボスを演じるのマフィア側とタイ人との取引現場を押さえようとするアンソニー・ウォン率いる警察側との心理戦を、それに2人のスパイを加えた計4人のクローズアップを要所要所に配置しながら、それが双方にとって痛みわけで終わるまで一瞬の弛緩もなく緊張感を持続させる演出にも関心しました。さらに、本作は一応犯罪映画という体裁をとっているものの、最終的には2人の主役それぞれの自己同一性を巡る人間ドラマとして充分“魅せる”つくりであったようにも思え、例えば同じスパイもの繋がりで言えば、その前年あたりに観た『SPY_N』という、ほとんどこちらを塞ぎこませるような作品とは比べものにならないほど面白かったと言えます。要するに、私は『インファナル・アフェア』をかなり評価していたのです。
がしかし、もともと私には、一部の例外を除けば(そこにどのような基準があるのかは自分でもわかりません)香港映画の続編を観るという習慣がなく、何故だか2作目を鑑賞することはありませんでした。しかし2作目の評判も上々らしく、今年ついに完結するという情報を得ていくうちに、観なければ後悔するだろうという危機感が沸いてきて、あわててdvdにて2作目を鑑賞、そして、つい先日完結編を観るに至ったというわけです。
それでは何故書けないのかというと、これは単純にそれぞれ1回しか観ていない上に、1作目を観てから随分と時間が経ってしまったからです。すでに、雑誌やインターネットで多くの批評や感想等を読みましたが、概ね好意的な印象はそれらと大差ないものの、では、この三部作の何が決定的でそのような評価に至ったのか、実は未だにわからずにいます。もちろん、三部作を連続してもう一度観られればそれは自ずとわかるのかもしれませんが、残念ながら今はその機会がありません。
ただし、嘗て熱狂した香港映画から遠ざかっていた私が、もう一度香港映画を再評価するきっかけとなった『少林サッカー』と同じく、この三部作も、“香港ノワール”とここでは一応読んでおきますが、そのジャンルにおけるエポックであったことはどうやら間違い無いのではないかと思ってはいます。
とは言ってみたものの非常に致命的なのは、私が“香港ノワール”を実はそれほど観ていないということです。いきなり袋小路に迷い込みましたが、とりあえず、ここで私の香港映画史をざっと書きなぐりつつ、そこから何かが見えて気はしまいかと微かに期待してみましょう。
小学生時代、ブルース・リーからジャッキーチェン(及びその周辺)へと受け継がれる、エンターテインメントとしてのクンフーアクションで映画に目覚めた私は、ジャッキー・チェンが幾度かの失敗を経て、本格的にアメリカに進出し始めた時期を境に、90年代に到るまで香港映画から遠く離れていました。その後ヨーロッパ映画やアメリカ映画をはじめ、より広大な“世界”を発見していく過程において、それらがあまりに稚拙な印象を齎し始めたという相対的な要因に拠るのですが、やはり当時、70年代後半〜80年代にかけてのいくつかの作品に私が感じ取ってきた、香港映画の絶対的な魅力が明らかに減退したように感じられてしまったということもあるのでしょう。ただしここで言う“香港映画の絶対的な魅力”とやらは多分に曖昧かつ偏向的なものに過ぎず、その意味で当時の私は、香港映画のある一形態しか見ていなかったことも指摘できるでしょう。
ちょうど90年代前半に、ジョン・ウーに出会います。『男たちの挽歌』は1986年の作品ですが、実際に彼を発見したのはもう少し後になってからです。恐らくこの辺りから“香港ノワール”という言葉が使われ始めたのではないかと思うのですが、『男たちの挽歌』はそれほどまでの衝撃度を持ちえていたということでしょうか。アメリカ進出後のジョン・ウーを、私は特に評価していませんが、『男たちの挽歌』に関してはそれなりに感動したことを覚えています。二丁拳銃と踊るように死んでいく男たちとスローモーション。これらを“スタイリッシュ”だと、今は思いません。その代わり私は、これらを“出鱈目さの美学”と位置づけることで評価しています。
90年代に入り、ウォン・カーウァイの登場に直面した辺りから、次第に香港映画に対する考え方が変化してくるのですが、それまでの香港映画とはあまりにかけ離れたウォン・カーウァイの作品は、その洗練されたスタイル故か、その作品を香港映画として認識することにいささか抵抗があったのもまた事実です。よって私の中でのウォン・カーウァイ作品はむしろ、国籍を超えたところで評価したのであって、やはり“香港映画が復活した”とは到底思えませんでした。
しかしそんな中、90年代から徐々に頭角を現して来たチャウ・シンチーがあの『少林サッカー』を完成させた意味は大きかったといえるでしょう。香港映画史上最高の興行収入を記録した本作は、私の幼少時代の記憶を呼び覚ます程の傑作でした。何よりあまりに出鱈目な御都合主義的展開は私を大いに感動させ、やっと香港映画復活の兆しを見ることが出来たのです。
さて、駆け足で私の中の香港映画史を振り返ってみましたが、そこからわかったことがあるとすれば、香港映画は出鱈目だったということででしょうか。もちろんここで言う“出鱈目”とは、最大の褒め言葉として使っています。つまり、脚本の精巧さ、編集がもたらすリズム、ショットの強度などがそこに無くても、出鱈目さゆえに輝いていたと、かなり強引ながらそう言いたいのです。いきおい、『インファナル・アフェア』の上映に立ち会った時も、そのような思考で臨んだと言えるでしょう。だとすれば、もし『インファナル・アフェア』が出鱈目さの魅力に溢れていた場合の結論は容易に出せたと思います。しかし、恐らくそうではなかったのでしょう。故に、私の思考は混沌の只中へと陥るほかなかったのです。
(後編に続く)
2005年05月25日 22:43 | 邦題:あ行

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]