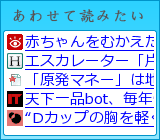2005年06月01日
『インファナル・アフェア』三部作(後編)〜香港映画に何を求めるか
 このシリーズに関する文章を書くことが出来ないなどと宣言した割に、いつものように長々とと書きはじめてしまっているのですが、少なくともこの文章に結論めいたものを求めることは出来ないと思われます。ただし、未だ現在進行形で思考している状態であるとはいえ、仮にもレビューという形式をとっている以上、作品について何らかの言及をしたいという気持がないわけではないので、下記の文章では、『インファナル・アフェア』三部作を観た上で私の感性に引っかかったいくつかのシーンを思いつくままに列挙しつつ、その思考の過程を書いていければと思います。
このシリーズに関する文章を書くことが出来ないなどと宣言した割に、いつものように長々とと書きはじめてしまっているのですが、少なくともこの文章に結論めいたものを求めることは出来ないと思われます。ただし、未だ現在進行形で思考している状態であるとはいえ、仮にもレビューという形式をとっている以上、作品について何らかの言及をしたいという気持がないわけではないので、下記の文章では、『インファナル・アフェア』三部作を観た上で私の感性に引っかかったいくつかのシーンを思いつくままに列挙しつつ、その思考の過程を書いていければと思います。
ところで、私の中の香港映画は出鱈目さにおいて輝いていた、と先に書きました。しかし、『インファナル・アフェア』を初めて観たとき、本作をそのように位置づけて安心することが出来なかった、と。それどころか、あまりに的確で破綻無く、正攻法で作られているがゆえに隙が無いその様に、ある種の違和感を感じたのです。いくら“フィルムノワール”にある種の法則があるとはいえ、それが香港映画にかかればたちどころに出鱈目さで塗り替えられ、換骨奪胎されてしまうだろうというこちらの期待は、そこである種の肩透かしを食らうことになります。しかしそれはそれで決して悪くない体験であったという事実が、曰く言い難い感情に繋がったということです。
さて、『インファナル・アフェア』三部作のそれぞれの原題を見ると、1作目は“無間道”、2作目は“無間序曲”、そして3作目は“終極無間”と言う感じで、それぞれに“無間”という言葉が用いられているのがわかります。公式サイトによれば、この“無間”は中国仏教経典に由来していて、それはそのまま“地獄”という言葉に置き換えられるそうです。三部作全編を“無間=地獄”という概念が垂直に貫いていること。この連作が、多くの“ノワール”作品に見られる“善悪の曖昧さ”を超え、より深刻な“救いのなさ”の境地へと突き進んでいることの意味は大きいと思います。人間の卑小なエゴなど軽く飲み込んでしまうような“大きな流れ”が意識的に視覚化されていることが、あるいはその他の“ノワール”とは一線を画す要因となっているのかもしれません。実際、『インファナル・アフェア』三部作には様々な形で仏教的行動や言及が存在しています。タイトルバックにおける仏像の存在に始まり、「因果応報、物事には時期がある」などと語ってみせるエリック・ツァンの行動や思想などはその最たるものです。
ところで、この“無間=地獄”ですが、これがまさに終わりの無い苦しみを意味するということが、3作目のスポットがアンディ・ラウのほうに当てられていたことを説明するではないでしょうか。『インファナル・アフェア 終極無間』は、1作目のトニー・レオンの死から数ヶ月遡りつつ、現在のアンディ・ラウが追い詰められていく過程が描かれています。彼は未だ“無間”の只中にいる。では一方の主役であるトニー・レオンはどうだったのか。常に自らの立場を顧みつつ自己同一性を追い求める“倫理的存在”の彼には、最終的に“死”という結末が与えられますが、その“死”こそ“無間”からの唯一の抜け道だったのだと思いました。極一般的に考えれば、死ぬことはそのまま“終わり”を意味するからです。残されたアンディ・ラウの終わり無き“地獄”は、まるでトニー・レオンの“地獄”まで引き受けるかのように展開していきます。同じスパイという身分を演じながら、一方は死に一方はその“地獄”まで引き受けねばならない。自分の姿にトニー・レオンを重ねる段階(鏡に映る幻影としてのトニー・レオン)から、もう自分が誰なのかわからなくなるまでに次第に精神の均衡を失っていくアンディ・ラウ。常に自己同一性を求めたトニー・レオンより弱かったが故に、死ぬことも出来ずその“終極”に止まるほかないのです。その意味で、3作目は完全にアンディ・ラウの映画だと言えるでしょう。
それにしても、この連作はなんと厳密に構成されていることでしょうか。端的に言って、曖昧さがことごとく排除されています。細かなエピソードにまで辻褄をあわせようとしていく姿勢には、物語が進んでいく内に心地よさすら覚えるのですが、それは言い換えれば、『インファナル・アフェア』シリーズが“アメリカ映画的”であって、それが香港映画的出鱈目さを画面から追いやったのだとも思うのです。しかしながら、殺人の前の一瞬の静けさ、それを平穏さと言っても良いのですが、その“間”の素晴らしさを観てしまうと、それはアジア映画特有のものではないかという故の無い幻想に囚われたりもします。そういった意味で、大変興味深い映画であることは確かです。よく言われているように、『ゴッドファーザー』シリーズへの目配せが確かに認められます。とりわけ2作目のパーティシーンとそこに流れる弦楽奏、あるいは、マフィアの政治(=表社会)進出の経緯などを指摘出来ますが、『ゴッドファーザー』以上に、この連作には“苦悩”が染み付いています。だとすればそれは、先に書いた“大きな流れ=仏教思想”に拠るものでしょう。その“苦悩”を色にたとえれば、それはやはり“黒=ノワール”なのではないか。そう考えると、カリーナ・ラウとケリー・チャンという対照的なキャラクター設定も大層“ノワール的”だと言うことに気づきます。そのどちらもが、二人の主役にとって“ファム・ファタール=運命の女”なのですから。
もう一つ、このシリーズで魅力的なのが食事シーンです。ノワールにおける食事シーンはことのほか不吉さが漂うものです。とりわけ、香港ノワールは食事のシーンがすこぶる魅力的だと思います。すぐそこにある危機を感じさせながら、じわじわと物語のネジを巻いていく感覚。本作には魅力的な食事シーンがいくつかありますが、特に2作目の、マフィアの大ボスが死んだ後、配下のボス4人が鍋をつつきながら腹を探りあうシーン。表情の楽天性とは裏腹に、誰がいつ寝返るかもしれないという裏切りの空間。フランシス・ンとエリック・ツァンがお互いの命をかける駆け引きの場も、何の変哲も無い食堂でした。
ファム・ファタールと裏切りの空間。二人の監督が、本作をノワールとして位置付けようとしているのは間違いないでしょう。
さて、結果的にいろいろと書き連ねましたが、『インファナル・アフェア』三部作は、これまでの香港映画とはやや趣を異にしながらも、ジャンルとしてのノワールを描いた野心作だと思います。がしかし、それは私が香港映画に求めていたこととは別種の次元での話です。例えばジョニー・トー監督の『PTU』のような、出鱈目極まるノワールの極北系を観るにつけ、私個人としてどちらをより好むのかを、改めて考えてみなければならないようです。
2005年06月01日 12:59 | 邦題:あ行
Excerpt: 最初にお断り。『インファナル・アフェア?? 終極無間』は多少のネタバレなしに語れな
From: Days of Books, Films
Date: 2005.06.03

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]