2006年06月30日
『花よりもなほ』には、強いて文句をつける箇所もない
原題:花よりもなほ
上映時間:127分
監督:是枝裕和
確かに『誰も知らない』の次が“人情時代劇エンターテインメント”と聞けば、いささか驚きを隠せませんでした。しかし、是枝監督が描こうとしていたものが、やはりと言うべきか、“その先に見えてくるもの”だということがわかった今、これだけのキャストを出演させてでも彼がやりたいことはあまり変わっていなかったのだろうと思います。
本作のキャストは本当に豪華過ぎるほど。そして衣装にも美術にも並ならぬ拘りが感じられました(スタッフがまた…)。古田新太のキャラクターがいかにもはまり役で、彼を中心とした掛け合いの妙(いわゆるボケとツッコミ)は悪くなく、その他ベテラン勢の演出も安心しきって観られるものでした。
是枝監督の映画作家としての力量は、本作のような喜劇においてもいかんなく発揮されていたのではないでしょうか。現在、時代劇を多くの観客に向けて作るとはこういうことか、と関心した次第。
まぁ四の五の言わず、こういう作品は観て楽しんでください、ということで。
2006年06月26日
マザー、さん
先週末、久方ぶりに親孝行でも、というわけでもなかったのですが、母親と食事をしてきました。
普段はまるで電車に乗ることなどない母を、溜池山王まで来させるのは非常に困難を極めます。大体実家から1時間ほどかかるのですが、電車に乗らない母は、車中での時間の潰し方もわからず、ただひたすらボーっとしていたのだそう。本当はそんなところまで出向いてくるのは嫌だったはずですが、生来の自己中心的人間である私を心得ている母は、それを嫌がれば食事の機会を逸すると言うことを重々承知していたのでしょう。慣れない道程ですから、30分も早く着いてしまったらしいです。
ほとんど思い出したときにしか連絡もしない親不孝な私ですから、こういう時にしか母親の近況を聞いてあげられる機会がないのですが、どうやら素晴らしい引退生活をしているようで。旅行が好きなのは前から知っていたのですが、まさか毎月のように外国へ旅行しているなどとは思いませんでした。外国語が苦手な母が、身振り手振りで図々しさを最大限全面に押し出しながら外国人と会話している様が目に浮かび、まぁそこまで生活を楽しんでいるのであれば、こちらが心配することなど何もないなぁ、といささか拍子抜けした次第です。一応気を使って、「今日は俺が払うよ」などと言う私を尻目に、「どうせあんたお金ないんでしょうが」と言い放ち会計をすませようとする母は、隠居後の孤独で暗い生活という貧しいイメージからは程遠く、一応元気に一人暮らしを楽しんでいるはずの私の財布の心配までする母を見るにつけ、突如、“親孝行したい時に親はなし”という言葉が、実はこの場合には当てはまらないな、と思った次第。正しくは、“親孝行したい時に、親は旅行中”という感じです。まぁそれはそれで喜ばしいことではありますが。
実はその日、15:00頃から映画を観る予定を組んでいたのですが、昼に待ち合わせて、散々食事をゴチになった挙げ句、「じゃぁ俺は映画に行くから」とは流石に言えず、食事の後、喫茶店にまで付き合って、私はそこでもビールを2杯ほど飲み、食事の時に飲んだワインとあわせてかなりいい感じになってしまいました。で、結局は映画にも間に合わず、それでもまだタイミングがあう映画は無いだろうかとケータイで探してはみたのですが、その内眠くなってきまして、結局は映画を観ずに帰宅しました。
というわけで、土曜日に映画を観られなかったので、日曜日は何とか1本、『花よりもなほ』を鑑賞。先週は平日にシネマアートン下北沢で『セキ☆ララ』と『童貞。をプロデュース』を観ていたので、個人的なノルマは消化できました。
で、『花よりもなほ』ですが、思ったとおり劇場は満席に近く、しかし、すぐ上の階で上映していた『デス・ノート 前編』の混雑振りのほうが凄くて、まぁ私は観ないでしょうから関係ありませんが、その光景を見るにつけ、先日のシネマ・アンジェリカの寂しさが思い出され、だからといって無力な私はどうすることも出来ず、せめて今度あそこに行く時には誰かを誘って行こう、などと悠長に考えるのでした。
それぞれの映画については、別途。
『花よりもなほ』では、またぞろ隣の隣の女性客2人組が、上映中普通に(!)会話し始める始末で、ああいう客をブラックリストに入れて、次回来た時にはにべも無く入場を断るような、そんな制度が確立しないものだろうかと、またしてもありえない空想に浸り、鑑賞後の高揚感とは別種の、表現しがたい不快感に苛まれつつ、日曜日を終えました。
2006年06月23日
『最後通告』に関する私の文章も、結局何が言いたいのやら……
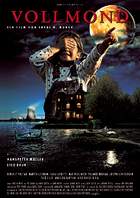 原題:Vollmond
原題:Vollmond
上映時間:124分
監督:フレディ・M・ムーラー
スイス映画と聞いてすぐさま思い浮かぶのがたった4人の映画作家でしかないという私、しかもそれらのほとんどは未見で、つまり、スイス映画をほとんど知らないという結論に至るのですが、厄介なのはそのわりにはスイス映画に対しあるイメージを抱いてしまっているということ、改めて考えると私も相当通俗的な人間だということを再認識するのですが、だからといってそのイメージのおかげでスイス映画を積極的に敬遠しているわけではありません。そもそも、東京に住んでいても一般公開されるスイス映画などほとんど無いわけで、こちらが望もうとそう簡単には観られないのが現状なのです。
そんな折も折、渋谷にあるシネマ・アンジェリカという劇場が「スイス映画月間」と称した特集を組んでいるという事実にはやはり興味を惹かれてしまいます。たしかこの劇場に最後に訪れたのはまだ改名する前のことで、確か『ふたりにクギづけ』を観た時だったと思うのですが、以前よりあまり人が入っている印象がなかったこの劇場でダニエル・シュミットやフレディ・M・ムーラーの旧作を果敢にも上映するという姿勢に賛同し、何とか一日だけでも参加しようと決めたのです。
本来であれば、先日見逃した『夢駆ける馬ドリーマー』を観る予定だったのですが、嘗てユーロ・スペースで公開されていたことを、移転したユーロ・スペースの壁に飾られているチラシを見て初めて知った私の無知ぶりを反省する意味も込めて、相対的に貴重であろうフレディ・M・ムーラーの『最後通告』の方を選びました。
恐らく観客は10人にも満たないだろうという私の予想は、まぁ概ね正しかったわけですが、結果的に事態はそんな心無い予想をさらに上回っていました。上映開始の13:00より20分ほど早く到着してみると、観客は私一人。ぎりぎりで駆け込んでくる客もなく、最後まで客席には私ただ一人。このような経験を、まさか東京で、しかも、渋谷でするなどとは思ってもいませんでした。もう随分前に、福島駅近くのシネコンで『マトリックス』を鑑賞した時も確かに一人きりでしたが、あの時感じた爽快感(言うまでもなく東京ではかなり人気があったので)を、今回ばかりは感じることがありませんでした。もちろんそれは孤独からではなく、映画を上映することの難しさ、ひいては劇場を運営していくことの困難を考えざるを得なかったからです。それなりに名前のある作家で、しかも土曜日の日中でも、こういった事態が起こりえるということを目のあたりにしました。
ところでそんな中で観たこの『最後通告』と言う映画、様々な意味で言葉にしがたい映画でした。私は『山の焚火』も未見なのでこの監督については批評やインタビューを通してしか知り得ませんでしたが、ほとんど根拠もなく、こういうスイス映画もあるのか、と少なからず驚いた次第。大雑把に言ってしまえば、ミステリーとファンタジーがない交ぜになった批評的寓話だと思うのですが、本作に込められた寓意をどれだけ積極的(あるいは肯定的に?)に汲み取ろうとするのかで、作品の評価が分かれるところでしょう。
原題は「Vollmond」。これは“満月”という意味で、それはそのまま本作における重要なファクターとなります。“最後通告”という邦題は、本作のミステリー的要素(犯罪的要素)を強調したと言う点でやや説明的ではありますが、決して作品の内容と離れているわけではありません。
冒頭、ゴミが堆積し透明度の低い水中をカメラは映し出します。カメラはしばらく水中を彷徨うと、上方にある光のほうをを見上げ、そして水面へと移動し水中からファインダーを出す。水中から出てきたカメラは、湖の辺(ここで観客は、湖の中を観ていたことを知ります)にある一軒の瀟洒な邸宅と、そこから出てきたと思われる一人の目隠しをした少女が少女が、両手を伸ばして湖の方におぼつかない足取りで歩いてくるのを目撃します。ここまでがワンカットで撮られたファーストシークエンスは悪くなく、その先の展開を期待させるものでした。
本作は、12人の子供(いずれも10歳)が忽然と姿を消し、その原因を刑事が探っていくという、言ってみれば非常に分かりやすいプロットではあるのですが、しかし、子供が失踪した理由が非常に謎めいているため、物語の進行にしたがって通常のミステリーとは異なる相貌を呈していきます。つまり、追うべき犯人などおらず、刑事以下大人たちは右往左往するほかないのです。謎の解明という軸が、いつのまにか子供たちから大人たちへの警告(これこそが最後通告なのですが)へとずらされていき、しまいには超現実的な世界すら垣間見える程。その過程で、子供を失った大人たちは、マスコミの加熱報道に憤ってみたり、極度に神経をすり減らしてみたり、あるいは、恋に落ちたりもする(とくにこのシーンは印象的で、あのように男女が手を取り合う場面を、私は久々に観た気がします)。そして、子供たちが投げかけた問いは最後まで宙吊りにされ、最悪の結末を迎えて物語は幕を閉じます。
とにかく様々な問題提起が、本作には渦巻いています。この問題提起には恐らく、監督の寓意があからさまに反映されており、そのまま観るものに投げかけられているのですが、果たして、私にはその意図が充分に伝わらなかったと言わねばなりません。いや、言わんとすることはわからないでもないのですが、それが映画的な感動に繋がるのかどうか、私にとって重要なのは、まさにその点なのです。
大人たちがテレヴィの公開生放送を利用して、子供たちに呼びかけるシーンがありました。
そこでの大人たちの愚かしい行動は、いかにも映画的な仰々しさに満ちていて悪くはなかったのですが、やはり、そこに至る過程の描き方に若干無理があり、また、登場人物が多い割りに、それぞれのキャラクターの差異が明確でなかったように思われたのは残念な部分でした。
ハッピーエンドを避けた結末自体は、あれで良かったように思うのですが……。
私にも特に結論めいたことは書けません。
繰り返しますが、私の根拠のない“スイス映画観”が、良い意味で軌道修正されたのは確かです。2時間を超える上映時間をかろうじて耐えることも出来たので。まぁそれが収穫だったということで、この不可思議な映画に関しは、実際に観ていただき、それぞれに感じていただくほかないということで。
2006年06月20日
「1st Cut〜映画美学校セレクション」その2
ちょっと時間が経ってしまいましたが、その1があってその2がないのはアレだろうという判断から、5/31に観た3本に関して簡単に。
・『如雨露』(監督・脚本:吉井亜矢子 2003/16mm/31分)
・『春雨ワンダフル』(監督・脚本:青山あゆみ 2003/16mm⇒DV/36分)
・『INAZUMA 稲妻』(監督:西山洋市 脚本:片桐絵梨子 2004/DV/31分)
『如雨露』は、そのあふれ出るイメージをどのように捉えるのかで評価が分かれる気がします。コマ撮りの特撮はなかなか頑張っていたと思いますが、ところどころに挿入される抽象的なイメージのおかげで何となく全体の印象がそれこそ水で薄まったようになってしまいました。もしそれが監督の狙いだったのなら、まさに狙い通りだったのかもしれません。
『春雨ワンダフル』は非常に奇妙なドライブ感覚があって、その突飛な物語の中に様々な要素が盛り込まれているのに決して破綻しておらず、だからといって小さくまとまっているわけではないあたりに感動しました。ビワコが木陰で子供を生んでから走り出すシーンが特に好きでした。前妻の愛人である出鱈目な外国人の演出にも素直に笑ってしまいました。非常に好感の持てる作品。
そして『INAZUMA 稲妻』。多分に漏れず、私も本作観たさにこの日を選んだわけですが、私が鑑賞前に思い描いていたイメージを軽く裏切るような(しかしこのニュアンスを伝えるのは至難の業なのですが)展開や演出に、いろいろ考えてしまいました。劇中、芝居と現実が溶解していくあたりはなかなか面白く、それと同じくして対立の構図が次第に横滑り(ズレて)していくのを観た私は、最終的になんだか煙に巻かれているような気になり、それを例えば、ミヒャエル・ハネケの『カフカの城』を観た後のような感覚ということになるのですが、それでも決定的に異なるのは、『INAZUMA 稲妻』が“情念の映画”だという点でしょうか。ファインダーの中心に存在する十字が頭から離れません。
というわけで、2日間に渡って観た「1st Cut〜映画美学校セレクション」、個人的には楽しめました。
来年こそは、メインのプログラムを観たいと思います。
なお、『蘇州の猫』のレビューはこれから書き始めますが、ちゃんと書きあがるかどうかは甚だ不安です。傑作ということに全く疑いがないのですが……
2006年06月19日
「ZUGABE in TOKYO」にて、西尾監督と初対面のような再会を果たす
先週金曜日、池ノ上にある「シネマボカン」にて催された「ZUGABE in TOKYO」という上映イベントに行ってきました。これは友人である西尾孔志監督(当ブログでは、度々「イカ監督」というハンドルで書き込んでくれてます)が主催する関西発のインディーズ上映プロジェクトで、大阪・名古屋に続き、今回初めて東京で開催されるとのことだったので、喜び勇んで駆けつけたというわけです。
2日間の上映のうち、私はあいにく1日のみの参加となりましたが、その時に観た2本の作品はいずれも大変面白い作品でした。このために大阪から来た西尾監督や彼の友人らと深夜まで飲みながら映画話で盛り上がったのですが、いやはや、世の中には凄い人がたくさんいるなぁという、当たり前と言えば当たり前の結論に至り、かなりの刺激を受けてきた次第。以下、簡単な作品評です。
■『ハートに火をつけて』(伊藤康弘/1991/16mm→DV//31分)
大阪芸術大学の卒業制作として撮られた本作は、その名の通り、ドアーズの名曲がふんだんに使われた問題作というべき秀作。B級アクションという言葉が最大の賛辞になると思われるのですが、監督の言葉によれば、制作には1年を要したとのこと。それが技術的な問題なのか、あるいは制作的な問題なのかわかりませんが、本作に度々観られる人物のクローズアップの迫力は、ただ人物が画面に大写しになっているというだけでなく、そこに何か異様な薄気味悪さが漂っているのですが、しかし本作は、そんなクローズアップの背後に、不穏な死だったり犯罪だったりロマンスだったりが横たわり、それらが等しく“狂気”に染められているという辺りが何とも面白かったです。これはひとえに、私個人の嗜好性によるのかもしれませんが。
拘られた人物配置、切り替えしの妙、カーアクションにおける編集のリズム等、注目すべき点も多く、作品に漂う時代性を超越して、まさに“現在の映画”としてより多くの人に観ていただきたい映画だったと思います。
■『悪い冗談』(西尾孔志/2001/DV/77分)
本作もまた、ビジュアルアーツ大阪の卒業制作作品ということでしたが、実はそれを聞いたのは上映後で、私はこれを西尾監督の新作だとばかり思いこんで鑑賞しました。
あの『ナショナルアンセム』より前に撮られたのですから、“相変わらず”という言葉は相応しくないのですが、それを承知で言わせていただければ、西尾監督の作品は“相変わらず不思議だ”と言えます。しかし、それが通俗的に“難解”であるなら批判の一つも言えるのでしょうが、これがまた“悪い冗談”のように面白い。本人は否定するかもしれませんが、本作はすでに、西尾監督のスタイルの萌芽が随所に見られます。反=メソッド的演出、“意味”からの飛翔、ジャンルからの逸脱などの要素が、本作の不思議さを形成しているのですが、にもかかわらず、その都度こちらの予想を凌駕した“悪い冗談”がこれでもかと画面を横溢し、それを観ている我々観客は、時に呆気にとられ、時に笑い、最後にはこんな映画を卒業制作に持つ監督に対し嫉妬するしかないという事実。
何でしょうか、この感覚は。まぁこれもきっと“悪い冗談”なのでしょうから、あまり深く考えないようにしなければならないでしょう。
ともあれ、非常に有意義な夜でした。
西尾監督をはじめ、お話させていただいた方々、ありがとうございました。皆さんとお話して痛感しました。もっともっと映画を観なければ、と。またあのような機会が持てたらと切に思います。
【関連リンク】
・ZUGABE
・私信〜ナショナルアンセム』によせて〜
・『おちょんちゃんの愛と冒険と革命』に“反応”出来る貴重な体験
2006年06月14日
“エログロ映画”の饗宴〜「笑うポルノ ヌケるコメディ」より4本
開館時より充実したプログラムを組みながら、渋谷でも独自の位置を獲得しつつある名画座・シネマヴェーラ渋谷ですが、先日終了した「笑うポルノ ヌケるコメディ」という特集上映にどうしても観たかった作品が2本含まれていたので、階下のユーロ・スペースには移転後も何度となく通っていたものの未だ足を踏み入れたことのなかったこの劇場に、初めて行ってきました。
この特集上映のサブタイトルは“日活ロマンポルノvs東映ピンキーバイオレンス 「笑い」の頂上決戦 and More!”というもので、2本立てのプログラムも東映と日活それぞれの作品の対決という形で組んでいるため、いやでも東映と日活のカラーの差異が際立ってしまうのですが、そのおかげで、私の好みがどちらに近いかということを確認できたので、その意味でなかなか有意義な試みだったと思います。
そもそも私が観たかった2作品は、共に、東映が岡田茂の号令でエログロ路線に走り出した70年台の作品なので、それに付随するかたちで観ることになった日活作品の印象がどうしても弱いのは、それら日活作品の出来とはあまり関係のないことなのかもしれません。破天荒という言葉が似合う東映エログロ路線こそ私が観たかったものなので、どちらかと言えば、シニックな笑いや繊細な演出という言葉が思い浮かぶ日活ロマンポルノも嫌いではなかったものの、やはり前者の、まさに映画という形式を逆手に取ったかのようなはめのはずし方とか開き直ったような態度に惹かれてしまいます。
やっぱり映画にはセックス(エロ)とバイオレンス(グロ)が必要だと未だに信じている部分もある私としては、何も普段からそんな映画ばかり観ているわけではないにせよ、かように制作側の強い意志と圧倒的菜娯楽性の両方を実感出来る作品であるなら喜んで観に駆けつけたいと思うし、小奇麗にまとまったセックス描写や残酷さが剥ぎ取られた審美的なバイオレンスシーンも時にはいいけれども、観ているこちら側も、どうしてこんな作品を作ろうとしたのかが皆目検討もつかないという意味で反動的にエロやグロに徹した作品(ウォーホル=ポール・モリセイの諸作品など。観てはいませんが、ジェス・フランコの作品もそんな部類に入るような…)の貴重さをより好むでしょう。
今回の特集上映では、そんな東映の“エロ”と“グロ”の代表作をそれぞれ観る事ができたので、個人的には大満足だったと言えます。
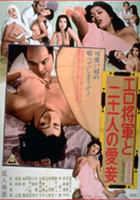 まずは『エロ将軍と二十一人の愛妾』ですが、この人を食ったタイトルのセンスには素直に脱帽するほかありません。本作は確かにポルノ映画なのだからセックスシーンも多いわけですが決してそれだけではなく、例えば“女ねずみ小僧”を演じる池玲子の傘を用いた美しい立ち回りだとか、それぞれ毛沢山・陳万紅というほとんど度を越して安直な名を持つ中国人を演じた由利徹と岡八郎のギャグ、ほとんど物語に貢献しないと言う意味で贅沢な無駄としか言いようのない大泉滉の独特な存在感など観るべき細部がこれでもかと盛り込まれています。そして、恐らく映画史上ほとんど類を見ないような(これに拮抗し得るのは、最近観た『ドッグデイズ』の乱交シーンかもしれません)、全裸姿の大奥と死刑囚とのセックスバトルロワイヤルシーンに至ってはその迫力、夢幻性、荒唐無稽さのどれをとっても壮大と言うほかなく、反権力的な結末も含め、鈴木即文の力技はまったく見事でした。何作か観た『トラック野郎』シリーズも悪くありませんが、本作には得体の知れないパワーが溢れていたような気がします。文句なしの傑作!
まずは『エロ将軍と二十一人の愛妾』ですが、この人を食ったタイトルのセンスには素直に脱帽するほかありません。本作は確かにポルノ映画なのだからセックスシーンも多いわけですが決してそれだけではなく、例えば“女ねずみ小僧”を演じる池玲子の傘を用いた美しい立ち回りだとか、それぞれ毛沢山・陳万紅というほとんど度を越して安直な名を持つ中国人を演じた由利徹と岡八郎のギャグ、ほとんど物語に貢献しないと言う意味で贅沢な無駄としか言いようのない大泉滉の独特な存在感など観るべき細部がこれでもかと盛り込まれています。そして、恐らく映画史上ほとんど類を見ないような(これに拮抗し得るのは、最近観た『ドッグデイズ』の乱交シーンかもしれません)、全裸姿の大奥と死刑囚とのセックスバトルロワイヤルシーンに至ってはその迫力、夢幻性、荒唐無稽さのどれをとっても壮大と言うほかなく、反権力的な結末も含め、鈴木即文の力技はまったく見事でした。何作か観た『トラック野郎』シリーズも悪くありませんが、本作には得体の知れないパワーが溢れていたような気がします。文句なしの傑作!
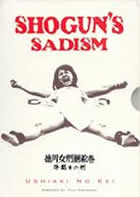 次に『徳川女刑罰絵巻 牛裂きの刑』ですが、何度か当ブログでも言及してきたように、本作はその存在自体が幻のような作品で、一応海外ではdvd化されているものの、そのタイトルが「SHOGUN'S SADISM」という実も蓋もないほどのやりすぎ感を醸しだしているので、未見の方もこの内容は推して知るべしという感じがしないでもありません。何しろあの伝説的なヤラセ映画『スナッフ』に乗じた作品なのですから。
次に『徳川女刑罰絵巻 牛裂きの刑』ですが、何度か当ブログでも言及してきたように、本作はその存在自体が幻のような作品で、一応海外ではdvd化されているものの、そのタイトルが「SHOGUN'S SADISM」という実も蓋もないほどのやりすぎ感を醸しだしているので、未見の方もこの内容は推して知るべしという感じがしないでもありません。何しろあの伝説的なヤラセ映画『スナッフ』に乗じた作品なのですから。
本作は強引に2つのパートに分けられていて、タイトルに副った内容はどう見ても前半部分だけのように見受けられましたが、まぁこの際そういう真面目な意見は自粛するとしましょう。ここに収められている数々の拷問シーン、そのバリエーションもさることながら、その描写や音も非常に頑張っています。見所はやはり内村レナに施される牛裂きの刑ということになるでしょうが、このシーンは残酷であるだけでなく、意外にもよく出来たモンタージュなのです。両手足に紐でつながれた牛が興奮して四方に走り出す瞬間と、苦悶の表情を浮かべる内村レナ、そしてそれを不快に盛り上げようとする音響、これらが短い時間で渾然一体となって観るものを不意打ちする瞬間には心から感動した次第。
川谷拓三が殺されるためだけにある後半部分は、“牛裂きの刑”ではなく“鋸引きの刑”がクライマックスなので、どうしても取って付けた感は否めませんが、この“鋸引きの刑”を執行するのが役人ではなく、たまたまその前を通りかかった狂人だというアイデアが何とも陰惨で素晴らしく、結局この映画にはほんの1ミクロンも“救い”が存在しないという潔さ。
ちなみに監督の牧口雄二は、翌年に同じスタッフで『女獄門帖 引き裂かれた尼僧』という全く同じように狂気に満ちた問題作を撮ったそうで、こちらも死ぬまでには観てみたいと密かに思っています。
このような素晴らしい企画を実現させたシネマヴェーラ渋谷は、今、東京で最も貴重な劇場の一つだと確信しました。ユーロ・スペースとシネマヴェーラ渋谷のハシゴだけでも、かなり充実した映画体験が約束されるでしょう。
2006年06月12日
ダグラス・サークは偉大だ〜『愛するときと死するとき』と『誰かあの娘に会ったかい?』を観て
一応クリアしてみたものの、裏ダンジョンが多数残されているのでまだまだ止められそうにない「ドラゴンクエスト 少年ヤンガスと不思議のダンジョン」の所為、とまでは言い切れませんが、先週はウィークデーにレイトショーを1本観ただけで、土曜日こそはと思い、目下最も期待している作品の一つである『夢駆ける馬ドリーマー』を観ようと決め、ジムを終えて劇場に駆けつけると、渋東シネタワーには何故かこの作品の名前が見当たらず、確かに「必見備忘録 2006.6月編」にはここで上映されている旨を記したはずだが…と途方に暮れ、ではどこでやっているのだろうと、普段使わない携帯電話のサイトを確認してみると、すぐ近くのシネフロントで上映中とあるので、ああ、自分で誤って記した情報を鵜呑みにしていたのか、でもまぁ近いし良かった良かったと思ったのも束の間、すでに上映が始まっていることに気づき、今日はこの映画のために全てのスケジュールを調整したのに、これでは何のための土曜日だろうかと情けなくなり、たったそれだけで今日はもう映画なんか観ないぞと思ってすぐさま帰宅するあたり、あまりに大人気ないといえば大人気ないのですが、では家に帰って普段はなかなか観られないヴィデオやdvdを鑑賞するなどして映画に触れておけばいいのに、結局はテレヴィの前でひたすらコントローラーを握り続けるという体たらく、だからゲームは恐ろしいと言うほかありません。でもまた一つ、ダンジョンをクリアできました。
さて、そんなどーでもいいことはさておき、昨日は某所にて某氏が主催する上映会(一応伏せておきますが、調べればすぐに判明するでしょう)に参加したのですが、アメリカ時代の貴重なダグラス・サーク2作品を字幕なしで観るというその企画、字幕なしというあたりがやや引っかかるところではありましたが、事前にあらすじを配ってくれると言うし、台詞の大半をたとえ理解出来なくても多分、いや、絶対に面白いはずだと言う根拠のない確信はあったので、雨の中京橋までいそいそと出かけていったのです。
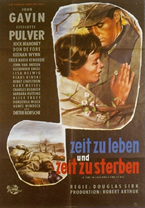 果たして、その2本のサーク作品は滅法面白く、それは事前に配布されたあらすじが比較的よく書けていたからという理由もあるにせよ、やはり素晴らしい映画とは、その台詞の内容をほとんど無視して画面だけを観ていても感動的で面白いのだということが確認出来た次第。それは、嘗て同時通訳という形で観たジャック・ロジエ『トルチュ島に漂流した人たち』を観ながら段々と台詞が耳に入らなくなっていった稀有な体験を想起させ、つまり、ダグラス・サークもまた偉大なのだということが言いたいのです。
果たして、その2本のサーク作品は滅法面白く、それは事前に配布されたあらすじが比較的よく書けていたからという理由もあるにせよ、やはり素晴らしい映画とは、その台詞の内容をほとんど無視して画面だけを観ていても感動的で面白いのだということが確認出来た次第。それは、嘗て同時通訳という形で観たジャック・ロジエ『トルチュ島に漂流した人たち』を観ながら段々と台詞が耳に入らなくなっていった稀有な体験を想起させ、つまり、ダグラス・サークもまた偉大なのだということが言いたいのです。
最初に観た『愛するときと死するとき』(A Time to Love and A Time to Die/1958/113分)は、男と女のメロドラマ的な側面よりもむしろ、戦争を媒介にした残酷な因果律という印象が強かったです。撃つものと撃たれるものがいて、それらの時間的・空間的な距離を埋めるかのように、悲劇的で美しいロマンスがある、という感じでしょうか。まったくの思いつきですが。
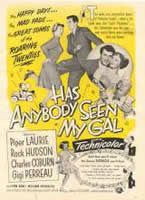 2作目の『誰かあの娘に会ったかい?』(Has Anybody Seen My Gal/1952/88分)に至ってはもうただ傑作だという以外ありません。サーク初の長編カラー映画(テクニカラー)にして心躍るコメディである本作には、ジェームス・ディーンがカメオ出演していたり、老人と子供による感動的なダンスシーンがあったり、反復されることでその精度があがっていくギャグがあったり、大胆に装飾されたサイクリングシーンがあったり、神がかった動物のアクションがあったりと、88分という時間があまりに贅沢に感じられるほどの出来栄えで、さりげないラストとはいえ、これこそが真のハッピーエンドだとでも言いたくなるような幸福感がそこにはあります。主催者側の説明では、現在日本にたった1本だけある16mmフィルムとのことで、確かにところどころ観づらい箇所もありましたが、そんな瑣末なことは結果的にどうでもよくなってしまうような映画でした。
2作目の『誰かあの娘に会ったかい?』(Has Anybody Seen My Gal/1952/88分)に至ってはもうただ傑作だという以外ありません。サーク初の長編カラー映画(テクニカラー)にして心躍るコメディである本作には、ジェームス・ディーンがカメオ出演していたり、老人と子供による感動的なダンスシーンがあったり、反復されることでその精度があがっていくギャグがあったり、大胆に装飾されたサイクリングシーンがあったり、神がかった動物のアクションがあったりと、88分という時間があまりに贅沢に感じられるほどの出来栄えで、さりげないラストとはいえ、これこそが真のハッピーエンドだとでも言いたくなるような幸福感がそこにはあります。主催者側の説明では、現在日本にたった1本だけある16mmフィルムとのことで、確かにところどころ観づらい箇所もありましたが、そんな瑣末なことは結果的にどうでもよくなってしまうような映画でした。
朋友・こヴィさんにいただいて以来、未だ観る機会がなかった『風と共に散る』ですが、今こそ観る時だと確信しました。個人的に機は熟したという感じです。そして同様に、「サーク・オン・サーク」も今こそ読まれるべき本ということなのでしょう。
2006年06月08日
『太陽に恋して』、“軽く”て“若い”佳作
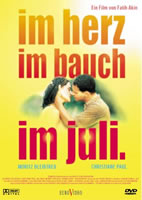 原題:Im Juli.
原題:Im Juli.
上映時間:100分
監督:ファティ・アキン
渋谷におけるウィークデーのレイトショーなど、多くても15人ほどの観客とともに観るのが自分には最も都合の良い環境だと最近とみに思っているのですが、昨日、なかなか評判のいいファティ・アキンの『太陽に恋して』を観にシアターNに行くと、何と上映1時間前にもかかわらず整理券番号が21番で、いくらネットでの評判が良いとは言ってもそれだけでこの番号と言うのはありえない、誰かのトークショーでもあるのだろうかと、その日を選んでしまったことを失敗だったと悔やんだのですが、よくよく考えればなんてことはない、ただ昨日が水曜日で映画サービスデーだっただけなのでした。普段も大体の映画を1000円で鑑賞するため、それに気づかなかったというわけです。
まぁいずれにせよ、私の選択が失敗だったことに何ら変わりはなく、それは、この整理券番号では、私が普段シアターNであればここ(シアター1であれば中央最後列右端)、と決めている席が取れなかったばかりか、隣に座った中年女性2人組が、上映開始に間に合わず遅れてきたことまではまだ許せるとしても、席に座るなり、あろうことか彼女達にとっては小声と認識されているのかもしれない大声で断続的にぺちゃくちゃと話始めるので、なかなか良い出だしで始まったこのロードムービーにところどころで集中することができず、久々に腹に据えかねる思いでした。運が悪かったと言えばそれまでで、だからそういう日に映画を観にいくことを選択した自分を責めるしかなかった、と。余程のことがない限り、サービスデーに劇場に行くのはやめたほうが良さそうです。
という次第なのですが、この『太陽に恋して』というありがちな邦題を持つドイツ映画は決して悪くはなく、それなりに楽しめる佳作といった印象。冒頭、夏のヨーロッパの田舎道と思しき一本道の奥の方から一台の自動車が画面手前に向け緩やかに走ってきます。そして画面手前へと自動車が近づくにつれ、次第に画面全体の彩度が落ちはじめ、車が停車するころには何故か画面が夜のように暗くなる。西部劇でもあるまいし、何故今、“アメリカの夜”なのか? というこちらの疑問は、自動車を運転していた男が車から降り、サングラス越しに太陽を見上げるショットで容易に解消されます。その一連のシークエンスを観て、なるほど、やりたかったのはこういうことか、と何だか嬉しくなり、一本道、照りつける太陽、そして自動車という、いかにもロードムービー的なファクターを冒頭に持つこの映画への期待が高まりました。
最近では『ミュンヘン』にまで出演していて驚かされたモーリッツ・ブライブトロイは、本作であまりに類型的なキャラクターを演じていますが、その時感じた意外性は、実はこの映画全編にわたって共通するものでした。ある場所からある目的地への移動そのものはそれほど多く描かれず、その移動の過程で巻き起こる数々のエピソードやロマンス、アクションにこそ比重が置かれている『太陽に恋して』は、私の感覚から言えば所謂ロードムービーと言い切れないところがあるにはあるのですが、一つのエンターテインメントとして本作を眺めるなら、そのご都合主義的な展開や典型的とも言えるラスト近くのキスシーンのカメラワークも含め、ドイツ映画というよりはむしろアメリカ映画的な佳作と言うべきものだったと思います。
ややロマンティックが過ぎる映像(どことなく中島哲也的だったと思います)にはまるで感じる部分がなかったものの、作品のもつコミカルな雰囲気(本作にはそれほど笑えない細かいギャグのようなものが散見されました)には合っていたのかもしれません。
ともあれ、あまりドイツ映画に馴染みのなかった方でも、本作の“軽さ”は、ドイツ映画が持つイメージ(未だそのようなものがあるかどうかはわかりませんが)は少なからず払拭されるのではないでしょうか。むしろ、異文化との出会い、若さと躍動感という点においては、良い意味でいささかも“ドイツ的”ではありません。ガトリフやクストリッツァに比されるのも、ある側面では納得です。
『愛より強く』は是非おさえておかなければと思いました。
2006年06月06日
過酷さもまた、美しい記憶へと変わるだろうか…
日本でも毎年、それなりの数の映画祭が開催されますが、そもそも人ごみが苦手な私は、本来であればその手の催事に積極的に参加するような人間ではありません。普段ほとんど渋谷でしか映画を観ない私はそもそも“渋谷の客層”に慣れてしまっているということ、あるいは、私が観る多くの映画は余程の場合を除けば満席にはならず、かなりゆったりと映画を観る事が出来るということ、自宅から近いので早朝から整理券を確保することも困難ではないということがその理由です。よって、そういった状況とはまるで正反対、とまでは言いませんが、かなり事情が異なる「〜映画祭」の類には、出来れば行きたくはないというのが正直なところです。
しかしながら日本には、映画祭の時にしか観ることの出来ない映画というものが少なからずあって、次回いつ上映されるともわからないそれらの貴重な作品を観るためには、個人的な事情に拘ってはいられません。例えそれが映画を観る環境とはいえない場所だろうと、その客層がどうしても自分の肌に合わなかろうと、チケットの値段が高かろうと、その映画祭の趣旨にはほとんど賛同出来なかろうと、可能な限り駆けその貴重な作品を目に焼き付けたいという強い思いが、私をして映画祭というもの参加せしめてきたのでしょう。
さて、先日朋友・こヴィ氏から一通のメールが来ました。
そこには「ドイツ映画祭のチケット取りました」とだけ書かれてあり、ああ、そう言えば…と公式サイトを覗いてみると、ヘルツォークの新作やルビッチ特集などという魅力的なプログラムが組まれていて唸らされましたが、7月の下旬と言えば、私が珍しく映画から離れて“青”を求め始める時期と正確に一致しているので、ああ、今年の予定も未だ決まっていない次期から、映画の予定など入れてもいいものだろうかと逡巡することしきりでした。しかし、前々からルビッチの『牡蠣と王女』は傑作と聞くし、「ドイツ時代のラングとムルナウ」で来日したアリョーシャ・ツィンマーマン氏のピアノ演奏付きというのもまた貴重な機会だろうという判断から、まずは7/16のチケットを購入し、やはり迷った挙げ句に7/17のヘルツォークも取ってしまいまったのです。
ちょうどそれらチケットを取った後「チケットぴあ」をチラチラと覗いていたら、同じ週に「第28回 ぴあフィルムフェスティバル」が開催されることに気づき、そのプログラムには新作の公開が待ち遠しかった「群青いろ」の廣末哲万監督の未公開作品が2本も含まれているので、それがたとえウィークデーでも、やはりこれを逃したら観られない可能性もあるぞという危機感からは逃れられず、気づけば2枚とも購入……。それはつまり、その日は会社を休むことに他ならないのですが、こればかりはいたし方ありません(本当か?)。
PFFにはその他にも魅力的な作品が上映されるようで、森田芳光のデビュー2作目『ライブイン茅ヶ崎』などはかなり貴重だし、園 子温の『紀子の食卓』にも興味は惹かれ、日本ではまだ“未知の監督”と言っていい、ヌリ・ビルゲ・ジェイランの『UZAK/冬の街』にいたってはさしたる理由がないものの傑作の予感すら漂っているのですが、ただでさえその週は日曜から「ドイツ映画祭」で、20日も会社を休むのが決定しているのに、いったいどうすればいいのかわからなくなり、いっそ夏休みを随分と早めてその週は全部休んでしまいたいなどという無謀な欲求も沸いてきましたが、そういう生活を送っているからこそ、夏の“青さ”がまた貴重であることに疑いはなく、夏休みはやはりそちらに取っておこうと決め、同時に、かなり過酷な週になるであろう7月の第4週に対し、早くからコンディションを整えておこうと決意するのでした。
2006年06月05日
そりゃあ疲れるわ、と……
日曜日を一週間の始まりとするなら、先週は長短編あわせて11本の映画を観たことになります。
多くは渋谷や下北沢なので、自宅からは比較的近い距離にある劇場ではあったのですが、日々レイトショーに通うという行為を通して思ったことは、映画を観るという行為はやはり、気づかぬうちに結構体力を消耗するということ、3日の土曜日などは、そんな疲れた身体に鞭打ってジムに行ってからアテネ・フランセに急いだためか、あの貴重な『ゲアトルーズ』の上映に何とか滑り込めたのは良かったものの、程なく猛烈な睡魔に襲われ、数回気を失ってしまいました。結果、1/3程完全に意識を失っており、いったい何のためにお茶の水まで駆けつけたのかわからなくなった私は、余りの情けなさゆえに、終映後は逃げるように水道橋へと急いだ次第。悔やんでも悔やみきれません。
その影響からか、日曜日に予定していた『嫌われ松子の一生』も何となくスルーし、結局は自宅で洗濯をしたり料理をしたり酒を飲んだりゲームをしたりと、ダラダラ過ごすうちに気が付けば日曜の深夜。それなりに疲れはとれたものの、何だか消化不良な週末でした。
まぁこんな時もあらーね、と開き直ってはみるのですが、今現在観なければならない映画はやはり厳しく存在するのであり、かようにのんびりと過ごす休日もまったく悪くはないものの、そのしわ寄せは月末に近づくに従って必ず押し寄せてきて、例えば先日ソクーロフの『ファザー、サン』を見逃した時のように深い後悔へと変わることが目に見えているので、いかにその辺りのバランスを取るか、大事なのはこれかな、と思うのです。
一先ず今週もまたウィークデーに2本ほど鑑賞する予定ですが、その内1本は先週と同じアテネ・フランセなので、同じ過ちを繰り返さないよう、充分睡眠をとってから臨みたいと思います。
なお、先週終了した「笑うポルノ、ヌケるコメディ」、及び「1st Cut」に関する雑考は明日以降に更新予定です。
2006年06月02日
『ドッグ・デイズ』を観ても特に驚いてはならない現実に、私は生きている
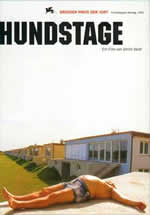 原題:HUNDSTAGE
原題:HUNDSTAGE
上映時間:121分
監督:ウルリヒ・ ザイドル
ミヒャエル・ハネケ特集の記憶も未だ覚めやらぬうちに、こうも凄い逸材がオーストリアから現われるとは。あのヴェルナー・ヘルツォークが本作の監督を激賞しているのですが、確かに未だ聞きなれぬ名前を持つこの監督、やはりあたりに衝撃を走らせてデビューを果たしつつも、もはや映画を撮らなくなって久しいハーモニー・コリンの初期作品と比べてみると、その手触りが大きく異なるような気がします。より社会的、とでも言いましょうか…。
監督の名前はウルリヒ・ザイドル。1980年にドキュメンタリー作家としてスタートした彼は、約20年を経て、長編劇映画を撮りました。それがこの『ドッグ・デイズ』という映画です。すでに国際的な評価を獲得していたらしいウルリヒ・ザイドルですが、この第2のデビュー作というべき映画は、私の想像を遥かに超えた映画であると同時に、これまでスクリーンで一度も観た事がなかったような、ある意味ショッキングというかスキャンダラスというか、そんな画面を私に見せてくれたという意味で、今のところ他のどの映画とも異なる、やや大仰な言い方をすれば、孤高の作品だと言うことが出来るかと思います。
例えば今、『ドッグ・デイズ』とミヒャエル・ハネケの作品を、その題材を巡って、あるいはそのスタイルを巡って比較したいという気持ちが無いわけではありませんが、ここではあえてそれを回避し、ウルリヒ・ ザイドル監督が撮った初の長編に対する率直な感想を書くに留めておきます。
『ドッグ・デイズ』の説話的構成自体は、それほど特異なものではありません。
ウィーン郊外の新興住宅地に暮らす数人の人物にスポットを当て、彼らが1年中で最も暑い数日間(これを“ドッグ・デイズ”と呼ぶらしいです)をいかに過ごしているのかが並行的に描かれるのですが、ほとんど繋がりの無いそれぞれの日常が、ラストに至って(消して見事にではなく)かろうじて繋がるという、言ってみればそのような構成になっています。
構成という一要素だけ抽出すれば、『マグノリア』や『クラッシュ』とさほど変わりませんし、所謂ドキュメンタリー的な表現についても、それこそハーモニー・コリンやダルデンヌ兄弟、ドグマ95の諸作品などもあり、まるで珍しくもありません。
では、『ドッグ・デイズ』のオリジナリティはどのような部分にあるのでしょうか。
実はそれをピンポイントで指摘するのは難しいのですが、私が思うに、徹底したリアリズムの中にフィクショナルな(≒映画的な)ファクターが、かなり絶妙な按配で配置されているところだと思っています。つまり、いささか乱暴な言い方ではありますが、『ドッグ・デイズ』は単なるリアリズム指向の映画に収まらず、物語るための仕掛け(言い換えれば、誰にでも了解可能な分かりやすさ)まで計算されているということです。本作で初めてフィクションに挑戦した監督が腐心したのは、恐らく、“いかに物語るか”ということだったのではないかと思うのです。
ところでリアリズムに関して言うなら、映画におけるリアリズムの多くは所詮“作られたもの”であるに違いないのですが、にもかかわらず、登場する人物や背景が、現実世界にも実在することを微塵も疑わせない演出、ここでいうリアリズムはそのような意味です。あるいは、“現実そのまま”であることなどありえないと知りつつも、“それが現実だ”と思わせてしまう演出とでもいいましょうか。そのために監督は、主要な登場人物に素人を起用しているし、劇映画らしからぬ、あまりにとるに足らないが故にいやおうなく“リアル”足らざるを得ない日常描写を、ほとんど反=映画的ともいえる姿勢で積極的に取り入れていくのです。その意味でも、ウルリヒ・ザイドルはかなりしたたかな戦略家かもしれません。
さて、では『ドッグ・デイズ』という映画におけるフィクショナルな部分とはどこを指すのか。それは、ウィーンの郊外に住んでいるという点を除けばそもそも互いの関係性など無いに等しいそれぞれの登場人物が、それがフィクションであるが故に、ある状況や装置を介して相互に絡み合っていくという説話構造です。改めて言うまでもなく、フィクションの構造自体に偶然が介入する余地はないのですが、本作においても、物語の進行とともにそれぞれの日常は相互に緻密に計算された接点を持っていき、そしてラストの雨においてそれらが控えめながら統合されるのです。そう、あの“雨”の存在こそがこの映画のフィクション性を際立たせていると思います。ちょうど『マグノリア』で突如降ってくる“蛙”のように、“雨”もまた等しく彼らのもとに降り注ぐ。しかしそれが分かりやすい答えを導き出す“雨”でないことも、ウルリヒ・ザイドルの倫理だったのでしょう。
つまり『ドッグ・デイズ』は、細部は徹底的にリアリズムに拘りつつ、換言すればドキュメンタリー的な演出を用いつつ、その構造は極めてフィクショナルな映画だということです。インタビューを読むと、監督は順撮りに固執したようですが、それはどこかで物語が異なる方向に飛翔する可能性に、常に意識的だったからではないでしょうか。そういう自由度はドキュメンタリー的と言えるでしょうし、納得いく太陽が出るまで撮影を中断したり、酔う演出では本当に酒を飲ませ、暑がる演出ではヒーターで周囲の気温を上げるという、言わば俳優達の体調まで操作しようとするリアリズムは、まさに物語に貢献させると言う意味で非常にフィクショナルでもあります。このあたりのバランス、曖昧さと厳密さとのバランスにこそ、本作のオリジナリティが認められると思うのです。
かようにして“いかに物語るか”を突き詰められた『ドッグ・デイズ』に、私は、厳密なドキュメントが普遍的な物語に変わる様を感じることが出来ました。あの登場人物のいずれかが、仮に自分だったとしても一向に不思議ではないという感覚。彼らの日常は一見、非=日常的でありながらも、実はあれこそが現代の都市に生きる人間の日常に他ならないということ。実際、私が生きている現実が、あの異様に映りもする光景と、いったいどこが違うというのか。彼らもまた社会に生きる人間であり、我々同様、嫉妬や恐怖や虚無や憎悪や悲しみや愛おしさという、誰もが持つ感情を共有しているのです。
つまり私は、『ドッグ・デイズ』を観ても驚いてはならない現実に生きているということなのでしょう。
『ドッグ・デイズ』は、優れて批評的にあるいは倫理的に、それを教えてくれるのです。
2006年06月01日
『あんにょんキムチ』、宙吊りのアイデンティティに向き合うこと
 原題:あんにょんキムチ
原題:あんにょんキムチ
上映時間:52分
監督:松江哲明
本作は公開当時(1999年)当時21歳だった松江監督が、今は亡き(と書かねばなりません)今村昌平が開校した日本映画学校の卒業制作として撮った処女作です。韓国系日本人が、祖父の生き様を知っていくことで自らのアイデンティティと正面から向き合っていくというこのドキュメンタリー、私はまず、そのタイトルに興味が惹かれました。“あんにょん”とは、“こんにちは”という挨拶を意味しますが、韓国語に限らずその他の外国語にもよく見られるように、それはそのまま別れの挨拶、つまり“さようなら”という意も兼ねています。キムチが大嫌いな松江監督の、韓国という国に対するアンビバレントな感情が、この二重の意味を持つタイトルに端的に表わされていると思ったからです。
松江監督の妹が全編にわたってナレーションを担当し、この家族のバックグラウンドや現況を淡々と説明する手法は観ていて分かりやすく、その声のトーンも作品の雰囲気に合っていました。一通りの家族紹介が終った後、監督である兄の紹介になるのですが、この時、自分の部屋で確かカップラーメンのようなものを食べながら、テレヴィ画面に映る映画を熱心に観ている姿に奇妙な親近感を感じ、そういえば自分も21歳くらいの時はこんな感じだったなぁ、などと思いながらちょっと笑ってしまった次第です。もちろん監督はその時カメラの存在を知っていたはずですが、あの演出(とあえて言わせてもらいます)に漂うリアリティには説得力がありました。
演出と言えば、監督が妹と2人きりで語らう場面が本当におかしくて、とりわけ質問者である監督が、妹のあっけらかんとしていながらも妙に的確な意見に対し、自身の曖昧さ故か、監督のほうから望んだ対話が次第に空転していかざるを得ない様は“演出ならざる演出”と言うほかなく、監督自身の出自に対する不確かで説明しがたい感情が画面に滲み出ていて感動しました。そしてそれが一度だけでなく、後半にもう一度繰り返さ、やはり同じような結果になるあたりにも。
ともに暮らす父や母、未亡人となった祖母から、3人の叔母、祖父を知る友人へとインタビュー重ねていくうち、次第に明らかになっていく祖父の人間性。同時に、臨終に際し「哲明バカヤロー!」と言い放って死んでいった祖父への、怠惰や無理解から生まれた拭いがたい贖罪の意識を真に思い知ることになった松江監督が、久々に酒を飲んで酔った帰り道で「あの素晴らしい愛をもう一度」を歌い涙する場面は、松江哲明個人としての意識と、泣き崩れる自分の姿までも手持ちのビデオカメラに収めようとする監督としての意識とが拮抗した、本作の中でもっとも美しい場面でした。街頭の明かりだけの薄暗さで、しかも、泣きながらカメラを持っているがゆえにぶれまくる画面にもかかわらず、そこには画面の審美主義とは遠くはなれた美しさが確かにあったのです。
松江監督は、韓国の田舎にある祖父の故郷にまで赴くことで、それまで意識的に宙吊りにしてきた自らのアイデンティティに対し、一応の結論を出したかのようでした。“一応の”としたのは、同じ在日コリアンである彼の親類縁者にたいする最後のインタビューとその答えとなる身振りが、その簡潔さと表情の明るさに比して、深い問題を提起していたようにも思えたからです。2つの国旗のどちらかを選び振らせるということ。しかしそこに暗い影はなく、彼らは極日常的な表情でそれに応じています。彼らはこれまでも、そしてこれからもそのように生きるという決意が微笑ましく画面を充実させている様に、ついつい観ている私の表情も緩んだのでした。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]



