2006年05月31日
必見備忘録 2006.6月編
とうとう観る事が叶わなかった『ファザー、サン』に関する文章の一切を、今後は読まないことにいたします。どこかで上映される機会があれば無論駆けつけたいと思いますが、5月は観るべき映画が多すぎたため、限られた時間を有効に使うためにはどうしても作品に個人的で残酷なプライオリティをつけざるを得ず、その中でこうした作品が漏れてしまうしか無かったという事実に、とりあえずはため息を漏らすしかありません。この落とし前は、すでにかなり話題になっているので黙っていても『ファザー、サン』より客入りが見込めるであろう『太陽』の初日に駆けつけるくらいではつかないでしょう。
しかしながら、シネマヴェーラ渋谷のラディカルなプログラミングにより長らく観たかった『エロ将軍と二十一人の愛妾』や『徳川女刑罰絵巻 牛裂きの刑』をついに観る事ができた喜びは一入でした。
『ダヴィンチ・コード』や『アンジェラ』といった話題作も積極的に観なければならないとは思いますが、「神代特集」すら一本も観られていない今、第三者に強引に劇場まで手を引っ張っていかれない限り、もはや自力では行けそうにありません。
そんな5月に続く6月も、どうやら忙しくなる模様。どうなることやら……
『家の鍵』(上映中)
(岩波ホール 11:30/14:30/17:30〜19:25)
『嫌われ松子の一生』(上映中)
(シネクイント 10:30/13:20/16:10/19:00〜21:30)
『夢駆ける馬ドリーマー』(上映中)
(渋東シネタワー 11:30/13:55/16:20/18:45〜20:45)
『ダック・シーズン』(上映中)
(シアター・イメージフォーラム 12:50/14:50/16:50/18:50〜20:35)
『インプリント ぼっけえ、きょうてえ』(上映中)
(シアター・イメージフォーラム 21:30〜22:38)
『ビッグ・リバー』(上映中)
(テアトル新宿 11:30/14:00/16:30/19:00〜21:05)
『アンリ・カルティエ=ブレッソン 瞬間の記憶』(上映中)
(ライズX 12:05/13:55/15:45/17:35/19:25〜20:50)
『ロシアン・ドールズ』(上映中)
(シャンテ シネ 10:35/13:25/16:20/19:10〜21:35)
『花よりもなほ』(6/3〜)
(渋谷シネパレス 10:00/12:40/15:20/18:00/20:40〜22:55)
『≒天明屋尚』(6/3〜)
(ライズX 21:20〜22:40)
『セキ★ララ』(6/3〜)
(シネマアートン下北沢 21:00〜22:23)
『ココシリ』(6/3〜)
(シャンテ シネ 10:25/12:40/14:55/17:10/19:25〜21:10)
「映画の授業 part.1 part.2」(〜6/10)
(アテネ・フランセ文化センターにて)
「フランス古典映画への誘い」(6/6〜7/2)
(東京国立近代美術館フィルムセンター、東京日仏学院にて)
「生と死と、エロスの輪舞 田中登の官能美学」(5/27〜6/23)
(ラピュタ阿佐ヶ谷にてレイトショー 6/10(土)〜16(金)『人妻暴行集団致死事件』 6/17(土)〜23(金)『(秘)色情めす市場』)
「黒沢清による「絶対に成熟しない」KUROSAWA映画まつり」(6/3〜6/30)
(シネマヴェーラ渋谷にて)
『家の鍵』はどうも場所的に行きづらく足が遠のいておりますが、何とか。
『嫌われ松子の一生』はどうでしょう。賞賛の声が多いようですが……若干の不安を抱えつつ。
『夢駆ける馬ドリーマー』は馬が出てくるという以外に理由はありません。
『ダック・シーズン』は南米で撮られ、モノクロで、ジャームッシュやカウリスマキに比されていると言う点で、嘗て観た佳作『ある日、突然』とシンクロしたため。
『インプリント ぼっけえ、きょうてえ』がすでにテレヴィで放送されていたとは知りませんでしたが、今回は完全版の上映ということと、アメリカで上映禁止になったという、いつもながらのスキャンダリスト・三池に対する敬意として。
『ビッグ・リバー』はその監督の文章に触れ、大いに興味が涌いてきたため。
『アンリ・カルティエ=ブレッソン 瞬間の記憶』はかなり盛況のようで。先日通りかかったら、ライズX前にチケット完売との張り紙がありました。映画としてより教養として観ておきたい作品。
『ロシアン・ドールズ』は未だまともに観た事がないセドリック・クラピッシュ作品ですが、そろそろ観ないとまずいだろうなぁ、ということで。
『花よりもなほ』は是枝作品であれば行かないわけにはいかないという理由で。
『≒天明屋尚』には、映画好きというより絵を描くのが好きな一個人として興味があります。
『セキ★ララ』は松江監督の旧作2本を観て、その出来栄えに感心したため。
『ココシリ』は東京国際映画祭の時から気になっていたのですが、予告編で駄目押しされたので。
その他4つの特集上映がありますが、そちらも新作同様の心構えで臨みたいと思います。
2006年05月30日
「1st Cut〜映画美学校セレクション」その1
昨日はユーロ・スペースで開催中の「1st Cut〜映画美学校セレクション」に参加してきました。「1st Cut」についてはリンク先を参照していただくとして、この特集上映の本編は、どちらかと言えば6/3から始まるプログラムの方なのでしょうが、私としては、嘗て上映された作品の中で見逃したものや印象深かったものを再見することを目的としているため、とりあえずは現在日替わりで上映されている旧作のほうに重点を置いて鑑賞しているというわけです。
昨日観た作品は下記の通りです。いずれも私にとっては広義の“ファンタジー”に属するものでした。
・『犬を撃つ』(監督・脚本:木村有理子 1999/16mm/32分)
・『蘇州の猫』(監督・脚本:内田雅章 2001/16mm/33分)
・『MySweetPlanet』(監督:瀬々敬久 脚本:齊藤有希 2003/19分/16mm)
『犬を撃つ』の主演は、今や監督として活躍している堀江慶氏でした。記憶と現実が交錯するファンタジーと言えば分かりやすいのですが、ところどころホラー的なテイストもあり。私にはラストがやや難解でした。
『MySweetPlanet』はこれまたファンタジックなピンク映画ということで、一箇所で思わず笑ってしまった次第。女性器を真正面から捉える場合、あのような手段が残されていたとは…意表をつかれました。
そして『蘇州の猫』。実を言えば、昨日はとにかく『蘇州の猫』をもう一度観たいという思いのみで駆けつけた次第。2度目を鑑賞して細部を確認出来たこと、そして、前回以上に感動出来たことが大きな収穫でした。これこそ真のファンタジーだと快哉を叫びました。ここにはほとんど魔術的な魅力すら漂っているかのようです。本作については、今度こそ作品評を書きたいと思っています。
この特集上映には明日も参加予定です。
本当は本日も参加するつもりでしたが、急遽予定を変更、シネマアートン下北沢で公開中の松江哲明監督の旧作2本立てに行ってきます。
2006年05月29日
まるでタイプの違う3本、いずれも大いに楽しむ
先週は3本の映画を観ました。
土曜日にほとんど思いつきで観た『かもめ食堂』は噂に違わぬ佳作、立ち見、とまでは行きませんでしたが、ほぼ満席だったようです。客層も幅広く、こういう誰が観ても面白い邦画が年に12本公開されれば、観客数も随分増えるのではないだろうかと安易に考えてはみたものの、いや、そんなに単純ではないな、とやはり思考を改めた次第。
『かもめ食堂』を観た所為で、予定していた「ギィ・ブルタン展」には行かれずじまい。わざわざロメールのヴィデオを3本も抱えてきてくれたこヴィさん、すいませんでした。近く渋谷ででも会いましょう。
さて日曜は以前から決めていた特集上映「笑うポルノ ヌケるコメディ」より『徳川女刑罰絵巻 牛裂きの刑』と『(本)噂のストリッパー』を朝一番の2本立てで。こちらは当然のことながら『かもめ食堂』の時とは打って変わって、15人程度しか埋まっておらず、個人的にはべストな状態で鑑賞出来ました。
2本のうち、目当ては『徳川女刑罰絵巻 牛裂きの刑』のほうでした。この映画は、嘗て「封印されるということ〜『放送禁止映像大全』を読んで」という記事にも書いたように、ソフト化もされておらず、観る事が困難な作品でした。常軌を逸した拷問の連鎖により、ほとんどギリギリで作品が成り立っているという本作が、ただのスナッフフィルムと見做されて我々の目から遠ざけられてきたようなのですが、実際に観てみると、これがなかなかの出来栄えで、その強引な二部構成や残酷描写など、例えるなら、アレハンドロ・ホドロフスキーの怪作『エル・トポ』を想起させる面白さ。日曜の午前中に相応しい映画かと言われれば閉口するほかありませんが、『エル・トポ』という言葉に反応した方は、本日、あるいはこの特集上映の最終日である6/2に、是非ともシネマヴェーラ渋谷まで足を運んでいただければと思います。
ところで今週からもう6月に入ります。5月はあまりに観るべき作品が多すぎて、ほとんど“底抜けてんやわんや”という状態でしたが、6月はどうでしょうか。絶対に外せないアテネ・フランセ「映画の授業 part.2」や「1stCUT ver.2005」がありますが、スケジュールはまた別途ということで。
2006年05月24日
『亀も空を飛ぶ』は“映画”に他ならないという至極当たり前の結論を出したい
 原題:TURTLES CAN FLY
原題:TURTLES CAN FLY
上映時間:97分
監督:バフマン・ゴバディ
『亀も空を飛ぶ』は昨年からずっと観たいと思っていた作品で、すでに2度、鑑賞のチャンスを逃していましたが、この度ユーロ・スペースの「バフマン・ゴバディ特集」でやっと鑑賞出来ました。実は私、客がほとんど入っていないレイトショーを好んでいるのですが、この映画を10数人しかいない観客の一人として観られたことを、非常に幸せだと思いました。
本作を観て直感的に感じたことが3点あります。まず、空が画面の半分を占める映画だということ、もう一つは、泣き叫ぶ子供の映画ということ、そして最後は、人が振り返る映画だということです。事実のみこのように書くと、何とも味気なく、およそ本作には似つかわしくないなどと言われそうな、ほとんど温もりを欠いた文章と取られるかも知れませんが、誤解のないように言い添えれば、私はこの3つの特質にこそ心を揺さぶられたのです。仮に本作が、その宣伝文句にあったように“叙事詩”的であったとするなら、私の印象が叙情的なものではなく、叙事的なそれであったとしても、本作を貶めていることにはなりません。むしろ、私はこのクルド映画を心から賞賛したいほどなのです。
バフマン・ゴバディ監督作品は初めて観ました。私はクルドの歴史や現状をほとんど知らぬまま鑑賞したのですが、優れた映画とは、その背景にどれほどの過去(あるいは現在)があろうとも、例えば超ロングで切り取られた岩山の斜面や息を飲むような青空一つで、例えば純朴ながらも紛れもなく“子供であることを超えている”人物の顔一つで、例えば強い拒絶感を示し毅然として前へ前へと進もうとしつつも、背後に微かな連帯や愛を感じ取ってしまったが故に振り返るという動作でそれに応えようとする少女の動きと視線一つで、画面の背後に厳然として横たわる歴史や現況をあっさりと無効化し、まさに眼前の画面そのもので観客を感動させることの出来る映画だと常日頃思っている私にとって、いかにクルドという土地に関して無学であろうともそんなこととは関係のない次元で、『亀も空を飛ぶ』はほとんど傑作と言える出来栄えだと思いました。
私は本作をドキュメンタリー的だとは思いませんでした。難民である少女・アグリンが絶望の内に自死する様を、冒頭とラストとに分割してみせる手法などは非常に映画的でもあり、随所にちりばめられたちょっとした笑いもまた、この悲劇的な物語を物語ろうとする監督の、説話的なテクニックだったのだとも思うのです。ほとんどのカメラはFIXで、かつ、幾度か観られた美しいロングショットの存在は、手法としての所謂(狭義の)ドキュメンタリー的撮影技法からは遠いものだったように思うのです。
しかし、にもかかわらず、と言わねばなりません。にもかかわらず、あの子供たちの、演出とは思えないような豊か過ぎる表情、全身に力が漲っているかのような疾走、そしてあの涙の生々しさはいったいどういうことでしょうか。まるでその現場に立ち会っているかのような感覚に、私は少なからず驚きました。それは確かにドキュメンタリー的だと言えるのかもしれませんが、さらに言うなら、それこそが“映画”というものなのかもしれません。
映画館で“映画”に値する作品を観た。今私に出来るのは、この当たり前の結論を“叙事的に”出すことだけなのです。
2006年05月22日
生まれて初めての“まともな”ベッドが、私の生活を変えつつある…
一人暮らしを始めて早や9年。
私は自宅にいるのがほとんど趣味みたいなものですから、インテリアにもそれなりの拘りがあるのですが、にもかかわらず、これまでベッドというものを購入したことがありませんでした。
その最大の理由は、ズバリ、場所を取るからなのですが、では、9年間いったいどんな物体に寝ていたのか。いくらなんでも床に直で寝ると言う選択肢はなかったので、何らかの寝具を使っていたわけですが。
所謂ベッド以外の寝具で、私が自宅に置いてもいいと思うためには、それが“片付けられる”ものでなければなりませんでした。その一点にのみ拘った挙げ句、最初の2年間はエアベッドなる代物を購入したのです。これはその名の通り、空気で出来たベッド(のようなもの)で、その構造上、非常に脆い。そして、人が来た時に片付けることが出来たのが唯一の存在意義だったこのエアベッドの寝心地は、当たり前ですが決して良いとは言えず、それが手動であろうと電動であろうと、膨らませる際の心的・物理的ストレスは予想以上で、とても都市生活者とは言えない奇妙に原始的な生活を強いられてきたのでほとほと嫌になり、結局はその部屋までも引き払うことにしたのです。別に部屋自体はいたって普通だったのですが、まぁあくまで全体感として嫌になったということで。
次に引っ越した部屋の最大の利点は、予め部屋の壁にベッドが内蔵されていたことです。
ガチャーン!…ガッチャーン…!!と仰々しい音を立てながら壁から姿を表すその内蔵ベッドには、もちろんマットレスと呼べる代物は装着されておらず、申し訳程度の万年煎餅極薄シートみたいなものがペタっとくっ付いているのみ。ほとんど鉄の骨組みの上に一枚の木を置いたような、そんな“ベッドらしからぬ”ベッドだったのです。まぁしかし、やはり普段は仕舞っておくことが出来るし、ベッドを仕舞ってしまえば、もうテレビとテーブルくらいしかないガランとした部屋だったので、しょっちゅう友人を呼ぶことが出来たのは幸いでした。そんな生活が4年ばかり続き、さてそろそろ引っ越すかなと、今住んでいるマンションを探し当てるのですが……
今の部屋はこれまでに比べいくぶんか広いので、そろそろちゃんとしたベッドでも買うか…と多少は考えましたが、やはり“慣れていない”のでしょう、またぞろ性懲りもなくエアベッドを購入、その終焉に際して、このような出来事があったのを既に読んだかたもいらっしゃるかと思います。
というわけで、多少はまともな睡眠を得るため次に購入したのは、3つに分離可能なマットレスでした。普通のマットレスと違って、これまた“片付けることが出来る”という点に拘った結果です。どうやら私は、それほどまでに部屋に家具を置くのが嫌だったということでしょうか。ともかくそのマットレスは、その通気性ゼロの構造的欠陥だけに眼をつぶれば、まぁまぁ快適な睡眠を提供してくれました。ある時は座布団のように、ある時はソファのように変幻自在なファブリックとして、それは活躍してくれもしました。しかし、例えばたまにホテルの大きなベッドに寝たりだとか、映画で男女がベッドに横たわっている絵を幾度となく見たりだとかするうち、今はどこの家にも当たり前のように存在するベッドというものに対する羨望が9年以上かけて徐々に高まっていたのでしょう。つい先日、とうとうベッドを購入する決意をしたのです。
先週の金曜日に届いたそのベッドのために、半日かけて部屋の模様替えをし、ベッドカバーやらベッドシーツやら、私にとってはほとんどありえなかった、クッションなども購入してしまう始末、“まともな”ベッドの導入がこれほど私の生活に変化を与えるとは思ってもみませんでした。その快適さは、これまでの私の睡眠を全否定しかねないほど。その代わり、ベッドに寝転がって観るエリック・ロメールはなんて素晴らしいんだ、ベッドに寄りかかって観るアニエス・ジャウィはまったく悪くない、などとほとんどこじつけとしか思えない喜びを齎してくれました。誰がどう観ても『夏物語』は素晴らしいし、誰がどう観ても『みんな誰かの愛しい人』は悪くないというのに……。
そんなこんなで先週末は、若干映画館からは遠ざかっていました。とにかく家に、いや、“ベッドのある”家にいたかったので。というわけで劇場で観たのは『ナイロビの蜂』1本のみです。最後にとってつけた感じがしないでもありませんが、この映画、なかなかの力作だったことを付け加えておきます。レイチェル・ワイズ好きであれば迷わず劇場へ、程よく省略された“ベッドシーン”だけでも必見でしょう。
2006年05月18日
『夜よ、こんにちは』、マルコ・ベロッキオはファンタジスタである
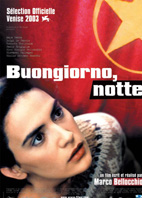 原題:BUONGIORNO, NOTTE
原題:BUONGIORNO, NOTTE
上映時間:105分
監督:マルコ・ベロッキオ
イタリア現代史における重大なテロ事件である、「赤い旅団」によるアルド・モロ元首相誘拐殺人は、マルコ・トゥリオ・ジョルダーナの『輝ける青春』においても間接的に描かれていましたが、この2人の映画作家の視点は大きく異なっています。もっとも、『輝ける青春』ではソニア・ベルガマスコ演じるジュリアが、テロリズムに傾倒していく過程と、投獄を契機に改心し改めて家族というものを見直していく様子に重点が置かれ、「赤い旅団」そのものに関して多くを語っているわけではありませんでしたが。
どちらかと言えば、60年代後半以降のイタリア現代史という逆らいがたい大流がまずあり、それに翻弄されつつもなお失われることの無い普遍的な愛や友情を、ある“家族”のを通して描こうとした『輝ける青春』は、“政治を間接的に取り込んだ青春映画”だと思っているのですが、一方の『夜よ、こんにちは』は、「赤い旅団」の内部から、その中で唯一の女性テロリストであるマヤ・サンサの人間性の変遷を通して歴史的な事件を対象化したと言う意味で、“青春の痛みを政治的に描いたドラマ”ではないか、と。ここで言う“政治”という言葉を用いたのは、内部と外部それぞれの相互干渉的な関係性が主題になっていたと思われたからです。あるいは、歴史や事件として政治を取り上げるというより、ドラマそのものが帯びる政治性が際立っていたということでしょうか。
本作において驚くべきは、マルコ・ベロッキオのあまりに独創的な語り口です。この“政治的”事件が主に、テロリストとしてのマヤ・サンサの瞳の揺らぎを媒介として語られるところが素晴らしい。マヤ・サンサの大きな瞳は、何より雄弁に彼女自身を語ります。とりわけ印象的だったのは、モロ首相を演じたロベルト・ヘルリッカが監禁される小部屋を、小さな覗き穴から凝視するマヤ・サンサのクローズアップです。その瞳には、彼女の中に渦巻くカオティックな感情が込められていたと思うのです。
主要な舞台である、とあるアパートの一室、あの限定的空間の内部と外部。さらに、そのアパートの中に設けられた監禁部屋の内部と外部。そしてマヤ・サンサ自身の内部(心情)と外部(行動)。それらが相互に干渉しあう時、そこには繊細極まりないサスペンスが生起し、それを観ている観客はただそのサスペンスに息を飲むほかありません。そしてサスペンスといえば、マヤ・サンサが働く図書館の螺旋階段とエレヴェータもまた実にサスペンスフルな場として描かれていたことが思い出されます。中盤で繰り返し登場する、エレヴェーター内部からその外部に向けられたカメラの視線が、遂にその内部へと切り返される瞬間には文字通り手に汗握ってしまったし、後半で図書館に警官がどっと押し寄せた時、それを発見したマヤ・サンサが逃げるように螺旋階段を下りていく描写と彼女を追っているかのような警官達とのカットバックにもまた、高度に映画的なサスペンスが画面を支配していたと思います。そう、本作はまさにサスペンスそのものだったと言ってもいいかもしれません。
そしてラストシーン。テロリストとしてのイデオロギーが時間軸とともに揺らいでいくマヤ・サンサが最後に見たものは、「赤い旅団」から開放されたモロ首相が、霧雨の中を歩いていくイメージでした。それはもちろん、現実にはありえなかった幻影に他なりません。彼女が夢想した現実と目の前に横たわる真の現実の差異が生んだあの光景は、例えば、モロ首相が物語のラストで無残に殺されるシーンを見せる正攻法に比べ、より残酷ですらあったと思います。それが幻に過ぎないという現実が、最後の最後に示されることになるからです。しかし同時にあのイメージは、何と美しいファンタジーとして私の目に映ったことか。そこには肯定や否定を超えた、まさに映画ならではの“夢”としか形容できない何かがありました。陰惨な歴史的事件を題材にしつつ、マルコ・ベロッキオはその緊張感極まる物語の最後に、ふと現実ではない、もしかすると“起こりえたかもしれない”光景を紛れ込ませたのです。
このシークエンスを観て感じた新鮮な驚きは、マルコ・ベロッキオを映画のファンタジスタだと確信するに充分でした。私はマルコ・ベロッキオの旧作を全て、たとえ一生かかってでも何としても観なければならない、そのようにも決意するのでした。
2006年05月15日
これで何回目だろう…?
すでにご存知の方も多かろうと思いますが、とりあえず何度目かのマイナーチェンジを完了いたしました。今回もまた、アーカイブ関連です。これまではあるカテゴリーをクリックすると、そのカテゴリーに含まれるエントリーが全文表示されてしまっていました。嘗ての私の文章は長いものが多く(だからと言って現在それが改善されているとは言えません)、いきおい、カテゴリーアーカイブの読み込みにやや時間が掛かっていました。そこで、今回からは、アーカイブに一覧を持たせることで、それを回避した次第。
かといってこのマイナーチェンジによって格段に使いやすくなったのかと言えば、これがもう一つといわねばなりません。というのも、個別エントリーへの一覧が出来たのは喜ばしいものの、私の映画評以外の文章はタイトルを読んだだけでは一体何について書いてあるのか非常にわかりづらいからです。各エントリーの冒頭くらい読むことが出来、その上で“さらに読む”というリンクがあったほうがより親切と言えば親切なんですが、そもそも私は“追記”という機能を一度も使ったことがないので、そのようにするためには、全エントリーを事実上書き直さなければなりません。毎日暇で暇でしょうがないというわけではない一介の会社員である私には流石にそんなことをやってられず、止む無くこのような形に落ち着いたという感じです。
さて、実はもう一点変更したことがあります。
当ブログはどうやらスパム業者にとって喜ばしいつくりになっているらしく、最近などは日に100件程のスパムコメント/トラックバックを一方的に受けるという、全く持って悲惨な状況でした。それでも何とか見つけては削除という行為で対応していたものの、そろそろ体力(我慢)の限界!ということで、今後はひとまず、コメントのみ、承認制にしたいと思います、というかすでにそうなっているはずです。
ただし、基本的にスパム以外のコメントにつきましては、普通に掲載していきますので、ご心配なく。いちいち内容を確かめたりもせず、基本は機械的に掲載という感じになりますので。コメントされる方にとっては、表示されるまでに若干のタイムラグが生じてしまいますが、これもスパムが落ち着くまでの一時的な処置ですので、どうかご了承くださいますよう、宜しくお願いいたします。
というわけで、先週も映画のほうはぼちぼち。ヴィデオを含め4本ほど観ましたが、詳細はまた追って。
悩みのタネが2つほど減りましたので、向こう数日間は映画評に専念したいと思いますが、そうはいいつつも実は今現在、ドラクエのスピンオフゲームをやっている最中でして、これがまたとんでもなく狂暴なゲームなのでこちらにも本腰を入れざるを得ず、それは例えれば「ドラクエII」ばりに狂暴だということになるその新作ゲームをクリアするまでにはあと数週間ほどかかるかもしれないので、かなり興味深かった作品についてもあまり長文を書くことが出来ませんが、読む方にしてみれば、その方が簡潔でわかりやすいしむしろありがたいくらいだ、と思うのかもしれず、だったらとりあえずその要望に応えてやろうじゃあないか、といささか複雑な気分で強引に納得しているところです。
2006年05月11日
『ブロークバック・マウンテン』については黙して語らず
原題:BROKEBACK MOUNTAIN
上映時間:134分
監督:アン・リー
とりわけ大きな期待を寄せていたわけではないのですが、鑑賞後に感じた正直な感想は、長い割りにはどうにも食い足りないというものでした。4人の主要キャストの好演は疑うべくもないのですが…
アン・リーの演出は的確だったと思います。2人のバックグラウンドやそれぞれの性格も簡潔に説明されていたし、この物語ではどうしたって添え物でしかないそれぞれの妻を演じたミシェル・ウィリアムズとアン・ハサウェイにも、特に文句をつける部分はありません。
実は私、珍しく(?)物語のみを追ってしまうという観方をしてしまったのかもしれません。それというのも、ブロークバック・マウンテンを舞台にした冒頭の数十分に、その背景の美しさにもかかわらず退屈だと感じてしまったがゆえに、最後までほとんど漠とした感覚のまま機械的に観てしまったので、画面の連鎖やショットの強さ、抒情性や叙事性などに対する感性をまるで働かせることが出来なかったのです。そして、この風変わりな西部の物語“のみ”をひたすら消化していった結果、およそ賞賛とは程遠い複雑な気持ちになってしまったというわけです。
もちろん、ただ物語“だけ”を追いかけたって滅法面白い映画が存在するということも経験から知っています。つまり、私はこの『ブロークバック・マウンテン』という映画が好みではなかったということなのでしょう。その証拠に、漠とした私の感覚を一瞬でも目覚めさせる瞬間が、本作にはなかったからです。ミシェル・ウィリアムズとアン・ハサウェイが共に体を張ったあのラブシーンですら(2人が共に裸体を晒したこと自体は強く肯定したいと思いますが)。
どうして本作にほとんど乗れなかったのか、その理由も未だ判然としないのですが、まぁ積極的に本作を貶めたいとも思わず、つまりここは、黙して語らずという手段を半ば強引に選びたいと思います。
2006年05月08日
「イタリア映画祭2006」雑感
 今年初参加となった「イタリア映画祭2006」、全12作品中私がセレクトしたのは3本。実は少なく見積もっても後2本は観たい作品があったのですが、どうにもあの会場のあの雰囲気になじめず、流石に連日通うのも辛いなと思ったので。
今年初参加となった「イタリア映画祭2006」、全12作品中私がセレクトしたのは3本。実は少なく見積もっても後2本は観たい作品があったのですが、どうにもあの会場のあの雰囲気になじめず、流石に連日通うのも辛いなと思ったので。
偶々開会式に出席する機会を得たのですが、数人いたゲストの中に、あの(!)マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督や、あの(!)ジュゼッペ・ピッチョーニ監督や、あの(!)サンドラ・チェッカレッリが紛れ込んでいて思わず声を上げそうになるほど驚いた次第。とりわけ、ちょうど『輝ける青春』のdvdを購入し再見した直後だったこともあり、やや大柄でベージュのスーツを着込んだマルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督に見入ってしまいました。右の写真ではわかりにくいのですが、右端にいるのが彼です。
さて、以下簡単に3作品の雑感を書いておきたいと思います。
■私が望む人生(La vita che vorrei/2004年/125分/監督:ジュゼッペ・ピッチョーニ)
主演する2人は同じでも、前作『ぼくの瞳の光』とはかなり違った印象の本作。それは“劇中劇”というスタイルがとられているからなのかもしれません。特に際立っていたのが、現実と虚構の境界を逢えて曖昧にした構成でしょうか。劇中で演じらる役は19世紀が舞台なのですが、目に見えない心情が現実のそれであるのか、あるいはあくまで役を演じているだけなのかという部分を、繊細に描き出していたように思われます。ルイジ・ロカーショの演技はほとんど申し分なく、彼ほど髭のある姿と無い姿に落差がある俳優もそうはいないのではないかと思いました。サンドラ・チェッカレッリは個人的に非常に好みなので何とも言いがたいところですが、『キングス&クイーン』のエマニュエル・ドゥヴォスのように素晴らしかったとだけ書いておきます。
■13歳の夏に僕は生まれた(Quando sei nato, non puoi più nasconderti/2005年/115分/監督:マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ)
マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ作品は3本しか観ておりませんが、彼が描く“出会い(再会)”や“別れ”の場面は本当に心を揺さぶられる思いで、例えば本作において、遭難しかけた息子が救助された施設から仲間に見送られながら去るシーンだとか、その後、父親の友人夫婦との再会に涙ながらに抱き合うシーンだとかに何故あれほど心を動かされるのか、本当に不思議なほどあっさりとしていながら抒情を超えた何かがそこにはあるような気がしていて、未だそれが何であるのかはわからないままですが、一方で彼は、ネオレアリズモのように、というと若干語弊があるのかもしれませんが、非常に硬質で冷たい画面をも同じ作品に紛れ込ませることに長けていて、それはこの映画の終り方にも関わってくるので詳述はしませんが、とにかくグイグイと作品に引き込まれる感じがしました。これは一般公開もされますので、未見の方は是非。何人かのキャストが重なっていながら、『輝ける青春』とはまた違う感動がありました。
■瞳を見ればわかる(Te lo leggo negli occhi/2005年/82分/監督:ヴァリア・サンテッラ)
上記2作品は監督で選びましたが、本作は私にしては珍しく、主演女優で決めました。とはいっても、ステファニア・サンドレッリをこれまで積極的に観ていたわけでもなかった私ですが、すでに60歳を超えた彼女の余りに堂々としたイタリア女優ぶりは、それだけで私の目を惹き付けるだろうという予測はほとんど正しかったと思いました。監督はヴァリア・サンテッラ 。処女長編ということでしたが、なるほど、どことなくモレッティ的だったかもしれないとしたり顔で言ってみたくなるほど、82分という絶妙な上映時間で程よくまとまっていた作品でした。
ともあれ、今は東京でもイタリア映画が普通に公開される機会はそれほど多くはないので、イタリア映画好きとしては、また来年も参加することになりそうです。なお、今回私が観た作品はすでにdvd化されているようですので、イタリア語が聞き取れる方はそちらで観る機会も残されています。
2006年05月06日
たとえ拙いリメイクでも、『ロンゲスト・ヤード』は今観られるべき映画である
 原題:THE LONGEST YARD
原題:THE LONGEST YARD
上映時間:114分
監督:ピーター・シーガル
昨年鑑賞した『フライト・オブ・フェニックス』に続き、2年連続でロバート・アルドリッチのリメイクを観られるということが果たしてどれだけ幸福なのでしょうか。こちらとしては、観る前からどうしたってアルドリッチのほうが面白いに決まっていると思い込んでいるし、配給側も、ハリウッドメジャー作品であるにもかかわらず東京での上映が3館のみという、一体誰が本作の興行収入に期待しているのかわからないような扱いなので何だか哀れにも思えてくるという始末なのですが、仮にもアルドリッチのリメイクである以上、『フライト・オブ・フェニックス』程度に楽しませてくれるなら、金を払う価値はあるだろうという思いから、劇場にかけつけた次第。
個人的に、リメイク作にオリジナルのキャストが顔を出すというのがあまり好きになれず、それは確かにオリジナルへのオマージュと言えなくもないのですが、大方は老齢に差し掛かったオリジナルのキャストが、それほど大きな扱いというわけにもいかずに画面に登場しなければならないことが果たして幸福なオマージュ足りえるのかという疑問がいまだに消えません。オリジナルの主人公であるバート・レイノルズは本作において、どうやら2005年度のラジー賞・ワースト助演男優賞にノミネートされたらしいのですが、オリジナルから30年以上も経った今彼を担ぎ出して、ワースト助演男優賞にノミネートするなど、あまりに生真面目すぎて苦笑も出来ず、いっそのことどこかの映画祭で助演男優賞くらい与えたほうが、本人にとってもよほどダメージが大きかっただろうと悔やまれぬでもありません。やはりオリジナルでバート・レイノルズをいたぶる看守長役だったエド・ローターが、刑務所長を務めるジェームズ・クロムウェルのただのゴルフ仲間としてほとんど数秒だけ画面に顔を出すという部分に軽く頬を緩めるという程度は出来たものの、オリジナルへのオマージュというならいっそのこと『フライト・オブ・フェニックス』のように、ウィリアム・アルドリッチをプロデューサーに据えるくらいはしてほしかったと思います。
しかしながら、このリメイクは決して惨憺たる出来栄えというわけではなく、かなりの程度をオリジナルに忠実足らんとする姿勢には、本当にそうだったのかは別としても、やはりオリジナルへの深い愛情を感じ取ってしまうし、アダム・サンドラーを個人的にはそれほど良くはしりませんが、彼も決して悪くはありませんでした。アメフトのプロ選手として活躍した経歴を持つボブ・サップを頭の足りない腕力だけの大男として描き、彼のプレイシーンをほとんど見せなかった部分は決定的に正しいとすら思います。設定上の変更はむしろ『フライト・オブ・フェニックス』のほうが大きかった程で、オリジナルを知らない人間でもそれなりに楽しめる映画にはなっていました。ただし、だからこそどうしても言っておきたいのは、ここまで原作に忠実にしていながら、何故あの円陣場面を描かなかったのか。オリジナルで幾度も繰り返されたあの極めて感動的な円陣場面を、私は観たかった。オリジナルのラストシーンで使われるスローモーションの素晴らしさを無視し、それが今のハリウッドだと言わんばかりに序盤から馬鹿のひとつ覚えのように連発されるスローモーションに何とか耐えられたのも、あの円陣とあの掛け声が聞きたかったからです。それが残念でなりません。
まぁ以上のようなことは、オリジナルを何度も観ている人間のほとんど反動的ないちゃもんに過ぎず、この手の馬鹿馬鹿しい普通のアメリカ映画を普通に愛している方にとってはいかなる影響も及ぼさないものでしょう。それでいいし、かくいう私もこのリメイク作を友人・知人に薦めることに何ら抵抗があるわけではないのです。こういうアメリカ映画は、"今こそ”積極的に観られなければならない、私はそう思ってさえいるので、常日頃、こういう映画からは意識的に遠ざかっている人にほど、『ロンゲスト・ヤード』を協力にプッシュしておきたいと思います。
2006年05月04日
もはや制御不可能な自分の肉体と精神に戦慄する
GW真っ只中の今、私は有楽町にある、とあるマンガ喫茶でこの文章を書いています。もちろん、こんな朝から有楽町に居ることなど稀なわけですが、現在開催中の「イタリア映画祭2006」の整理券をとるためだったら致し方ありません。それにしても渋谷のそれに比べ、ここ有楽町のマンガ喫茶は快適です。とにかく客が少ない。それがこの時間だからなのかどうかわかりませんが。まだ上映まで2時間程あるので、今日は昼食もこの中でとろうかと思っています。
さてさて、ここで話は唐突に5/1に遡ります。GWは基本的に映画中心の日々を送っていますが、以外にも好評だった先日の記事(もう繰り返したくはないこと)に続き、またぞろ自らネタを作ってしまったので、一酔狂ブロガーとしてここで報告しない手はないと思った次第。
5/1といえばメーデーですが、実は私、諸事情によりメーデーに参加せねばなりませんでした。まぁそれはたいした問題ではないのですが、例によって例のごとく、その後の“打ち上げ方”が不味かったわけです。大体14:00過ぎくらいに行進を終えた我々は、まず新宿東口のダーツバーに向かいました。ダーツなどこれまで一度しかやったことがないのにそこそこ楽しめてしまい、気づけばワインをがぶ飲みしていました。と、ここで断っておかねばならないのは、行進している最中も、私はシャンパン(250ml)とビール(350ml)を5本程飲み干していたのです。つまり、すでに一軒目のダーツバーで相当出来上がっていたことになります。しかしながら、自らの意思に反してGWの貴重な一日を潰さねばならなかった我々の猛攻は、ここで終わるはずもありません。夕方頃から叙々苑で焼き肉を頬張り、もちろんそこでも酒を飲み(もはや曖昧にしか記憶なし)、もうそのころはかなり疲れていたはずの体にさらに鞭打って、今度はボーリングへと流れ、私が記憶している限りではガーターを連発しながらそこでも酒を飲みまくって、やっと帰った“らしい”のです。そう、すでに私には帰宅した記憶すら残されてはいませんでした。どのように、何時ごろ帰宅したのか、ついでに言えば、ボーリングでの記憶も95%くらい消失しているのです。
さて、とりあえずは帰宅できたらしい私、翌朝起きてみると、枕元に“およそありえないオブジェ”を発見しうました。それはほとんどシュールレアリスティックなオブジェでもあり、これまで一度たりとも目にしたことのないものです。どうしてそんなものが枕元に置かれているのか、私には皆目見当がつきません。が、それを置いた犯人は私自身をおいてありえないのです。部屋の鍵はきちんと閉められていたのですから。まさに密室の謎!!
そこにあった超現実主義的なオブジェ、それは、汁気の全く無い、伸びきったカップラーメンにハブラシが垂直に突き刺さったものでした。カップラーメンとハブラシ。ミシンと蝙蝠傘の不意の出逢いのようにそのオブジェが美しかったかと問われれば、やはり口を噤むしかないでしょう。さらに驚くべきことに、私は泥酔して帰宅した後、すでにカップラーメンを平らげていたのです。いったい何を考えていたのでしょうか、いや、何も考えてはいなかったはず。思考する余裕すらなかった私の唯一の抵抗、それがあの忌まわしきオブジェだったのでしょう。
つまり私は、
打ち上げ解散→帰宅途中にコンビにでラーメンを購入→帰宅後ラーメンを食べる→さらにもう一つラーメンを食べようとする→やっぱりお腹がいっぱいで食べられずはずもない→ここで想像力が爆発、あるいは故の無い怒りに囚われた結果、洗面所にハブラシを取りにいく→ハブラシをラーメンに突き刺す→力尽きて(あるいは満足して?)就寝
大方そういう経緯をたどって朝を迎えたということなのでしょう。とにかく朝起きてそれを発見した瞬間、呆れるを通り越して、さらに苦笑すら通り越して、ほとんど恐怖の感情しかありませんでした。もはや制御不可能なこの肉体と精神に。
この話を読んだ方は、きっと、そんなことは自分には絶対にありえないと確信することでしょう。しかしそうでしょうか。この実話の主人公など、いくらでも交換可能な人物です。いや、むしろこの物語の主人公は貴方かもしれないのです……などとミヒャエル・ハネケめいたことを言いつつ、今、他ならぬカップラーメンを食べながら、この文章を書いています。
お後がよろしいようで……
『隠された記憶』
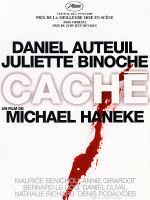 原題:Caché
原題:Caché
上映時間:117分
監督:ミヒャエル・ハネケ
本作における最大の挑発は、あのラストシーンに隠されているのでしょうか。それは果たして、われわれ日本人にも理解可能なものであるのか、否か。あるいは、理解を超えた何かであるのか。それらを考え直すために、もう一度観てみようと思います。
2006年05月03日
『ベニーズ ビデオ』、氷河化する感情
 原題:Benny's Video
原題:Benny's Video
上映時間:105分
監督:ミヒャエル・ハネケ
本作の主人公・ベニー役のアルノ・フリッシュはこの作品でデビューした後、『ファニー・ゲーム』で再びハネケと組みます。初めて『ファニー・ゲーム』を観た時、何だか凄い俳優がいるものだな、と思ったのですが、その5年前に出演した本作の彼は未だ幼さが残りながらも、その行動は『ファニー・ゲーム』のそれに非常に近く、ほとんど悪気などないかのようでいてこちらの感情を逆撫でするような、空恐ろしいものでした。こんな奴が実際に近くにいたら嫌だろうな、などと思っているうちに、そう思っている自分の中にも似たような部分があるんじゃないのかと思わせるあたり、ハネケの演出はやはり一貫しているというべきでしょうか。
ビデオで撮影した豚の屠殺シーンをベニーが自室に篭って鑑賞するシーンで、本作は始まります。豚の脳天がスタンガンで打ち抜かれる場面を、彼は繰り返し観る。再生しては巻き戻し、時にはコマ送りで。映画研究者のスザンネ・シェアマンによれば“感情の氷河化”三部作の2作目に当たる本作、そのタイトルには“ビデオ”という言葉が使われていますが、ハネケの作品を何本か観ていれば容易にわかるように、テレビやビデオの画面は他の作品でも幾度と無く登場します。私は本作を鑑賞した時、『ファニー・ゲーム』は恐らく本作をよりラディカルに作り直したものではないかと思ったのですが、それは、主人公を演じる俳優が同じという点以上に、“巻き戻す”(=時間を操作する)という行為が共通していたからです(ちなみに、最新作である『隠された記憶』にも、それは共通しています)。
ベニーがある少女を殺してしまうシーンを、観客はビデオの画面を通して観ることになります。固定されたビデオカメラは、その視界に全てを映すことが出来ず、殺人の全貌は専ら音によって明かされます。次第にその大きさを増していく少女の悲鳴と3度繰り返されるスタンガンの銃声、そしてそれを冷酷に見つめるビデオカメラ(=観客の視線)。このシーンは後半にもう一度繰り返されますが、ここで“繰り返す”という行為へのハネケの執着を感じないわけにはいきません。
何故ベニーはビデオの画面に惹かれるのか。そこに映されたものが、現実ではない、あくまで操作可能な虚構であるからなのか。もはや言うまでもなく、そこに納得できる答えなど用意されていません。少なくとも思うことは、テレビに映っている映像は、そこにある全てが信ずるに足るかのようで、実際にはいかなる真実をも映してはいないのではないか、ということです。ハネケにとってのテレビやビデオは、人間が“感情の氷河化”に向かうための一つの契機なのではないでしょうか。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]



