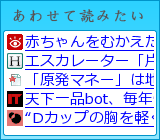2008年06月11日
『コロッサル・ユース』に言葉を奪われて
Colossal Youth/2006年/ポルトガル・フランス・スイス/155分/ペドロ・コスタ
ペドロ・コスタの新作『コロッサル・ユース』は、これまで以上に私の言葉を奪う映画でした。
恐らく、『コロッサル・ユース』を前に、「いやぁ〜面白かったな〜」などという言葉を発することの出来る人は皆無ではないか、とすら思います。もちろん、そのように言う権利は残されているし、その逆もまたしかりではあるのですが、私に関して言うなら、どうもそういった反応が出来ないでおります。
ペドロ・コスタの映画は、観客に対して、“厳しさ”を強いるタイプの映画だと、あくまで漠然と思ってきましたが、反面、今目の前でのっぴきならないことが起こっているという事件性だったり、観るものの感性を激しく揺さぶるような画面の凶暴性だったり、あるいは、観ること/観られることを考えさせずにはおかない批評性といったものが映画自体に横溢していて、それはつまり、『コロッサル・ユース』がこの上なく豊かな映画というふうにも結論できてしまうのです。
恐らく私には、本作を“理解”出来てなどいないでしょう。
しかし、少しずつ形を変えながら、主人公・ヴェントゥーラの口から幾度も読み上げられる手紙の文面(加えて、それを読むヴェントゥーラ自身の声)に対し、自分でも驚くほど感動しました。
次元が歪んだかのように遠近感がデフォルメされた美術館における照明と足音にも、そして、獰猛な獣が牙を剥いたかなような影にも。
そう、ペドロ・コスタはついに、影を我が物にしてしまったような気がします。影と光は表裏一体。つまりペドロ・コスタは、他でもない「映画」を我が物にしてしまったのではないか、ということに気づきました。いささか大袈裟ですが、そんなことを思わせる作家が、今、世界に何人いるでしょうか。
2008年06月11日 19:05 | 邦題:か行

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]