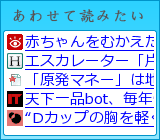2007年11月12日
あらためて『モンド・トラッショ』を観てわかったこと
 Mondo Trasho/1969年/アメリカ/95分/ジョン・ウォーターズ
Mondo Trasho/1969年/アメリカ/95分/ジョン・ウォーターズ
もう何年も前に観たきり、その時何をどう思ったかすら忘れてしまっていた『モンド・トラッショ』の古びたヴィデオをあらためて借りてきたのは、一つには最近リメイクされた『ヘアスプレー』を鑑賞したことがその理由に挙げられるのですが、さらにもう一つ、ジョン・ウォーターズの著書「悪趣味映画作法(新装版)」を読んで、『モンド・トラッショ』はそれほど“ゴミのような”映画だったのかどうかを確認しようと思ったからです。
ジョン・ウォーターズの作品は、大別するなら、ドリームランド・プロダクション時代とメジャー進出以降とで2つに分けることが出来ます。監督を含め仲間3人でスタートしたインディーズ時代を経て、不良仲間たちが徐々に集まり始めたことで結成されたドリームランド・プロダクションは、その顔ぶれだけをみても、かなりイカレていました。ディヴァイン、メアリー・ヴィヴィアン・ピアース、デヴィッド・ロカリー、そしてミンク・ストール。ジョン・ウォーターズの初期作品に欠かせないこのキャストたちは、ジョン・ウォーターズ的な演出によって、負の光を放射していたと思います。
さて、ここでいうジョン・ウォーターズ的演出。これが問題なわけです。基本的にジョン・ウォーターズは、即興の人ではなく、何度もリハーサルを繰り返すタイプの監督ですが、これがまったくそうは見えてくれません。それは私にとって、行き当たりばったりで、ド素人的で、演劇的なオーバーリアクションでしかなく、本当に酷い代物なのです。しかし、にもかかわらず、惹きつけられてしまうのは何故か? 監督自身が言うように、たとえそれが“狙った上での”演出だったにせよ、それでは到底説明しきれていない気がするのです。
私が思うに、重要なのは、並外れたビジュアルセンスと俳優たちの声(あるいは背景音)だったのです。断っておかねばならないのは、ここに挙げた2つのファクターにしても、やはりほとんど出鱈目と言ってしまってかまわないということ。それは依然としてド素人の範疇を出なかったり、ほとんど演出放棄にすら見えてしまったりもする。ただ、やはり“センス”というものは、光るべきところで光る、としか言いようがありません。ジョン・ウォーターズの片腕と言って差し支えないヴィンセント・ペラーニョによるあの常軌を逸した衣装とメイクのセンス。あるいは、まるで“ゴダール的ソニマージュ”、とまでは言いませんが、やっつけ仕事的ないい加減さをいささかも隠そうとしない音のセンス(これは本当のことですが、『モンド・トラッショ』には、『気狂いピエロ』における音の使い方にうり二つのシーンがあるのです。制作年からいって、ジョン・ウォーターズがパクった可能性がないではありませんが、それは考えづらいでしょう)。16mmモノクロで撮られた『モンド・トラッショ』からして、それらはすでに開花していました。以降、絶頂点である『ピンク・フラミンゴ』まで、そのスタイルは、私が見る限り変わっていません。
『モンド・トラッショ』にはほとんど台詞が無く、脈絡のないイメージと音が連鎖します。はっきり言って冗長な映画ですし、テクニック的にも誉められた映画ではありません。“それ(映画)らしく見せよう”などと言う気持ちはまるで感じられず、フィクションであることをあえて放棄しているかのようでした。しかしだからでしょうか、そこにはドキュメンタリー的な、二度と起こりえないであろう瞬間が奇跡的に連続し、観る者を不意打ちし続けるのです。そのほとんどは倒錯的で、グロテスクで、反キリスト教的。あらゆるものを愚弄し、犯罪を積極的に肯定するという姿勢。それに耐えうるのは、やはりあのキャストしかいなかったのだと思います。ディバインは長編デビュー作から、“神聖”な存在だったのです。だからこそ、彼が唯一発する台詞「おお、マリアよ! 三位一体の神よ!」が脳裏に焼き付いているのかもしれません。
『モンド・トラッショ』はやはり、“ゴミのような”映画でした。
が、ジョン・ウォーターズにしか撮れなかった唯一無二の映画でもあったのだと、改めて理解させるに充分な映画でもあるのです。
2007年11月12日 12:20 | 邦題:ま行

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]