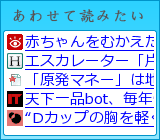2007年11月07日
『高麗葬』、映画ならではのいい加減さを前に文字通り絶句
 Goryeojang/1963年/韓国/87分/キム・ギヨン
Goryeojang/1963年/韓国/87分/キム・ギヨン
『下女』を二度見逃して以来、ようやくキム・ギヨン作品をスクリーンで観る機会を得ました。
不幸にして完全版という形ではなく、途中2巻分が失われた状態ではありましたが、それを差し引いても、本作はその堂々とした、異様な、悪い冗談のようで神がかった演出と画面設計において、紛れもない傑作だと思いました。と、今は大分冷静にこんなことを書けますが、鑑賞直後は絶句するほかなく、頭の中で「これは凄い…」という思いが繰り返されるばかりだったのですが。
タイトルクレジットは、画面いっぱいに埋め尽くされた漢字(詩?)の所々が変化し、スタッフやキャストのクレジットとして浮かび上がるという、意外にもにもモダンで秀逸なものでした(60年代ゴダール的)。
続いて冒頭、ラジオ番組かなにかの収録模様がスクリーンに映し出された時から、高麗時代が舞台のはずのこの映画に、何故このような“現代的”なシークエンスが?と呆気にとられたのですが、所謂学者たちが人口統制の必要性を説くというこのシークエンスのアイロニーも、いささか生ぬるく感じるような画面が後に続くことになろうとは…。
『高麗葬』は、非常に単純な要素で成り立っていると思います。飢えに苦しむ人々がいて、日々の食料もままならない彼らが、水と芋以外に信じられるのがシャーマニズムであり、そして姥捨て信仰です。これらが最終的に、破壊へと収斂されていくような映画、それが『高麗葬』だと思います。では何を破壊するのか。それはシャーマニズムを含めた旧来的な伝統に他なりません。ラストシーンにおいて、雨が振ることがあれほどまでにドラマティックだったのは、彼らがそれによって新しい生き方を獲得したからなのです。破壊が齎した生…『高麗葬』はあまりに独特なタッチで、それを描いていたのだと思います。
キム・ギヨンは、しかし、何とも形容しがたい監督です。彼が生真面目に人間存在の本質を描こうとしていたとはとても思えないような“いい加減さ”が、画面に漂っているのです。登場人物のグロテスクな側面だけに目を向ければ、なるほど、ブニュエル的と言えるのかもしれません。ただキム・ギヨンは、より映画ならではの自由さを身に纏っているような気がしました。演出や構図による、人物描写の極端なデフォルメ。時に仰々しく、現実感を欠いた劇伴。深刻さが極限に達しようとするあまり、それが笑いを誘ってしまうという逆説。“度を越す”という行為がここまで作品を輝かせていいものか、その点で、私は本作を高く評価します。
映画とはやはり嘘っぽくていい加減な芸術である、ということを、この『高麗葬』は思い知らせてくれるでしょう。少なくとも私は、『高麗葬』に比すべき映画を知りません。そんな映画が、これまた滅法“面白い”のだから、まったく性質が悪い…。
母国韓国はおろか、近年ベルリンやフランスなど、キム・ギヨンの再評価は世界規模に広がりつつあるようです。30本以上ある彼のフィルモグラフィーのうち、現在観られるのは20本強。キム・ギヨンの大規模なレトロスペクティブが、一日でも早く日本でも開催されることを願ってやみません。たった一作でそんなことを思わせてしまうキム・ギヨン。彼の作品は、私のこれまでの評価軸を揺るがせてしまう恐れがあるだけに、観るのが怖い気もするのですが。
なお、併映された『キム・ギヨンについて知っている二、三の事柄』(2006年/キム・ホンジュン)というドキュメンタリーでは、キム・ギヨンに影響を受けた若手映画作家たちが、キム・ギヨンとの出会いのエピソードや、それぞれの作品の特異性についてインタビューされていました。特に興味深い作品ではなかったというのが正直なところですが、キム・ギヨンの作品がヴィデオで普通に観られる韓国が羨ましいな、と。中でも、登場した多くの監督たちが口々に『火女』に衝撃を受けたと聞いてしまったので、とにかく『火女』が観たいという思いが膨らんでしまいました。
2007年11月07日 13:15 | 邦題:か行

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]