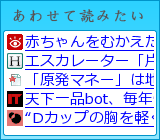2007年07月18日
最近観た6本の映画
先週から昨日にかけて、6本の映画を観ました。忘れないうちに、簡単に書いておくことにします。(本当は少し前にも、『ルック・オブ・ラブ』やガンダーラ映画祭における『童貞2』など、面白い作品を観ているのですが、随分時間が空いてしまって心もとないので、今回は割愛)
■石の微笑(クロード・シャブロル)
『フランドル』以来、久しぶりのフランス映画で、さらに言えばシャブロル自体も『パリところどころ』の一篇以来でかなり久々でした。前情報をまったく入れないまま、予告編の雰囲気が良かったので鑑賞したのですが、まったく驚くべき傑作でした。
本作を観て、そういえば自分は“サスペンス映画”というのを久しく観ていなかったと言う事実に思い至りました。本作を良質なサスペンス映画だと言いたいわけではありません。そういったジャンル的な見地に立って本作を観ても一向にかまわないのですが、私の感想としては、本作は今年観た数十本の映画の中でも際立っており、鑑賞後、これほど途方に暮れさせる映画も無かったろう、ということにつきます。
冒頭の移動撮影から完全に引き込まれ、気づけば映画は終わっていたという感じです。いや、一点だけ驚いた箇所もあって、それはあるシーンにおけるズームなんですが、これについては観ていただくほかないので、詳述は避けます。ああいったズームを目の当たりにすると、ついついサスペンスという言葉を漏らしてしまいそうになるのですが、最後まで観れば、本作を、ただただ映画だ、と体全体で体感することになるでしょう。
“石の微笑”というタイトルも、なかなか悪くありません。実はそのままなんですけど。
■Fragment(佐々木誠)
ドキュメンタリーを観る時、私はとかく、その手法(語り口)だったり、あるいは監督と対象との距離だったりを注視してしまうのですが、本作は、そのどちらにおいても特筆すべきことはあまり無かったというのが正直なところ。ただし、題材の面白さがそれを補っていたように思います。
“カオティックな世界”を表現するために、あえて、わかりやすさから遠ざかってみること。本作の編集には、そのような思いが込められていたようです。
■誰とでも寝る女(前田弘二)
■女(前田弘二)
以前、テアトル新宿で特集されていた時に見逃していて、そのことがずっと気がかりでした。何故あの時、この見知らぬ監督の作品を観たいと思ったのか。それがまったく思い出せないのですが、やはりタイトルのインパクトと数枚のスチールからでしょうか。
今私は、恐らく冨永昌敬以来と思われる、比類なき才能にめぐり合えた喜びを噛みしめているところです。これら30分強の2本の中篇には、それほどまでにノックアウトされました。
前田弘二の面白さはどこにあるのか。あまりにも日常的な台詞回しからアドリブかと思わせるような、しかし、まったくもって厳密であったに違いない演出にあるのか。あるいは、何かが画面に生起しそうで、やはりそれは誤解だったと思わせておいて、最後には予想を超えた“オチ”がつくようなシークエンスショットにあるのか。あるいは、常に背中あわせである“笑い”と“恐怖”が、同時に画面に収まってしまう奇跡にこそあるのか。今後、この映画作家を追っていくことで明らかになるかもしれないし、ならないかもしれません。
これまでで影響を受けた映画作家に、エリック・ロメールを挙げるあたりの喰えなさ加減も悪くない。
いずれにせよ、前田弘二という名前は、今後決して忘れてはならない名前だと言うことを確信しています。
■腑抜けども、悲しみの愛を見せろ(吉田大八)
本作に関しては、事前に原作を読んでいました。普段、そういうことは意識的にしてこなかった私ですが、たまたま読んでいた文芸誌に発表されていたので。映画化の話を聞いたのは、そのずっと後だったのです。
冒頭の、いかにも田舎道らしい平和な1本道が、突如惨状へと姿を変えるあたりに始まり、本作には田舎特有の豊かな自然や田園風景が、時として、非常に残酷な何かを象徴しているかのごとき、風景描写が随所に配置されていました。この時、なんだか中島哲也監督近作の画面に似ているなぁと思ったのですが、後で調べてみると、撮影は『下妻物語』や『嫌われ松子の一生』の阿藤正一で、ついでに監督の吉田大八についても調べると、主にCMディレクターとして活躍してきたらしく、そのあたりも、かなり“中島的”だと思わずにはいられなかったわけですが、それらは別段、作品の評価とは何の関係もないと言えばなく、さらに言えば、原作を読んでいようがいまいがやはり関係なく、あくまで本作自体の出来を冷静に見極めたいと思いはするものの、やはり後半で顕著に見られる、“画面遊び”(私にはそうとしか思えませんでした)が気になってしまい、女優陣の健闘やキャスティングの面白さと相殺された、という感じです。
■ボルベール<帰郷>(ペドロ・アルモドバル)
本作を観て、アルモドバルが世界の巨匠の域に達しているということを実感。
愛情や情熱、血縁を表すばかりでなく、血そのものの色でもある“赤”が何度も画面に表れては消え、それと同じくして、5人の女性達の喜怒哀楽が直接的に画面に艶を与える。舞台となったラ・マンチャという田舎街も、マドリードの郊外も、決して華やかな街ではなく、厳しい環境とや貧しさにさらされているはずなのに、本作における画面の艶はどういうことでしょうか。もちろん、ペネロペ・クルス他、女優陣の好演がその一因でしょう。アルモドバル映画に登場する女性には、誰もが美人だと認めるような女性、というよりは、もっと深い次元における“女”が多い気がします。そして彼女達には、やはり“赤”が似合うのです。
ペネロペ・クルスが、「ボルベール」という古い歌を歌うシーンで、まだその存在を彼女には見せていない母親と不意に視線が交わったかに見えるショットがあるのですが、この切り替えしが見事。実は一方的な視線のはずなのに(事実、ペネロペ・クルスからの切り返しに母の姿はない)、それでもそこには双方のまなざしがついに交わったと思わせる、非常に感動的なシーンでした。
監督自身“コメディへの回帰”と言っているように、本作には思わず笑ってしまうようなシーンが多くあります。しかしそれらの笑いには、何故か哀愁が漂っているようで、そういったシーンが、私にアルモドバルの熟成を印象付けたのかもしれません。まさに誰にでも薦められる映画、と言っていいでしょう。
2007年07月18日 19:41 | 映画雑記

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]