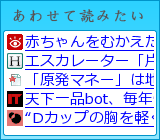2007年05月29日
東京芸術大学大学院映像研究科第一期生修了制作展
学生映画や、あるいはインディーズなど、総じて自主映画と言われるものを私が意識して観るようになってからまだ日が浅いのですが、では何故そうなるに至ったのか。たまたま観た自主映画が面白かったのか、あるいは将来的な可能性を感じ取ったのか、およそそんな理由だったのではないかと思います。
自主映画を観るに際して私が特に意識することはなく、所謂プロが撮った映画に接する時と変わらないか、というとこれがそうでもなく、まだ観ぬ作品に期待をするかしないか、という点で異なっているような気がします。ただしこの場合、むしろいらぬ期待をこめて鑑賞しようとしてしまう態度がいけないのであって、あらゆる作品に対し、はなから期待などしないに越したことはないのですが。作品への評価は観るまで定まらないし、また定まるべきではないので、あらゆる作品をニュートラルに観た方がいいに決まっているのです。だから現状ではむしろ、予めその旧作を鑑賞していたり、すでに評価が定まっている監督の作品を観る時より、まったく未知の映画作家に出会える自主映画を観る時のほうが、(多分無意識的に)より観ることを楽しめている、と言えるのかもしれません。もちろん、作品への評価はまた別の話です。
さて、今回「東京芸術大学大学院映像研究科第一期生修了制作展」にて鑑賞した6本の作品、これらもまた、ところどころ評価できたり出来なかったりしたわけですが、作られた映画はいかなる形であれ上映されるべきで、こういった機会にめぐり合えることは大いに喜ぶべきことです。昨今の異常ともいえるわが国の上映本数を考えると、それは尚更。まぁ今回は、黒沢清と北野武という2人の偉大な映画作家の名前が大きく影響しただろうことは想像に難くないし、だからこそユーロスペースのレイトショーに、ミヒャエル・ハネケとかキム・ギドクの特集上映レヴェルの客が押し寄せたのだろうと推察されますが、何にせよ、上映されてそれを観なければいかなる評価も出来ません。今回の特集上映がことごとく自分の好みと異なり、失望を隠せなかったとしても、自主映画を観ることに対する思いが変わることはないでしょう。これは私の中の大前提と言えるかと思います。
以下、各作品についての雑感を。
■『兎のダンス』(41分/HD/カラー/監督・脚本:池田千尋)
シーンごとの演出は悪くないのですが、全体としての調和にまで達しておらず(点が線になっていない印象)、あくまで表面的(これはよくない意味で)な雰囲気の“表現”にしか貢献していなかった気がしました。
2シーンほどで、この審美的な作品にしては美しくない夜のシーンがありましたが、照明にまで人員を割けなかったのかもしれません。
本作は、台詞や描写による“説明”を極力排しているように見受けられました。その手法上の良し悪しが問題ではもちろんなく、説明をしないという選択が、結果として、観客にどのように作用するものなのか、ということが問題なのだと思いました。行間を観客の想像や理想、妄想で埋めるという行為が出来る場合と出来ない場合、たとえ出来たとしても、説明しなかったことの脆弱さを際立たせてしまう場合など、可能性はいくつか考えられるのですが、とどのつまり、その部分は観客に委ねられているのです。
最近、こちらでほとんど思考しなくとも内容が理解できてしまうようなアメリカ映画を観たのですが、過剰なまでにわかりやすく具体的な描写を重ねることで引き出される情動というのもあり、それはそれで関心してしまいました。
話が脱線しましたが、本作から私が感じ取ったのは、唯一、ある種の雰囲気のみでした。雰囲気って何?という話はひとまず置くとしても、具体的な細部が良いとか悪いとか、そういった感情思い浮かびません。それが果たして何を意味するのか、それについても何とも言えません。
■『心』(64分/HD/カラー/監督・脚本・編集:月川翔)
現実世界における“事件”には、まだまだ聞いたこともないようなものが起きる可能性があると思っていますが、では映画における“事件”はどうでしょうか? 映画であるが故に、現実以上のヴァリエーション(まったくありえないような創造も含め)を個人的には期待したいところですが、観客との共感というレヴェルで考えてみると、やはり、映画においても現実的な事件を扱うことが多そうですし、さらに言えば、事件をどう描写するのかという問題もあって、その点こそ、監督が最も頭を悩ませる点なのではないか、などと思っています。
本作には、どこかで観たことのあるようなショットが散見されました。しかし、それ自体に関して言えば決して否定されるべきものではないと私は思っています。ただし、例えば、犯人の住処におけるいくつかの画面には、犯人像の(あるいは犯人の部屋そのものに対する)安易な類型化が見られ、そこは残念だったといわねばなりません。
映画自体の(または、監督の、と言い換えても良いのですが)勢いは充分感じさせます。中でも、ショット間の音の連鎖は印象的でした。本作には聾唖の少女が登場するので、逆説的に音に拘ったのだろうと予想されます。ちなみに、利重剛や役所広司に出演に関しては、それだけで観客に与えるインパクトが予め存在してしまう気がしますので、ここでは差し控えます。
■『エイリアンズ』(35分/HD/カラー/監督・脚本:渡辺裕子)
幾度が登場する白蛇のインサートが記憶に残っています。主人公が性同一性障害だったらしいのですが、そのキャラクターがドラマの中でどれほど生きていたのかが疑問。
ラスト近く、湖のほとりにおけるドタバタは湖面からのショットで撮られており、本作で唯一面白いと思った場面。ただし、あのラストショットが正しかったのかどうか…。文字通り、空いた口が塞がりませんでした。
積極的に褒めたいとは思いませんでしたが、この先がちょっとだけ気になる監督。
■『A Bao A Qu』(85分/35mm/カラー/監督・脚本:加藤直輝)
主人公の小説家を演じた俳優に対する、何とも言えぬ違和感が途中からどんどん膨らんで行き、ラストまで好転することがありませんでした。物語の陰鬱さに、演出が追いついていないという印象。そうかと思えば、通り魔に恋人を殺された女性が、その当時の状況を克明に独白して聞かせるシーンを捉えたシークエンスショットは見事だったと思います。ショッキングな描写が多かったように思うのですが、そういうシーンを撮ってみたかったのだろうと思いこそすれ、文字通りのショックを観客に与えるまでには至っていないのではないかと思わせるあたりが弱いといえば弱い。
通り魔事件をおこしたある兄弟の兄のほうが、自宅の2階で母親を殺した後、ゆっくりと階段を降りてくる画面と音、別に珍しくないシーンとはいえ、あの手のわかりやすさは評価したいと思います。しかし、その兄が(あれは妄想の中の場面だったのかもしれませんが)、広場の真ん中からゆっくりとカメラの法に近づいてくるショットには閉口。兄が聞いていたという設定のカセットテープから聞こえてくる音楽は、なかなか面白いと思いました。
どうも全体的にちぐはぐな印象が拭えません。
■『CREEP』(52分/35mm/カラー/監督・脚本:酒井耕)
演出が極めて安定していたように思うのは、やはりプロ俳優(とりわけ斉藤陽一郎)の力なのかもしれませんが、それにしても面白いキャスティングでした。初音映莉子という女優の発見は一つの収穫。
後半に起こる大地震、その描写はもちろん、カメラを揺らすという例のアレですが、流石に『LOFT』におけるそれと比べると明らかに見劣りするものの、それが大地震だということはダイレクトに伝わってきました。
あの映画的なロケーション(山中にポツリと建つログハウスのみならず、冒頭にはうら寂しい海も)を見つけてきたことは評価したいと思います。
■『from DARK』(61分/35mm/モノクロ/監督・脚本:大門未希生)
唯一のモノクロ作品である本作は、唯一ジャンルへの接近が試みられているように見えました。はっきりとフィクションを宣言している潔さは悪くないと思います。ご丁寧にCGまで使われていますが、画面よりはむしろ音のほうに意識を奪われた感も。とにかく要所要所の音が大きすぎて、それは狙いなのか、それともこの日の上映がたまたまそうだったのかわかりませんが、途中でいい加減不愉快になってきたりも。
そんなこんなであまりいい印象はありません。
2007年05月29日 20:20 | 映画雑記

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]