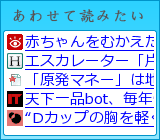2006年10月04日
『楽日』にはただ途方に暮れるばかりだ
原題:不散/Goodbye, Dragon Inn
上映時間:82分
監督:ツァイ・ミンリャン
ほとんど台詞も無く、物語すら明確とは言えないであろうこの映画が、どうして私を惹きつけてやまないのか、映画は時に、観客をそのような説明不可能としか言えない環境に置きざりにします。いや、台詞や明確な物語が不在だからといって、映画には画面があり、そして音があります。目で見て耳で聞くことが出来るものがあれば、それで充分だと思わせる映画、それが『楽日』であるとしか今は言えません。
その名前は幾度も目にしてはいたし、映画好きの友人による、ほとんど魂の叫びとでも形容したいほどの擁護ぶりを目の当たりにさえしていたのですが、私はツァイ・ミンリャンという監督の映画を観た事がありませんでした。だから、『楽日』は私にとっての大いなる“発見”であったと言えます。映画を、あるいは作家を発見する時、人は少なからず、歴史を遡って思考するものだと思うのですが、私の映画史の中に、果たしてここまで豊かな、というか贅沢極まりない時間を意識させる映画があっただろうかと、上映中もずっと考えこんでしまうほど、本作は感動的なまでに映画を観ることの幸福を感じさせてくれました。
『楽日』には数人の男女が登場します。かれらは映画館にいるけれども、映画を観るためにそこにいるのかどうかはわからないような存在です。主人公と言っていい留学生役の三田村恭伸は、どうも映画を観にその劇場に来たとは言いがたく、座席についたとしても、ふらふらと位置を変えたりしながら、ほとんど挙動不審者としか言いようの無い、極めて虚ろな人物として描かれています。いや、彼だけではありません。その日限りで閉館しようとしている福和大戯院という大きな映画館で、本当に『血闘竜門の宿』を観に来ているのは、たった2人だけだと言えるでしょう。嘗て『血闘竜門の宿』に主演した元俳優であるミャオ・ティエンとシー・チュン以外、誰もがそこにいる必然性などない人物たちです。だけれども彼らは間違いなくそこに存在している。曖昧に、そして時に如何わしく。
「この映画館には幽霊がいる」。ある男がそのように口にするシーンがあります。
その男が、三田村恭伸にタバコの火を貸すシーンの、あの湿り気を帯びたエロティックな画面はどういうことでしょうか。もちろん、そのシーンより前に存在するトイレのシーン(このシーンには終始“にやけ”が止まりませんでした)を想起するまでもなく、この劇場が“ホモセクシャルな男達のための場”としての機能を果たしていたということが暗喩的に仄めかされていたのですから、男同士のそんな何気ない仕草にエロティシズムが漂っていても不思議はないのですが、ここでもやはり指摘しておきたいのは、たった一言の台詞と、火を点けタバコをふかすという動作それ自体に漂う美しさと淫靡さなのです。その意味で、彼らがホモセクシャルかどうかなどという問題とはまるで無縁の美しさと言えるでしょう。雨音も薄暗い照明もまた、その美しさには欠かせませんが、私はこのシーンを観て、“画面を凝視する”という行為それ自体にの重要性を再認識しました。言い換えれば、映画における“画面の官能性”を目と耳で実感したということでしょうか。
しかしながら、「幽霊がいる」と呟く彼自身が幽霊でないとは誰も断言出来ません。その代わり、この福和大戯院という、消滅を運命付けられた建造物自体は、間違いなくそこに存在しているのです。監督自身が、あらゆるシーンを劇場から聞こえる声に従って撮った、と言っているように、この映画の主役はあくまでこの劇場であり、登場人物たちはやはり、いるのかいないのか曖昧な幽霊的存在でしかないのかもしれません。迷路のように入り組み、そしてところどころ朽ち果てつつある巨大な廃墟は、しかし、その命を未だ完全に消し去っておらず、確実にその場所にある。本作においてあまりに印象的な人々の足音(その音の素晴らしさは『ジェリー』を想起させます)は、むしろ、劇場自体が発した音だと言うことも出来るのです。
『楽日』において、人々は“出会う”ということを禁じられているかのようです。
それが最も印象的な形となって顕れるのが、足を引きずったもぎりの女性と、彼女が思いを寄せているらしい映写技師によるすれ違いです。この2人は映画の終わりまで(遂に劇場が閉館してしまってからも)、触れ合うことはもちろん、言葉を交わすこともありません。そしてこの一方通行性は、観客とスクリーンの関係に置き換えることが出来るでしょう。たった2人の元俳優がスクリーンに投げかける視線の一方通行性(本来映画を観るとはこういうものです)、あるいは、上映されている映画など観ようともしない虚ろな観客達を、スクリーンが一方的に見ていると言うことも可能です。彼らの視線は真に交わることがない。
上映が終った時、2人の元俳優が言葉を交わすという何気ないシーンに涙しそうになったのは、彼らから呟かれる「誰も映画を観なくなってしまった」という言葉に、失われつつある映画そのものに対する郷愁を感じ取ったからではなく、全てにおいて交わることの無かった一方通行の視線が遂に出会い、言葉が交わされたからなのでしょう。
その日を最後に閉館してしまう劇場に、幽霊のように曖昧な存在の人や、決して言葉を交わさな男女や、郷愁とともに画面を見つめる人がいる。彼らの足音を再び記憶から掘り起こしてみると、何故か足音だけが妙な存在感を纏っていたということに思い至りました。それらは紛れもなく、“生”の存在感として、“死”に瀕した劇場にこだましていただろうし、言い換えればそれだけが、あの劇場の存在を確固たるものにしていたのだろう、と。ただ老朽化した劇場に足音が響くだけで、やはりそれは豊かで、贅沢で、感動的なのです。本作が本当に傑作と呼べる作品なのかも、実はわからないままですが、それすらもこの際どうでもいい気がしてくるから不思議です。
つまり『楽日』は私を置き去りにしたまま、あの劇場のように遠くに去ってしまったということでしょうか。
これまでいろいろ書きましたが、結局何も言い得ていない気がしています。面白いの一言で済ませられず、思考による発見にも期待出来ないのなら、私は素直にただ途方に暮れてしまおう、そして出来ることなら、あの画面と音をこの先も記憶しておこうと思います。
2006年10月04日 18:13 | 邦題:ら行
Excerpt: この映画、見る人によってめちゃくちゃ色んな感想があるだろうけど、僕にとっては「雨
From: Days of Books, Films
Date: 2006.10.06
>かおるさん
劇中で流れていた映画、あれは撮影中も基本的にリアルタイムで流していたらしいですね。
映画はやはり、全身で体験する芸術だと改めて感じた次第です。
Posted by: [M] : 2006年10月09日 22:00
楽日は10月14日から渋谷シアターイメージフォーラムで2週間限定アンコールレイトショーを開くそうです。
もちろんまた見にいきます!
Posted by: サンク : 2006年10月07日 20:22
一般受けはしないだろうし、「おもしろかった!」と胸張って言える映画でもないし、正直あの長回しには眠くなったところもあったんですけど・・・。それでも自分もあの劇場にいる観客の1人になった気分になったし、セリフが少ない中でいろんなことを感じられた作品でした。
私も「楽日」が初ツァイ・ミンリャンでした。「西瓜」もすばらしかったです。フィルメックスも行きたいなぁ。もっとツァイ・ワールド(なんかヘン?)に浸ってみたいです。
Posted by: かおる : 2006年10月06日 20:21
今、遅れを取り戻すかのように過去作品を観ているところです。彼の画面は非常に独特で面白いですね。
私も常識的な男(?)ですが、映画の中のホモセクシャルには意外と寛容だったりします。若いうちにデレク・ジャーマンの『セバスチャン』なんかを観てしまったからですかね。
ともあれ、本作の空気をもう一度劇場で体感したいです。
Posted by: [M] : 2006年10月06日 18:45
私は常識的な男(?)なもので、過去のツァイ・ミンリャン作品には惹かれながら、ホモセクシュアルの部分には退いてしまいました。でもこの映画での「たまり場」の描写や空気にはぞっこんです。確かに、この映画の主役は映画館ですね。
Posted by: 雄 : 2006年10月06日 17:04

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]