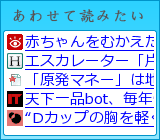2006年04月06日
『ヒストリー オブ バイオレンス』、あるいは暴力は暴力でしかないという現実を見定める決意
原題:A HISTORY OF VIOLENCE
上映時間:96 分
監督:デヴィッド・クローネンバーグ
映画の冒頭、とあるモーテルから男が二人出てきます。その内の一人がチェックアウトのためモーテルのフロントへ向かうと、残されたもう一人が車をフロントの前まで移動させます。ちょうど画面の手前に車、その奥にフロントがあるという位置関係です。車がフロントの前に停車するまでは確かワンカットで撮られていましたが、ショットはまだ続きます。奥にあるフロントのドアを開けて出てきた男は、遠目ながらペーパータオルか何かで手を拭き、それをダストボックスへと投げ込みます。その何気ない行為が、直感的にフロントで起きたであろう惨劇を予感させるのです。何故なら彼の手に付着したものが、間違いなく血であるということを確信させるほど、その演出が見事だったからです。カメラは近づいてくる殺人犯とそれを待つ相棒という画面を、その過程も含めワンカットで捉えます。車の左から右への横移動と殺人犯の手前から奥への緩慢な移動。俳優による静かなアクションとカメラの動きと奥行きを生かした構図。その時感じた興奮は、例えるなら、『ブレイキング・ニュース』冒頭の銃撃戦を目にした時と似たような感覚でしたが、それらはほとんど対極にいるかのようです。つまり静と動ということになりますが、『ヒストリー オブ バイオレンス』という映画には、何かを確信しているかのような、ほとんど不吉とも言えるような“静かな決意”のようなものを感じました。
相棒がモーテルのフロントに入ると、案の定、そこには2つの死体が血まみれで横たわっており、それを気にも留めない風なその男は、バックヤードに隠れていたであろう少女を見つけます。そして脅える少女に対し、一見穏やかな表情で少女に接しつつも、背中に隠した銃を抜く。ここでも銃声のみが響き、少女を撃つ瞬間を観ることはありません。フロントの2人もこの少女も、殺される瞬間が画面に映ることがないのです。それはその後に繰り広げられる、“暴力の無間連鎖”を際立たせるためだったのでしょうか。
ところで、ヴィゴ・モーテンセン演じる主人公は、ほとんど殺人兵器のように無駄の無い動きで人を殺します。その時の彼は、まさに反射的に人間を殺していくという意味で機械化しているとすら言えるのですが、それはある決定的な危機(それは友人のそれだったり家族のそれだったり、自分のだったりもします)に直面した瞬間、彼の“過去=暴力の歴史”が現実世界に顔を出すからです。よって、決して二重人格というわけではない彼は、必然的に2つの人格を使い分けねばなりません。しかしそれは、果たしてコントロール可能なのか。
全く対極にあると言っても過言ではない2つの人格の合間で彷徨うかに見えた主人上は、結果的には暴力を選択することになります。ここで重要なのはその動機ではなく、暴力から逃れられない主人公の諦念と、暴力それ自体の“暴力性”を客観的に描こうとするクローネンバーグの冷たい視線ではないか、そんな風に思いました。その証拠に、主人公が人を殺す時の描写は執拗に描かれます。至近距離から銃で頭を撃ち抜く瞬間を、頭を撃たれた男の銃創が痙攣し血がしたたる様を、あるいは腕を折った相手の顔面を掌底で連打する様を。
潜在的な凶暴性が顕在化する瞬間を体験するのは主人公だけでなく、その息子もまた暴力に目覚めるあたりが、唐突とは言え妙に説得力がありました。彼がエド・ハリスの背中をショットガンで打ち抜き、その足元に倒れていた父親に向かって肉片を飛び散らせる描写は、エド・ハリスとともに、それまでの家族思いで優しかった父親の虚像をも撃ったかのようで、つまり観客に“2重のショック”を与えているようで興味深く、かつ、とどめを刺される寸前で父親を救うという、所謂ハリウッド的なカタルシスもあるのですから、本作のクローネンバーグには驚くばかりです。
ラストシークエンスでは、食卓を囲む家族に主人公が戻ってくるのですが、あの場面をどのように受け止めたらよいのでしょうか。妻と息子が父親に食事を差し出すという行為が、“赦し”や“和解”を示唆しているであろうことはわかるのですが、それが全くの無言のうちに行われるということ。クローネンバーグはここで、結末を宙吊りにしたかったのではないかと思うのです。結局、暴力は暴力として常に我々の眼前に存在し、その存在には決して目を瞑ることなど出来ないが故に、一見再生したかに見えるあの家族が危うい均衡の上にかろうじて成立しているに過ぎないということ。その意味で、崩壊の予兆すら感じさせるラストの静けさが素晴らしい。
『ヒストリー オブ バイオレンス』は、黒沢清氏が青山真治氏の『Helpless』を評したのと同様な意味で“暴力映画”だったと思います。まるで似ていないこの2作品に共通するのは、暴力それ自体、あるいは暴力は暴力でしかないという現実を撮ろうとした監督の客観性だったのではないでしょうか。
2006年04月06日 12:04 | 邦題:は行
Excerpt: デビッド・リンチは、自分の作品につけられた「ノーマン・ロックウェル・ミーツ・ヒエ
From: Days of Books, Films
Date: 2006.04.11
Excerpt: 未明にライヴで観た、チャンピオンズ・リーグの興奮醒めやらぬまま新宿へ。デヴィッド・クローネンバーグ監督『ヒストリー・オブ・バイオレンス』を鑑賞。原題は『A...
From: BLOG IN PREPARATION
Date: 2006.04.20
>Ken-Uさま
私もラストシーンに漂うあの気まずさに感動してしまいました。間違いなく、あれは意図されたものでしょう。ただしそれは監督の“悪意”というより、むしろ“誠実さ”に起因している気がしました。
私もTBさせていただきます。
Posted by: [M] : 2006年04月20日 10:12
[M]さん、TBさせていただきました。
あの冒頭はとてもよかったですね。あっという間に作品の中に引き込まれしまいました。
あと、あのラストが”宙吊り”であることはたしかにそうだと思います。平穏であるはずの家庭がとても危うい均衡の上に成り立っている、という真実が剥きだしにされて、気まずい空気が漂っている。あの後味の悪さがなんともいえません。意図的に後味悪く演出してるんでしょうね。
Posted by: Ken-U : 2006年04月20日 02:35
>雄さん
なるほど、「偽善」といういうのもしっくりきますね。
だいたいあんな父親をすんなりと受け入れること自体に無理があるのですが、あのラストの食卓は、ほとんど現実離れした異様な空間ですしね。ありえないことが起こってしまうかもしれません。
いずれにせよ、ハリウッド的な結末ではなかったように思え、「宙吊り」という言葉を使いました。私も久々のクローネンバーグでしたが、彼は髪も切ってスッキリとイメチェンし若返ったみたいなので、私としてはまだまだこういう映画を連発してほしいです。
Posted by: [M] : 2006年04月11日 15:52
[M]さんのおっしゃる「冷たい視線」が際だっていましたね。もう少し「過剰」なものを想像していたので、ちょっとはぐらかされましたが。ラストに私は、妻と息子の表情に「赦し」より「偽善」に近いニュアンスを感じました。「宙吊り」ということは、どちらにも取れるのでしょうが。いずれにしろ、久しぶりにクローネンバーグを堪能しました。
Posted by: 雄 : 2006年04月11日 14:22
>ヴィ殿
息子ですが、私はあの時点で怒らないまま終るかな、とも思っていたんですが、まさかあのような形で爆発するとは。
そう、実は私もあの強引とも言えるラストに『ある子供』が思い浮かんだんです。しかしあのセックスシーンは凄かったですね。特に階段のシーンは、かなりカットを割って撮られていて、ほとんど格闘アクション的だったと思います。
Posted by: [M] : 2006年04月07日 16:35
いや、ほんと傑作でしたね。そして↑これも力作です! 息子はすでに学校でボコボコにしてまうとこで、「ああ、血は争えないか……」と思ってしまいますよね(哀しい)。夫のヒストリー(履歴)を知ってからの妻の態度、そしてあの倒錯的な行為の描き方はクローネンバーグならではで圧巻です。ラストは「ある子供」を思いだしました。
Posted by: こヴィ : 2006年04月06日 21:19

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]