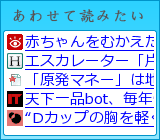2006年01月11日
『ある子供』に存在するフィクショナルな抒情性を肯定したい
当サイトを始めてから2本目に書いたレビューは、ダルデンヌ兄弟が撮った『息子のまなざし』でした。今、その文章を読み返してみると、興味深いことに、『ある子供』に対してこれから書こうとしている文章にも当てはまるであろう、いくつかの共通点が見い出せそうな気がしますが、同時に、明らかに異なる点もまた見受けられます。ここで、ではどちらにより感動したのかを比べることにあまり意義があるようには感じられないので、それには触れずにおきますが、ダルデンヌ兄弟が本作において、これまでと同様の“スタイル”を用いながらも、その着地点に劇的とも言えるシークエンスショットを配したことで、私は、彼らの作品が孕むある種のイメージに対する軌道修正を余儀なくされたような気がします。あくまで漠然としたこの思いを確認すべく、『ある子供』という映画を思い出して見ましょう。
「L'Enfant」という原題はそのまま「子供」と訳されます。前作の原題が「息子」というタイトルだったように、本作の原題もまた即物的かつ限定的な意味を与えられているように思えます。本作の邦題には“ある”という言葉が添えられていますが、原題は恐らくより狭義の「子供」(つまりブリュノのこと)を指していると思われ、そう考えると、“ある”という言葉はあまり適切ではないようなそんな気がしました。
さて、実は『ある子供』を観ながら、脳裏に何度と無くよぎった映画があります。ぶっきらぼうなタイトル、唐突な始まりと終わり、非=劇的な演出、そして何より、手から手へ紙幣が渡される瞬間の“不意打ちのクローズアップ”と紙幣を数える残酷な音の存在……私は『ある子供』を観ながら、ロベール・ブレッソンの『ラルジャン』を想起せずにはいられませんでした。
「金」という原題を持つ『ラルジャン』という映画は、そのタイトルが表すとおり、金が人に受け渡される瞬間の事件性を中心に据えつつ、1枚の紙幣がある男の人生を狂わせていくさまを簡潔極まりないショットの連鎖で描いた、ほ孤高の傑作とも言うべき作品ですが、『ある子供』で執拗に描かれた“紙幣の交換”を目にする時、そこに漂うある種の厳しさと、行為のそっけなさに反比例するショッキングな即物性が、『ラルジャン』の時のそれと通底するのではないかと思われたのです。『ある子供』は、“子供が子供を持ってしまうこと”を真摯に描いた作品だと私は思いますが、その過程で最も重要な役割を果たすのは、他でもない金(紙幣)です。主人公の自堕落な日常は資本主義的メカニズムに完全に支配され、そのシステムに無意識的に平伏しているとさえ思えます。その事実は主人公の、非=人道的ともいえる安易な行為を通じシステムの強度を際立せ、それが故に、ただただ痛ましい印象を齎すのではないでしょうか。
本作のカメラについて考えてみると、『息子のまなざし』と比べた場合、より客観的な存在だったように思われます。カメラがその眼差しを向けるべき対象が本作では2人だからなのか、確かなことはわかりませんが、どちらかというと、対象に冷めた視線を投げかける本作のカメラは、2人の背後に潜むベルギー地方都市のある現実を見据えているような気さえしました。子供が生まれたとはいえ、未だ幼さが残る2人の男女が頻繁にじゃれ合うシーンが幾度か見られましたが、カメラはその時、徹底的に無関心を装っているかのごとき印象を受けたのです。カメラの存在を意図的に印象付けた『息子のまなざし』と比べると、本作のカメラはより透明な存在へと変貌したのではないか、と。
もちろん、これまでのダルデンヌ兄弟作品がそうだったように、彼らの禁欲的とも言えるスタイルは健在でした。カメラの存在だけでなく、劇的な効果を伴った音楽は完全に排除され、自然音のみで構成されるという音響の面にもそれは明らかであり、そのあたりに漂う、“手段としてのドキュメンタリー的アプローチ”が批判の対象になってきたことも知らないではないのですが、だからと言って本作が、必ずしも間違ってはいない故にもはやある種の先入観にもなり兼ねない“擬似ドキュメンタリー批判”に当てはまるかというと、どうもそうではなさそうなのです。それは何故でしょうか。
その結論を出す前に、もう一点、気になったシーンに関して書いておきたいと思います。
それは、ブリュノ、ソニアそれぞれが交通量の多い幹線道路のような車道を横切るシーンです。それは、ある意味を込められているかのように何度か繰り返されます。車が流れる道路を垂直に横断するという運動は、『ロゼッタ』でも幾度か見られました。推測するに、ダルデンヌ兄弟はこのショットを絶対に重視しているはずです。さらに言うなら、そのシーンでは車の音がより強調されているようにも聞こえました。轟音の中を、慎重に、轢かれないように渡って行く様を、何故あんなにも繰り返し描いたのでしょう。
『ロゼッタ』でも『ある子供』でも、道路の向こう側には主人公の住居なり隠れ家なりがありました。言わば“安息の場所”に至るまでの儀式のような意味が、あの道路には込められていたように思われます。多くの車が行き交う道路を、例えば“社会”と捉えてみると、彼らは、常に重くのしかかってくる“社会”の重圧や速度に押し流されまいとしていたのではないか、それがあの“道路を渡る”という動作に象徴されていたのではないか、と。
ブリュノが子供を売ったことが直接の引き金となり、2人は決別します。以降、母親であるソニアが道路を横切ることは無かったように思うのですが、それは彼女のほうが先に社会へと順応していったからではないでしょうか。一方のブリュノは未だ現実が見えておらず、つまり「子供」のまま犯罪を繰り返し、出口の見えない金銭と盗品とで成り立つ交換のメカニズムから脱し切れません。ある女性のバッグを引ったくった現場を通りかかりの男性に発見され、舎弟のような少年とスクーターで逃げまわるという、サスペンスに満ちたシークエンスがありましたが、彼らがたとえ“社会”と同じ速さで道路を疾走しようとも、遂にそれは叶わず冷たい川(ここもまた身を隠すための“安息の場所”と言えないこともありません)に身を浸すしかないのです。
ともあれ、この時すでに物語りは架橋を迎えています。少年が警察に捕まる瞬間を、遠目で、なす術も無く見つめることしか出来なかったブリュノはこの後、少年が残したバイクを引きながら町を彷徨い歩きます。ブリュノはどうしようとしているのか、彷徨する彼を見ているだけでは先の展開が読めず、逡巡しているかのようなブリュノの思考の不安定さと、観客が想像する先行きの不透明さが重なり、ここでもサスペンスが生起します。そして、物語はラストシーンへと歩を早めていくのです。
さて、ここで先述した疑問に立ち返りたいと思います。本作が何故“擬似ドキュメンタリー批判”に当てはまらないと思ったのか。その答えは本作のラストシーンを観れば明らかです。何十テイクも撮り直したという本作ラストの長いシークエンスショットは、警察に自首したブリュノと面会に来たソニアの姿を、ただ見つめ続けるというものです。自らの非=社会性、つまり、“自分は現実の見えない子供だった”という自覚がブリュノに芽生えたかに見えるあの涙。だからと言って、ブリュノは依然として刑務所の中、彼らに再生への光が差したからといって、現実にどれ程の希望が持てるのかなど、知れたものではありません。ダルデンヌ兄弟は、またしても唐突に彼らからカメラ=眼差しを閉ざしてしまうでしょう。ちょうど『息子のまなざし』のラストがそうだったように。しかし、あの長いシークエンスショットの後半、泣き崩れる2人をカメラに収めたダルデンヌ兄弟は、それまで固執してきたスタイルに反して、見方によっては安易とも図式的ともとれる“涙”で物語を締めくくりました。あのラストシーンを観ながら私は、「これは紛れもない虚構だ」という思いを強くしました。好き勝手生きてきたブリュノの、“改心の兆し”だけを観て、ソニアまでその涙に感染してしまうなどという御都合主義的なラストなど、ダルデンヌ兄弟のスタイルだったろうか、そう思いもしました。しかしそうは思いながらも同時に、私は心から感動を禁じ得ませんでした。それはあのような図式的なラストシーンゆえでもあるのです。そこには、あるフィクションを現実に模した形で撮ってきた(とい思われてきた)ダルデンヌ兄弟の、ある種の決意を感じました。私が感動したのは、彼らが描きたかったあの、あくまで映画的な抒情性に対してなのです。無論、そんな叙情性によって、観客に優しい余韻を残すようなことを、彼らはしません。すでに書いたとおり、彼らに“アカルイミライ”など約束されてはいないからです。にもかかわらず、本作のラストシーンは感動的です。カメラの透明な存在…先にそのような表現を用いましたが、それは言い換えれば、映画の原点ではないでしょうか。
『ある子供』は、擬似ドキュメンタリーとしてではなく、紛れも無いフィクションとして撮られていると、私は確信しています。そもそも私は、彼らの擬似ドキュメンタリー性を否定はしていませんでしたが、本作ラストの堂々たる抒情性を前に、改めて彼らを見直しました。少なくとも私は『ある子供』のあらゆるシーンの背後にそのような作為性を観ることで、心から感動した人間なのです。
2006年01月11日 23:00 | 邦題:あ行
Excerpt: 食べてもお腹はこわしません ダルデンヌ兄弟の作品は現時点ではこれ一本しか見ていないので、体系的に考察することは不可能なのですが、単純に一本の映画として見ると出来は悪くないが、映画がダルデンヌ兄弟を必要としているというレベルのものではないと感じまし...
From: 秋日和のカロリー軒
Date: 2006.01.14
Excerpt: 終日雨。恵比寿で映画2本。 ジャン=ピエール・ダルデンヌ、リュック・ダルデンヌ 監督(ダルデンヌ兄弟)の『ある子供』を鑑賞。原題は『L' ENFAN』 川と道路に挟まれた小さな小屋。コンクリートに囲まれたブリュノの居場所は薄暗く、見当たるのは寝床のダンボールくら...
From: BLOG IN PREPARATION
Date: 2006.02.02
Excerpt: 『ある子供』公式サイト 監督:ジャン=ピエール&リュック・ダルデンヌ出演:ジェレミー・レニエ デボラ・フランソワほか 【あらすじ】(goo映画より)定職につかず、少年たちを使って盗みを働き、盗品を売ってその日暮らしをしている20歳の青年ブリュノ。ある...
From: Swing des Spoutniks
Date: 2006.02.04
>Ken-U様
こんにちは。
全然場違いではありませんよ。ありがとうございます。
仰るとおり、その二者を明確に仕切ることに意味はないのかもしれません。上記文章中で私は、便宜的に二者を区別しましたが、それが意図されたものだったとはいえ、やや早計だったのかもしれません。どっちだって関係無いといわれれば、まったくその通りです。
「ここだ」というところで終るラストに関しては、私も同様に感動しました。ダルデンヌ兄弟の作品のラストは総じてあんな感じ終ります。私としてはまず『息子のまなざし』を強く推薦いたします。
Posted by: [M] : 2006年02月03日 12:37
[M]さん、うちの方にコメントありがとうございました。勢いあまってTBさせていただいたんですが、なにやら難解な議論がされているようで、ちょっと場違いだったかな、と少し後悔してしまいました。
現実世界がフィクション化を加速しているように思われる昨今、ドキュメンタリーとフィクションの境界は曖昧になっているように感じられます。そんな世界の中で、フィクションと(擬似)ドキュメンタリーを明確に仕切るのは難しそうですね。ぼくはどちらでもいい派です。
さて、擬似ドキュメンタリー批判とやらには関心がないせいか、ぼくはこの作品が素晴らしく思えました。ラストについても文句なしです。「ここだ」と思えるところで終わってくれましたよw
[M]さんが指摘されていた、冷淡なカメラ・ワークと「道路を渡る」ショットについては、ぼくも同じような思いを抱きました。
実は、ダルデンヌ兄弟の作品を観るのはこれが初めてだったんですが、過去の作品にも興味が湧きました。そのうち旧作も観てみたいと思います。
Posted by: Ken-U : 2006年02月02日 15:45
>koi様 秋日和様
改めまして、貴重なご意見をありがとうございます。
ご返事が遅れましたが、お二人のコメントを受けて思うところを書いてみます。
まず、これは大前提といってもいいと思うのですが、koiさんが仰るように、あらゆる映画にはフィクショナルな部分がある、ということ、私も日頃そのように映画を観て来たつもりですので、何ら異存はございません。そしてもう一点、ダルデンヌ兄弟が「擬似ドキュメンタリー的」な作品を撮っているという点に関して、私はそれを否定してはいません。拙文の最後のほうで、“〜擬似ドキュメンタリーとしてではなく、紛れも無いフィクションとして撮られている〜”と書いてしまったため、私がダルデンヌ兄弟の“擬似ドキュメンタリー性”を認めないかのように受け取られてしまったのかもしれません。彼らは確かにそのような撮り方を自分達の“スタイル”(それを“武器”と言い換えてもいいかもしれません)としている、これは事実だろうと思います。
さて、以上の前提に立った上で改めて考えてみます。
koiさんは、“作品中にフィクショナルな部分を見つけるのは難しい”と仰られましたが、やはり、私の思いは変わりません。確かに、その思いを適用させることで、あらゆる映画を同様に説明できてしまうという指摘はその通りでしょう。しかし先ほども触れたように、あらゆる映画にはフィクショナルな部分があるという前提に立てば、私が『ある子供』の作品中、ある箇所にそれを認めたところで矛盾はないはずです。まぁ書いた後であれこれと言い訳するようなことはあまりしたくないのですが、この文章の中での私の最大の主張は、ダルデンヌ兄弟のこれまでのスタイルは認めつつも、あえて戦略的に本作のフィクション性を強調することで、私のこれまでの“ダルデンヌ観”を修正し、新たな価値を認めてみたい、そのようなものでした。
ラストシーンの解釈に関するご指摘も、これまでの彼らの作品を受けた形で、私としては「刑務所での面会を受けてブリュノが泣く」という演出の存在をあえてフィクショナルで図式的だと解釈することで、同様に本作を顕揚したかったということなのです。
なにぶん、文章力の欠如によりその思いが伝わらなかったのはひとえに私の至らなさではありますが、書く以上、何とか新しい視点を提案できないだろうかという私なりの思いを何とか文章にした結果なのです。
秋日和さんが仰るように、私としては、彼らがどのようなスタイルで映画を撮ろうと関係ありません。ある人にはそれが鼻持ならないでしょうし、ある人には感動的かもしれませんが、「擬似ドキュメンタリー的」と見なされ得ることは考慮に入れはしても、少なくとも、それで作品を貶すことはしたくなかったというところです。koiさんも言われるように、その先にある可能性を考えてみたいという気持ちは私も同じです。
次に秋日和さんのご指摘にあった“「納まっている」という印象”、その意味するところを感覚的にわからないでもありません。ただ、非常に抽象的な話であるようにも思われ、秋日和さんと同様な(あるいは近似した)映画的感性を持つ方でないと、その言葉だけで納得するのは難しいように思います。私も『骨』は観ており、確かにあの映画は『ある子供』どころか、いかなる映画とも似ていないという印象を持ちましたが、ペドロ・コスタと比べてダルデンヌ兄弟が“優等生的”という風には思いません。私もこれまで自分の文章中で、ある作家や作品の名前を引き合いに出したりもしてきました。どちらかというと双方を顕揚する目的でそれを行ってきましたが、片方を貶す口実として、別の作家や作品の名前を出したこともあったと思います。しかし今、自戒を込めて言うなら、そのような行為は非=生産的であるとすら思っています。いずれにせよ、作品を測る価値基準は自分にしかないものでしょうから、感じ方の違いは平行線足らざるを得ない部分もありますが、秋日和さんが仰られたこと自体は、私は理解できるつもりです。
随分と長くなってしまいましたが、お二人のご意見は真摯に受け止めております。上記コメントでは納得できない部分もあるかもしれませんが、基本的な思いは全てレビューのほうに込めておりますので、今はこれ以上言及するのは難しかろうと思いますが、これに懲りず、今後とも宜しくお願いいたします。
ありがとうございました。
Posted by: [M] : 2006年01月16日 11:42
こんにちは、MさんとKoiさんの評を非常に非常に興味深く読ませていただきました。ボクはダルデンヌをこれ一本しか見ていないので、余り語る資格がないと思っているのですが、いちげん者なりに感じたことは『ある子供』は「納まっている」という印象をうけました。映画であることに程よく納まっていて、まあ、それを駄目だといってしまうと反動的になるのですが、例えば、カサヴェテスも小川伸介もとりあえず作家としてのいろんな意図がありながらもどっかでそれがどうでもよくなるくらいはみ出してしまっているという部分があると思うのです。
もうひとつ、ボクはどうしても題材として似ているペドロ・コスタの『骨』と比較してしまいます。そうなるとダルデンヌの方が良くも悪くも安心して見られてしまうのです。
それから、スタイルが最大の論点となっていると思うのですが、映画がショットのつながりであるかぎり、ボクは擬似フィクション形式でもなんでも構わないと思うのです。例えば、ウッディ・アレンが全編手持ちカメラで撮った『夫たち、妻たち』はもの凄い映画だと思ってまして、あれは論理的なところから離れて「野蛮人」に還って見てみると、やはり野蛮なことやってるから感覚が反応してるのではないかと、、、なので、ボクがまだ1回だけ見た限りでは、大学とかの論文ならAをもらうような作品なのではないかと感じたのです。
まとまりなくてスミセン。
Posted by: 秋日和 : 2006年01月14日 12:59
>keikoさま
私も先程ワインを1本空けまして、酔っ払ってはいませんが、思考は鈍っております。
あまりワクワクする文章ではないと思いますが、映画観たらまた感想をお寄せいただければと思います。
>koiさま
どうもお久しぶりです。
私なりに再考し、改めてお答えしたいと思います。このエントリーに書きますので、しばしお時間をください。
Posted by: [M] : 2006年01月14日 02:27
お久しぶりです。
今回の投稿、一言一句飲み込むほどに読みました。それだけ自分の見落としが思い起こされ、自分とは異なった見方に関心を抱かされたのです。特に『ラルジャン』との比較は盲点で、非常に興味深い考察でした。
けれども、やはり、どうしても気になる点がいくつかありました。以下、いくらか否定的な文脈になるかもしれませんが、どうかご容赦ください。
まず、やはりダルデンヌ兄弟の作品中にフィクショナルな部分を見つけるのは難しいように思います。と言いますのも、本来どんな映画も全てフィクションの部分を持っているように思われますし、この作品にフィクショナルな部分を見つけるなら、他のどんな映画でもそれは可能なのではないかという気がするからです。
むしろ、映画は「足し引き」の芸術だとよく言いますが(そういえば北野武も言っていました)、それならばダルデンヌ兄弟のカメラの基本的な被写体に対する近さと、「本物っぽい」手ブレ、ドキュメンタリーっぽい編集がほぼ全編にわたって繰り広げられ、それゆえ「ドキュメンタリーっぽさ」が「足し」の部分でかなり積み重なってしまっているわけですから、それをいくつかのショットで「引き算」するだけで、帳消しにするのは難しいように思います。
また、[M]様はラストシーンのことにも触れられていますが、あそこで泣くか泣かないかは、ドキュメンタリーかフィクションかということには直接的にも間接的にも関係しないのではないでしょうか。あのシーンで泣かなくてもフィクションと言え、実際の通り泣いてもドキュメンタリー的とも言えるように思います。
そうした場合、やはりダルデンヌ兄弟は「擬似ドキュメンタリー」的な作品を撮るということを前提に認め、ではそこで同語反復に陥らないためにどうすべきかを考えるのがいいように感じるのです。
そのあたりは、たどたどしい言葉遣いではありますが、自分のブログにも書いてみましたので、読んでいただけたらと思います。
貴重なスペースで長々と拙文を失礼いたしました。不肖の身ではありますが、今後ともよろしくお願い致します。
Posted by: koi : 2006年01月14日 01:21
こんばんは。
まだ新しい記事、
一行も読んでませんが、何かワクワクする雰囲気が漂ってます!
映画を観てからとっくり読ませて頂きたいと思います。
Posted by: Keiko(as 酔っ払い) : 2006年01月13日 22:39

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]