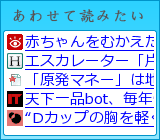2005年01月31日
『下妻物語』の遊戯性と厳格さ
 『下妻物語』を観終えた直後に感じたのは、やや居心地の悪い、しかしかすかな微笑を伴った“敗北感”でした。「やられた…」という思い、と言い換えてもかまいません。それは恐らく、観る前から「CM出身監督」と高を括っていたということでしょうが、結果的には(全てとはいえませんが)杞憂だったようです。短時間に映像(情報)を詰め込まなければならないCMは、いきおい、“過剰なわかりやすさ”を義務付けられている部分もありますが、それはあの時間内だから了解できるのであって、映画でそれをやられてしまうと、これはもう観るに耐えない代物に成り下がってしまうものだというのがこれまでの認識でした。この認識は、実際にCM出身監督の作品を観ることで確かめ得た部分もあるという意味では“正確”であり、一方で、それらの印象が齎してしまう偏見の可能性も否定できないという意味では“曖昧”でもありました。ここで今回私が感じた“敗北感”に立ち返れば、この後者に当たる認識が(ある程度)裏切られたことに拠ると言えるでしょう。
『下妻物語』を観終えた直後に感じたのは、やや居心地の悪い、しかしかすかな微笑を伴った“敗北感”でした。「やられた…」という思い、と言い換えてもかまいません。それは恐らく、観る前から「CM出身監督」と高を括っていたということでしょうが、結果的には(全てとはいえませんが)杞憂だったようです。短時間に映像(情報)を詰め込まなければならないCMは、いきおい、“過剰なわかりやすさ”を義務付けられている部分もありますが、それはあの時間内だから了解できるのであって、映画でそれをやられてしまうと、これはもう観るに耐えない代物に成り下がってしまうものだというのがこれまでの認識でした。この認識は、実際にCM出身監督の作品を観ることで確かめ得た部分もあるという意味では“正確”であり、一方で、それらの印象が齎してしまう偏見の可能性も否定できないという意味では“曖昧”でもありました。ここで今回私が感じた“敗北感”に立ち返れば、この後者に当たる認識が(ある程度)裏切られたことに拠ると言えるでしょう。
では『下妻物語』は“過剰さ”を内包していないのかいうと全くそんなことはなく、むしろ“過剰さ”は全編に溢れていると言えます。まずその“過剰さ”とは何かということですが、本作における(というのも、これは作品によって変わるものだからですが)それを敢えて定義すれば、「画面に付与された(有形・無形の)ギャグ要素が氾濫している状態」ということになります。冒頭の事故シーンにおける“映像的スローモーション”(極度に装飾的なそれは、あの「サッポロビール」のCMを直ちに思い出させるでしょう)からしてすでに明らかですが、さらにいくつかの例を挙げるなら、フレームを飾るイラストレーションや度々登場するテロップ(字幕)、頻発される直接的、間接的な固有名詞の類やそれを阻む電子音(ピー音)、あるいは深田恭子によるあのナレーションすらがそれに当たると思います。ほとんど“悪ノリ”とも言える程に好き勝手やっているかとも思われるその様は、『KILLBILL Vol.1』におけるタランティーノを想起させもします。お笑い芸人を起用するあたりの“臆面なさ”には容易に納得できない自分も居はしましたが、怪優・阿部サダヲの大胆極まりないかぶりモノに至っては、その“悪ノリ”を感じさせつつも、その度を越した存在感が物語を根底から揺さぶる様を目の当たりに出来て感動的でした。とどのつまり、『下妻物語』には“過剰さ”に覆われていたと結論したいのですが、しかし、それだけが私に“敗北感”を齎したわけではないのです。
『下妻物語』には、時折ハッと息を飲むような画面が存在します。それはあの茨城の、透明でイノセントな青空の挿入だとか、あるいは、深田恭子と土屋アンナの屋内での会話を左右のパンで大胆に切り取ったシーンだとか、やはりこの主人公2人の“友情の萌芽”を、かなりの高みからさりげなく捉えたパチンコ屋脇におけるロングショットの存在に見受けられるのですが、つまり、随所で反復されるギャグを“締める”画面の存在がかなり慎重に配置されていて、“過去との決別と新たなる人生への一歩を踏み出すこと”という、題材としてはそれほど珍しくない本作の主題を、最後まで飽きさせずに持続させる“生真面目な”説話手法に心底感心した結果、件の“敗北感”に至ったというわけです。
“過剰さ”に彩られながらも、CM的な“インパクト”のみで語ることをたやすく許そうとはしない厳格さ。“映画とは?”という根源的な問いを改めて考えさせるという意味で、極めて貴重な映画であることを認めざるを得ないでしょう。
2005年01月31日 05:25 | 邦題:さ行
Excerpt: 普段の自分ならよほどの事が無いと観に行く映画の一本とならないハズのタイトルとポスターデザインと出演者、、、 でも宣伝バンバンの話題作で無くてもじわじわ「あれ、面白いよー」ってなんとなく口コミっぽく伝わってくる映画ってありますよね。特にネット時代にな...
From: It's a Wonderful Life
Date: 2005.01.31

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]