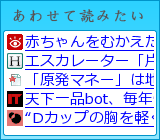2004年05月24日
『KILLBILL VOL.1/VOL.2』、映画とのラブストーリー
映画を観にいく時、その大小はあれど何らかの“興奮”を隠し切れないものですが、それはこれから観る映画の期待値にかかわらず、まさに“映画を観に劇場に足を運ぶ”ことに起因する興奮なのだと思います。映画を観に行くということ自体が持つ“興奮”、しかし、時としてこの“興奮”が度を越してしまうと、話は厄介です。冷静さを失い、“興奮”そのものに埋没してしまいかねないから。
ある意味“過剰”とも言えるそんな興奮を覚えることは至極稀です。しかしながら、クエンティン・タランティーノが6年ぶりに撮った『KILLBILL』には心底興奮したと告白しなければなりません。私自身の映画的ルーツである香港アクション映画への郷愁や、それが『新・仁義なき戦い』のテーマだと分かってはいても、画面との奇妙なマッチングにやはり興奮せずにはいられない布袋寅泰によるギターサウンドや、もちろん、タランティーノが久方ぶりに見せてくれるであろう、極度のシネフィル的サンプリングにも、その異常な興奮の原因を認めることが出来るかもしれません。しかし、それにも増して痛感した事実、それは、久しく意識していなかった“劇場に足を運ぶことの喜び”と、『KILLBILL』に溢れるタランティーノの“映画への愛”が、奇妙な形でシンクロしたかのような錯覚を覚えてしまったからなのかもしれません。この時点で私は、いささか冷静さを欠いていました。これは極めてまずい状態です。果たして、『KILLBILL』は手放しで賞賛すべき作品でしょうか? その問いに答えるには、今一度我に変える必要があるでしょう。
まず最初に、『KILLBILL』が2編として公開されたことについては、この際目を瞑りたいと思います。それを1本の作品として観たかったのは言うまでもありませんが、タランティーノ自身、ハーヴェイ・ワインスタインの提案を悪く思わなかったどころか、そんな“贅沢”が許されるならと、自ら面白がっていたのではないか、とも思えるからです。そして、すでに2編に分けられ公開されてしまった以上、まず前提としてそれを受け入れなければならない。以下は、2編を観終えた私の、言ってみれば苦さと幸福さとが混ざり合った、複雑な心境の告白でです。
さて、改めて冷静さを取り戻して考えてみれば、『VOL.1』は決して傑作とは言えません。タランティーノ的サンプリングの元ネタ探しに躍起になってみたり、飛び交う不自然な日本語に笑いを求めたりするという楽しみ方が無かったわけではありませんが、そのような喧騒に惑わされてしまうことにより、『VOL.1』に偏在する数々の欠点を見逃してしまうことは全くナンセンスだと言うほかはないでしょう。
“復讐は冷えてからが一番おいしい料理だ”『VOL.1』の冒頭に、そんな古い諺が出てきます。“冷える”とは言うまでも無く、時間の経過を意味します。これにより『KILLBILL』における復讐は、そう簡単に達成できないのだと知らされます。それは極めて長い道のりです。だからといって、タランティーノにおける“時間”とは、一方向に流れていくだけのものではないのは周知の通りです。つまり観客は、その復讐に途方も無い時間を要したという意識が希薄なまま、この復讐を追っていくしかないのです。実際、ユマ・サーマン演じる主人公が記する“復讐ノート”を見ると、決して順番どおりに復讐を達成していないことがわかります。ルーシー・リュー、そしてヴァニータ・グリーンは、ノートに見られる順番とは反対に死んでいくのですから。それは恐らく、青葉屋における大掛かりなアクションを『VOL.1』の見せ場にするためでしょう。事実、ヴァニタ・グリーンとの格闘は、物語の“つかみ”にこそふさわしい。死闘にいたるには青葉屋という装置が不可欠であり、『VOL.1』はその死闘により、ユマ・サーマンの強さのみが際立って終わるのです。あまりに無駄と言うほかない細部の描写、すなわち、沖縄で千葉真一と絡む挿話や、飛行機に絡む諸々のシーンや、たとえプロダクション I.Gが監修したとしても“オカズ”の一つに過ぎないアニメーションシーンなどは、説話的必然性を甚だしく欠き、ご愛嬌としては許せるという程度です。ということはやはり、『VOL.1』では、何よりもザ・ブライドの強さを後半部分への強い印象として残せばそれでよかったと言うことが出来ます。
ところで、『KILLBILL』の武術指導はユエン・ウーピンですが、もはやその事実は大きな期待を抱かせる要因にはなりません。その理由は彼の“相対的な”ネームバリューの低下に存しています。彼のハリウッドにおける特権は、作品を連発することで次第に薄められてしまいました。だとするなら、注目すべきは“誰が振付けたのか”ではなく、アクション自体が“どう撮られているか”ということになるでしょう。「そんなことはわかってるよ」と言わんばかりに、香港アクションフリークのタランティーノは、流石にその勘所は心得ているかに見えます。ヴァニータ・グリーンとの格闘を観ると、アタックとダメージの切り替えしが非常に効果的で、言い換えれば、そのカット割りは明らかに香港映画のそれだったと思います。お茶目な彼はいかにもオタクらしく、冒頭にショーブラザーズのマークなど入れてみるのですが、そんなサーヴィスなど無くてもアクションをみればそれが香港映画的だと了解できるのです。しかし、香港映画の枠をはみ出さないという点で、決して新しくはない。その代償としてかどうかはわかりませんが、『VOL.1』には、あまりに“過剰な”サーヴィスが溢れています。いや、それは観客へのサーヴィスではなく、彼が単にやりたかったことなのかもしれないのですが…(それが悪いとは言いませんし、むしろそこにこそ『VOL.1』の美点があるという見方もあるでしょう)。
閑話休題。ほとんど漫画的な強さだけが強調された『VOL.1』とは打って変わって、『VOL.2』は愛の物語です。その分、前編に比べて非常に地味な印象が拭えません。しかし、この落差に戸惑う暇もない程、実に堂々とした演出とシーン構成の冴えが全編に漲っています。その事実は、冒頭、モノクロームで撮られたデヴィッド・キャラダインとユマ・サーマンによる一連の会話とその後の殺戮を、教会の外側からのロングショットによって隠すという手法を観れば明らかだと思います。緊張感溢れる至近距離からの銃撃シーンをアップで捉えた『VOL.1』のファストシーンに対し、『VOL.2』では同じ舞台を全く別の次元で捉えている。始めから2部作を想定して撮られたと思うくらい、的確なオープニングです。さらに付け加えれば、『VOL.2』ではタランティーノ的“会話”を取り戻しているのです。『レザボア・ドッグス』から一貫して“(無駄な)会話”に拘ってきたタランティーノは、全体として決して派手なアクションの人ではなかったはず。その意味で、本来の姿に返ったと言うのは大袈裟過ぎるでしょうか。
例えば、マイケル・マドセンと彼が用心棒として働く店の店主との会話、あるいは、デヴィッド・キャラダインとユマ・サーマンの蜜月時代を回想するシーン(燃える炎を前に会話するシーンの美しさ)、さらには、まさに死につつあるマイケル・マドセンを前に、ダリル・ハンナがブラックマンバの猛毒ぶりを説明するシーンを想起しても良いですが、これらのシーンにおける演出の的確さは、才能ある“アメリカ映画”作家としてのタランティーノの“上手さ”を理解するのに充分過ぎるくらいです。『VOL.2』は、地味ですが良質の“アメリカ映画”という位置づけが可能だと思います。今、こういう“真面目なアメリカ映画”を撮ることが出来る監督が何人いるでしょうか。そう、『VOL.2』はすこぶる真面目な映画なのです。
この真面目さは、中国での修行シーンにおいても変りはしません。ゴードン・リュー演じるパイ・メイは、クンフー映画に不可欠とも言える“師匠”という役柄をそっくりそのまま生真面目に反復してみせます。あの、冗談かとも思えるような、過剰な演出というか模倣。にもかかわらず、ゴードン・リューがその長い顎鬚をなでながら「うむ」と頷く時、この図式的な演出と潔い御都合主義が、幸福に出会ったかのごとく画面が潤ってはいなかったでしょうか。だからこそ、千葉真一のご愛嬌的シーンとは比較にならないその真面目さに、私は感動せざるを得なかったのです。『VOL.2』において個人的に大好きなシーンであるあの修行シーンは、ほとんど逸脱寸前のところでかろうじて踏みとどまっている感もありますが、それが許される土壌を結果として築いてしまっているタランティーノは幸福であり、それこそが才能なのだと思いたい。何故なら、香港映画ファンに向けて作られているのかもしれない(もしくは、
ただそれを撮りたかっただけなのかもしれない)一連の修行シーンは、しかし、物語上無くてはならないシーンでもあるのです。タランティーノは、中国ロケを心底楽しんだのではないかとすら思いますが、それが見ているこちらに伝わるからこそ、冒頭に書いた“興奮”へと無防備に陥るほか無かったのです。
『VOL.2』が愛の物語だとは既に書きました。この壮大なラブ・ストーリーは、デヴィッド・キャラダイン無くしては成立し得なかったと思います。しかし、最終的に殺しあう二人が、子供を前に会話する場面の奇妙な違和感はただごとではありません。それは恐らく、あの子供の描き方によるものでしょう。彼女は、子役として役を“演じて”いるのだという当たり前の事実を、最後まで画面に定着させませんでした。つまり、“子供”としてただそこにいた、と言えばいいでしょうか。デヴィッド・キャラダインとユマ・サーマンの宿命的な対決など端から頭に無い彼女は、ひたすら無邪気ですが、無邪気さという演出的なカテゴリーにも収まってはいなかったはずです。これはタランティーノ映画において、一つの事件ではなかったかと思います。物語への加担を拒むような彼女の存在。それが違和感につながりつつ、さらにその先にある感動へと私を導いたのです。
もちろん、デヴィッド・キャラダイン以外にビル役はありえないと断言したくなるほど、彼の存在は異常なセクシーさを醸しだしていましたし、とりわけ、子供に食事を作ってあげるシーンの何気なさに潜むエロティシズムを秘めた声と動作には舌を巻きました。最後の対決を前に、ユマ・サーマンと会話するシーンの、悪役以上の人間的ずる賢さを体現するキャラダインは、『VOL.1』にほとんど出演していませんが、それは『VOL.1』がラブ・ストーリーではなかったからです。
でも、いささか強引ですがこう考えてみることは出来ないでしょうか。つまり、『KILLBILL』という途方も無いサーガは、映画への愛だけで一篇の映画を創り上げることが出来るかという、ほとんど図々しいまでの試みで、そうであるなら、『KILLBILL』は2編を通して、タランティーノと映画自身のラブ・ストーリーなのだ、と。映画好きの監督と、映画によるラブストーリーを地で演じること。これを嫉妬を込めずに見守ることは、私には不可能でした。よって、これまで書き連ねてきた文章は、そんなラブストーリーに嫉妬した人間の、恨み言のようなものだったのかもしれません。
2004年05月24日 18:37 | 邦題:か行

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]