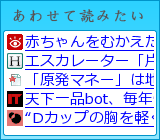2008年05月30日
『タクシデルミア ある剥製師の遺言』はいかにも東欧らしい
TAXIDERMIA/2006年/ハンガリー・オーストリア・フランス/91分/パールフィ・ジョルジ
パールフィ・ジョルジ監督の長編第2作目。
私は『ハックル』を見逃していたので、この監督のスタイルをまったく知らなかったのですが、会社の元・後輩が本作のことを教えてくれて、美大出身の彼女が反応するような映画であれば、それなりに面白いかも、ということで臨んだ次第。
さて、ハンガリー映画といっても、私の記憶に上がってくるのはタル・ベーラ監督くらいなのでいかなる定義も出来ませんが、なるほど、これが“東欧の映画”である、ということだけは、妙に納得できてしまうのです。その根底にある“陰鬱さ”というべきか、“アナーキズム”というべきか、あるいは“グロテスクさ”というべきか、とにかく私の東欧映画に対する漠としたイメージに本作が重なった気がした、というのが最初の印象です。
三世代にわたって風変わりな男の人生を追った『タクシデルミア ある剥製師の遺言』では、公開前から、その目を覆わしむるグロテスクな描写が話題になっていたようで、実際、それらはなかなかのインパクトを脳裏に焼き付けたわけですが、それらに一貫していたのは、ある種ファンタジックな創造性であって、現実にはほとんどありえないようなイメージなので、実際にそう思ったかどうかはわかりませんが、あくまでフィクションであるという点を最大限に利用しようとする監督の一貫性を感じることが出来、悪くないなと思いました。その点で、とあるインタビューに、好きな監督としてテリー・ギリアムはもちろんとして、アレハンドロ・ホドロフスキーの名前を挙げているのを読んだ時にも、それがたまたま私の嗜好性と合致したというだけなのですが、大いに納得したりも。
事物に対するフェティシズムを感じさせる場面が多く、それはそのまま、画面そのものの造形性にも反映されていたようでした。矛盾を恐れずに言えば、この監督は相当“視覚型”の監督だと思います。とりわけ、カメラが360度立回転するという離れ業は、物語の展開ともマッチしていて新鮮。恐らく本作のために考案されたであろう装置の数々だったり、一人の人間のフェティッシュな欲望を徹底して見つめるようなカメラの位置や動き、そして効果音等は、グロテスクを通り越して、むしろ笑ってしまうほど。それをシニカルと断じてしまっていいものかどうかわかりませんが、何にせよ、描写がグロテスクなまでにデフォルメされていて、何もかもが極端だという印象もあり。
最後に登場する剥製師だけが、自ら死を選んでいるという事実は重要かもしれません。
自分自身を剥製にしたいというほとんど無謀な欲望が、(当然ながら)完全な形では成し遂げられないという、ある意味衝撃的なラストに、観客は何を感じるのでしょう。
肯くか? のけぞるか? 悲しむか? 笑い飛ばすか?
2008年05月30日 18:41 | 邦題:た行

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]