2005年10月31日
必見備忘録 11月編
東京国際映画祭が閉幕し、今月はフィルメックスです。
観なければならない作品が多すぎるのですが、果たして何本観られるのか・・・
■『ランド・オブ・プレンティ』[上映中]
(シネカノン有楽町 10:25/13:05/15:45/18:25〜20:45)
■『ドミノ』[上映中]
(渋東シネタワー 10:20/13:10/16:00/18:50〜21:15)
■『ハックル』[上映中]
(シアター・イメージフォーラム 11:00/13:00/15:00/17:00/19:00〜20:30)
■『ブコウスキー オールドパンク』[上映中]
(シネ・アミューズ イースト/ウエスト 21:20〜23:15)
■『空中庭園』[上映中]
(ユーロスペース 11:00/12:00/13:20/14:20/15:40/16:40/18:00/19:00〜21:05)
■『TAKESHIS'』[上映中]
(渋谷シネパレス 11:30/13:50/16:10/18:30/20:50〜22:45)
■『ロバと王女(デジタルニューマスター版)』[上映中]
(ル・シネマ 11:00/13:00/15:00/17:00/19:00〜20:45)
■『アイドルたち』[上映中]
(アミューズCQN 21:30〜23:15)
■『モンドヴィーノ』[上映中]
(アミューズCQN 10:00/12:55/15:50/18:45〜21:15)
■『マカロニ・ウエスタン 800発の銃弾』[上映中]
(アミューズCQN 10:45/13:30/16:15/19:30〜21:55)
■『シャーリー・テンプル・ジャポン・パートII』[11/5〜11/11]
(UPLINK X 13:00/15:00/17:00/19:00〜20:10)
■「第6回東京フィルメックス」[2005年11月19日(土)〜11月27日(日)]
『ランド・オブ・プレンティ』には個人的に期待しています。実は先日、『アワーミュージック』とハシゴしようと思いましたが、とても疲れてしまったので、見送りました。これだけは外せません。
『ドミノ』はあまり評判がよろしくないようですが・・・キーラ・ナイトレイは好みなので。
『ハックル』『ブコウスキー〜』『空中庭園』は先月見逃しました。今月もそのまま見逃してしまう可能性大ですが、気が向いたら。
『TAKESHIS'』を観ないという選択肢は私の中にはありません。
『ロバと王女』は未見でした。嘗て澁澤龍彦がエッセイの中で触れていましたが、ドヌーブがどれほど魅力的か、この目で確かめてみたいと思います。
『アイドルたち』には、あの怪優ピエ−ル・クレマンティが出演しているというだけで胸が踊ります。
『モンドヴィーノ』は、映画としてというより、興味ある題材のドキュメンタリーとして。無論、映画としての評価をつけることになるかと思いますが。
『マカロニ・ウエスタン 800発の銃弾』は、チラシを観たときに胸騒ぎがしたので。アレックス・デ・ラ・イグレシア作品は全てを観ているわけではないのですが、西部劇ですからね、一応。
『シャーリー・テンプル・ジャポン・パートII』はやっと観られるという感じ。この期間中は本作を最優先させます。
「第6回東京フィルメックス」には観たい作品が多いのですが、恐らく2本観られればいいかな、と。『バッシング』(11/20 16:00〜有楽町朝日ホール)と『アコード・ファイナル』(11/26 19:00〜有楽町朝日ホール)です。東京国際映画祭にはいささか幻滅したので、こちらには期待しています。
『都市の夏』が公開されることでなんとも魅力的な「ドイツ映画史縦断1919-1980」には、スケジュールの都合上、多分一本も観られません。無念、そして無念……
2005年10月30日
封印されるということ〜『放送禁止映像大全』を読んで
先日、渋谷TSUTAYAの書籍コーナーを物色していた際、映画本の棚に『放送禁止映像大全』(天野ミチヒロ著 三才ブックス刊)という書籍を見つけ、パラパラとページをめくっていたら、『追悼のさわめき』(1988年 松井良彦監督)に関する件を発見。見開き2ページ分の、分量的にはかなり物足りない言及ではありましたが、『スパルタの海』あたりも取り上げられていて、どうやら浅く広くではありますが、この手の作品を網羅的に取り上げる著者の姿勢にはそれなりの対価を、というわけで結局購入してしまいました。
“封印された”とか“禁じられた”とか、あるいは“呪われた”とか称される、所謂放映(放送)困難(不可能)な作品群に対する興味は、恐らく、私がインターネットを使い出したあたりから加速度的に高まってきたものと思われます。私の興味の矛先は、無論、“封印されるに至った経緯”に向けられているのですが、それまで一部の関係者やマニアの間でしか語られてこなかったであろう各々の作品に潜む背景が、インターネットを通じてかなり一般的に共有されるようになってきたのではないでしょうか。そもそも人間には、隠されたり遠ざけられたりされているものを、何とかして観たい、知りたいという感情があると思うので、決してその手のマニアではない私も、それがこと映画(あるいはそれに準ずると判断できる映像作品)に関してであれば、やはり、何とかして観ることは出来ないだろうか、という思いに捉えられもするのです。
とはいっても、そのような目で実際にそれら封印作品を観ても、大概は拍子抜けすることが多く、例えばこの手の作品の中では最も有名で、典型的な封印作品である『ウルトラセブン 第12話』を観ても、いい大人の目には、“ウルトラセブンの1エピソード”くらいにしか見えないということ。つまり、それが我々の目から隠蔽されている原因を知ってしまえば、大半はもう観なくてもいいような作品が多いと思います。
現在の自主規制コードとは違い、嘗ての映画やテレヴィ番組には、所謂差別用語が頻発されたりしますが、たったそれ“だけ”の理由で封印されている作品の何と多いことか。そこに時代背景を超越した、ほとんど反=社会的ともいえる悪意が込められているのであればまだわからないこともありませんが、人間の根底にある差別意識はたかだか50年程度で変貌したり消滅したりするものではないし、現在においても当時とは別の言葉で同じような差別語はまかり通っていたりするのでしょうから、それが古く、今はあまり使われなくなった言葉だからという理由で、そんな過去を無かったかのようにただ抹殺し、我々の目から奪おうとする権力的思考そのもののほうがよほど悪意に満ちているような気がしないでもありません。もっとも、そこまで熱く語ってみせるほどそれら差別語の存在が原因となった封印作品を観たいとも思わないので、どちらでもいいのですが。
その手の“安易な”封印作品は無視するとして、ではどのような作品に興味が惹かれるのかといいますと、一言で言うなら、全体にドス黒い悪意が込められているかのような作品です。例えば、こちらは非常に有名な欠番作品になりますが、『怪奇大作戦』の第24話「狂鬼人間」のように、精神異常者(つまり狂人)に対するあからさまに差別的な台詞が出てくる陰惨極まりない作品だとか、あるいは、『ノストラダムスの大予言』のように、観客を小バカにしているとしか思えないオチと、人体的欠陥のある人間を虫けら同然に扱うような非=道徳的感性が画面を覆っているような作品です。
あるいは、ただもう理由も無く残酷な画面の連鎖のみで成り立っている、あの『スナッフ』(本物の殺人シーンが撮られたという触れ込みで話題になったインチキ映画)の日本版『徳川女刑罰絵巻 牛裂きの刑』や、ヒーロー映画のはずがただのリンチ映画と化してしまった『ウルトラ6兄弟 vs 怪獣軍団』のような、こんな映画を観て観客が一瞬でも喜んだり感動したりすると思ってしまった制作側の、明らかな認識不足というか出鱈目さにもかなりの勢いで魅了されます。
そして、私がその上映を願って止まない作品の頂点に位置するのが、冒頭で触れた『追悼のざわめき』なのです。
『追悼のざわめき』は、監督の強い要望でヴィデオ化やテレヴィ放映がなされないという特殊な作品で、今は無き中野武蔵野ホールの動員記録を塗り替えたことでも記憶さるべき怪作なのです。松井監督のその他の作品も、同様になかなか上映されない傑作揃いのようで、そのあたりの詳細については、「ムービー・パンクス」(星雲社刊)という書籍に監督のインタビューが掲載されているので、そちらを読んでいただければと思いますが、あらすじを読んだだけで、そんな物語をいったいどのように演出し撮影しているのかと興奮してしまう映画などそうあるものではなく、増してや、それがなかなか観られないというのがこちらの欲求を無限に高めてくれるのです。
こんな放映禁止作品を観た! という方のご意見があれば、是非お寄せいただきたいものです。
2005年10月29日
ザケンナ!
つまり、“ふざけるな!”という意味ですが。
昨日、『親切なクムジャさん』を観てきました。いやぁ、今回は端的に言って、自分がバカだったのかもしれません…その情けなさが裏返って、かような怒りに変わったわけで。
この怒りは無論、作品に向けられているのではありません。『親切なクムジャさん』については別途書くと思いますが、作品として、紛れも無いパク・チャヌク作品だったといえるでしょうし、その相対的な評価はわかりませんが、私は充分楽しめたのですから。
私が憤っている理由、それは2点あります。
一つは、監督はおろか、主演のイ・ヨンエすら来なかったことです。『親切なクムジャさん』は、後二週間も待てば、東京でも普通に公開される作品です。誰よりも早く作品評を書かねばならないとか、そういう理由が無ければ、わざわざ苦労してチケットを取る必要もないし、ましてや、そのためだけにオークションで法外な値段を支払う必要もないのです。では何故そのような行動に出たのかと言えば、それはもちろん、パク・チャヌク監督とイ・ヨンエが舞台挨拶に来るという付加価値があったからです。いや、実際のところ、二人をどうしても生で見たいと思っていたわけではなく、ただこんな機会でもなければ彼らに会うことは一生ないかもしれないし、来るなら見ておいたほうがいいな、という程度でしたが、そのような付加価値にはそれなりの対価を支払わねばならないのでしょうから、止む無くオークションで購入したのです。しかし彼らは来なかった。これはひとえに、配給会社側の不手際と断じざるを得ませんが、まぁギリギリまで交渉したのでしょうし、相手も国際的なスターですから、諦めがつかないこともありません。
しかし、その事実を何とか隠蔽せんがごとき配給会社側の行動というか提案に対し、更なる怒りがこみあげてきた次第です。それにはまったく腹に据えかねるものがあり、では一体どういうものだったかというと、イ・ヨンエを正式公開までに何とか呼べるよう、その場に居合わせた観客たちに、「イ・ヨンエさん、愛してます〜」などと韓国語で叫ばせ、その模様をヴィデオに収めると言うもので、私はあまりに頭にきたのでもちろんそんな奇行には出ませんでしたが、都合3回も起立させられ、舞台上に掲げられたイ・ヨンエの写真に向かって叫ばねばならないその他大勢の観客を、恐らくは「よしよし、いいぞいいぞ」と笑いながら見ていたであろう配給会社の連中の顔が頭に浮かんできたので、いっそのこと思い切りブーイングでもしてやろうかと大人気ない思いにとらわれたりも。韓流ブームに辛うじて乗ることで、何とかあれだけの観客を集めたにもかかわらず、私はその限りではないにしても、イ・ヨンエの来日“だけ”を心待ちにしていた多くのファンに対し、彼女のブッキングに失敗したばかりか、あのような道化めいた奇行を演じさせるなんて、それを悪質なサボタージュと言わずして何と言うのか。あの時、あの場にいた全員はほとんどバカ扱いされていたのだと、私は今でもそう思っています。
幸いにして、『親切なクムジャさん』の出来自体が何とか私の怒りを静めてくれもしましたが、やはり少なくとも、あのような特別招待作品の類には、もう参加しないことにしようと決意させるに充分でした。
2005年10月28日
第18回東京国際映画祭、とりあえずの速報
回を重ねるごとに会場としてのbunkamuraの肩身が狭くなってきているようにも感じられる東京国際映画祭が今年も始まりました、というより、後2日を残すのみとなりました。現在、渋谷にあるとあるインターネットカフェにてこの記事を書いているのも、先ほどまでオーチャードホールにて、パク・チャヌクの『3人組』を鑑賞していたからで、今から1時間後には、やはりパク・チャヌクの新作『親切なクムジャさん』を同じ場所で鑑賞する予定だからです。
六本木ヒルズのレッドカーペットとやらは何度となくテレヴィに映るのに、ここ渋谷のbunkamuraはというと、祭としての華やかさなどほとんど感じられず、毎日のように通っているbunkamura通りのそのままだと言えるでしょう。
昨年『カンフー・ハッスル』を観た時には、さすがにチャウ・シンチーの舞台挨拶があったからか、オーチャードホールはほとんど満席でしたが、先ほど観た『3人組』はと言うと、あのパク・チャヌク監督の初期作品であるにもかかわらず、会場はもう見事なまでにガラガラ。もちろん、今日は平日ですから、そんな時間にその場所にいること自体がおかしいのだと言われればそれまでですが。ただし、この後上映される『親切なクムジャさん』のほうには、パク・チャヌク監督と主演のイ・ヨンエさんの舞台挨拶があるようですし、かなり混み合うのではないかと予想されます。実際、チケットは発売開始(10/8 10:00~)の時点でまったく入手できず、仕方なくオークションで競り落としたくらいなのです。これでガラガラだったら、やってられません。
というわけで、そろそろ準備して出なければなりません。
それぞれの作品表はまた後日更新いたします。
2005年10月25日
『パリところどころ』を初公開から40年後に観る喜び
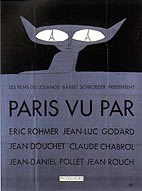 そのdvd化自体が事件といえば事件だったオムニバス『パリところどころ』。今はなきシネヴィヴァン六本木で80年代〜90年代にかけて何回かリヴァイヴァルされましたが、一度も足を運ぶことがないまま、今に至ってしまいました。そんな折、ニュープリントで公開されると聞けば、それがいくら普段積極的には行きたくない街・池袋での上映であろうともう見逃すわけにはいかず、公開から40年経ってやっと鑑賞出来た次第です。
そのdvd化自体が事件といえば事件だったオムニバス『パリところどころ』。今はなきシネヴィヴァン六本木で80年代〜90年代にかけて何回かリヴァイヴァルされましたが、一度も足を運ぶことがないまま、今に至ってしまいました。そんな折、ニュープリントで公開されると聞けば、それがいくら普段積極的には行きたくない街・池袋での上映であろうともう見逃すわけにはいかず、公開から40年経ってやっと鑑賞出来た次第です。
このように、なかなか観る事が出来なかった映画を何とか鑑賞できた時、その内容はさておき、とにかく観られたことが嬉しくなり、それだけで満足してしまいそうになるのですが、本作は冷静にみても6本のうち酷い出来だった作品は1本もなく、むしろ短編オムニバスとしては出色の出来栄えだったような気がします。少なくとも、嘗て観た『水の話/プチ・シネマ・バザール』と同等、あるいはそれ以上の見ごたえはありました。
私の中のパリという街は、実際に2度訪れ、あわせて2週間ほど滞在したにもかかわらず、思い出されるのは決まって映画の中のパリのほうで、現実に見たパリの街の記憶はかなり希薄だと言わねばなりません。実際、パリで何をしたのかといえば、毎日のようにプリングルスを食べながらワインをがぶ飲みした以外ほとんど思い出せず、観光らしきこともほとんどしないまま、ひたすらに街を彷徨していただけだったのですから。唯一覚えているのは、朝の薄ら寒い空気の陰鬱さで、私のパリは、いささかも花の都ではないのです。にもかかわらず、映画の中のパリは決まって魅力に溢れていたような気がするのはなんとも不思議な話、いや、実は当たり前の話なのかもしれません。それがスクリーンに映っている限り、私が観ていたのは実在するパリではなく、虚構としてのパリだったのですから。
そんなパリにまつわる6本の短編から成る本作で私が非常に感動したのは、ジャン・ルーシュが監督した第二話「北駅」です。私は夫婦間の、あるいは恋人同士の倦怠を描いた映画に惹かれる性向があるのですが、そんな好みを無視したところで、本作の凄さは揺るがないでしょう。出色はやはりラ・シャベル大通りにおける2人の男女の会話を捉え続けた移動撮影でしょう。そもそも3つのショットのみで成り立つ本編ですが、冒頭のアパルトマンにおける不安定な、いささか安易な言い方ではありますが、ある種ドキュメンタリー的な手持ちカメラの使用が齎す効果は絶大で、それは戸外に出ても一向に変化することなく、それ自体なんとも異様なあの長い横移動撮影は、しかし、作品の形式と内容の自然な融合にも感じられ、だからこそ、ラストのロングショットから受ける疎外感は尋常ではなく、ほとんど呆気にとられるうちに作品が終了してしまったのです。映画を観た後の余韻、などとよく言われますが、そんな余韻すら感じさせないうちにもう次の一篇が始まってしまうのですから、この『パリところどころ』という作品は、何とも過酷な映画だな、と思います。
以下、各篇で印象的だった箇所を思いつくままに列挙します。
第一話 ジャン=ダニエル・ポレ監督「サンドニ街」
現実以上に(!)“娼婦”を感じさせる女のふてぶてしさ。気弱で奥手な男と娼婦が共に食すスパゲッティの伸び具合がいい。
第三話 ジャン・ドゥーシェ監督「サンジェルマン・デ・プレ」
メキシコに旅立ったはずの軽薄な男が、実はメキシコになど行かず、美術学校でデッサンモデルとしていたことがバレた瞬間の表情と身振り。あの一発だけのギャグの異質さはいい。
第四話 エリック・ロメール監督「エトワール広場」
どうみても滑稽にしか映らない男同士の殴り合い。そして、エトワール広場をほとんど一周してしまう男の疾走感。細かい描写からちょっとしたサスペンスと生み出しているところ。
第五話 ジャン=リュック・ゴダール監督「モンパルナスとルヴァロワ」
ジョアンナ・シムカスのボブヘア。彼女が壁に寄りかかる様は『女と男のいる舗道』を想起させる。2人の男が彼女を罵る言葉が素晴らしい。カリーナ時代の終焉とリンクする。
第六話 クロード・シャブロル監督「ラ=ミュエット」
崩壊しつつあるブルジョア家庭の主婦が階段から転げ落ちるシーンの図式性。『気狂いピエロ』におけるカリーナの死のような出鱈目な描写に感動。
『パリところどころ』は、バルベ・シュレデールとピエール・コトレルの二人が設立したレ・フィルム・デュ・ロザンジュの記念すべき第一作目です。彼ら2人の映画史的重要性を本作を機に辿ってみることにもそれなりの価値があるのではないでしょうか。
2005年10月20日
『真夜中のピアニスト』、弱さゆえの肯定
 ジャック・オディアール監督は、前作『リード・マイ・リップス』がそうであったように、本作でも特定のジャンルを回避しているかのようです。たとえ本作の邦題に“真夜中”という言葉が使われていても、本作は単純にノワール調のサスペンスとはならず、だけれども“ピアニスト”という言葉が連想させる音楽的要素が物語を引っ張っているとも言い切れません。
ジャック・オディアール監督は、前作『リード・マイ・リップス』がそうであったように、本作でも特定のジャンルを回避しているかのようです。たとえ本作の邦題に“真夜中”という言葉が使われていても、本作は単純にノワール調のサスペンスとはならず、だけれども“ピアニスト”という言葉が連想させる音楽的要素が物語を引っ張っているとも言い切れません。
この邦題に関して言えば、どうしても“わかりやすさ”が先行してしまっている感が否めず、何とかジャンルへの接近を試みようとしているかのよう。個人的にはむしろ、原題『De Battre Mon Coeur S'est Arrete』を邦訳(とあるサイトによれば、「僕の鼓動は止まった」という意味)したほうがの方がより詩的な感じで作品の雰囲気に合っているような気がしないでもないのですが…
それはともかくとして、『真夜中のピアニスト』について若干の考察を。
本作は、奔放で横暴な父と、ピアニストだった亡き母との間で育ってきたある青年が、引き裂かれる寸前のアイデンティティに苦悩しながら自己の変革を成し遂げようもがく、そのように要約出来ると思いますが、この何かと何かに“引き裂かれながらもがく”という主題がとにかく様々な場面で目につくので、主題はその部分にあるのではないかと思いました
父を受け継いだ形で犯罪すれすれの不動産ブローカーになったトム(ロマン・デュリス)は、いわば“夜の世界”に生きる男で、それは彼の“精神的な弱さ”に原因を求めることが出来るような気がします。たった一人の肉親である父に対する愛情はありますが、その裏返しの感情もある。また、生きていくためとはいえ、非人道的ともいえるの仕事にもうんざりしている。だけれども、父も仕事も放り出してしまうことが出来ない。それはある一面においては彼の優しさだともいえるかもしれませんが、やはり弱さに端を発しているのです。そして、そのような閉塞状況における唯一の救い、それが“ピアノを習うこと”なのです。
『リード・マイ・リップス』との共通点は、この弱い男に対し、(精神的に)自立した女が配されている点に認められます。トムが密かに抱く夢はコンサートピアニストになるという途方も無いもので、同時にそれは、夜の世界から昼の世界に移り住むことに他なりませんが、これを不器用ながらも手助けする存在、それがある中国から来た留学生です。彼女は中国語しか話せず、トムはフランス語しか話せない。ここでは確かにディスコミュニケーションが成立していますが、それが次第に緩和されていく様が、実に丁寧に描かれています。留学生の女性が話す中国語に、字幕は出ません。よって、我々観客も、トムと同じ境遇に立たされることになります。ピアノのレッスンの後、2人は必ずお茶を飲むのですが、このシーンが重要なのは、互いに母国語をレッスンしあいながらコミュニケーションが少しずつ生成されていくからというより、彼らを結びつける唯一の媒体であるピアノに頼らず、2人の間に確実に存在している大きな差異に耐えながらも尚、その差を埋めていこうとする意思が一連のシーンに不思議な魅力を与えているからだと思います。
この留学生の部屋は、窓の傍にピアノが配置されています。ピアノをレッスンするのは午後の昼下がりですから、シーンには必ず日の光が差し込んでいます。室内でも照明の明かりは感じられず、恐らくは自然光で撮られたこの部屋の光景は、若干薄暗い中に差し込む光が、トムの意識の変容を表しているかのようで、その空間設計にはなかなか唸らされました。真夜中にほとんど明かりをつけずに自宅でピアノを弾くシーンとのコントラストがより鮮明に浮かび上がるこのピアノのレッスンシーンが、自己変革の過程として描かれていくのです。
しかしながら、その変革は容易には実現しないでしょう。事実、トムは、2年後に訪れる大きなチャンスを、自ら不意にしてしまうからです。父に対する、というより、自らの人生に対する最終的な決着は宙吊りにされたまま、それまで望んでいたであろう自己変革は志半ばで潰えてしまいます。それは果たして不幸なのか、それとも……
ところで、『真夜中のピアニスト』は1978年のアメリカ映画『マッド・フィンガーズ』(ジェームズ・トバック監督)のリメイクです。私は未見ですが、あらすじを読むと、その結末が大きく異なっているようです。それはまさしく、主人公の人生への折り合いのつけ方の違いとして描かれるのですが、『マッド・フィンガーズ』のほうがほとんど絶望的な結末だったのに比すると、『真夜中のピアニスト』の結末は、遂に変われなかった自己を肯定したという意味で、間逆の結論を導き出しているのです。ここは非常に興味深いところだと思います。
ピアニストになる夢は叶わず、父への愛憎に対する決着もつけられなかったトムは、しかし、ラストシーンにおいて、嘗ては留学生で現在はピアニストへと成長した中国人がコンサートでピアノを演奏する様を観るのですが、そのトムの目に、少なくとも絶望は感じられません。諦念ではなく、寛容の視線がそこには描かれているのです。もちろん、これを手放しでハッピーエンディングだとは言いがたいし、観る者に委ねられているとも思うのですが、少なくとも私には納得できるエンディングでした。
とにかく人物のキャラクター造形が丁寧で、俳優の演出に長けているジャック・オディアール監督ですが、とりわけ、登場シーンはそれほど多くないですが、父の恋人役のエマニュエル・ドゥヴォスは実に魅力的で、40歳を超える彼女の容姿は決して好みではないものの、“フランス的”としか形容しようの無いエロティシズムを漂わせています。
エロティシズムといえば、本作でロマン・デュリスは妙にもてる役柄ですが、彼と女性とのやり取りにも注目していただければ、本作をより楽しめるのではないでしょうか。
2005年10月17日
ヴェンダース5本
先週末は何となく劇場に行くことも無く、それは本当に“何となく”で、雨が降っていたからとか、体調が芳しくなかったからとか、観たい作品が無かったからとかいう積極的な理由があったわけではありません。実はもうすぐ移転してしまうユーロスペースに『空中庭園』を、とも思って行きかけたのですが、時間的に若干中途半端で、直近の回に行くにはギリギリ、次の回まで待つのも消耗といえば消耗だな、と思った次第。とにかくユーロスペースにギリギリで駆け込んであまりいい思いをしたことがなく、それだけは避けたかったということです。
で、こんな時こそヴェンダースをまとめて観るチャンスだ、とばかりにTSUTAYAに行き、80年代以降の作品を中心に5本をレンタル。今週は平日飲みに行かず、この5作品を土曜日までに絶対に観ることを決意。内訳は下記の通り。
『まわり道』(1974)
『ハメット』(1982)
『ベルリン天使の詩』(1987)
『夢の涯てまでも』(1991)
『時の翼にのって/ファラウェイ・ソー・クロース!』(1993)
昨日は『まわり道』のみを鑑賞しましたが、これは嘗て観たような気がしていたのに、実は観ていなかった作品で、ここにも一瞬だけリサ・クロイツァーが出ていました。70年代のヴェンダースが彼女を好んで起用していたことをあらためて確認。それどころか、『ラ・パロマ』のピーター・カーンが出演していて、ここでもダニエル・シュミットとの繋がりを発見。彼が詩を朗読する場面の疎外感は本作を覆うそれに等しく、物語は疎外と孤独と迂回を主題に、何ら結論めいたものを出そうとしません。が、やはり本作にもコカコーラが何度も登場していて、“アメリカ”への遥かな視線を感じたりも。なかなか見ごたえのある作品でした。
その他の作品については、先日の「ヴェンダース・ナイト」を受けてのセレクトですが、とりわけ『ハメット』以降のヴェンダースとアメリカとの関係をこれらの作品から考えてみたかったというわけです。すでに2本の新作の公開が予定されているので、それらを観る前に未見だったヴェンダースを全て制覇出来ればと思っております。
さて、とうとうゴダールの新作『アワー・ミュージック』が公開されたようですが、評判はどのような感じでしょうか。これからネットを徘徊してみようかと思いますが、観られた方、感想など聞かせていただければ幸いです。私も今週末くらいにいければと思います。
というわけで、「必見備忘録10月編」も若干修正しておきます。
2005年10月13日
『不安』、非=ネオレアリズモな怪作
すでに50年以上前に撮られた本作ではありますが、今尚人間の情動が生々しく目の前に迫ってくるようです。浮気を隠そうとする妻(イングリッド・バーグマン)が次第に追い詰められヒステリックになる様の、すぐそばにいるかのように具体的なイメージ。
パリで公開された当時、場末の小劇場でしか公開されなかったと、どこかでゴダールが書いていましたが、本作はロッセリーニのフィルモグラフィの中で、どうやら失敗作扱いされているようなのです。イングリッド・バーグマンとの訣別と結びつければ、本作に漂うノワール調の雰囲気(印象的な影の効果)にも容易に納得してしまいそうになるのですが、その辺りの事情についてはこの際無視したいと思います。
浮気をネタに強請りをはたらく情夫の元恋人とイングリッド・バーグマンが、夜のキャバレーで落ち合う場面。このとき、二人は共にカメラを正面から見据え、互いの主張をし合う。この切り返しは、私が知っているネオレアリズモのイメージからは程遠く、ほとんど不気味とも言える程強烈な印象を齎します。その後にある重大な秘密が暴露されることになりますが、その前兆に相応しい、途轍もない緊張感を生みだすことに成功していると思いました。人物を真正面から撮ること。そのことの不自然さが、ここでは重要なのです。
物語の終焉がいささか予定調和的だな、と思って調べてみると、どうやら現在発売されているヴァージョンは、「Non credo piu' all'amore (La paura)」というタイトルで77年に公開されたもので、配給業者によってバーグマンの説明的なオフの声が追加され、自殺未遂のシークェンスを削除してハッピー・エンドに変えられた短縮・修正版らしいのです。だとすれば、オリジナルのヴァージョンは、もしかするとより陰鬱とした終焉だったのかもしれません。その真相を知るには、今のところ、オリジナル版が公開されるのを待つしかないようです。ただし、本作はこのままでも一見の価値があるという事実に変わりはありません。
『ランド・オブ・ザ・デッド』、これはこれでいいのだと思わせる映画
アメリカ映画のある部分の神話を築き上げながら、そのジャンルの新作を監督するのに20年もの時間を要さねばならなかったジョージ・A・ロメロは不幸だとも言えます。そんな不幸を背負いつつも尚、ハリウッドシステムに上手く折り合いをつけようとはしなかったロメロが、今回ユニヴァーサルの制作で監督し、さらにこのようにいかにも簡潔で贅沢なアメリカ映画をふと差し出すのであれば、特にゾンビ映画のファンではない私でも、やはり喜ぶべき事態として劇場に足を運ばねばならないと思いました。
空間は平面に限定され、人間もゾンビも、等しく“敵”となりえるような絶望的な状況と、それを高みから見下ろすデニス・ホッパーという図式が、現在のアメリカに等しいのかどうかはこの際問わずにおきます。いくらゾンビが知識を身につけはじめようとも、侵略意識が芽生えようとも、彼等が人間を喰らう仕草と描写を、私は観たいのであり、実際、ロメロは見せてくれました。それは間違いなく一つの価値として、私に届きました。
全体としてやや食い足りない感もあったにせよ、アメリカ映画のしかるべき描写をそのまま反復しようとするロメロのいい意味での図々しさ(ロバート・ジョイのあの仕草!)、イタリア映画史における過剰な存在であるダリオ・アルジェントとの、もはや過去となったパートナーシップが、アーシア・アルジェントの起用という形で変奏されていること、あるいは、“あの『イージー・ライダー』の”という冠を年月と共に消滅させているかのように、あらゆる映画に出鱈目なほど出演している感じがしないでもないデニス・ホッパーが、自らの牙城をゾンビ達の侵略されることによってどんどんうろたえていきながらも、部下を平然と撃ち殺す瞬間だけは誰よりも冷酷な表情をしたこと等々、感動的なシーンも決して少なくはないのです。
ラストを鑑みると、きっとまた続編も作られるのでしょう。
恐らく私は、他の監督の手による続編は観ないと思います。いつかロメロが監督するときには必ず駆けつけると思いますが、それまでにまた長い沈黙が訪れなければいいと思っています。
『トゥルーへの手紙』、“ホームムービー”のメッセージなるもの
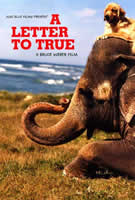 俗に言う“ホームムービー”(あるいは“ホームビデオ”でもかまいませんが)と一般的に公開されている映画との差異はどこにあるのでしょうか。しばしば“ホームムービー”が観るに耐えないのは、それを撮っている人間(及び、その周辺)が観るということが大前提となっていること、つまり、ごく限られた人間が楽しむために撮られているからだと思います。それが物語を伴ったフィクションという形式を取ろうと、日常を切り取ったドキュメンタリーという形式を取ろうと、“ホームムービー”とはある閉じられた空間においてのみ“映画”足りえてしまうという、何とも特殊なものではないでしょうか。
俗に言う“ホームムービー”(あるいは“ホームビデオ”でもかまいませんが)と一般的に公開されている映画との差異はどこにあるのでしょうか。しばしば“ホームムービー”が観るに耐えないのは、それを撮っている人間(及び、その周辺)が観るということが大前提となっていること、つまり、ごく限られた人間が楽しむために撮られているからだと思います。それが物語を伴ったフィクションという形式を取ろうと、日常を切り取ったドキュメンタリーという形式を取ろうと、“ホームムービー”とはある閉じられた空間においてのみ“映画”足りえてしまうという、何とも特殊なものではないでしょうか。
ブルース・ウェバーが9.11を受けて撮ったドキュメンタリー『トゥルーへの手紙』は、非常に個人的な思いから出発しているようです。その出発点とは、愛犬・トゥルーに宛てた手紙を書こうと思い立った時に等しいのですが、その意味で極めて個人的な“ホームムービー”である本作は、しかし、観ている間早く時間が過ぎてゆくことだけを願うような、凡百の“ホームムービー”とはその質を異にしています。それはどのような点においてか。
最大の相違点は、ブルース・ウェバーがカメラマンであるという事実に存しているでしょう。先ず持ってその技術が違う。もちろん、機材も違う。または、そのキャストとして連なることになる人脈が違う。当然のことながら、彼はただの犬好きではないのであり、夕暮れ時の海辺で犬たちがはしゃぐ様を捉えたフィックスのスローモーションの美しさは、“ホームムービー”のように、誰にでも撮れてしまうものではないのです。
そしてもう一つの相違点は、この映画に託されたメッセージ性の存在です。個人的な出発点を持つ本作は、自分自身やその周辺のみに向けてではなく、恐らく“世界”に向けて作られているということだと思います。
ブルース・ウェバーが作品として世に残したかったものは、トゥルー他、ウェバー家のゴールデン・レトリバー達の愛らしい姿ではなく、その犬達にこめられた世界への、愛と平和へのメッセージであると、一先ずは言えるのかもしれません。しかし、そのような紋切り型を、ここでは自粛したいと思います。実際、78分の上映時間中それなりの部分を占める過去の映画の引用や、ラスト近くのマーティン・ルーサー・キングJr.の演説など、その平和への思いとやらが非常に散文的に配置されているためか、ある直線的なメッセージとしてブルース・ウェバーの思いが私に伝わることなど無かったからです。もちろん、私は映画から何らかのメッセージを読み取ろうとして日々映画を観ているわけではないのですから、それは当然だとも思うのですが。
しかし、『トゥルーへの手紙』を、あるメッセージの伝達をその存在意義にしている作品と断じてしまうのは、偏見に過ぎないのかもしれません。本作には、端的に美しいといえるシーンが存在するし、ブルース・ウェバー自身の、自然体で放浪者的な生き方にある共感や発見を見い出す可能性もないとは言えないのです。
私の場合、本作を観た“だけ”で、世界の平和について考えてみることなどいささかもありませんでしたが、その世界を繋ぐ海の、あの圧倒的な存在感と美しさ、そして、その海をサーフボードに乗って滑っていくトゥルーの、混迷する世界など微塵も感じさせないようなあっけらかんとした表情のほうが、よほど印象的でした。
2005年10月11日
『男の敵』、あるいはフォードを如何に見ればよいか
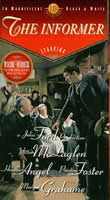 原題を『THE INFORMER』とする本作は、文字通り、ある密告者を主人公に据えた映画です。普通に考えれば『密告者』とすべき邦題を、何故『男の敵』としたのか、その経緯についてはわかりません。そもそもここでいう“男”とは、いったい誰を指しているのか。いずれにせよ、“密告者”であろうと“男の敵”であろうと、負の存在としてのとある人間を意味しているという点では共通していると思います。
原題を『THE INFORMER』とする本作は、文字通り、ある密告者を主人公に据えた映画です。普通に考えれば『密告者』とすべき邦題を、何故『男の敵』としたのか、その経緯についてはわかりません。そもそもここでいう“男”とは、いったい誰を指しているのか。いずれにせよ、“密告者”であろうと“男の敵”であろうと、負の存在としてのとある人間を意味しているという点では共通していると思います。
実はこの映画、嘗て一部分だけをスクリーンで鑑賞したことがありました。昨年アテネフランセで行われた映画狂人による公演に行った際、冒頭のとあるシークエンスを観る事が出来たのです。そのシークエンスは、主人公ジッポーを演じるヴィクター・マクラグレンが、恋人役のヘザー・エンジェルが別の男(といっても、彼女は娼婦なので単なる客に過ぎないのですが)に言い寄られているのを見つけ、まず加えていたタバコを肩越しに放り投げ、次いでその男の腰の辺りをむんずと抱きかかえ放り投げてしまうという、ちょっと笑ってしまうようなシークエンスなのですが、映画狂人先生がこのシーンをわざわざ見せたのは、フォードにあって最もフォード的な身振りが“何かを投げること”に他ならないということの証左としてであり、別に本作がフォード初のアカデミー監督賞受賞作で、それまでアクション専門の監督と見なされていた彼が、遂に芸術的評価を得ることになったきっかけとなった作品という事実とは何の関係もありません。
130本以上に及ぶジョン・フォードのフィルモグラフィーのうち、私が観ているものなどほんの1割程度で、一生かかっても全てを観ることなど出来ないでしょう。もはや東京においても、特殊な機会にしかスクリーンで観られないフォード作品ですが、さしあたり渋谷TSUTAYAにある作品だけでも全て観ようと決意し、時々思い出したように観る事にしているのです。
『男の敵』は、同じ1935年に撮られた『周遊する蒸気船』をすでに観ていた私にとって、かなり趣の違う作品でした。夜のダブリンを舞台にしたセットは霧と影が強調され、それがモノクロ画面だからという理由を超え、画面は黒で覆い尽くされているかのようです。所謂ノワール的な雰囲気の中、主人公ジッポーは恋人のために友人を警察に売り渡すのですが、警官が密告を受けその友人を見つけ出し、遂には撃ち殺す時の描写など、警官の長い影が強調され、表現主義的なアプローチも垣間見られます。
面白いのは、このジッポーという主人公がとにかくよく酒を飲むこと。彼は全ての酒を一息に飲み干し、しまいにはラッパ飲みでウォッカをあおるのですが、この酒を飲む描写は西部劇におけるフォードの演出にも繋がります。飲み干したグラスは投げつけられ、いかにもフォード的な身振りだと言えるのかもしれません。
しかし、このように酒を飲むシーンに漂うフォード的楽天性が本作の主題ではもちろんなく、本作はあくまで密告者の人間性と、その束の間の救済にフォードの視線が注がれているのだと思います。
ユダにたとえられた裏切り者ジッポーは、組織の報復を受け銃弾を浴びますが、彼が死の間際にたどり着いた教会で、彼はある老婆に出会うのです。その老婆は、ジッポーが裏切った友人の母親なのですが、まさに聖母マリアとして撮られたようなその老婆のクローズアップが、ジッポーの救済を意味していたのが印象的でした。
投げるという行為が、物語を始動させるということ。
映画狂人氏のフォード論は大変興味深く、かつ刺激的でもありますが、今後観ることになるフォード作品においては、そういった面にだけ視線を向けるのではなく、何とか独自の視点を発見できればいいと、今はそのように思っております。
とにもかくにも、ジョン・フォードはやっぱり面白い。
ヴェンダース!ヴェンダース!ヴェンダース!
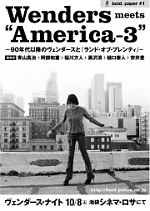 8日(土)は、boid主催「ヴェンダース・ナイト 〜もうひとつのアメリカ〜」を観に池袋シネマ・ロサへ。あまりの混雑ぶりに若干のパニック状態になり、23:00の開始予定が大幅に遅れました。私は予約していたから良かったものの、キャンセル待ちにあれほどの列が出来るオールナイト上映というものを初めて体験し、しばし呆然。ひとえに黒沢清氏のトークと、その日のみ限定配布される冊子目当てということでしょう。全体的に客層は若く、最終的には補助席が出る程超満員でした。ng氏と一番後ろを陣取っていると、開始直前くらいにこヴィ氏の姿も。ちょうど私の隣が一席空いたままで、結局、31歳の男3人が仲良く並んでヴェンダース体験という、まぁこれも人生初体験でした。
8日(土)は、boid主催「ヴェンダース・ナイト 〜もうひとつのアメリカ〜」を観に池袋シネマ・ロサへ。あまりの混雑ぶりに若干のパニック状態になり、23:00の開始予定が大幅に遅れました。私は予約していたから良かったものの、キャンセル待ちにあれほどの列が出来るオールナイト上映というものを初めて体験し、しばし呆然。ひとえに黒沢清氏のトークと、その日のみ限定配布される冊子目当てということでしょう。全体的に客層は若く、最終的には補助席が出る程超満員でした。ng氏と一番後ろを陣取っていると、開始直前くらいにこヴィ氏の姿も。ちょうど私の隣が一席空いたままで、結局、31歳の男3人が仲良く並んでヴェンダース体験という、まぁこれも人生初体験でした。
上映された作品は『ミリオンダラー・ホテル』『アメリカの友人』『都会のアリス』の3作品。実はその日中に借りてきたdvd4本を観てしまわねばならず、その所為で昼寝も出来なかったので、オールナイト最後の作品である『都会のアリス』を観る頃には、ちょうど車中の緩やかな振動が眠気を誘うように、あの緩慢で心地よい移動に次ぐ移動が確実に私を睡眠へと誘うだろうと半ば覚悟を決めていました。
初見だったのは黒沢清氏と同じように、『ミリオンダラー・ホテル』のみでした。
彼がそうだったように、私もこの作品は“気が付いたら終っていた”のであり、ヴィデオが発売された後も、個人的に好みではないミラ・ジョヴォビッチが写ったパッケージ写真を見ると、手にとるのを躊躇ってしまっていたのです。ng氏は観ていることすら忘れていたし、こヴィ氏は封切りで観て以来どうしても許せない作品だったと言うので、期待と不安がちょうど半々の状態で臨みました。
黒沢清氏が指摘していたように、本作はヴェンダースらしからぬカメラの動きが散見され、冒頭のスローモーションに始まり、(boid主宰・樋口氏によれば)“ゴダール的”スローモーション、半ばコメディ的な早回し、そしてラスト近くの360度ターンなどなど、なるほど、これは確かにヴェンダースにおいて何かが吹っ切れたような感じがしないでもなく、それが嬉々としてかやけっぱちにかどうかは知りませんが、様々なチャレンジをしているような気がしました。
私は恥ずかしながら、『夢の果てまでも』や『リスボン物語』、そして『エンド・オブ・バイオレンス』など、90年代以降のヴェンダースをほとんど観ておらず、よって、本作に込められた“意図”を未だ吟味しえずにいるのですが、そもそもシネマスコープが好きなこともあり、本作は思った以上に楽しめました。これは90年代以降の諸作品を観た上で再度検討してみたいとも思うのですが、とりわけ、空撮と縦移動(パンアップ・パンダウン等)にヴェンダースの新しい視点(それがよく言われているような「ヴェンダースのアメリカ」に繋がるかどうかも含め)を発見できるのではないか、などという考えが浮かびました。
『アメリカの友人』は言うまでもなく傑作、すでに5回は観ていましたが、劇場では初めてでした。これほど俳優としての映画監督が出演している映画もまたなかろうと思うのですが、その人選がまた途方も無いといえば途方も無く、ヴェンダースにとっては師と言ってもいいだろうニコラス・レイを始め、やはり呪われた映画作家であるサミュエル・フラー、「73年の世代」における同士ダニエル・シュミット、こちらもポスト・ヌーヴェルヴァーグの同士とあえて位置付けたい欲望に駆られるジャン・ユスターシュなど、いずれも所謂“正統な”映画史に亀裂を入れるような映画作家ばかりが召喚され、彼らがまさに彼らとしての異様な存在感を画面に定着させている様がただそれだけで観るものを撃つこの作品は、やはり映画作家“でも”あるデニス・ホッパーのウエスタンハットや、ジュークボックスに見られる「アメリカ」の存在と相まって、まさにヴェンダースにしか撮れない特異なアメリカ映画として生れ落ちたのだと思います。
『都会のアリス』に関しては、途中、予想通り睡魔に襲われ意識を完全に失ってしまったものの、やはり劇場では初体験であり、2回ほど観てはいましたが、リサ・クロイツァーが『アメリカの友人』のブルーノ・ガンツの妻だったことをあらためて発見したり、ラストの空撮は『ミリオンダラー・ホテル』へとリンクしているんじゃないかなどと妄想してみたり、フォードへの言及(モーテルのテレヴィと新聞記事)の直接性がヌーヴェル・ヴァーグのそれだと一人浮かれてみたりして、半分くらいは寝てしまったかもしれない本作ではありますが、それも含め、充実した映画体験でした。
11月にアテネフランセで開催される「ドイツ映画史縦断1919-1980」でデビュー作『都市の夏』が公開されるようですが、平日なので行けそうにありません。ひとまず今週から来週にかけ、ヴィデオで観られるヴェンダース作品を全て網羅したいなと思っております。
ng氏、こヴィ氏、お疲れ様でした。
2005年10月05日
『シン・シティ』を前に、語ることを自粛したい理由
 まず断っておかなければなりません。下記は、『シン・シティ』のレビューとは程遠く、よって、鑑賞の参考にはなり難い文章です。予めご了承いただければと思います。
まず断っておかなければなりません。下記は、『シン・シティ』のレビューとは程遠く、よって、鑑賞の参考にはなり難い文章です。予めご了承いただければと思います。
ロバート・ロドリゲスが10年来映画化を熱望していたという本作は、それが限りなく“アニメーション”に酷似しているという意味で、限りなく“映画から遠い何ものか”へと変貌したかのようです。『シン・シティ』を観終えた私の脳裏には、およそ映画を観終えた時の感情とは別種の、何とも表現しがたい思いがよぎりました。だけれども実際、そんな私の思いとは無関係に、『シン・シティ』は紛れも無い“映画”として、堂々と公開されています。それもそのはずです。ロバート・ロドリゲスは『エル・マリアッチ』以来、一貫して“映画監督”であったし、それは本作の撮影にあたり、彼が全米監督協会を脱退したところで、いささかも揺るぎはしない事実です。たとえ本作において、原作者のフランク・ミラーが共同監督として名を連ねたからといって、ロバート・ロドリゲスが“映画監督”でなくなりはしません。にもかかわらず、『シン・シティ』を映画だと断言することに若干の躊躇が要されるのは、いったい何故でしょうか。
この問題は、『シン・シティ』が面白いとかつまらないとか、そういった問題とは無縁です。それでも実際はどうだったのかと尋ねられれば、結果的にそれなりに楽しむことが出来たと答えるでしょう。事実、展開やスピード感、バイオレンス(殺人描写)、ユーモア、キャスティングの妙など、総じてロバート・ロドリゲス的だったとしたり顔で言ってしまうことだってそれほど困難ではありません。そればかりか、例えば『パラサイト』あたりと比べれば、こちらのほうが断然面白かったと断言することに対して、何の躊躇もないとさえ言えます。ですからここで問題にしていることは、本作の出来とはあくまで無関係なのです。
ところで、嘗て、これに似た思いを味わったことがあります。曽利文彦監督の『ピンポン』という映画を観た時です。たまたま原作を読んでいた私は、卓球シーンのカット割りがそのままCGで表現されている様を観て、やはり同じような思いに囚われました。これは映画だろうか、アニメーションだろうか、と。もちろん、フィルムで撮られ、映写機から放射された光がスクリーンに何らかの像を映し出し、しかるべき場で上映されれば、それは間違いなく映画であるはずです。しかし、映画に違いないものを目の前にしつつも、何故それを映画だと認めることにある種の困難を伴ったのか、その理由は恐らく、私の中で映画とアニメーション(とここでは一先ずそう呼びます)が厳密に区別されているからなのです。
映画とコミックは、誰がどう観ても全く異なる芸術です。一方は事物が運動し、一方は事物が運動しない、という唯物論的な意味で。しかし、映画とアニメーションとなると、一般的に後者は、それが劇場で上映されれば“映画作品”と同等に見なされています。私はその現象自体に対し何らかの意義を申し立てたいわけではありませんし、そんなことはどちらでもいいのです。問題は、私がアニメーションを映画とは思っていないということ。好き嫌いという嗜好とは何の関係も無く、どちらかと言われればアニメーションも積極的に嫌いではありませんが、それでもとにかくアニメーションはアニメーションであり映画ではない、そういう立場をとっているのです。だから何だということはなく、それが正しいことなのかどうかも関係なく、ただ現在はそのように考えている、というだけなのですが。
映画とアニメーションがどのような意味で異なるのかを詳述はしませんが、簡単に言うなら、映画とは、作家が必ずしも意図し得ないものが画面に映ってしまう可能性をに孕んだ、極めて曖昧で、同時に多様性を帯びた稀有な芸術であるということです。写真と絵という根本的な違いもさることながら、所謂アニメーションとはその点が異なると思うのです。
ちなみに誤解の無いように言い添えておくと、私は映画におけるCGやアニメーションの部分的な存在自体を肯定も否定もしていません。それらは相対的に良かったり悪かったりする、という程度で、それを積極的に顕揚しようとも貶めようとも思いません。
さらにいえば、現在、世界にはコミック的な映画は掃いて捨てるほど存在し、コミックを原作とした映画が市場を賑わせているという認識くらいは人並みに持っています。そして、それらがどれほど下らない作品でも、それが“映画”である限り、あくまで映画作品として接するようにはしているつもりです。
だけれども、『シン・シティ』のように徹底してコミックに忠実たろうとする作品に接した時、ある違和感を隠しきれずにいるのもまた事実なのです。『シン・シティ』の映像表現がどれほど斬新で、映画史を揺るがすほど革新的な手法で撮られたものだったとしても、やはり、私にとっては素直に肯くことなど出来ないでしょう。だけれども本作を完全に“映画ではない!”と言い切れないのは、登場人物がCGで再現された原作どおりのキャラクターではなく、(一応)生身の人間が演じているからです。原作者兼監督であるフランク・ミラーの前に、俳優たちはCG合成用のブルーバックしかないスタジオで、ひたすら原作に同化しようと努めたことでしょう。事実上脚本など無く、原作コミックが脚本だったと、ロバート・ロドリゲスがインタビューに答えるのをどこかで読みましたが、しかし、この発言は図らずもこの映画の限界を表してはいないだろうか、私はそんな風に思いました。
『シン・シティ』は決してつまらない映画ではありません。むしろ、ハリウッド的大衆性をあからさまに無視したモノクロ・パートカラーのざらついた画面やノワール的なボイスオーヴァーの存在、あるいは、豪華なキャストを多数起用した割りには低予算で仕上げてしまった監督のしたたかさ等、好感が持てる部分もある映画です。しかし、先に長々と書いたいくつかの理由により、他の映画作品と同じレヴェルで本作を語ることなど出来ないのです。そして今後も、当サイトでアニメーション(及びそれに準ずると判断された作品)を取り上げることはなかろうと、今はそのように決意しております。
2005年10月03日
必見備忘録 10月編
今月は久方ぶりのオールナイトがあります。
先月『輝ける青春』で慣らしたので、多分寝ずにいられると思うのですが…
■『アワーミュージック』[上映中]
(シャンテ・シネ 11:05/12:50/14:50/16:55/18:55〜20:30)
■『ドミノ』[10/22〜]
(渋東シネタワー)
■『ハックル』[10/22〜]
(シアター・イメージフォーラム 11:00/13:00/15:00/17:00/19:00〜20:30)
■「パリところどころ(ニュープリント版)」[10/8〜]
(池袋シネマ・ロサ 21:00〜)
■『ブコウスキー オールドパンク』[10/8〜]
(シネ・アミューズ イースト/ウエスト 21:20〜23:15)
■『空中庭園』[10/8〜]
(ユーロスペース 11:00/12:00/13:20/14:20/15:40/16:40/18:00/19:00〜21:05)
■『サヨナラCOLOR』[上映中]
(ユーロスペース 10.8(土)〜 20:30〜22:40)
■「東京国際映画祭2005」[2005年10月22日(土)〜10月30日(日)]
『ハッカビーズ』は先月見逃したので。恵比寿はどうも足が遠のいていけません。
『パリところどころ(ニュープリント版)』の上映はほとんど事件というべきものです。必見。
「ヴェンダース・ナイト 〜もうひとつのアメリカ〜」はすでに予約済み。当サイトをご覧になっている方も、恐らく5人は行くのではないでしょうか?
「ATG 挑発のフィルモグラフィ」は、本来であれば14日の吉田喜重作品に行きたかったのですが、所用があるので、行かれたら16日の大島渚2作品へ。共にフィルムでは初体験です。
『トゥルーへの手紙』は、海の映像が美しかったから。
『ブコウスキー オールドパンク』は、R-18指定の如何わしさに惹かれて。
『空中庭園』は、ソニンのエロティシズムを目撃したいがため。予告編で観た血の雨はどのようなタイミングで降るのか。
『真夜中のピアニスト』には期待しています。ジャック・オディアールですから。
『サヨナラCOLOR』は、このところすこぶるいい評判ばかりを耳にするので。
今月は東京国際映画祭2005が開幕します。
すでに観る作品は決めてあるので、後はチケットが取れるかどうか……
ちなみに、昨年もう二度と行かないと決めたので、「東京ファンタスティック映画祭」は見送ります。
夏はまだそこにあるようで…
 そろそろ涼しくなってきたな、と思いきや、とても長袖など着ていられないような天候になったり、まだまだ秋とは言えない気がしている今日この頃、私は無類の暑がりですから、未だ自宅の冷房を切らすことなく、文字通り“お寒い状況”が続いており、あまりに冷房をつけっぱなしにしているせいか、あるいは設定温度が度を越して低いせいかはわかりませんが、ここ2日ほど冷房の下の方から大量の水が噴出してきて、困り果てております。
そろそろ涼しくなってきたな、と思いきや、とても長袖など着ていられないような天候になったり、まだまだ秋とは言えない気がしている今日この頃、私は無類の暑がりですから、未だ自宅の冷房を切らすことなく、文字通り“お寒い状況”が続いており、あまりに冷房をつけっぱなしにしているせいか、あるいは設定温度が度を越して低いせいかはわかりませんが、ここ2日ほど冷房の下の方から大量の水が噴出してきて、困り果てております。
こういった場合、大体は掃除していないことが原因みたいですが、フィルターの掃除は1週間まえにしたばかりだし、昨年も同じように使用していたはずなので、つまり故障ということなのかもしれません。もうすぐ暖房の季節になるので、ちゃんと暖かい風が出てくるようであれば、一先ず来年まではこのような水浸し状況に陥る心配も無かろうと思われるため、修理は見送ろうかと考えています。まったく、自身のあまりの季節感のなさに辟易しつつも、暑いものは暑いので、そのように生まれたことを呪うしかありません。
しかしながら、今年はそれまで大嫌いだった夏が、一変して大好きな季節に変化したことで記憶される年で、生まれてから今年の夏ほど海に行った夏はなく、その夏が少しずつ遠のいていくのを見るにつけ、一抹の寂しさを募らせたりするくらいです。そんなこともあり、まだ秋とはいえない強い日差しの日であれば、海に行ったっていいじゃないかということで、先週末は七里ヶ浜のほうまで足を延ばしてきました。以前より一度行ってみたかったイタリアンが目的地です。
昼過ぎに到着したらすでに満席で、数人が外で待っていました。私は本来性急な人間なので、映画以外で何かを待つことに耐えられないほうですが、なるほど、このロケーションであればしかたないな、と思わせるような、まったく素晴らしいというほかないロケーションにそのイタリアンはあって、「アマルフィイ」という店名も強ち大げさではないなと激しく納得した次第。ほとんど断崖に建っているこの建物は、嘗て訪れたカプリ島のレストランを髣髴とさせ、東京から一時間強でこのような場所に来られること事態にあらためて驚き、その驚きとともに、運ばれてきたピッツァやらリゾットやらパスタやらをどんどん平らげ、気が付けばワインのボトルも軽く空けてしまった、と。
強い日差しに照り付けられながら昼間から飲むワインというのは、まさに夏の特権だと思うのですが、すでに終った夏がまだそこにあるかのような錯覚は、ワインに酔っていたからというだけではとても説明できないものであり、とにかく行ってみればわかると、今はそのようにしか言えません。今年の夏はこれで完全に終るのでしょうが、最後の最後でなかなかいい体験が出来たなと、満足しています。
さてさて、映画のほうはさしあたり『シン・シティ』のみ。
TSUTAYAからメールが来ていたので、また半額セールだと思い込み、よく読まずに5本のヴィデオを持ってレジに行ったところ、ただポイントが5倍になるだけで通常料金のままだったという、いつもながらの体たらく。それでもやっぱりそのままレンタルしましたが。作品は下記の通りです。
『SWEET SIXTEEN』(ケン・ローチ)
『アイス・ストーム』(アン・リー)
『復讐は俺に任せろ』(フリッツ・ラング)
『ベルトルッチの殺し』(ベルナルド・ベルトルッチ)
『男の敵』(ジョン・フォード)
『アイス・ストーム』は朋友・こヴィ氏のリコメンドと今年のベネツィアつながりで。それ以外はその場のノリで決めました。レビューは随時。
昨日書き上げた『ミリオンダラー・ベイビー』のレビュー、いざ書き上げてみるといささかも短くはなく、これじゃあ何も変わっていないじゃないかと、誰が思うよりも先に私自身が思ってしまったのですが、この作品についてはまぁ特例と思っていただければ。予告していた通り、今後は頻度をあげることを第一目標にいたします。
『ミリオンダラー・ベイビー』、闇そして光
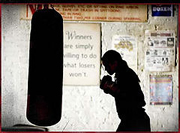
前作『ミスティック・リバー』に続き、クリント・イーストウッドが新たに撮りあげたこの作品を前に、私はまたもや言葉を失いました。もちろんそれは、“尊厳”が中心に据えられた物語自体の厳しさに対して、という部分もありますが、それよりもむしろ、主要なシークエンスにおける画面上の黒く、そして深い“闇”の存在が、私を言葉ごと飲み込んでいったからだとまずは言えます。
撮影監督であるトム・スターンの画面設計は、前作にも増して、闇と、そして光の存在を重視していたような気がします。例えば、闇が支配する古いジムの一箇所だけを照らす小さな明かりを頼りに、一人きりで黙々と練習するヒラリー・スワンクのほうへ、一度目はモーガン・フリーマンが、そして二度目はイーストウッドがぬうっと姿を現す時を思い出してください。彼らは、闇から光のほうに一歩歩みだすことで、ヒラリー・スワンクに初めて心を開いたのです。目には見えない彼らの心情が、繊細な照明によって見事に観るものに訴えかけていました。本作はほとんどが屋内の撮影ですから、そこには何らかの照明が必要とされるのですが、にもかかわらず目に付くのは、積極的とも言える闇の存在なのです。
本作における闇は、多くのシーンで幾度も反復され、その黒さを画面に定着させます。そしてそれは、目に見える黒さとしての闇ばかりではありません。モーガン・フリーマン演じるスクラップの失明した片目、あるいは、イーストウッド演じるフランキーが抱える娘との確執や、スクラップを失明させてしまったというトラウマもまた、暗喩としての闇と捉えられるのではないでしょうか。
ところで、『ミリオンダラー・ベイビー』において注目せざるを得ないのは、スクラップによるナレーションの存在です。スクラップのナレーションを中心に置くこと。彼は、状況説明をするばかりか、作品世界の構築という役割も負っています。語り部としての彼の存在を置くことで、この救いの無い(様に見える)物語を別の角度から再構築しています。そして、抑揚を抑えながら事実を淡々と述べることで、“伝える”という作業に徹している。その証拠に、物語自体は、そのナレーションによって左右されません。まず、ナレーションを物語りに介入させないこと、それを条件に、イーストウッドは、スクラップを中心に置いたのではないか、とすら思います。
だけれども、このナレーターだけが全編を掌握するのもまた事実です。神の視線に例えられもするこのナレーターという存在ですが、本作においては、そこに微妙な“感情”が存在していいるのがわかるでしょう。スクラップの存在は、比喩的にも決して超越的な神ではなく、飽くまで元ボクサーで片目を失った生身の人間としてあるのです。
そもそも本作において、神はいかなる救いの手も差し伸べません。信心深いフランキーが毎日ミサに通ったところで、最終的な決着は、フランキー自身でつけるほかなかったのですから。よって、神の存在を否定せんがごとき終焉へと至った本作のナレーションが生身の人間のそれであったということは、必然だったのかもしれません。そして、繰り返せば、ラスト近くでフランキーが神父に自分の思いを打ち明けたあの教会でらすら、深い闇が支配しているのです。
闇の存在もさることながら、イーストウッドは本作でも視線の高低差を生かした演出を施しています。イーストウッド組とも言える美術ヘンリー・バムステッドの腕が冴えるあの古く味のあるボクシングジムにおいて、フランキーの事務所は常にリングを見下ろせる位置にあります。最初はただ怪訝な表情でマギーを見下ろすだけのイーストウッドが、とうとうマギーと同じ高さで視線を交し合い、握手をする。このシーン感動的なのは、闇から光へという平行移動の運動と、視線の上下運動が交差するまさにその瞬間に交わされるからだと思います。
客席上方にいるフランキーとスクラップがリング上で苦戦するマギーを見下ろした後に、やはりと言うべきか、リングサイドにまで降りていって断ったはずのセコンドになってしまうというシークエンスもまた、握手のシーンと同様に捉えることが出来るでしょう。
あるいは、マギーに対するある重大な決心をしたフランキーが、ほとんど真っ暗なロッカールームでスクラップと会話を交わすシーン。ベンチに腰掛けたフランキーには、顔の半分ほどしか見えないくらい闇に支配され、傍らに立つスクラップもやはり、辛うじて上半身に間接的な光が差す程度です。途方も無い決意を胸にしたフランキーを、スクラップは見下ろしています。それまでどちらかと言えば、対等な高さで視線を交し合っていた二人が、見下ろす・見上げるという関係に変化しています。しかしすでにその意思を揺るぎないものとしているフランキーは、スクラップに対しほとんど言葉を発しないまま、光のあるほうへと去っていくのです。私はこのシークエンスを観て、この演出こそがイーストウッドだと理由も無く断言したくなりました。
それにしても、マギーがタイトル戦において、唐突なフックを喰らって倒れるシーンを初めて観たときは、二重の驚きがありました。一つは、まさかこんな展開が…という驚き。もう一つは、イーストウッドらしからぬあのスローモーションに対する驚きです。
それまでいかにも無駄なく力強い簡潔さでシーンを積み重ねてきたあのイーストウッドが、まさかあのように劇的とも言えるスローモーションを使うなどとは思ってもみませんでした。しかし思い出してみると、イーストウッドはマギーのほとんど全ての試合において、ノックアウトの直後にあの忌まわしき凶器となるスツールを、何度も何度もリング上に置くショットを見せているのです。しかし、このタイトル戦でスツールをリング上に置くのは、イーストウッドではない別の人間です。だからこそ、彼が懸命にスツールに手を伸ばそうとするショットもまたスローモーションで切り返されるのですが、一見すればボクサーに一時の休息を与えるあのスツールが、ボクサーの生命を奪う凶器にも変貌するのだという残酷な思いが、あのスローモーションには込められていたのではないでしょうか。カメラの視点は倒れたマギーのものになり、リングを照らす無数の光が、真っ暗な闇に暗転したとき、マギーの人生もまた、無残にも闇に彩られることになるという意味で、忘れがたく、そして極めて重要なシーンだと思うのです。
忘れがたいと言えば、もう1シーン。
マギーの思いとは裏腹に、家族から散々な仕打ちを受けた日の夜、フランキーと二人でとあるダイナーに立ち寄るシークエンスがあります。車中、彼女は自分の父親と飼っていた犬の話をし、男と女としての、もしくは擬似的な父と娘としての二人の距離が、グッと縮まる印象的な会話の後、マギーが嘗て父と共によく訪れたというダイナーにフランキーを連れて行きます。そのシークエンスが終わるとき、店の外に据えられたカメラは、ゆっくりとズームダウンしながらダイナーの外観をじっくりと画面に収めます。あるシーンの終わりとして、その舞台となる場所を引きで撮ることでシーンを終える手法自体はとりたてて珍しくはないのですが、初めてこのショットを目にしたとき、そういった常套的手法とは異質の肌触りを感じ、やや動揺しました。このショットにはかなり重要な意味が込められているのではないか、と。わざわざダイナーの看板まで律儀に見せ、そのドアの曇りガラス越しでは中にいる二人が判別できるわけでもないのに、では何故このようなショットを撮ったのだろう、と。
『ミリオンダラー・ベイビー』は、そのダイナーのショットで幕を閉じます。より遠景の外観から、今度はゆっくりズームアップしていきながら、前述のショットとほとんど同じ構図でそのダイナーが映る。そしてダイナーの中には、確かに人影がある。しかしそれが、姿を消したフランキーかどうかはわかりません。ただ、私は先に観た、あの不可解だったショットの意味が、ごく自然に了解されたような気がしたのです。闇の中にあって、そのダイナーにはほのかな光が灯っています。フランキーの選択は善悪という概念に基づかれたものというより、光と闇のどちらかを選ばねばならない過酷なものだったのかもしれません。そしてそれがどのような形であれ、あらゆる闇には光が差し込まれる余地があるのではないでしょうか。
観るものへと委ねられたラストシーンに、あえて結論は出すべきではないでしょうが、あのダイナーの控えめな光は、どことなく優しかった、そんな気がするのです。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]



