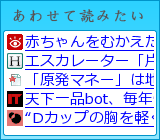2005年09月15日
『春の底』と『阿佐ヶ谷ベルボーイズ』、インディーズも侮りがたし
上映時間:23分/41分
監督:松村真吾/広末哲万
まずは『春の底』という短編に関して。
DV・モノクロで撮られた23分の本作には、脚本が存在せず、設定だけ与えられた俳優が即興で演じたのだといいます。ファーストシーンは恋人同士の口論ですが、興奮気味の彼女の演技が果たして“リアル”だったのかどうか、正直わかりませんでした。子どもを孕ませた彼が中絶代金を工面するために、ある初老の男性の息子に成りすまして手紙を書きますが、その字の下手さ加減は悪くない。誠実であろうとするわりに、やっていることがあまりに杜撰で出鱈目であるという部分が、なかなか良く描けていたと思います。
全体的に画面に落ち着きがなく、室内でかなり低い位置に据えられたカメラも、生きていたとは言いがたかったのですが、決して不愉快な作品ではありませんでした。
もう一本の『阿佐ヶ谷ベルボーイズ』は、『ある朝スウプは』に続いて廣末哲万の主演。今回は監督と編集も兼ねています。どちらかというと抑制された演技をする廣末哲万が、ある瞬間にその感情を爆発させるシーンは、前作同様感動を禁じ得ません。
近年、映画にこれほどまでの居心地の悪さを感じたこともそうありませんでした。居心地の悪さとは、その場にある空気がなかなか透明になろうとしない状態だと思いますが、そのような場を生み出すのは、並大抵ではないはず。高い演出力はそれだけで証明されるのではないでしょうか。
3つの場所での出来事が並行して描かれる本作では、その編集にも注視したいところ。物語が進んでいくに従って、それぞれの場面が異様な緊張関係を保っていく。あるシーンの切れ目と次に続くシーンには、目に見えない一瞬の“危うさ”が存在していて、それがシーンごとの緊張関係を生んでいくかのようです。
登場する誰もが、他者の感情を共有出来ない。同僚の死を前に、それぞれがそれぞれの闇を抱えながら右往左往し、それでも生きていくしかないという諦念すら感じますが、本作はそのような諦念に最後の最後で光を点す。それが同僚の女性と廣末哲万との切り替えしとして描かれる時、曰く言い難い安堵感を覚えました。
小さな作品ではありますが、その独特な存在感は長らく記憶に残るでしょう。私はこういう作品が好きなのかもしれません。
2005年09月15日 12:27 | 邦題:あ行, 邦題:は行

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]