2006年08月30日
必見備忘録 2006.9月編
いつのまに『家の鍵』やってたんだよ! もう終っちゃうじゃんかよ! ザケンナ!!
と、つい理不尽に憤りたくもなるワタクシですが、今日これから観にいく映画を含めると、8月は14本の映画を観たことになります。本来であれば今月は海三昧の予定でしたがそれもなかなか叶わず、結局は映画を観るしかなかったということでしょうか。
9月も観たい映画が沢山あるので、今月以上に頑張らねばならなそうです。
『マイアミ・バイス』(9/2〜)
(渋東シネタワー 10:00/12:55/15:50/18:45〜21:15)
本作は次回“アメリカ映画研究会”の課題作なので必須。
『弓』(9/9〜)
(ル・シネマ 10:50/12:50/14:50/16:50/ 19:00)
キム・ギドクは本当に映画を止めてしまうのでしょうか…? そうならないことを祈りつつ。
『ハードキャンディ』(上映中)
(シネマライズ 9:40/12:00/14:20/16:40/19:00)
なんだかんだでまだ観てません。そろそろ落ち着いたか?
『太陽』(上映中)
(新宿ジョイシネマ 9:20/11:30〜13:25)
やっと拡大公開されました。今度こそ。
『グエムル 漢江(ハンガン)の怪物』(9/2〜)
(新宿東亜興行チェーン 11:25/13:50/16:15/18:40〜20:50)
これが渋谷でやらないのはおかしい。どことなく傑作の予感が…
『マッチポイント』(上映中)
(恵比寿ガーデンシネマ 11:00/13:40/16:20/19:00〜21:20)
スカーレット・ヨハンソンの美しさがただごとではないことを確認するため。
『46億年の恋』(上映中)
(シネマート六本木 11:30/14:00/16:30/19:00〜20:40)
最近、まともに三池を観れていません。この劇場にも行ったことありません。
『楽日』(上映中)
(ユーロスペース 11:20/13:15/15:10/17:05/19:00〜20:40)
実はツァイ・ミンリャン初体験だったり。
『迷子』(上映中)
(ユーロスペース 21:00〜22:40)
もちろんリー・カンションも初体験。
『太陽の傷』(9/16〜)
(ユーロスペース 21:00〜23:00)
これも忘れてました。予告編が良かったので期待。
『西瓜』(9/23〜)
(シアター・イメージフォーラム 12:30/14:50/16:10/18:30)
こヴぃさん、ありがとう。ではご提案どおり、本作から入ってみるとします。
『トリノ、24時からの恋人たち』(9/2〜)
(ル・シネマ 11:15/13:20/15:25/17:30/19:35〜21:25)
現代版ニューシネマ・パラダイスってこの映画でしょうか。イタリーで大ヒットしたとか。観たい。
『40歳の童貞男』(9/2〜)
(ユナイテッド・シネマとしまえん 時間は直接劇場へ)
なんでこれが豊島園だけなんでしょう? とりあえずR-15。
「妄執、異形の人々 Mondo Cinemaverisque」
(シネマヴェーラ渋谷 9/2〜)
どんなことがあっても『女獄門帖 引き裂かれた尼僧』だけは絶対。
「チャンバラ時代劇ぐらふぃてぃ」
(新文芸坐 9/9〜22)
山中貞雄 だけは何とか・・・。
「ドキュメンタリー・ドリームショー 山形in東京2006」
(9/16〜29 ポレポレ東中野 9/30〜 アテネ・フランセ文化センター)
『鉄西区』一挙上映のために休暇願い出す予定。その他も観たい作品目白押しです。
2006年08月29日
『ゆれる』、開かれたフィクション
 原題:ゆれる
原題:ゆれる
上映時間:119分
監督:西川美和
『ゆれる』の物語を最初に読んだ時、すぐに想起されたのが『ソン・フレール-兄との約束-』(2003年/パトリス・シェロー)というフランス映画でした。実際、その物語はまるで異なるものの、兄弟における互いの視線が変容していくさまを物語の中心に据えてある点、あるいは台詞に頼らず、じっくりと対象を見つめようとするカメラの存在、“救済”とも捉えられるラストショットなど、『ゆれる』を鑑賞した今もなお、その近親性を指摘することが出来るのです。そして本作は、『ソンフレール』がそうだったように、硬質な叙事性と繊細な叙情性を併せ持った、見所のある映画でした。『蛇イチゴ』を見逃したばかりに、この才能を感じさせる女性監督の登場に立ち会うことが出来なかったことが悔やまれますが、若干31歳の西川美和は、私の中では『犬猫』の井口奈巳以来の注目すべき女性監督の一人として記憶されることになるでしょう。
この映画のタイトルである“ゆれる”という言葉には、その言葉どおり、かなり微妙な感情が込められているでしょうし、また、視覚的メタファーとしても、例えば吊り橋だとか川面だとか風に揺れる木々や草花などを思い起こすことが出来ます。どこと無く青みがかった画面における、様々な“ゆれ”が、そのまま本作の主題になっているのだと思います。
例えば、2つの相反する事物や概念があるとして、その片方からもう片方へは、そのほとんどが“直線的に”移行されるわけではありません。愛と憎しみ、有罪と無罪、現在と過去、大人と子供…。それらの対立概念における事実や感情は、絶えず揺らぎながら徐々に移行していくものではないか、と。もちろん、時間という概念は、常に直線的に経過していくものですが、それとて映画の中では解体されることがほとんど、行きつ戻りつ、揺れながら進んでいくものなのです。
そんな、わざわざ書くまでもない当たり前のことが、本作では敢えて注視されていると思いました。
見所はやはり、オダリギジョーと香川照之とのダイアローグに収斂されていると言えるでしょう。
とりわけ二度繰り返される面会所のシークエンスは、通常の切り替えし以外にもフィクションならではのカメラアングル、すなわち、普通ではありえない真横からのショットがあったりして、監督の野心を感じさせました。香川照之が、ほとんど諦念を全面に出しつつも抑えた演出、あるいは静けさを破り唐突に逆上する瞬間の演出は見事としか言いようの無い程。香川照之は、『フリック』の時も凄かったですが、本作はさらにその上を行っていたのではないか、とすら思います。
カメラに関して言うなら、適度なロングショットが作品の雰囲気を作り出していたし、先に書いたように、安直な擬似ドキュメンタリー的テクニックに頼らず、しっかりとフィクショナルな空間を創出していたように思います。
その出自をみるにつけ、ドキュメンタリー的な演出を予想していたのですが、例えば静から動への演出(瞬間的な情動の炸裂)などは、ほとんど反=ドキュメンタリー的に見事に演出されていたと言えるし、あるいは後半で呆けてしまう父親役の伊武雅刀の痴呆の兆しを、短い1ショットだけで表す手腕もまた簡潔で好感が持てました(先に普通に洗濯をする姿を見せていたから、後半のそれが効いていたのです)。
そしてラスト。あの香川照之の、言語を絶した微笑みの美しさには、ラストショットとしての強度が充分備わっていたと思います。たとえその直後に画面が暗転し、映画が唐突に終焉を迎えようとも、観客は“その先にあるもの”について、思考を巡らすことができる。そういう点は、やはり是枝的と言えるのかもしれませんが、少なくとも私はあのラストショットを肯定します。
『ゆれる』は、裁判シーンや真相の究明が中心に据えられているように見えて、実はそのような分かりやすい構図におさまってはくれません。誰かが犯罪者なのか、あるいはそうでないのか。重要なのはむしろ、その過程にあるだろう感情の、意識の、記憶の“ゆらぎ”そのものであり、西川美和はそれを何とか画面に定着させたかったのではないかと思います。結論的なメッセージを本作から読み取ることがなかったのはその所為であり、だから本作は優れて開かれたフィクションなのです。
久々に俳優陣の熱を感じさせるこの映画を、私は予想以上に楽しむことが出来ました。
ちなみに、ある2人の人物の切り替えしで物語が終わり、そのラストショットが非常に含みを持たせた笑顔である映画がもう一本ありました。広末哲万監督×高橋泉脚本(群青いろ)による『阿佐ヶ谷ベルボーイズ』は、『ゆれる』同様、ラストシーンの“その先”を思考させる映画です。
2006年08月28日
夏をあきらめて映画三昧
先週末が終日どんよりとした天候だったことで、私の最後の海は無くなってしまいました。それは同時に、私の中での夏の終わりを確信させることになり、同時に、また元の映画生活への帰還を決意させるものでした。もう一度くらい“青”いイメージに染まりたかった気もしないではありませんが、それでも今年はこれまで以上に“青”を満喫できたし、その結果、かなり“黒”くなることも出来たので、概ね満足です。
さて、夏をあきらめたからか、先週末は怒涛の映画鑑賞。所謂反動というやつです。
『スーパーマン リターンズ』、『ディセント』、『青春☆金属バット』、そしてテレヴィで『クリムゾン・リバー』と、計4本の映画を。(追記:やはりテレヴィで『タッチ』も観たので計5本でした。あまりのまさかあんな形で終るとは思っておらず、観たことすら忘れておりました)
レビューも滞っているので、こちらのほうも今日から勢いをつけて更新していければと思います。
このところ、年に数回はわが身を襲うブログスランプとでも言うべき状態が続いており、なかなか長文を書くことが出来ないのですが、長いシークエンスショットが無理なら、ここは一つカットを細かく割って、何とか形にしていくつもりです。
それにしても、確か2年前にも日曜洋画劇場で『クリムゾン・リバー』をやってましたが、なんでまた観てしまったのか…折角TSUTAYAで4本もヴィデオを借りてきたのに、たいして面白くも無いこの映画を観てしまうのは、恐らく、白い目のドミニク・サンダを観たいがためなのだと、強引に納得するとしましょう。
2006年08月22日
黒い三人の男
先週は久々に“青”に同化。といってもいつもどおり、湘南の海は灰色だったわけですが、空は青く、この夏体験した中で最も強い日差しに恵まれ、それなりに黒かった私の身体はさらに黒く焼け、このまま渋谷のセンター街でも歩けば、それこそ“センター害”に勘違いされてしまいそうな感じも。服装が異なるのがせめてもの救いでしょうか。
そろそろ夏も終ってしまうし、酒ばかり飲んでないでたまにはビーチを満喫しようじゃあないか、と思ったかどうかは定かではありませんが、今回はトム・クルーズ好きな朋友・ng氏とフリスビーに興じたりも。たしか昨年も大洗のビーチで同じようなことをした記憶があるのですが、あの時は他にも数人いたし、ビーチもそれほど混んではいなかったからよかったものの、今回はかなり混雑した湘南のビーチで、明らかに30overの黒い男二人が、白や黄色やレインボーストライプのビキニに包まれたギャルたちが無邪気に水遊びする様を、結果的に邪魔するようなかたちでフリスビーを投げ合っているという光景はいかがなものかと、やはり自問自答は避けられませんでしたが、そろそろ治癒しつつある右手首のリハビリを兼ねたフリスビーは思いのほか悪くなく、だんだんと調子に乗ってきた私は、すでに酒が入っているのをいいことに、目の前を通り過ぎようとするギャルの頭すれすれを狙って投げるという、ほとんど悪乗りティーンエイジャーのような奇行に走ってしまい、相手のng氏を苦笑させてしまいました。
そんな光景を、もう一人の朋友・nw氏は黙って見ながらやはり苦笑しているのかと思いきや、彼は完全に爆睡していたらしいのですが、それどころか、我々よりもさらに“危ない”見ず知らずの男から、「クスリはないかなぁ…」などと詰め寄られていた模様。nw氏は、どう穿って見てもジャンキーには見えないのですが、本物のジャンキーから見れば、あるいは仲間だと思われたのかも。フリスビーを終えて私とng氏が戻ってきた時には、クスリにありつけなかったその男が、我々のテリトリーに上半身を侵入させてふて寝していました。その光景はあまりに異常で、ジャンキーに理屈は通用しないと判断した我々三人は、もうそろそろいい時間だからなどといい訳しつつ、そそくさとその場を後にしたのでした。
その後、もはや定番と化したイベントのように、生しらすを求めてビーチ近くの食堂に。
いつもとは別の場所に行ってみようということで前知識無しで入ったその食堂というかレストランは、江ノ島ビュータワーの5Fにある、およそレストランらしからぬ「おしゃれ工房 遊」という名前でした。客は我々のほかに一人もいませんでしたが、ビーチを見下ろせる絶好のロケーションで飲むビールはまったく悪くなく、ついつい長居をしてしまうほど。店内には何故か大きな熊のロボットが演奏しているグランドピアノがあったり、クリスマスツリーがあったりと、極めて季節感を欠いた超現実的な空間ではありましたが、つまみも美味しいし値段も高くなく、思いのほかかなり満足した我々は、来年からはここだな、と深く頷きあった次第。
今年は梅雨が長引いたり台風が接近したりで、正確に二回分の“青”を逃していますが、そうこうしているうちに、夏も終わりに近づいています。せめて後一回は海に、と目論んでいますが、どうなることやら…。ちなみに今、私の右腕はかなりの筋肉痛に悲鳴を上げています。まさかフリスビーくらいで!?
鬼束ちひろの「infection」という曲に“いつの間に私はこんなに弱くなったのだろう”という一節がありますが、私の心境もまさにそれと同様。この右腕のリハビリを兼ねて、今週か来週、今年最後の海に行ければもうこの夏に思い残すことはありません。
ちなみに先週観た映画は『ジョルジュ・バタイユ ママン』のみ。本作には最後まで疑問を拭うことが出来ず、私にとってはあまり面白くない映画でした。平日のレイトだったからか客の入りも悪かったです。結構期待していただけに、失望も大きかったのかもしれません。この1本で判断することなど出来ないのを承知で、バタイユの映画化はやっぱり不可能なのかもしれない、などと思わざるを得ませんでした。
現在は『ゆれる』の文章を書いてます。
2006年08月17日
酒と共に語る
先日少し触れましたが、昨日はmixiで知り合ったお二方と「70〜80年代アメリカアクション映画について語る」と題した集まりがありました。お二人とは随分前に一度お会いしていたのですが、その時はゆっくりお話出来なかったので、今回、改めて存分に語らおうということになったのです。
さて、改めて告白するまでもありませんが、私にとって“70〜80年代アメリカアクション映画”というジャンルを語るというのは非常に困難です。映画を本格的に見始めた時、私の興味はどちらかと言えばヨーロッパ映画、しかもより“芸術的”といわれるような作品にあったので、なかなかそのジャンルに興味が向かなかったからです。もちろん、しかるべきアメリカ映画は観ていたものの、その邦題がいかにも通俗的で出鱈目極まるB級アクションに関しては、ほとんど敬遠すらしていたと言えるでしょう。そんな中でかろうじて出合った監督たち、つまり、ロバート・アルドリッチやリチャード・フライシャー、サミュエル・フラーやサム・ペキンパー、あるいはドン・シーゲルやクリント・イーストウッドらに関しては例外的に偏愛し、それは今でも変わりませんが、そういった“教科書的”なセレクトの域を出ることはなかったのです。
そんな私にとって、昨日の集まりは刺激に満ちていました。
とにかく彼らが観てきた映画(とりわけ80年代アクション映画)の本数は途方も無く、聞こえてくる映画のタイトルを追うのがやっとでした。彼らの知識はそのストーリーに留まらず、何十人ものスタッフやキャストの名前が縦横無尽に引用され、そして素晴らしいことに、それらの作品や人物への惜しみない愛情が聞いている私にも伝わってくる。ああ、なんていう人たちだろう、彼らのような人間にここまで愛されるのなら、不毛の80年代B級アクションも報われるだろうなぁ、と感慨も深く、彼らの10分の1も映画を観ていない私まで幸せな気分になってくるのでした。
今回、共通認識として皆である映画を事前に観ておいてください、と言われていました。その映画は、恐らくこういう機会でもない限り私が観る事が無かったであろう『L.A.大捜査線/狼たちの街』というアクション映画でした。ウィリアム・フリードキンが1985年に撮った本作、観てみると、これがまたとんでもない魅力に溢れている。フリードキンを大して知らなかった私の目を、ほとんど冷水をぶっ掛けて一気に覚ましたのです。なるほど、北野武の初期の狂暴さは、この延長線上にあったのかと納得もさせられます。
この作品が、それこそ血肉となっているようなお二人の会話は聞いていて本当に面白く、そこからはもう、映画好きならではの会話の展開、すなわち、一人のスタッフを基点に別の作品へ、そこから同時代に撮られたまた別の作品へ、今度はあるキャストを深く掘り下げ、またその人物を基点に別の作品へと、4時間以上ぶっ通しで語り合うというものでした。私も何とか自分の知識を総動員してみたものの、またもや“世の中上には上がいる”という思いを強くなるばかりでした。が、同時に、これまで私が弱かったこの手のジャンルに対する渇望が涌いてきたので、その意味でもかなり刺激的な体験でした。
ここでは、昨晩話題にあがった映画のタイトルを全て出すことなど到底出来ませんが、いかに濃い夜だったかは、何となく伝わったでしょうか。この集まりを1年も続けたら、私の弱点もかなり補強されるはずです。
では最後に、水野晴男よろしくこのようにまとめておきたいと思います。
いやぁ、酒と共に映画を語るって、本当にいいものですね。それではまた、ご一緒に楽しみましょう
2006年08月14日
大停電の朝
今朝、いつものようにシャワーを浴びていると、突然全ての電気・ガスが消えてしまいました。すぐさま冷水と化したシャワーを無理やり浴び切ってブレイカーを見ると、一つも落ちてはいません。部屋の外はなにやら慌しい喧騒に包まれ始め、裸なのですぐに外に飛び出すことも出来ない私は、しばし、途方に暮れるしかありませんでした。しかし、月曜日なのでそうそう悠長なことも言っていられず、このマンションの電源が落ちたのかなぁ、などと考えながら朝の準備を淡々とこなしたのですが、この時期、クーラーを使えないというのは暑がりの私にとって予想以上に厳しく、それは例えば、下水道に頭の先まで浸かっているのと同じくらい不快極まりないと言っても決して大げさではないほどです。
ドライヤーも使えないので、とにかく日光で髪を乾かそうと濡れたままとりあえず着替えて外に出てみると、大家さんが「この辺一体全部停電です」と一言。そんなこともあるんだなぁと自転車にのって青山通りに出た瞬間に観た光景は自体の大きさを物語っていました。そこには、池尻大橋から田園都市線に乗れなかったと思しき人々が溢れ、皆渋谷方面に向かって歩いていたのです。パトカーやら消防車やらがサイレンを鳴らしながら何台も通り過ぎる青山通りを何とか進むと、通り沿いにあるコンビニの電気は全て落ちているし、信号はまだ動いていましたが、明らかにいつもの青山通りではありませんでした。
渋谷に着いてみるとJR以外はほとんど運転を見合わせており、警察官の姿もちらほら。私はJR利用者なので何とかなりましたが、駅の放送によれば、どうやら都内広域で停電が発生していて、交通が大混乱しているようでした。私が都内に住み始めてからこのようなことはなかったのではないでしょうか。幸いにしてまだお盆休み中ですから、渋谷はそれほどパニックにはなっていなかったようですが。
世界中で物騒な出来事が頻発している昨今、こういった自体に直面すると真っ先に思い浮かぶのが“テロ”という言葉ですが、それは昨日、『ユナイテッド93』というアメリカ映画を観てしまったこととも決して無関係ではありません。東京のような都市は、電力の供給を断ち切られてしまえば、まるで機能しなくなってしまうということが、図らずも証明されてしまった気がしました。この暑さがそれに拍車をかけることももまた言うまでもありません。
どうやらニュースに拠ればテロの可能性はないようです。
でもこういう地味な、しかし非=暴力的なテロがあってもおかしくないよなぁ、なんて思う月曜日の朝です。
というわけで、昨日観た『水の花』と『ユナイテッド93』に関してはまた別途。
とりわけ『ユナイテッド93』は、ポール・グリーングラスに「よくやった!」と言いたくなる佳作でした。本作の出来栄えを観て、『ボーン・スプレマシー』のことは忘れてあげようと思いました。
2006年08月09日
KIYOSHI KUROSAWA EARLY DAYS
ある監督に興味を持てば、彼、または彼女が初めて撮った映画を観たいという気持ちが自然と涌いてくるものです。その監督が誰に、あるいはどんな作品に影響を受けたのか、作品の持つフォルムは現在と比べてどのように変わっているのか、あるいはいないのかを確かめられれば、今後その監督の作品に触れる際の、一つの手がかりを持つことが出来るからです。
同時代的にある監督のデビュー作に立ち会えることは、だから、非常に幸福なことだと思います。しかし私は年齢的に、これまで観てきたほとんどの監督のデビュー作を、後追いで観るしかありませんでした。驚きと共に監督を発見するという特権に対する憧れ。これは嘗ても今も、変わらず抱き続けているものです。
ところで黒沢清監督。
彼のデビュー作である『神田川淫乱戦争』を観たのはもう随分前です。その出来栄えにはかなり驚かされましたが、その時はまだ、彼が学生時代に撮った8mmの存在すら知らなかったと思います。その後、様々な本を通してどうやらその8mmは傑作らしいということを知るのですが、果たして自分にそれを確かめる機会があるのだろうかとほとんど諦めていたので、今回の特集上映は大きな価値があったと思います。
今回上映された6作品のうち、私が観られたのはBプログラムの3作品のみ。最も観たかった『SCHOOL DAYS』を鑑賞出来なかったのは2006年最大の失態として記憶されるでしょうが、その日は私にとって同じくらい重要な『錆びた缶空』を鑑賞出来たので、致し方なしといったところです。加えて、蓮實重彦氏と青山真治氏に挟まれる形で黒沢清氏の話を間近で聞くことが出来たことは、前日の失態を、帳消しにしたとは言いませんが、かなり薄めてくれたとは思います。この3人の鼎談は本当に面白かった。
あれほどの人数がアテネフランセに押しかけたのを、私は始めて目にしました。
1時間以上前に到着したにもかかわらず、すでに4FからB1Fまで列が出来ていたと書けば、若き日の黒沢作品を観たいという観客の熱狂も伝わるでしょうか。最終的には、会場のあらゆる隙間を観客が埋め、恐らくフル回転していたはずの冷房もほとんど効いていないような状態でした。ペドロ・コスタの時ですら、ここまでではなかったと、同行した[R]氏にふと漏らしてしまったほどです。
2名の映画作家とその精神的な師による鼎談の中身に、特に大きな発見があったわけではありません。それは嘗て、どこかで聞いたり読んだりしたことのある内容と重なる部分が多かったように思います。しかし、やはりそれを本人の口から聞くという体験は特別なものです。青山氏の口から伊丹十三という固有名詞が出てきた時の黒沢氏と蓮實氏の表情など、そうそう観られるものではありません。個人的には、日本を代表すると言っていい映画作家2名が、一人の初老を前に律儀に“生徒”として納まっているという構図が最も興味深かったです。どこかで採録でもされたら、買ってしまうだろうと思います。
さて、肝腎の黒沢初期8mm作品に関してですが、映画史的なパースペクティブがあるようで、結構出鱈目でもある、みたいな軽さを存分に楽しめました。鑑賞したのは下記3作品。
■東京から遠くはなれて 1978(35分)
監督/田山秀之 撮影/黒沢清 出演/万田邦敏 黒沢清
■しがらみ学園 1980(63分)
監督/黒沢清 出演/森達也 久保田美佳 鈴木良紀
■逃走前夜 1982(8分)
監督/黒沢清 万田邦敏 出演/浅野秀二 塩田明彦
いずれもデジタル上映でした。「BOW30映画祭」のパンフレットで、6月に行われた蓮實氏と黒沢氏による対談を読むと、8mm作品をデジタル化してdvdに変換しておこうかと思っている、今はかろうじて観られるが、あと何回か映写機にかけると多分フィルムが切れる、などと言う発言を読んでいたところだったので、ああやっぱり、とデジタル上映にも納得しました。本当はフィルムで観たかった気もしますが。
『東京から遠くはなれて』は、パロディアス・ユニティ結成時の朋友・田山秀之氏が監督し、黒沢氏は撮影と出演。ラストで機関銃をぶっ放す黒沢氏とそれに続く俯瞰のロングショット。会場は沸いていたが、私は結構感動してしまいました。
『しがらみ学園』の主演は『A』『A2』の森達也氏です。若い。若すぎる。アメリカ映画的な銃撃戦があったり、小津的なダイアローグやカメラ位置があったり、ゴダール的な言い回しがあったりで、あまりにも贅沢。一つの作品にこれだけの要素が詰め込まれて63分だから驚きます。素晴らしい1本。PFF入賞も肯けます。
『逃走前夜』には塩田明彦氏が出演していたようですが、気づきませんでした。前半を万田邦敏氏が、後半を黒沢氏が撮影したそうですが、特に後半のシークエンスショット、あれは『ソナチネ』の花火の打ち合いシーンをはるかに準備するものすごいシーンでした。前半はやはりゴダール的。
Aプログラムを観られなかったのは本当に残念ですが、すでにdvd化してあるということで、何かの拍子に発売されることを期待したいです。
今年は『叫』がヴェネツィアにも招待されているし、『LOFT』の公開ももうすぐなので、とりあえず急いで2冊の本を読んでおこうと思います。
ともあれ、あまりにも充実した一日でした。
結果的には黒沢清監督を再度驚きと共に発見できた、そんな気さえしているのですから。
2006年08月08日
第28回PFFとPFFスペシャルに参加できた幸福、または『錆びた缶空』に関する覚書
もう随分と時間が経ってしまいましたが、今年は「ぴあフィルムフェスティバル」に初めて参加しました。平日に会社を休んでまで観たかった作品は2本。共に群青いろの作品です。
『鼻唄泥棒』も『14歳』も、私にとっては非常に意義深い作品でした。彼らは少なくとも現在の私にとって、最も重要な映画作家であることを確信出来たので。まだ彼らの作品を観ていない方には、とりあえずdvd化されている『ある朝スウプは』と『さよなら さようなら』を観ていただくほかありませんが、何となく彼らのことををやたらに喧伝したくないという気持ちが募ってきて、だからこの記事も書けずにいたのです。よってここでも、作品の詳細については書かずにおきます。必見、などと高らかに宣言することも止めておききましょう。とりあえず『14歳』が正式公開された暁には、必ず誰かを連れ添ってもう一度観にいくつもりです。その人(たち)だけに、私は自分の群青いろに対する思いを語ることが出来るのだと今は思っています。
とりあえずは、日に日にその重要度を増していく「ぴあフィルムフェスティバル」に感謝。来年は是非コンペティション作品も鑑賞したいと思います。
ところで、その「ぴあフィルムフェスティバル」に嘗て出品された作品を大々的に回顧した「PFFスペシャル」。今では日本を代表しかねない作家へと変貌を遂げた、あるいは遂げつつある作家の自主映画を観る事が出来るこの稀有な試みは、それだけで賞賛に値します。告知に充分な時間も予算もかけられなかったようですが、それでもこの試みに賛同したユーロスペースはやはり素晴らしい劇場だと思います。私が観たかった数作品はそのほとんどが平日の上映だったので、鑑賞は諦めていましたが、どうやらこっそりと追加上映が決まったらしく、そこにはあの松井良彦の『錆びた缶空』や豊島圭介の『悲しいだけ』などが含まれていて驚き、それを知ってしまった以上、万難を排してユーロスペースに駆けつけることが私の義務だと確信しました。
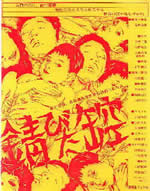
金曜日21:00のユーロスペースには、ざっと30人程の観客しかいませんでした。これから鑑賞する作品について考えると、私にはそれくらいがベストな環境だと思われましたが。
ここではとりわけ、『錆びた缶空』についてのみ思いつくままに書いておきたいと思います。
私が長年にわたり鑑賞を切望している『追悼のざわめき』の松井監督ですが、今回が初鑑賞になります。果たして、松井監督の3本のフィルモグラフィーのうち処女作である本作は、期待に違わぬ作品でした。撮影は石井聰亙、8mmの荒れた質感は途轍もない生々しさを画面に刻み込んでいました。
『錆びた缶空』はホモセクシュアルの性交シーンで始まります。かなりのクローズアップで切り取られた彼らの体の一部が幾重にも積み重ねられていくこのシーンに、私は最初、ある種の違和感を感じていました。それがいかにも審美主義的で、スキャンダラスに思えたからです。しかし、彼らが会話し始めるや否や、私が感じた違和感はたちどころに消え去りました。そこに流れているであろう空気、ぶっきらぼうな声や生活音、仕草などが孕む、例えようも無い生々しさ。リアルというよりも、あくまで生の証としての生々しさが、時にユーモアに、時にグロテスクに私の脳裏に響いていく。それは『鬼畜大宴会』を観た時に感じた生々しさをはるかに凌駕していました。ゲリラ的に撮影されたであろうさまざまなロケーションもまた時代を色濃く反映しており、ホモセクシュアルの三角関係という、決して万人が共有しえぬ題材にもかかわらず、そこには映画における“普遍的な何か”(それは愛だったり破滅だったりするのでしょう)が距離無しで観客を撃ち抜いているかのようでした。それは稀有な映画体験であったと同時に、まったく感動的な映画体験でした。
私にとっての松井監督は、現在進行形で発見されるべき監督なんだと思います。
なお、ここでは詳述しませんが、その他3本の作品もかなり独特で、魅力的でした。「ぴあフィルムフェスティバル」の歴史と今日的意義を充分に感じさせるこの催しに参加できたことを、今はただ幸福に感じています。
ダニエル・シュミット、逝く
週末、たっぷりと時間があったのにもかかわらず、どうも自宅でブログを更新する気にならないのはなぜなのか。先週金曜日から昨日にかけて、映画も8本観ているし、記事を書くネタには事欠かないはずなんですが。あまりに充実していたから、という理由が妥当かもしれません。だからこそ、インターネットなどほとんど必要が無かった、ということでしょうか。
そうこうしているうちに、ダニエル・シュミットの訃報。
ディスプレイの前で「まさか…」と声を漏らしてしまいました。2ちゃんねるの映画板でそんな記事を発見しても、俄かには信じられません。しかし、どうやらシュミットは本当に亡くなってしまったようです。
一人の映画作家が亡くなっても、私に出来ることなど何もありません。誰が読むでもない、こんな文章を書くくらいがせいぜいです。今後も、このような経験を幾度も繰り返していくのだろうな、などと思いながら、それでも私は映画を観続けるでしょう。
せめて、スイス映画特集でシュミットを観ておくべきでした……
スイスから遠く離れた東京にて、合掌。
2006年08月03日
ある日の会話〜『M:i:III』を観て
 原題:MISSION IMPOSSIBLE III
原題:MISSION IMPOSSIBLE III
上映時間:126分
監督:J・J・エイブラムス
[M]:このところ、トム・クルーズの新作といえば一緒に観に行くのが通例となってきたね。で、こうして飲みながら話すとやけに盛り上がるんだけど、それはやっぱり我々がトム・クルーズ党だからなのか、それとも彼が出演しているここ最近の映画が面白いのか、どっちだろうね。率直に言って今回のどうだった?
ng:最近の彼が面白いっていうのはあるんじゃないかな。しかし今回のは面白かったね、かなり。今までのシリーズで一番面白いかもしれない。
[M]:それは俺も同じだな。確かに最高傑作だと思うよ。これまでと明らかに何かが違ったよね。トム・クルーズに関しては相変わらずだったけど、やっぱり新しい点もあった気がする。
これまでと何が違うのか?
ng:何か、映像がさ。CGの使い方というか見せ方という点で、今回は良かった。例えば、トム・クルーズがミサイルの爆撃でふっ飛ぶシーンがあったじゃん? あのデカい爆発と、爆風でちょっと不自然にふっ飛んで車に叩きつけられて窓ガラスが割れるっていう、あれは最高でしたよ。今回はアクションも結構自分でやっているよね。
[M]:ああ、あそこね。一瞬ふわっと浮いてから叩きつけられる感じね。あのシーンも含めて、今回のトム・クルーズはさ、『宇宙戦争』の彼とダブらない? 何か全速力で逃げるシーンの印象が強いんだよ。常に劣勢に追い込まれるクルーズ、というかね。例えば冒頭のシーン、あれはラスト近くのクライマックスを冒頭に持ってくるという、まぁアメリカ映画ではそれほど珍しくないドラマ構成なんだけどさ、あの時のトム・クルーズの演出は、ちょっと新しくなかった?
ng:確かにね。10数えるうちに、トム・クルーズの態度がどんどん変わっていってさ。恋人の足が撃たれた時、「お前を絶対に殺してやる!」なんて激昂してたね。感情むき出しって言う感じで。所謂ヒーローとしてのトム・クルーズ像を、今回は自ら壊したのかもしれない。いや、それはここ数年の彼に共通しているのかも。激昂したかと思えば、次のカウントで急に情けない表情に戻ってさ。あの表情、やっぱり『宇宙戦争』で、ダコタ・ファニングに子守唄を歌ってやれない時の何とも言えない表情に重なるかも。
[M]:今回新しく起用されたJ・J・エイブラムスは、テレビ出身なんだよね。『LOST』って観た? お前アメリカのドラマ結構観てるんでしょ。
ng:ああ、あの監督なんだ? 第1話だけ観たけど、なるほどね。言われてみれば……。
[M]:これが劇場デビュー作だから大抜擢だけど、なるほど、ドラマに力点を置いたっていうのもこれまでとは違う点なんだろうね。特に『M:i-2』と比べるとさ、あれは多少は楽しめたとは言え、やっぱりなかなか酷い出来栄えだったと思う。あまりにアクションに傾倒するあまり、ドラマ性が疎かになった、なんて阿部和重が言ってたけど、今回はそんな批評に対する一つの回答でもあるかもしれない。
ng:実際、どういう点にドラマ性が出てたと思う?
[M]:人物の背景を描こうとしていた部分かなぁ。最初がいきなり婚約パーティのシーンだったでしょう? 恋人がいて、彼女は家族になろうとしている。イーサン・ハントのバックグラウンドは、これまであまり重視されなかったし、もちろんそれはこのシリーズが“スパイ映画”だからだと思うけど、今回は、例えば3作を通して出演しているあの黒人(=ヴィング・レイムス)とトム・クルーズとの会話は、ほとんど奥さんがどーのこーのとか結婚がどーのこーのとかそんなのばっかだったじゃん。しかもほとんどがミッションの最中っていう。イーサン・ハントが普通の人間の生活を送ろうとしているという点は重要だと思う。『M:i-2』でもロマンスくらいはあったけど、最後まで独身だったでしょう。でも今回は即席とはいえ結婚式まで挙げてしまう。ミッションのほかに家族というファクターが加われば、ドラマ的要素は強くなるのは必然じゃないかね。もちろん、それも監督の撮り方次第だけど。ただ、そのドラマが人間性に深く踏み込んでいたのかと言われると……
ng:そういえばイーサンの上司も「家族が一番だ」とか言ってたよね。あの黒人も似たようなこと言ってたし。そもそも最初のパーティシーンが結構丁寧に描かれてた気がしたんだけどさ。何か彼女の親類とかいっぱい出てきてたじゃない? あの辺りもお前の言う背景を描くっていうことかね。
変な弟みたいのは途中にも出てきてたけど、あいつは何なの? 全然大事なシーンじゃなかったでしょう?
[M]:あれは恋人の弟でしょう。確かに大事なシーンではなかった気がするけど。
しかしあれだね、これはやっぱりシリーズものだから、一応しかるべきシーンは引き継がれていたな。
ng:ワイヤーで降りてきて地面すれすれでピタっと止まるとことか。ただ、もうすでにそれが見せ場だとは言えないでしょう。
好きなシーンについて
[M]:まぁね。じゃあ本作の見せ場はどこなんだ、っていう話だけど。
ng:俺が一番良かったのは、あのバチカン潜入前のシーン。あれは良かったナァ…。
[M]:見せ場っていうにはあまりに小さいな……でもあそこは最高だった。実は俺もあのシーンが好きなんだよ。素晴らしいね、あそこは。イタリア語を話すトム・クルーズとジョナサン・リース・マイヤーズ、っていうだけじゃなく、彼らの身振りのわざとらしさとか、怒鳴ってくるイタリア人の感動的なイタリア人らしさときたらもう…。しまいには怒ってた彼が最後に「ciao!」なんつって。いいよなぁ、ああいう小さい挿話。たまらないね。
ng:あとさ、最初のヘリコプターのチェイスシーン。あの舞台、設定ではベルリンで、ベルリンに本当にあんな風力発電プラントはあるのかはわからないけど、よく撮れてると思うよ。ミサイルが風車に直撃するCGなんかは凄かったね。
[M]:風車の破片が地面に突き刺さるあたりもね。羊の群れに風車の破片がズバッと刺さるイメージはなかなか記憶に残る。しかも、あのシーンは言ってみれば二重に追われるシーンじゃない? 一つは追手のヘリに、もう一つは救出した部下の頭に埋め込まれた時限装置の爆発に。空間的なチェイスと時間的なチェイスが幾度も切り返されて、ちょっとスピルバーグを思い出したよ。高度なサスペンスというかね。
サスペンスと言えばさ、トム・クルーズがフィリップ・シーモア・ホフマンに成りすました時に、用心棒がトイレに入って来て近づこうとするじゃん。偽声のコンパイル完了まであと30秒あって、そこでやっぱり時間的にも空間的にも追われているんだよね。もちろんギリギリで間に合うんだけど。上手いよね、ああいうの。
ng:うん。しかしヘリのシーンの最後はなかなかショッキングだったね。
[M]:よくぞ見せてくれたって感じだよ、あのシーンは。しかもクローズアップだからね。俺はまた、小規模の爆発になって、ヘリが落ちるなんて予想してたんだけどさ。そしたら“脳内の”爆発だからね。迫力が無い代わりに妙にリアルで。ほんの一瞬「キュン」っていう音がして、彼女の表情が変わるっていうあの演出は、ほとんどSFホラーみたいな感じだったよ。不気味で、残酷で。
ng:確か全部で3回くらい見せてたね。監督、あの顔が撮りたかったんだろうなぁ…。左目が完全に逝っちゃってたね。右目も斜め上を見てたし。
本作はスパイ映画なのか?
[M]:『M:i:III』は何映画になると思う? 今回もサスペンス要素とかアクション要素はあったじゃない? で、ドラマ性もある。俺としてはまず、アクションの質がスパイ映画におけるアクションではないという気がしたんだけど。ビルから飛び降りるシーンがあったけど、あれなんかジャッキー・チェンのアクションそのままじゃないか、と。『Who Am I?』という映画にも、ジャッキー・チェンがビルの斜面を滑り降りるシーンがあってね。一か八か的なアクションだよね、あれは。スパイ映画のアクションは、そういうものだろうかなんて思ったんだけど。やっぱりジャッキー・チェンの『アクシデンタル・スパイ』っつう映画もさ、スパイ映画とは言えないんじゃないか、と。まぁジャッキー・チェンの映画と『M:i:III』を比べてもしょうがないんだけどさぁ。
ng:う〜ん、難しいね。俺としてはあえてジャンルに当てはめるなら、トム・クルーズ映画としか言えないけどね。まぁ『宇宙戦争』の時にも話したけど、結局このシリーズは彼がプロデューサーなわけじゃない? トム・クルーズのために存在する映画というかね。トム・クルーズはもはや一つのジャンルということかな。
[M]:なるほど。そう言われてしまうと同意するしかないなぁ。ただそれでも敢えて考えるとさ、『M:i:III』はやっぱりスパイ映画的な要素が強い気もするんだよ。だけれども、そうじゃない要素も多分にあるっていうさ。
そもそもそんなに沢山のスパイ映画を観てるわけじゃないから、確かなことは言えないんだけど、スパイ映画のアクションシーンってさ、指令系と実行系に分かれているものなんじゃないかと。主人公が完全に一人で敵を倒したり活躍したりするというよりは、チームプレイなんだよね。今回は確かにチームプレイに力点が置かれていて、指令系であるヴィング・レイムスと実行系であるトム・クルーズや部下とが、同じ画面でアクションするということがほとんど無いよね。そもそもスパイとは常に作戦に基づいて行動するものでしょう。指令と実行がカットバックされればされるほど、それは通常のアクションシーンとは離れていくと思うんだよ。あくまで私見だけど。
ng:そういえば今回は距離と時間の計測がやけに強調されてなかった? 30秒で開始だとか、1分で戻るだとか、そこまでは800mだとかさ。具体的な数字が沢山出てきてたよね。それってつまり、スパイ映画の特徴なのかもね。
[M]:正確な数字が出てくればくるほど、アクションは非現実的になると思う。でもその非現実性がスパイ映画の特性だとすれば、『M:i:III』はしっかりとスパイ映画しているということになるね。だってスパイ映画のアクションはさ、常に時間との戦いでしょ? 今回も48時間という時間制限が設けられていたけど、限られた時間の中で出来るだけスマートに不可能を可能にしようとするのがスパイ映画じゃないかなぁ。
ng:でも、そんなにスマートじゃなかったよね、今回は。上海についてすぐ、仲間と最後の作戦について話しあうけど、あそこでトム・クルーズが窓ガラスに計算式を書き始めるじゃん、一心不乱に計算しててさ。あれ最高に可笑しかったんだけど。あまりに非現実的で滑稽でね。でも今回が一番人間的だったかもしれないね。
[M]:冷静なんだか興奮しているのか分からない、むしろその間を行ったり来たりしてる感じだったね。ああいう演出、ものすごくトム・クルーズに似合っていると思う。人間的という部分で、さっきの話に戻るけど、トム・クルーズが逃げている印象が強いって言ったのもさ、もちろん、今回もこれまでどおり、一つ一つのミッションは、多少の難はあっても結果的には極めてハリウッド的に完遂されていくけど、今回重要視されたらしいドラマ性って、つまりイーサン・ハントの人間性っつうことでしょう。家族=恋人だったり、部下だったりを失うことを恐れるっていう極当たり前の感情が、ドラマ性を浮き上がらせているんだと思うんだよね。本当は彼が逃げ惑うシーンなんてそんなに無かったんだろうし、目立ってたわけではなかったはずなんだけど、そういったドラマ性があったからこそ、逃げ惑うイーサンが印象的に記憶されているのかも。感情的になったりしどろもどろになったり弱々しくなったりするイーサン・ハントを見せるというのが、今回の狙いだったということかな。
ng:やり手スパイのイーサン・ハントが、今回ばかりはあっけなく自分の秘密を悟られるよね、奥さんに。「何があったのか話して」って詰め寄られた時、話そうか迷ってたでしょ? 完璧さを誇るスパイがただの夫になる瞬間。守るべき家族っていうのが大きなテーマになっているのは、こういった点からも窺えるのかも。
やっぱりアメリカ映画
[M]:結局さ、「ラビットフット」っていうのは何だったの? っていうかただのマクガフィンに過ぎないよね、結果的には。その証拠に、最後の「ラビットフット」を奪うっていうミッションはほとんど描かれない。あそこは振り子の原理、かどうかしらないけど、とにかくあるビルから隣のビルに飛び移るっていうのを見せたかっただけで、「ラビットフット」を奪うシーンなんて1シーンもない。奪ったという事実はトム・クルーズが無線で告げる一言によってのみ示されるだけだよね。
ng:面白くなってくるのはむしろその後、冒頭のシーンがまた出てくる辺りからじゃないかな。俺的には、トム・クルーズが自ら電気ショックを促すシーンで、まさに死ぬ直前に一言「I love you..」って言うシーンが面白かったね。あんなこと言っちゃってそれが妙に絵になっちゃうのがトム・クルーズなんだって思ったけど。
[M]:電気ショックの時、加えていた木片がバキッって折れるんだよね。あれは悪くない。そういえば、銃を使ったことがない奥さんにトム・クルーズが使い方をレクチャーするシーン、あれは、序盤に出てきた、部下に銃の組み立て方を教えているシーンがあったからこそ生きてくるシーンだったと思った。でもさ、その後無事生き返ったトム・クルーズが…
ng:生き返るなり銃を構える(笑) ありえねーだろ!って思うけど、あれが今のアメリカ映画なのかね。確かに絵にはなってるかもしれないけど、あれはやりすぎかなぁ…
[M]:アメリカ映画っていう点について言えばさ、あそこまで壮大な物語の最後の決戦が、やっぱり殴り合いなんだよね。そこには最新兵器も仲間もいなくて、言ってみれば喧嘩でしょう。で、フィリップ・シーモア・ホフマンは、何の関係も無い通りかかっただけのトラックに轢かれて死ぬ、と。呆気ないと言えば言えるし、いかにもアメリカ映画だな、とも言える。
ng:あのラストシーンだって、そうじゃん。最後には絵に書いたような大団円ですよ。何故か奥さんはIMFの本部で仲間と談笑してるしさ。それで皆が祝福するわけですよ、拍手喝采で。あの黒人なんか両手を上に挙げてめっちゃ嬉しそうだったけど。
ああいうシーンもさ、あんなんで良いのかって思わなくもないよね。ハッピーエンドではい終わりみたいなさ。
[M]:よくも悪くもアメリカ映画だっていうことかね。アメリカ映画というものに守られているというか。逆に言えば、こちらを動揺させるような映画では決して無いということでしょう。楽しい映画ではあるんだけど、それだけに終らない作品が存在する以上、相対的にこの映画の出来がどれほどの出来なのかはやっぱり考えてみる必要があるかもしれない。俺達は普通に、というかそれ以上に楽しんだんだけどさ。
トム・クルーズには、是非もっと小さな映画に出て欲しい、というか制作して欲しいと思う。彼のアクション映画は楽しめるけど、もうこれで行くところまでいったのかな、という感じもするんだよね。
ng:小さな映画ねぇ…。でもトム・クルーズはやっぱり変わらない気もするけど…
2006年08月01日
必見備忘録 2006.8月編
7月はそれなりに映画を観る事ができたものの、逃した(あるいは現在進行形で逃しつつある)作品も多く、総括すれば若干消化不良気味でした。もちろん、時期的にそうなるのは分かりきっていたので今更悔やんでみても始まりませんが。
『ゆれる』にあれだけの人が集まるというのは単純な誤算でしたし、「BOW30年祭」に関してもどうやらこちらの予想を超えている模様。行くつもりでいたら劇場が変わっていたなんて作品もありまして、とにかく観るべき作品の多くを見逃した感じ。その辺は、今後の下高井戸シネマあたりに期待したいところです。
まぁあれだけ特集上映や映画祭の類が重なってしまうと、どうしたって観る事ができない作品が出てきてしまうものですし、これまでもそうやって取捨選択してきたのですから、もう開き直るしかないな、と思います。
『チーズとうじ虫』(〜8/4)
(ポレポレ東中野 10:30/21:10〜23:00)
上映終了まで後4日。間に合うだろうか……
『姐御 ANEGO』(〜8/4)
(シアター・イメージフォーラム 21:00〜22:45)
ついこの前チラシを入手したばかりなのに、やはり後4日で終了。早すぎ。
『キングス&クイーン』(上映中)
(シアター・イメージフォーラム 20:50〜23:20)
これはもう一度スクリーンで観ておきたい。後何日上映されるかは、客入り次第とのこと。
『ゆれる』(上映中)
(アミューズCQN 11:00/13:40/16:20/19:00〜21:15)
是枝に師事した監督がオダジョーを出演させた場合、こういう熱狂が生まれるということを実感。
『美しい人』(上映中)
(ル・シネマ 時間は要確認)
先月は見逃しましたが、まだ観る気は残っています。
『ピンクナルシス』(上映中)
(シアターN渋谷 21:20〜22:40)
これは大学生の時に観た記憶があるのですが、タイトル以外まるで思い出せないので。
『水の花』(8/5〜)
(ユーロスペース 11:00/13:00/15:00/17:00/19:00)
PFF受賞作には大いに期待したいところ。
『ハードキャンディ』(8/5〜)
(シネマライズ 9:40/12:00/14:20/16:40/19:00)
2005年のサンダンスで絶賛された、ミュージックヴィデオ出身の映像派。これだけ聞くと敬遠しそうですが、うまく化けることを期待して。
『太陽』(8/5〜)
(銀座シネパトス 11:00/13:15/14:10/15:30/16:25/17:45/20:00)
今度こそ封切りで観なければ。前評判も高し。
「世界の映画作家シリーズ(38) エリック・ロメール「喜劇とことわざ」シリーズ」
(新文芸座 8/19 22:30〜)
私の体力と相談してGO!が出れば。贅沢な一時が保障されるでしょう。
「KIYOSHI KUROSAWA EARLY DAYS」
(アテネフランセ文化センター 8/4〜8/5)
8/5をピンポイントで狙います。ゴダールよりこっちだ! 賛同者求む。
「没後50年 溝口健二 国際シンポジウム」
(有楽町朝日ホール 8/24)
これから上司と相談です。OKが出れば是非に。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]



