2005年04月28日
カンヌ映画祭2005
 コンペティション部門他、ラインナップの発表を受けて遅ればせながら雑感をば。
コンペティション部門他、ラインナップの発表を受けて遅ればせながら雑感をば。
審査委員長はエミール・クストリッツァです。昨年の反動で、今回はヨーロッパ作品が選ばれそうな予感も。映画祭荒らしとも言えるキム・ギドクの『弓』は「ある視点」での上映ですから、アジア勢での注目はジョニー・トーと小林政広ということになるでしょうか。
ジョニー・トーの作品は全く観たことがないのですが、先日、現在ユーロスペースにて公開中の『PTU』の予告編を観ました。またぞろ“タランティーノ大絶賛”などとうたわれておりましたが、それはともかく、ちょっと無視できない存在になってきたなと思っています。
一方の小林政広は、前作『フリック』にかなり関心したクチなので、今回上映される『バッシング』も、その題材の今日性をどの程度はぐらかし、裏切ってくれるのかが楽しみではあります。
その他日本からは、青山真治の『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』が「ある視点」で、鈴木清順の『オペレッタ狸御殿』が「アウト・オブ・コンペティション」で公開されますが、上記2作品以上に驚いたのは「監督週間」に柳町光男の『カミュなんて知らない』が出品されることで、本作は今年の秋にも国内で正式公開されるとか。このニュースには興奮しました。
コンペティションのラインナップは、もう出鱈目なくらい巨匠ぞろいです。
デビッド・クローネンバーグ、ダルデンヌ兄弟、アトム・エゴヤン、アモス・ギタイ、ミヒャエル・ハネケ、ホウ・シャオシェン、ジム・ジャームッシュ、ロバート・ロドリゲス、ガス・ヴァン・サント、ラース・フォン・トリアー、そしてヴィム・ヴェンダース。あ、マルコ・トゥリオ・ジョルダーナまでいます。しかしおそらく、どの作品がパルム・ドールになっても、昨年のヤギラユウヤ君みたいにマスコミが騒ぎそうなファクターはなさそうですから、まぁ安心と言えば安心です。
「アウト・オブ・コンペティション」には、あのミシェル・ピッコリ先生の顔も。前作『黒い海岸』(なんという魅惑的なタイトル!)は劇場公開されず、シネフィル・イマジカで放映されたのみでdvd等も発売していないようなので、今回出品される作品も恐らくほとんど無視されてしまうんだろうなぁと、他人事ながら多少の悔しさが募ります。
というわけで、この文章を最後まで読んだ方、マルコ・フェッレーリの『最後の晩餐』とジャン=リュック・ゴダールの『軽蔑』の2本をレンタルしに、今すぐTSUTAYAに駆けつけましょう。ミシェル・ピッコリ万歳。
2005年04月25日
スパニッシュ・キャッスル・マジック
 先週末は恐らく生まれてはじめてとなるスペイン映画のハシゴという、何とも濃厚な映画体験をいたしました。
先週末は恐らく生まれてはじめてとなるスペイン映画のハシゴという、何とも濃厚な映画体験をいたしました。
1本目は新宿武蔵野館にて『海を飛ぶ夢』。同日が初日だった『甘い人生』は2館割いての上映で、『海を飛ぶ夢』を見に来た客は、劇場の端に追いやられた感も。『甘い人生』のほうはとにかく女性客の熱狂が凄まじく、すでに3回先の回まで満席だったようです。先日参加した「韓流シネマフェスティヴァル」をさらに上回るかのような加熱ぶりを何とか写真におさめようとしたのですが、シャッター音が鳴った瞬間に、彼女たちの視線がこちらに突き刺さるのを危惧し断念。まぁそれでもオスカーを獲った『海を飛ぶ夢』のほうも満席で、こちらもかなり年齢層が高かったと思います。
ほとんど事前情報を仕入れなかった私は、とにかくハビエル・バルデムのメイクに驚きました。老けメイクとしては、ここ数年で出色の完成度です。内容につきましては現在思案中ですが、何シーンか目を見張るショットがあり、そのテーマの重さに比べ、しかるべきシーンにおけるショットの強度が勝っていたという点において、評価できる作品だったと思います。
鑑賞後、次の『バッド・エデュケーション』の整理券を求め、テアトル・タイムズスクエアへ。新宿タカシマヤなど映画以外ではまず訪れることの無い場所なので、2時間と言う時間をどのように潰せば良いか検討もつかず、結局劇場近くのイタリアンでビールやらワインやらを飲みながらパソコンをいじるほかなく、その居心地の悪さは、私の“新宿嫌い”に拍車をかけることに。アルモドバル級の監督でなければ、今後も極力避けたい劇場です。
で、作品の方はというと、もはや安心して観られる監督であるアルモドバルなので、安心して観ているうちに気づいたら終了してしまった程。だからと言って何も覚えていないとかそういうわけではありません。タイトルバックのデザインなどはかなり好みで流石というべきポップセンスを感じましたし、2人の俳優はともに美しく演出も申し分なかったと言えるでしょう。まだ監督のインタビュー等を目にしていないのでわかりませんが、本策がどの程度自伝的だったのかがやや気になります。
今週末に『インファナル・アフェアIII』を鑑賞すれば、先日書いた備忘録にあったリストを何とか制覇できます。しかし、レビューのほうが大分滞りつつありますので、そうそう喜んでもいられません。というわけで、今月は「短評」の割合が高くなること必至です。
2005年04月22日
ある日の会話〜『コーヒー&シガレッツ』を観て
確かキミは食事後のコーヒーが好きだとか言ってたよね? やっぱりあれかね、劇中でイギー・ポップが言っていたように、コーヒーとタバコは最高のコンビなの? 俺はコーヒーを飲まないから、その心地よさみたいなものが感覚的に理解出来なくてさ。自宅はともかく、どんな店に入ってもコーヒーではなく酒を頼んでしまう悪癖みたいなものから逃れられずにいるから。
---まぁそう言われれば否定はしないよ。確かに酒とは違った意味で、リラックスできる瞬間ではあるんじゃないかなぁ。流石にコーヒーとタバコが昼飯だ、とは言い切れないがね。食事とはちゃんとするし。
そうか…ただ、確かにこの映画はコーヒーを飲まない俺でもその魅惑みたいなものは充分伝わったなぁ。確実に言えるのは、ジャームッシュは、コーヒーとタバコを媒介とした人間同士の空気感をこそ描いていたとことだと思う。11の物語のうち、誰も一人きりで登場しないよね。つまりそこには絶対に会話があるということ。その内容はそれこそバラバラだけど、必ずコーヒーとタバコを介した会話だったということかな。
---これ、一番最初の「STRANGE TO MEET YOU(奇妙な出会い)」は1986年に撮られてるんだよね。86年っていったら、『ストレンジャー・ザン・パラダイス』から2年くらいか。全て撮り終えたのが2003年で、その17年の間にいくらかスタイルが変わっていてもおかしくないわけだけど、これが見事に変わっていなかったな。映画制作に対するジャームッシュの姿勢は、常に一貫しているということだろうね。まず人間ありき、そこからイメージを浮かべるみたいな。
1作目のカメラは『ザンパラ』つながりでトム・ディチロ、2作目はやはり『ミステリー・トレイン』つながりでロビー・ミューラー、以降はフレデリック・エルムズだね。1作目と2作目には5年の空白があるんだけど、全11作を貫くスタイルは、やっぱり1作目のトム・ディチロが決定付けたと思う。モノクロ、ヴィスタサイズ、加えて、テーブルを俯瞰で捉えたショット。これがまたいい。コーヒーカップで「乾杯」なんて、いかにもジャームッシュが好きそうな演出でしょう。プロダクションデザインもすごく印象的で、四角いテーブルは必ずといっていいほど黒と白の格子柄でさ。タバコの白とコーヒーの黒。この“そっけなさ”が何ともいいんだよね。モノトーンがここまで表情豊かに見えるのはやっぱり凄いことだと思う。
ところで、キミは何作目が一番好みだった?
---俺は5作目の「RENEE(ルネ)」かな。あのルネ・フレンチっていう女性は何者なんだろう。その話し方、雑誌のページをめくる仕草やなんかがサイコーだったね。コーヒーのお変わりを口実に言い寄ってくるE・J・ロドリゲスをやや上目で見つめる表情なんてもう…
それに笑ったのが、彼女が読んでいる雑誌。何を真剣に読んでいるかと思えば、およそ彼女に似つかわしくない拳銃のカタログみたいなものでさ、こちらが予め想像してしまうイメージを軽く裏切っていく感じが好きだね。どの作品にも、ちょっとしたサプライズ=裏切りみたいなものが上手く按配されていたでしょ。ジャームッシュは基本的にその場のノリを重視してこの作品を作ったらしいけど、だからといって全く脚本がないわけじゃなくて、脚本はあくまでフレキシブルであるというスタンス。違う作品で幾度か同じ話題が登場するのも、もちろん意図されたものだよね。
それはその通りだと思う。実はかなり設計されているんだよね。でも恐らく意図せず共通点が生まれているのもあって、それは本当に些細な事で俺の妄想に過ぎない可能性も高いんだけどさ、3作目「SOMEWHERE IN CALIFORNIA(カリフォルニアのどこかで)」でイギー・ポップがトム・ウェイツに言う
"Hey,cigarettes and coffee,man.That's a combination."
っていう感動的な台詞があるでしょ。
それと、10作目の「DELIRIUM(幻覚)」でGZA(ウータン・クラン)がビル・マーレイに
"Aren't you Bill Murray,man?"
って尋ねるシーン。この2つの台詞に共通しているのが、"man"っていう親しみをこめた呼びかけなんだよね。この2人がミュージシャンだっていう共通項がまたそれを示唆しているんだけど、まぁ端的に言ってこの手の言い回しが好きなだけで、だから何ということもないんだけど。この2つの話はミュージシャンでありながら禁煙してたり、音楽と医学の深遠な(?)関係性について熱く論じてみたり、とにかく可笑しかったなぁ。
でも一番好きなのを挙げろと言われれば、6作目の「NO PROBLEM(問題なし)」だろうね。どちらかというとヨーロッパ寄りの2人の黒人の乾いた友情が、対話にならざる対話として紡がれていく。果たして本当に友情をテーマとしているのかどうかも曖昧なんだけど、あのカフェの雰囲気も不味そうなコーヒーも2人の座り方も不思議なサイコロも、どれも本当に素晴らしかったと思う。素直に感動したナァ……
---なるほどね。ところでジャームッシュとタバコと言えば、『ブルー・イン・ザ・フェイス』を思い出すけど、あのジャームッシュもタバコに対する思い入れを熱く語ってたよね。映画とタバコの関係とかさ。『コーヒー&シガレッツ』にはルー・リードにも出演して欲しかったよ。
ああ、あのジャームッシュは良かったね。タバコを本当に美味そうに吸うんだよね。今回の「SOMEWHERE IN CALIFORNIA(カリフォルニアのどこかで)」でも、イギー・ポップとトム・ウェイツが実に美味そうにタバコを吸ってた。反=タバコを訴えながら、あれだもんね。かといってそれがシニカルかというとそんな政治的メッセージに回収されず、彼らのリアクションはリアクションそのものでしかないというか。ジャームッシュの演出は画面の中でこそ、なんとなく力の抜けた、とぼけた風合いがあるけど、ショットそのものの強度はかなりのものだよ。それは『パーマネント・バケーション』からずっと変わっていないよね。
---最後に11作目の「CHAMPAGNE(シャンパン)」に関してだけど、あれはちょっと異質な感じがしなかった?
まず彼らが飲んでいるのは、コーヒーカップではなく紙コップに注がれたコーヒーだということ。それと、そのコーヒーをシャンパンに見立てている部分が、それまでの10篇とは異なる部分だったと思う。過去のニューヨークに思いをめぐらせ、懐古的に語る二人ではあるけど、一瞬漂おうとしている悲壮感みたいなものが、「人生を祝うため」の乾杯へとシフトしていき、あの美しいマーラーが聞こえてくる。その他10篇は、ある意味入れ替え可能だったかもしれないけど、これは間違いなく11篇の最後として撮られたものだと思うね。最も美しい一篇を挙げろといわれれば、やっぱりこの11作目を選ぶしかないな、と思うよ。
さて、じゃぁそろそろ二回目に行こうか。次の回、そろそろ始まっちゃうから…
2005年04月18日
私信〜ナショナルアンセム』によせて〜
西尾孔志(イカ監督)様
拝啓
あらためまして、「第一回 フィルムエキシビジョン in OSAKA(CO2)」グランプリ獲得、おめでとうございます。初めてお話させていただいただいて以降、貴兄の“二面性”にはただならぬものを感じていましたが、私の予感はどうやら間違ってはいなかったようです。思えば、私がmixiを始めたばかりの頃、最初にマイミクシィに登録させていただいたのが縁で、今回はこうして貴兄のデビュー作『ナショナルアンセム』のヴィデオまでお贈りいただきまして、感謝とともに深く感動しております。以下に記されることになる、若干長い文章をそのままお礼に代えさせていただければと思います。
さて、とは言って見たものの、『ナショナルアンセム』は私の想像をはるかに超えた、何とも形容しがたい作品だったと言わねばなりません。インディーズ作品と聞いた瞬間、まずはピンク、次にドキュメンタリーというジャンルを直ちに思い描いてしまう私のような通俗的な人間にしてみれば、この“不条理な恐怖に彩られた人間ドラマ”をどのように咀嚼すべきか、本来であればわざわざヴィデオまでお贈りいただいたのですから、同年代の一観客として貴兄に親しみをこめた賛辞の一つでも申し上げたいところですが、貴兄には数倍劣る一介の映画好きとしては歯痒い思いを禁じ得ません。
そのような状況でしたので、当初この文章は、監督への質問を事前にさせていただいた上で、インタビュー形式にしようかとも思っていたほどです。それが本作を理解する上で、最も有効な手段であり、貴兄への感謝足りえると思えたのですが、全く私の怠惰ゆえにそれが実現できそうにないと思い、このような形で作品を論じることになりました。その点、ご了承いただければと思います。
ところで、黒沢清氏は『ナショナルアンセム』にこのような賛辞を送っています。
彼らしい簡潔で力強い賛辞だと思いますが、実は、私の率直な感想も、ほとんどこれを超えるものではありません。恥も外聞も捨て「全くその通りだ!」とだけ叫べば、あるいは貴兄にも伝わるのかもしれませんね。しかし、それではこれまで何のためにこのブログを続けてきたのか分からないというものです。ここはやはり、無理矢理にでも貴兄に私の思うところを伝えねばならないだろう、今はそのような心境です。
そもそも『ナショナルアンセム』という題名は何を意味するのでしょうか。それを文字通り“国歌”と受け取って良いものか、監督はいかなるメタファーとしてこの言葉を選んだのか、そんなことを考えつつ観始めると、冒頭のテロップに次いで、ある口笛が聞こえてきます。それは不気味と言うほか無いなんとも陰惨な音色で、もちろん、これまでに聞いたことのない曲です。それは同時に、物語に大きく関わってくる重要な音だとも気づかせるのですが、だからといって、その口笛がそのまま“ナショナルアンセム”だったのかどうかは、今もって結論できずにいますが、一つだけ言えるのは、ラスト近くに登場する、あのぶっきらぼうに書かれたマニフェスト“宣言 我々は一人ずつが世界と戦う国家である”と深く関係しているということでしょうか。物語の最終局面で始めて登場する“国家”という言葉。国家と国歌。深読みしようと思えばいくらでも出来ますが、ここでは結論を出さず、先に進めます。
まず導入部がいいですね。状況を説明する字幕は、これから死ぬであろう男の死を予め告げてしまっています。よって、その事件自体に特に驚くわけでもなく、事実だけがただそこにある、といった感じがしました。このシーンで、あの男が車道に飛び降りて死ぬ瞬間をあえて見せなかったこと。後述しますが、本作は終始そのような展開で進んでいきます。そこから控えめなタイトルが表れるまでに、口笛に次いでもう一つの重要な音である「とおりゃんせ」が流れてきますが、あらゆる映画の、とりわけ、本作を一応便宜上“ホラー”とするなら、ホラー映画のオープニングがいかに重要かを、貴兄は流石に心得ていらっしゃる。作品全体のトーンは、ファーストシークエンスで宣言されるもので、『ナショナルアンセム』はそれに概ね成功していました。まずはその部分に驚きましたね。それどころか、実は、『ナショナルアンセム』は最後まで“驚くことばかり”でした。それはいかなる部分だったか、いくつかのレヴェルで説明したいと思います。
まず挙げられるのは、カメラの位置(構図)と動きです。
仰角と俯瞰、そして近景と遠景。フィックスとパン。そしてトラヴェリング。『ナショナルアンセム』では、こうしたカメラ技法がふんだんに盛り込まれています。とりわけ、貴兄は俯瞰とロングショットにこだわっていたように思うのですが、いかがでしょうか。
最初の殺人が起こる場面を思い出してみると、あるマンションの一室から、カメラはゆっくりゆっくりと窓に向かって進んでいきます。そして、階下の公園にいる親子を確認できたとき、すでに口笛を聞いて“感染”してしまった男が歩み寄っていく。かなりロングで見下ろされた親子は、やはり死なねばならないだろうなと瞬時に思ったのですが、案の定、男は持っていた傘で母親の頭を殴るのです。それをロングの俯瞰で見せることで齎される、あの“とぼけた”空気感。全くあれには舌を巻きました。
構図へのこだわりは全編を通して一貫していますが、際立っていたのは、独特の遠近法です。画面の奥行きを生かした演出は、特にあの姉妹に絡む場面(室内・川原・土手)で発揮されていたように思いますが、デビュー作といえど、この遠近法が生み出す効果を相当計算されたのではないでしょうか。
もちろん、昨今のジャパニーズホラーの定石ともいえるパンを最大限に生かした演出(特に風呂場で姉と思しき亡霊が妹を覗き込む場面)にも素直に驚いたと言わねばなりません。それがたとえどこかで観たような仕掛けでも、やはり恐ろしいものは恐ろしいのだという自信のようなものが伝わりました。よくぞあのシーンを、ワンシーンで撮り終えましたね。
さて、“どこかで観たような”、という話が出てきたところで、やはり本作がいかに映画史的記憶の宝庫であるかを指摘しなければならないでしょう。この1時間40分の作品内に、いったいどれ程の映画史的記憶が溢れていたことでしょう。誰もが指摘するであろう黒沢清は言うに及ばず、私が気付いた直接的・間接的引用だけでも、北野武、青山真治、中田秀夫、清水崇、鈴木清順、熊切和嘉等の曲者に加え、ジョージ・A・ロメロやトビー・フーパー、ウィリアム・フリードキン、そしてジャン=リュック・ゴダールまでもが総動員されていたように見受けられました。そして驚くべきことに、それらはある一定のトーンで制御されながら画面に顔を出しているのです。これを荒唐無稽と言わずして、なんと言いましょうか! この事実に驚愕せずにいることは、いくら一介の映画好きであるわたしにとっても不可能でした。まさに、映画史的記憶の勝利だと、他人事ながら狂喜乱舞してしまいました。とはいえ、これは私の思い込みに過ぎないかもしれませんし、貴兄としては故意に模倣したのではなく、結果として似てしまっただけだと主張されるかもしれません。しかしそれはこの際どうでもいい話です。画面に表象された映画作家たちの痕跡を観て、観客である私が幸福だったという事実以外に、ここで言うべきことはないのですから。その意味で、本作は確かに観る者を選別する作品であると言ってしまうと乱暴すぎるでしょうか。しかし、過去に誰かがいったように、あらゆる表現はやりつくされているのです。となれば後は、作家にどれだけの映画史が刻まれているか、日々産み落とされる映画作品の差は、その点にしか認められないのかもしれません。歴史を体(目)で吸収すること、常々思うのですが、新しさとは、もはやそのような地点からしか生まれないのだ、と。
閑話休題。しかしながら、私が手放しで『ナショナルアンセム』を絶賛しているかといえば、その問いかけにはいささか表情を強張らせねばなりません。本作においては、“音”に対する繊細な感性が幾分か欠けていたのではないかと思うのです。それは、画面のそれに反して、人物の会話における遠近感の欠如として端的に表れていました。そこには録音における技術的な困難さがあったのだと推測出来はするものの、やはり残念というほかありません。人物の声に関してさらに言えば、これは専ら演出に関わる事だと思いますが、およそ抑揚を欠いた発声に違和感を感じざるを得なかったのもまた事実です。仮にその演出が、ブレッソン的な禁欲主義から考案された厳しさだったとしても、私にはそこまでの強度が感じられませんでした。無論、プロの役者などほとんどいなかったのかもしれませんし、例えば、『神田川淫乱戦争』に登場していた人物だって似たようなものだったと指摘することも不可能ではありませんが、本作のようにある重要な役割を与えられた登場人物が比較的多い場合、どうしても台詞とそれを発する人物の演出に、たとえインディーズだからといって目を瞑るわけにはいきませんでした。それでも、刑事役の男性と、俳優として出演していた貴兄の演技は、決して悪くなかった思います。
さて、まさかここまで長文になろうとは思っていませんでしたが、生意気ついでにあと少しだけお付き合いください。これから述べることが、恐らく最も強く主張しておきたいことなのですから。
先にホラー映画という位置づけをさせていただいた『ナショナルアンセム』ですが、正直に言えば、この映画は全体を通した印象として、およそジャンルというものを悉く崩壊させていく画面の連鎖から成っているのではないかと思うのです。ジャンルとは、映画を観るにあたり、観客が安心するための目に見えない装置です。安心と言って悪ければ、共通認識のための装置とでも言いましょうか。それが『ナショナルアンセム』には、無い。
何かが起こり、そこにしかるべき原因が認められるとき、人はそれまでの経験と記憶を頼りに多少なりとも事件を理解した気になるのですが、目の前で起こった出来事が、ほとんど不条理な、こちらの了解をことごとく溶かしてしまうようなことである場合、人はうろたえるでしょう。
これを映画に転化させて考えれば、これは人を怖がらせる映画だろうとか、人を笑わせる映画だろうとか、あるいは、人に緊張感を強いる映画だろうとかいう、ジャンルに基づいた思考回路は、そのどれでもない作品を観たとき、うろたえるしかないのです。少なくとも、私はうろたえました。たとえそこに多くの映画作品を読み取ったところで、こちらの思いはいちいちずらされていく。それは一歩間違えば、観客によって“失敗作”という烙印を押されかねず、“下手糞!”という野次と共に記憶から消えていく運命にもなりかねない、危険な賭けです。しかし、『ナショナルアンセム』はどのようにしてか、それを免れていると思いました。では、いかにしてそのような事態を免れているのか。
『ナショナルアンセム』に認められる最も顕著な特徴、それは“決定的瞬間の廃棄”と“超現実主義的描写”の微妙なバランス感覚です。尋常ならざる事態が着実に世界を蝕んでいくという切羽詰った状況にもかかわらず、確実なことが何一つ描かれない。だからと言って、確実なことなど何も無いのだ、という強い意思すらも感じられません。ただ“ある”かただ“無い”のどちらかなのです。それぞれの描写はある行為が完結する前に唐突に断ち切られ、観客が理解しようとするギリギリのところで流産する。そこにあるべきショットが無く、変わりにありえないショットが挿入されたりもする。しかし、ショット同士の繋ぎは高度で、説話自体が破綻しているわけでは決してない。まったく、こう書いていても、自分で何を書いているのか分からなくなってくる程です。
観客が、これまでの経験と記憶から、そうあってほしいと願い予想しうるショットなど一切無いと言えます。しかし、それを観ている以上、何かを想像せずに観る事など出来ない。この堂々巡りの内に、しかし、物語は唐突に終焉へと向かうのです。ラスト20分のあんな展開など、一体誰が予想しえたでしょうか。もはや、死んだはずの人間が生きていたところで驚きはしない地点に、観客はワープさせられるのです。看護婦がバイオリンにあわせ、カメラの前で一心不乱に踊り狂う様を見たところで、それを出鱈目だと断罪出来る健全な思考など、もう残ってはいないのです。暴力は暴力にあらず。死もまた死にあらず。愛もまた愛にあらず。何かがあるが、何もない。これ以上荒唐無稽な映画に、私は果たして、出会ったことがあったでしょうか。
ここで前言を覆さねばなりません。『ナショナルアンセム』は、危険な賭けに負けることを免れているというより、勝敗とは別の場所に位置しながら、観客を挑発しているのです。その挑発に乗ったが最後、貴兄は誰よりも不適な笑みを浮かべながら、口笛を吹くことでしょう。その音色こそが、『ナショナルアンセム』なのです。
以上、果たしてお礼の言葉足りえたかどうかわかりませんが、未熟な文章力ゆえ、大目に見ていただければと思います。『おちょんちゃんの愛と冒険と革命』の東京での上映、楽しみにしております。監督の舞台挨拶はともかくとして、その機会に何とかお会いできれば、それに勝る喜びはありません。
2005.4.18
[M]
満足の6本(ソダーバーグを除く)
先週末は2日間で6本の映画を鑑賞しました。内2本はヴィデオでの鑑賞でしたが、ここ最近のペースを考えればかなり充実した週末だったと。たかだか6本観ただけで、ほとんど無条件にいい週末になってしまうのですから、我ながらその単細胞さを自覚してしまいますが。
すでに土曜日の記事にも書きましたが、16日は『コースト・ガード』、『フライト・オブ・フェニックス』、そして帰宅後『飛べ!フェニックス』を。17日は『愛の神、エロス』、『コンスタンティン』、そして帰宅後『インファナル・アフェアII 無間序曲』を鑑賞。それぞれに何点か言いたいことはあるのですが、中でも異質なものとして私の目に映ったのが『愛の神、エロス』のなかの一篇「ペンローズの悩み」で、あまりの退屈さにそのほとんどを居眠りしてしまうほど。なんとなくではありますが、かねがね私とソダーバーグは合わないのではないかと思っていたので、『オーシャンズ12』も予め避けたくらいでしたが、ここに来てその思いは固まりました。やはり、私はソダーバーグに魅力を感じない、と。それでも『愛の神、エロス』の他ニ篇に関しては概ね満足出来たので、2:1で70点くらいの評価でしょうか。まぁこの点数にいかなる信憑性もありませんが。
ところで、4月10日付観客動員(興行通信社調べ 2005年4月9日・4月10日)によれば、『フライト・オブ・フェニックス』は公開一週目で9位に位置づけているのですが、私が観た新宿東亜興行チェーン(新宿グランドオデヲン?)の客入りはほとんど惨憺たるもので、『フライト・オブ・フェニックス』はあのように大きな劇場での公開こそ相応しいとは言うものの、ガラガラの客席にまばらな中年男性ばかりが目立ち、今どき入れ替え制をとらない昔ながらの興行形態なので、前の回からずうっと眠りっぱなしのスーツ姿の男性サラリーマンを横目に観なければならないのは何とも不健康だし、この不幸な『フライト・オブ・フェニックス』が本当に第9位だという数字が全く信じられず、きっと今週水曜日に更新される段階になれば、もともとそんなもの存在しなかったかのようにベスト10からは消滅してしまうんだろうな、と。それほど大した出来ではないこのリメイク映画ですが、しかし、ロバート・アルドリッチの息子であるウィリアム・アルドリッチが制作しているからという理由だけで何とかそこに美点を見つけようとしている私は、細かい欠点を挙げればいくらでも挙げられそうな『フライト・オブ・フェニックス』を貶す気には到底なれないのです。このあまりにも悲しい状況に直面してしまうと、いまや“反スティーブン・ソダーバーグ”を標榜している私にしてみれば、一度も観てはいませんが、『オーシャンズ12』などよりも『フライト・オブ・フェニックス』の方がよっぽど貴重な映画だと故の無い断言をしたくもなります。アメリカ映画を愛する皆様、『飛べ!フェニックス』よりは劣るものの、『フライト・オブ・フェニックス』のように面白く貴重な映画をどうかお見逃しなきよう。
『コンスタンティン』に関しては、実は『マトリックス』以上の荒唐無稽さを期待していた部分もありましたが、意外にも普通に観られてしまうあたり、こちらの期待が大きすぎたということでしょうか。ただし、これまでその存在は多少気になっていたものの、その出演作から考えても、実は好きな女優だと言うことを隠していたレイチェル・ワイズを、今後は大っぴらに「好きだ!」と言う事にしようと決意させてくれた点には感謝しなければなりません。キアヌ・リーブスとのラブシーンが1シーンもなかったことは、個人的にかなり評価できます。もしラストにキスシーンなどあろうものなら、腹に据えかねる作品に堕していただろうと思います。もちろん、それはあくまで映画的な話で、レイチェル・ワイズへの偏愛とは何の関係もありません。
最後に『インファナル・アフェアII 無間序曲』ですが、人が死ぬ瞬間に訪れる一瞬の静けさは、もしかすると『ゴッド・ファーザー』よりも上手いかもしれない、と。とりあえず今週末に『インファナル・アフェアIII 終極無間』は必見です。蛇足ですが、エリック・ツァンは私が子供の時に観た『大福星』の時から声の高さが全く変わっておらず、にもかかわらずマフィアのボスとしての鋭い表情にはそれなりに凄みがあって、彼はいいなぁ、とひたすら思い続けました。
2005年04月16日
「韓流シネマフェスティヴァル」に渦巻く熱狂を間近に見る
メディアを通して目にしてきた“韓流”という言葉、“流”という文字が示すとおり、一過性の“流行語”に過ぎないとはいえ、およそ今問題視されている日韓の政治情勢などとは無縁に、その言葉が日々大量消費される様がいやでも飛び込んでくるという状況は、個人的にはあまり楽観出来ないものの、それらはあくまでテレヴィや雑誌の中で繰り広げられる虚構だと思い込もうとしていた部分も大きかったのですが、本日朝から駆けつけるに到った「韓流シネマフェスティヴァル」において、その虚構は紛れも無い“現実”として、決して広くは無い劇場全体を包み込んでいました。いや、この異常なまでの韓国ブームのおかげで日本で観る事が困難だった作品が上映され、現実にその恩恵を授かってきた私の立場からすれば、図らずもその中にキム・ギドクの未公開作品が2つも紛れ込んでいるこのような映画祭自体には感謝せねばならず、やはりここはこれまでの姿勢を改め、その“強い流れ”の只中へ身を投じるくらいの覚悟は必要だとも思われ、こうして土曜日の朝から歌舞伎町に足を運んだのです。
開場10分前に滑り込むと、午前9時過ぎという時間帯にも関わらず劇場内は予想以上の観客が。しかもその観客の9割は、テレヴィの中で「○○様〜!!」と黄土色の声を上げ、空港で感激のあまり泣き出したり、あまりのショックに卒倒したりしてきたあのご婦人方で占められているかのようでした。これに似た光景は、渋谷にあるル・シネマで時折かかる、“文化的な香り”を漂わせた作品周辺にやはり観られるのですが、これまでル・シネマで幾度かそのような光景を観てきた私でも、本日体験したあの異様な光景には、少なからぬ衝撃を受けました。ましてや、いくら韓国四天王の一人であるチャン・ドンゴンが主演しているとはいえ、キム・ギドク監督の作品であったという事実が、その驚きに拍車をかけたのです。毎週劇場に足を運んでいるとはいえ、頻度から言えば渋谷のミニシアターが多く、いきおい、あのような光景に出くわすこと自体がほとんど無かったのですから。と思って記憶を辿っていたら、過去にも一度だけありました。渋谷にしては普段から中高年の姿を目にし易いユーロ・スペースで後悔された『ルーヴル美術館の〜』を観ようとしたときです。ただしあの映画には、ル・シネマの場合とそう変わらないであろう原因が認められましたし、やはり今回のパターンとは違うものです。
ところで、劇場での彼女たちを観察してみると、多くは友人と連れ立って観に来ている普通の女性たちなのですが、何故か携帯電話を手に興奮した面持ちで話している人々が目に付き始め、その携帯には何が映っているだろうかと興味本位で覗き込むと、それらはチャン・ドンゴンの待ちうけ画面や実際に空港で撮ったであろうスナップショットの類で、つまり彼女たちは、全員とは言えないにしても、やはり私がこれまでテレヴィで目にしてきた女性たちに他ならなかったのだと改めて納得し、だからこそ、決して趣味が良いとは言えないチャン・ドンゴンやイ・ビョンホンのポートレイトが印刷されたキーホルダーをバッグに装着しているのを見ても決して溜息を漏らさず、彼女たちのおかげで私も本日『コースト・ガード』が観られるのだと自分に言い聞かせました。パンフレットや関連書籍の売り場には結構な人だかりもあり、私も後15歳年齢を重ねてもなお、あのように映画作品に熱狂できる人間でいたいものだと、遠い未来に思いをはせるくらいの冷静さは保てていたようです。
ちなみに、5月にももう一度、この映画祭に足を運びます。本日同様キム・ギドク作品ですが、四天王が出演していない『受取人不明』に、果たして本日と同じ光景を見ることが出来るのかどうか、それをみるのもまた一興です。
2005年04月14日
必見備忘録 4月編 改訂版
前回記した備忘録は、読み返すと余りにもアナが多く、いささかも“控えめなラインナップ”ではないという事実に気づいてしまったので、ここに改訂版として必見作品を再度リスト化してみます。
■『バッド・エデュケーション』[上映中]
(テアトルタイムズスクエア 11:05/13:40/16:15/18:50/21:15〜23:00)
■『海を飛ぶ夢 』[4/16〜]
(新宿武蔵野館 11:20/13:50/16:20/18:50〜21:05)
■『コンスタンティン』[4/16〜]
(渋谷ピカデリー 11:00/13:40/16:20/19:00〜21:15)
■『愛の神、エロス』[4/16〜]
(ル・シネマ 11:00/13:30/16:00/19:00〜21:05)
■『インファナル・アフェアIII』[4/16〜]
(渋谷東急 11:00/13:35/16:10/18:45〜21:00)
■『フライト・オブ・フェニックス』[上映中]
(新宿東亜興行チェーン 11:20/13:45/16:10/18:35〜20:45)
・・・随分とあるじゃないか!
今月中に全てを鑑賞するのは不可能に近いです。
16日はシネマスクエアとうきゅうにて朝から『コースト・ガード』を鑑賞するので、そのついでに渋谷では公開しない映画を観てしまおうかと。ただし、時間的に3本観られれば奇跡、といったところ。
『バッド・エデュケーション』はすでに5回以上予告編を観ていますが、まずはずすことは無いだろうと。
やはりスペインの『海を飛ぶ夢 』は、アメナーバルですから50/50といったところ。ただ今回はその物語にかなり興味を惹かれております。
『コンスタンティン』に関しては、これを観ずに映画ブログなど運営できまいといった確信から。
『愛の神、エロス』は前回のヴェネツィア映画祭から注目したいたので。目当ては、久方ぶりのアントニオーニです。
『インファナル・アフェアIII』はテレヴィCMでも予告しているようですね。まぁ『インファナル・アフェア』を観ておいて、これを観ない理由はない、といった感じで。
『フライト・オブ・フェニックス』はもちろん、逆説的にロバート・アルドリッチの偉大さを確認するためですが、この手の痛快なアメリカ映画は健康にも良いので定期的に観ておかないといけませんから。
というわけで、次第に映画館とジム以外のあらゆる場所から遠ざかりつつある[M]でした。
2005年04月11日
回避的な桜
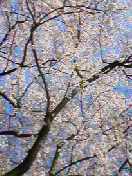 昨日の風と本日の雨により、東京の桜も大分散ってしまったでしょう。今年はそうなってしまう前に花見が出来たので、私としてはかなり満足していますが。
昨日の風と本日の雨により、東京の桜も大分散ってしまったでしょう。今年はそうなってしまう前に花見が出来たので、私としてはかなり満足していますが。
先日告白したように、昨年のこの時期は骨折による肉体的・精神的疲労でとても花見どころではなかったのですが、今年はどうしても花見をしたいと思っておりました。だからと言って私は毎年花見を欠かさない程、四季の移り変わりを愛でる感性も意欲も実はありません。では、何故急遽花見を思い立ったのかと言えば、『サイドウェイ』を観てしまったからに他なりません。4人がワインを飲みながら談笑するあのピクニックシーンがどうにも頭から離れず、時期的なタイミングもあってそれを実践してみたと、まぁこういうわけです。
前日の金曜夜にng氏と代々木公園で待ち合わせ場所を取っておいたのですが、これが思った以上に大正解で、そのポジショニング全く持って完璧。当日の天気も上々で、我々男性3人は、女性陣よりもはるかにテンションが高く、いきおい、酒のペースもかなり速かったように思います。まぁ実際の代々木公園は、どこを見渡しても人・人・人で、『サイドウェイ』のあの光景には及ぶべくもありませんでしたが、それでも普段、休日といえば朝から劇場に行ってしまうような私にとって、ことのほか新鮮な体験であったのは間違いなく、また来年も是非実現させたいと思っているほどです。
さて、土曜日はそういうわけで映画を観られず、先週は昨日鑑賞した『アビエイター』一本だけでした。渋谷TOEI2という劇場での鑑賞でしたが、何を間違えたのか、最初に駆けつけたのは渋谷東急で、比較的余裕をもって家を出たにもかかわらず、最終的には小走りで引き返したり。渋谷TOEI2は比較的大きな劇場ですので、50人強といった客入りも相対的に見れば、決して“入っている”とは言えない感じでした。
3時間弱の上映時間に関してはとりわけ退屈することなく鑑賞出来ました。仮にもう2つ程エピソードが追加され、4時間になっていたとしても、例えばRKO買収やハワード・ホークスとのいさかい等、こちらの興味をくすぐる内容であれば充分耐えられたとは思います。『アビエイター』は、その名のごとく、“飛行機狂”としてのハワード・ヒューズという側面に光があてられていたので、映画制作に関する描写がそれほどありませんでしたね。後半の多くは、彼の強迫神経症と潔癖症の症状が執拗に描かれていましたが、今回のレオナルド・ディカプリオはこれまで以上に相当力が入っていて、狂気の体現者としての彼の演出は流石といった感じ。そのメイクも含め、特に文句のつけようがありません。時間はかかるかもしれませんが、別途作品豹を書くことになろうかと。
週末に書き上げられなかった文章は、今週断続的に更新していく予定です。
2005年04月08日
如何にして書くか、ということ
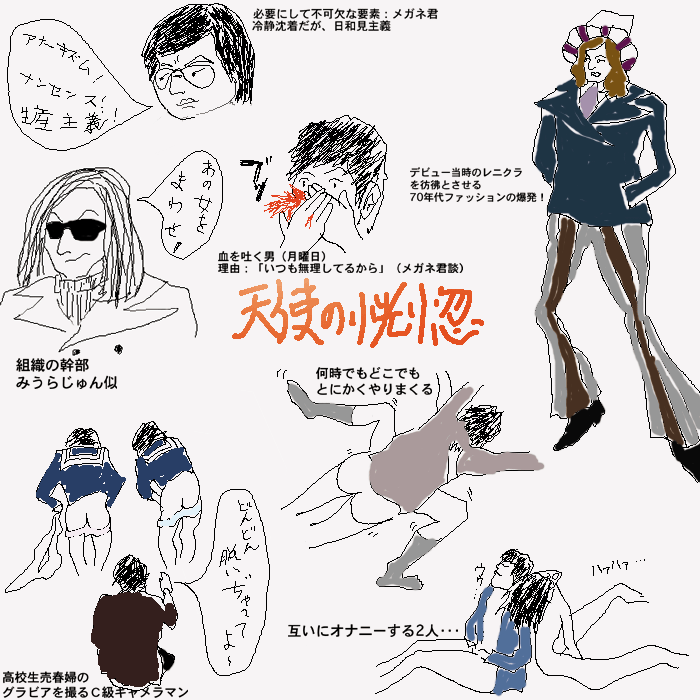
このサイトを始めて、もうそろそろ一年が経とうとしておりますが、知らず知らずの内に、ざっと182本の文章を書いたことになります。だから何だ、というお話なのですが、その中で一定数を占める映画作品のテクストを書くに当たっては、如何にして書こうかと、これでも頭を悩ませています。所謂普通のレビュー形式、対話形式、そして先日新しく導入した手紙形式と、いくらかでも工夫しつつ映画作品を絶賛してみたり、首をひねってみたりしてきました。
一体何人くらいが読むのかわからない上に、そのような小細工が果たして有効なものかも一向にわからないまま文章を書き続けるのはそれなりに骨が折れる作業なのですが、そうすることで多少なりとも発見に繋がったり、自分というものを見つめなおしたり出来るわけで、さらに言えば、コメントやTBにより生まれるコミュニケーションにもそれなりの意味を見出しつつあり、だからこそ、読まれるための工夫みたいなものは、日々考えていきたいと思うのです。
人に映画作品を薦めるという行為自体が、実は好きなのかもしれません。
まだ自分のサイトを持っていない時期から、いい作品に出会ったりすると、図々しくリコメンドしたりしてきたので、当ブログも半分はその延長線上にあるのかもしれません。
いずれにせよ、今後も新たなスタイルを模索していきたいと思います。
皆さんは映画レビューにどのような形式を求めているのでしょうか? ご意見などお聞かせいただければと思います。
(画像はクリックで拡大します。これは数年前に友人に宛てたものですが、PC内に残っていたので、なんとなく公開してみます。まぁこれも一つのスタイル、というわけで。)
2005年04月06日
時効につき、告白します
実は昨日、会社のお花見がありました。といっても、新入社員が場所取りに借り出されたりするような戸外のお花見ではなく、社食を開放し、社内から桜を愛でるというもの。ただし、もう何年も参加しているにもかかわらず、桜などまともに観た例ががありません。食事もろくにとらず、ひたすら飲むのです。ガブガブ・・・ガブガブ、と。
あの悲惨極まりない日から、丸一年が経過しました。
そろそろ時効かなと思いますので、今日は昨年の今頃わが身に降りかかった不幸を記しておきたいと思います。そう、あれはちょうど社内のお花見が元凶だったのです……
まぁ端的に言うとですね、泥酔したわけです。社内で。
ちょうど夕方6時頃から飲み始め、ジョッキでモエ・エ・シャンドンを数杯飲みながら談笑。まだ仕事が残っていたので、軽く飲んで退散するつもりでした。が、赤ワインと白ワインを交互に何杯も何杯も飲んでいるうちに、というより、もうこの時点で仕事のことは完全に頭から消え去っていて、そこが仮にも会社内であることもあっさりと忘れ、つまり、“どうにも止まらない”私がいたのです。
3時間ほど飲んだ後自席に戻り、すぐさま2軒目へと移動することになるのですが、この辺りを境に、私の記憶はほとんどありません。先輩と飲みに行ったことと、飲んだ店だけはなんとなく覚えているのですが、約5時間程の記憶がまるまる喪失しています。さて、悲惨なのはいよいよここからです。
2軒目を出て少し経った後、気が付いたら自宅の鍵がありません。すでに深夜1時を回っているので、管理人さんを起こすわけにも行かず、はたと困りました。しかしその後、どのような思考が働いたのかは思い出せず、多分、どこかで朝まで時間でも潰そうと思ったのでしょう。で、バッグをまさぐると何も入っていないのです。所謂“すっからかん”というヤツです。頭の中は“???”、と同時に、これは非常に不味い事態だな、と本人は思ったはずです。金も鍵も、そして生命線とも言える携帯電話すら無いのですから。
別にショックで気を失っていたわけでは無いと思うのですが、恐らくしばらく途方にくれた状態だったのでしょう、次に気づいた時私は、何故だか自宅マンションの2.5mくらいはあるであろう塀の上によじ登った状態でした。私の自宅はオートロックで、鍵がなければもちろん、敷地内にも入ることができません。だから、塀をよじ登ったのだと思うのですが、ここが泥酔者の思考がショートしている所以、仮に塀を越えたところで、玄関にはやはり鍵がかかっているのは自明であるにもかかわらず、私は果敢にも、その塀から飛び降りた、というより、頭からダイブしたのです。窪塚洋介氏がやはりマンションの9Fからダイブした事件が昨年6月ですから、約2ヶ月程彼の行動を先取りしていたことになりますが、まぁそれはともかくとして、マンションの9Fとはいかないまでも、2.5mの高さからダイブすればそれなりの対価を支払わねばならないことくらいは私でもわかっていたはずなのですが……我を失うことの怖さというものを改めて思い知りました。
ではダイブ後の私の状態を振り返ってみます。
ちょうど鼻の付け根あたりから落ちたわけですが、とっさに両手を付いたのが幸いし、急所に程近い部分を強打したにも関わらず大事には至らなかったのだと思います。が、相当量の出血があったのもまた事実。瞬く間に地面が赤黒く染まっていきました。そして、そのショックでようやく我に返ったのです。全身の感覚は酒のせいで大分麻痺しているので、痛みはそれほど感じませんでしたが、自らの流血に慣れていない私は、軽い目眩に襲われつつも、何とか自宅玄関までたどり着いたのです。しかし先述したように、もちろん家の中には入れません。鍵がないのですから。その代わりと言っては何ですが、玄関先にはビニール袋に入った苺3パックが、誰かに踏み潰されたようにグチャグチャに変形した状態で置かれていて、それだけでも不可解なのに、あろうことか無くしたはずの携帯電話がグチャグチャの苺に突き刺さったまま、いかにもその最期とばかりに悲しげな様相を呈していたのです。無論、携帯電話の電源は入らず、苺の汁が直接の契機となって没しました。例えば、フィルム・ノワールなどで、殺し屋がターゲットに対し、「お前は狙われているんだぞ」というメッセージをこめた不快なプレゼントとも言うべき贈り物を届けることが間々あります。動物の死骸だとか、腐った食べ物だとか。そんなシーンをイメージしていただければ、その当時の私の心境をご理解いただけるかもしれません。あまりにも不可解な、しかし当然ながら、全ては私自身による行動の結果。ここで再度、諦めの深いため息とともに途方にくれました。ともあれ、この辺りの一連の行動につきましては、詳述できないと言うのが正直なところです。思い出せないのですから。
ようやく出血が収まりかけ、次第に正常な意識を取り戻しつつあった私は、とにかく誰かに連絡を取り、泊めてもらおうと考えました。もう疲れ果てていたので、とにかく寝たかったのでしょう。しかし、強烈な苺臭を放つ携帯電話は、ただのオブジェと化しています。そこで私は、近くにある当時行きつけだったレストランバーに行くことになります。事情を説明した上で電話を借り、当時は自宅からタクシーでワンメーターの場所に住んでいた友人で、最近このブログにも顔を出してくれているng氏の家に泊めてもらおうと考えたのです。実はこんなこともあろうかと(?)、ng氏の電話番号だけは暗記していたのでした。我ながら、その先見性には驚くばかりです。
レストランバーに足を踏み入れた瞬間の、凍りついたバーテンダーの表情は今でもよく覚えています。開口一番、「…喧嘩ですか……?」と恐る恐る尋ねる彼に、「いや、ちょっと高いところから落ちちゃいまして…」とはにかみながら答える私。はにかみついでに、「すみませんが、電話をお借りしたいのですが。携帯電話が壊れてしまったもので」と懇願してみると、私よりも焦燥を隠しきれない彼は、「とにかく血を洗い流してください!」と洗面所に促してくれました。
血だらけの顔を洗い、服に付いた血を拭いていると、ジャケットの胸ポケットに何故かクレジットカードが一枚だけ入っていることに気づきました。何故そんなことが…、ということはもはや考えずに、とりあえずこれで何とかなると、多少自信を取り戻した私は、洗面所を出るなり、「ただで電話を借りるのもあれなので、一杯だけワインをください」などと、相応しからぬ余裕を見せつつ、電話を借りることにたいする罪悪感を消そうとしたのです。もちろん、そんな状態の私に「本当に飲んで大丈夫ですか?」と尋ねるのは至極当然のことですが、私はとにかく、事態を平穏にやり過ごすことしか眼中になかったので「大丈夫です、もう血は止まっていますから」と、さらなる余裕を見せました。その後電話を借り、これ見よがしにカードで一杯分の精算をすると、逃げるように店を出てタクシーを拾い行き先を告げるのですが、やはり私はまだ正気ではなかったのでしょう、本来ならワンメーターで到着するはずの距離にもかかわらず、約20分ほどあーでもないこーでもないと運転手を困らせ、終いには「もうここで結構です」と、未だng氏の家まではかなりの距離がある地点でタクシーを降り、ふらふらしながら渋谷区神山町を徘徊することになります。すると10分ほど歩いたところで、遠くからng氏が自転車で近づいてくるのがわかり、ようやく全身の力が抜けました。古くからの友人であるはずの彼が、その時ばかりは間違いなく“神”として私の目には映ったのは言うまでもありません。
ng氏宅でウーロン茶を飲みながら事態を説明した後は泥のように眠るのですが、翌朝起きてみると、昨日の時点では感じなかった痛みが全身を貫きました。とりわけ、右手が全く動きません。しかし、その日はウィークデーだったので、いつもどおり出社しなければならず、無理やりシャワーを浴び、ng氏には「今財布に入っている有り金を全部貸してくれ」と、全くもって図々しさの極みとも言うべきお願いをするのですが、こちらの言うとおりに金を差し出すng氏を見て、やはり持つべきものは(泥酔して怪我した挙げ句全ての持ち物を紛失した時に助けてくれる)親友だなと確信し、その時ばかりはng氏に最大限の感謝をした次第です。
こうして書いてみると、随分といろいろあったナァ・・・と感慨もひとしおですが、最後に実害を総括しておきますと、結局右手の骨は骨折していて、全治2ヶ月の重傷。鼻の頭には1cm近い陥没が出来、こちらの傷跡は未だ顔の中心部分に残っています。現金20000円、カード類、免許証、財布は見つからず、先述したように携帯電話は壊れました。何と言いますか、言葉もありません。
全ての傷が完治し、その後十分な反省期間を経たので、不安要素だった昨日のお花見からも無事帰還しました。もうあれほど酔う事はなかろうと思いますが、やはり暴走する時は自分ではなかなか制止出来ないこともあるやもしれません。この文章を読んでいる友人・知人の方々、どうか私めを見捨てないでやってください。加えて、皆様くれぐれもご自愛くださいませ。
映画とは関係ない話を、長々と失礼しました。
ただ、この事件の2ヵ月後に当サイトをオープンすることになったことを鑑みるに、私の反省とサイトオープンの間に何らかの関係性があるのではないか、だとすれば、それはそれで結果的には悪くなかったのではないかと、あるいはそのように思ってしまうこともまた否定できないのです。まぁわざわざこうして記録に残したわけですから、今後はこの文章を読み返すことで、自らを戒めていければと思っております。
『サイドウェイ』を観て自覚したある種の思いを…
 M・S様
M・S様
ご無沙汰しております。桜の季節になりましたが、飲みすぎて体を壊してなどいませんでしょうか? つい我を忘れてしまいがちなところがある貴兄が、いつまた大怪我してしまうかもしれないと、時折心配になります。くれぐれも酒にはご注意ください。
さて、なんだか説教じみた文句から始めてしまいましたが、別にそういうつもりはないのです。もちろん私がわざわざこのような便りを出すのですから、その内容は映画に関する以外はありません。実は、貴兄に是非とも観ていただきたい作品がありまして、おせっかいながらこうしてご連絡させていただきました。
映画好きの貴兄ですから、アレクサンダー・ペインという監督はご存知のことと思います。かつて“『アバウト・シュミット』を見逃した”などとおっしゃっていたような気がするので、あるいはすでに注目されている監督なのかもしれません。
ともあれ、彼の新作『サイドウェイ』をお台場シネマ・メディアージュにて鑑賞しました。その数日後、今度は六本木ヒルズ内のTOHO CINEMAにて再度鑑賞し、誰に頼まれたわけでもありませんが、本作を会う人ごとに語気を強めて薦めるという、ほとんどテロみたいなことをしておりまして、この便りもその一環というわけです。
もちろん、本作がオスカーを受賞したとか、とりわけアメリカの批評家連中に絶賛されているからといった要因がそうさせているのではありません。貴兄が再三にわたって言っているように、それらは、未だに映画宣伝に良く用いられる「今年一番の傑作! (ニューズウィーク誌)」のような、空疎で陳腐な情報よりはいくらか興奮させられるものの、取り立てて喧伝する程の価値がないことを知っているからです。もちろん、シネフィルでもない私が騒ぎ立てているからといって、その作品に絶対的価値があるなどという錯覚は自粛しているつもりですので、以下の言葉は、親しい友人の戯言として軽く聞き流していただければ良いのですが。
それにしてもこの『サイドウェイ』の公開規模はあまりに地味だと言うほかありません。最近池袋での上映が始まったようですが、少なくとも『ロング・エンゲージメント』などよりは10倍は面白く、貴重な作品にもかかわらずです!! ただし、あまり派手に公開すべき作品ではないような気がしないでもなく、やはり、このくらいひっそりと公開されている方が相応しいのかもしれません。
さて、世間での『サイドウェイ』は、スター不在の地味な映画だけれど脚本の素晴らしさがそれを補っている、とか、ワインの熟成を味わうようにじっくりと味わいたい大人の映画だ、などといわれているようです。それらに対し特に異存は無いものの、私はとにかくこのように結論したいと思います。『サイドウェイ』は端的に言って滅法“面白い”アメリカ映画だ、と。
ここでいう“面白い”という言葉、これほど曖昧な言葉もまた無いのですが、今回はあえてこの凡庸な言葉を選びたいと思います。それは映画の感想としては最も稚拙で回避的なのアティテュードだと、貴兄はおっしゃるかもしれません。そうでなければ、この映画のいかなる細部が感動的だったのか、それを言ってみろとお思いにもなるでしょう。そして実際にその通りかもしれません。
ところで、『サイドウェイ』の原題は「Sideways」ですが、何故邦題が「サイドウェイズ」とならなかったのかお分かりですか? もちろん、観ていない貴兄にはわかりかねると思いますが、実は私にもわかりません。そこに重要な意味など無いことだけは何となく分かりますが。では、原題の「Sideways」とはどのような意味か。ごく一般には“寄り道”と訳されるようです。しかし、このタイトルに見られるように複数形で用いる場合、“遠回りの”や“回避的な”という意味としても用いられるのです。と、ここまで書けば、先に記した私の“回避的な言葉”が、本作を意識したものであることはお分かりいただけますか。いや、本当は全くの嘘で、ただの偶然に過ぎないのですが……
まぁ聞いてください。
そもそも貴兄は映画に何を求めていますか? 何を唐突に、と思われるでしょうが、私は『サイドウェイ』を観た上で、実は少なからず反省をしているのです。何故なら、気づいてしまったからです。このところ、自分が救いがたいほどに硬直した状態で映画を観ていたということに。ここで暴言とわかりつつもあえて言わせていただければ、仮に貴兄がこの映画を観た場合、このように思われるのではないでしょうか。私なりの見解を述べさせていただきます。
--------------------------------------------------------------------
■70年代のヨーロッパ映画的な“淡い”画面は、ある戸外の限られたシーンでは確かに悪くない効果をあげていたものの、ドライブシーンで導入される分割画面は、時間的制約が要請する小さなエピソードの省略以上の効果をあげることのない、つまり悪く言えば、新味のなさを印象付けられた。
■ワインの成熟と中年に差し掛かった人間とを重ね合わせる説話手法は、それ自体に大きな錯誤が認められないとはいえ、だからといってそのもっともらしさを称揚したい気にはなれない。
■それぞれの俳優はキャラクターの造形にかなり貢献しているが、裏を解せば、想像を大きく超えることもないまま、瞬時に視線を奪うほどの演出が見られるわけでもない。
■確かによく練られた脚本だが、アメリカの多くの批評家たちが絶賛したという外的要因なしに、果たしてこの脚本を手放しで賞賛し得たのかどうか。
■つまり、決して悪くはないし観る価値はあるが、だからと言って途方に暮れるほどの出来ではない。
--------------------------------------------------------------------
以上はあくまで私の想像の産物ですから、これを読んだ貴兄が腹を立てたとしても、それは至極当然のことですが、もう少しお付き合いください。
実際、私自身が上述したように感じもしたのですが、ここで誤解していただきたくないのは、上記のような感想を受けた上で、結局映画などただ“面白いか”“面白くないか”のどちらかに収斂されるのだ、などと暴力的な結論を出したいわけではないし、細部よりも、行間を読むがごとく、全体に流れる緩やかなメッセージをこそ捉えるべきだ、などという反動的な結論を導きたいわけでもないのです。ここで言いたいのは、映画における凡庸さが時として齎す感動にも、やはり真摯であるべきではないかということなのです。より緩やかに自らの感性を弛緩させることもまた必要なのではないか、と。これはまったく自戒を込めた独り言と捉えていただいても良いのですが、『サイドウェイ』は私に、そのようなことを気づかせてくれました。ややもすれば、映画作品に突出した細部やら、想像を超えるような斬新な演出やら、こちらの人生を狂わせ兼ねないような過剰さやらを求めたがる、恐らく初めて感じたわけではない自らの救いがたさ。この手の救いがたさは、例えば貴兄も好きな『カノン』においてフィリップ・ナオンの口から何度も繰り返される、あの“悪魔的モノローグ”のように不条理で救いがたいと、今では自覚しています。
いろいろと書いてしまいましたが、では、『サイドウェイ』のいかなる部分が“面白かった”のかは、あえて書かずにおきます。でも本作を観る上で是非とも心を解きほぐして観ていただきたいシーンだけは書かせてください。それは以下になります。
・最初のテイスティングシーン
・ワイナリーを疾走するシーン
・最初の4人の食事シーン
・事故を偽装するシーン
そういえば我々もワイナリーに行きましたね。あの時は飲酒運転で死ぬ思いでしたが、本作を観てあの時のことを思い出しました。偶然にも、最近はカリフォルニアワインばかり飲んでいるのですが、安くてもそれなりに重宝してます。
貴兄も是非、ボトル片手に『サイドウェイ』をご覧ください。
それでは、また近々。
2005年04月03日
4月はJ&Jで始まる
昨日はジムに行った後夜まで特にすることが無く、本来であれば『アビエイター』を観るつもりでしたが、何となく気分が“アビエイター向き”ではなく、“明快なアクション”を欲していたこともあり、えーいままよ、とばかりに90%は観るのを諦めていた『香港国際警察/NEWPOLICE STORY』を観にいってしまいました。
今回のジャッキーは笑いません。泣いてばかりです。画面も暗く陰惨な色調で統一されているかのようでした。バスやラーメン、クライマックスの落下など、『ポリス・ストーリー/香港国際警察』に通じる要素が見受けられはしたものの、どちらかというとアクションよりはドラマに力が入れられていたような気がします。その証拠に、今回描かれるキャラクターは、それぞれある過去を引きずっていて、それが現在に影響してくるという、過去のジャッキー映画とはやや趣が違う作品なのです。体を張った殺人的なアクションと、ギャグ。この徹底的な表面性こそが過去の香港時代のジャッキー映画の肝だったと思います。しかし本作において、監督のベニー・チャンはドラマとしての深さを求めたのだと思います。もちろんだからといって、ジャッキー他、若手俳優のアクションが“ぬるい”と言いたいのではありません。流石に命綱なしでビルから落ちて見せたりはしませんが、それでも流石香港映画と言うべき、その高低差を生かした“縦軸のアクション”はきちんと存在するのです。言わば、“大人のジャッキー映画”として、充分に楽しめる出来だと言えるでしょう。ただし、ラストの対決シーンのロケーションや構図が、『インファナル・アフェア』のクライマックスに酷似してしまった点を考えてみると、その興行的な数字はともかくとして、香港映画復活の契機となった『インファナル・アフェア』の優位は変わらないのではないか、とも思ってしまいました。いや、少なくとも、『ポリス・ストーリー/香港国際警察』を超えることは無かったと結論したいと思います。
続いて本日は正午より『コーヒー&シガレッツ』を鑑賞。これは別途レビューにしたいと思いますが、かなり私好みの映画でした。良くも悪くも、ジャームッシュの映画だと断言できます。18年間にわたるジャームッシュのサイドワークを、是非その目で確かめてください。“乾いた笑い”に滅法弱い私は、何シーンかで声に出して笑ってしまったと告白しておきます。
『サイドウェイ』のレビューは、何となくこれまでとは違った形でのレビューを書ければといろいろ考えているのですが、いい案がまったくと言っていい程見つかりません。これは、文章の質ではなく、そのスタイルに関する問題なのですが、まぁあまり凝ったことをして策におぼれてしまうと、またぞろ後輩から指摘を食らうかもしれないので、その辺は周到に避けつつ、思い浮かばなかったら、やはりこれまでどおりのレビューになろうかと思います。
2005年04月02日
『カナリア』、“期待”してしまうことの理不尽さ
原題:カナリア
上映時間:132分
監督:塩田明彦
作品間の振幅の大きさで言えば、現在の日本映画界でも特筆に価するであろう塩田明彦監督ですが、本作に関してはこちらの勝手な期待値を超えることがなかった。
ただし、それはテーマとして、あるいは撮影手法としての是枝裕和監督との類似性とは何の関係もありません。たとえ『ディスタンス』や『誰もしらない』を観ていなかったとしても、その評価は変わらなかっただろうと思うからです。
一つ一つのエピソードはほとんど言うべきところがない程、良かったと思います。西島秀俊は言うに及ばず、つぐみ、水橋研二、甲田益也子の演出は流石というべきものがありました。
しかし何故でしょう、あの重厚な主題を前にして、この満足感の欠如は。
期待が大きすぎたのでしょうか。であれば、私はこの映画に何を求めていたのか。
ほとんど故の無い幻想を抱きつつ、作品の出来とはいかなる関係もない部分で、その評価に影響を与えてしまう“期待”という抽象的存在。『カナリア』は、その理不尽とも言える問題を提起してくれたという意味で、重要な作品だったのかもしれません。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]



