2006年09月29日
とりあえず、ザケンナ!と言いたい
昨日の午後8時ごろから今朝方まで、当ブログの閲覧が出来なかったようです。
たまーに数分間見られなかったことはこれまでにもあったものの、今回の障害はこれまでで長時間に及ぶものでした。
夜、自宅にてホスティングしている会社のサポートにメールしようと思いましたが、そのサポートフォームからは何度挑戦してもエラーが出てメールもまともに送れず、何ということか!と怒りが頂点に達しようとした時、朋友ng氏がわが家に遊びに来たので、そんなことは忘れてワインをがぶ飲みしてしまいました。
ブログが閲覧できないばかりか、管理画面へのアクセスも不可能だったため、このまま全ての記事が吹っ飛んでしまったらどうしようか、などと一抹の不安がよぎりました。私は怠惰な人間ですから、記事のバックアップなどとっていないし、サーバーの障害でデータが消えてしまえば、もうこれまでの存在が無かったかのようになってしまうのは自明。何とか事なきを得ましたが、ちょっとその辺の危機管理もしていかないとまずいかな、と。ざっと450の記事が全て消えた場合、恐らくもうブログを書く気になどなれないでしょうから、これを機に、記事のバックアップをとっておきたいと思います。
映画ブログの中でも末端に位置する当ブログにアクセスできなくなっても、大した影響はないものと思い込んでいますが、一応昨日から今朝にかけてアクセスしてくださった方のために、こんな文章を書いた次第です。
このサーバーもそろそろ潮時かもしれません。。。
2006年09月28日
映画短評 2006年8月編
■『スーパーマン リターンズ』
SUPERMAN RETURNS/2006年/アメリカ/154分/ブライアン・シンガー
そもそも『スーパーマン』自体にさしたる思い入れのない私、映画版を何本か観た記憶があるものの、その物語、というか見せ場も含めてほとんど記憶になかったのですが、“あの”ブライアン・シンガーが、まず成功は約束されたであろう『X-MEN:ファイナルディシジョン』より本作を選んだと言うことで、彼自信のスーパーマンに対する思い入れは、どうやら並ならぬものだったようです。
しかし、ブライアン・シンガーは何故アメコミ原作ばかりを撮るようになってしまったのでしょう。今思えば、『パブリック・アクセス』などはなかなか楽しめ、『ユージュアル・サスペクツ』や『ゴールデンボーイ』はあまりいただけませんでした。しかし『X-メン』も『X-MEN2』も悪くなかったように思うのです。つまりこの2本で、もはや一つのジャンルと言っていい“アメコミ映画”に目覚めたということなのか。
まぁさしあたりそれはどうでもいいとして、『スーパーマン リターンズ』ですが、ほとんど知識ゼロの状態でもそれなりには楽しめました。ケヴィン・スペイシー演じるレックス・ルーサーの部下に、スーパーマンがボコボコにリンチされたりしていましたが、あの辺りの心無さは『X-MEN2』でも遺憾なく発揮されていたものであり、結構いい線いっていたんじゃないか、と思います。
でもまぁやはり長かった気もします。もっともっとスーパーマンの“超人性”を画面で見せて欲しかったような気も。もともとこのジャンルに全く思い入れのない私とはいえ、アメリカ製のアクション映画はやっぱり大好きなんです。だからこそ…という心残りがないではありません。
■『青春☆金属バッド』
2006年/日本/96分/熊切和嘉
たとえ前作にあまり乗れなかったとしても、その作品を観てしまう監督がいます。それは恐らく、その監督の潜在的な何かを信じていたりだとか、世代的な親近感を感じていたりだとか、あるいはまさにデビューの現場に立ち会っただとか、様々な理由によるのでしょうが、私にとっての熊切監督もそのような監督であると言えます。
私の場合、1997年のユーロスペースで『鬼畜大宴会』を観たときに監督を間近で観てからというもの、この自分と同じ年の監督にただならぬ才能を感じていました。こんな映画を自分と同じ年の人間が撮ってしまったことに動揺したというわけです。
しかし『鬼畜大宴会』以降、傑作と呼べる作品は一つもありませんでした。嫌いではないが、そんなに良いとも言えない、それでも出来る限り彼の新作を追うと決めたのですが、本作もまた、似たような印象ではあります。しかしもはや、彼に突出した何かを求める時期ではないのかもしれません。あまりに下らない日本映画は沢山あるのでしょうし、その中で熊切監督の作品には必ず評価できる点があるので、それで満足だと態度を改めなければいけないのかも。
やはり予備知識はほとんどゼロだったので、若松孝ニの登場には普通に驚きました。
■『ハード キャンディ』
HARD CANDY/2005年/アメリカ/103分/デヴィッド・スレイド
本作を観ようと思ったのは、“女(本作では少女)が男を襲う”という映画を久々に観たかったからです。腕力では普通男性に叶わないはずの女性が、映画では時に、男性をいたぶったり屈服させたりします。その過程、あるいはその方法が大いに気になったことと、やはり、いったいどんな女性がそのような立場足りえるのかを観たかったのです。
本作の画面はかなり独特でした。シネマスコープにもかかわらず、その多くがクローズアップで、それがまた異様な緊張感を生み出していたような。物語の多くは屋内で展開していくので、引きの絵がほとんどないのですが、では何故シネマスコープという画面サイズを選んだのか、なるほどそういう効果を狙ったのか、などと一人で納得。
主演のエレン・ペイジは当時18歳。14歳の役も無理なく演じていました。前半で子供っぽい表情を見せつつ、後半では冷酷な復讐者に変貌するという難しい役どころではありますが、長編デビュー作にしてはかなり健闘していたと思います。とりわけ、本作最大の見所である去勢シーンにおける複雑な表情は見事だと言えるでしょう。
途中形勢逆転がありつつも、結局最後は女が勝つ。『恐怖のメロディ』のように、女性が落ちていくのではなく、男性が“自ら”死なざるを得ないあたりが興味深く、結局誰が良いのか悪いのか、ほとんど判然としないまま、勝ち誇った表情のエレン・ペイジが歩いていくというラストショットも悪くなかったです。そこには、陰惨でありつつも奇妙に晴れ晴れとした雰囲気が漂い、この映画を締めくくるに相応しいショットだったのでしょう。
エレン・ペイジは『X-MEN:ファイナル ディシジョン』にも出演しているらしいので、是非観ておきたいと思います。今後、こんな役のオファーばかりが来ないことを願うばかりです。
2006年09月26日
“映画短評”復活に関して
最近、あまりに早く一週間が過ぎ去っていくので、いよいよ俺の人生も…などと嫌でも考えざるを得ませんが、私の場合、このブログはあくまで“映画を観る”という行為に比すると、大分下方に位置しているためか、週に例えば3本も映画を観てしまうと、その体験が私自信に齎す様々な恩恵(それはもちろん、プラスの場合もあれば稀にマイナスの場合もありますが)について思い巡らしているうちに、一本の記事もかけないまままた新しい週が始まってしまうという、そんな事態に陥ってしまうこともしばしばです。
つまり、映画を観ることと記事を書くことのバランスが、映画を観れば観るほど崩れていってしまうということで、まぁだったらこんなブログはやめてしまえということにもなるのでしょうが、幸いにしてか不幸にしてか、いくら駄文でもこうして文章を書くこと自体苦痛ではなく、苦痛があるとすれば、私のいかにもさもしい気持ちの存在、すなわち、何とか観ることと書くことのバランスを保ってこのブログのあるかないか分からないようなクオリティ維持しなければという思いこそが苦痛の根源であると改めて思い至った次第。
性格上、読み手のことをいささかも考えない文章など書けず、かといって映画中心の実生活上、観ることをその下位に置くわけにもいかない私にとって、ああ、もう無くしてから大分時間が経つけれど、思えば“映画短評”というカテゴリーの存在は便利だったナァ、などと過去の遺物を思い起こしてみたり。自分で作って自分で葬ったのなら、また自分で復活させればいいじゃん! ということで、今月からまた復活させます。鑑賞した全ての映画に詳細な論考を書くことはどうしたって無理だ、という私の諦念はやはり消し去ることは出来ず、元来不器用な私が今思いつく妥協案として。普段は本当にデタラメな私が、どうして映画に関してはそうなれないのか、これが不思議でしょうがないのですが、そんなことを考える暇があったら一本でも多くの映画に触れたほうが良さそうなので、早速8月以降の短評を書いていくとします。
ちなみに、先週は念願の『女獄門帖 引き裂かれた尼僧』を『盲獣』とともに鑑賞。おかげで濃い土曜日を過ごすことが出来ました。そして昨日はこれまた念願だった『鉄西区』を。9時間4分の陶酔、などと片付けてしまうのはあまりにもったいないので、本作に関しては別途どこかで触れることになるでしょう。平日にも関わらず、ポレポレ東中野がほぼ満席だったのには驚きました。本作により、私の最長鑑賞時間が更新されました。無論、帰宅後はへとへとですぐさま眠りにつきましたが、とりあえず今は凄かったとしか言えません。
2006年09月19日
今観るべき2本のアジア映画
この連休中で5本の映画を観ましたが、その内の2本の出来栄えには心底驚かされ、あまり軽々しくそう言ってしまうことには抵抗があるものの、やはり傑作と言いほかないという結論に達した次第です。そしてこれは偶然なのかどうか、その2本がいずれもアジア映画であったということ、さらに、それぞれがまるで異なる趣の映画だったということが嬉しくもありました。
もちろん、若干うとうとしてしまったので何も言う資格はないものの、『太陽』におけるユーモラスなやり取りや尋常ならざるシークエンスショットは興味深かったですし、あるいは『マッチポイント』におけるスカーレット・ヨハンソンの前半と後半のキャラクターが変貌していくあたりも悪くはなかったです。または『40歳の童貞男』における、下品さをギャグと友情と恋愛とで帳消しにしてしまう強引な展開などはいかにもアメリカ的であり、これも小品ながら観て良かったと思わせる作品ではありましたが、それにしてもやはり、前述した2つのアジア映画におけるエンターテインメント性・芸術性・作家性、どれをとっても感動的であり、私としてはこちらのほうをより賞賛したいと思っています。
さて、本来であればここでその2作品の名前を挙げたいところですが、それもあまりに芸が無さ過ぎるのではないかとも思われるので、以下ではそれぞれに思いつくいくつかの抽象的な言葉を断片的に挙げ、それらの言葉に反応した方が劇場に足を運んでいただければ。
アジア映画(1):ジャンル映画/家族/水/非情/爽快感
アジア映画(2):雨/長回し/愛/足音/詩情
最後に付け加えておくと、諸事情により溝口特集に足を運べなかったことは残念至極でした。この連休を逃すと、もう恵比寿にはいけないかもしれません。それともう一つ、『パビリオン山椒魚』の混雑は予想以上で、『ゆれる』の教訓をいささかも生かせなかった自分に呆れましたが、そのおかげで前述のアジア映画を観る事が出来たので、それはやっぱり幸運だったと言うべきでしょう。先週はせっかく「冨永昌敬特集」を観たので、次回の『パビリオン山椒魚』は是非早めに行ってチケットを確保したいと思います。
2006年09月15日
『ディセント』における2回の裏切りとは
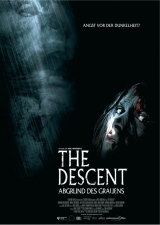 原題:THE DESCENT
原題:THE DESCENT
上映時間:99分
監督:ニール・マーシャル
ほとんど前情報を得ずに、だけれども漠たるイメージだけは抱きつつこの映画を観ました。
本作が2005年のブリティッシュ・インディペンデント映画賞で作品賞と監督賞を受賞したらしい、というのも観た後に知ったのですが、なるほど、100分以内でとまとめられている割には見せ場も多く、そのほとんどがセオリー通りの恐がらせ方とはいえ、悪くない残酷ショットがあったりして、こういうのを“拾い物”と言うんだろうな、などと思った次第。
観ようと決めたのはチラシを目にしたからだと思いますが、その時は、数人の女性が洞窟に閉じ込められて互いに疑心暗鬼になり、結局人間が一番恐いという、言ってみればありがちな恐怖映画だと思い込んでいました。ありがちな、などと書きましたが、そういう映画は嫌いではなく、安易に未知の生命体を登場させたりするくらいなら人間同士で殺しあってくれたほうが面白いとも思うので、実は結構期待していたわけです。
冒頭のシークエンスで、車のフロントガラスに対向車の積んでいた鉄柱みたいなものが突き刺さるシーンがあります。これが本作における最初の死ですが、まぁこれは事故であって殺人ではありません。しかし、子供の残酷な死という、映画ではその倫理的視点から容易には描けないものを、その残酷さを直接的には見せずに、しかしやはりどう見ても子供は残酷に死んだ、という事実を画面に登場させるこのシーンは非常に短いカットながら悪くないなと思い、いよいよ期待も高まっていきました。
さて、事故のショックからなかなか立ち直れない主人公の女性を見かねてか、彼女の友人達は事故から1年後、みんなで冒険旅行をして何とか元気付けようと画策します。そして問題の洞窟に入っていくわけです。まぁそれほど無理の無い展開でしょう。主人公にとって初対面の女性も含まれるその一行が、出発前に顔合わせをしますが、こういうシーンは結構重要で、ここでそれぞれのキャラクターを観客にわからせておかないとその後に生まれるであろう恐怖に説得力がなくなってしまうからです。
では洞窟に入った6人の女性にいかなる恐怖が襲い掛かるのか。普通に考えれば迷って出口を見失ったり、足場が崩れ落ちたり、装備品をなくしたり、まぁその手のトラブルが原因でみんながパニックに陥る、みたいなことを想像するでしょう。私もまさにそんな展開を予想しつつ、中盤までは普通に楽しんでいました。
しかし、大体40〜50分を過ぎた辺りからでしょうか、なにやら怪しげな生命体の存在が明らかになってきます。そしてその生命体が、唐突に画面に登場した瞬間、私のテンションは一気に下がってしまいました。なんだよ、そんな展開かよ…と。限りなく人間に近いそのクリーチャーは、例えれば山海塾のように全身白塗りで、壁を登ったり天井に張り付いたりと虫の様な俊敏性を持っており、その動き自体はそれほど悪くないのですが、そんなことで一度下がったこちらのテンションは一向に上がってきてはくれません。まだ期待できる部分があるとするなら、それは彼らがいかに残虐に女性達を殺すのか、あるいは殺されるのか、そしてもう一つは、女性同士が裏切りあい殺しあう可能性です。
クリーチャーの生態にそれほど新味はなく、目が見えない代わりに音に敏感という生態は、接近した時のサスペンスを盛り上げるためのものだと思うのですが、面白いのは彼らの数。それがいったいどれほど存在するのかが次第に明らかになり、遂には大軍に囲まれるというあたりでしょうか。
6人いた女性はクリーチャーに喰われたり、ほとんど自滅したりしながら減っていきますが、ここからの展開でこのニール・マーシャルという監督は魅せてくれました。ある一人の裏切り者の存在を描くことで、主人公の女性はクリーチャーとその裏切り者に対する怒りを徐々に爆発させていく。夫と息子を同時に失い、失意に暮れていた彼女の顔も動きも、今ではまるで別人のように逞しく変貌しています。彼女がクリーチャーを容赦なく殺していく過程も悪くなく、遂に裏切り者を追いつめたとき、彼女がとった行動は、非常に胸のすくものでした。ほとんど心無さを感じてしまうほどに、その裏切りの代償は大きかったのです。一人の主人公を、ここまで大胆に変貌させてしまったあたりは素直に楽しめ、このまま洞窟から脱出、逃げてはいおしまい、という結末でもよかったように思えます。
しかし、です。
ラストシーンの、あの夢幻的な画面。つまり主人公のトラウマめいたものが、やっと溶解していくというシーンなのですが、途中でも挟まれるこういったシーンにはあまり共感できません。それが無ければ、この映画は90分に治まったのではないでしょうか。それが恐怖を根底から支えるというものであれば話は別ですが、恐怖映画である以上、恐怖の演出に徹底して欲しかった、というのが最終的な結論です。結果的に本作には2度裏切られたわけですが、それでも楽しめた作品ではありました。
2006年09月14日
たとえ錯覚でも、『弓』では奇跡が起こっていると思った
 原題:THE BOW
原題:THE BOW
上映時間:90分
監督:キム・ギドク
本作のエンディングロール冒頭には“キム・ギドクによる第12番目の作品”というような一文が記されていました。インタビューを読むと、この一文はどうやら配給側が入れたらしいのですが、何故わざわざこのような宣言を滑り込ませるに至ったのか、この『弓』という作品を振り返ってみると、それが何となくわかるような気もしますし、逆によくわからない気も。12という数字は、なるほど、一つの区切りを示す数字であると言えなくもありませんが、キム・ギドクの場合、どの作品にも(と言っても『鰐』、『野生動物保護区域』、『実際状況』は正式公開されておらず未見)共通する要素はありつつも、一作一作まるで別世界のように異なる映画でもあって、12作目という区切りがどれほどの説得力を持つか、私にはよくわかりません。『弓』を撮ることで彼が何かを“閉じた”という印象もあまりなく、だから実際には、あくまで配給側によるちょっとした配慮、というだけなのかもしれません。尋常ではないペースで映画を撮り続けているキム・ギドクは、現在韓国において、あまりよろしくない状況に置かれているらしいのですが、次回作『時計』もすでに完成しているようですし、個人的には、この12という数字が、不吉な数字として世の中に認知されてしまうことだけはあって欲しくないと思っています。
現実にはとてもありえないような特異な状況におかれつつ、社会から疎外された人間を描いてきたキム・ギドクは、本作においても海に浮かぶ漁船といういかにもギドク的なイメージを核に、ある愛の物語を描いています。キム・ギドクの映画が3つにカテゴライズされるのはもはや周知の事実と言えるでしょうが、では本作は果たしてどのカテゴリーに属するのでしょうか。『弓』では、口を利かない(実際には話している言葉が観客には聞こえないということですが)老人と少女に焦点が当てられています。いや、敢えて言うなら、この映画の主人公はその老人1人だと言えるかもしれません。彼は少女と結婚することを待ち望んでいて、その少女に寄ってたかる男達に対し、怒りをあらわにしながら追い払う。そうかと思えば、少女と2人きりの時は穏やかに微笑んだり、時には悲嘆にくれたりもする。その表情や身振りは、キム・ギドクの演出ならではとも言うべき非常に繊細かつ大胆なものです。そう考えてみると、『弓』は『悪い男』『魚と寝る女』と同系譜に属する“クローズアップ映画”だと捉えることが出来るような気がします。しかし、主に“怒り”を描いた初期作品と本作が異なるのは、登場する老人にも少女にも“怒り”とは異なるもう一つの側面があって、その側面もまた同レヴェルで強調されているからです。ちょうど、本作に何度も出てくる重要な小道具である弓にも、武器と楽器という相反する側面があるように。この相反する側面は、ラストシーンで象徴的に描かれる生と死へと置き換えることが出来そうだ、などとも思えます。
それにしても、『弓』を観て改めて確信したことがあります。それは、キム・ギドクの世界が、まったく唯一無二だということです。いったいどういう部分が唯一無二なのか、という問いを発する暇もないほどに、それは圧倒的な説得力を持って、私の前にただある。これは驚くべきことです。
彼が描く寓話(としかいいようがありません)は神話のように普遍的でもあり、だけれども、我々が生きる現実と上手く重ね合わせることが困難です。ありそうでありえない。これがキム・ギドクの映画であり、かつ、彼の人生でもあるのでしょう。
キム・ギドクの想像力は、本作でも爆発しています。例えば、弓占い。あれは彼が創出した架空の占いのようですが、ブランコに乗って揺れる少女に向かって弓を3本射て、それが刺さった位置で判断しているのかどうかは定かではありませんが、とにかくその儀式を経た少女の脳裏に占うべき人間の未来が見えるという、非常に独創的なものです。このシーンは3回繰り返されますが、面白いのはその占いの結果が観客には知らされないということ。謎は謎のまま。この点もまたいかにもキム・ギトク的ですが、3〜4箇所のカメラで撮られたこの弓占いシーンは、そのカット割りの周到さからみても、非常に重要なシーンであることがわかります。死と隣り合わせのこの危険な占いにおいては、2人の間の信頼関係があからさまに顕れてしまうからです。実際、老人と少女の間にそれまでありえなかった“怒り”の感情が芽生えた時、つまり、信頼が揺らいだ時、この危険な占いは第三者の手によって中断されるのです。その第三者とは、少女が恋心を描く青年に他なりません。そしてこの招かれざる客の出現が、この寓話を新たなステージへと昇華させることになります。
青年が登場するまで、老人と少女の生活には彼らだけの論理があり、それは誰にも犯すことの出来ない強固な壁(本作では漁船を囲む広大な海がそのメタファーだったように思います)に守られていました。しかし、まるで“社会”を体現しているかのような青年が2人の間に亀裂を入れることで、結果的にもう一つの選択肢が生まれる。別離でも再生でもない、もう一つの結末が。仮にそのどちらかの結末であっても、この映画は成り立っていたでしょう。しかし、キム・ギドクはそのようにはしませんでした。本作が神話的な崇高さを纏うことになるのも、キム・ギドクによって創造されたこの結末の存在に拠るのです。
死を覚悟した老人の悲愴な決意を前に、少女は失いかけた老人に対する情を取り戻します。そして、まさに儀式と呼ぶに相応しい2人だけの結婚式に至る。色鮮やかな衣装に身に纏った2人は、一見幸福に包まれているかに見えます。儀式の後、2人がボートに乗って漁船から遠く離れていくのを、青年はただ途方に暮れながら見ることしか出来ません。愛の勝利、などという陳腐な言葉すら浮かびそうにもなるこの一連のシークエンスはしかし、その後のある種奇跡にも似た悲劇を際立たせるためのものだったのかもしれません。
映画は時に、いかなる説明をも寄せ付けないようなシーンで観客を呆気なく置き去りにしますが、老人が大空に矢を放ち、その後自らの肉体を海の中に沈めるというシーンに、我々はどのような説明を加えるべきなのでしょう。いや、果たしてそんなことが可能なのか。
老人が命を絶った、という事実を知っているのかどうかすら疑わしい少女が眠りから目覚めると、突如足を大股に開き、まるでセックスをしているかのように一人悶えだすのですが、稀有な事態がただ目の前で起こっているということをただ観てしまう他ないという意味で、先述したシーンに等しい。大股を開いて悶える少女の股間近くに、これまた突然一本の矢が突き刺さろうとも、その矢が当たったわけでもないのに少女の秘部から鮮血が溢れようとも、たとえその矢が先に老人が放ってであろう矢だということを了解できたところで、やはりそんな奇跡が起きてしまっていることを、我々はただ見つめ続けるしかない出来ないのです。
もちろんこの一連のシークエンスに、それらしい説明をつけることが出来ないわけではありません。画面を観ながら、その真意(そんなものが本当にあるのかどうかは別として)に想像をめぐらすことだって可能です。しかしまったく幸いなことに、私はこのほとんど映画ならではの奇跡としかいいようのないシーンの強度に圧倒されてしまったがゆえに、目の前で起こりつつある出来事を説明的に解釈しようなどとは思いませんでした。そしてその強烈な印象が、この映画の神話性を高めるに至ったのだと今は確信してます。
ことほど左様に、『弓』という90分の映画はあらゆる解釈を無効にしつつ、しかし必ず観るものを打つ、そんな映画です。ラストで漁船がゆっくりと沈んでいくショットがありますが、あのように恰好な映画的素材をまるでスペクタクルとして撮ろうとせず、にもかかわらず、そこには叙情性と叙事性が同時に顔を出しているかのような感覚を覚えてしまうのです。あのような芸当をやってのけるキム・ギドクの凄さ、これはもう、いささかも似てはいないものの、ロバート・アルドリッチの凄さとか、モンテ・ヘルマンの凄さとか、そのようななかなか説明出来そうも無い凄さの粋に達していると思います。最後は結局比喩に逃げざるを得ない、しかし最初から比喩の対象などないという意味で、やはりキム・ギドクは唯一無二の映画作家なのです。
2006年09月08日
『ジョルジュ・バタイユ ママン』、映画≠小説
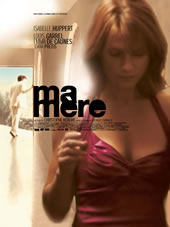 原題:MA MERE
原題:MA MERE
上映時間:110分
監督:クリストフ・オノレ
本作は、“死”と“エロス”の思想家だったジョルジュ・バタイユの遺作「聖なる神」から「わが母」を映画化したものです。バタイユといえば迷わず「眼球譚」と答えてしまうだろう私、学生時代にこれを読んで大いに衝撃を受けて以来、幾度か彼の著作に挑戦し、時に挫折したりしながら結局全部読み終えたのは「眼球譚」に加え「マダムエドワルダ」と「死者」だけという、なんともまぁ情けない限りですが、澁澤龍彦の著作を読めば、彼の名前が何度も登場するし、なんだか分かったような気になったりもしたものです。ただし恐らく、ではバタイユとは誰か、と聞かれても、ああ、そうだなぁ……などといいながら最終的に言葉を濁してしまうに違いないでしょう。
さて、タイトルに敢えて「ジョルジュ・バタイユ」とつけたことで観る人間をかなり選んでいるらしい本作、イザベル・ユペールとルイ・ガレルが親子なんていう物語で、しかもR-18指定などと聞くだけで、ただならぬ期待を抱かせずにはおきませんでしたが、実際に観てみると、これがまぁ何とも言いがたい作品で、簡単に言ってしまえば面白くはない映画でした。ただ私の場合、“面白くない”という言葉は賛辞として使うことも多く、だから、もう少しだけ検証してみたいと思います。これは一体、どんな映画なのでしょう。
近親相姦の話だ、と言って言えないことはありません。あるいは人間の本性(エロス)を巡る話だとも。しかし、そんな話は今どき珍しくもなんともないとは思います。私にとって肝要なのは、バタイユ的なエロス(とかいいつつもそんなものは説明出来ませんが)がどのように映像化されているのか、という部分かと。
R-18ということで、当然セックスシーンは数回にわたって登場します。
しかし近親相姦といいつつも、親子のセックスは実は直接的には描かれてはいませんでした。描かれるセックスの多くは息子と、母にあてがわれた別の女性(ジョアンナ・プレイス)とによるものです。バイセクシャルだったり暴力的だったりするセックスは、キリスト教的な見地に立てばそれだけで相当背徳的で冒涜的でもあるのでしょうが、それが映画として描かれた場合、途端に通俗的になってしまいかねないのは、この映画が背負う宿命なのでしょうか。確かに、あれらサディスティックなセックスは、そのディテールも含め、原作にも書かれていそうな気配が漂ってはいたのですが…。
母親が息子の潜在的なエロスを白日のもとに暴き出す――それはすこぶる魅力的なテーマですが、どうもその過程があまりにも端折られているのか、急速に変貌していく息子と、同じく急速に死へと走る母親に対する違和感が否めませんでした。これもまた、バタイユの著作が、どうしても映画というメディアとなかなか折り合いをつけようとはしなかったということなのかもしれません。あらゆる倒錯の描写も、単なるエピソードとしてしか映らず、そこに流れる何かどろどろとした得体の知れない情念のようなものが、綺麗にそぎ落とされていたような気も。まぁこんなこともあくまでイメージでしかなく、私の思い込みに過ぎないのでしょう。
感動的な場面が無かったわけではありません。ラストシーンで、母親の遺体を前にした息子が、何かに取り付かれたように、おもむろに自慰行為を始めるのですが、あれがエロスとタナトスの緊張感極まる関係性というやつだ、とか説明されたとしたら、ああ、そうかもなぁ、と納得は出来ます。それが神への最大の冒涜、なのかどうかは分かりませんが……
結局私は、バタイユの映画など観たくはなかったのかもしれません。いや、そんな映画の存在は、知らないほうが幸せだったのです。そもそも比較することが不可能な小説と映画。この二者の間にある決定的差異を、本作は思い知らせてくれました。強いて言うなら、それが本作を観た上での最大の収穫だったということです。もう一つ、この「わが母」という小説を読んでみようと思わせてくれたことも。
冒頭の話に立ち返れば、本作はそのままの意味で面白くはないけれど、何も収穫がないという類の映画でもない、ということで曖昧に結論しておきます。
『水の花』は嫉妬の対象足りえる映画である
 原題:水の花
原題:水の花
上映時間:111分
監督:木下雄介
監督の木下雄介は、『鳥籠』という作品で「第25回ぴあフィルムフェスティバル/PFFアワード2003」で準グランプリと観客賞のダブル受賞を果たした結果、第15回PFFスカラシップの権利を手にし、若干24歳で本作を撮りあげました。つまり本作は、長編劇映画デビュー作になります。
『水の花』を観た誰しもが、この映画の独特な画面設計を思い出すでしょう。強固なフィックスショットと横移動が、いずれもかなりの長回しで撮られているのを観て感じることは2つ。それは、木下監督の作家性と、日本映画のある種の潮流です。もちろん、そんなものが本当にあるかどうかは定かではないのですが、ふとその2点について思いをめぐらせたりしました。
本作は大きく3つのパートにわけることが出来ます。まずは主人公である2人の少女、美奈子と優が置かれている現状があくまで控えめに示されるシークエンス。次にその2人の出会いから東北の海沿いにある祖父母の家に到着するまでのシークエンス。そして、彼女達による数日間の共同生活とそれが終焉するまでのシークエンス、という具合に。
物語は非常に明快、そもそもここに描かれた世界はかなり限られたものです。その分、異父姉妹である美奈子と優の、それぞれの感情の動きをじっくりと見据えようとする画面の連鎖だけが印象に残ります。監督がフィックスによるワンシーンワンショットに拘ったのも、映画においては決して画面に映ってはくれない“感情”の静かな揺らぎ、それは時に殺意にまで到達しかねない憎悪にも似た感情だったり、無垢で無邪気な感情だったり、あるいは優しさのようなものだったりもするのですが、それらをいかにして観客に“伝える”のか、画面に映らない感情は、しかし、画面を通してしか観客には伝わらないのです。本作におけるワンシーンワンショットは、だから、決して小手先のテクニックではないと私は思いました。
頑ななフィックスショットにも増して私の記憶に深く刻まれたのが、2度にわたって画面を躍動させる長い横移動のショットです。1度目は、娘の捜索願を出した警察署から、黒沢あすかが一人で出てきて歩き出す場面。感極まった彼女は突然泣き出し、それでもふらふらしながら歩いているのですが、途中で躓いてしまう。そこからまた立ち直って再度歩き出すまでを捉えた、画面左から右にかけての横移動がどれほどの強度をもっていたことか。彼女の演出もさることながら、いつ画面が切り替わってしまうのか不安にさせるかのような、あの緩慢な横移動が素晴らしい。対象までの距離、歩く速度、運動が途切れる瞬間の演出などが、映画の文法からややはみ出した過剰さを微塵も感じさせず、あくまで静かに画面を漲らせていました。
2度目にそれを目にするのはラスト、優を失い一人になった美奈子が、海沿いの道をやはり画面左から右に歩く場面です。1度目のシーンと異なるのは、このシーンには歩く対象以外にもう一つの運動があること。それは言うまでもなく、画面手前に向かって押し寄せるいささか荒れた海の波です。美奈子の心の内が、その力ない動きと共に、荒い波としても表現されているようなそのシーンでも、やはり、彼女は立ち止まるのです。そして次の瞬間、座り込んでしまった彼女が立ち上がった時に、カメラは正面から美奈子を捉える。あの瞬間、映画が終るということが直感で理解されました。つまり、あのラストシーンは見事なそれだったということでしょう。
古びた祖父母の家の庭で優がバレエを踊るシーンも忘れがたい。ピアノの音がそのまま伴奏に変わっていくシーンは常套とはいえ感動的で、それがあのぎこちないバレエを妙に盛り上げています。画面はやはり寄りもしないし引きもしない。しかし素っ気無さを感じさせず、むしろあまりに潤った画面に私も感情を乱されそうになったことを最後に記しておきたいと思います。
一つつまらない告白をします。
これまで映画を撮ることなど微塵も考えたことのなかった私ですが、それでも今、死ぬまでに何らかの映像を撮ってみたいと思わないこともないのです。もちろん、上映されるあてのないそんな映像は、映画とは無縁のものに違いないとすでに諦観してもいるのですが。
では何故こんな話を書くのかというと、私が撮ってみたいと思っていた映像(あくまで映画ではありません)は、まさにこの『水の花』のようなそれだったということに気づいてしまったからです。これは正直に言うとショックというほか無く、畜生!最初からあんな海撮りやがって!と思わず嫉妬めいた言葉が漏れてきそうにもなるのですが、だからこそというか、私は木下監督が本作を撮った24歳という年齢をこそ重視したいと思っています。才能というやつは恐ろしいです。
2006年09月05日
どう見ても激ワルオヤジに感動
先週末はTSUTAYAでヴィデオを4本借りていたのでそれを観るのに必死で、結局劇場鑑賞は1本のみでした。借りてきた作品はいずれも旧作。前に借りたのに観ないで返してしまったものだとか、その名前のみ聞いてはいたけれど長らく手に取ることがなかったものとか、やはりもう一度観ておきたいものだとかそういった類の、主にアメリカ映画を中心に。
いずれも面白かったのですが、特に劇場で観なかったことを後悔したのが、『ゴースト・オブ・マーズ』。渋谷ではシネマ・ソサエティ(現 シネマ・アンジェリカ)のみで公開されたらしいのですが、まさに劇場で観るべきアメリカ映画の傑作でした。その他、ペキンパーの遺作やらマンキウィッツの遺作だとかフランケンハイマーの最も輝いていた時の秀作だとか、まぁそんな感じで。何とか全て観る事ができましたが、やはり、一介のサラリーマンにとって、しかも怠惰な私にとって、週に4本のヴィデオを観るのは、それがほとんど“消化”になってしまいがちであるという点で厳しく、週末は“絶対に”劇場に足を運ばねばならないことを考えると、2本くらいが適当かな、などと結論した次第。
劇場で観たのは盛んにテレヴィcmが流れている、どう贔屓目に見ても刑事には見えないワルそうな男2人が麻薬マフィアに潜入する映画ですが、今、男が銃を構える姿をを最も魅力的に描く監督の一人であるマイケル・マンは、本作においてもやはり、あの銃の構え方を見せてくれるので嬉しくなり、それに加えて本作では、銃(あるいは対戦車ライフルみたいなもの)をぶっ放す瞬間の爆音とそれが対象(人だったり車だったり)にヒットする際の衝撃が凄まじく、なかなか魅せてくれました。あまり期待はしていませんでしたが、予想以上の出来栄え。安っぽいcmに辟易せず、是非劇場に足を運んでいただきたい作品です。日曜の午後一にしては渋谷でも大きな劇場に属する某劇場は4/1程度しか埋まっておらず、なんとも寂しい限りでしたので。今どきの女性は、ああいうワルが嫌いではないのでしょうから、女性にこそ観ていただきたいと思います。
今週もTSUTAYAが半額なのですが、いろいろ忙しいこともあって一本も借りていないので、せめて何本かのレビューをサクっと更新していきます。
(追記)
そういえば書き忘れてました。恐らくそのタイトルに“シネマ”という言葉が使われているという理由で朋友・こヴィ氏がプレゼントしてくれた梁石日の「シネマ・シネマ・シネマ」を先日読了しました。限りなく事実に基づいていると思しきこの小説、“映画作りとは”という問いにある程度は答えを出すものでしたが、それよりも随分と前に、黒沢清氏がより端的にそれを指摘していたのを思い出してしまいました。
曰く、「愚鈍で憂鬱で反動的で、尚且つまったくもって楽天的な徒労こそ映画作りである」。
だから何だ、というわけではないのですが。
こヴィさん、ありがとうございました。実はまだ借りているロメール数本を観終えていません。何とか今週中に観られれば、とは思っています。いつもすみません。
2006年09月01日
夏よさらば
30日の夜、当ブログにもよく顔を出してくれるエノキさんの熱烈なリコメンドを受けて、『ブライアン・ジョーンズ ストーンズから消えた男』を観にいく予定でした。一回だけでは飽き足りないエノキさんは、もう一度観たいからということで私に付き合ってくれたのです。
劇場はシネクイント。あまり行きたくはない劇場でしたが、エノキさんによると、平日の最終回はかなり空いているとのことでしたので、それならということで近くにあるカフェ「人間関係」で上映まで時間を潰そうと言うことに。20:30の上映開始を前に、ビールを2杯ほど引っかけてテンションを上げた我々は、20:00を回ったあたりで劇場にイン。あのシネクイントのロビーが、上映30分前でこんなに空いていることに喜びながら意気揚々とチケットを買いに行くと、何だか申し訳なさそうな顔をした販売員が、「あの・・・先週から上映時間が変わりまして、19:30が最終回となっております・・・」と一言。あまりに唐突なその言葉に、一瞬言葉を失った我々ですが、すでに上映開始から30分以上経過しているのでそのまま途中入場するわけにもいかず、苦笑しながらとぼとぼと劇場を後にしたのです。まぁ事前に上映時間を調べておかなかった我々に非があるのですが、やっぱりあそこの劇場とは相性が悪いのか、なんて思ったりもしました。だからといって、“死ねクイント”とまでは思いませんが。
結局飲みなおすことになった我々は、その悔しさを振り払わんがごとく、午前2時近くまで飲みまくった次第。15日まで上映してますから、どこかでもう一度リベンジできればと思っています。エノキさん、お疲れさまでした。二日酔いは大丈夫でしたか?
さて、どうして平日からそんなに飲んだのかというと、実は昨日、最後の夏休みをとっていたからです。もちろん、海に行くつもりだったのですが、二日酔いにならなかった代わりに朝起きることができず、海も断念。しょうがないので映画を、ということで『ハードキャンディ』を観てきました。
以外にも20人くらいの観客が入っていた本作は予想以上の出来栄え。確かに“映像派的”なショットもありはしたものの、我慢ならないというレヴェルではなく、シネマスコープなのに多くのショットが表情のクローズアップという不思議な、しかし効果的でもあった画面に見入ってしまいました。主演のエレン・ペイジの演技は驚くべきもので、今後を大いに期待させる女優です。デビッド・スレイドという監督名も覚えておきたいと思います。
今日から9月。海に行くことはもう無いと思うので、これからまた映画中心の生活をおくっていきたいと思います。さらば夏。待ってろ映画。という感じで。
『ユナイテッド93』、映画における真実や客観性について考える
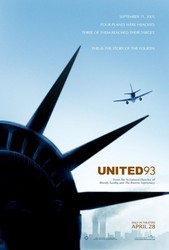 原題:UNITED 93
原題:UNITED 93
上映時間:111分
監督:ポール・グリーングラス
アメリカ同時多発テロが起こった2001年9月11日、ハイジャックされた四機のうち、一機だけが目標に到達することなく墜落しました。本作では、その最後の一機が離陸する前あたりから墜落までを、ほとんど実際に起こったのと同じ時間進行で描かれています。
『ユナイテッド93』は、とかくその手法に注目が集められているようです。
カメラがハンディのみだったり、登場人物には無名の役者が占め、管制官や軍人には実際の事件に立ち会った人間が演じていたりするがゆえに、ほとんどドキュメンタリーと見紛うリアルな出来栄えだという批評には概ね同意するものの、やはり本作はフィクションでしかないという事実をここで再確認しておきたいと思います。本作においてもまた、他のハリウッド映画同様に計算された演出がなされているのですから。無論、私はここで言う“計算された演出”をネガティブなイメージとしては捉えてはいません。それは映画の歴史と同じくらい昔からとられた、極当たり前の手法に過ぎないからです。
確かに、本作における“説明描写の不在”は、あたかもその現場にいるかのような臨場感を味あわせてもくれますし、例えばそれぞれの人物から発せられる日常会話も、物語に貢献する意味のある言葉の連なりとは言いがたく、それはまるで、何も起こらない日常を無作為に切り取ったかのように、ドラマティックとは程遠いものであるがゆえ、逆にリアルであると言うことが出来る。
イスラムの信仰に厚い数人の若者がいる。西海岸に旅行しようとしている人がいる。あるいは仕事で飛行機に乗ろうとしている人がいる。それぞれにはそれぞれの日常があって、彼らは偶々、同じ飛行機に乗り合わせただけ、というような描き方が、本作ではなされています。だから、コーランを読み、壁に向かって深く祈る若者たちを、予めテロリストとしてその背後にあるだろう“悪意”を全面に押し出すようなことはしていません。その意味では、よく言われているように、本作はアメリカ側にもイラク側にも立場を置かない、あくまで客観的に事実を描こうとした映画だと言えないこともないでしょう。
しかしながら、映画において、真の客観性などそう簡単に実現できるものではありません。このことは“フィクションとドキュメンタリーの差異は何か”という、厄介極まりない問題と重なってくることなのですが、カメラアングル一つ変えるだけで、そこには何らかの“意志”が介在してしまうというのが映画ですから、例えば一台のすえつけられた監視カメラで撮られた映像だけで成立した映画であれば別でしょうが、とにかくこの『ユナイテッド93』という映画においても、イデオロギー的に限りなく中立(であるかのよう)な撮り方は可能にしても、やはりそこに客観性などありはしないということを改めて考えた次第です。
政治的な意見表明などしようとも思っておらず、いわんや911の現場に身を置いたわけでもない私にとって、『ユナイテッド93』もまた、あまたある映画の中の1本に過ぎません。少なくとも私の目には、数箇所でいかにもハリウッド的(≒映画的)な演出だと確信出来るシークエンスがありました。座席に備え付けられた電話やそれぞれの携帯電話で、泣きながら家族に遺言のようなものを託すシーンの連鎖などはその最たるものです。ここにはある一つのパニック映画の定石が、律儀に反復されているということでしょう。そして、それはこの映画をいささかも貶めるものではありません。
本作は、実際の被害者家族や友人への取材に基づき、何とか真実に近づこうという意思の元に作られた映画であるかもしれず、それが逆に、劇映画という範疇を超越した意見や批判、あるいは賞賛を生んでいるのかもしれませんが、私としては、あくまで本作を、1本のアメリカ映画(あるいはパニック映画)として評価したいと思います。少なくとも、この映画を真実の物語と信じてしまうことだけは、避けなければならない。『ユナイテッド93』はフィクションだという当たり前の事実があって、その上でこの映画のカメラだとか、演出だとか、構成だとかを評価したいと思うのです。これが、映画を観るということを、新しい世界(視点)を発見することだと捉えている私の結論です。1本の劇映画である『ユナイテッド93』ですが、私に新たな視点を与えたという事実に変わりはないのですから。
最後に、ポール・グリーングラスについての現段階での評価は、やはりドキュメンタリー的と称された『ブラッディ・サンデー』を観た上で改めて考えてみるとします。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]



