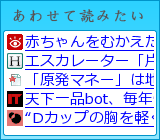2004年06月28日
ヴィデオショップ ノスタルジー
今、『KILLBILL』に関するテクストを書いている途中なのですが、レンタルヴィデオ店での5年間のうちに、その映画的感性と知識に磨きをかけたタランティーノ、実は私も学生時代3年ほどレンタルヴィデオ店で働いていたことがあって、そのことを今日の日記と強引に結び付けようと、一端中止してこちらを書いています。
私が働いていたヴィデオ店は、数年前すでに別の店舗に変わっていますので、再びその場所を訪れてノスタルジックな郷愁に浸ることは出来ないのですが、タランティーノよりは間違いなく少ない本数だとはいえ、こちらもそれなりに映画漬けの日々を送っていたわけで、仕事中はもちろん、店員の特権を最大限に(時には限度を超えて)利用し持ち帰ったヴィデオを、飽きずに観まくっていたことを思い出します。お世辞にも映画が好きだとはいえないだろう店長と、かなりのアメリカ映画好きだったであろう副店長と、その他映画とはほとんど無縁の学生やフリーターで構成されていたそのヴィデオ店は、地方都市の駅前のくたびれた店という、いかにもな店構えで、もちろんヴィデオレンタルだけではやっていけないので、2階にCDを置いてみたり、店頭にプリクラを設置してみたりして、その延命に躍起になっていましたが、私がやめた後数年で別の書店チェーンに店を乗っ取られた現状を見ると、それも虚しい徒労だったということでしょうか。
その当時の私の楽しみといえば、店内に“隠された”傑作たちに光を当てるという、非常に“意味のある”作業でした。映画のことなどまるでわからない店長がある作品に対し、一応ジャンルわけしてある店内の配置のしかるべき位置にその作品を収めようとするのですが、無知からくるあまりにも杜撰な商品管理ゆえに、例えばベルトラン・ブリエの『バルスーズ』をあろうことかアメリカンソフトポルノコーナーに追いやったりしてしまうので、こういう作品を探し出し、“[M]のリコメンド”などというコーナーを一番目立つ新作棚の隣にひっそりと設け、コメントつきで紹介するという有意義な仕事に勤しんだのですが、その仕事が私に教えてくれたのは、ジャンルという曖昧なものをとりあえず括弧にくくり、作家の名前を記憶することの重要性に他なりませんでした。今思い出すと赤面してしまいますが、あの当時は無邪気にそんな考えを抱いていました。
でも、私にとってあの店の存在はやはり非常に大きかったのです。タランティーノにおけるロバート・ロドリゲスのような存在には遂に出会うことが出来ませんでしたが、孤独に映画を楽しむ術と、あまりに偏った嗜好性を軌道修正することを学ぶことが出来たという意味で、実に貴重な体験をさせてもらいました。店長を含む当時の同僚たちがこの日記を読む可能性がどれくらいあるかわかりませんが、一応感謝の言葉で締めたいと思います。
2004年06月27日
現在のアクション〜『マッハ!!!!!!!!』とジャッキー・チェン
 7/24から劇場公開される『マッハ!!!!!!!!』という映画に注目しています。90年代以降、日本でも少しずつ紹介されてきたタイ映画ですが、実はほとんど見ていません。それなりにヒットした『アタックナンバーハーフ』ですら見逃しているくらいです。唯一、オキサイド・パン、ダニー・パン兄弟の『レイン』をヴィデオで鑑賞したくらいで、だいたい監督の名前がなかなか頭に入らないのがその原因と言いますか、いや、そんなこといったら悪いですね。最近になってようやくペンエーグ・ラッタナルアーンという監督の名前を覚えましたが、覚えただけですでに満足している私に、タイ映画について文章を書く資格などそもそもないのです。
7/24から劇場公開される『マッハ!!!!!!!!』という映画に注目しています。90年代以降、日本でも少しずつ紹介されてきたタイ映画ですが、実はほとんど見ていません。それなりにヒットした『アタックナンバーハーフ』ですら見逃しているくらいです。唯一、オキサイド・パン、ダニー・パン兄弟の『レイン』をヴィデオで鑑賞したくらいで、だいたい監督の名前がなかなか頭に入らないのがその原因と言いますか、いや、そんなこといったら悪いですね。最近になってようやくペンエーグ・ラッタナルアーンという監督の名前を覚えましたが、覚えただけですでに満足している私に、タイ映画について文章を書く資格などそもそもないのです。
がしかし、冒頭に挙げた『マッハ!!!!!!!!』に対してはただならぬ期待を寄せていて、それは偏に、この映画がアクション映画だからなのですが、その題名から感じられる気合いは並大抵ではなく、エクスクラメーションが8つも並んだタイトルは私の知るかぎり映画史上初めてではないかと思われます。もちろん、ただアクション映画だと言う理由だけで期待してしまうほど、世の中には面白いアクション映画ばかりがあるわけではないのですが、『マッハ!!!!!!!!』には、どことなく『少林サッカー』における“生真面目な馬鹿馬鹿しさ”に通ずる魅力が備わっているようで、こちらの期待をいやが上にも高めるのです。第一、予告編に見られる数々の“公約”からしてすでにハリウッド製“香港”アクションに対する挑戦であり、同時にブルース・リーへの郷愁とも感じられてしまうのですが、この映画には、何よりB級のノリを隠そうともしていない潔さが感じられ、B級具合をCGで塗り固め、結果失敗した『マトリックス』三部作などよりよっぽど誠実な映画だと、観てもいないのに言ってしまいたくなるくらいです。
もう随分と遠い昔になりますが、『プロジェクトA』という映画の中でジャッキー・チェンが高い時計台からノースタントで落ちて見せたときのことを思うと、昨今見られるようなのような技術を使えば、何もあんな風に体を痛めつけることもなかったろうにといたたまれなくもなりますが、やはりノースタントが売りだったジャッキー・チェンも、新作『メダリオン』に至ってはワイヤーを使っていることを考えると、あのジャッキー・チェンですらワイヤーを使わねばならないのかと、いささか残念な気持ちになったりします。まぁ、こんなことは本当に大きなお世話で、“ノースタント・ノーCG”が美徳だと思ってしまうことはほとんど反動的だと言ってもいいくらいですが、例えば『SPY_N』のような映画を観てしまうと、いくらスタンリー・トン監督だとはいえあまりに悲惨なこの映画を支持することは出来ないわけで、某有名女優のプロモーションヴィデオとまでは言いませんが、香港のお家芸ともいえるワイヤーアクションの無駄使いだと言いたくもなり、ワイヤーアクション自体に疑問を抱きたくもなるのですが、少なくとも『マッハ!!!!!!!!』には、予めそのような不安材料が無いわけですから、出来れば初日にでも駆けつけて、その“公約”とやらを確認したいと思います。
2004年06月23日
現象としての『ロスト・イン・トランスレーション』
 シネマライズの初日・2日目観客動員、興行収入が新記録達成したという『ロスト・イン・トランスレーション』をいまさらながら鑑賞したわけですが、公開して間もない頃の混雑振りは確かにすごかった模様、全回立ち見なんて聞くと、それがどんな映画だろうと行く気が失せてしまい、あんなタバコも吸えないような映画館で1時間以上待っている苦痛にはとても耐えられないという結論に至ってしまいます。あれだけヒット作(飽くまで単館レベルですが)を生み出す劇場なのですから、今すぐ整理券制にしてくださいよ、ライズさん!
シネマライズの初日・2日目観客動員、興行収入が新記録達成したという『ロスト・イン・トランスレーション』をいまさらながら鑑賞したわけですが、公開して間もない頃の混雑振りは確かにすごかった模様、全回立ち見なんて聞くと、それがどんな映画だろうと行く気が失せてしまい、あんなタバコも吸えないような映画館で1時間以上待っている苦痛にはとても耐えられないという結論に至ってしまいます。あれだけヒット作(飽くまで単館レベルですが)を生み出す劇場なのですから、今すぐ整理券制にしてくださいよ、ライズさん!
ところで、『ロスト・イン・トランスレーション』に何故あれだけの人が集まったのかを考えてみると、それは多分、ソフィア・コッポラの名前に反応したと言うより、もっと抽象的な理由がそこに隠されているのではないかと思うのです。前作『ヴァージン・スーサイズ』の公開時よりも、日本における彼女の存在がよりポピュラーになっているのは事実だと思います。あの当時、ソフィア・コッポラという名前に反応し得た人間は、今のように大多数ではなかったはず。もちろん、一部の人間にとってはすでに“コッポラの娘”として、または“X-GIRL”のクリエイターとして、もしくはファッションカメラマンとして知られていたのですが、現在のように(極端に言えば)誰もが知る女性ではなかったはずなのです。『ヴァージン・スーサイズ』の出来自体にここでは言及しませんが、例えば“ガーリー趣味”と評されもした彼女の処女監督作に対する多くのメディアにおける注目度も、決して高くは無かったのではないでしょうか。しかしそうだとしても、以前とは違ってより多くのポピュラリティを獲得した彼女の映画に、あれほどの人が集まっても不思議ではない、とは言いきれないと思います。ではどうやって説明がつくのか? もちろん、メディアの力がまず第一に挙げられるのは言うまでもありません。彼女の実兄が監督した『CQ』についてどれだけ多くの人間が語ったのかを考えてみると、やはりメディアの力は大きいのです。しかし恐らく、それ以上に強い力学を見落としてしまうと、現在の“東京におけるソフィア・コッポラ”を語るには足りないと思われるのです。
では、“東京におけるソフィア・コッポラ”が持つ磁力とは何なのでしょう。私が思うに、それは彼女自身がすでに東京のカルチャーアイコンと化しているということと無縁ではなく、多くの(映画好きとまではいかない)女性たちは、飽くまで便宜上“TOKYO CULTURE”と呼びますが、そのエッジを感じたいから『ロスト・イン・トランスレーション』に足を運ぶのだろうと。これに似た現象は、数年前やはり渋谷においてすでに見られていたわけで、それは『バッファロー'66』にまつわるヴィンセント・ギャロ崇拝なのですが、『ブラウンバニー』へと引き継がれたかに見えるギャロ信仰は、日本というか東京特有のもので、観る人は、何故か自分とギャロを重ね合わせてしまいがちなところが、あまりに日本的だったといえると思いますが、今回のソフィア・コッポラに関してもそれに似た風景があると言えるのではないかと思います。まして『ロスト・イン・トランスレーション』は東京をその舞台としていますし、シネマライズ近くのカラオケBOXや、渋谷駅前のスクランブル交差点などもスクリーンに映るわけです。これを見ないと東京の“今"(といってもすでに1年近く前ですが)を取り逃がしてしまう、そんな集団的(無)意識が、シネマライズ周辺に渦巻いていたのではないでしょうか。もちろん、以上は全く持って故のない指摘でもあり、それが真実だなどと間違っても言えませんが。ただし、ヴィンセント・ギャロとは映画製作に対するアプローチの異なるソフィア・コッポラは、『ロスト・イン・トランスレーション』にある種の“身近さ”“わかりやすさ”を与えていて、見終えた観客たちは少なからず“満足感(もしくは、幸福感)”を覚え、それがクチコミによってさらなる観客の増加に繋がるという、言ってみれば幸福なサイクルに上手く乗ったのであり、これも彼女の才能を端的に示すものだとも思います。
実際、渋谷周辺に住んでいる身としては、毎日通るような風景を映画で観るというのも奇妙な体験でしたが、『ロスト・イン・トランスレーション』に見出せる“面白さ”は、もちろんその事実にとどまらず、とりわけ魅力的な2人の俳優・女優の演技とか、渋谷での隠し撮りシーンとか、西新宿の雑踏を一瞬でもロマンティックな風景に変えて見せたキャメラとか、そういうところにあったのかな、とたった今思いました。
上記文章は、頗るわかりにくいのですが、実は『ロスト・イン・トランスレーション』への賛辞にほかなりません。正直に告白すれば、あのガーリーな『ヴァージン・スーサイズ』に2度足を運び、ヴィデオでも3回は見ている私は、このたびソフィア・コッポラの才能に改めて気づいてしまったのですが、しかしながら、『ヴァージン・スーサイズ』を観ていない人には、『ロスト・イン・トランスレーション』の面白さ“だけ”を体験させたくなくて、「ああ、あれはコメディだね・・・悪くないけど・・・」などとやや斜に構えた感じで言い放ってしまうのです。われながらその心の狭さに辟易しますが、やっぱりいい映画は多くの人に観られるべきなのでしょうから、これを機に残りわずかとなった上映期間を孤独に宣伝して回ろうかと、そんな風に思ったり思わなかったり…
さてさて、本日はレイトショーで『21グラム』を観てきました。品川プリンスシネマという、普段であれば絶対に行かないような場所で。いずれ何らかのテクストになろうかと思いますが、今、ひとつだけ後悔しているのはパンフレットを買いそびれたことです。あのようなシネコンにおいては、レイトショーの場合、上映前にパンフを買っておかないといけないのですね。シネコンに慣れないもので、終わってから右往左往してしまいました。近く、渋谷シネパレスにでも行って、パンフレットだけでも購入させてもらおうかと思っています。
2004年06月19日
泣かない感動
 このサイトを見ているような映画好きな方でしたら、これまでに映画を見ながら泣いた経験があるのではないでしょうか。かく言う私にも、2回ほどそんな経験が。この2回という数字、多いか少ないかと問われれば、恐らく少ないほうに属すると思います。ただしこれは飽くまで、生きてきた年数と見た映画の本数を鑑み、“相対的に”少ないという意味ですが。無論、何事かに“感動”した結果涙を流したのですから、少ないとはいえ、人並に“感動”できる人間だといえると思いますが、ある時ある人から「え〜!? あの映画で泣けなかったんだ〜?」などといわれてしまうと、まるで私が頭でっかちで冷酷で、どんな映画にも感動しない奴だと言われているようで、「ちょっと待ってくださいyo」といささか反論したい気分になります。
このサイトを見ているような映画好きな方でしたら、これまでに映画を見ながら泣いた経験があるのではないでしょうか。かく言う私にも、2回ほどそんな経験が。この2回という数字、多いか少ないかと問われれば、恐らく少ないほうに属すると思います。ただしこれは飽くまで、生きてきた年数と見た映画の本数を鑑み、“相対的に”少ないという意味ですが。無論、何事かに“感動”した結果涙を流したのですから、少ないとはいえ、人並に“感動”できる人間だといえると思いますが、ある時ある人から「え〜!? あの映画で泣けなかったんだ〜?」などといわれてしまうと、まるで私が頭でっかちで冷酷で、どんな映画にも感動しない奴だと言われているようで、「ちょっと待ってくださいyo」といささか反論したい気分になります。
さて、人は“感動”を求めて映画をみると言って言えない事はありません。言うまでもなくこの“感動”というやつは、“泣くこと”にイコールではなく、“強くこころが動かされる”という程度の意味で捉えていただきたいのですが。別段泣ける映画でなくとも、人はその映画に“感動”できるわけで、さらに言えば、トータルとしてあまりに冗長で稚拙で美的感覚が欠如しているような映画にも、どこかに“感動的な”細部を発見することも出来るわけです。ここで私の問題に立ち返ると、これまで幾度と無く“感動”してきたにもかかわらずほとんど泣くことが無かったという事実、全く大きなお世話なのですが、これをいかにも不自然だと感じる人がいるのです。
今更何故こんなわかりきったことを書いているかというと、実はただ書くことが無いからなのですが、そう言い切ってしまうと身も蓋もないので話を戻すと、“感動”=“涙”という図式が世間に罷り通っているような気がしてならないからです。いや、それ自体はなんら問題は無いですし、同調できる部分もあるのですが、例えば映画の宣伝文句に顕著な“感動作”とかいう言葉に、どうしても違和感を感じてしまうのです。「まぁいいから泣けよ」と言われているみたいで。全体としての物語に感動するのは、言ってみれば珍しくもなんとも無く、そんなことはすでに小説で証明されています。問題は、映画でなければ描き得ない部分に“感動”した場合、その感情がなかなか共有され難いということです。例えば、『ショーシャンクの空に』を観て、が涙を流す人もいれば、あの如何わしい『カノン』に感動を禁じえない人もいるのです。後者においては、所謂“感動作”とは無縁の、奇特な映画に属すると思いますが、ある細部に目を向けたとき、説明しがたい動揺が無いとも言えないわけです。つまり言いたかったことは、あらゆる映画に“感動”出来る細部を見つけられれば、映画体験がより充実するのではないか、ということです。
つい最近ある作品を観て不覚にも涙してしまった経験からこんな文章を書いてしまいました。恐らく7〜8年ぶりだったので、涙を流す自分に少なからず驚いてしまい、“じゃあどんな部分に感動したんだろう?”という感情が沸いてきて、遂には、“感動”するということについて改めて考えるにいたったと。何のオチも無い話ですが、こんなこともあります。
2004年06月14日
『LA MOTOCYCLETTE(オートバイ)』、記憶に残る画面と台詞
 97年のリバイバル時に見逃し、作品の出来はさておき、何としても見ておきたかった作品『あの胸にもういちど』(仏語ver)を鑑賞することが出来ました。マンディアルグの著作は以前にも読んだことがあるのですが、原作である「LA MOTOCYCLETTE(オートバイ)」は未読で、しかし、アメリカでは『NAKED UNDER LEATHER(革の下は裸)』などという如何わしいタイトルでソフトポルノとして公開されたくらいですから、「城の中のイギリス人」とまでは言いませんが、 それなりのエロティックさを堪能できるかもしれないという淡い期待を込めて見てみることにしました。ジャック・カーディフ監督の作品は初めてでしたが、監督としてよりもむしろ撮影監督としてのキャリアの豊富さ、それに加え、いくつかのHPや書籍を調べたところ、どうやら“実験的アプローチで撮られたメロドラマ”らしく、その説明に漂う胡散臭さに無条件に惹かれ、このたび奇跡的に(知る限りでは、仏語verのヴィデオは入手困難)鑑賞するに至ったのです。
97年のリバイバル時に見逃し、作品の出来はさておき、何としても見ておきたかった作品『あの胸にもういちど』(仏語ver)を鑑賞することが出来ました。マンディアルグの著作は以前にも読んだことがあるのですが、原作である「LA MOTOCYCLETTE(オートバイ)」は未読で、しかし、アメリカでは『NAKED UNDER LEATHER(革の下は裸)』などという如何わしいタイトルでソフトポルノとして公開されたくらいですから、「城の中のイギリス人」とまでは言いませんが、 それなりのエロティックさを堪能できるかもしれないという淡い期待を込めて見てみることにしました。ジャック・カーディフ監督の作品は初めてでしたが、監督としてよりもむしろ撮影監督としてのキャリアの豊富さ、それに加え、いくつかのHPや書籍を調べたところ、どうやら“実験的アプローチで撮られたメロドラマ”らしく、その説明に漂う胡散臭さに無条件に惹かれ、このたび奇跡的に(知る限りでは、仏語verのヴィデオは入手困難)鑑賞するに至ったのです。
アラン・ドロンもマリアンヌ・フェイスフルも、この作品に出演したことを激しく後悔しているらしいなどと聞くと、こちらの倒錯的な期待も高まると言 うものですが、見終えてみると、なるほど、とりわけこの時期はまだ乗りに乗っていたアラン・ドロンにしてみれば、なんとも不可解な、というよりほとんどだらし ない出来栄えだといえるでしょう。『サムライ』や『冒険者たち』の後に、このような作品に出るなんて、クスリでもやってたのかナァ・・と思いきや、実際にキメ キメだったのはマリアンヌ・フェイスフルの方で、あの(中途半端な)怪演もうなずけます。
その辺の話はいろいろ書かれているので、ここでは映画自体の話を。いかにも60年代の邦題らしい『あの胸にもういちど』というタイトルはさておき、原題である『LA MOTOCYCLETTE』が示すとおり、この映画はオートバイそのものが画面の大半をしめる作品です。冒頭、マリアンヌ・フェイスフルがシュールレアリスティ ックな夢を見ます。このシーンからしてすでに、ジャック・カーディフの実験場と化していると言えます。フィルムは派手に彩色され、極端に細かいカット割により 、様々なイメージが連続的に画面を彩ります。今見ると、ちょっと恥ずかしくなるようなショットもあり、ああ、のっけから失敗しているな、と思いはするものの、 マリアンヌ・フェイスフルをマゾヒスティックな女にし、変装したアラン・ドロンに鞭打たれるシーンを見せてくれただけで満足だと言うべきでしょうか。また、こ れは時代の要請なのか、原作に忠実なのかは分かりかねますが、所謂エロティック・シンボリズムというやつが幾度か見られました。分かりやすいところで、オート バイにガソリンを入れる際に、注入口に管が挿入される描写をわざわざクローズアップで見せるシーン。そもそもレザーのつなぎからして、妙にエロティックさが強調され、特に着替えるシーンをこんなに丁寧に、しかもいくつかのカットに割った上でみせる必要がどこにあるのかを考えてみると、当時のアメリカ人の 感性にはポルノとしか映らなかったとしても不思議ではありません。
この映画の多くの台詞は、マリアンヌ・フェイスフルのモノローグに終始すると言っても過言ではなく、もし全ての台詞が彼女のモノローグだけだったら、『恋ざんげ』のように、真に実験的な作品になったのかもしれませんが、それはさておき、これらの台詞はもしかすると原作者の言葉をそのまま引用しただけなん じゃないかとも思われ、しかも、その一語一語が妙な雰囲気を生み出すことに成 功 していて、「太陽よ! 私を燃やして!」などと彼女が朝焼けに向かって言うとき、決して面白くないこの映画を、ロマンスでもメロドラマでもない、言ってみればジャンルを超越 した異空間へと飛翔させていたと言ったら、やはり言いすぎでしょうか。
こんなことばかり書いてはいますが、心から感動的だったシーンもあって、それはラストに起こる事故のシーンなのですが、非常にあっけなくその身が 空中に放り出され、前方のクルマのフロントガラスに頭から突き刺さる瞬間は、映画における事故のシーンの中でもなかなか悪くなくて、つい『軽蔑』のラストの事故シーンを思い出してしまったほどです。決して良い作品とはいえませんが、記憶の底辺にある奇妙な染みを残したとだけは断言できる作品でした。
2004年06月11日
レトロスペクティヴ of サム・ペキンパー
 映画に関する本を読む、そのほとんどがスポーツジムで運動をしながら、というのがごく当たり前の日常と化しています。運動しながらテレヴィを見たり、雑誌を読んだりすることも稀にありますが、基本的には書籍を読むようにしているのには理由がありまして、それは、疲れというか苦しさを忘れることが出来るからです。実際、読んでいる本にのめりこんでいくと、時間が経つのを忘れてしまい、ふと時計を見ると、すでに1時間が経過していることなどざらです。逆に言えば、面白くない本をセレク トしたときなど、今おかれている苦しさが5倍くらいになって跳ね返ってくる錯覚を覚え、1分が5分になるのです。数年前は、運動しているときの暇つぶし程度にしか 考えていなかったのが、今となっては、「今日は読む本がないからジムに行くのはやめよう」などと、全く本末転倒というか、手段の目的化現象と言うか、我ながら 何のためにジムに行っているのか分からなくなってきます。いや、多分本を読むために行っているのでしょう。おおっぴらに認めたくはありませんが。
映画に関する本を読む、そのほとんどがスポーツジムで運動をしながら、というのがごく当たり前の日常と化しています。運動しながらテレヴィを見たり、雑誌を読んだりすることも稀にありますが、基本的には書籍を読むようにしているのには理由がありまして、それは、疲れというか苦しさを忘れることが出来るからです。実際、読んでいる本にのめりこんでいくと、時間が経つのを忘れてしまい、ふと時計を見ると、すでに1時間が経過していることなどざらです。逆に言えば、面白くない本をセレク トしたときなど、今おかれている苦しさが5倍くらいになって跳ね返ってくる錯覚を覚え、1分が5分になるのです。数年前は、運動しているときの暇つぶし程度にしか 考えていなかったのが、今となっては、「今日は読む本がないからジムに行くのはやめよう」などと、全く本末転倒というか、手段の目的化現象と言うか、我ながら 何のためにジムに行っているのか分からなくなってきます。いや、多分本を読むために行っているのでしょう。おおっぴらに認めたくはありませんが。
さて、今読んでいる映画の本の話題に移りますと、それは「e/m ブック ス vol10 サム・ペキンパー」(定価\2,100 Esquire Magazine Japan刊)というもので、このシリーズは過去にも数冊読んだことがあるのですが、詳細なフィルモグラフィーやインタビューなどを確認するには、それなりに重宝しています。何故今サム・ペキンパーか、という問いに対しては、「わかりません」というほかありませんが、折角だから現在観る事が可能な彼の監督作品を、全て見直そうかと思っています。極私的レトロスペクティヴ of ペキンパーといったところです。
つい先日、40代の(恐らく映画好きな)男性と話す機会がありまして、たまたまそのとき手にしていた前述の本を見るなり、“にやり”と笑い興味深げだ ったので、軽い気持ちで「ペキンパーの映画を見たことがありますか?」などと問い かけたら、その男性は待ってましたと言わんばかりに食いついてきて、「『ワイル ドバンチ』はLD持ってるよ〜」とやや得意げに言われてしまい、「しまった!」と思ったときには時すでに遅く、『ダンディー少佐』や『戦争のはらわた』などの 名前が次から次に出てきて、終いにはリアルタイムで観た『ゲッタウェイ』についての、時代考証をも視野に入れたノスタルジックな話にまで発展してしまい、こち らはリアルタイムで観たペキンパー作品などないので、苦々しく嫉妬を込めてその話を聞くほかはありませんでした。それにしても、その男性は映画が好きな人でしょうからさておくとしても、当時(1960年代〜70年代)いったいどれほどの“普通の人”がペキンパー作品を見に行ったのでしょう。今となっては知るよしもありませんが、少なくとも現在私の周りにいる友人たちを思い浮かべてみても、堂々と「ペキンパーが好きだ」といえる人間は3人といないのもまた事実です。あくまで友人の少ない私の周りに関しての話ですが…
今回のレトロスペクティヴを終えたら、偉大なるペキンパーの凄さを、 今まで以上に吹聴してまわろうかと考えています。
2004年06月10日
“つまらなさ”を考える
多くの映画を観れば、必然的に面白くない映画に当ってしまうものですが、そんな時、何故これほどつまらないのかを考えるようにしています。ただ只管自分の好みと合わないといってしまえばそれまでですが、それが主観的とはいえ、絶対に理由があ るはずです。その答えを見つけることは、しかし、それほど不毛なことではなくて、むしろ未来の映画鑑賞のために有益だと、私は思っています。目を背けたい部分 に敢えて思考を働かせること、その行為により、潜在的な嫌悪の対象を顕在化させることが出来れば、少なくとも積極的に嫌いになれる。金を払って映画を見る以上 、消極的な態度はなるべく避けたいと思います。こんな前振りをしたのですから、以下に続くテクストは、“積極的につまらない”映画に関するそれになるわけですが、とりあえずここでは『ペイチェック 〜消された記憶〜』という作品に犠牲になってもらいます。
何故この作品が槍玉にあがってしまったのか。監督であるジョン・ウーに対する過度の期待からなのか、というとそれがそういうわけでもなくて、もちろん彼に対するほのかな期待が無かったと言ったら嘘になりますが、すでに『M:I-2 』 を見てしまっている私としては、そこまで無邪気になれるはずもありません。では、『ペイチェック〜消された記憶〜』のつまらなさは何なのでしょう。極めて主観的に語らせていただきます。
記憶のない主人公を据えての“巻き込まれ型アクション”という構造は 、昨今さして珍しくありません。体がすべてを覚えていた、という『ボーン・アイデ ンティティ』と違い、ここでの主人公は、未来の自分が過去の自分に託した20あるアイテムを、そのつど有効に機能させることで物語が進んでいきます。『ボーン ・アイデンティティ』と言えば、そもそもマット・デイモンが演じるはずだった主人公をベン・アフレックが演じるというミスキャストぶりに、“つまらなさ”の一 端を見ることができます。それはもちろん、彼が悪しき大根役者だと言いたいのではなく、“知性”を身に纏っているはずの主人公として、彼が適切ではない感じがし たからです。あの顔と図体の大きさが原因というより、むしろ表情にこそ端的に表れている“緩慢さ”が、まずは解せませんでした。この致命的なミスキャストは、ヒ ロインにも当てはまります。ユマ・サーマン自体は悪くないのですが、傍らにベン・アフレックを据えた時、彼女のほうが“知的”だという印象がどうにも拭えず、ひょっとすると殴り合ってもユマのほうが強いんじゃないかと錯覚してしまうほどです。まぁ、『KILLBILL』の印象はそれほど強かったということですが。
ミスキャストの話はこれくらいにして話を進めます。彼は様々なアイテムを使用しながら、窮地を脱していきます。さながら「バイオハザード」(ゲームのほうです)のごとく、何に使うのか分からないはずのアイテムの使用方が瞬時に 了 解され、使用されていく。ここで映画における御都合主義が登場するわけですが 、それを繰り返し何度も見せ付けられるのは決して心地いいものではありません。 “映画がゲームに似てしまう”という不幸な瞬間が、そのままこの映画の主題になっ ているのですから。
“アクションの人”ジョン・ウーの持ち味などほとんど見られませんでした。いくつかのジョン・ウー的アイコン(白い鳩・スローモーション)だけが、 虚しく自己模倣されるばかりです。かなり力の入ったバイクチェイスシーンも、その力の入れ具合からか、物語から大きく浮いていました。そして、何よりいただけ なかったのが、あのフラッシュバックです。最後まで幾度と無く繰り返された、あの手の映像手法(テクノロジーを前面に押し出したかのような、ノイジーな画面が サブリミナル的に挿入される)には正直うんざりです。フラッシュバックという、 実に“映画的”な手法に対する、悪意ともとれる回答。それらしい画面を見せることで、現代的なSF映画たろうとする姿勢。これらの理由から、私はこの映画に全く乗ることが出来ませんでした。
ここまで書いておいて思うのですが、上記のようなテクストは書いていて 気持ちのいいものではないですね。まぁ、こちらは金を払って見ているわけで、 その分の精算はしてやろうと思ったまでです。
2004年06月08日
映画とは何か
 このサイト を見る人の中で、自ら“映画好き”だと自称する人はどのくらいいるのかわかりませんが、敢えて“映画好き”の人に問いかけたいと思います。
このサイト を見る人の中で、自ら“映画好き”だと自称する人はどのくらいいるのかわかりませんが、敢えて“映画好き”の人に問いかけたいと思います。
映画は芸術でしょうか? それとも、娯楽でしょうか? 私はこの問題が、人間同士のコミュニケーションを考える上で、それなりの重要性を持っていると 思うのですが、ここには大まかな分類として4つの回答が考えられるでしょう。
-----------------------------------
1.映画は芸術である
2.映画は芸靴でもあり娯楽でもある
3.映画は娯楽である
4.映画は芸術でも娯楽でもない何物かである
-----------------------------------
予めその答えを上記の様に分類してしまいましたが、この問いについて 、果たしてどれくらいの人々が意識的でしょうか。これは私の経験に留まりますが 、人が何らかの事物を考えたりするとき、まず考えるべき事物がおかれている状況を(ほとんど無意識的かもしれませんが)思い浮かべるのが常です。それは、分別 のある人間にとって(ここは強調すべきところです)、自分の考えなり思想を、容易に絶対視することが困難だからです。もしこんなことを聞かれたら、どこかで読 んだり見たり聞いたりした誰かの発言を、やはり無意識的に思い起こして、何らかの答えを出すのだと思います。それを承知で、改めて、人間にとって映画とはどの 様に位置すべきでしょう?
思えば、こんな大それた問いは、改めて私自身が問いかける必要性など無いですし、端的に言って、「お前に何がわかる」と言われるべきことだとは先刻承知し ています。多分、私自身もそう言い放ってしまうでしょう。例えば、そこに何らかの正論(めいたもの)ががまかり通ったところで、「だから何だ、ボケ!」と言わ れてしまえばそれまでです。なぜなら、“映画とは何か”などと考えずとも、人は、日常的に映画を観て、映画について思いをめぐらせ、そして、映画について語るこ とができるからです。
もちろん、私がここで何らかの答えを出そうなどと考えているわけでは ありません。所謂“振り逃げ”というやつです。ただ、ある種の映画を見たとき、 その 答えがフッと浮かんでしまうことも無いとは言えない。その時人は、“映画とは何か”という問いかけに、絶対的な自信をもって答えることが出来るのかどうか。 私見 では、その時に初めて本当の“映画好き”になれるのかもしれないと、密かに思い込んでいます。そんなことを考えながら、これから『KILLBILL』についてのテクス ト をいかなる方向性で書こうかと考えるのですが、だからといってそこには納得できる答えなどなくて、そこだけポッカリと穴が開いているかもしれません。
2004年06月07日
『クリムゾンリバー』、安直なクンフーのグローバル化
 やっとの思 いで完成させた『ミスティック・リバー』に関するテクストではありますが、読み返してみると、予告していたとおりなんとも纏まりを欠いたものに仕上がっています。もはや言い訳は不可能、誰に頼まれたわけでもないのですから、これはこれで甘受せねばなりません。しかし、今回苦労したのにはもうひとつの理由が。それ は 他でもない私自身の“怠惰”にあるのですが、簡単に“怠惰”と書いてはいても、その途方もない力はとても人間の太刀打ちできる代物ではなくて、“誠実”であるこ とはいささかも抵抗足りえず、“責任感”すら雲散霧消させてしまうほどの、邪悪な力なのであり、これに抗うのは並大抵ではありません。こちらの意思や決意すら、あっさりと踏み潰してヘラヘラ笑っている存在、それこそが“怠惰”の恐ろしさです 。おそらくこれほどの屈辱を味わったのは、大学受験のために勉強していた時以来ではないかと思います。「よし、ちょっと眠いから2時間だけ寝て、また再開しよう」などと前向きに、しかし安易な私の思いをことごとく打ち砕き 、仕舞には「結局眠気をこらえて勉強しても頭に入らないから無駄だ」とまで思わせてしまう。あの時は見て見ぬ振りをしてやり過ごしましたが、未だに彼奴は私のすぐ真後ろでニタニタ笑っていたということになります。何たる恐ろしさ…これは全く言い訳ではなく、紛れもない真実なのです!! と声を荒げておいてこのバカ バカしい話題にけりをつけ、次の話題に移るとします。
やっとの思 いで完成させた『ミスティック・リバー』に関するテクストではありますが、読み返してみると、予告していたとおりなんとも纏まりを欠いたものに仕上がっています。もはや言い訳は不可能、誰に頼まれたわけでもないのですから、これはこれで甘受せねばなりません。しかし、今回苦労したのにはもうひとつの理由が。それ は 他でもない私自身の“怠惰”にあるのですが、簡単に“怠惰”と書いてはいても、その途方もない力はとても人間の太刀打ちできる代物ではなくて、“誠実”であるこ とはいささかも抵抗足りえず、“責任感”すら雲散霧消させてしまうほどの、邪悪な力なのであり、これに抗うのは並大抵ではありません。こちらの意思や決意すら、あっさりと踏み潰してヘラヘラ笑っている存在、それこそが“怠惰”の恐ろしさです 。おそらくこれほどの屈辱を味わったのは、大学受験のために勉強していた時以来ではないかと思います。「よし、ちょっと眠いから2時間だけ寝て、また再開しよう」などと前向きに、しかし安易な私の思いをことごとく打ち砕き 、仕舞には「結局眠気をこらえて勉強しても頭に入らないから無駄だ」とまで思わせてしまう。あの時は見て見ぬ振りをしてやり過ごしましたが、未だに彼奴は私のすぐ真後ろでニタニタ笑っていたということになります。何たる恐ろしさ…これは全く言い訳ではなく、紛れもない真実なのです!! と声を荒げておいてこのバカ バカしい話題にけりをつけ、次の話題に移るとします。
昨日テレヴィで放送していた『クリムゾン・リバー』、まぁ、こんなもの観ているからいつまでたってもテクストが書きあがらないんだyo! というセル フ 突っ込みはさておき、確かヴィデオが発売された直後に見ていたのですが、せっかくジャン・レノとブノワ・マジメルがわざわざ日本まで来たのだから、リュック ・ベッソン脚本などという安易なアジテーションみたいな宣伝文句のせいではないとは言え、多分劇場では観ないだろう『クリムゾン・リバー2』の代わりに、もう 一度見直してみたわけです。いつ頃からそうなったのかは覚えていませんが、現在「日曜洋画劇場」では、作品が始まる前に著名人による見所解説みたいなものが あって、どういう経緯で決められるのかはわかりませんが、今回は作家の猪瀬直樹氏がそれを担当していました。彼の発言のなかで「映像がいい」というものと「 黒の存在感がある」みたいなものがありましたが、あまりに具体性を欠いたその発言は、いくらテレヴィとはいえ、容易に納得しがたいところがありました。今は亡 き淀川長治氏が解説を担当していたころと比べるのは酷でしょうが、あのような無意味な解説の意味を問いたい気分です。さて、そんなことはさておき、この 映画にはヴァンサン・カッセルによるクンフーアクションシーンがあります。何よりもこのシーンに対する違和感があったのは、そこに物語的必然性が全く無いか らで、例えばヴァンサン・カッセルの強さを示したかったのだとしても、それがクンフーである理由は無いですし、その後のシーンにおいても、ヴァンサン・カッセ ルは強い存在というより、ジャン・レノに対する“無鉄砲な若手刑事”以上の説話的役割を与えられていなかったとさえ思われ、そうなってくるとあのシーンは一種のサーヴィスなのだと言ってしまえばそれまでですが、それならばもう少し格闘シーンを増やしたほうが良かったのではないかという気がします。つまり、いかにも中途半端だったあのクンフーアクションは、あの程度のアクションで満足する観客のためだけに向けられたのであり、恐ろしく退屈な場面でした。映画における強さとは 、決してそんなものではないはずです。
それはそうと、もうひとつ気になったのは、何故ドミニク・サンダがあのような役を引き受けるに至ったのかということです。猪瀬氏の言う“黒さ”に支配された部屋で顔の半分も見えず、一瞬の光が当たったかと思えば、目を潰したと思 わ れる特殊メイクで画面に映るのみでした。『暗殺の森』の彼女の、目を見張るよ うな美しさばかりを思い出してしまうのはいささかノスタルジックすぎるのかもしれませんが、彼女も苦しい状況にあるのでしょうか。真意はわかりませんが、寂しさが募ります。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]