2004年05月31日
『ウェイキング・ライフ』に始まりイーストウッドで締める週末
 『エレファ ン ト』を観て以来、映画館からやや遠ざかりつつあるのですが、ただなんとなく暑くて渋谷の雑踏から出来るだけ遠ざかりたいというだけの理由しかなく、仮にも自身を“映画好き”とは言いがたい現状にいたたまれない感じがしないでもないのですが、それでもTSUTAYAにだけは足を運んで、ヴィデオを5本ほど借りてきまし た。
『エレファ ン ト』を観て以来、映画館からやや遠ざかりつつあるのですが、ただなんとなく暑くて渋谷の雑踏から出来るだけ遠ざかりたいというだけの理由しかなく、仮にも自身を“映画好き”とは言いがたい現状にいたたまれない感じがしないでもないのですが、それでもTSUTAYAにだけは足を運んで、ヴィデオを5本ほど借りてきまし た。
『テープ』におけるミニマムな手法には舌を巻くほかなかったリチャー ド・リンクレイターの前作『ウェイキング・ライフ』、これは、私の数少ない友人の中でも、とりわけ映画好きな部類に入る若手建築家T氏による、熱いリコメンド によってようやく手にとったわけですが、こちらの期待を裏切らない作品でした。 その理由は、『ウェイキング・ライフ』がアニメーションに対する一つの批評でもあるのではないか、と言う点に存しています。その前に、“アニメーションは映画 なのか”という問いがなされなければならないと思いますが、厳密に言えば“映画” ではないアニメーションが堂々とアカデミー賞を取ってしまうくらいですから、現在の一般的な認識は誤っているというか、そもそもそんなことは考える必要すらなくな っ てきているのかもしれません。まぁ、ここではその話は置いておいて話を戻すと 、アニメーションは、ある“物語”にしかるべき“絵”を付与した結果生み出されるもので、であるからこそ、そこには(映画で言う)即興的なものははじめから排除さ れ、偶然の入り込む余地などないはずです。その意味で“物語”とは不可分なアニメーションであるはずの『ウェイキング・ライフ』には、しか し、“物語”など無いに等しく、あるのは人間と動作と言葉だけなのですが、それは言うまでも無く、まず“映画”として撮られたものにMACによるデジタルペインティン グが施されたからで、ここにおいて、『ウェイキング・ライフ』は“アニメーシ ョンであり、映画だ”という、やや矛盾を孕んだ結論が下されると思います。劇中でも、映画とは決して“先ずストーリーありき"ではなく、“先ず人間ありき、大事なのは聖なる瞬間を撮ることだ”と語られていたように記憶していますし、中盤に出てくるあの、ストーリーの無い小説を書く男との対話も、その事実を示唆しているかと。本当に興味深い映画でした。
その後、『ラブ・ストリームス』『カリフォルニア・ドールス』、そして 『恐怖のメロディ』といずれも傑作のアメリカ映画により、こちらの感性を心地よく刺激されたのですが、その後に観る予定だった『ブラックサンデー』にはオープニングからどうにも乗れず、結局は20分くらい見て深い眠りにつきました。上記のうち未見だった『ラブ・ストリームス』よりも、2度目に観た『カリフォルニア・ドールス』が相変わらず面白く、あきらかに「ここは笑うシーンだ」と記憶していたにもかかわらず、そのシーンになるとただ只管笑い転げたという事実により思い起こされるのは、「そういえば、『少林サッカー』以来久しく劇場で笑っていないな…」という事実で、最近では『KILLBILL Vol.2』における、中国での修行シーンに乾いた笑いを誘われたものの、それでも笑い転げるとまではいかなかったので、もっともっとアメリカ映画に笑わせてほしいと強く思った次第です。
2004年05月26日
『ぼくの小さな恋人たち』、何故こうも美しいのか…
青山真治氏をして“ 非妥協・非転向の作家”と言わしめたジャン・ユスターシュが1974年に撮った作品です。ル・コルビュジェが建てた住宅群があることでも知られるフランスの田舎・ペサックを舞台にしていますが、その長閑な舞台から予想されるノスタルジックな 印象など実はあまりなくて、それよりなにより興味を抱いたのは、主人公・ダニエルが歩く速度、というか歩くシーンそのものがすばらしく、数回出てくるこの歩くシーンを見た瞬間、『カノン』のフィリップ・ナオンを思い出さずにはいられませんでした。早くもゆっくりでもなく、本当に絶妙としか言いようのない速度を保ちながら、ダニエルが歩くシーンが数シーン出てくるのですが、『カノン』におけるような“独善的モノローグ”が歩行に重なることで、彼の強い意志、というかほとんど不条理なエゴイズムを印象付けたのに対し、本作において、ダニエルの目線はどこを見ているのかもわからず、無論歩いているのだから前を向いているのでしょ うが、果たして未来を見ているのか、過去を思い出しているのか、もしくは、目の前の女の子を見ているだけなのかまったくわからず、だとするなら、一連の歩行シーンに感動したのは、彼の歩行という運動そのものに惹かれていたのだということになります。
もうひとつ印象的だった箇所、それは、ダニエルが少しだけ成長し、言い換えれば大人になって、離れていた故郷に戻るところで映画は終わるのですが、ラストシーンで、ダニエルは友達だった女の子に再会し、嘗てのように無邪気さを装ってその女の子と遊ぶのですが、このとき、大人になってしまったダニエルがその女の子の胸に触る瞬間の表情が画面に映ったとき、その不意打ちの美しさに非常に感動しました。明らかに行き過ぎた行為をしてしまったダニエルの表情に刻まれた諦念は、そのまま本作全体に纏いつくトーンに他ならなか ったのです。だからこの映画は決してノスタルジックな青春映画なのではなく、ついに女性を嫌悪の、と言って悪ければ、性の対象として見てしまうことになる少年の、残酷な未来と憂いとを捉えた、極めて陰鬱な映画です。アルチュール・ランボーの詩から引用されたタイトルもそれを示唆しているかと。だからと言って、その事実は『ぼくの小さな子供たち』の価値を貶めるものでは決してなく、むしろ掛け値なしの傑作だと強く思う次第です。
2004年05月24日
『KILLBILL VOL.1/VOL.2』、映画とのラブストーリー
映画を観にいく時、その大小はあれど何らかの“興奮”を隠し切れないものですが、それはこれから観る映画の期待値にかかわらず、まさに“映画を観に劇場に足を運ぶ”ことに起因する興奮なのだと思います。映画を観に行くということ自体が持つ“興奮”、しかし、時としてこの“興奮”が度を越してしまうと、話は厄介です。冷静さを失い、“興奮”そのものに埋没してしまいかねないから。
ある意味“過剰”とも言えるそんな興奮を覚えることは至極稀です。しかしながら、クエンティン・タランティーノが6年ぶりに撮った『KILLBILL』には心底興奮したと告白しなければなりません。私自身の映画的ルーツである香港アクション映画への郷愁や、それが『新・仁義なき戦い』のテーマだと分かってはいても、画面との奇妙なマッチングにやはり興奮せずにはいられない布袋寅泰によるギターサウンドや、もちろん、タランティーノが久方ぶりに見せてくれるであろう、極度のシネフィル的サンプリングにも、その異常な興奮の原因を認めることが出来るかもしれません。しかし、それにも増して痛感した事実、それは、久しく意識していなかった“劇場に足を運ぶことの喜び”と、『KILLBILL』に溢れるタランティーノの“映画への愛”が、奇妙な形でシンクロしたかのような錯覚を覚えてしまったからなのかもしれません。この時点で私は、いささか冷静さを欠いていました。これは極めてまずい状態です。果たして、『KILLBILL』は手放しで賞賛すべき作品でしょうか? その問いに答えるには、今一度我に変える必要があるでしょう。
まず最初に、『KILLBILL』が2編として公開されたことについては、この際目を瞑りたいと思います。それを1本の作品として観たかったのは言うまでもありませんが、タランティーノ自身、ハーヴェイ・ワインスタインの提案を悪く思わなかったどころか、そんな“贅沢”が許されるならと、自ら面白がっていたのではないか、とも思えるからです。そして、すでに2編に分けられ公開されてしまった以上、まず前提としてそれを受け入れなければならない。以下は、2編を観終えた私の、言ってみれば苦さと幸福さとが混ざり合った、複雑な心境の告白でです。
さて、改めて冷静さを取り戻して考えてみれば、『VOL.1』は決して傑作とは言えません。タランティーノ的サンプリングの元ネタ探しに躍起になってみたり、飛び交う不自然な日本語に笑いを求めたりするという楽しみ方が無かったわけではありませんが、そのような喧騒に惑わされてしまうことにより、『VOL.1』に偏在する数々の欠点を見逃してしまうことは全くナンセンスだと言うほかはないでしょう。
“復讐は冷えてからが一番おいしい料理だ”『VOL.1』の冒頭に、そんな古い諺が出てきます。“冷える”とは言うまでも無く、時間の経過を意味します。これにより『KILLBILL』における復讐は、そう簡単に達成できないのだと知らされます。それは極めて長い道のりです。だからといって、タランティーノにおける“時間”とは、一方向に流れていくだけのものではないのは周知の通りです。つまり観客は、その復讐に途方も無い時間を要したという意識が希薄なまま、この復讐を追っていくしかないのです。実際、ユマ・サーマン演じる主人公が記する“復讐ノート”を見ると、決して順番どおりに復讐を達成していないことがわかります。ルーシー・リュー、そしてヴァニータ・グリーンは、ノートに見られる順番とは反対に死んでいくのですから。それは恐らく、青葉屋における大掛かりなアクションを『VOL.1』の見せ場にするためでしょう。事実、ヴァニタ・グリーンとの格闘は、物語の“つかみ”にこそふさわしい。死闘にいたるには青葉屋という装置が不可欠であり、『VOL.1』はその死闘により、ユマ・サーマンの強さのみが際立って終わるのです。あまりに無駄と言うほかない細部の描写、すなわち、沖縄で千葉真一と絡む挿話や、飛行機に絡む諸々のシーンや、たとえプロダクション I.Gが監修したとしても“オカズ”の一つに過ぎないアニメーションシーンなどは、説話的必然性を甚だしく欠き、ご愛嬌としては許せるという程度です。ということはやはり、『VOL.1』では、何よりもザ・ブライドの強さを後半部分への強い印象として残せばそれでよかったと言うことが出来ます。
ところで、『KILLBILL』の武術指導はユエン・ウーピンですが、もはやその事実は大きな期待を抱かせる要因にはなりません。その理由は彼の“相対的な”ネームバリューの低下に存しています。彼のハリウッドにおける特権は、作品を連発することで次第に薄められてしまいました。だとするなら、注目すべきは“誰が振付けたのか”ではなく、アクション自体が“どう撮られているか”ということになるでしょう。「そんなことはわかってるよ」と言わんばかりに、香港アクションフリークのタランティーノは、流石にその勘所は心得ているかに見えます。ヴァニータ・グリーンとの格闘を観ると、アタックとダメージの切り替えしが非常に効果的で、言い換えれば、そのカット割りは明らかに香港映画のそれだったと思います。お茶目な彼はいかにもオタクらしく、冒頭にショーブラザーズのマークなど入れてみるのですが、そんなサーヴィスなど無くてもアクションをみればそれが香港映画的だと了解できるのです。しかし、香港映画の枠をはみ出さないという点で、決して新しくはない。その代償としてかどうかはわかりませんが、『VOL.1』には、あまりに“過剰な”サーヴィスが溢れています。いや、それは観客へのサーヴィスではなく、彼が単にやりたかったことなのかもしれないのですが…(それが悪いとは言いませんし、むしろそこにこそ『VOL.1』の美点があるという見方もあるでしょう)。
閑話休題。ほとんど漫画的な強さだけが強調された『VOL.1』とは打って変わって、『VOL.2』は愛の物語です。その分、前編に比べて非常に地味な印象が拭えません。しかし、この落差に戸惑う暇もない程、実に堂々とした演出とシーン構成の冴えが全編に漲っています。その事実は、冒頭、モノクロームで撮られたデヴィッド・キャラダインとユマ・サーマンによる一連の会話とその後の殺戮を、教会の外側からのロングショットによって隠すという手法を観れば明らかだと思います。緊張感溢れる至近距離からの銃撃シーンをアップで捉えた『VOL.1』のファストシーンに対し、『VOL.2』では同じ舞台を全く別の次元で捉えている。始めから2部作を想定して撮られたと思うくらい、的確なオープニングです。さらに付け加えれば、『VOL.2』ではタランティーノ的“会話”を取り戻しているのです。『レザボア・ドッグス』から一貫して“(無駄な)会話”に拘ってきたタランティーノは、全体として決して派手なアクションの人ではなかったはず。その意味で、本来の姿に返ったと言うのは大袈裟過ぎるでしょうか。
例えば、マイケル・マドセンと彼が用心棒として働く店の店主との会話、あるいは、デヴィッド・キャラダインとユマ・サーマンの蜜月時代を回想するシーン(燃える炎を前に会話するシーンの美しさ)、さらには、まさに死につつあるマイケル・マドセンを前に、ダリル・ハンナがブラックマンバの猛毒ぶりを説明するシーンを想起しても良いですが、これらのシーンにおける演出の的確さは、才能ある“アメリカ映画”作家としてのタランティーノの“上手さ”を理解するのに充分過ぎるくらいです。『VOL.2』は、地味ですが良質の“アメリカ映画”という位置づけが可能だと思います。今、こういう“真面目なアメリカ映画”を撮ることが出来る監督が何人いるでしょうか。そう、『VOL.2』はすこぶる真面目な映画なのです。
この真面目さは、中国での修行シーンにおいても変りはしません。ゴードン・リュー演じるパイ・メイは、クンフー映画に不可欠とも言える“師匠”という役柄をそっくりそのまま生真面目に反復してみせます。あの、冗談かとも思えるような、過剰な演出というか模倣。にもかかわらず、ゴードン・リューがその長い顎鬚をなでながら「うむ」と頷く時、この図式的な演出と潔い御都合主義が、幸福に出会ったかのごとく画面が潤ってはいなかったでしょうか。だからこそ、千葉真一のご愛嬌的シーンとは比較にならないその真面目さに、私は感動せざるを得なかったのです。『VOL.2』において個人的に大好きなシーンであるあの修行シーンは、ほとんど逸脱寸前のところでかろうじて踏みとどまっている感もありますが、それが許される土壌を結果として築いてしまっているタランティーノは幸福であり、それこそが才能なのだと思いたい。何故なら、香港映画ファンに向けて作られているのかもしれない(もしくは、
ただそれを撮りたかっただけなのかもしれない)一連の修行シーンは、しかし、物語上無くてはならないシーンでもあるのです。タランティーノは、中国ロケを心底楽しんだのではないかとすら思いますが、それが見ているこちらに伝わるからこそ、冒頭に書いた“興奮”へと無防備に陥るほか無かったのです。
『VOL.2』が愛の物語だとは既に書きました。この壮大なラブ・ストーリーは、デヴィッド・キャラダイン無くしては成立し得なかったと思います。しかし、最終的に殺しあう二人が、子供を前に会話する場面の奇妙な違和感はただごとではありません。それは恐らく、あの子供の描き方によるものでしょう。彼女は、子役として役を“演じて”いるのだという当たり前の事実を、最後まで画面に定着させませんでした。つまり、“子供”としてただそこにいた、と言えばいいでしょうか。デヴィッド・キャラダインとユマ・サーマンの宿命的な対決など端から頭に無い彼女は、ひたすら無邪気ですが、無邪気さという演出的なカテゴリーにも収まってはいなかったはずです。これはタランティーノ映画において、一つの事件ではなかったかと思います。物語への加担を拒むような彼女の存在。それが違和感につながりつつ、さらにその先にある感動へと私を導いたのです。
もちろん、デヴィッド・キャラダイン以外にビル役はありえないと断言したくなるほど、彼の存在は異常なセクシーさを醸しだしていましたし、とりわけ、子供に食事を作ってあげるシーンの何気なさに潜むエロティシズムを秘めた声と動作には舌を巻きました。最後の対決を前に、ユマ・サーマンと会話するシーンの、悪役以上の人間的ずる賢さを体現するキャラダインは、『VOL.1』にほとんど出演していませんが、それは『VOL.1』がラブ・ストーリーではなかったからです。
でも、いささか強引ですがこう考えてみることは出来ないでしょうか。つまり、『KILLBILL』という途方も無いサーガは、映画への愛だけで一篇の映画を創り上げることが出来るかという、ほとんど図々しいまでの試みで、そうであるなら、『KILLBILL』は2編を通して、タランティーノと映画自身のラブ・ストーリーなのだ、と。映画好きの監督と、映画によるラブストーリーを地で演じること。これを嫉妬を込めずに見守ることは、私には不可能でした。よって、これまで書き連ねてきた文章は、そんなラブストーリーに嫉妬した人間の、恨み言のようなものだったのかもしれません。
2004年05月22日
『ミスティック・リバー』、視線の残酷な法則
 すべての監督作品を観たわけではないので、飽くまで個人的体験の範囲内に限られてしまいますが、クリント・イーストウッドの作品について何かを語ることには、決まって困難が付きまといます。その監督作品を第三者に薦めることには何の躊躇も抱きはしませんが、作品が孕み持つ“凄さ”を容易には言い表せないからです。初監督作『恐怖のメロディ』では、驚くべき才能を感じ、『許されざる者』では、その厳しさに戦慄を覚えました。しかしだからといって、たとえばヴィム・ヴェンダースの、あるいはサム・ペキンパーの、もしくはフランソワ・トリュフォーの作品を薦めるときのようにはいかないのです。しかし、その理由は未だに判然としません。24本目の監督作『ミスティック・リバー』という“恐るべき”作品を観終えたとしても、やはり事態は一向に改善されないのです。はじめからこんなことを書いてしまうと、あたかもこれから『ミスティック・リバー』について何らかの言葉を連ねようとしていること自体の不可能性を予め告白し、その困難から逃げようとしているかのようですし、敢えて言うならまったくその通りです。そんな負け戦に挑もうとしているのも、それは『ミスティック・リバー』がそうさせるから、と言わざるを得ません。よって、以下の文章にはある種の諦念が含まれていますが、泣き言はやめて本題に入ります。
すべての監督作品を観たわけではないので、飽くまで個人的体験の範囲内に限られてしまいますが、クリント・イーストウッドの作品について何かを語ることには、決まって困難が付きまといます。その監督作品を第三者に薦めることには何の躊躇も抱きはしませんが、作品が孕み持つ“凄さ”を容易には言い表せないからです。初監督作『恐怖のメロディ』では、驚くべき才能を感じ、『許されざる者』では、その厳しさに戦慄を覚えました。しかしだからといって、たとえばヴィム・ヴェンダースの、あるいはサム・ペキンパーの、もしくはフランソワ・トリュフォーの作品を薦めるときのようにはいかないのです。しかし、その理由は未だに判然としません。24本目の監督作『ミスティック・リバー』という“恐るべき”作品を観終えたとしても、やはり事態は一向に改善されないのです。はじめからこんなことを書いてしまうと、あたかもこれから『ミスティック・リバー』について何らかの言葉を連ねようとしていること自体の不可能性を予め告白し、その困難から逃げようとしているかのようですし、敢えて言うならまったくその通りです。そんな負け戦に挑もうとしているのも、それは『ミスティック・リバー』がそうさせるから、と言わざるを得ません。よって、以下の文章にはある種の諦念が含まれていますが、泣き言はやめて本題に入ります。
『ミスティック・リバー』に善悪の二項対立は存在しない、とまずは言うことが出来ます。仮にそのように見えるもの同士の葛藤があったにせよ、両者は互いにいつその立場が逆転するかわからないからです。いみじくも、ショーン・ペン扮するジミーが言っているように、「些細な決定が人生を変えてしまう」のだとすれば、両者は一瞬でいれかわる可能性を秘めていると言えます。その意味で、“流れ”は消して人間の意志で変えられるものではない、というのが『ミスティック・リバー』の主題だと思います。ここで言う“流れ”とは、“人生”という言葉に換言することも出来、また、タイトルでもあるMystic Riverの流れそのものを指してもいます。
ここで唐突に「mystic」という言葉の意味を調べてみると、
-----------------------------------------------------
mys・tic [mistik]〔形〕《通例限定》
1 (聖霊などを)象徴する,霊妙な
2 秘伝の,秘密の,魔術的
3 不可解な,なぞの.
4 神秘論者の;神秘主義の.
プログレッシブ英和中辞典第3版 より(小学館刊)
-----------------------------------------------------
とあります。ボストンにMystic Riverという川が実在するかどうかは知りません。しかし、劇中のあの暗く不吉な川は、上記1〜3のいずれかの意味に当てはめて考えると、(なんとなく)しっくり来るのでないでしょうか。つまり、Mystic Riverは“(匿名の)謎めいた川”として在るのであって、実在するかどうかはやはり問題ではないでしょう。
閑話休題。さて、この物語は極めて悲劇的だと言う外ありません。起きてしまったことを悔やむことも、別の選択肢を選んだ可能性を思い描くことも、共に許されてはいないのですから。そして、『ミスティック・リバー』において、その悲劇性はまず、同じ高さで交わることのない視線によって、より印象付けられると思います。劇中に幾度と無く出てきた、上方から下方に放たれる視線の存在。では、それは何故か。“視線の高低差”はある決定的な事実を表しています。すなわち、上方から視線を受ける存在である下方にいる人物は、物語上より多くの悲劇を引き受けなければならないという残酷な法則です。このことから『ミスティック・リバー』は、極めて厳しい視線よるサスペンスだと言うことが出来ます。
例えば『ミスティック・リバー』において、多くのシークエンスがヘリから川を映した俯瞰撮影で始まるのはもちろん偶然ではなく、ラストを除けばほとんどが暗く、不吉な印象を与えるこのショットは、その短さに反比例して非常に陰鬱とした印象を与えますが、それは主題そのものを語っているのです。一方通行の川の流れが暗示するのは、どうにもならない運命性にとどまらず、カメラに見下ろされたが故の悲劇性です。その意味で、常に見下ろされるしかないこの川こそが最も悲劇的な舞台であるのは言うまでもありません。だからこそ、「謎めいた川」は殺人の舞台として選ばれることにもなるのでしょうし、その結果、「罪」だけが沈殿していくことにもなるのです。
ここで思い出したいのは、ティム・ロビンスが最も見下ろされていた人物だという事実です。妻であるマーシャ・ゲイ・ハーデンは、幾度となく彼に上からの視線を浴びせていましたし、殺害されるショーン・ペンの娘・ケイティと彼がバーで偶然出会う場面でも、カウンター上のケイティを一方的に見上げることしか出来ませんでした。そもそも、少年時代にデイブだけが連れ去られ、幼児性愛者の二人組みによって監禁され、暗闇が支配する穴倉において、彼らから最初に見下ろされた時点で、すでに悲劇は避けられない運命にあったのです。冒頭のストリートホッケーのシーンにおいて、少年時代のティム・ロビンスが誤ってボールを排水溝に落としてしまいますが、実際に落ちたのはボールの形をしたデイブの少年時代そのものだったのではないでしょうか。排水溝に流れる水はやがて川に流れ出るかもしれませんが、ボールだけはずっと底から出て行くことはないのですから。
『ミスティック・リバー』において、「あの時こうしていれば…」という後悔は許されません。どれほど悔やんでも、大きな流れそのものは変わらないし、決して後戻りはできないのです。『ミスティック・リバー』における最大の悲劇は、映画においてでさえ、時間は取り返せないという事実に存しています。ラストに映る、日を受けた川の流れは、感動的でもあり同時に悲しくもあります。罪が埋められ、その罪を洗い流そうとするミスティック・リバーを観る者はこの時、数度にわたり繰り返された、川の俯瞰撮影の意味を理解するでしょう。そして同時に、深い魂の揺れを体験することになります。この魂の揺れは、感動という一語には置き換えられない何物かです。それが何なのかは、やはりわからないままなのですが…
2004年05月21日
『息子のまなざし』、カメラと物語の共存
 「Le Fils」という原題は仏語で“息子”という意味です。映画興行の視点から見れば、原題と邦題に奇妙な差異が生まれるという現象は今では珍しくありませんが、その邦題に鼻白むことが多々あっても、この映画のように積極的に肯定したくなるものは少ないと思います。極私的な結論を言えば、この邦題も含め、「息子のまなざし」は傑作と呼ぶに値します。あの感動的なラストシーンにはそう言わせるだけの強度がありました。観客の視線が唐突に断ち切られたとき、何かが終わるのではなく、でも何かが始まる確信も持てません。「息子のまなざし」と言う映画において、カメラはただ2人を見つめていたのであって、いや、それしか出来なかったのだという(当たり前の)事実だけが残るのです。観るものの瞳がスクリーンから離れて行く前に、2人を見ていた“まなざし”が、自らの瞳を閉じてしまった、とも言えるかもしれません。感動的なのは、映画が終わっても、2人の行方に安易に結論めいたものを出さず、だからといって厳しく突き放すでもない、まさに不可視の存在としての“まなざし”が確かにそこにあった、と感じることが出来たことです。この“まなざし”の持つ力が、そのまま映画の力となっているのですから。
「Le Fils」という原題は仏語で“息子”という意味です。映画興行の視点から見れば、原題と邦題に奇妙な差異が生まれるという現象は今では珍しくありませんが、その邦題に鼻白むことが多々あっても、この映画のように積極的に肯定したくなるものは少ないと思います。極私的な結論を言えば、この邦題も含め、「息子のまなざし」は傑作と呼ぶに値します。あの感動的なラストシーンにはそう言わせるだけの強度がありました。観客の視線が唐突に断ち切られたとき、何かが終わるのではなく、でも何かが始まる確信も持てません。「息子のまなざし」と言う映画において、カメラはただ2人を見つめていたのであって、いや、それしか出来なかったのだという(当たり前の)事実だけが残るのです。観るものの瞳がスクリーンから離れて行く前に、2人を見ていた“まなざし”が、自らの瞳を閉じてしまった、とも言えるかもしれません。感動的なのは、映画が終わっても、2人の行方に安易に結論めいたものを出さず、だからといって厳しく突き放すでもない、まさに不可視の存在としての“まなざし”が確かにそこにあった、と感じることが出来たことです。この“まなざし”の持つ力が、そのまま映画の力となっているのですから。
“まなざし”とは、ひとまず映画におけるカメラの視線に置き換えてみることができます。そして、私自身は「息子のまなざし」を題名の通り“まなざし(=視線)の映画”だと思わずにはいられません。例えば、オリヴィエとアガリが、最初に会話するシーン。オリヴィエが住む、それほど広くはない部屋で2人は向き合っています。お互い何を言ったら良いのかわからない(いや、実際はそういう記号すら無かったかもしれません)表情を、カメラは、切り返しや(効果的な)クローズアップという技術とは無縁の領域で、元夫婦の無言の横顔を数回に渡り、右へ左へパンします。そこでは、視線が行き交うのではなく、濃密な停滞を余儀なくされ、結果、ある種の“淀み”を画面に定着させていました。その“淀み”が何なのか、まだこの時点ではわかりません。この映画全体を通して言えることですが、ダルデンヌ兄弟はこのシーンでもカメラの存在を観客に十分意識させています。この居心地の悪さはなんだろう、と思いつつも、しかし、物語がどのような方向に進んでいくのかがわからないのでどうすることも出来ない。
居心地の悪さと言えば、本作にはオリヴィエとフランシスが並んで食事するシーンが2回あります。夜食を食べに来たオリヴィエが、期せずしてフランシス会ってしまうシーン。そして、材木工場に向かう途中で立ち寄るカフェで、休憩がてらアップルパイを食べるシーン。この2シーンは物語上重要ですが、それが食事のシーンだからと言って、二人を饒舌に喋らせることはもちろんありません。結果として、これらのシーンを経るごとに二人の物理的・精神的な“距離”は少しづつ近づいていきますが、見ていてここまで居心地が悪く、同時に感動的だったシーンは、記憶を辿っても簡単には思い出せません(カサヴェテスの「こわれゆく女」で、ジーナ・ローランズが夫であるピーター・フォークの仕事仲間たちに食事をもてなすシーン。いつ破綻するかもわからないというギリギリの緊張感のなかで、誰かが歌ったり笑ったりしているという、やはり居心地が悪く、同時にほとんど奇跡のようなシーンでしたが、それとも違うような気がします)。
話を元に戻せば、この作品では、何故カメラの存在をあからさまに意識させていたのか、その必然性があったはずです。映画は、カメラの存在を意識させないことで成り立ってきたようなもの、とはいまさら言うまでもありません。とすれば、いかにも不自然にカメラの存在を誇示させる本作は、そうするだけの意図があったのではないでしょうか? 本来視線は目に見えません。しかし、見えないはずの視線を“感じた”時、ある予感が不意に頭をよぎりました。実は、未だにそれが何だったのかという結論は出ていません。恐らく監督は、何かの“答え”を導き出すことを、周到に避けていたのではないでしょうか。詳細な説明(描写)によって、観客の自由を奪うことに抗うつもりだったのかもしれないと言ったら言いすぎかもしれませんが、このように目に見えない監督の意図などに思考をめぐらせるより、スクリーンに見えていることから何かを導き出すほうがより現実的なので、この話はここら辺で。
それはそうと、どうやってこんなシーンを撮ったのか? と思わせるようなカメラとオリヴィエの距離。ダルテンヌ兄弟は、限界まで対象に近づけるよう「ミニマ」というカメラを使用したそうです。オリヴィエの眼鏡越しにフランシスをのぞき込むシーンや、車中のシーン見られる強烈な現実感は、それに追うところが大きいと思います。“まなざし”は、自在に動く足を獲得し、オリヴィエの後ろ姿に隠れ、フランシスの寝顔をのぞき込み、その都度逡巡しているかのようでした。だから(と言えるかどうかわかりませんが)、本作からは押しつけがましい主張が感じられない。それは、カメラ自体の迷いみたいなものが画面を覆い尽くしているからかもしれません。
いわゆる“叙情的”な編集や、それに準ずる描写の不在。もっともらしい演技の不在。効果的な音楽の不在。「イゴールの約束」も「ロゼッタ」もまったく同様の撮り方をしていたような気がします。このスタイルは、しかし、観客を圧迫するものではなく、音楽の不在に関して言えば、本作においてその背景に流れる“音”は、音楽の不在に反してかなり積極的に耳に残ります。そこに聞こえるのは、金槌で釘を打つ音、電ノコで木を切る音、そして、車のエンジン音や、二人の足音… どれもが、ただ音としてそこにあります。あまりに日常的過ぎて聞き流してしまいそうなこれらの音ですが、これら音の断片が、作品に忘れがたいリズムを刻み込んでいるのは、否定できません。音それ自体が、通常のボリュームを超えて、映像と並置していたような気がするからです。私にはゴダールが作り出した“ソニマージュ”という言葉が想起されましたが、それは、先述した音と映像の、主従関係のない共存を実感したからです。
さて、最後にもう一度“まなざし”に話を戻すと、この映画における“まなざし”とは、誰かのものだったのでしょうか。最初に述べた邦題うんぬんに関する部分で、その結論は出ているようなものです。映画制作に不可欠な存在であるカメラ(=まなざし)とその存在を、目に見えない“物語”と並置させること。この事実だけ見ても、ダルデンヌ兄弟の並ならぬ才能が見て取れるのではないでしょうか。
2004年05月20日
『ブラウン バニー』、アメリカと同化したヴィンセント・ギャロの孤独
映画監督ヴィンセント・ギャロは、主人公パド・クレイではない、という、ごく当たり前の事実の確認をしたくなるほど、この映画をめぐる数々の文章には、「監督=主人公」という図式を当てはめないと気が済まないようなものが多いような気がします。というのも、例えば「この映画はヴィンセント・ギャロのナルシスティックなオナニー映画だ!」という意見に見え隠れする、一見正当性を持ってしまいかねない「監督=主人公」という図式が、決定的に的を外しているからです。「ブラウン・バニー」とは、恋愛に対して全くオナニーの域を出ない、孤独で、強烈なエゴイスト=パド・クレイを、監督=ヴィンセント・ギャロが、ほとんど神経症的な真摯さで、“誠実に”撮った映画だと思うのです。恐らく、“「ブラウン・バニー」=監督のオナニー映画”と評する人は、ヴィンセント・ギャロを積極的に嫌いなのかもしれません。多くの同時代的な、(アメリカ的)感性と「ブラウン・バニー」には、大きなズレもあるのでしょう。製作/監督/音楽/撮影/主演と、全てをコントロールせねばならないというオブセッションからくる、病的とも言えるヴィンセント・ギャロの映画へのアプローチは、恐らく全的な肯定か、全的な否定しか生みません。しかし、かような“好き/嫌い”の嗜好性はひとまず置いても、この映画をスキャンダラスでナルシスティックな作品だと断罪するのは決定的な読み違いではないでしょうか。カンヌにおける多くの酷評、アメリカでの猛攻撃が話題づくりに貢献してしまった「ブラウン・バニー」であれば、こういう意見は映画を観なくても言える“つまらない”意見です。「ブラウン・バニー」という映画を語っているつもりが、全く作品外的な“状況”を説明しているに過ぎないと言ったら、本当に“観た”人は怒るのでしょうか。「ブラウン・バニー」が良い映画なのか悪い映画なのかは、あまり問題ではありませんし、誰がどう思ってもかまいません。しかし、「ブラウン・バニー」に関する文章を書く以上、“観た”つもりになって、“観なくても”言えるような言葉を連ねるだけはやめようと思います。いや、これはこの映画だけに関することではないのですが。
さて、この映画は端的に言って、失意のバイクレーサーが車でアメリカを横断する映画、だと言うことが出来ます。ナラティブな面だけに焦点を当てれば単純極まりない。しかし、この“単純だ”という事実は決してこの映画を貶めるものではありません。なぜなら、「ブラウン・バニー」は、観客の感性に直接訴えかける映画で、そこに“複雑さ”は微塵も必要とされていないからです。つまり、ここでの映像に与えられた役割は、観るものの“理解”にではなく、“感動”に直結させることにこそあると言えるでしょう。であるがゆえに、スクリーンには一見退屈な画面が延々と連鎖されていきます。極力複雑さから遠ざかり、飽くまで単純で無愛想な画面の連鎖がそこにはあるのです。車内にカメラがあれば、主人公パド・クレイの横顔と、目の前に続いていく道路を切り取っていくだけ。車外においても、カメラは対象をFIXで見つめ続け、ヴィンセント・ギャロ演じる主人公の姿と、彼をただ受け入れるかのようなアメリカの風景が画面の大半を占める。かつての恋人・デイジーを演じるクロエ・セヴェニーも、合間に挟まれる回想シーンとラスト近くに少し出てくるだけ。言い換えれば、この映画のほとんどが主人公であるパド・クレイとアメリカの風景のみで成り立っています。このことを、監督であるヴィンセント・ギャロは“ミニマル”という言葉で説明しています。「ブラウン・バニー」は、“〜だけ”という言葉の繰り返しにより、全体が構成される映画で、この事実に異論を挟む余地はないでしょう。しかしだからといって、“単純さ”は“分かりやすさ”へとその立場を譲り渡したりはしないのです。例えば、全体を貫く直線的かつ説明的な物語と、視覚的には極度に刺激的でやはり説明的な映像が、観客をある定められた地点に導いていくのが昨今の“ハリウッド大作”(無論、全てではありません)や、それに準じた方法論で撮られた、世界に偏在する“アメリカ映画”(同じく全てではありません)だとするなら、「ブラウン・バニー」のエクストリームなラディカルさは、反ハリウッド的・反アメリカ映画的と言えます。では、以上を踏まえて、「ブラウン・バニー」自体に話を戻してみると、私自身がこの映画のどこにエモーションを見出したのか? という疑問にぶつかります。先述したように、何らかのエモーションがダイレクトに伝わるこの映画において、この疑問に対する答えを説明するのは難しい。なぜなら、この映画を“理解”するという思いこみほど、無益なものは無い気がするからです。よって、以降の文章は、ほとんど悪あがきに終始するでしょう。再度、私が観た「ブラウン・バニー」を思い出してみます。
私が最も感動したシーン、それは、アメリカのどこかの塩田のような場所で、パド・クレイが車からバイクを出し、そしてそのバイクを疾走させるシーンを長回しで捉えたシーンです。カメラは、遠ざかっていくパド・クレイを執拗に追い続けます。彼の姿は次第に小さくなって、最後にはそれが蜃気楼なのか、肉眼で捉えられる現実の姿なのか、わからなくなる。まさしくこの時点で、パド・クレイとアメリカの風景が完全に同化したかのような、奇跡のようなシーンです。パド・クレイとアメリカの風景、どちらが欠けても成立しない「ブラウン・バニー」において、延々と続く道路こそが、バドクレイの孤独であり、抑えきれないエゴでなのではないか。何度も繰り返されるバドクレイの横顔のアップは、そのままアメリカの虚ろな風景であり、纏いつく風(=自然)なのではないか。そんな思いがよぎりました。さらに、延々と続いていく道路といえば、「ブラウン・バニー」におけるほとんどの道路は車内から映されたもので、フロントガラスというフィルターを介して切り取られていました。そして、あのフロントガラスには、雨が乾いた後のような汚れが付着していました。では、なぜ道路は車内から映されねばならなかったのでしょう。想像するに、あの汚れたフロントガラスを介した風景こそが、過去に囚われたパド・クレイの視線そのものだったのではないか、と。雨(=過去)に打たれたまま、拭き取られる事もなくなく放置されたままのフロントガラスと、恋人に先立たれた事実を、過去として受け入れられず目をつぶるパド・クレイ。ここでは、風景とパド・クレイとの境界線があっさり破棄され、互いに過去と闘っている、そんな気がしました。似たような境界線の破棄は、ラスト近く、モーテルでのシークエンスにも見受けられます。その境界線とは、現実と幻想の境界線に他なりません。かつての恋人・デイジーは確かにスクリーンに映っている。すでに亡くなっているはずの彼女なのに、カメラは、幾度と無く彼女の手や足のクローズアップを映していました。まるで現実にそこに居るかのように。その後、それら全てはパド・クレイの幻想だと分かった時、やはりここでも現実と幻想の曖昧な境界線は溶けてなくなっていたことに気がつきます。境界線が溶解すること、過去と現在の差異を認めないこと。私はここに、「ブラウン・バニー」の主題を見ました。
アルチュール・ランボーは、永遠を、太陽が空に溶け込むのを、見つけました。あまりに有名な「地獄の季節」にあるこのフレイズを持ち出したのは、いささか短絡的かもしれませんが、反復され、またその反復を繰り返し、さらに一定のリズムと化した反復もまた反復されるしかないスクリーン上のパド・クレイの行為が、終わることのない“永遠”という一語を想起させたからです。前述した塩田におけるシークエンスでは、パド・クレイが“太陽と空に溶け込”んでいた、といえない事もありません。そして、ラストシーンがまたもやフロントガラスに切り取られた道路で終わっていたという事実が、この思いを強めました。この詩が表しているランボー自身の感覚は知る由もありませんし、お門違いといわれてもしょうがないのですが、パド・クレイはそんな終わらない道路をノロノロと進んで行くしかないのだと思い、そこにいくらかでも“共感”めいた感情を持ってしまった私は、すでに「ブラウン・バニー」を絶賛することしか出来ません。この映画に掴まれてしまい、もはや逃げ場などなくなった、ということでしょうか。そう考えると、あれこれ並べた上記の文章も、不毛な文章でしかないないのかもしれません。それならば今は、その事実をグっと飲み込むしかないと思っています。
最後に、これまでの文章で、ラストの“衝撃的な”部分にまったく触れなかったのは、私なりの倫理というか、意地のようなものです。それにしてもあのシーンは“衝撃的な”というほどのことはなくて、“別段悪くない”という程度のシーンだったと思うのですが、これも個人の感想に過ぎません。それでも一つだけ言うなら、ドゥシャン・マカヴェイエフやジョン・ウォーターズの記憶はそれほど簡単になくなりはしないし、センセーショナルな画面だけを求めて1800円払うくらいなら、このサイトから数秒後に飛べる世界を彷徨うほうがよほど気が利いていると思うのです。
2004年05月19日
映画と旅〜Milano,Paris,Marseille〜

期待は萎んでいき、不安は膨れ上がっていく
 ミラノの夜は、碌に英語も話せない若者をどのように受け入れたのか。どうやらあまり歓迎してくれないらしい。ただ映画が好きなだけの僕には、何の武器も無い。第一日目の夜、ミラノに到着した僕はすぐに途方に暮れることになる。日本から予約したはずのホテルが全く見つからないのだ。無論、電話をするだけの勇気と会話能力など持ち合わせていないのだから、そうなると頼れるのは警察官くらいか。と、そこに2人の警官“らしき”人物いて、貧しい旅人を訝しげに見ている。誰かを助けるという行為とは無縁の、ほとんど悪意に満ちたような視線に怖気づきながらも、僕は「ここに行きたい」とイタリア語で問いかけてみた。旅先で最初の会話。その直後、ああ、失敗だったと思うに到ったのは、何のことは無い、相手の話すイタリア語を1mmも理解できないと気付いたからだ。格好つけてイタリア語なんて話すんじゃなかった。何の収穫も得られぬまま、「Grazie」を連発する情けなさといったら…。その後も数十分歩き回った挙句、結局、目的のホテルはすぐ近くにあった。単に僕がその周りをぐるぐると旋回していただけの話だ。部屋に入るなり、その先の不安に苛まれる。明日から本当に大丈夫だろうか? ふと鞄に目をやると、飛行機でキープしておいた赤ワインが2本あった。今日はこれでも飲んで寝てしまおう。明日は朝早くからパリに発たねばならない。
ミラノの夜は、碌に英語も話せない若者をどのように受け入れたのか。どうやらあまり歓迎してくれないらしい。ただ映画が好きなだけの僕には、何の武器も無い。第一日目の夜、ミラノに到着した僕はすぐに途方に暮れることになる。日本から予約したはずのホテルが全く見つからないのだ。無論、電話をするだけの勇気と会話能力など持ち合わせていないのだから、そうなると頼れるのは警察官くらいか。と、そこに2人の警官“らしき”人物いて、貧しい旅人を訝しげに見ている。誰かを助けるという行為とは無縁の、ほとんど悪意に満ちたような視線に怖気づきながらも、僕は「ここに行きたい」とイタリア語で問いかけてみた。旅先で最初の会話。その直後、ああ、失敗だったと思うに到ったのは、何のことは無い、相手の話すイタリア語を1mmも理解できないと気付いたからだ。格好つけてイタリア語なんて話すんじゃなかった。何の収穫も得られぬまま、「Grazie」を連発する情けなさといったら…。その後も数十分歩き回った挙句、結局、目的のホテルはすぐ近くにあった。単に僕がその周りをぐるぐると旋回していただけの話だ。部屋に入るなり、その先の不安に苛まれる。明日から本当に大丈夫だろうか? ふと鞄に目をやると、飛行機でキープしておいた赤ワインが2本あった。今日はこれでも飲んで寝てしまおう。明日は朝早くからパリに発たねばならない。
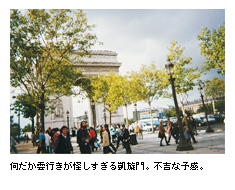 早朝にチェックアウトし、空港へ。完璧に組まれた計画に未だ大きな狂いは無い。マラパルテ邸に踏み込むという途方も無い目的だけが、かろうじて自分を支えていた。パリはどんな街だろう。ゴダールの、トリュフォーの、ユスターシュの、カラックスのパリ。そう夢想する瞬間だけ、不安から解放される気がした。
早朝にチェックアウトし、空港へ。完璧に組まれた計画に未だ大きな狂いは無い。マラパルテ邸に踏み込むという途方も無い目的だけが、かろうじて自分を支えていた。パリはどんな街だろう。ゴダールの、トリュフォーの、ユスターシュの、カラックスのパリ。そう夢想する瞬間だけ、不安から解放される気がした。
パリの憂鬱と特効薬
パリは冷たい。空気もそして人間も。このパリがあのスクリーンに映っていたパリなのか? そうなんだ、やっぱり映画は如何わしいのだ、すべては虚構なのだと、映画自体にまで当たる始末。途方に暮れることしばしば。ジャン=ポール・ベルモンド演じるミシェル・ポワカールの最期(※1)を真似て「最低だ…」と呟いてみても、事態は一向に変化を見せない。そう、パリの第一印象は最低だった。何故そう思ったのかは、よく思い出せないけど。そもそも印象なんてそんなものなのだ。
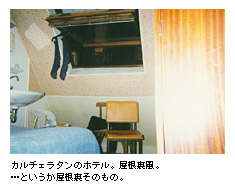 やっとの思いで見つけたホテルは、パリ大学近くの屋根裏部屋みたいなところ。とりあえず、ここ2〜3日暮らすだけだし、シャワーは共同だけれどまぁいい。ただ一つ、お願いだからシャワーの電球ぐらい替えてくれよ。真っ暗な密室での悪戦苦闘は、僕をより多く疲れさせるに充分だった。
やっとの思いで見つけたホテルは、パリ大学近くの屋根裏部屋みたいなところ。とりあえず、ここ2〜3日暮らすだけだし、シャワーは共同だけれどまぁいい。ただ一つ、お願いだからシャワーの電球ぐらい替えてくれよ。真っ暗な密室での悪戦苦闘は、僕をより多く疲れさせるに充分だった。
映画の旅としてのパリでの目的は、実は特に無かった。まずは旅の雰囲気を掴む、それが目的だったと言えば言えるか。さて、どうしたものか。相変わらず食欲は無い。とりあえず地下鉄でいろいろ回ってみるしかなさそうだ。そろそろ出かけるか・・・と鞄を見ると、またしても赤ワインの小瓶が見える。そうだった、今朝またキープしてきたんだった。ほぼ一気に飲み干す。すると一気に気分が晴れる。何だか力が漲る。おお、そうだよ、こうすればいいんじゃん!!! 僕がこの旅で最初に学んだこと、それは、出かける前には赤ワインを飲み干せ、である。以来数週間に及ぶこの映画の旅には、日に一本以上のワインが消費されていくことになる。特効薬…僕は赤ワインをそう呼ぶことにした。
モンパルナスでゲンズブールに合掌
 無目的のパリではあったが、セルジュ・ゲンズブール(※2)の墓にだけは詣でておきたかった。彼の精神的な師であるボリス・ヴィアンは「墓につばをかけろ」という小説を残したが、ここでは全く別の話。僕がそうしたかったわけではないから。
無目的のパリではあったが、セルジュ・ゲンズブール(※2)の墓にだけは詣でておきたかった。彼の精神的な師であるボリス・ヴィアンは「墓につばをかけろ」という小説を残したが、ここでは全く別の話。僕がそうしたかったわけではないから。
パリ・モンパルナスにある墓地に、彼はいる。その墓地には、多くの偉人たちがゲンズブールと同じように眠っているので、何だか墓地というより観光名所みたいだ。“有名人MAP”みたいな看板もあった。ゲンズブールの墓に付くと、まず目に付くのがキャベツと無数のカルネ。キャベツは彼が1976年に制作したアルバム名「L'homme a Tete de Chou(キャベツ頭の男)」からきている。トレードマークみたいなものか。カルネとは、パリの地下鉄の切符の名称。ここに来たゲンズブールファンは、カルネの裏に追悼のメッセージを書いてそれを残すらしい。堂に入っては堂に従う。僕もそれを真似た。何て書いたのかは覚えていないけれど。祖母の墓には滅多に顔を出さないのに、あのおばあちゃん子だった僕も、これでは怒られてしまうだろう。帰国したらちゃんと墓参りに行くので、待っててください。
港町・マルセイユには何が?
そんなこんなでパリには3日くらいいただろうか。結構楽しみにしていたポンピドゥーセンター(※3)は長期工事に付き閉館中だし、何より行列が嫌いな僕には、ルーヴルに行く気力もない。美術館には行きたかったけれど、この旅行の目的は別にあるから。そんなパリの収穫といえば、いや、本当は何の収穫でもないのだが、日本で買うより安くお酒が買えたこと。その当時の僕は、PERNOD(※4)というフランス産のリキュールにはまっていた。日本よりちょっと安いだけのPERNOを、僕は喜び勇んで買った。もちろん、自分へのお土産として。まだ旅の始まりに近いのに、愚かにも僕はこの重たいビンを旅の終わりまでずっと持ち歩くことになる。馬鹿としか言いようがない。
さて、パリで夜行の切符を買って、いざ南仏へ。南仏最大の目的は、『気狂いピエロ』のロケ地に訪れること。アデュー、悲しきパリ! 夜行に乗るのは初めてだが、「地球の歩き方」を熟読しつつ、何とか切符を手にした。寝台車に乗り、切符に書かれている部屋へ。そこは二段ベッドがぶっきらぼうに二台配置された部屋だ。ふと隣のベッドを見やると、そこには美しきパリジェンヌが。この旅最初の胸の高鳴り。ベッドで荷を解いている間中、僕は何て話しかけようか考えていた。彼女は本を読んでいたが、どうやらちらちらとこちらを見ているような気もする。一分が永遠に感じられたが、自意識過剰な僕は遂に意を決し、ありったけの引きつった笑顔で彼女に微笑む。そして僕が話しかけようとした瞬間、彼女の口からたった一言漏れたのは「Bon soir」という挨拶のみ。そして、すぐに読みかけの本に目を落としてしまった。僕がその時言えたのは、かなりの悲しみを含んだ「Bon soir…」だけだった。
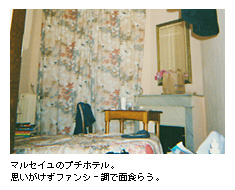 早朝のマルセイユは、肌寒かった。しかも、どの店も閉まっている。南仏の太陽と海は何処へ? あるのは曇り空とグレーの海だけだった。だから、というわけではないが、マルセイユでの記憶はほとんどない。あるのは、親切だったホテルの主人の笑顔くらいだろうか。あ、一つだけ忘れえぬ記憶がある。僕はものすごく偏食で、食べられないものが多い。だからと言うべきかわからないが、兎に角食べ物に対する関心が極端に低い。食べられればいい、それが持論である。旅を始めて数日経ち、特効薬を得たことで不安から解放された僕は、マルセイユに着いた頃には人並みに腹が減るようになっていたのだが、何を食べればいいのかがわからない。そんな時、目の前にマクドナルドがあった。ちなみに、日本において、マクドナルドで当時僕が食べられたメニューは(普通の)ハンバーガーとポテトだけだった。チーズは食べられないし、マヨネーズもタルタルソースも駄目とくれば、必然的にその2つしかない。マックなら世界中味が同じ筈だ! と喜び勇んで入ったマルセイユのマクドナルド。でも、僕は何処までもついていない男だった。日本で慣れ親しんだ、(普通の)ハンバーガーがないのだ。いや、もっと言えば、日本と同じメニューがビッグマックとポテトしかない。別にマクドナルドにその国のオリジナリティなんて求めていないにもかかわらず、あるのは見たこともないようなメニューばかり。何故かケーキまである。う〜む…だからと言って、かなり腹は減っている。どうすべきか。よし、ここはビッグマックにチャレンジである。ビッグマックは英語だけど、流石にそれくらいの英語は通じるマルセイユのマクドナルドで、僕は初めて食べられなかったビッグマックを食べた。
早朝のマルセイユは、肌寒かった。しかも、どの店も閉まっている。南仏の太陽と海は何処へ? あるのは曇り空とグレーの海だけだった。だから、というわけではないが、マルセイユでの記憶はほとんどない。あるのは、親切だったホテルの主人の笑顔くらいだろうか。あ、一つだけ忘れえぬ記憶がある。僕はものすごく偏食で、食べられないものが多い。だからと言うべきかわからないが、兎に角食べ物に対する関心が極端に低い。食べられればいい、それが持論である。旅を始めて数日経ち、特効薬を得たことで不安から解放された僕は、マルセイユに着いた頃には人並みに腹が減るようになっていたのだが、何を食べればいいのかがわからない。そんな時、目の前にマクドナルドがあった。ちなみに、日本において、マクドナルドで当時僕が食べられたメニューは(普通の)ハンバーガーとポテトだけだった。チーズは食べられないし、マヨネーズもタルタルソースも駄目とくれば、必然的にその2つしかない。マックなら世界中味が同じ筈だ! と喜び勇んで入ったマルセイユのマクドナルド。でも、僕は何処までもついていない男だった。日本で慣れ親しんだ、(普通の)ハンバーガーがないのだ。いや、もっと言えば、日本と同じメニューがビッグマックとポテトしかない。別にマクドナルドにその国のオリジナリティなんて求めていないにもかかわらず、あるのは見たこともないようなメニューばかり。何故かケーキまである。う〜む…だからと言って、かなり腹は減っている。どうすべきか。よし、ここはビッグマックにチャレンジである。ビッグマックは英語だけど、流石にそれくらいの英語は通じるマルセイユのマクドナルドで、僕は初めて食べられなかったビッグマックを食べた。
その時の感動は、どうも上手く説明できそうにない。端的に美味い。この上無く美味い。チーズもマヨネーズも、ビッグマックにおいては不可欠だと声高に叫びたくなるほどに美味かった。そんなこんなで、僕は現在、マクドナルドのメニューのほとんどを食べることが出来る。人間、極限状態になると、本当に不可能が可能になるものだと、馬鹿な僕は心底痛感した。この思い出は、そうそう忘れられそうにない。ちなみに、フィレオフィッシュは今でも苦手である。
(※1) あまりにも有名な『勝手にしやがれ』のラストシーン。初のゴダール体験は、にくい演出家としての彼であった。映画に現実が紛れ込んでいる、それがあまりに稚拙な第一印象。その後の旅が、ミシェル・ポワカールと逆の過程を辿ることになるのは、ただの偶然である。(※2) パリですべきことは唯一つ、それが彼の墓を詣でることだった。ロックばかり聴いていた自分が、あのエロティックな囁き声に魅了されるなんて、夢にも思っていなかったが。もし今、ゲンズブールが好きかと言われたら、迷わずこう答えるのが正しい。「俺も好きじゃない」
(※3) しかも、実は2年後再度訪れたパリでも、ここだけはその表情を変えなかった。工事中にあれほど苛立ったのは初めてかもしれない。“ピアノ”と聞いて最初にレンゾ・ピアノが思い浮かんだと言い張る貴方、嘘はつかないように。
(※4) 18歳のとき、とある酒場でとある男性にこの酒を教わらなかったら、今の自分はないであろうと断言できる。初めて飲んだ瞬間に好き嫌いが決まる踏み絵のようなリキュール。もし歯磨き粉の味がするなら、もう2度と飲まないほうがいいだろう。
映画と旅〜INTRODUCTION〜

澁澤龍彦という作家がいます。彼はすでに約17年前に亡くなっていますが、敢えて「います」と記したことに深い意味などありません。ただ、「いました」とは書きたくなかった、それだけのことです。私が学生時代に“旅”への想いを強めるに到った直接の契機はある映画作品でしたが、もう一つ、澁澤氏の著作から受けた影響も少なくありません。彼の死後出版された著作に『滞欧日記』(1993年 河出書房新社 写真は文庫版)というものがありますが、誤解を恐れずに言えば、この作品は私の“旅”そのものだったということ。言ってみれば、“旅”のきっかけが映画、“旅”のスタイルは『滞欧日記』だったということになるでしょうか。
『滞欧日記』は、澁澤氏の四度にわたるヨーロッパ旅行のあいだに彼が毎日つけていた日記を書籍化したものですが、ここではその中身の詳述はしません。しかし是非記しておきたいのは、書物で読んだことを“確認”する行為に等しかった澁澤氏の“旅”のスタイルが、次第に変化していったということです。すなわち、予定通りに行動し、既に知っている事物の“確認”に走ろうとする彼のスタイルが時には通用しなくなり、予想外の“発見”をしたり、未知の誘惑に抗いがたくなっていくのです。旅慣れなかった書斎派が、偶然の出来事を愉しんだり、見知らぬ外国人と会話したりするうちに旅慣れてきて、次第に“旅”そのものを生きるようになっていったということでしょう。そして、私の数少ない旅の経験も、まさにこのような変化の過程を辿ることになるのです。いかにしてその場所を“積極的に生きる”のか。そういえば当時から私は“旅行”ではなく、“旅”をしたのだと、根拠も無く言い放っていましたが、それは“旅を行った”という自覚は無く、知らぬ間に“旅に生きた”という感覚があるからです。ほとんどこじつけとも言えそうなこんな戯言ですが、私はこの差を虚構化したくない、とだけ言っておきます。曖昧な、しかし感覚的というより実体験として。
何故今になって過去の旅をWEB上で再現するのか(事実、ここにある“旅”を終えてから、かなりの時間が経過しています)。それはひとえに、私が体験した世界に再度光を当てたかったから、という至極個人的な理由に拠る部分もあります。しかしながら、私が“旅”をした時には体験し得なかったインターネットというメディアが可能にした、“無意識”の(決して“無償”ではありません)情報の共有が、見知らぬ人間の手助けになるやもしれない、そんなおこがましい気持ちも無かったわけではないのです。当時、もし私がインターネットを日常的に利用していたなら、何らかの情報を得るためにあれほどの苦労を強いられることは無かったはずです。ノウハウの共有と言えば聞こえは良すぎるのですが、ある情報に光を当てるとは、そういうことなのかもしれないと思ったということです。
ほとんど恥ずべき虚栄心の表れと化したここにある文章なので、非常に恥ずかしいことですが、それらには、どうしても“私自身”が露呈せざるを得ません。しかし、当時の“青さ”を、現在の視点から対象化することに、私はもう躊躇しませんし、過去の自分を隠すつもりもありません。“青さ”は“青さ”として読まれれば、そこには“青い”なりの価値が表出するかもしれない。この希望無しに、このコンテンツは成り立たないでしょう。
映画の旅と題してはいますが、ここには映画とは直接関係のないエピソードも出てくるかと思います。しかも、旅のきっかけになった映画も3本だけで、ざっと以下の通りです。
『軽蔑』 (仏=伊 1963年 ジャン=リュック・ゴダール監督)
生まれて初めて海外への“旅”を熱望するきっかけになった作品。マラパルテ邸をこの目に焼き付けるゾ! という尊大な計画(当時はそう思い込んでいました)の果てに見たものはどんな光景だったのか!?『気狂いピエロ』 (仏=伊 1965年 ジャン=リュック・ゴダール監督)
恐らく、ヴィデオも含めて30回は観ているだろうこの作品において確かめたかったのは、アンナ・カリーナが歌うシーンの森の美しさと、ラストシーンが撮られた(?)あの“何処でもない”島の所在である。フォード・ギャラクシーは無いし、連れ行くパートナーもいないが、太陽と海の青さは、私の目の前に確かにあった。『冒険者たち』 (仏 1967年 ロベール・アンリコ監督)
一度目の“旅”を終え、かなり満足したはずの自分が再度旅立つことになったのは、あの要塞島の非=現実的な光景が忘れられなかったからである。劇中、ジョアンナ・シムカスによって語られる台詞だけが、その手がかりになった。初の2人旅の行方は如何に…
だからと言って、映画好きとそうでない人をふるいにかける気はさらさらありません。上記の映画を観ていない人も、“旅”の普遍的な冒険性は感じていただけると思いますので。あるいは、私が意識せず、ある映画の舞台を結果として訪れたということもあるかもしれません。しかし、恐らくその辺には深く触れずに置くと思います。そもそも私の“旅”は、明確な目的あってのものだったからです。目的もなく偶然記憶に残った挿話については、私自身の記憶も曖昧なのです。それは予めご了承いただき、それでも尚“ある生々しい感動”が伝わればそれで充分だと思います。
このコンテンツは、“旅行ガイド”としては甚だしく不十分な代物ですが、私が知りうる限りの情報は、気がつく範囲で記しておきたいと思います。だからといって、決して実用としてではなく、飽くまで日記の変奏として捉えていただければ幸いです。ちょうど過去の日記を読むみたいな感覚で。
cinemabourg*に関する2,3の事柄
■cinemabourg*(シネマブール)は、映画作品に関する文章を中心に、直接的・間接的に映画に接点を持つ日常について、筆者[M]が思うままに綴ることを目的としたブログです。
■ここに掲載されている文章にはおよそ“映画を批評する”という精神が欠如しています。その長短に関わらず、あくまで私的な雑文以上のものではありません。ただしだからといって、冗談の域を超えた事実の歪曲や誹謗中傷を書くような趣味は持ち合わせておらず、姿勢としては極めて真面目に書いております。
■cinemabourg*では、必ずしも劇場で見た作品のみを扱っているわけではありません。ヴィデオやdvd等のメディアで鑑賞したものに関しては、タイトル脇に(V)と記すことで区別しています。
■直接的であれ間接的であれ、当サイトのすべての文章・イラストレーションを使用(引用)したことによって引き起こされるあらゆる問題に対して責任は持ちませんので、ご了承ください。
■掲載されているリンク、画像は許可無く張られたものです。何か問題がある場合は、すぐに削除いたします。
■コメント・トラックバックは大いに歓迎しますが、記事に全く関係ない内容のものなど、独断と偏見により削除する場合があります。
■IE6のみで動作確認しています。それ以前のヴァージョンや他のブラウザではレイアウトが壊れてしまう可能性があります。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]



