2007年02月26日
1933年に映画は一つの完成形をみせていたという一例
私が日仏学院に行く時は必ず数人の知った顔があり、東京における映画好きの数もそれで予想されてしまうものですが、昨日、「世界の映画と共にある都市、パリ」という特集上映に足を運んだ時もやはり、ああ、あの人もいる、あ、あの人もいるなぁ、あの人はいないのかしら? などという感じで、まぁいつもながらの光景に収まっていくのですが、1本目の『黙示録の四騎士』はフランス語字幕のみだったからか、観客もまばらでちょっと拍子抜けしつつ、しかし作品自体はわけがわからない箇所も多くあったとは言え、約2時間30分もってしまうあたりが素晴らしいといえば素晴らしく、四騎士の疾走がパリの空にインサートされる描写は若干仰々しかったとはいえ、なかなかの迫力だと思いました。
その後、カフェで次のルビッチを待ちながら最近奇跡的に入手出来たNINTENDO DS Liteで「大人の常識力トレーニングDS」に勤しんでいると、ポンポンと肩を叩かれ、振り向いてみると、そこには最近卒業制作を撮りあげて公開を待つばかりの[R]君がいて、ブルータスお前もか、と言いつつ最近の映画話に花を咲かせました。その後上映された『生活の設計』は8割方埋まっていて、やはりルビッチは偉大過ぎるという結論に。今年は後何本のルビッチが観られるかわかりませんが、早々と2007年のべスト入りが約束された次第。
そうそう、土曜日は韓国アートフィルム・ショーケースから『不機嫌な男たち』も観ました。
イメージフォーラムにおける“性器露出率”は東京でも圧倒的な高さだと認識していますが、『不機嫌な男たち』におけるセックスシーンの決して美しくはない“音”は、その描写以上に印象的で、未だ耳の奥で反響しているようです。近年、本作ほど人に説明出来ない映画を観ていないかもしれません。とりあえず悪くはなかったと言うほかありませんが、私の前列に座っていた初老の夫婦は、開始40分くらいの何度目かの濡れ場で、とうとう席を立っていきました。さりげなく聞こえてきた「そろそろ出ようか」という呟きもまた、本作の一側面を如実に表していたのだと、今は思っています。
2007年02月25日
超・必見備忘録 2007.3月編
ガレルを逃してしまったことが悔やまれてならない2月でしたが、貴重なキム・ギドク初期作品が観られる
3月はあれこれ期待できそうです。韓国と言えば、イメージフォーラムの「韓国アートフィルム・ショーケース」はこの機会に是非コンプリートしておきたいところです。
『ドリームガールズ』(渋東シネタワー 上映中)
何となく大文字のアメリカ映画を観られそうな予感。
『叫(さけび) 』(シネセゾン渋谷or新宿武蔵野館 上映中)
言わずもがなです。
『孔雀 我が家の風景』(Q-AXシネマ 上映中)
ベルリン映画祭銀熊賞・中国・撮影監督出身。この3つのキーワードで決めました。
『松ヶ根乱射事件』(テアトル新宿 上映中)
言わずもがな、です。
『今宵、フィッツジェラルド劇場で』(ル・シネマ 3/3〜)
久々に遺作というものに立ち会う気がします。アディオス,アルトマン。
『パリ、ジュテーム』(恵比寿ガーデンシネマor新宿武蔵野館 3/3〜)
非常に楽しみ。何本当たりがあるでしょうか。
『やわらかい生活』『ストロベリーショートケイクス』(新文芸坐
3/17)
ナイス二本立て。観られるか!?
『絶対の愛』(ユーロスペース 3/10〜)
言わずもがな?です。
『素粒子』(ユーロスペース 3/24〜)
ドイツ映画祭で見逃したので。
「ナインティーズ:廃墟としての90年代」(シネマヴェーラ渋谷 上映中)
すでに2回ほど挫折していますが、観たい2作品だけは。
「スーパー・ギドク・マンダラ」(ユーロスペース 上映中)
未見の初期作品だけは何があっても観にいきます。
「第2回ガンダーラ映画祭」(下北沢LA CAMERA 3/15〜)
前回参加出来なかったので今回は。自転車で駆けつけます。
「フランス映画祭の現在・過去・未来」(ユーロスペース 3/17〜23)
「ジャック・ドゥミ特集 結晶(クリスタル)の罠」という素晴らしい特集があります。
「韓国アートフィルム・ショーケース」(シアター・イメージフォーラム 上映中)
全部で4作品ありますが、どうやら全て観たほうがよさそうです。
2007年02月22日
私と「STUDIO VOICE」
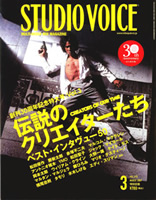 今、手元に「STUDIO VOICE」(MARCH 2007 VOL.375)があります。発売してすぐに購入しましたが、その時は別の本を読んでいたので、今になってやっと読み始めた次第。
今、手元に「STUDIO VOICE」(MARCH 2007 VOL.375)があります。発売してすぐに購入しましたが、その時は別の本を読んでいたので、今になってやっと読み始めた次第。
今号は、“30th Anniversary -永久保存版-”と題されています。つまり、この雑誌ももう30周年を迎えたということになります。年数だけで言うならかろうじて私よりも後輩というところですが、私が読み始めたのは90年くらいからですから、とてもそんなことは言えません。
さて、ざっと2年数ヶ月ぶりに「STUDIO VOICE」を購入しましたが、どうやら“創刊30周年記念特大号:Vol.3”とあるので、永久保存版はすでに2号出てしまっている模様。そこでサイトを見てみると、Vol.1が「写真集の現在」、Vol.2が「『80'sカルチャー』総括!」と、いかにもボイス好みの特集が続いていました。
Vol.3である今号は「伝説のクリエイターたち ベストインタビュー50」。表紙に並んだ名前を見て、どうやらこれは自分が嘗て読んできたものが多そうだと直感しましたが、映画特集ではないにせよ表紙は松田優作だし、『叫』や『ドリーム・ガールズ』の映画評があるし、今読み進めている「吉田喜重 変貌の倫理」の書評もあるので、久々に買ってみようと思ったのです。
読み始めると、そこに登場するインタビューの多くは読んだことがあるものでした。それもそのはず、91年ごろから「STUDIO VOICE」は私にとってことのほか重要な雑誌で、まさにボイスがあったからこそ今の私があるのだと言っても、決して言い過ぎではないのですから。
私が出版方面への就職を決意したのも、実のところ、この雑誌に何らかの影響を受けてのことでした。
大学生の時、とにかく時間だけはあった私は、もちろん映画もよく観ていましたが、今では気恥ずかしくてそう口に出来ない、あの“サブカルチャー”という言葉に狂っていたのでした。それが何だったのか、未だに上手く説明出来ませんが、いずれにせよ「STUDIO VOICE」という雑誌を抜きには語れないでしょう。ちょうど大学に入学してすぐくらいに、未だアンダーグラウンドな雰囲気を漂わせていたクラブカルチャーにどっぷりと染まり、そこで様々な人種と出会ううちに、ファッションやら音楽やら写真やら建築やら文学やらデザインやら、つまり、「STUDIO VOICE」が好んで特集しそうなあらゆるカルチャーを貪欲に吸収しようとしていたわけで、まさに「STUDIO VOICE」を媒介として、様々なジャンルを横断していったのです。
その後就職が決まり、新入社員紹介、みたいな感じで社内報に載ることになって、その撮影時に数人のカメラマンや先輩社員たちの前で、“「STUDIO VOICE」のような雑誌を作りたい”などと発言して大方の失笑を買った時には、まだ出版業界の実状などまるでわかっていない、単なる青二才だったということになるでしょうが、それでも何だかんだ言って25歳くらいまではずっと定期購読していた「STUDIO VOICE」を、では何故読まなくなっていったのか。まぁ考えてみるまでもなく、スポンジのようにあらゆるジャンルを自分のものにしたいなどという青い時期は過ぎ去り、気づかぬうちに、ある特定の分野に対してのみ、情熱を注ぐようになっていったからでしょう。あるいはこの業界に入って、雑誌全般を見る目が変わった、とも言うべきかもしれません。年齢を重ねるに従って読む雑誌が変わってしまうのは珍しくないし、さらに言えば、もはや映画に関連した雑誌以外はほとんど買わなくなってしまったのですから。
しかしながら、今号はそんな私には何ともノスタルジックな思いを抱かせてくれたという意味で、非常に興味深い。何十冊もあった「STUDIO VOICE」も、現在の住所に引っ越してきた8年前にそのほとんどを処分してしまい、今はもう読み直すことも出来ないので。あの時、私と「STUDIO VOICE」との連綿と続いてきた関係に、ある種のピリオドが打たれたのでしょう。以来、映画関係の特集以外はほとんど購入せず、その存在すら薄れかかっていた私にとって、当時熱狂したクリエイターたちのインタビューは、本当に懐かしい。
実は一度も面白いとは思ったことがないウィリアム・クラインのリバイバルに駆けつけたり、GUCCIの広告に衝撃を受けてマリオ・テスティーノの名前を連呼したり、ブロンソンズの存在に嫉妬したり、パンクファッションの歴史について友人と夜通し語り合ったりしたのも、全て「STUDIO VOICE」に熱狂していた時期に重なります。ゴダール特集やゲンズブール特集号を求めて古書店を歩きまわるなんて、今では考えられません。ピーター・ビアードよろしく、誰に見せるわけでもない自分の手帳にコラージュ作品を作っていたなんて、今だからこそ言えることです。
あらためて眺めてみると、やはりなかなか面白い雑誌だということに気づきました。
今後も毎号買うということはないでしょうが、その存在は記憶から消してしまわないようにしなければと思います。
2007年02月19日
でもバカリズムには大爆笑
久々に1本も映画を観ないという週末。
昨日など、最初は「雨だから」という理由がかろうじて成り立ってはいたものの、午後からはカラッと晴れてしまうし、「購入したりダビングしてもらったヴィデオなりdvdなりを観るゾ」という決意でそれを正当化しようと思うのですが、何となくギターを弾いてみたり、料理してみたり、お笑い番組を観たりしているうちにあっという間に時間が過ぎ去っていき、最後は開き直って、「ああ、映画に追われない休日というのもたまには悪くないな」などと結論する始末。別に誰に急き立てられてこういう生活を送っているでもないのに、まったく馬鹿げたヤツです、私は。
言わんこっちゃない、と言う声が聞こえてきそうですが、月曜の朝から映画が観たくてたまらず、とりあえず今日はシネマヴェーラのラストに滑り込むと決意しました。明日は『見えない雲』だ、と思って調べてみたら、すでに終了。ついでにガレルも昨日で終了。嗚呼…。
追記:
決意も虚しく、やはり仕事を抜け出せないようです。
こういう時に限って……。
2007年02月15日
『ディパーテッド』に対するいくつかの覚書
 ディパーテッド/THE DEPARTED/2006年/アメリカ/152分/マーティン・スコセッシ
ディパーテッド/THE DEPARTED/2006年/アメリカ/152分/マーティン・スコセッシ
本作はリメイクである、という前提が厳然としてあるのですが、リメイクとはどういうものか、リメイクにはどのように接するべきか、鑑賞後にそんなことを考えてしまいました。ネタ元と比した上で作品としてどちらの出来が良かったか、などという安易な比較論で済ませてはならないのではないか、という気がしたからです。そういった比較は、確かに人を饒舌にさせるかもしれず、また一つのエンターテインメントとして楽しめもするのでしょうが、やはりあまり生産的だとは思えなくなってきました。事実、私自身、リメイク作品をその手の比較論的な扱いで安易に語ってきたこともあるのですが、撮られた年代や国籍、俳優、そして何より監督が異なることが多いリメイク作品というやつは、やはり、それを一つの独立した作品として見なければならないのだろう、そんな風に思ったわけです。まぁ当たり前と言えば当たり前かもしれないことに、改めて気がついた、と。
実のところ、このリメイク映画に関して、すでに不毛な比較論めいたものを書き上げてしまってからこんなことを書いている次第なので、今、あらためて『ディパーテッド』について書くべきことなど残されていないに等しいのですが、今はとりあえず、2006年のアメリカ映画である『ディパーテッド』で印象的だったシーンを列挙しておくことで、この映画に対する私の態度を表明しておくに留めます。
なお、下記の文章に、特に結論めいたものはありません。
■冒頭、ジャック・ニコルソンの“顔”と“声”に頼った一連のシークエンスは、いかにもベテラン演技派俳優としての“顔”がやっと画面に登場した瞬間、ある種の安堵を覚えさせると同時に、いささか気恥ずかしくもなった。すでにあるイメージの反復、それを刺激(もしくは驚き)へと変貌させるのは難しい。
■とりわけ、マッド・デイモンの演出に対する既視感。しかし彼はだんだん、天才的な男というイメージからかけ離れて行くので、むしろ後半の彼のほうが好みである(ラスト近くで、もう1人存在したスパイ仲間を殺す瞬間は悪くない)。
■久々に観たアイリスインとアイリスアウトに反応。
■編集のめまぐるしさ。それは、本作が現代のアメリカ映画だということを宣言しているかのよう。
■白い粉が、まるで射精のシンボルであるかのように宙に舞うシーンには閉口するほかはない。それがこちらの勝手な解釈であろうとも、あのようなシーンは肯定出来ない。
■レオナルド・ディカプリオとヴェラ・ファーミガが結ばれるシーンの描き方は、様々な意味で、それがアメリカ映画であることを意識させたが、スコセッシにとってはあまり重要なシーンではなかったのかもしれない。
■ジャック・ニコルソンは今回、いかにも狂ったマフィアのボスという役を演じていたが、非常に表層的に見えてならなかった。彼がどの程度スコセッシの演出に口を出したのかはわからないが…。しかしながら、潜入捜査官であるレオナルド・ディカプリオと、ほとんど“顔だけで”腹のさぐりあいをするシーンは素晴らしい。このバラツキは戦略なのか、否か。
■随分と設定を変えている、ということはつまり、スコセッシの描きたかった方へと作品を引き寄せている割に、やはり『インファナル・アフェア』を強く意識せざるを得なかったのだな、と思われるシーンがあって、そのシーンはとりわけ印象に残っているが、前後の説明的なショットの分、重要なシーンにもかかわらずそこだけは弱いと思わざるを得なかった。
■レオナルド・ディカプリオとマット・デイモンが相対して銃を構え合うというシーンをあえて避け、“(ある)死者”という原題に即しているともとれるようなラストシーンを選んだことに対しては、素直に賞賛したい。マーク・ウォールバーグの演出は見事だったと思う。
ざっとこんなところです。
面白かったかと問われれば、恐らく面白かったと答えるでしょう。
『インファナル・アフェア』を未見のまま本作に臨んだ方の率直な感想を聞いてみたいとも思いますが、答えは何となく予想出来るので、まぁそういう野暮な質問はしないことにしましょう。
2007年02月13日
『エレクション』における過剰な静けさ
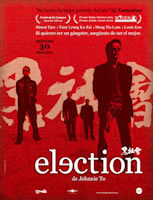 エレクション/ELECTION 黒社會/2005年/香港/101分/ジョニー・トー
エレクション/ELECTION 黒社會/2005年/香港/101分/ジョニー・トー
作品の中に、その流れを断ち切るようなズレ(あるいは亀裂とでも言いましょうか)を忍び込ませる作家。私の中のジョニー・トーはそのような作家として位置づけられていますが、本作にも深く感動せずには居られないシーンがあり、ああ、やっぱりジョニー・トーの映画を観ているのだということを実感。しかも作品自体の出来も素晴らしく、「ほとんど傑作だよね」と同行した女性に言い放ってしまう始末。本当に傑作を観た場合、大概は黙りこくってしまい、気軽に誰かに話しかけることなど無いのですが、今回はそう言わずに居られなかったのです。それはどこかで、続編の公開を何とか実現させて欲しいという思いが発露した結果なのかもしれません。
物語はいたってシンプルなのに、どこか一筋縄ではいかないような感覚、ともすると本作はそんな感覚を観客に抱かせるかもしれません。それは恐らく、物語自体を過剰に彩るアクション(これは別に、銃撃戦や格闘シーンに限ったものではなく、登場人物のあらゆる運動を評しているのですが)の所為ではないかと思われました。過剰さとは時に、ほとんど静寂に包まれた画面においても生起してくるのです。
それが最も印象付けられたシーンは、組織の長老幹部が一同に会して次期会長を選出するための議論の最中、組織の重鎮にしてもっとも影響力の強いウォン・ティンラム演じるタンが、幹部たちに茶を振舞うシーンでした。幹部たちは、次期会長候補である2人の男のうちどちらを選ぶか、自らの未来の安泰を左右するこの重要な選挙に際し、ある者は保身のため、ある者は組織の将来のために、ほとんど互いに一歩も譲れないかのような議論を展開している。その時、まるで鶴の一声であるかのように、それまで口をつぐんでいたタンが静かに、しかし重い言葉を発するのです。幹部たちを諭すかのようなその言葉に、それまでの議論にはあっさりと終止符が打たれます。その時点で次期会長が決定されるのですが、その時、タンは幹部たちに自らが淹れた茶を振舞うのです。タンを取り囲むように起立した幹部たちは、それが場に最も相応しいかのようにまったく無言のまま、注がれた茶を飲み干していく…。
その様を、やや引き気味のカメラがさも“大事そうに”画面に納めるのです。そしてまったく同じシーンが2度繰り返されます。その間一切の会話は無く、すでに老齢に差し掛かった組織の男達が、ただ湯飲みを受け取り、立ち上がって茶を飲むというだけのシーンです。しかし、この静けさはいったいどういうことでしょうか。ただ私は、その控えめでありながらも稀有な一連のシーンを観て、戦慄するほかありませんでした。なるほど、この静かで暴力性など微塵も感じられない画面だからこそ、組織の厳しさが十全に伝わるのだ、などという知的な思考の介在する余地などまるでなく、ただただ、場違いとも断絶とも言えそうなこのシーンに驚き、深く感動してしまったのです。その瞬間、『ブレイキング・ニュース』における、やはり過剰な料理場面を思い出さずには居られなかったものの、ある種麻薬のように人を惹きつけてやまないジョニー・トーの過剰さに参ってしまいました。やはりそれは紛れもないアクションなのです。
相変わらず途方もないロングショットに驚かされもしましたし(レオン・カーフェイが2人の部下に拷問をするシーンの鮮烈なロングショット!)、フルショットにおける黒いユーモアも流石(ラム・シューのやられ損ぶり!)、どれほどの馬鹿が見ても分りやすい格闘&銃撃シーンの職人芸(ニック・チョンの殺人兵器のような動き!)にもやはり関心することしきりでした。一反は心を許しあったかに見えた新会長サイモン・ヤムとレオン・カーファイの蜜月を一瞬で無かったことにしてしまうかのようなあの執拗な殺人シーンも、物語的展開からすればやはり驚くべきシーンだったわけですが、それでもやはり、私にとってのジョニー・トーを考える上で、先述したシーンの衝撃は大きく、鑑賞後もそのシーンばかりが反芻されたのでした。
同行した女性に感想を求めてみると、そもそも香港映画をあまり見ないという彼女は、やはりというべきか、困惑した表情を浮かべていたのですが、一言、「みんなでお茶を飲むシーンは素晴らしかった」などと言うので、こちらも人に誇りうるほど香港映画に精通しているわけでもないのに、そうかい君もなかなかわかっているね、などと言いつつ、何とか共感の念を示そうとしたりも。まぁ私もいい加減ですが、“黒社會”という原題を持つこの映画において、それを観た2人が感動したシーンが、共に“お茶を飲む”というシーンだったことは、やはり偶然ではないのでしょう。
2007年02月05日
“黒社会”もの2本〜香港vs.アメリカ
昨日は恒例のフットサルへ。今回はいつもより参加者が少なかったものの、我々のチームに外国人の助っ人が入り、それはそれで大いに盛り上がりました。彼は某雑誌のモデル。自称・元アヤックスのユースという彼、その真偽はこの際あまり問題ではなく、いかに彼自身が楽しめたかということが大事だ、と私は思っていて、どうやら左腿を痛めてしまったらしいのですが、それでも終了後の表情を見るに、2時間を充分楽しまれた様子だったので良かったです。また一緒にプレイしたいですね。
さて、こちらも1ヶ月半ぶりのフットサルだったためか、終った後ぐったりと疲れ果ててしまい、その後観る予定だったダニエル・シュミット『ヘカテ』に行けませんでした。それが当然であるかのようにお誘いいただいた[R]君、ありがとう&ごめんなさい。
というわけで週末の映画は2本のみ。ジョニー・トー『エレクション』とスコセッシ『ディパーテッド』です。
別途それぞれの雑感は書きますが、ジョニー・トーはやはり素晴らしい。
この続編が公開されないとなると、大いに問題ありです。フィルメックスのチケットが速攻で完売していましたが、その時に無理してでも観ておくんだったと後悔しています。
『ディパーテッド』は、数多あるアメリカ映画の一つとして観た場合と、『インファナル・アフェア』のリメイクとして観た場合とで、印象が大きく異なることが避けられないという意味で、なかなか難しい映画かと。リメイクというものを観るということを、少なからず考えさせられる1本であることは間違いないでしょう。
今週は週末の連休を生かし、4〜5本は観たいと思います。
それにしても今日は体中が痛い……。
『マジシャンズ』は、ある側面において評価さるべき映画である
 マジシャンズ/THE MAGICIANS/2005年/韓国/95分/ソン・イルゴン
マジシャンズ/THE MAGICIANS/2005年/韓国/95分/ソン・イルゴン
“95分ワンカットの奇跡がくれた、魔法のようなエンディング―――”
この映画のキャッチコピーです。さて、このコピーを読んで、どのような思いを抱くでしょうか。
映画好きであれば、すぐさま2本の作品名が浮かぶはずです。
1本は『ロープ』、そしてもう1本は『エルミタージュ幻想』。そこで、では、いったいどんな監督がそんなことをやってのけたのかと探ってみると、監督:ソン・イルゴンとある。私の場合はここで「観るぞ」と決意しました。私は寡聞にしてこの固有名詞に反応することが出来ず、であるからこそ、この映画を積極的に観る気になったというわけです。諸刃の剣とも言えそうなワンシーンワンカットという芸当が、輝かしい発見となるか、あるいは無残な失敗に終るのかを確認したかったので。恐らくフィルムではなく、ヴィデオで撮られているはずだという予想くらいはしていましたが、それ以上の詳細はあえて見ずにおき、本作に臨んだというわけです。
冒頭のショット(というか本作はこのショットが全てなのですが)を観て、何となく嫌な予感がしました。この映画は、退屈極まりないものになるんじゃぁなかろうか、と。どこと無く抽象的で、観る人が観れば幻想的とでも言うのかもしれないその画面に全く乗れず、ああ、このまま95分間もこの絵に耐えられるだろうかと気が滅入ってきて、そう思ったことには恐らくその日の体調なども無関係では無かったと思うのですが、とにかく乗れなかったのです。せめてこの映画がワンカットで撮られていなければ、どこかでこちらを立ち直らせるショットがあるのではないかと期待も出来たのですが、不幸にして本作はワンカットなのです。ということはつまり、95分間持続するショットがどこかで劇的に、その色彩なりテンポなり動きなりを変貌させることは不可能に近いことではないかと思い至りました。この緩やかで抽象的な画面がずっと続くのであれば、もうダメだ、と。
ところで本作のカメラは、本当に良く動きます。舞台となるとあるカフェから外の森へ、そしてまた中に入ったり階段を上ったり下りたり、また外に出たり…。このカメラの動きの緩やかな持続性に、私は少しずつ慣れていったように思えます。気になってしかたなかったあの画面が、徐々に自分のものになっていく、そんな感覚といえばいいでしょうか。これはまったく予想外の出来事で、ひとまず冒頭の段階で劇場を後にしなかったのは正解だったということになります。
さて、そうは言ってみても、やはり乗りきれない箇所は何度もあって、それは想像するだけで過酷な撮影技術上の問題というよりも、もっぱら物語りというか演出上のそれだったわけで。本作ではすでに死んでいるはずの女性が、実体をもった人間として画面に幾度と無く登場します。既にこの世には居ないその女性を、人間、と言い切ってしまうのも可笑しな話ですが、彼女は少なくとも、現実世界にある“もの”に(画面上では)触れることが出来る。しかし、そこにいる誰もが、彼女の存在には気づかない。まぁこのあたりの描写は容易に想像できるという点でありがちといえばありがちですし、かといってそれほど頻繁に映画で目にする描写ではありません。その意図するところをわからないでもないし、動きをやめないカメラと、死者であるところの彼女の奇妙なアクションとがある調和を生んでいたことを決して無視しているわけでもないのですが、それはやはり、私の求める(もっと単純に言えば、好みの)演出ではありませんでした。よって、彼女が登場する部分にはほとんど乗れなかったのですが(手首を切る瞬間の鮮烈な赤い血飛沫だけは別)、反面、例えば途中で登場する元スノーボーダーの坊主との会話におけるちぐはぐなやり取りと沈黙をも含んだテンポなどは非常に印象的で良かったと思いますし、何より、いよいよ全員が同じ舞台に立ち、最後のライブをするというラストシークエンスなどは、それまで観てきた画面の印象とはいささかズレている楽曲のポップさと抒情的とも言えるメロディーラインに不意撃ちの感動を齎され、そのライブシーンによって、全体としての印象も結構肯定的になってしまうほど。もしあれが“本当の”ライブだったら、私の感動もより大きなものになっていたことでしょう。なるほど、映画におけるラストシーンというのはやはり重要なのだということを実感。
『マジシャンズ』は傑作でも何でもない映画ですが、その挑戦的な姿勢を評価したい映画であることだけは確かなのです。
2007年02月02日
超・必見備忘録 2007.2月編
年末から1月の後半まである事情のためなかなか忙しかったのですが、やっと開放されました。今月はやや短いものの、少なくとも先月より多くの映画を観にいきたいと決意しております。
さて、先月はこの「必見備忘録」をも更新出来なかったのですが、今月より、「超」という字を加えました。もう具体的に私が観ると決めた映画以外は書きません。どうしても観たかったとしても、日程的に観られない特集上映なども書かずにおきます。つまり、下記に挙げられた映画は絶対に観ると決意した映画だということになります。もちろん、突発的に観たくなる映画もあるでしょうが、観ると決めた映画は観る、そういう姿勢で2007年は臨みたいと思ってます。
ちなみに、2/3の爆音オールナイトに行けないのは返す返す残念。行かれる方は、シークレット上映の中身を是非お教えください。。。
マキノと90年代特集は、時間的にどちらか一方しかいけないかもしれませんが、まだ読めないので、一応両方書いておきます。
『エレクション』(テアトル新宿 上映中)
続編はちゃんと公開されるのでしょうか。にもかかわらず、すでに傑作の予感が…。
『ディパーテッド』(渋谷TOEI2 上映中)
こちらは大入りの模様。まぁ観ないわけにはいかないでしょう。
『マリー・アントワネット』(渋東シネタワー 上映中)
ソフィア・コッポラもとうとうミニシアターを脱しました。これは一つのモードといえるかもしれません…。
『ユメ十夜』(シネ・アミューズ イースト/ウエスト 上映中)
こちらの客入りはどうでしょうか。念のため、早めにチケットを確保したいな、と。
『幽閉者(テロリスト) 』(ユーロスペース 上映中)
先日、会社のFさんから『天使の恍惚』を借りました。久々に再見することだし、良いタイミングです。
『ワサップ!』(シアター・イメージフォーラム 上映中)
ラリー・クラーク監督はデビューから付き合っているので。今回はPG-12。
『キムチを売る女』(シアター・イメージフォーラム 上映中)
これを観た[R]君からメールが。一言、「必見です!」。もちろん、こちらもそのつもりでした。
『フリージア』(アミューズCQN 2/3〜)
熊切監督も何だかんだ言いつつ外せません。同じ年だし、というのを別にしても。
『恋人たちの失われた革命』(恵比寿ガーデンシネマ 上映中)
ガレル、ガレル、ガレル……『ドリーマーズ』のことは頭から排除して観たいと思います。
『みえない雲』(シネカノン有楽町 上映中)
これも有楽町だけ…。レイトなので、平日ねらいで。
「ダニエル・シュミット監督回顧」(ユーロスペース 2/3〜)
残念ながらアテネのほうには一回もいけず…『ラ・パロマ』と『カンヌ映画通り』だけは観たかったのに。最低でも1本は。
「帰ってきた「次郎長三国志」とマキノ時代劇大行進!」(シネマヴェーラ渋谷 上映中)
大盛況の模様。最低でも2本は。
「ナインティーズ:廃墟としての90年代」(シネマヴェーラ渋谷 2/17〜)
瀬々敬久と諏訪敦彦だけは。ついこないだのようで、もう結構前である90年代。映画に時代性が刻まれているのか、あるいはいないのか。
「世界の映画と共にある都市、パリ」(東京日仏学院 上映中)
またとんでもなく素晴らしい企画。2/24・25のルビッチとイオセリアーニ、3/2・3のラウル・ルイス。そして極めつけは、3/3・4のマルコ・フェレーリ!! 溜息がでるようなプログラミング。みんなして鑑賞後、幸福な溜息を漏らしましょう。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]
author : [M]



